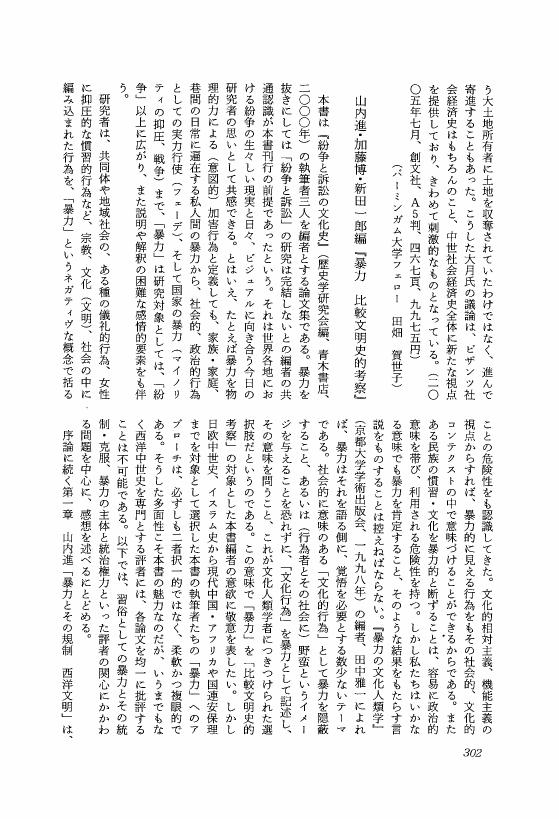3 0 0 0 OA (書評)村上一博著「日本近代婚姻法史論」
- 著者
- 宇野 文重
- 出版者
- 法制史学会
- 雑誌
- 法制史研究 (ISSN:04412508)
- 巻号頁・発行日
- vol.2004, no.54, pp.145-150, 2005-03-30 (Released:2010-05-10)
- 著者
- 児玉 寛
- 出版者
- 法制史学会
- 雑誌
- 法制史研究 (ISSN:04412508)
- 巻号頁・発行日
- vol.2004, no.54, pp.230-234, 2005-03-30 (Released:2010-05-10)
3 0 0 0 村上淳一「近代法の形成」
3 0 0 0 安政年間における箱館奉行支配上役衆の廻浦について
- 著者
- 杉谷 昭
- 出版者
- 法制史学会
- 雑誌
- 法制史研究 (ISSN:04412508)
- 巻号頁・発行日
- no.22, pp.105-125,VIII, 1972
The paper submitted by the present writer deals the historical data for investigation of Ezochi (Hokkaido) in 1857—'59. In the middle of the nineteenth century, the Tokugawa Shogunate reinforced political and economical regulation in Ezochi.<BR>Under the shogunal government, the magistrates and the mandataries at Hakodate carried out their policy by means of the patrols around Ezochi. The documents owned by the Hokkaido Government Office (_??__??__??__??_) are the diaries of those patrols around Ezochi in 1857—'59. These data are highly valuable in explaining the shogunal policy toward Ezochi in those days.
3 0 0 0 OA (書評)山内進・加藤博・新田一郎編著「暴力 比較文明史的考察」
- 著者
- 服部 良久
- 出版者
- 法制史学会
- 雑誌
- 法制史研究 (ISSN:04412508)
- 巻号頁・発行日
- vol.2006, no.56, pp.302-307, 2006 (Released:2012-07-17)
3 0 0 0 OA (書評)赤井節著「「ヘブライ法における同害報復の刑罰に就いて」(法制史研究第五号)」
- 著者
- 隈崎 渡
- 出版者
- 法制史学会
- 雑誌
- 法制史研究 (ISSN:04412508)
- 巻号頁・発行日
- vol.1957, no.7, pp.261-262, 1957-03-30 (Released:2009-11-16)
- 著者
- 一柳 俊夫
- 出版者
- 法制史学会
- 雑誌
- 法制史研究 (ISSN:04412508)
- 巻号頁・発行日
- vol.1966, no.16, pp.215-217, 1967-03-30 (Released:2009-11-16)
3 0 0 0 (書評)石尾芳久著「大政奉還と討幕の密勅」
- 著者
- 田中 彰
- 出版者
- 法制史学会
- 雑誌
- 法制史研究 (ISSN:04412508)
- 巻号頁・発行日
- no.30, pp.221-224, 1980
3 0 0 0 OA (書評)瀧川政次郎著「「告訴人拘禁法の源流」(国学院法学第一四巻第四号)」
- 著者
- 梅田 康夫
- 出版者
- 法制史学会
- 雑誌
- 法制史研究 (ISSN:04412508)
- 巻号頁・発行日
- vol.1978, no.28, pp.213-216, 1979-03-15 (Released:2009-11-16)
3 0 0 0 OA (書評)明治大学法学部八十五年史編纂委員会著「明治法律学校における 法学と法学教育」
- 著者
- 杉谷 昭
- 出版者
- 法制史学会
- 雑誌
- 法制史研究 (ISSN:04412508)
- 巻号頁・発行日
- vol.1968, no.18, pp.150-151, 1968-10-20 (Released:2009-11-16)
2 0 0 0 OA 平安期の死刑停止について
- 著者
- 梅田 康夫
- 出版者
- Japan Legal History Association
- 雑誌
- 法制史研究 (ISSN:04412508)
- 巻号頁・発行日
- vol.66, pp.1-37,en3, 2017-03-30 (Released:2023-01-13)
平安期において弘仁年間より保元の乱に至るまで、三百年以上にわたり正式な形で死刑が行なわれなかった。このことは古くから知られ、これまで各種の文献で取り上げられてきた。本稿ではまず前提となる問題として、死刑の廃止ではなく停止であること、そして停止の時期やその実態について確認した上で、そのような現象がもたらされた背景、原因について論じ、死刑停止の歴史的意義を究明せんとした。 これまで死刑停止の背景、原因については、様々なことが指摘されてきた。それらはいずれもその要因の一つであると考えられる。なかでもとりわけ怨霊の問題が最も重要視され、筆者自身もかつてそのように考えてきた。しかしながら、非業の死とは結びつかない犯行の明白な一般庶民による凶悪な犯罪についても死刑執行が宥恕される事例が存在することは、怨霊恐怖の点からだけでは十分に説明できない。また死刑が復活したことについてその理由等は従来あまり論じられず、それ以降も公家社会では死刑は基本的に忌避されていたとする見解さえ存在する。本稿では、死刑復活後は公家社会でも死刑が行なわれたということを前提として、死刑が復活した際における後白河天皇宣命案に関する分析等から穢の問題を最も重視し、この問題を穢を媒介として天皇と朝廷のあり方、王権の変容との関連から考察した。 保元の乱後に出された後白河天皇宣命案は、従来からも取り上げられてきた史料である。本稿では、乱の経緯とその後の処置について神前に報告するのが、死穢すなわち死の穢によって延滞したとある部分に特に注目した。死刑の執行によって、穢が重要な問題となっていたことがわかる。穢は九世紀半ば以降に制度化され、それは天皇が祭祀王として純化されていく過程と並行していた。天皇による死刑の裁可は死穢の忌避という点から次第に行なわれなくなり、また死刑の執行は觸穢による宮中・内裏への波及を防ぐ意味で回避されるようになった。 このようにして全く行なわれなくなった死刑が復活したのは、保元の乱という内乱の後であった。そこには単なる武家の台頭ということのみならず、朝廷と天皇をめぐる公家社会における大きな変化があった。祭祀王としての天皇の純化が完成した段階で院政という新たな政治形態が確立し、世俗王としての院=上皇が治天の君としての権力を行使することになった。そして、穢の観念が世俗化、希薄化し拡散していく中で、死刑への忌避感情もまたかつてのように厳格なものではなくなっていった。その結果、天皇の清浄性を保持しつつ、院=上皇による刑政への関与、死刑の裁可という途が開けていった。 死刑の停止は「薬子の変」、その復活は保元の乱という、いずれも上皇と天皇の対立、王権の分裂を契機に進行した。それは王権の変容過程の中で生起した、特殊な現象であったといえる。
2 0 0 0 OA 松本尚子著『ホイマン『ドイツ・ポリツァイ法事始』と近世末期ドイツの諸国家学』
- 著者
- 海老原 明夫
- 出版者
- Japan Legal History Association
- 雑誌
- 法制史研究 (ISSN:04412508)
- 巻号頁・発行日
- vol.67, pp.455-461, 2018-03-30 (Released:2023-11-30)
2 0 0 0 OA マヌ法典にあらわれた相続
- 著者
- 田邊 繁子
- 出版者
- Japan Legal History Association
- 雑誌
- 法制史研究 (ISSN:04412508)
- 巻号頁・発行日
- vol.1956, no.6, pp.28-63,en1, 1956-03-30 (Released:2009-11-16)
- 被引用文献数
- 1 1
Die nicht zur Beackerung an die Gemeindeglieder überwiesenen Stücke, kurz alles was nicht getheilt worden war, gehörten zur gemeinen Mark. Nach der Einbringung der Ernte erhielten auch die Äcker Allmendecha-rakter. Das Markrecht war eine Pertinenz des im markrechtigten Dorfe besessenen Hauses and Hofes. Wohnstatt and Ackerland sind mit dem gehorten Markrecht als ein Ganzes betrachtet and ebenfalls Hufe genannt worden. Daher hat es immer nur so viele Berechtigungen gegeben, als vollberechtigte Häuser and Höfe in den Dorfschaften vorhanden waren. Mit den Hausern and Höfen hat indessen auch die Anzahl der Markre-chten gewechselt.Die Antheile an der gemeinen Mark and die Markberechtigungen waren ursprünglich in einer and derselben Mark verhältnissmäßig gleich groß. Die Größe der Berechtigung richtet sick wesentlich offenbar, wie die Größe des Besitztums selbst, nach dem Bedürfnisse eines jeden Genossen. Durch spätere Ansiedlungen, Veräußerungen and Theilungen hat sick jedoch dieser ursprüngliche Stand der Dinge gänzlich verändert. Dazu kamen nun noch die Veräußerungen and Theilungen der einzelnen Höfe and der mit ihnen getrennten Marktheile in halbe and viertels Were, in gauze, halbe, drittels, viertels and sechstels Gewelden and Rotten, dann die Vereinigung oft sehr vieler Marktheile in einer and derselben Hand, wodurch die ursprüngliche Gleichheit der Berechtigung völlig vernichtet worden ist. Dieser gänzlich veränderte Zustand führte zu neuen Anor-dnungen und Einrichtungen. Die Art and Weise der Benutzung der ungetheilten Mark wurde von der Gemeinde genau regulirt, die Größe der Rechtigung nicht mehr nach dem Bedürfnisse eines jeden Genossen, sondern ein für alle Mal bestimmt oder jedes Jahr wieder neu bestim-mt, oder auch auf ein bestimmtes Quantum fixirt.Beisassens Marknutzung war eine bloße Begünstigung. Erst seit dem 16ten and 17ten Jahrhundert, hat sich dieses geändert, indem nun in manchen Dorfern auch die Kotter and anderen Beisassen als Gemeinde-genossen betrachtet worden sind.
2 0 0 0 OA 何故イングランド法制史はまだ書き上げられていないのか
- 著者
- ベイカー J.H.
- 出版者
- 法制史学会
- 雑誌
- 法制史研究 (ISSN:04412508)
- 巻号頁・発行日
- vol.1999, no.49, pp.107-133, 2000-03-30 (Released:2009-11-16)
- 著者
- 小菅 芳太郎
- 出版者
- Japan Legal History Association
- 雑誌
- 法制史研究 (ISSN:04412508)
- 巻号頁・発行日
- vol.1958, no.8, pp.315a-316, 1958
2 0 0 0 OA 西田友広著『鎌倉幕府の検断と国制』
- 著者
- 新田 一郎
- 出版者
- 法制史学会
- 雑誌
- 法制史研究 (ISSN:04412508)
- 巻号頁・発行日
- vol.62, pp.143-148, 2013-03-30 (Released:2018-04-04)
2 0 0 0 OA 高山博著『中世シチリア王国の研究―異文化が交差する地中海世界』
- 著者
- 西川 洋一
- 出版者
- Japan Legal History Association
- 雑誌
- 法制史研究 (ISSN:04412508)
- 巻号頁・発行日
- vol.66, pp.379-384, 2017-03-30 (Released:2023-01-13)
- 被引用文献数
- 1
2 0 0 0 古代ギリシア史研究と奴隷制
- 著者
- 伊藤 貞夫
- 出版者
- 法制史学会
- 雑誌
- 法制史研究 (ISSN:04412508)
- 巻号頁・発行日
- no.55, pp.121-154,10, 2005
近年におけるギリシア・ローマ経済史研究で目を惹くのは、M・I・フィンリーの古代経済論への諸家の対応である。プリミティヴィズムとモダニズムとの対抗として要約される、この種の研究視角は数多くの成果を生んできたが、そのなかにあってフィンリーの古代史観の一つの軸をなしながら、方法論的に十分な檢討と意義の評価を受けていないのが彼の奴隷制論である。その特徴は、古典期のアテネやローマ盛期のイタリア・シチリアに見られる大量かつ集中的な奴隷使役を、古典古代にあっても特殊な事例と看做し、相対化するところにある。小論は、前五世紀のクレタで刻されたゴルチュンの「法典」を中心に、関連の古典史料や金石文をも勘案しつつ、軍事的征服と負債とにそれぞれ起因する二種の中間的隷属状況の、古代ギリシアにおける広汎な存在を確認し、かつ後者の型の古典期アテネにおける存続を想定するP・J・ローズとE・M・ハリスの説を批判したのちに、都市国家市民団内部の民主化による中間的隷属者の消滅が代替労働力としての典型的奴隷の使役を促したとするフィンリーの試論を、古典古代社会の歴史的展開の理解に有用な視点を供するもの、と積極的に評価する。フィンリー説の背景にあるのは古代オリエントについての知見であるが、加うるに近代以前の中国と日本の身分制に関する研究成果を以てすべし、との提言で小論は閉じられる。
- 著者
- 河上 倫逸
- 出版者
- 法制史学会
- 雑誌
- 法制史研究 (ISSN:04412508)
- 巻号頁・発行日
- vol.1977, no.27, pp.342-344, 1978-03-30 (Released:2009-11-16)
2 0 0 0 OA ベケット論争と二重処罰禁止原則
- 著者
- 苑田 亜矢
- 出版者
- 法制史学会
- 雑誌
- 法制史研究 (ISSN:04412508)
- 巻号頁・発行日
- vol.61, pp.117-150,en8, 2012-03-30 (Released:2017-08-22)
本稿は、二重の危険〔の禁止〕の原則の歴史的起源を辿る際に必ず言及されてきたベケット論争における二重処罰禁止原則に焦点を当て、二重処罰禁止原則がカンタベリ大司教トマス・ベケット自身によって主張されたとする、従来の研究においては自明視されてきた点を、再検討するものである。ベケット論争とは、一二世紀後半にイングランド国王ヘンリ二世とトマスとの間で生じた、主として裁判管轄権をめぐる争いのことである。この論争の一契機となったのは、ヘンリ二世によって成文化された一一六四年のクラレンドン法であり、特に問題となった条項の一つが第三条である。第三条は、犯罪を行なった聖職者に対する世俗裁判権の行使を宣言しているとともに、教会裁判所における有罪判決に基づく聖職剥奪という制裁後の世俗裁判所における処罰を定めている。それ故にトマスは、聖職者の特権と二重処罰禁止原則を主張して、これに反対したとされている。従来の研究において、トマスが二重処罰禁止原則を主張したとする根拠として用いられてきた史料のほぼ全ては、トマスの死後に作成されたトマス伝等であり、それらはどれもトマス自身の手によるものではない。そこで、トマス自身の書翰の分析を試みたところ、トマスは、二重処罰禁止原則ではなく、例外なき聖職者の特権を主張したとみることができることが判明した。このトマスの主張は、当時の教会法理論と合致するものではない。というのは、ベケット論争開始から一一七〇年のトマス死去までの間、ボローニャ学派であれ、アングロ・ノルマン学派であれ、彼らの教会法理論の中では、二重処罰が容認されているからである。また、トマスの死後、教会法理論の中からは二重処罰容認の考えが消えるが、それに変わって登場するのは二重処罰禁止原則ではなく、聖職者の特権の主張である。二重処罰禁止原則を採用して主張する考え方は、ベケット論争当時、ボローニャ学派のみならず、イングランドでは、アングロ・ノルマン学派においても、国王においても、トマスにおいても、そして(大)司教達においても見られない。それが見られるのは、イングランドにおいては、トマスの死後に作成されたトマス伝等においてのみである。この点が、二重の危険の原則(或いは二重処罰禁止原則)の歴史的起源の文脈でベケット論争に言及する場合の注意点である。