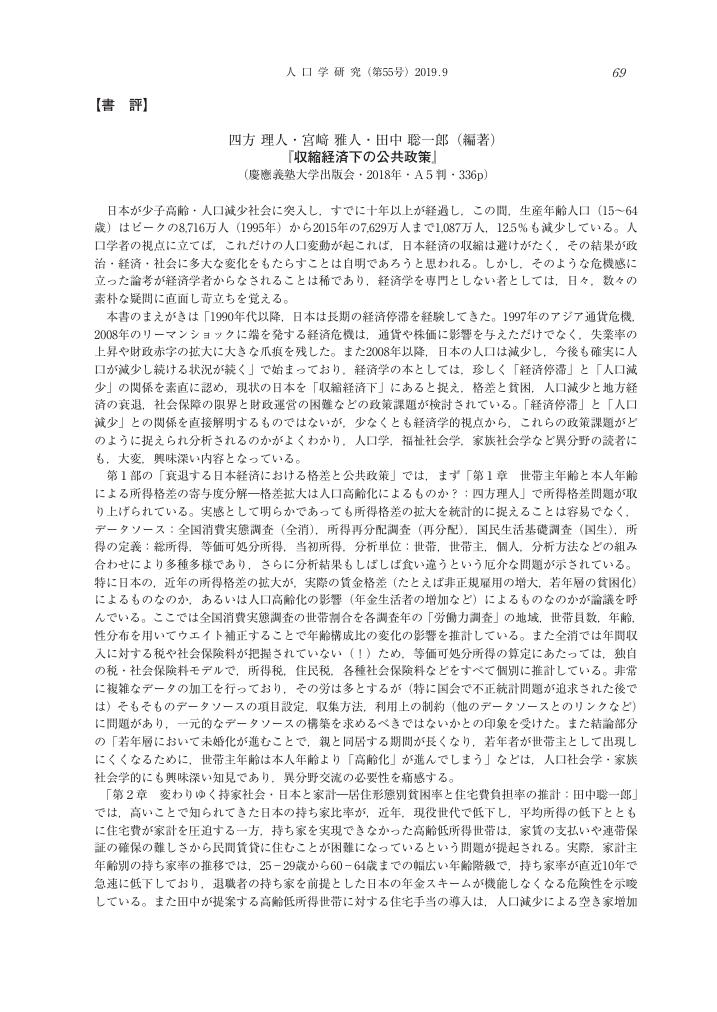5 0 0 0 OA 昭和41年「丙午」に関連する社会人口学的行動の研究
- 著者
- 坂井 博通
- 出版者
- 日本人口学会
- 雑誌
- 人口学研究 (ISSN:03868311)
- 巻号頁・発行日
- vol.18, pp.29-38, 1995-05-31 (Released:2017-09-12)
近年「丙午」研究の範囲が広がり, 1906年と1966年以外の「丙午」にも明かりが投げかけられると同時に1966年の「丙午」に関しては,ミクロデータを用いて出生間隔の研究もなされ始めた。しかし,今までの「丙午」研究は,次の3つの視点(1)「丙午」の影響が及んだ範囲, (2)「丙午」生まれの子ども側から見た特徴, (3)「丙午」が与えた社会人口学的影響,が欠けていると考えられるために, 1966年の「丙午」を例に検討を行った。「丙午」の影響が及んだ範囲に関しては,主に人口動態統計を用いて,「丙午」を含む前後20年の出生数,出生性比の動向を観察した結果, (1-1)在日韓国・朝鮮人や在日中国人, (1-2)外国在住の日本人, (1-3)非嫡出子に関しても「丙午」の影響が見られたことを確認し,「丙午」迷信の内容が,マスコミだけでなくパーソナルな伝播により普及した可能性が大きいことを示唆した。また,「丙午」の影響測定には,出生数と出生性比の両方を検討する必要を述べた。「丙午」生まれの子ども側から見た特徴に関しては,主に厚生省人口問題研究所が1985年に行った「昭和60年度 家族ライフコースと世帯構造変化に関する人口学的調査」(サンプル数7,708)の全国調査の分析により,他の年次生まれの子どもと比較して,「丙午」生まれの子どもは, (2-1)父方のおじ,おばは多くないが,母方のおじ,おばが多く,その母親の出産意欲に母親自身の兄弟姉妹数が正の影響を及ぼした可能性のあること, (2-2)特に第2子の場合,男女とも兄弟姉妹数が多いこと, (2-3)父がホワイトカラーの割合が大きく,迷信から自由な出産が多かった可能性があること, (2-4)「丙午」前後生まれの者も含めて「丙午」の迷信をよく知り,さらに,自分も「丙午であっても出産した」と答える割合が大きい,という知見を得た。「丙午」と関連する社会人口学的影響に関しては,人口動態統計と人口移動統計により,「丙午」の年において, (3-1)例年より低い3月の出生性比と例年より高い4月の出生性比, (3-2)低い移動性比, (3-3)女子の自殺の増加,自殺率の上昇, (3-4)母子世帯の増加と翌年の減少,「丙午」と翌年の性病罹患数の増加,を見出した。その原因に関しては,それぞれ,「丙午」と関連させて,「丙午」年度生まれの女子を忌避する届出操作,出産を控えた女子の人口移動の活発化,女性の価値の低下,家庭内禁欲に伴う家庭外性行動の活発化の観点から論じた。
- 著者
- 打越 文弥 麦山 亮太
- 出版者
- 日本人口学会
- 雑誌
- 人口学研究 (ISSN:03868311)
- 巻号頁・発行日
- vol.56, pp.9-23, 2020 (Released:2020-11-09)
- 参考文献数
- 26
本研究は職業構造の変化に着目して,日本における性別職域分離の趨勢について検討する。日本における根強い男女の不平等を理解するための示唆があるにもかかわらず,職域分離に関する知見は限られており,また一貫していない。本研究では,こうした趨勢に関する知見の非一貫性が,(1)職業分布の変化と(2)職業内における分離の変化を峻別してこなかった点に求め,両者を数量化して分けることの重要性を指摘する。本研究では性別職域分離は(1)日本の労働市場のジェンダーにおける特徴を規定していた製造業が衰退することと(2)専門職やサービス職が増加することによる職業分布の相対的な変化の2つによって変化するかを検証した。1980年から2005年の国勢調査を用いた分析から,以下の結果を得た。第一に,日本の職域分離の趨勢は僅かに減少傾向にある。第2に,分離の変化を分解した結果,職業分布の変化によって分離は拡大している。これに対して,性別構成効果は,職業内の分離を解消する方向に寄与していた。第3に,職業別の男女割合から,1980年時点で女性が多くを占めていた職業からの女性の移動が,日本の職域分離の変化を理解する際の重要な要因であることが新たな知見として明らかとなった。
5 0 0 0 OA 江戸町人の結婚・出生行動分析 : 1860年代末の日本橋・神田の戸籍資料による
- 著者
- 斎藤 修 友部 謙一
- 出版者
- 日本人口学会
- 雑誌
- 人口学研究 (ISSN:03868311)
- 巻号頁・発行日
- vol.11, pp.59-62, 1988-05-30 (Released:2017-09-12)
5 0 0 0 OA 女性事務職の賃金と就業行動 : 男女雇用機会均等法施行後の三時点比較
- 著者
- 寺村 絵里子
- 出版者
- 日本人口学会
- 雑誌
- 人口学研究 (ISSN:03868311)
- 巻号頁・発行日
- no.48, pp.6-22, 2012-06-30
本研究は,政府統計のリサンプリング・データを用いて,日本の女性労働者の最大多数の職種である女性事務職の賃金と就業行動の3時点(1992年,1997年,2002年)の変化を検証したものである。分析の結果,女性事務職はかつての米国同様に結婚(又は出産)退職まで働く若年層の仕事から中高年層の仕事へと広がりをみせていた。さらに賃金関数を推計すると,女性事務職については1997年時点から徐々に賃金は低下傾向にあった。また,事務職の中でも,中高年まで賃金を維持し続けることができるのは会計事務の仕事であり,正社員として会計事務で働くことはさらに正の効果をもたらしていた。事務職として勤めていた者の再就職についてみると,高学歴層である大卒・院卒者は三時点を通じてむしろ離職確率を高めていた。1992-2002年の間に限定すると,高い人的資本を持つ者が就業継続する(できる)ようになったとはいえない。高学歴化する女性事務職の活用について,さらなる検討が使用者である企業側にも求められる。
- 著者
- 原 俊彦
- 出版者
- 日本人口学会
- 雑誌
- 人口学研究 (ISSN:03868311)
- 巻号頁・発行日
- vol.55, pp.69-72, 2019 (Released:2019-10-25)
5 0 0 0 昭和41年「丙午」に関連する社会人口学的行動の研究
- 著者
- 坂井 博通
- 出版者
- 日本人口学会
- 雑誌
- 人口学研究 (ISSN:03868311)
- 巻号頁・発行日
- vol.18, pp.29-38, 1995
近年「丙午」研究の範囲が広がり, 1906年と1966年以外の「丙午」にも明かりが投げかけられると同時に1966年の「丙午」に関しては,ミクロデータを用いて出生間隔の研究もなされ始めた。しかし,今までの「丙午」研究は,次の3つの視点(1)「丙午」の影響が及んだ範囲, (2)「丙午」生まれの子ども側から見た特徴, (3)「丙午」が与えた社会人口学的影響,が欠けていると考えられるために, 1966年の「丙午」を例に検討を行った。「丙午」の影響が及んだ範囲に関しては,主に人口動態統計を用いて,「丙午」を含む前後20年の出生数,出生性比の動向を観察した結果, (1-1)在日韓国・朝鮮人や在日中国人, (1-2)外国在住の日本人, (1-3)非嫡出子に関しても「丙午」の影響が見られたことを確認し,「丙午」迷信の内容が,マスコミだけでなくパーソナルな伝播により普及した可能性が大きいことを示唆した。また,「丙午」の影響測定には,出生数と出生性比の両方を検討する必要を述べた。「丙午」生まれの子ども側から見た特徴に関しては,主に厚生省人口問題研究所が1985年に行った「昭和60年度 家族ライフコースと世帯構造変化に関する人口学的調査」(サンプル数7,708)の全国調査の分析により,他の年次生まれの子どもと比較して,「丙午」生まれの子どもは, (2-1)父方のおじ,おばは多くないが,母方のおじ,おばが多く,その母親の出産意欲に母親自身の兄弟姉妹数が正の影響を及ぼした可能性のあること, (2-2)特に第2子の場合,男女とも兄弟姉妹数が多いこと, (2-3)父がホワイトカラーの割合が大きく,迷信から自由な出産が多かった可能性があること, (2-4)「丙午」前後生まれの者も含めて「丙午」の迷信をよく知り,さらに,自分も「丙午であっても出産した」と答える割合が大きい,という知見を得た。「丙午」と関連する社会人口学的影響に関しては,人口動態統計と人口移動統計により,「丙午」の年において, (3-1)例年より低い3月の出生性比と例年より高い4月の出生性比, (3-2)低い移動性比, (3-3)女子の自殺の増加,自殺率の上昇, (3-4)母子世帯の増加と翌年の減少,「丙午」と翌年の性病罹患数の増加,を見出した。その原因に関しては,それぞれ,「丙午」と関連させて,「丙午」年度生まれの女子を忌避する届出操作,出産を控えた女子の人口移動の活発化,女性の価値の低下,家庭内禁欲に伴う家庭外性行動の活発化の観点から論じた。
4 0 0 0 OA 家族形成過程へのきょうだい数の影響
- 著者
- 廣嶋 清志
- 出版者
- 日本人口学会
- 雑誌
- 人口学研究 (ISSN:03868311)
- 巻号頁・発行日
- vol.6, pp.31-40, 1984-05-21 (Released:2017-09-12)
Since the middle of the 1970's, the major part of reproductive populatoin has been the generation born during the period of rapid fertility decline after the War. Author examined microscopically this trend through the observation of the effects of sibling number on marriage, birth etc., using survey data of 2,034 couples with at least one child younger than 6.25 years old. The main findings are as follows. (1) The effect of sibling number on school career has been robust and negative for both husband and wife and been strengthened for newer cohorts. (2) Residential relation which expresses whether a couple lives with or near their parents is negatively and strongly affected by the number of siblings. The number of siblings of spouse reversely affects it. (3) As for age at marriage, the indirect effects of sibling number is stronger through school career and co-residence with parents than direct effects. Nevertheless if wife is only child, which is assumed to be unadvantageous by the necessity to co-reside with her parents, wife's age at marriage is higher. But this effect has been being attenuated. Co-residence with parents or parent-in-laws has a positive effect on age at marriage for both husband and wife. Psychological cost accompanied by co-residence with parents may raise age at marriage. (4) School career of husband has positive effect on fertility. Indirect effect of sibling number through this can be inferred as negative. Effects through age at marriage are negative for wife and positive for husband. Direct effect of husband's sibling number on fertility is small but positive. These effects of sibling number allow us to speculate that the decrease in number of siblings has been one of the factors affecting the expansion in educational enrollment rate and also one of factors raising age at marriage through school career and co-residence with parents. The decrease in number of siblings is to continue for around 1965 birth cohort. Therefore changes in demographic behavior through the change of sibling number will last until the beginning of the 1990's.
4 0 0 0 OA 人口高齢化の経済問題(第29回大会シンポジウム報告論文)
- 著者
- 兼清 弘之
- 出版者
- 日本人口学会
- 雑誌
- 人口学研究 (ISSN:03868311)
- 巻号頁・発行日
- vol.1, pp.1-6, 1978-03-01 (Released:2017-09-12)
4 0 0 0 OA 小地域生命表のベイジアン・アプローチ
- 著者
- 府川 哲夫 清水 時彦
- 出版者
- 日本人口学会
- 雑誌
- 人口学研究 (ISSN:03868311)
- 巻号頁・発行日
- no.13, pp.37-49, 1990-05-30
都道府県別生命表の作成は,かなり以前から行われており,厚生省統計情報部でも昭和40年から5年ごとに作成している。これに対し,市区町村別生命表は,死亡数の少ない小地域で観察される死亡率の不安定性という困難な問題のため,あまり研究が進んでいない。しかし,このような小地域における死亡率の推定には,ベイズ統計学が強力な手法となることが明らかにされてきている。「地域別生命表に関する研究班」(主任研究者:鈴木雪夫 多摩大学教授・東京大学名誉教授)では,小地域生命表の作成にベイズ統計学の手法を適用して1989年3月に「1985年市区町村別生命表」を発表した。本論文では,上記研究班での研究をもとに,ベイズ統計学の手法を生命表作成に適用する際の方法論を,伝統的統計学の手法との比較を含めて検討し,ベイズ統計学を用いた効果を論じ,結果として得られた市区町村別平均寿命を用いて死亡水準に関する若干の地域分析を行った。市区町村別生命表における性・年齢階級別中央死亡率の推定は,当該市区町村を含むより広い地域の死亡率の情報を利用するという形でベイズ統計学の手法を適用している。この方法は,ある市区町村の死亡率の推定において,その市区町村を含むより広い地域の死亡率を当該市区町村における観測結果により補整するという点できわめて自然なものであるといえる。このため,性・年齢階級別の推定死亡率は安定し,その結果,ほとんど全ての市区町村で平均寿命に対する標準誤差が0.5年以内に収まることがわかった。北海道の全市区町村を例に,ベイズ統計学の手法を適用した場合と適用しない場合の,女の平均寿命に対する標準誤差を比較してみると,全ての市区町村でベイズ統計学の手法を適用した場合の方が精度がよく,特に人口規模の小さい市町村においてその効果が顕著であることがいえる。市区町村別生命表の結果を用いて地域の死亡率の特徴を考察すると, (1)長野,岐阜,静岡の3県は男の平均寿命が高い市町村が多いが,男の90歳以上の死亡率は全国平均値より高い, (2)有明海沿岸の市町村は男女とも比較的平均寿命が高いが,特に女の80歳以上の死亡率はきわだって低い,等のことがわかった。このように,市区町村別生命表の結果を用いて,従来観察できなかった小地域の死亡水準に関する分析が可能となった。
4 0 0 0 OA 小地域生命表のベイジアン・アプローチ
- 著者
- 府川 哲夫 清水 時彦
- 出版者
- 日本人口学会
- 雑誌
- 人口学研究 (ISSN:03868311)
- 巻号頁・発行日
- vol.13, pp.37-49, 1990-05-30 (Released:2017-09-12)
都道府県別生命表の作成は,かなり以前から行われており,厚生省統計情報部でも昭和40年から5年ごとに作成している。これに対し,市区町村別生命表は,死亡数の少ない小地域で観察される死亡率の不安定性という困難な問題のため,あまり研究が進んでいない。しかし,このような小地域における死亡率の推定には,ベイズ統計学が強力な手法となることが明らかにされてきている。「地域別生命表に関する研究班」(主任研究者:鈴木雪夫 多摩大学教授・東京大学名誉教授)では,小地域生命表の作成にベイズ統計学の手法を適用して1989年3月に「1985年市区町村別生命表」を発表した。本論文では,上記研究班での研究をもとに,ベイズ統計学の手法を生命表作成に適用する際の方法論を,伝統的統計学の手法との比較を含めて検討し,ベイズ統計学を用いた効果を論じ,結果として得られた市区町村別平均寿命を用いて死亡水準に関する若干の地域分析を行った。市区町村別生命表における性・年齢階級別中央死亡率の推定は,当該市区町村を含むより広い地域の死亡率の情報を利用するという形でベイズ統計学の手法を適用している。この方法は,ある市区町村の死亡率の推定において,その市区町村を含むより広い地域の死亡率を当該市区町村における観測結果により補整するという点できわめて自然なものであるといえる。このため,性・年齢階級別の推定死亡率は安定し,その結果,ほとんど全ての市区町村で平均寿命に対する標準誤差が0.5年以内に収まることがわかった。北海道の全市区町村を例に,ベイズ統計学の手法を適用した場合と適用しない場合の,女の平均寿命に対する標準誤差を比較してみると,全ての市区町村でベイズ統計学の手法を適用した場合の方が精度がよく,特に人口規模の小さい市町村においてその効果が顕著であることがいえる。市区町村別生命表の結果を用いて地域の死亡率の特徴を考察すると, (1)長野,岐阜,静岡の3県は男の平均寿命が高い市町村が多いが,男の90歳以上の死亡率は全国平均値より高い, (2)有明海沿岸の市町村は男女とも比較的平均寿命が高いが,特に女の80歳以上の死亡率はきわだって低い,等のことがわかった。このように,市区町村別生命表の結果を用いて,従来観察できなかった小地域の死亡水準に関する分析が可能となった。
- 著者
- 原 俊彦
- 出版者
- 日本人口学会
- 雑誌
- 人口学研究 (ISSN:03868311)
- 巻号頁・発行日
- vol.54, pp.69-72, 2018 (Released:2018-10-15)
3 0 0 0 OA 明治・大正・昭和戦前期における死産統計の信頼性
- 著者
- 村越 一哲
- 出版者
- 日本人口学会
- 雑誌
- 人口学研究 (ISSN:03868311)
- 巻号頁・発行日
- vol.49, pp.1-16, 2013-06-30 (Released:2017-09-12)
本稿は,死産統計の信頼性を明治,大正および昭和戦前期を対象として検討することを目的とした。まず大阪府の「墓地及埋葬取締細則」と「産婆規則」の内容を提示し,死産の無届を減らす方向に作用したと指摘されている1884(明治17)年の「墓地及埋葬取締規則」だけでなく,1899(明治32)年に定められた「産婆規則」が「墓地及埋葬取締細則」を改正させ,それがさらなる死産の無届減少につながったのではないかと推測した。20世紀に入っても死産統計の精度が高まる余地が残されていたという主張である。では20世紀において届出改善が進んだのはいつか,そして届出が改善された後の死産統計は信頼できるのか。つぎにこれらの問いのうち,前者つまり無届が減少した時期を,死産率と新生児死亡率の動きから検討した。母体の健康状態の影響を直接受ける死産率と新生児死亡率は,上昇する場合,低下する場合のいずれであっても同じ方向に動く傾向にあることを説明したうえで,1900年代の死産率と新生児死亡率は整合的な動きをしていないことを示した。そこからいまだ届出改善が進みつつあったのではないかと推測したのである。他方,1910年以降の両死亡率の動きは整合的であることから届出改善が進んだ結果と解釈した。さらに,先に示した問いのうち,届出が改善された後の死産統計は信頼できるのかという問いについて検討した。無届が減少した後にも新生児死亡(出生後の子どもの死亡)を死産として届け出るという「届出違い」が残存していたことから,「届出違い」数を推計し,そのことをとおして1910年以降における死産統計の精度を明らかにしようと試みた。昭和戦前期を基準としたとき,登録死産数に占める推計された「届出違い」数の割合は,1910年代では最大20%,また1920年代前半では最大10%であった。明治末年から大正期においては,いまだ無視できないほどの届出違いが残存していたのである。いいかえれば,登録死産数の最大10%から20%を除けば現実に近い死産率を求められるという程度の精度であったということである。
3 0 0 0 OA 雇用形態が男性の結婚に与える影響
- 著者
- 趙 〓 水ノ上 智邦
- 出版者
- 日本人口学会
- 雑誌
- 人口学研究 (ISSN:03868311)
- 巻号頁・発行日
- vol.50, pp.75-89, 2014-06-30 (Released:2017-09-12)
- 被引用文献数
- 1
本研究の目的は,晩婚化・非婚化問題の原因解明のため,男性の結婚に焦点を当て,男性の結婚経験は雇用形態によりどのような影響を受けているのかについて「就業構造基本調査(平成19年)」(総務省)を用いて実証的に分析することである。本稿では,女性は結婚相手の選択に際し,男性の将来所得を示すシグナルを観察し,それを基に結婚を決定しているという仮説を立てる。男性の将来所得のシグナルとしては,現在の雇用形態(正規雇用,非正規雇用),初職の雇用形態,職業や学歴などが利用されると考えられる。上記仮説を,「就業構造基本調査」の個票データを用いて検証し,男性の結婚経験率に与える要因を分析した。さらに,その要因が年齢階級によってどのように変容するのかを分析している。分析結果から得られた知見は次の通りである。第1に,将来所得のシグナルである雇用形態が,全年齢階級にわたって男性の結婚経験に影響を与える。具体的には非正規雇用と非就業であることが結婚経験率を低下させる。第2に,初職の雇用形態が非正規であったことは,それ以前の世代とは異なり,バブル崩壊以後に大学を卒業した世代に対して結婚経験の確率を低下させた可能性がある。第3に,学歴は20代から30代においては将来所得のシグナルとして有効ではなく,むしろ高学歴であることは若年層において結婚のタイミングを遅らせる効果を持つことが明らかになった。
- 著者
- 原 俊彦
- 出版者
- 日本人口学会
- 雑誌
- 人口学研究 (ISSN:03868311)
- 巻号頁・発行日
- pp.1904003, (Released:2019-08-01)
3 0 0 0 OA 出生力に対する公務員的就業環境効果の分析
- 著者
- 新谷 由里子
- 出版者
- 日本人口学会
- 雑誌
- 人口学研究 (ISSN:03868311)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, pp.41-50, 1999-12-01 (Released:2017-09-12)
3 0 0 0 OA 移民第二世代の教育達成に見る階層的地位の世代間変動─高校在学率に注目した分析─
- 著者
- 是川 夕
- 出版者
- 日本人口学会
- 雑誌
- 人口学研究 (ISSN:03868311)
- 巻号頁・発行日
- vol.54, pp.19-42, 2018 (Released:2018-10-15)
- 参考文献数
- 52
日本の移民研究では1990年代以降,外国籍人口の急増に伴い,移民第二世代の教育問題が注目されてきている。これは,社会的統合を重視する欧米の移民研究において特に重視されて来た論点であり,同論点の検証に当たっては,移民第二世代が学校で実際に経験する困難さだけではなく,親の階層的地位や移民の編入様式に注目する「分節化された同化理論」など,広く社会構造との関連を視野に入れた分析枠組みが用いられてきた。しかしながら,日本では移民第二世代の学校文化への適応に焦点を当てた臨床的なアプローチは数多く行われて来たものの,複数の移民集団に横断的な教育達成の状況やその要因についてナショナルレベルのデータから明らかにした研究はまれであった。また,その際,分節化された同化理論が想定するように,親世代の階層的地位や編入様式など,広く社会構造との関係に注目した研究は少なかったといえよう。こうした状況を受け,本研究では国勢調査の個票データを用いて,母親の国籍別に見た子どもの高校在学率に焦点を当てた研究を行うことで,移民第二世代の教育達成の状況とその要因について明らかにする。また,分節化された同化理論に基づくことで,移民第一世代と第二世代の階層的地位の世代間変動に注目した分析を行う。その結果,外国籍の母を持つ子どもの場合,日本人の母を持つ場合と比較してその高校在学率は低い傾向にあるものの,それは移民第二世代一般に見られる傾向であり,親世代での階層的地位と子どもの高校在学との結びつきは相対的に弱いことが示された。つまり,分節化された同化理論は日本には妥当しない可能性が高いといえる。その一方で,移民の低い教育達成は,子ども自身の日本国内での居住期間の長期化に伴う日本社会への適応によって自然と解消する可能性が低いことも示された。これは多言語での情報提供や日本語教室など教育現場に対する今後のより一層の政策的支援の必要性を示すものである。
- 著者
- 原 剛
- 出版者
- 日本人口学会
- 雑誌
- 人口学研究 (ISSN:03868311)
- 巻号頁・発行日
- no.18, pp.84-85, 1995-05-31
3 0 0 0 OA 人口高齢化と福祉政策の課題 : スウェーデンの経験に学ぶ
- 著者
- 丸尾 直美
- 出版者
- 日本人口学会
- 雑誌
- 人口学研究 (ISSN:03868311)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, pp.5-14, 1994-05-31 (Released:2017-09-12)
In this paper I tried to show how the ageing of the population influences the change in the growth of employment, employment structure, the savings ratio, economic growth and the cost of social security. In the latter part of the paper I suggested a close correlation between the average marriadge age of woman, the total fertility rate and the work participation ratio of woman. According to the latest demograghic forecast by the Japanese Government, the proportion of the elderly (65 years old and over) to the total population will be 17% in 2000 and more than 25% in the 2020s respectively. On the other hand, the productive age population between 15 and 64 years old, which has been increasing, is forecast to decline from the middle of the 1990s. As a result, the proportion of the aged to the working population will increase markedly. The correlation between the proportion of the elderly and the social security benefits / national income ration is quite high. Simple regressions (OLS) suggest that the percentage ratio of elderly people in the working population (No/Nw in regression (1)〜(2)) is one of the main variables that explain the behaviour of the percentage ratios of social security benefits in national income as the following regressions show. [numerical formula](1) [numerical formula](2) Based on the 1960〜1991 annual data. B: Social security benefits, Y: National income, Nw: Total working population=productive age population multiplied by (1-u), No: Population of the elderly (65 years old and over), u: Unemployment ratio as a ratio of total working force, U_2: Unemployment as a ratio of employees, dw/w: Rate of increase of employees compensation per employee, Bm: Social insurance benefits for health service, D_1: Dummy variable 1960〜1973=0, 1974〜1988=1. This dummy variable explains the change in political situation since 1973. 1973 was called the "First year of welfare"., R^^-^2: Adjusted determinant coefficent, D.W.: Durbin Watson ratio, Figures in parentheses under coefficients of explainig variables are t statistics. The correlation between the work participation ratio, the average marriadge age of woman and the total fertility rate is also impressive as Fig. 9 and 10 show. However, the correlation is not inevitable as the recent experience in Sweden suggests. Active family policy based on universalism must be introduced in Japan.
3 0 0 0 OA 若年の勤労観,就業行動と出生率の変化
- 著者
- 古郡 靹子
- 出版者
- 日本人口学会
- 雑誌
- 人口学研究 (ISSN:03868311)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, pp.45-55, 1992-05-30 (Released:2017-09-12)
本稿では,若年の勤労観,就業行動の変化の実態を把握し,それを人口問題の主要課題である出生率の低下現象との関係で分析・検討する。若年の就業行動の変化は,アルバイトの日常化,フリーター的労働者の出現,離転職(希望)者の増加などに特徴的に表われている。最近の若年層は従来の雇用形態やライフスタイルとは違った,より自分流の経済関与のあり方を選択してきている。離転職関数の時系列分析と横断面分析を行なった結果は,景気変動のような一時的な要因に加え,人口構造の変化や仕事の選択基準の変化が若年の就業行動を変えてきていることを示している。若年者は,労働時間の長い企業,仕事の多すぎる企業を敬遠するようになってきた。これは,生活水準の向上とそれにともなう社会観,人生観の変化を反映したものであろう。若年層の就業行動の変化は,その勤労観の変化と呼応したものである。物質的な欲望が充足され,生活が安定すると,個人の生活を犠牲にしてまで働こうとする者が少なくなってくる。各種の調査は,最近の若年者が仕事志向型から仕事と余暇の両立志向型に移ってきていること,いわゆる会社人間となって組織に縛られることを嫌う者が増えていることを明らかにしている。若年者の意識や就業行動の変化は,当然,結婚や出産の行動にも反映する。ベッカー流のモデルに従い,出生率の分析を行なってみると,女子の市場賃金に加えて,余暇・娯楽時間の動向が出生率を左右する要因になっている。物質的な経済原則のもとでは,若年の余暇・娯楽志向が強まり,その上に子供の養育に費用もかかりすぎるとなると,それが出生率に影響を与えるのも当然のことだろう。わが国では晩婚化が進み,出生率は低下の一途をたどってきた。しかし,出生率を上げることが望まれるならば,税制による優遇措置,児童手当の引き上げのような直接経済的な施策もさることながら,子供を育てる上での障害を取り除き,心にゆとりのある生活ができるような社会環境を整備することも大事だろう。それには,たとえば,労働時間の短縮,雇用形態の弾力化,育児休業制度,教育制度の改革,職場環境の整備などを行なう必要がある。
3 0 0 0 OA 人口高齢化時代の子供と老人
- 著者
- 河野 稠果
- 出版者
- 日本人口学会
- 雑誌
- 人口学研究 (ISSN:03868311)
- 巻号頁・発行日
- vol.13, pp.5-13, 1990-05-30 (Released:2017-09-12)
本論文は,人口高齢化の影響について,特に子供と老人という従属人口の二つのグループを取り上げ,彼等の相対的経済的地位,彼等の生活の質が高齢化社会の到来によってどのように変化して行くのかを考察することを目的とする。出生率が低下し,中高年の死亡率が改善されれば,人口高齢化が起こり,年少人口は相対的においても実数においても増加する。そうなれば年少人口が社会経済的に有利であり,逆に老年人口は不利なことばかりだろうか。これに対し,プレストンは事実は全く逆だと主張する。人口高齢化の状況において老人の生活はむしろ良くなっており,むしろ割を食うのは年少人口であると論ずる。本報告は,年少人口が相対的に小さいことがその構成員に必ずしも有利な条件を与えないこと,逆に数の大きい老年人口はその数の大いさのためにむしろ良い効果を生ずるという"プレストン効果"が,日本の場合に当てはまるかどうかを検証しようとした。ここで2種類のデータを用いた。一つは「厚生行政基礎調査」による支出データであり,他は総務庁の「全国消費実態調査」による所得データである。前者は1975, 80, 85年の3年次に対するものであり,後者は1979年と84年の2年次のものである。そこで,個票の段階にまで遡り, equivalence scaleという世帯の規模による修正係数で一々を割り,インフレーターを掛けて時系列比較を可能にし,ついで世帯の殻をとって,世帯員個人のデータを年齢別に集計したものである。以上の分析の結論は,日本においてもプレストン効果が意外に見られるのではないかという点である。過去10年間をとってもわが国の生活水準は老若を問わず向上した。その全般的向上のために,プレストン効果は必ずしも格別に明らかではないが,少なくともこれまで高齢化によって老人の生活は悪くなっていないし,むしろ子供と比較して恵まれた状況になりつつあることは紛れもない事実だと思われる。人口高齢化の過程で,弱者は高齢者だけだというのは思い込みである。社会的弱者は従属人口の二つのカテゴリーである老人と子供だとして,複眼的に人口現象を眺める必要がある。