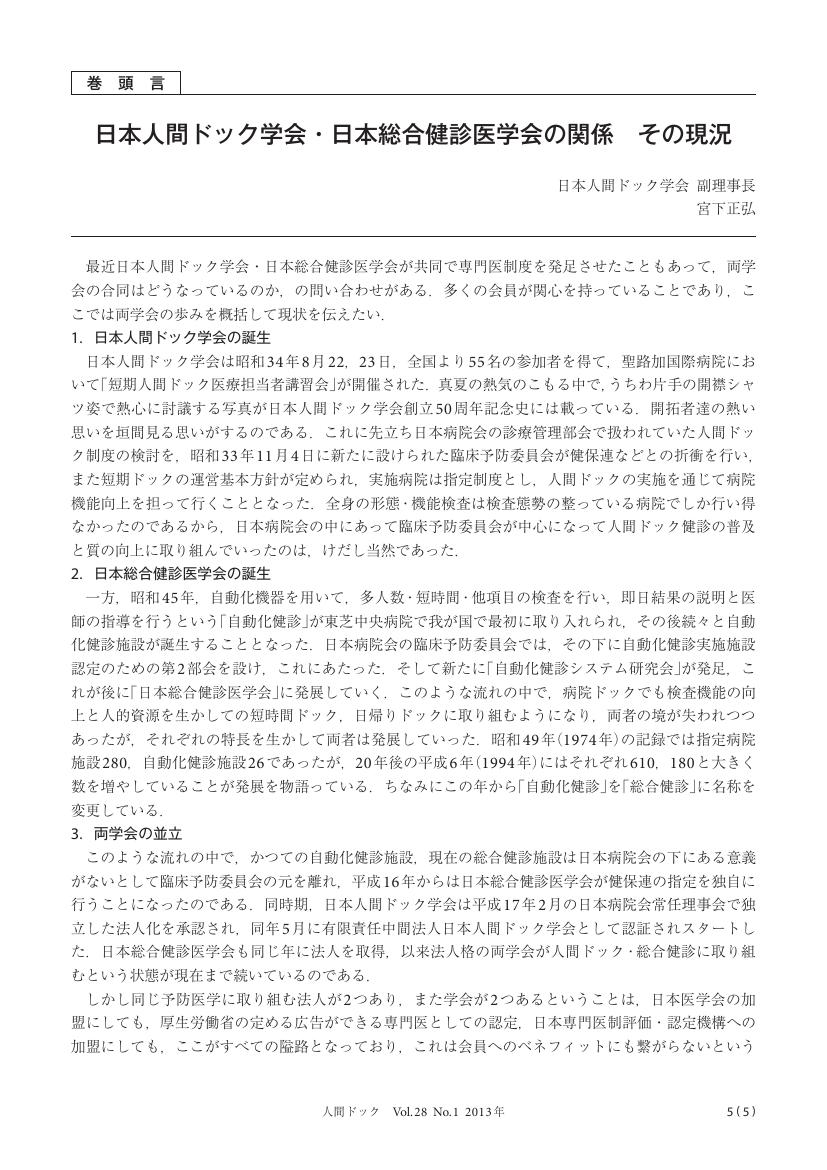1 0 0 0 OA 随時尿から早朝尿への変更による尿蛋白・尿潜血陽性率の減少および運用面の変化
- 著者
- 馬嶋 健一郎 佐々木 美和 星野 絵里 島本 武嗣 村木 洋介
- 出版者
- 公益社団法人 日本人間ドック学会
- 雑誌
- 人間ドック (Ningen Dock) (ISSN:18801021)
- 巻号頁・発行日
- vol.32, no.3, pp.476-481, 2017 (Released:2017-12-22)
- 参考文献数
- 24
目的:健診の尿検査において,随時尿と早朝尿での尿蛋白陽性率,尿潜血陽性率および運用面での変化を検討した.方法:亀田メディカルセンターの健診受診者のうち,2012年6~10月までの随時尿群2,619名と,2013年6~10月までの早朝尿群2,512名を対象とした.主要な評価項目として随時尿群と早朝尿群の尿蛋白陽性率を比較し,尿蛋白を減少させる要因についてロジスティック回帰分析にて検討した.副次的評価項目として,尿潜血陽性率の変化を検討し,運用面の変化や受診者の流れなどを調査した.結果:尿蛋白陽性率は随時尿群3.9%(102/2,619),早朝尿群1.8%(45/2,512)であり,有意に早朝尿において低かった.また,ロジスティック回帰分析では,早朝尿は尿蛋白陽性率低下の独立した要因だった.尿潜血陽性率は随時尿群で陽性は6.2%(162/2,619),早朝尿群では1.8%(45/2,512)であり,有意に早朝尿において低かった.運用面では,早朝尿導入で看護スタッフの問診終了時間が早くなった.結論:随時尿に比べ,早朝尿検査は尿蛋白陽性率を減らすことができ,運営面では人間ドックの流れがスムーズになることが期待される.
1 0 0 0 OA 脳ドックのガイドライン2008について
- 著者
- 小林 祥泰
- 出版者
- 公益社団法人 日本人間ドック学会
- 雑誌
- 人間ドック (Ningen Dock) (ISSN:18801021)
- 巻号頁・発行日
- vol.24, no.1, pp.7-16, 2009 (Released:2013-09-30)
1 0 0 0 OA 大腸がん検診の現状と今後の展望
- 著者
- 加藤 智弘 伊藤 恭子
- 出版者
- 公益社団法人 日本人間ドック学会
- 雑誌
- 人間ドック (Ningen Dock) (ISSN:18801021)
- 巻号頁・発行日
- vol.33, no.1, pp.7-21, 2018 (Released:2018-08-16)
- 参考文献数
- 89
近年の大腸がんの高い罹患率により大腸がんによる死亡率も高くなり,現在のところ,がん死亡率でみると,男性では3位,女性では1位となっており,診断・治療とともに,その発見も重要な課題項目といえる.その点で大腸がん検診スクリーニングは大きな役割が期待されている.しかしながら,毎年ある程度の受診件数があるものの,精密検査対象者の受診率は他のがんと比較すると圧倒的に低い.このような背景のもと,本稿では大腸がん検診スクリーニングに関する現状と,関連する多くの検査手段について概観した.すなわち,検診のうち,対策型検診で中心となる便潜血検査法について,また,任意型検診,あるいは対策型検診の精密検査対象者への検査として,従来の検査法に加えて,新たな有力な検査法のいくつかについても概説を行った.これらの検査のメリット・デメリットを十分に理解することで,検診受診者に対しては,その情報を還元することにより,結果として,大腸がんの発見,ひいては死亡率の低下をもたらすことに繋がると思われる.
1 0 0 0 OA 健診者におけるびらん性および非びらん性胃食道逆流症の臨床的検討
- 著者
- 船津 和夫 斗米 馨 栗原 浩次 本間 優 山下 毅 細合 浩司 横山 雅子 近藤 修二 中村 治雄
- 出版者
- 公益社団法人 日本人間ドック学会
- 雑誌
- 人間ドック (Ningen Dock) (ISSN:18801021)
- 巻号頁・発行日
- vol.22, no.5, pp.811-817, 2008-03-31 (Released:2012-08-20)
- 参考文献数
- 15
- 被引用文献数
- 1
目的:医療機関受診者に比べ一般健康人により近い健診受診者を対象として,胃食道逆流症(gastroesophagealreflux disease:GERD)の実態調査を施行した.方法:上部消化器疾患で治療中の人を除いた胃内視鏡検査受診者659名(男性368名,女性291名)を対象とした.内視鏡所見とfrequency scale for the symptoms of GERD(FSSG)問診票のスコアを基に対象者をびらん性胃食道逆流症(erosive gastroesophageal reflux disease:e-GERD),非びらん性胃食道逆流症(nOn-erosivegastroesophagealreflux disease:NERD),非GERDの3群に分け,各群の性別発見頻度と血糖,血清脂質,高感度C-反応性蛋白(CRP)などの生活習慣病関連因子,血圧,ならびにメタボリックシンドロームの合併率を比較検討した.結果:NERDの頻度は男女ともe-GERDより多かった.e-GERDは女性より男性に高頻度でみられ,NERD,非GERDに比べ,血圧が高く,血糖,血清脂質,高感度CRPなどがより高値を呈し,メタボリックシンドロームの合併率が高かった.一方,NERDはやぜ気味の人に多くみられ,血糖,血清脂質,高感度CRP,血圧は非GERDよりもさらに低値を示し,メタボリックシンドロームの合併率も3群のなかで最も低かった.結論:e-GERDは肥満に起因する生活習慣病の1つと考えられたが,NERDはやぜ気味の人に多くみられ,生活習慣病関連因子の異常が少ないことから,e-GERDとは異なる病態を有することが示唆された.
1 0 0 0 OA 多量飲酒者に対する通常の特定保健指導の効果 -非飲酒者,少量飲酒者との比較-
- 著者
- 豊田 将之 村本 あき子 津下 一代
- 出版者
- 公益社団法人 日本人間ドック学会
- 雑誌
- 人間ドック (Ningen Dock) (ISSN:18801021)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, no.1, pp.39-47, 2016 (Released:2016-09-29)
- 参考文献数
- 12
目的:多量飲酒者に対する特定保健指導の効果を検証するため,特定保健指導の初回支援から6ヵ月後の飲酒習慣と検査データについて検討を行った.方法:同一健康保険組合の積極的支援終了者のうち,今回初めて特定保健指導に参加した男性555名を対象とした.特定保健指導の初回支援時(以下,初回支援時)に飲酒量を確認した.毎日飲酒・エタノール量40g/日以上群,毎日飲酒・エタノール量40g/日未満群,飲酒時々・なし群の3群に分け,特定健康診査時の検査データを群間比較,保健指導前後の検査データの群内比較を行った.さらに,毎日飲酒・エタノール量40g/日以上群内で,6ヵ月後のエタノール量20g/日以上減酒の有無,初回支援時の減酒計画立案の有無によりそれぞれ2群に分け,6ヵ月後までの検査データ変化量の群間比較を行った.保健指導の方法は3群で共通であり,初回はグループ支援で実施した.結果:特定健康診査時には3群間で体重,脂質,肝機能,血糖に有意差があった.保健指導前後比較において3群ともに有意な減量,検査データ改善がみられた.毎日飲酒・エタノール量40g/日以上群のうち減酒の有無2群間比較では,体重減少が減酒あり群で1.81±2.49kgであったのに対し,減酒なし群では0.33±2.46kg減少と有意差を認めた.BMI,腹囲,AST,γ-GTPの各変化量は減酒あり群で有意に大きかった.減酒計画の有無では有意差はみられなかった.結論:特定保健指導による減量および検査データ改善効果は,飲酒量が多い対象者にも一定の効果がみられた.特にエタノール量が20g/日以上減少した群で改善効果が大きかった.
1 0 0 0 OA 日本人男性における内臓脂肪面積からみるメタボリックシンドローム診断基準の有用性の検討
- 著者
- 長岡 芳 鍵小野 美和 藤田 紀乃 和田 昭彦 松井 寛 大橋 儒郁 飯田 忠行
- 出版者
- 公益社団法人 日本人間ドック学会
- 雑誌
- 人間ドック (Ningen Dock) (ISSN:18801021)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, no.3, pp.539-546, 2011 (Released:2012-03-27)
- 参考文献数
- 37
目的:メタボリックシンドローム(以下,MSとする)の診断基準について,腹部CTにおける内臓脂肪面積を至適基準として腹囲判定および腹囲判定後の診断基準の妥当性を検討した.対象と方法:男性194名を対象とした.検査項目は,年齢(歳),身長(cm),体重(kg),BMI,腹囲(cm),最高血圧(mmHg),最低血圧(mmHg),HDLコレステロール(mg/dL),トリグリセリド(mg/dL),空腹時血糖(mg/dL),内臓脂肪面積(cm2),皮下脂肪面積(cm2)とした.内臓脂肪面積を至適基準として腹囲判定の感度・特異度・陽性尤度比を計算し,妥当性を検討した.また,腹囲が異常でかつMS診断基準のうち2つ以上の異常値について,内臓脂肪面積を至適基準としてMS診断基準の感度・特異度・陽性尤度比を計算し,妥当性を検討した.結果:腹囲判定は見落とし率が低く,感度は高値であった.MS診断基準と内臓脂肪面積との関連は見出されなかった.結論:内臓脂肪面積とMS診断基準の関連において,腹囲判定は見落とし率が低く,感度からも有用と考えられる.腹囲判定後の診断基準については検討の必要性が示唆された.
1 0 0 0 OA 人間ドックにおける血尿の意義
- 著者
- 辻 裕之 遠藤 繁之 原 茂子 大本 由樹 天川 和久 謝 勲東 山本 敬 橋本 光代 小川 恭子 奥田 近夫 有元 佐多雄 加藤 久人 横尾 郁子 有賀 明子 神野 豊久 荒瀬 康司
- 出版者
- 公益社団法人 日本人間ドック学会
- 雑誌
- 人間ドック (Ningen Dock) (ISSN:18801021)
- 巻号頁・発行日
- vol.30, no.3, pp.563-569, 2015 (Released:2015-12-22)
- 参考文献数
- 11
目的:人間ドックにおける尿潜血の意義を検証する.方法:2011年2月からの1年間に虎の門病院付属健康管理センター(以下,当センター)人間ドックを受診した16,018例(男性10,841例,女性5,177例)について尿潜血の結果を集計し,推算糸球体濾過値(以下,eGFR)との関連を検討した.次に2008年から2011年の4年間に当センター人間ドックを受診したのべ58,337例(男性40,185例,女性18,152例)について,腹部超音波検査で腎・尿路結石,またその後の検索を含めて腎細胞がんおよび膀胱がんと診断された例について,受診時の尿潜血の結果を検討した.結果:年齢を含めた多変量解析を行うと,尿潜血とeGFR低値との間には有意な関係を認めなかった.また,超音波上腎結石を有する場合でも,尿潜血陽性を示すのはわずか18.5%に過ぎなかった.さらに,腎細胞がん例で8.3%,膀胱がんでも28.6%のみに尿潜血は陽性であった.結論:人間ドックにおいて尿潜血は従来考えられていたより陽性率が高いが,少なくとも単回の検尿における潜血陽性は,CKDや泌尿器科疾患を期待したほど有効には示唆していないと考えられた.今後,尿潜血陽性例の検索をどこまで行うのが妥当なのか,医療経済学的観点も加味した新たな指針が望まれる.
1 0 0 0 OA 最近の動向から見た子宮頸がん検診の判定と事後指導に対する提案
- 著者
- 岩崎 武輝 奥村 次郎 山本 嘉昭 松井 薫 水口 善夫 宇野 正敏
- 出版者
- 公益社団法人 日本人間ドック学会
- 雑誌
- 人間ドック (Ningen Dock) (ISSN:18801021)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, no.3, pp.531-538, 2011 (Released:2012-03-27)
- 参考文献数
- 16
目的:今までの子宮頸部細胞診のいわゆる日母分類からベセスダ新分類の移行に伴い,成績判定及び事後指導に関する日本人間ドック学会のガイドラインを再考する必要が出てきた.武田病院グループ健診施設の婦人科部門の子宮頸がん検診において,ベセスダ新分類を導入した判定基準を作成し,それを基に今後事後指導を実施したいと考える.方法:武田病院グループ5健診施設のうち,同一検査所に依頼している4施設の,2010年2月初めから6月末までの子宮頸がん検診受診者4,948人について,受診者年齢・ベセスダ分類・日母Class分類を行った.新分類に基づいて,健診施設としての判定及び診断をつけ,それに対応した事後指導表を新たに作成した.結果:武田病院グループの4健診施設における最近5ヵ月間の子宮頸がん検診受診者数は4,948人であった.ベセスダシステム2001分類では,異常なしを示すNILMは4,853人であった.従来の日母Class分類では,異常なしを示すClass I,IIは4,914人であった.異常なしに関して,単純に計算すると新分類(ベセスダ分類)では従来分類(日母分類)に比べて61人の減少,総受診者数の1.23ポイント減となった.主な原因は,採取方法による細胞数の不足によるものと考えられた.新分類では,NILMは異常なしの結果報告でよく,それ以外の診断のついた受診者はすべて受診勧奨となり,要精密検査の紹介状を必要とする事後指導が必要であった.新分類の結果に対する受診者への平易な説明文が重要と思われた.結論:NILM以外に判定された区分は,すべてD判定となり,事後指導が必要である.今後,現在学会で分類されているA,B,C,D,Eと子宮頸部細胞診結果の対応を,新しくベセスダ分類に対応した判定区分の新ガイドラインを学会としても設定すべきと考えられた.
1 0 0 0 OA 健康日本21がめざす,ライフスタイルとしての『こころ』の健康
- 著者
- 足達 淑子
- 出版者
- 公益社団法人 日本人間ドック学会
- 雑誌
- 人間ドック (Ningen Dock) (ISSN:18801021)
- 巻号頁・発行日
- vol.20, no.5, pp.968-977, 2006-03-31 (Released:2012-08-20)
1 0 0 0 OA 高尿酸血症と高インスリン血症の関連性について
- 著者
- 田邉 真帆 荒瀬 康司 辻 裕之 謝 勲東 大本 由樹 天川 和久 加藤 久人 有元 佐多雄 奥田 近夫 小川 恭子 岩男 暁子 尾形 知英 橋本 光代 四倉 淑枝 山本 敬 宮川 めぐみ 原 茂子
- 出版者
- 公益社団法人 日本人間ドック学会
- 雑誌
- 人間ドック (Ningen Dock) (ISSN:18801021)
- 巻号頁・発行日
- vol.27, no.3, pp.603-610, 2012 (Released:2012-12-27)
- 参考文献数
- 26
目的:高尿酸血症はインスリン抵抗性を基盤とするメタボリック症候群(MS)の一症候である.今回尿酸と耐糖能異常の関係を検討するため,高尿酸血症と高インスリン血症の関連について検討した.対象と方法:75g経口糖負荷試験(OGTT)を施行した人間ドック受診者全1,175例とOGTT糖尿病型を除外した1,007例の尿酸(UA)とインスリン(IRI)動態を検討した.UA>7.0mg/dLとUA≦7.0mg/dLに区分し,UA>7.0mg/dLを高尿酸値例(高UA群),UA≦7.0 mg/dLを正常尿酸値例(正常UA群)とした.さらにUA値を四分位に区分し第1四分位-第4四分位とした(Q1-4).IRI分泌ピーク値が負荷後30分である場合をIRI分泌正常型,IRI分泌ピーク値が負荷後60分以降である場合をIRI分泌遅延型とした.結果:血清UA値を四分位により分けた4グループの血糖曲線,IRI反応を比較したところ,UAが高いほど,血中血糖(PG)は軽度の上昇を示し,血中IRIは有意に高反応を示した.脂肪肝合併は全1,175例でも高UA群が56.5%(157/278),正常UA群が44.1%(396/897),糖尿病型を除外した1,007例においても高UA群が55.3%(141/255),正常UA群が40.8%(307/752)であり,高UA群に多くみられた.IRI分泌ではIRI分泌遅延型の頻度は全1,175例でも,糖尿病型を除外した1,007例においても高UA群の方が高率であった.結語:高尿酸血症は高インスリン血症と関連を認めた.
1 0 0 0 OA 日本人間ドック学会・日本総合健診医学会の関係 その現況
- 著者
- 宮下 正弘
- 出版者
- 公益社団法人 日本人間ドック学会
- 雑誌
- 人間ドック (Ningen Dock) (ISSN:18801021)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, no.1, pp.5-6, 2013 (Released:2013-09-30)
1 0 0 0 OA 「アミノインデックス技術」を用いた新規婦人科がんスクリーニング法の有用性
- 著者
- 宮城 悦子 沼崎 令子 中西 透 片岡 史夫 猿木 信裕 井畑 穰 伊藤 則雄 吉田 憲生 新原 温子 村松 孝彦 今泉 明 山本 浩史 高須 万里子 光島 徹 杤久保 修 山門 實 青木 大輔 平原 史樹
- 出版者
- 公益社団法人 日本人間ドック学会
- 雑誌
- 人間ドック (Ningen Dock) (ISSN:18801021)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, no.5, pp.749-755, 2012 (Released:2012-07-13)
- 参考文献数
- 17
目的:血漿中アミノ酸濃度はがんを含む各種疾患により変化する.血漿中アミノ酸プロファイルから健康状態や疾病の可能性を把握する「アミノインデックス技術」は複数がんのスクリーニング法として臨床実用化されている.本研究は多施設共同試験により3種の婦人科がん(子宮頸がん,子宮体がん,卵巣がん)の判別を行う指標式を「アミノインデックス技術」を用いて導出し,その有用性を検討することを目的とした.方法:複数施設で子宮頸がん患者208例,子宮体がん患者186例,卵巣がん患者102例,婦人科良性疾患患者305例,健康人1,631例を対象として採血し,血漿中アミノ酸濃度をLC-MSにより測定した.結果:3種の婦人科がん患者の血漿中アミノ酸濃度変化は共通性が高く,婦人科がんのいずれかに罹患している可能性を判別する一つの指標式を「アミノインデックス技術」を用いて導出し,その判別性能評価を行った.導出された指標式の特異度95%での感度は子宮頸がん52%,子宮体がん58%,卵巣がん77%であり,いずれもⅠ期症例から高い感度を示した.また,子宮頸がんでは腺癌も高い感度を示す,子宮体がんではCA125より有意に感度が高い,卵巣がんではCA125と同程度の感度を示すなどの特徴を有していた.結論:「アミノインデックス技術」により導出された,3種の婦人科がんのいずれかに罹患している可能性を評価する一つの指標式は,3種の婦人科がんの簡便な血液検査のスクリーニング法として有用であることが示唆された.
1 0 0 0 OA 血漿中アミノ酸濃度変化を利用した前立腺がんの診断
- 著者
- 三浦 猛 岡本 直幸 今泉 明 山本 浩史 村松 孝彦 山門 實 宮城 洋平
- 出版者
- 公益社団法人 日本人間ドック学会
- 雑誌
- 人間ドック (Ningen Dock) (ISSN:18801021)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, no.1, pp.51-55, 2011 (Released:2012-08-03)
- 参考文献数
- 13
- 被引用文献数
- 2
目的:血漿中アミノ酸濃度は,生理学的な代謝状態を反映することが知られており,肝臓機能障害時や種々のがんで血漿中アミノ酸濃度が変化することが示唆されている.前立腺がんの早期発見,治療につながる新しい診断マーカーの開発を目的とし,前立腺がん患者と対照者との血漿中アミノ酸濃度の比較に基づき,アミノ酸を変数とした多変量解析により作成した判別式「アミノインデックス」による前立腺がん判別の可能性を検討した.方法:前立腺がん患者と対照として人間ドック受診者の血漿中アミノ酸濃度を測定した.患者群と対照群とのアミノ酸濃度を比較し,個々のアミノ酸濃度変化を,変数選択を伴う多重ロジスティック回帰により,前立腺がん患者を判別する判別式「アミノインデックス」を導出,前立腺がんの診断能の評価を行った.判別能の評価基準としては,ROC曲線下面積(ROC_AUC)を採用した.結果:対照群と比較し,前立腺がん患者は,Alanine, Histidine,Asparagine, Prolineの増加,Triptophanの減少が見られた.導出された前立腺がんを判別する「アミノインデックス」は,ROC_AUC=0.74の判別能を有し,早期がんも検出できた.またPSAとは有意な相関は見られなかった.結論:前立腺がんを判別する「アミノインデックス」は,前立腺がんの新しい診断マーカーとなる可能性が示された.また,PSAと独立した指標であることから,PSAとの併用による有用性が示唆された.
1 0 0 0 OA BMIと皮下・内臓脂肪肥満によるメタボリックシンドロームの関連
- 著者
- 長岡 芳 鍵小野 美和 藤田 紀乃 和田 昭彦 松井 寛 大橋 儒郁 飯田 忠行
- 出版者
- 公益社団法人 日本人間ドック学会
- 雑誌
- 人間ドック (Ningen Dock) (ISSN:18801021)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, no.3, pp.486-493, 2010 (Released:2013-07-31)
- 参考文献数
- 24
- 被引用文献数
- 1
目的:腹部CT法による皮下脂肪・内臓脂肪肥満とBMIから日本のメタボリックシンドローム診断基準との関連を調べ,肝機能との関連も検討した.対象と方法:男性174名,女性63名を対象とし,平均年齢は,男性46.6±11.3歳,女性49.2±12.4歳であった.内臓脂肪面積とBMIにより,正常群:内臓脂肪面積100cm2未満・BMI25未満,皮下脂肪型肥満群:内臓脂肪面積100cm2未満・BMI25以上,内臓脂肪蓄積型肥満群:内臓脂肪面積100cm2以上・BMI25未満,内臓脂肪型肥満群:内臓脂肪面積100cm2以上・BMI25以上に分けた.4群間について年齢,最高・最低血圧,HDL・LDLコレステロール,中性脂肪,血糖,HbA1c,AST,ALT,γ-GTPを比較した.結果:内臓脂肪の増加は,男性で血圧と肝機能異常に関与した.皮下脂肪の増加は,男女ともにHDLコレステロールの低下と,女性のALTの増加に関与した.内臓・皮下の両脂肪の増加があると,HDLコレステロールの低下,HbA1c,γ-GTPの上昇に関与した.結論:メタボリックシンドロームの疑いに関しては,内臓脂肪面積と皮下脂肪面積を測定し,性別による分析を加味し,予防対策に活かす必要性が示唆された.
1 0 0 0 OA 胃X線検査によるヘリコバクターピロリ感染の予測についての検討
- 著者
- 木村 美奈子 飯塚 政弘 保坂 薫子 大隅 康之 相良 志穂
- 出版者
- 公益社団法人 日本人間ドック学会
- 雑誌
- 人間ドック (Ningen Dock) (ISSN:18801021)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, no.5, pp.774-780, 2014 (Released:2014-06-27)
- 参考文献数
- 21
目的:近年,胃がん発生の危険因子であるHelicobacter pylori(H. pylori)の血中抗体と血清ペプシノゲン(PG)を用いた胃がんリスク検診が注目されており,当施設でも平成23年度よりこれらの検査をオプション検査として導入した.今回,胃X線検査で描出された所見とH. pylori抗体およびPG検査結果を比較することにより,胃X線検査のH. pylori感染予測における有用性を検討した.対象と方法:平成23年4月~平成24年3月の当施設健診受診者のうち,胃X 線検査と同時にH. pylori抗体検査またはPG検査を行った200人を対象とし,胃X線検査による萎縮性胃炎を中心とした慢性胃炎(以下,慢性胃炎)の有無とH. pylori抗体・PG検査結果を比較し,胃X線検査によるH. pylori感染診断の精度について検討を行った.結果:H. pylori抗体陽性例の96.8%,H. pylori抗体・PGともに陽性例の100%に胃X線検査で慢性胃炎が認められた.H. pylori抗体・PGともに陰性例では,胃X 線検査で慢性胃炎が認められた頻度は8.9%であった.H. pylori抗体陽性例およびH. pylori抗体陰性かつPG陽性例をH. pylori感染例と考えた場合,胃X線検査では感度91.5%,特異度93.3%,正診率92.3%でH. pylori感染が診断できた.結論:胃X線検査はH. pylori感染の予測において有用な検査と考えられた.
1 0 0 0 OA 内臓脂肪面積および腹囲のカットオフ値に関する検討
- 著者
- 井本 貴之 加藤 千春 横地 隆 吉兼 直文 翠 尚子 別所 祐次 酒井 康子 岩田 全充
- 出版者
- 公益社団法人 日本人間ドック学会
- 雑誌
- 人間ドック (Ningen Dock) (ISSN:18801021)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, no.3, pp.541-549, 2010 (Released:2013-07-31)
- 参考文献数
- 30
- 被引用文献数
- 2
目的:メタボリックシンドロームのリスク集積を検出する内臓脂肪面積(visceral fat area:VFA)および腹囲の最適カットオフ値を男女別に検討し,VFAと血漿アディポネクチン濃度との関連からその妥当性を確かめること.方法:健康支援センターウェルポにて節目健診を受診した男性:8,470人(47.3±8.2歳),女性:1,626人(47.5±4.7歳)を対象とした.ROC曲線分析により高血圧,脂質異常,高血糖のうち2つ以上の合併を検出するVFAおよび腹囲の最適カットオフ値を男女別に求めた.また,VFAと腹囲の単回帰分析からVFAの最適カットオフ値に対応する腹囲を求めた.対象者のVFAを0cm2から20cm2毎に群別し,各群に属する対象者の血漿アディポネクチン濃度の平均値を多重比較した.結果:ROC曲線分析の結果,VFA・腹囲の最適カットオフ値は男性76.3cm2・84.2cm,女性47.3 cm2・80.5cmであった.また,単回帰分析の結果,VFAの最適カットオフ値に対応する腹囲として男性85.2cm,女性80.1cmが得られた.さらに,VFAについて男性60~80cm2より大,女性40~60cm2より大の群間において血漿アディポネクチン濃度の平均値に有意な差が示されず,それらの値はVFAの最適カットオフ値と近似していた.これはVFAの増大に伴うアディポネクチン分泌の減少に下限が存在する可能性を示唆する.結論:VFA・腹囲の現行基準,特に女性の腹囲基準90cmについては見直す必要がある.
- 著者
- 辻 裕之 宮川 めぐみ 有元 佐多雄 謝 勲東 中島 弘 原 茂子
- 出版者
- 公益社団法人 日本人間ドック学会
- 雑誌
- 人間ドック (Ningen Dock) (ISSN:18801021)
- 巻号頁・発行日
- vol.22, no.3, pp.383-388, 2007-09-28 (Released:2012-08-20)
- 参考文献数
- 3
- 被引用文献数
- 1
目的:血清尿酸値(UA)および尿pHと,メタボリック症候群(MetS)との関連について検討する.方法:虎の門病院人間ドックでの21年間の受診者のべ225,826名(男性168,042名,女性57,784名)を対象として,UAおよび尿pHと,MetSとの関連について多角的に分析した.また本研究でのMetSの判定基準は,ウエスト周囲径のかわりに肥満指数(body mass index:BMI)25以上を使用した.結果:21年の経過で男女ともにUAの上昇,尿pHの低下およびMetS発現率の上昇が見られ,UAおよび尿pHは,MetS関連諸因子(血圧・空腹時血糖・中性脂肪・HDL cholesterolおよびBMI),さらに自己申告による疾患有病率の大部分と関連していた.さらに初診時BM正常者のその後のMetS発現率を初診時の尿酸値および尿pHとの関連でみると,初診時に高尿酸血症(UA:7.1mg/dl以上),または酸性尿(pH:5.5未満)があると,その後のMetS発現率は有意に高値であった。結論:UAと尿pHは,MetSと関連する因子や疾患有病率と有意な関連性があり,MetSおよび関連疾患発症のリスク因子であることが示された.さらに初回受診時のUAと尿pHが,その後のMetS発症に関連していることから,これらはMetSの先行指標となりうるものと考えられた.
1 0 0 0 OA 年間医療費削減の観点からの人間ドック健診受診の意義
- 著者
- 福井 敏樹 山内 一裕 丸山 美江 佐藤 真美 高橋 英孝 山門 實
- 出版者
- 公益社団法人 日本人間ドック学会
- 雑誌
- 人間ドック (Ningen Dock) (ISSN:18801021)
- 巻号頁・発行日
- vol.27, no.1, pp.29-35, 2012 (Released:2012-10-03)
- 参考文献数
- 13
目的:人間ドック健診は,生活習慣病の発症予防と早期治療,がんの早期発見と早期治療を大きな目的としている.しかしながら人間ドック健診と一般健診受診者の医療費について比較検討した報告はこれまでほとんどない.したがって今回我々は,通常の健診を毎年受けている集団(一般健診群)と毎年人間ドックを受け続けている集団(ドック健診群)における医療費の経年変化を比較検討し,毎年人間ドック健診を受け続けていれば,本当に一般健診以上の医療費削減効果があるのかを検討した.方法:対象は四国エリアの40歳代および50歳代のNTTグループ社員.平成15年度から17年度までの3年間連続での一般健診群と3年間連続でのドック健診群における年間医療費を,平成18年度から22年度まで5年間前向きに追跡した.結果:男性については,40歳代および50歳代の一般健診群では経年的に年間医療費が増加する傾向が見られた.5年間の累積医療費の両群の差は,40歳代は,男性約14.3万円,女性約-6.9万円であった.50歳代は,男性約33.0万円,女性約4.0万円であった.男性においては40歳代,50歳代共に両群の差が年々大きくなっていった.結論:50歳代男性では,人間ドック健診と一般健診との費用差額を考慮しても,毎年人間ドック健診を受けることに医療費削減効果があることが示された.
1 0 0 0 OA 人間ドックへの視野検査導入の意義について
- 著者
- 宮本 祐一 木村 美樹 柿本 陽子 福岡 直美 水城 比呂子
- 出版者
- 公益社団法人 日本人間ドック学会
- 雑誌
- 人間ドック (Ningen Dock) (ISSN:18801021)
- 巻号頁・発行日
- vol.27, no.1, pp.36-40, 2012 (Released:2012-10-03)
- 参考文献数
- 20
目的:40歳以上の緑内障有病率は5.0%である.その78%が広義の原発開放隅角緑内障であり,その92%が正常眼圧緑内障,normal tension glaucoma(以下,NTG)である.このNTGの発見へのfrequency doubling technology (FDT)視野計の有用性を検討した.方法:2010年5月17日より2011年1月31日までのFDT実施4,014名の中のFDT陽性者235名(5.9%)中108名が眼科を受診した.その診断結果を検討した.結果:NTGが56名,原発開放隅角緑内障が5名,原発閉塞隅角緑内障が1名,続発緑内障が1名であった.FDT陰性で眼底検査,眼圧検査で精査となりNTG,原発開放隅角緑内障と診断された5名を含めると68名の緑内障が発見された.FDTのみの異常者172名,精査受診者68名,発見緑内障49名,眼底,眼圧のみの異常者88名,精査受診者48名,発見緑内障19名,特に,発見緑内障68例中3例のみが眼圧での陽性者であった.すなわちFDT検査がなければ68例中49例の緑内障が発見できず,眼底,眼圧のみでは19例の発見であり,FDT導入によって,発見率は3.6倍に増加した.2009年度の眼底,眼圧のみでは4,313名中10名の緑内障が発見されたのみであり,発見率は0.23%であったが,FDT導入後の眼底,眼圧,FDTのいずれかを行った総数は4,051名であり,緑内障発見率は1.68%と有意に増加した.結論:人間ドックにおいて,NTGの発見にはFDT視野計がきわめて有用である.