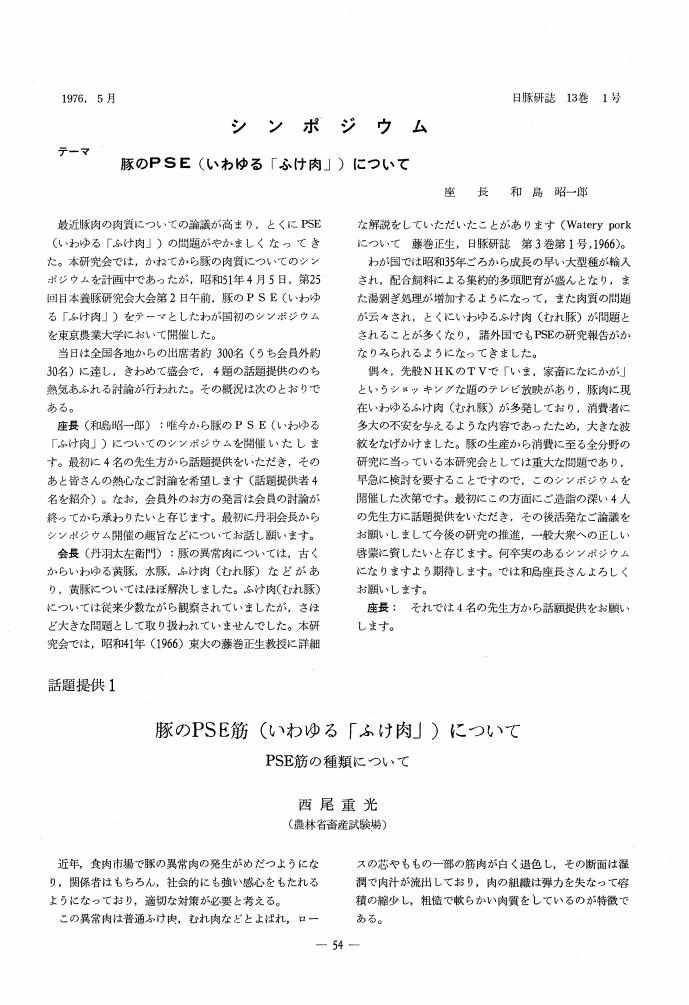5 0 0 0 OA 豚の椎骨数の変異と椎骨数の異なる豚の発育, 飼料の利用性および屠体形質について
- 著者
- 与沢 松作 仙田 国晃 野原 弘 高橋 正行
- 出版者
- 日本養豚学会
- 雑誌
- 日本養豚研究会誌 (ISSN:03888460)
- 巻号頁・発行日
- vol.2, no.2, pp.56-65, 1965-12-28 (Released:2011-06-08)
- 参考文献数
- 8
1 当試験場及び富山県経済連滑川種豚場産の子豚517頭 (Y. Y331頭, Y. L70頭, L. L116頭) の椎骨数を調査したところY. Yは20型4.5%, 21型71.6%, 22型23.6%, 23型0.3%, Y. Lは21型40.0%, 22型60%, L. Lは21型2.6%, 22型85.3%, 23型12.1%で品種による椎骨数の違いが認められた。2 F1では椎骨型の変異の巾は小さくなり, またヨークシャーとランドレースの中間的数値よりランドレースに近い椎骨の増加が認められた。3 種雄豚の系統別の胸・腰椎数変異の発現率は系統的に異なる傾向が認められた。4 胸腰椎数の heritability 推定値は高く, 高い遺伝力を期待できることが判明した。5 胸・腰椎数21型および22型各20頭 (ヨークシャー) を用いて飼養試験を行ったところ発育, 飼料要求率には差は認められなかった。6 屠体成績は22型が21型より背腰長I, II, IIIは長く有意な差が認められた。大割肉片ではロース・バラは22型が21型より割合が多くなるが, 逆にハムは小さくなることが認められ2%水準で有意であった。7 ロース長は22型が21型より長く1%で有意であり逆にロース面積は21型が22型より大きくなる傾向が認められたが有意ではなかった。8 背脂肪は22型が21型より薄くなる傾向が認められた。9 椎骨1個あたりの長さは22型が21型より長くなる傾向が認められた。
3 0 0 0 OA 豚精液に関する免疫学的研究
- 著者
- 安田 泰久 丸山 淳一 丹羽 太左衛門
- 出版者
- 日本養豚学会
- 雑誌
- 日本養豚研究会誌 (ISSN:03888460)
- 巻号頁・発行日
- vol.5, no.3, pp.119-125, 1968-12-31 (Released:2011-06-08)
- 参考文献数
- 37
豚精液および精漿で家兎を免疫して, それに対して産生した抗体を用いて, 精液および精漿の抗原系の追求を行なった。1) 沈降素抗体価は, 免疫後1週目から精液および精漿の抗体産生が認められ, 2週目においては10:1×29以上の抗体価を示した。また, 精液は精漿よりも抗原性の高いことが認められた。2) OUCHTERLONY 法で抗原系を検討した。a. Landrace 種と Yorkshire 種において, 精液には抗原系の差が認められなかった。しかし, 精漿においては沈降線の出現部位と出現時間に差が認められた。b. 精液の分離時において各々の遠心速度によって得た精漿の抗原系には差が認められなかった。c. 雄性生殖腺液の抗原系において, 精巣上体精液の抗原系は弱く, 数も少なかった。しかし, 精のう液の抗原系は強く, 抗原系の数も多いことが認められた。豚精液の主要な抗原成分は精のう液に由来するものと考えられる。
1 0 0 0 OA 豚のケージ飼いと平飼いの肉質について
- 著者
- 和賀井 文作
- 出版者
- 日本養豚学会
- 雑誌
- 日本養豚研究会誌 (ISSN:03888460)
- 巻号頁・発行日
- vol.1, no.2, pp.64-69, 1964-12-28 (Released:2011-06-08)
- 参考文献数
- 12
バークシャー種10頭を用い, ケージ飼いと平飼いによる肉質を組織化学的に比較した結果は, つぎのとおりである。1. 背最長筋と棘上筋, 大腿直筋の筋線維の厚径は, ケージ飼いのものがわずかに細いが, 有意差は認められない。2. 筋肉の屠殺直後のpH値は, 部位により異なるが, ケージ飼いと平飼いとの間には差異が認められない。3. 生肉を4週間冷蔵庫 (0℃~4℃)中に保存し, 時間の経過に伴なう筋線維の厚径, 筋線維数, 筋核, グリコーゲン, pH値の変化などを比較したが, ケージ飼いと平飼いとの間にはほとんど差異が認められない。
1 0 0 0 OA 豚の呼吸エネルギー代謝に関する研究 5. 育成豚の生理反応に及ぼす暑熱環境の影響
- 著者
- 戸原 三郎 佐藤 至 中村 彰 中西 五十 佐久間 勇次
- 出版者
- 日本養豚学会
- 雑誌
- 日本養豚研究会誌 (ISSN:03888460)
- 巻号頁・発行日
- vol.20, no.3, pp.147-153, 1983-10-20 (Released:2011-06-08)
- 参考文献数
- 21
環境温度を22℃以下のA区と22.1~26.0℃のB区, 26.0以上のC区に分け, 6頭の育成豚 (平均体重29.74±5.41kg) を用い, CO2発生量とO2消費量, 呼吸商, 熱発生量, 呼吸数, 心拍数を比較した。1. CO2発生量はA区が平均15, 64±3.39l/hrで最も少く, B区はA区より15%, C区はB区より18%多くなり, 環境温度の上昇に伴い有意に増加した。2. O2消費量はA区が平均17.32±2.73l/hrで最も少く, B区はA区より4%, C区はB区より27%多くなり, 環境温度の上昇に伴い, 増加の傾向が認められた。3. 呼吸商はA区が平均0.91±0.12で最も少かったが, B区は増加しC区は減少しており, 温度の上昇に伴う一定した変化は認められなかった。4. 熱発生量はA区が平均6.51±1.11Cal/kg0.75hrで最も少く, B区はA区より23%, C区はB区より15%多くなり, 環境温度の上昇に伴い有意に増加した。5. 呼吸数はA区が平均26.5±4.2回/分で最も少く, B区はA区より71%, C区はB区より120%多くなり, 環境温度の上昇に伴い急激に増加した。6. 心拍数はA区が平均111.3±7.6回/分で最も少く, B区はA区より10%, C区はB区より8%多くなり, 環境温度の上昇に伴い有意に増加した。7. 環境温度とCO2発生量, O2消費量, 熱発生量, 呼吸数, 心拍数との間には, かなり高い有意な正の相関が認められた。
1 0 0 0 OA シンポジウム
- 出版者
- 日本養豚学会
- 雑誌
- 日本養豚研究会誌 (ISSN:03888460)
- 巻号頁・発行日
- vol.13, no.1, pp.54a-64, 1976-05-31 (Released:2011-06-08)
1 0 0 0 OA 日本養豚研究会10年の歩み
- 出版者
- 日本養豚学会
- 雑誌
- 日本養豚研究会誌 (ISSN:03888460)
- 巻号頁・発行日
- vol.11, no.2, pp.89-94, 1974-09-30 (Released:2011-06-08)
1 0 0 0 西南暖地における豚の放牧に関する研究
- 著者
- 佐藤 勲 井上 正四郎 安藤 忠治 稲沢 昭
- 出版者
- The Japanese Society of Swine Science
- 雑誌
- 日本養豚研究会誌 (ISSN:03888460)
- 巻号頁・発行日
- vol.2, no.2, pp.45-49, 1965
1 50頭1群による甘藷畑放牧の結果, 発育および飼料の利用性において, 前報よりはややよくなかった。また, ヨークシャーとF<sub>1</sub>の発育差は, 所要日数で約25日, 1日平均増体重で約160gで, F<sub>1</sub>の有利性を示した。<br>2 放牧中の事故豚は, へい死1頭, 病豚6頭で隔離治療の必要があった。<br>3 50頭1群の放牧に要した所要労力は, 遊休労働時間を除いて, 1頭1日当り1.9分で, 1頭当りの労働費は337円となった。<br>これは, 生産費のうちの2.2%であった。<br>4 飼料費は, 1頭当りを, 甘藷生産費でみると8,371円, 原料用甘藷価格でみると, 9,416円であった。これは, 生産費のうちの54.2%にあたる。<br>5 素畜費は, 最近, 子豚価格の高騰により5,540円を要し, 生産費のうち35.9%をしめている。<br>6 販売費用は, 1頭当り1,661円で, 総売上げの8.3%, 収益の39%をしめた。<br>7 甘藷畑41.74aに, 50頭放牧した場合の経済価値は, 自給飼料利用価172,960円となり, これから甘藷生産費を除くと, 127,482円であった。すなわち, 甘藷1kg当りの利用価は, 20.35円で原料用甘藷価格の約2.5倍になった。<br>8 この場合の139日間における1日平均収益は926円であった。<br>9 枝肉価格と採算の限界では, 枝肉kg当り290円が限界で, 1日1000円の収益を得るためには, 枝肉価格は330円を下まわってはだめで, その場合の飼料費は, 8,363円, 素畜費は, 5,532円が最高の限界となる。
- 著者
- 浅井 孝康 上山 謙一 山根 礼吉
- 出版者
- The Japanese Society of Swine Science
- 雑誌
- 日本養豚研究会誌 (ISSN:03888460)
- 巻号頁・発行日
- vol.5, no.1, pp.1-5, 1968
肉豚の省力管理の一方法として, 生体重20kgおよび50kgから1回に2日分の飼料を夫々給与したA区, B区, 並びに生体重20kgおよび50kgから1回に3日分の飼料を夫々給与したC区, D区および1日2回給与した対照区の発育成績, 飼料消費量, 屠体成績を要約すると次のとおりである。<br>(1) 試験期間 (20~90kg) における試験区の所日要数はD区, C区, B区, A区の順に短かく夫々108日, 114日, 117日, 121日を要し, 1日平均増体重はD区が653<i>g</i>で最も大きく, 次いでC区, B区, A区の順に夫々605<i>g</i>, 599<i>g</i>, 579<i>g</i>であった。対照区は所要日数114日, 1日平均増体重615<i>g</i>で, 分散分析の結果は試験区各区間および試験区各区と対照区の間に有意な差は認められなかったが, 対照区に比較して試験区は発育速度がやゝ劣り, また20kgから開始した場合は50kgから開始した場合より発育速度がやゝ劣る傾向が見受けられた。<br>(2) この間の1頭当り平均飼料消費量は試験区ではD区が243.9kgで最も少なく, 次いでC区, B区, A区の順に夫々259.0kg, 263.5kg, 271.1kgであった。対照区は251.5kgで試験区は対照区に比較して僅かであるが飼料消費量が多い傾向が見受けられた。<br>(3) 飼料要求率はD区が3.46で最も小さく, 次いでC区, B区, A区の順に夫々3.75, 3.76, 3.87で, 対照区は3.59であった。<br>(4) 枝肉歩留はC区が73.52%で最も高く, 次いでD区, B区, A区の順に夫々72.39%, 72.25%, 72.02%で, 対照区は75.04%であった。<br>背脂肪層の厚さは各区とも薄く, 滑らかで良好であった。脂肪層の厚さの平均はC区が2.21cmで最も薄く, 次いでB区, A区, D区の順に夫々2.32cm, 2.75cm, 2.78cmで, 対照区は2.50cmであった。
1 0 0 0 西南暖地における豚の放牧に関する研究
- 著者
- 佐藤 勲 長友 安雄 安藤 忠治 稲沢 昭
- 出版者
- The Japanese Society of Swine Science
- 雑誌
- 日本養豚研究会誌 (ISSN:03888460)
- 巻号頁・発行日
- vol.1, no.1, pp.14-22, 1964
1) 豚の放牧による肥育は飼料の利用性, 発育, 斎度, 寄生虫, 皮膚病などにより問題があるとされていたが, 甘藷畑で放牧肥育を実施した結果, 1日平均659g~730gとすぐれた発育を示した。その発育に比較して飼料要求率は3.61~3.92とやや悪るく, 発育にバラツキが見られた。<br>2) 省力管理は期待できる。すなわち, 甘藷の収穫, 調理, 給与の手間がかからずに, しかも飼育管理でも1頭当り, 2時間53分, 1日1頭当り換算すると2分02秒であった。<br>3) 甘藷畑10aに肥育豚を10頭放牧して仕上げることができるかどうかは, 収量と放牧時期, 方法によるが, 本試験の結果では可能であり, 放牧豚はきわめて上手に甘藷を採食し, ロスが少なかった。<br>4) 甘藷畑放牧においては, 体重20kgより開始しても発育の停滞および事故はなかった。<br>5) 放牧期間中数回の降霜があったが, 降霜後の甘藷を採食しても事故はなく, また甘藷の品種による嗜好性の相違があった。<br>6) 肥育末期の舎飼は発育を良好にし, しかも飼料の利用性もよくなった。すなわち, BL区で1日平均増体重が14g, L区で12g半放牧区がすぐれ, 飼料要求率では, BL区で0.25, L区で0.3半放牧区がすぐれていた。<br>7) 甘藷の採食量は多く, 牧区拡張当日はやや過食の傾向があるので放牧方法を検討する必要がある。<br>8) 総給与量 (風乾量) に対し40%の甘藷を採食したが, 皮下脂肪が比較的うすく, 肉質良好, 腎臓脂肪が少なかった。<br>9) 寄生虫の被害は殆んどなかった。<br>10) 放牧のため発生したと考えられる疾病および事故はなかったが, 電気牧柵を利用した放牧であるため, 脱柵の習慣がついたものが生体重70kg時に1頭あった。これは甘藷を堀りながら前進するため架線が高いと知らぬまに脱柵していることから習慣となったものである。
1 0 0 0 豚の生態行動に関する研究
- 著者
- 美斉津 康民 河上 尚実 八木 満寿雄 瑞穂 当
- 出版者
- The Japanese Society of Swine Science
- 雑誌
- 日本養豚研究会誌 (ISSN:03888460)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, no.1, pp.1-6, 1980
豚舎設計の基礎となる各種の数値を得ることは, 合理的な構造の豚舎を建設する上で重要なことである。本研究では, 仕切柵の必要とする高さを知る目的で, 豚のとび越し高さ, および, とび越し習性について実験を行ない, 次のような結果を得た。<br>(1) 豚が柵をとび越す動作は, 柵に前肢をかけることから始まり, 後肢をのばして上体をずり上げたあと, さらに床面を蹴るなどして, その反動を利用しながら体の重心を移動してゆき, とび越しを終る。なお, 豚の場合には, 助走して飛越するという行動は全く見られなかった。<br>(2) 強制的に豚を追い出した場合には, 体重40kg台に100cmをとび越した豚が最高であり, 自由条件では80~90kg時点の95cmが最高とび越し高さであった。<br>(3) 性別で見れば, 自由条件では, 去勢豚は雌豚に比べて明らかに高いとび越し高さを示した。しかし強制条件においては, 性別による差は顕著ではなかった。<br>(4) 体発育との関係では, 自由・強制いずれの条件でも, 平均値としては発育の遅れた豚群が優位を示したが, 最高とび越し高さにおいては発育良好群にその事例が多かった。<br>(5) 生後日令との関連でみると, 肥育開始当初は強制条件でのとび越し高さの方が高く, 肥育後半では自由条件の方がとび越し高さが高い。したがって, 種々の管理条件において豚が脱柵する危険性は, 肥育期間全体を通じてほぼ同等であると考えられる。<br>(6) 今回の実験の範囲においては, 肥育豚舎における仕切柵の高さは100cmでほぼ万全であり, 偶発的な脱柵を忍容するならば, 90cmでも実用上問題はないと思われる。
1 0 0 0 OA 豚パルボウイルスの消毒効果
1 0 0 0 OA 豚におけるストレス制御につといて
- 著者
- M. ROGIERS 北野 訓敏
- 出版者
- 日本養豚学会
- 雑誌
- 日本養豚研究会誌 (ISSN:03888460)
- 巻号頁・発行日
- vol.10, no.2, pp.83-95, 1973-08-31 (Released:2011-06-08)
- 参考文献数
- 12
以上要約しますと, 豚は離乳から肥育豚舎に行くまで度々移動させられたり, 精神的に障害をうけるので, 相当な精神的なストレスを受けるため, Selye によって報告されている“適応症候群”にまで進行することが考えられます。このため異化作用は促進して胃腸障害を引き起すことになると思われます。消化管に関連した数多くの臨床的障害は離乳後に典型的に発生するものであり, その障害は下痢症, 出血性腸炎, 成長の停止, 飼料効率の低下であります。消化管にみられる病理解剖学的病変は, 離乳後と同様に実験的ストレスを与えた場合にも観察されました。離乳後の損失を出来るだけ少なくする方法としては, 広範囲に適用される抗生物質の多量に入った所謂“ストレス飼料”を投与することが必要であります。また, アザペロンの様な精神安定剤は良好な治療効果を示すことが出来ます。アザペロンは豚の精神的平衡を維持し, 発生が予測される胃腸障害を予防するものであり, その原因的治療剤としてすぐれた薬剤であると考えられます。
1 0 0 0 OA 豚精液の低温保存に関する研究
- 著者
- 糟谷 泰 河部 和雄
- 出版者
- 日本養豚学会
- 雑誌
- 日本養豚研究会誌 (ISSN:03888460)
- 巻号頁・発行日
- vol.13, no.1, pp.22-26, 1976-05-31 (Released:2011-06-08)
- 参考文献数
- 18
豚精液の低温保存に適する保存液を調製するための基礎資料を得る目的で, 分離採取濃厚精液および保存液構成々分として一般的に用られている9物質の水溶液について, その浸透圧とpHを測定した。1. 分離採取濃厚精液の浸透圧は300~320mOsm/lで, 同一個体内においても採取毎にこの程度の変動があった。2. 保存液の至適浸透圧と考えられる300mOsm/lの浸透圧となる各水溶液の濃度はブドウ糖-5.4%, 脱脂粉乳-10.8%, トリス-3.6%, クエン酸-6%, Na2HPO4・12H2O-4.8%, KH2PO4-2.4%, 重炭酸%Na-1.4%, クエン酸Na-3.2%, グリシン-2.3%であった。3. 分離採取濃厚精液のpHは7.2~7.7と弱アルカリ性を示し, 同一個体内においても採取毎にこの程度の変動があった。4. 保存液構成々分の各水溶液のpHは, ブドウ糖, 脱脂粉乳, グリシン, クエン酸がそれぞれ5.8, 6.6, 6.1, 2<と酸性を示し, トリス, Na2HP4・12H2O, 重炭酸Na, クエン酸Naがそれぞれ10.8, 9.2, 8.6, 8.1とアルカリ性を示した。
1 0 0 0 OA 産肉能力検定のページ
- 出版者
- 日本養豚学会
- 雑誌
- 日本養豚研究会誌 (ISSN:03888460)
- 巻号頁・発行日
- vol.7, no.1, pp.69-69, 1970-04-30 (Released:2011-06-08)
1 0 0 0 OA 新生豚の血漿カテコールアミン濃度に対する寒冷の影響
- 著者
- 宮腰 裕 太田 達郎 咲山 久美子
- 出版者
- 日本養豚学会
- 雑誌
- 日本養豚研究会誌 (ISSN:03888460)
- 巻号頁・発行日
- vol.23, no.4, pp.192-195, 1986-12-30 (Released:2011-06-08)
- 参考文献数
- 10
1腹6頭の子豚 (Landrace×Hampshire) を実験に用い, 2日齢から14日齢までの間に, 寒冷ストレスおよび取扱いのストレスをそれぞれ2回負荷して, 血漿カテコールアミン濃度を測定し, 平常時の値と比較した。実験時の子豚の直腸温, 吸乳量およびヘマトクリット値は日齢に伴う正常な変動を示し, また, 血漿グルコース濃度には与えられたストレスによると思われる変化が認められなかった。7日齢以前のストレス負荷時における血漿中のノルエピネフリン (NE) およびエピネフリン (E) の値は平常よりも高い傾向を示したが, 10日齢以降ではその傾向が明らかではなかった。NE/E比はストレス負荷時の値が平常時よりも有意に高く (P<0.05), また寒冷ストレス時の値が取扱いストレス時の値よりも高かった。以上のことから新生期におけるストレスに対する血中カテコールアミン放出反応が認められ, 特に寒冷ストレスに対してはノルエピネフリン濃度が相対的に高くなることが示された。