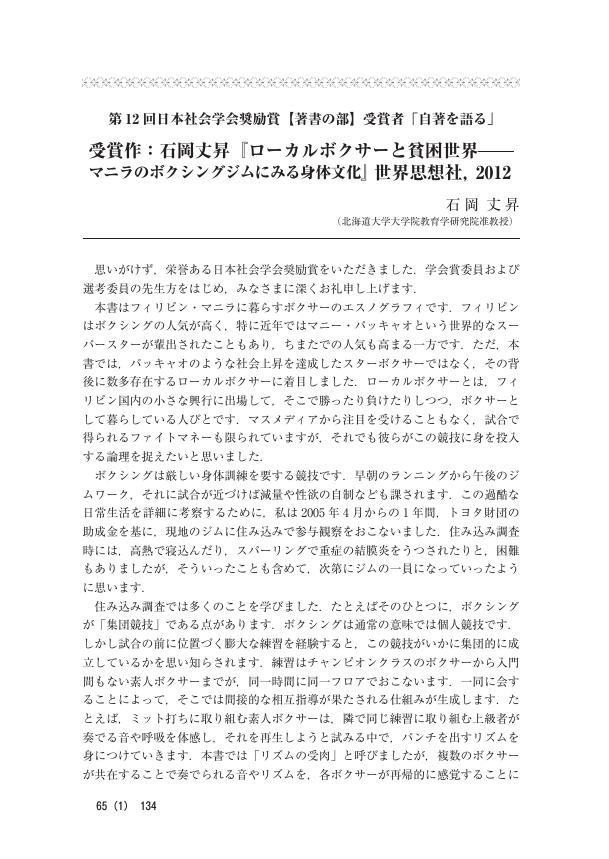- 著者
- 呉 学殊
- 出版者
- 日本社会学会
- 雑誌
- 社会学評論 (ISSN:00215414)
- 巻号頁・発行日
- vol.66, no.1, pp.146-148, 2015
2 0 0 0 テーマ別研究動向 (子ども)
- 著者
- 元森 絵里子
- 出版者
- 日本社会学会
- 雑誌
- 社会学評論 (ISSN:00215414)
- 巻号頁・発行日
- vol.66, no.1, pp.123-133, 2015
2 0 0 0 テーマ別研究動向 (ソーシャルキャピタル)
- 著者
- 三隅 一人
- 出版者
- 日本社会学会
- 雑誌
- 社会学評論 (ISSN:00215414)
- 巻号頁・発行日
- vol.66, no.1, pp.134-144, 2015
2 0 0 0 テーマ別研究動向 (ソーシャルキャピタル)
- 著者
- 三隅 一人
- 出版者
- 日本社会学会
- 雑誌
- 社会学評論 (ISSN:00215414)
- 巻号頁・発行日
- vol.66, no.1, pp.134-144, 2015
2 0 0 0 非正規雇用から正規雇用への移動における企業規模間格差
- 著者
- 福井 康貴
- 出版者
- 日本社会学会
- 雑誌
- 社会学評論 (ISSN:00215414)
- 巻号頁・発行日
- vol.66, no.1, pp.73-88, 2015
- 被引用文献数
- 3
本稿は, 二重構造論の枠組みを非正規雇用の問題に導入することで, 若年期の非正規雇用から正規雇用への移動という現象に従来とは異なる図柄を示す. 二重構造論によれば, 各セクターの雇用慣行の違いから, 求められる職業能力や市場環境への反応は異なっていると考えられる. また下位セクターから上位セクターへの移動も困難だと予想される. そこで, 初職に非正規雇用として就業した若年層を対象として, (1) 非正規雇用時の職業と市場環境が正規雇用時の従業先に与える影響と, (2) 非正規雇用時の従業先が正規雇用時の従業先に与える影響を, 2005年SSM調査のデータを用いて検証した.<br>分析の結果, 大企業・官公庁では専門職が正規就業しやすく, 初職に就いた後の景気後退が正規就業を妨げているのにたいして, 中小企業では熟練職が正規就業しやすく, 学卒時の市場環境の悪さや初職に就くまでの間断が正規就業に負の影響を与えていた. また, 大企業・官公庁の出身者が大企業・官公庁で正規雇用として就業しやすく, 非正規雇用時の従業先が正規雇用時の従業先に影響を与えることが明らかになった. 以上の結果は, 日本における非正規雇用からの移動において, 労働市場の構造のなかでの非正規労働者の位置づけが, 望ましい従業先への到達チャンスに影響することを示しており, 二重構造論的な視角の有効性が示唆される.
- 著者
- 福井 康貴
- 出版者
- 日本社会学会
- 雑誌
- 社会学評論 (ISSN:00215414)
- 巻号頁・発行日
- vol.66, no.1, pp.73-88, 2015
- 被引用文献数
- 3
本稿は, 二重構造論の枠組みを非正規雇用の問題に導入することで, 若年期の非正規雇用から正規雇用への移動という現象に従来とは異なる図柄を示す. 二重構造論によれば, 各セクターの雇用慣行の違いから, 求められる職業能力や市場環境への反応は異なっていると考えられる. また下位セクターから上位セクターへの移動も困難だと予想される. そこで, 初職に非正規雇用として就業した若年層を対象として, (1) 非正規雇用時の職業と市場環境が正規雇用時の従業先に与える影響と, (2) 非正規雇用時の従業先が正規雇用時の従業先に与える影響を, 2005年SSM調査のデータを用いて検証した.<br>分析の結果, 大企業・官公庁では専門職が正規就業しやすく, 初職に就いた後の景気後退が正規就業を妨げているのにたいして, 中小企業では熟練職が正規就業しやすく, 学卒時の市場環境の悪さや初職に就くまでの間断が正規就業に負の影響を与えていた. また, 大企業・官公庁の出身者が大企業・官公庁で正規雇用として就業しやすく, 非正規雇用時の従業先が正規雇用時の従業先に影響を与えることが明らかになった. 以上の結果は, 日本における非正規雇用からの移動において, 労働市場の構造のなかでの非正規労働者の位置づけが, 望ましい従業先への到達チャンスに影響することを示しており, 二重構造論的な視角の有効性が示唆される.
2 0 0 0 階層帰属意識における調査員効果について
- 著者
- 小林 大祐
- 出版者
- 日本社会学会
- 雑誌
- 社会学評論 (ISSN:00215414)
- 巻号頁・発行日
- vol.66, no.1, pp.19-38, 2015
階層帰属意識の分布は, 自記式に比べ他記式の調査でより高くなることが報告されているが, その要因については, これまで厳密に検証されてきたわけではなかった. この理由としては, モード間の傾向差のなかに混在するさまざまな要因を弁別できるようなデータセットがなかったことが大きい. 本稿は, 個別面接法と郵送法という異なる調査モードで実施されているが, 同じ階層帰属意識項目をもち, 同一年に実施された2つの調査データを比較することで, 調査モードが階層帰属意識にどのような影響を与えているか検証するものである. 分析の結果, 回答者の属性をコントロールしても, 個別面接法において階層帰属意識を高く回答する傾向が見られ, 調査モードの違いが, 何らかの測定誤差を生み出していることが示唆された. 続いて, 確認された傾向差が, 調査員の存在に由来するものかどうか, そうであれば階層帰属意識を答える際に働くバイアスとはどのようなものなのかを検討した. その結果, 男性サンプルでは中位に, 女性サンプルではより高く偏る傾向が観察された. これらの結果は, どのような階層的位置が「社会的に望ましい」, もしくは調査員に対して抵抗なく回答できるのかという, 価値規範の側面が, 所属階層を測定する際に無視できないことを示すものである.
- 著者
- 小林 大祐
- 出版者
- 日本社会学会
- 雑誌
- 社会学評論 (ISSN:00215414)
- 巻号頁・発行日
- vol.66, no.1, pp.19-38, 2015
階層帰属意識の分布は, 自記式に比べ他記式の調査でより高くなることが報告されているが, その要因については, これまで厳密に検証されてきたわけではなかった. この理由としては, モード間の傾向差のなかに混在するさまざまな要因を弁別できるようなデータセットがなかったことが大きい. 本稿は, 個別面接法と郵送法という異なる調査モードで実施されているが, 同じ階層帰属意識項目をもち, 同一年に実施された2つの調査データを比較することで, 調査モードが階層帰属意識にどのような影響を与えているか検証するものである. 分析の結果, 回答者の属性をコントロールしても, 個別面接法において階層帰属意識を高く回答する傾向が見られ, 調査モードの違いが, 何らかの測定誤差を生み出していることが示唆された. 続いて, 確認された傾向差が, 調査員の存在に由来するものかどうか, そうであれば階層帰属意識を答える際に働くバイアスとはどのようなものなのかを検討した. その結果, 男性サンプルでは中位に, 女性サンプルではより高く偏る傾向が観察された. これらの結果は, どのような階層的位置が「社会的に望ましい」, もしくは調査員に対して抵抗なく回答できるのかという, 価値規範の側面が, 所属階層を測定する際に無視できないことを示すものである.
- 著者
- 土場 学
- 出版者
- 日本社会学会
- 雑誌
- 社会学評論 (ISSN:00215414)
- 巻号頁・発行日
- vol.44, no.3, pp.314-329,361, 1993-12-30
現代社会の高度の複合性を支えているのは、権力や貨幣と並んで、愛というメディア (シンボルによって一般化されたコミュニケーション・メディア) である。本稿の目的は、ルーマンのメディア論に基づいて、産業化あるいは近代化の名のもとにくくられる社会変動のなかで愛というメディアが果たした役割を明らかにすることであり、またそれにより「社会変動のメディア論的モデル」の可能性を開示することである。そのさい、社会変動のメディア論的モデルは、従来の社会変動論のようにミクロ・レベルあるいはマクロ・レベルのいずれか一方に一貫して変動のメカニズムを想定するのではなく、むしろミクロとマクロを連結するメカニズムとしてのメディアに理論的焦点を当て、そのメディアを機能させる意味空間 (ゼマンティーク) に生じた「ゆらぎ」が社会変動をもたらす、という発想に基づく。本稿では、この社会変動のメディア論的モデルに基づいて、産業化あるいは近代化を特徴づける重要な社会変動の一つである「近代家族」の成立の過程を、愛というメディアの自律化の過程として説明することを試みる。そしてそこにおいて、愛というメディアのゼマンティークの歴史的変遷が、少しずつ、しかし着実に近代家族の成立のための条件を整えてきたことを明らかにする。
- 著者
- 石岡 丈昇
- 出版者
- 日本社会学会
- 雑誌
- 社会学評論 (ISSN:00215414)
- 巻号頁・発行日
- vol.65, no.1, pp.134-135, 2014 (Released:2015-07-04)
2 0 0 0 OA 安藤喜代美著『現代家族における墓制と葬送――その構造とメンタリティの変容』
- 著者
- 中筋 由紀子
- 出版者
- 日本社会学会
- 雑誌
- 社会学評論 (ISSN:00215414)
- 巻号頁・発行日
- vol.65, no.1, pp.142-143, 2014 (Released:2015-07-04)
- 参考文献数
- 1
2 0 0 0 OA 英雄になりきれぬままに
- 著者
- 伊藤 智樹
- 出版者
- 日本社会学会
- 雑誌
- 社会学評論 (ISSN:00215414)
- 巻号頁・発行日
- vol.61, no.1, pp.52-68, 2010-06-30 (Released:2012-03-01)
- 参考文献数
- 23
本稿は,パーキンソン病のセルフヘルプ・グループへのナラティヴ・アプローチの試みである.パーキンソン病の生き難さは,ふたつの層に分けて理解できる.ひとつは,振るえやすくみ足といった身体的な症状が,しばしば病いをもつ人に相互行為上の無能力を自覚させ,「恥ずべきこと」と感じさせる生き難さである.もうひとつは,「回復の物語」(A. Frank)が自分には適合しないことを前提にせざるをえないにもかかわらず,それに代わって頼りにできる物語が容易には得られない生き難さである.薬物療法と外科療法は身体症状をある程度コントロールする手段として発達してきているが,それらに過度の望みをかけることには弊害もある.したがって,人々にとっては,それらの療法を頼みとしつつも,一方では冷静に距離をとるための,いわばよりどころとなる物語が必要となる.セルフヘルプ・グループでのフィールドワークから,そうした情況を生きるためのものとして「リハビリ」の物語と,病いを笑う語りとをピックアップできる.これらは,ふたつの層の生き難さに対して,それぞれの仕方で緩和するようにはたらき,病いを生きるための貴重な資源となる.しかし,それと同時に,これらの物語/語りは,それぞれ見逃せない弱みを抱え込んでいるため,それらが「語られるべきである」というように倫理性を込めることには慎重になる必要がある.
- 著者
- 伊藤 美登里
- 出版者
- The Japan Sociological Society
- 雑誌
- 社会学評論 (ISSN:00215414)
- 巻号頁・発行日
- vol.65, no.3, pp.409-425, 2014
U.ベックは, ローカル次元において連帯と承認を作り出す仕組みとして市民労働という政策理念を提案した. この理念が現実社会との関連でいかに変容したか, 他方で社会においてはいかなる変化がもたらされているか, これらを考察することが本稿の目的である.<br>研究の結果次のようなことが判明した. 市民労働の政策理念は, 政策的実践に移される過程で, ある部分が市民参加に, 別の部分が市民労働という名のワークフェア政策としてのモデル事業に採用され, 分裂していった. 現在の市民労働と市民参加は, ベックの市民労働の構成要素をそれぞれ部分的に継承しつつ, 中間集団や福祉国家の機能を部分的に代替している. 政策的実践としての市民労働と市民参加の存在は, 「家事労働」「市民参加」「ケア活動」といった概念の境界を流動化したが, 「職業労働」概念の境界は相対的に強固なままである.<br>ベックの市民労働には, 元来, 社会変革の意図が含まれていた. すなわち, この政策理念は, 職業労働と市民参加と家事労働やケア活動の境界を流動化し, それらの活動すべてを包括するような方向, すなわち労働概念の意味変容へ向かうことを意図して提案された試みであった. しかし, 現状においては, そもそもの批判対象であった職業労働の構造を強化する政策にこの市民労働の名称が使われている. 他方, 市民参加においては, 部分的にではあるが, 市民労働の政策理念が生かされ一定の成果をあげている.
- 著者
- 櫛原 克哉
- 出版者
- 日本社会学会
- 雑誌
- 社会学評論 (ISSN:00215414)
- 巻号頁・発行日
- vol.65, no.4, pp.574-591, 2015
本稿は, 社会生活への適応に困難を感じたために, 精神医療機関を利用した経験のある人々の語りを考察した. 近年の精神薬理学や臨床心理学的治療の拡充を受け, 精神医学においては従来の心理的・内面的な要因を対象とした治療に代わり, 患者の脳を中心とする生物学的要因や可視的な行動の矯正といった「フラット」な領域の治療が推進されている. N. Roseは, このような管理技術の浸透を, 精神医学の統治の「フラット化」の現象として指摘する.統治のフラット化を被治療者の観点から考察すべく, 筆者は医療機関への通院経験がある6名を対象にインタビュー調査を実施した. その結果, 「全人格型の語り」と「場面型の語り」の2類型が導出された. 「全人格型の語り」は心理学的な因果関係の文脈から過去との連続性を有する自己を導出するのに対し, 「場面型の語り」は現在属する社会環境内で問題となる思考や行動を限局的に調整しようと試みる断片的な自己という性質を有した.2つの語りは, 精神医学の治療構造の分裂を反映し, 医学のフラット化が不均質に浸透したことにより, 治療対象となる自己も分裂して生起することが確認された. このことから, 精神医療における統治により, 社会環境に適合的な自己が「フラットに」産出される一方で, 心理学的な主題に回帰して「精神の深部」を参照するような自己が, フラットな統治を下支えし治療の求心力として作用していることが示唆された.
2 0 0 0 大学教員の研究業績に対する性別の影響
- 著者
- 坂無 淳
- 出版者
- 日本社会学会
- 雑誌
- 社会学評論 (ISSN:00215414)
- 巻号頁・発行日
- vol.65, no.4, pp.592-610, 2015
本稿では, 大学教員の研究業績の男女差について分析を行う. 多くの先行研究では, 平均的には男性の業績が多い傾向が示されている. しかし, 研究業績には性別という属性以外に多くの規定要因があり, それらの要因を統制したうえでも, なお性別が規定要因となるかを明らかにする必要がある. そこで, 2010年に日本の地方国立大学で行った調査から, 大学教員の1年間の論文数を従属変数とした統計的な分析を行う. その結果, 単純に平均値を比較すると, 年1本ほど男性の論文数が多い傾向があった. つぎに, 性別に加え, キャリア年数, 研究以外の業務量 (授業担当数や学内会議数), 出張日数, 分野, 職階を独立変数に入れた重回帰分析と, 低い値に偏る従属変数の分布に適合した負の二項分布回帰を行った. その結果, 性別は規定要因とならず, むしろ分野や出張日数が強い規定要因となった. 具体的には, 分野では医歯薬学と比べて, 他分野では少なく (農学は除く), 出張日数が多い人は論文数が多い傾向がある. また, 婚姻や育児状況, それらと性別の交互作用など家族面の要因を独立変数としても, それらは規定要因とはならなかった. 結論として, 他の要因を統制すると, 性別は研究業績の規定要因とならず, 性別という属性に基づく研究業績の差は見られない. くわえて, 出張日数が研究業績に与える影響の大きさと, 多様な状況にある研究者への出張支援の重要さが示唆される.
2 0 0 0 大学教員の研究業績に対する性別の影響
- 著者
- 坂無 淳
- 出版者
- 日本社会学会
- 雑誌
- 社会学評論 (ISSN:00215414)
- 巻号頁・発行日
- vol.65, no.4, pp.592-610, 2015
本稿では, 大学教員の研究業績の男女差について分析を行う. 多くの先行研究では, 平均的には男性の業績が多い傾向が示されている. しかし, 研究業績には性別という属性以外に多くの規定要因があり, それらの要因を統制したうえでも, なお性別が規定要因となるかを明らかにする必要がある. そこで, 2010年に日本の地方国立大学で行った調査から, 大学教員の1年間の論文数を従属変数とした統計的な分析を行う. その結果, 単純に平均値を比較すると, 年1本ほど男性の論文数が多い傾向があった. つぎに, 性別に加え, キャリア年数, 研究以外の業務量 (授業担当数や学内会議数), 出張日数, 分野, 職階を独立変数に入れた重回帰分析と, 低い値に偏る従属変数の分布に適合した負の二項分布回帰を行った. その結果, 性別は規定要因とならず, むしろ分野や出張日数が強い規定要因となった. 具体的には, 分野では医歯薬学と比べて, 他分野では少なく (農学は除く), 出張日数が多い人は論文数が多い傾向がある. また, 婚姻や育児状況, それらと性別の交互作用など家族面の要因を独立変数としても, それらは規定要因とはならなかった. 結論として, 他の要因を統制すると, 性別は研究業績の規定要因とならず, 性別という属性に基づく研究業績の差は見られない. くわえて, 出張日数が研究業績に与える影響の大きさと, 多様な状況にある研究者への出張支援の重要さが示唆される.
2 0 0 0 園井ゆり著『里親制度の家族社会学――養育家族の可能性』
- 著者
- 和泉 広恵
- 出版者
- 日本社会学会
- 雑誌
- 社会学評論 (ISSN:00215414)
- 巻号頁・発行日
- vol.65, no.4, pp.616-618, 2015
2 0 0 0 園井ゆり著『里親制度の家族社会学――養育家族の可能性』
- 著者
- 和泉 広恵
- 出版者
- 日本社会学会
- 雑誌
- 社会学評論 (ISSN:00215414)
- 巻号頁・発行日
- vol.65, no.4, pp.616-618, 2015
2 0 0 0 OA 組織文化論から組織シンボリズムへ
- 著者
- 竹中 克久
- 出版者
- 日本社会学会
- 雑誌
- 社会学評論 (ISSN:00215414)
- 巻号頁・発行日
- vol.53, no.2, pp.36-51, 2002-09-30 (Released:2009-10-19)
- 参考文献数
- 25
本稿では組織文化に関する2つの理論について言及する.1つは組織文化論であり, もう1つは組織シンボリズムである.双方とも「組織文化」という対象を共有しているにもかかわらず, そのアプローチにおいて著しい差異を示している.一方は組織成員の基本的仮定としての組織文化に着目し, 他方は組織文化を成員, 非成員を問わず当事者による解釈の対象としてのシンボルとみなす.前者についてはE.H.シャインの議論を, 後者についてはM. J.ハッチの議論を手がかりに分析する.結論としては, 筆者の立脚するスタンスは組織シンボリズムのそれに近い.組織文化のレベルに関しては, 基本的仮定のレベルよりシンボルとしての人工物のレベルを, 文化への関与に関しては, 特権的なリーダーより非特権的なフォロワーの視点をそれぞれ重視する.また, 組織文化論が組織と組織文化を合理性/非合理性という基準で明確に区分して位置づけるのに対し, 組織シンボリズムは組織それ自体を非合理的なシンボルとして考察するという視座を提起しており, 本稿でもこの見解を支持する.このような組織シンボリズムの視座は, これまで明確に理論化されてはこなかった, 組織アイデンティティやコーポレート・アイデンティティの分析に有効性をもつばかりでなく, 組織論の伝統的テーマであるリーダーシップ論や官僚制の逆機能, 組織変動の難しさの解明に新たな知見をもたらすものである.