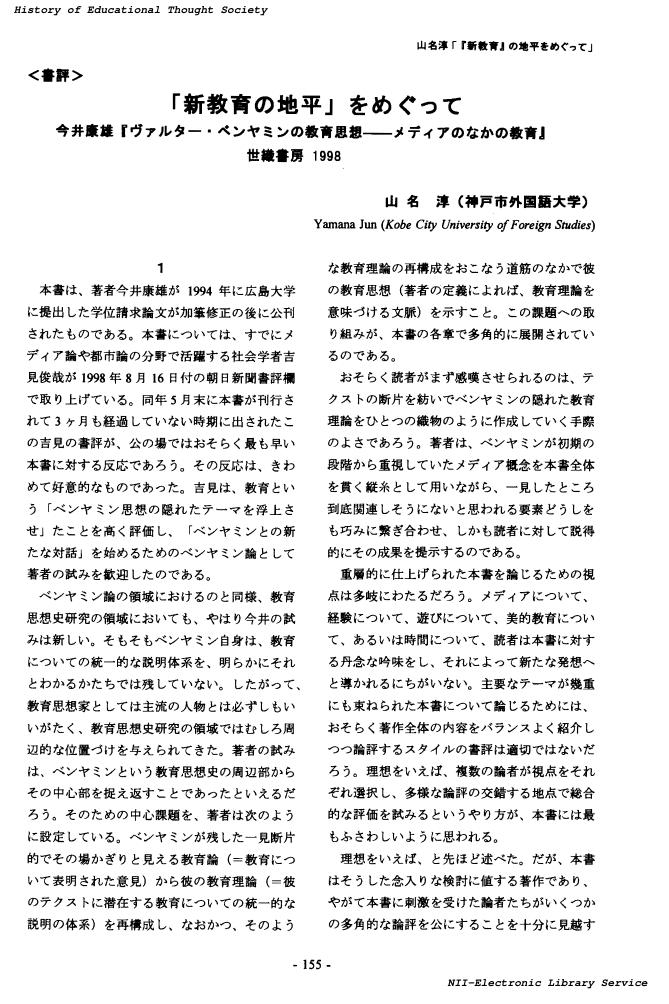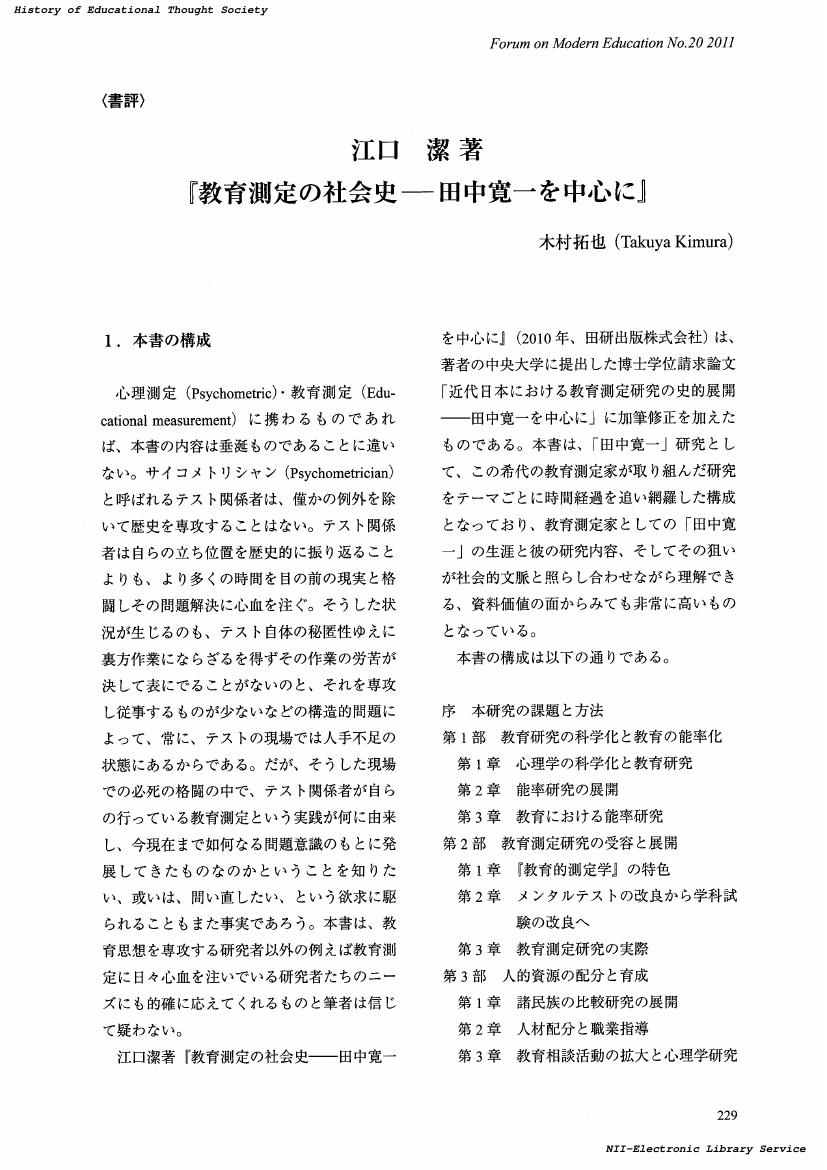- 著者
- 山名 淳
- 出版者
- 教育思想史学会
- 雑誌
- 近代教育フォーラム (ISSN:09196560)
- 巻号頁・発行日
- vol.7, pp.155-162, 1998-09-26 (Released:2017-08-10)
- 著者
- 松下 晴彦
- 出版者
- 教育思想史学会
- 雑誌
- 近代教育フォーラム (ISSN:09196560)
- 巻号頁・発行日
- vol.22, pp.287-291, 2013-09-14 (Released:2017-08-10)
- 著者
- 渡邊 隆信
- 出版者
- 教育思想史学会
- 雑誌
- 近代教育フォーラム (ISSN:09196560)
- 巻号頁・発行日
- vol.9, pp.65-72, 2000-09-25 (Released:2017-08-10)
- 著者
- 鬢櫛 久美子
- 出版者
- 教育思想史学会
- 雑誌
- 近代教育フォーラム (ISSN:09196560)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, pp.73-81, 2008-09-12 (Released:2017-08-10)
下司氏は、正統派精神分析、自我心理学派のリーダーであるH.ハルトマンをキーパーソンに、精神分析理論の変容を思想史として検討した。その結果、ハルトマンが精神分析を「自然科学化」、「発達心理学化」したことを明らかにし、ここに精神分析と教育の連関が生まれたと主張している。精神分析の思想史研究としては、論理も明晰で説得力も十分なものである。しかし、「『臨床の知』は教育をどこに導くのか」という問いが掲げられているにも関わらず、「臨床の知」とは何かということに関してほとんど言及していない。そこで、議論を活性化する試みとして、1. 「臨床の知」とは何かを、教育学の議論から探る。2. 理論やパラダイムと「臨床の知」の関係について考察する。3. キーパーソンを理論的指導者ハルトマンからE. H. エリクソンに変えることで、実践と理論の間にあるものを探る。この3点から、下司氏の精緻な研究の周辺にあるものを掘り起こしてみたい。
- 著者
- 駒込 武
- 出版者
- 教育思想史学会
- 雑誌
- 近代教育フォーラム (ISSN:09196560)
- 巻号頁・発行日
- vol.12, pp.83-96, 2003-09-27 (Released:2017-08-10)
本論文では林茂生という台湾人知識人がコロンビア大学に提出した学位論文に即して植民地教育の問題点を浮かび上がらせるとともに、当時の教育研究の中での位置づけを検討した。林の論文の基本的視座は、植民地教育と近代教育をほぼ同一視しながら、総督府の抑制的教育政策を批判するというものだった。しかし、1920年代に文化的同化政策が強化される状況の中でデューイの思想を流用しつつ、近代教育とは「内側から個々人を発達させる」ものであるという観点から植民地教育を批判した。その内容はアカデミックな教育研究の世界では黙殺される一方、台南長老教中学という学校を「台湾民衆の教育機関」として組織していく構想も1930年代には圧殺された。そこから浮かび上がってくる問題は、近代教育という理念の両義性であり、教育とは「日本人を日本人にまで陶冶する」(近藤壽治)ことであるという発想の暴力性である。
1 0 0 0 OA 公教育の成立 : フランス革命と第三共和政の場合(報告,シンポジウム)
- 著者
- 尾上 雅信
- 出版者
- 教育思想史学会
- 雑誌
- 近代教育フォーラム (ISSN:09196560)
- 巻号頁・発行日
- vol.6, pp.137-142, 1997-10-17 (Released:2017-08-10)
- 著者
- 矢野 智司
- 出版者
- 教育思想史学会
- 雑誌
- 近代教育フォーラム (ISSN:09196560)
- 巻号頁・発行日
- vol.24, pp.194, 2015-09-12 (Released:2017-08-10)
- 著者
- 松下 晴彦
- 出版者
- 教育思想史学会
- 雑誌
- 近代教育フォーラム (ISSN:09196560)
- 巻号頁・発行日
- vol.19, pp.83-91, 2010
古屋論文は、多くの課題を提示しているが、主要なテーマは1888年のデューイによる個体性、個と普遍(国家、社会)、民主主義の観念の検討である。古屋論文では「中心化と脱中心化」(モナドロジー)という方法をとるが、本稿では、観念の歴史(認識)という観点から、有機体的観念論期のデューイ思想の発展を辿る。すなわち「1888年のデューイというモナド」に焦点化するというよりも、初期デューイ思想の形而上学的・倫理学的展開において、ライプニッツや民主主義がどのように扱われたかという視点である。「個と普遍」論争については、古屋論文がライプニッツを起点としているのに対し、デューイ(タルド)とライプニッツを結ぶ線は、アリストテレスに行き着くこと、またこの観念史を19世紀末に受け継いだパースが個的なものに対し、「不確定なもの」から解釈している点を再評価する。
- 著者
- 小玉 重夫
- 出版者
- 教育思想史学会
- 雑誌
- 近代教育フォーラム (ISSN:09196560)
- 巻号頁・発行日
- vol.19, pp.31-36, 2010
物語を、他者との出会いと共同作業のなかでの語り直しのプロセスとしてとらえる場合、重要なのは他者の性格とその位置である。そこには、了解可能な他者と了解不可能な他者という、二重の他者性があり、この両者の関係をどのようにとらえるかが問題となる。この問題は、他者の側からだけでなく、他者を了解、あるいは不了解する語りの当事者=主体の側からも、深められなければならない。この点について近年精力的な問題提起を行っているジュディス・バトラーの議論をふまえていえば、他者からの問いかけに対する応答を迫られることによって、物語る主体が脱中心化されるという視点は、他者の他者性を徹底させるうえで、重要なてがかりを提供する。
1 0 0 0 OA 近代日本の児童研究の系譜における認識論的転換 : 分析視角の移動とその近代学校論的意味
- 著者
- 河野 誠哉
- 出版者
- 教育思想史学会
- 雑誌
- 近代教育フォーラム (ISSN:09196560)
- 巻号頁・発行日
- vol.11, pp.175-188, 2002-12-04 (Released:2017-08-10)
科学の名を冠する調査的実践の歴史的系譜のなかで、児童という存在はいかなる分析視角のもとで捉えられてきたのか。こうした問題関心のもとに、本稿は、近代日本において取り組まれた2つの大規模児童測定調査(明治期における医学士・三島通良によるそれと、大正末における心理学者・大伴茂によるそれ)をとりあげ、これらを分かつ「隔たり」に注目するところから出発して、近代日本の児童研究の系譜のなかで児童を対象化するまなざしの根本的な転換について論じる。ここで本稿が指摘するのは、個人性への分析視角の移動と、それに伴って生じた教育臨床的なまなざしの成立という局面である。また、そのうえで、大正末から昭和初年にかけての時期において、このような根本的な転換をへて生まれることになった新しいタイプの科学的知の実践のもつ、近代学校論的な含意について検討していく。それは、当時の学校システムが直面しつつあった危機的状況への対応として、新たに要請された実践であったというのが、ここでの論点である。
- 著者
- 小林 大祐
- 出版者
- 教育思想史学会
- 雑誌
- 近代教育フォーラム (ISSN:09196560)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, 2017
1 0 0 0 OA デューイというモナドが映す有機的統一の思想 : 若きデューイと「個人の時代」を考える(報告論文,デューイというモナドが映す有機的統一の思想-若きデューイと「個人の時代」を考える-,フォーラム2)
- 著者
- 古屋 恵太
- 出版者
- 教育思想史学会
- 雑誌
- 近代教育フォーラム (ISSN:09196560)
- 巻号頁・発行日
- vol.19, pp.57-72, 2010-09-19 (Released:2017-08-10)
本論文は、初期デューイのライプニッツ論そのものとそれを育んだヘーゲル主義という近景にまず焦点を合わせる(中心化)。次に、アメリカを離れ、フランスのタルドを、同時代にライプニッツ論を著したという理由だけで視野の外から取り上げて提示する(脱中心化)。ヘーゲル主義の影響が生涯デューイに残り続けたとする近年の研究や、同時代にデューイと同様にライプニッツについて論じたタルドも手掛かりとしながら、若きデューイの有機的統一の思想と個性論を考察することを通して、「個人の時代」(ルノー)と対時してみたい。それは、本論文の方法論的枠組みであるライプニッツの中心化-脱中心化の論理を、タルドと同じく「ライプニッツの子ども」である初期デューイの思想そのものに見出すことでもあるだろう。
1 0 0 0 OA 近代教育[学・思想]批判と教育学教育 : 批判の後にくるもの(アゴラ)
- 著者
- 松浦 良充
- 出版者
- 教育思想史学会
- 雑誌
- 近代教育フォーラム (ISSN:09196560)
- 巻号頁・発行日
- vol.5, pp.167-173, 1996-09-06 (Released:2017-08-10)
- 著者
- 小林 正泰
- 出版者
- 教育思想史学会
- 雑誌
- 近代教育フォーラム (ISSN:09196560)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, pp.112-118, 2016
- 著者
- 小林 正泰
- 出版者
- 教育思想史学会
- 雑誌
- 近代教育フォーラム (ISSN:09196560)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, pp.112-118, 2016 (Released:2017-09-30)
1 0 0 0 OA 生きられた学校と近代学校批判(報告論文, シンポジウム1 戦後教育史と近代教育学批判)
- 著者
- 木村 元
- 出版者
- 教育思想史学会
- 雑誌
- 近代教育フォーラム (ISSN:09196560)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, pp.86-94, 2016 (Released:2017-09-30)
1 0 0 0 OA 江口潔著, 『教育測定の社会史-田中寛一を中心に』, 田研出版株式会社, 2010年8月
- 著者
- 木村 拓也
- 出版者
- 教育思想史学会
- 雑誌
- 近代教育フォーラム (ISSN:09196560)
- 巻号頁・発行日
- vol.20, pp.229-234, 2011-09-18 (Released:2017-08-10)
- 著者
- 尾崎 博美
- 出版者
- 教育思想史学会
- 雑誌
- 近代教育フォーラム (ISSN:09196560)
- 巻号頁・発行日
- vol.24, pp.42-49, 2015-09-12 (Released:2017-08-10)
「公衆」と「大衆」を分かつものは何か。「トランザクション」によって形成される「公衆性」を「知性」の一様式として捉えるとき、「公衆」とは実体ある集団の名前ではなく「個人」の一様態として特徴づけられる。「集団=協働」に基づく「行為」や「関係性」の観点から「公衆性」を形成する「教育」としてデューイの「デモクラシー」を描くことを試みる。
- 著者
- 藤川 信夫
- 出版者
- 教育思想史学会
- 雑誌
- 近代教育フォーラム (ISSN:09196560)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, pp.161-170, 2012-10-13 (Released:2017-08-10)
シンポジウム「共同性/協働性/協同性」における山名淳氏、生澤繁樹氏、小国喜弘氏による報告、いずれも興味深いものであったとはいえ、それぞれかなり内容の詰まった発表であり、少なくとも論者にとっては、限られたシンポジウムの時間内で消化することができなかった。そこで、以下では、筆者自身の学習の意味も込めて、まず第1章で生澤氏と小国氏の報告論文の内容を簡潔に整理して相互に関連づけることにする。さらに第2章では論者自身のアジール論を展開し、その上で第3章において、3名の報告者の報告論文を対比しつつ、自己反省を兼ねて、アジール論の問題点を指摘してみたいと思う。
- 著者
- 宮寺 晃夫
- 出版者
- 教育思想史学会
- 雑誌
- 近代教育フォーラム (ISSN:09196560)
- 巻号頁・発行日
- vol.16, pp.221-231, 2007
プラトンの『国家』、アリストテレスの『政治学』は、政治学と教育学にまたがる古典とみなされるし、シュライエルマッハーの『教育学講義』には、教育学を政治学と並ぶ倫理学の一部門とする発想がみられる。そうした政治と教育を重ね合わせて論じる構想が、今日どうして萎えてしまったのか。それには、政治の介入を許さない、教育学の側の理由-「オフリミット」論などといわれるだけではなく、政治学の側にも理由があるように思われる。本稿では、政治哲学者ハンナ・アーレント(1906-75)の所論を読みながら、政治学が教育学を遠ざけてきた/いる理由にふれ、両者のリユニオンの難しさの一端を明らかにしたい。