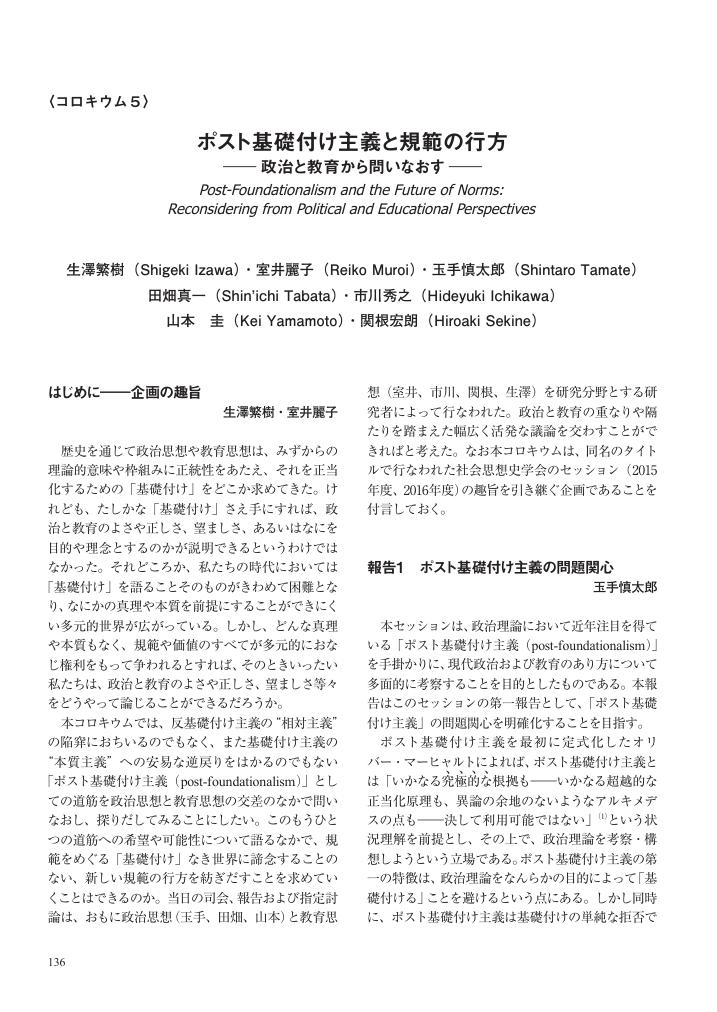1 0 0 0 OA ポスト基礎付け主義と規範の行方 : 政治と教育から問いなおす(コロキウム5)
- 著者
- 生澤 繁樹 室井 麗子 玉手 慎太郎 田畑 真一 Ichikawa Hideyuki 山本 圭 関根 宏朗
- 出版者
- 教育思想史学会
- 雑誌
- 近代教育フォーラム (ISSN:09196560)
- 巻号頁・発行日
- vol.27, pp.136-144, 2018 (Released:2019-09-07)
1 0 0 0 OA 教育学のフロイト受容を問いなおす : 宮澤康人氏の仕事を中心に(コロキウム4)
1 0 0 0 OA 視線の攻防、視線の快楽 : 近代日本の演説指南書にみる知識人の「身振り」
- 著者
- 秋田 摩紀
- 出版者
- 教育思想史学会
- 雑誌
- 近代教育フォーラム (ISSN:09196560)
- 巻号頁・発行日
- vol.13, pp.211-225, 2004-09-18 (Released:2017-08-10)
演説指南書とは、明治10年代から大量に出版されつづけた弁論術の総合マニュアル本である。これらの書物には、あるべき演説の姿や演説者像が図解つきの身振り手振りの技法という形で刻印されており、それはまた演説がまだ新奇な作法であった近代日本に理想とされた知識人像でもあった。本稿はこれらの身振り教授の図を手がかりに、学者に代表される知識人が不特定多数の人々にどのように見られたがっていたかという知識人の欲望を解き明かす。細かな計算つくの「技法」は、見られることに対する不安に裏打ちされていたが、明治40年代から大正時代にかけて、この不安は快楽に転換する。それとともに、身振りは演説者と聴衆を熱狂の渦にまきこむ重要な要素となっていく。演説の身振りを教えることをめぐる問題圏は、たんに演説者の文字通りの身振りだけではなく、近代以後、知識人に理想とされる「身振り」(振る舞い)がどのように構成されてきたかの考察をも含むものである。
- 著者
- 広田 照幸
- 出版者
- 教育思想史学会
- 雑誌
- 近代教育フォーラム (ISSN:09196560)
- 巻号頁・発行日
- vol.11, pp.87-96, 2002-12-04 (Released:2017-08-10)
本稿は、現代における「教える-学ぶ」関係のゆらぎを、現代社会のイデオロギー状況の変化から説明し、今後の方向の可能性について考察した。まず、教える行為と学ぶ行為とが、必ずしも原理的に結びついているわけではなく、常に偶然性をともなって成立するしかないことを指摘した。そのうえで、現代は、教える側が自らの行為を正当化するイデオロギーを喪失し、学ぶ側が優位な関係へと変化してきたこと、またそれゆえに、一方では学ぶ側にすり寄った学校論や教育関係論が流行し、他方では、社会からの些事にわたる要求を引き受けて、教える側が、多方面で不定型なものへと、その役割を広げてきたことを指摘した。今後の可能な方向は、学ぶ側を誘惑したり恫喝したりする仕掛けを考案する戦略、「教える」をやめる戦略、「教える」をイデオロギー的に復権する戦略などが考えられる。いずれを選ぶべきかは、価値的な選択にならざるをえない。
1 0 0 0 OA 「精神分析の影響」というトリック : 教育との接続という問いの立て方をめぐって(司会論文,フロイトからフロイト主義へ/病因論から教育言説ヘ-精神分析の心理学化と因果論の変容-,フォーラム2)
- 著者
- 西平 直
- 出版者
- 教育思想史学会
- 雑誌
- 近代教育フォーラム (ISSN:09196560)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, pp.63-72, 2008-09-12 (Released:2017-08-10)
教育における精神分析の影響。その問題を学説史に即して考察した論考(下司論文)を手掛かりに、まず、精神分析の「科学化」を媒介とした教育との接続を確認し、次に、フロイト精神分析に遡って「科学化される以前」の姿を確認し、そこから何が変質したのか、その転換を確認する。その上で、こうした問いの立て方とはまったく別に、フロイト精神分析それ自身のうちに「教育学的含意」を探る可能性に言及し、その作業は「教育」概念そのものを新たに規定する作業とワンセットになっていることを論じた。同時に、そうした考察を通して、「精神分析の影響」という問いの立て方が、罠にもなれば、議論を活性化する起爆剤ともなることを示した。
1 0 0 0 OA 捉え返される意志 失われた中動態を手がかりとして
- 著者
- 山口 裕毅
- 出版者
- 教育思想史学会
- 雑誌
- 近代教育フォーラム (ISSN:09196560)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, pp.23, 2017 (Released:2018-09-08)
1 0 0 0 OA ポストトゥルースの時代における教育と政治 : よみがえる亡霊、来たるべき市民
- 著者
- 小玉 重夫
- 出版者
- 教育思想史学会
- 雑誌
- 近代教育フォーラム (ISSN:09196560)
- 巻号頁・発行日
- vol.27, pp.31-38, 2018 (Released:2019-09-07)
- 著者
- 山内 清郎
- 出版者
- 教育思想史学会
- 雑誌
- 近代教育フォーラム (ISSN:09196560)
- 巻号頁・発行日
- vol.24, pp.134-141, 2015
本シンポジウムでは「『公/私』枠組みの入れ籠的な二重構造」という課題設定のもと、同志社大学と新島襄、慶応義塾大学と福澤諭吉の事例が報告され、その解明のための論証がなされた。だが私学の「理念」という側面から見たとき、そこにはすでに先立って「神話化」と「世俗化」のせめぎ合いの場が存在し、『福翁自伝』ほかのテクスト・史料であっても、新島のエピソード・事件であっても、それらは、素朴に現実を表現する「開かれた窓」でもなく、また、歴史史料に対する懐疑派たちが言うような史実を反映しない「閉ざしてしまっている壁」でもなく、「ゆがんだガラス」としての「史料」「証拠」という意味合いをもっているのではないか。このように「証拠」「史料」を「ゆがんだガラス」と見立てる方法論にしたがえば、「『公/私』の枠組みの入れ籠的な二重構造」の複雑さにアプローチする別の方途がありうるのではないか。その方向性を模索した。
- 著者
- 藤井 佳世
- 出版者
- 教育思想史学会
- 雑誌
- 近代教育フォーラム (ISSN:09196560)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, pp.214-217, 2020
- 著者
- 青柳 宏幸
- 出版者
- 教育思想史学会
- 雑誌
- 近代教育フォーラム (ISSN:09196560)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, pp.1-14, 2012-10-13 (Released:2017-08-10)
マルクスが「資本論」において「全体的に発達した個人」という表現を用いたとき、彼がその表現によって表現しようとしていたのはプロレタリアートという近代的な労働者のすがたであった。「全体的に発達した個人」という表現によってマルクスは富一般の創造手段としての労働の主体とされているプロレタリアートのすがたを批判的に把握しようとした。マルクスにおいて「全体的に発達した個人」とは機械制大工業の発展の結果として必然的に現れる人間像を記述したものであり、意識的にその実現をめざすべき教育目的などではなかったのである。マルクスは自由時間を享受した主体は労働時間においても単なる労働の主体ではない「別の主体」になると考えていた。そして、労働者の「別の主体」への転化すなわち人間の解放は、資本制的生産関係の下での機械の発展のなかで既に密やかに始まりつつあると考えていたのである。
1 0 0 0 OA 「高等」教育とはなにか : 思想史が問う(コロキウム5)
- 著者
- 清水 禎文
- 出版者
- 教育思想史学会
- 雑誌
- 近代教育フォーラム (ISSN:09196560)
- 巻号頁・発行日
- vol.13, pp.143-149, 2004
近代とは、認識論に基因する新たな人間像の提示、またその人間像に基づく人間的諸権利の発見及びその制度化への努力であった。それは本質的には、人間に自由をもたらす解放の理念であった。しかし、当初の理念が希薄化し、官僚化した制度のみがひたすら合理化へと向かうなかで、最終的には意味の失われた「鉄の檻」に至るというアイロニーをもたらした。新たな認識論上の革命でもないかぎり、そこから逃れることはできない。こうした状況のなかにあって、実践的な課題としては、認知のみならず身体に刻み込まれる習熟と模倣、あるいは関係性と自己創出は、新たな教育を切りひらく有効な手段となりうるであろう。
1 0 0 0 OA ピュタゴラス主義とは何か(シンポジウム コメント論文)
- 著者
- 加藤 守通
- 出版者
- 教育思想史学会
- 雑誌
- 近代教育フォーラム (ISSN:09196560)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, pp.102-109, 2020 (Released:2021-09-11)
- 著者
- 小玉 亮子
- 出版者
- 教育思想史学会
- 雑誌
- 近代教育フォーラム (ISSN:09196560)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, pp.129-138, 2016
- 著者
- 小玉 重夫
- 出版者
- 教育思想史学会
- 雑誌
- 近代教育フォーラム (ISSN:09196560)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, pp.89-102, 2006
グローバリゼーションが国民国家にかわる新たな政治社会の構成原理をもたらすのかどうか、もしそうだとすればその条件は何なのか。本稿では、アンソニー・ギデンズ、ハート=ネグリ、ジョルジョ・アガンベンの3者の思想に注目し、この問題を検討した。まず、ギデンズは、「第三の道」において旧式の福祉国家とは異なる包含のシナリオに定位した議論を提起した。だが、それは包含と排除のアポリアを顕在化させるものであった。これに対して、ハート=ネグリとアガンベンは、包含と排除の機制を見据え、マルチチュードとホモ・サケルという、対照的な議論を展開した。ハート=ネグリの場合は、マルチチュードの構成的権力によって包含/排除の境界線を反転させる構想を提起した。それに対してアガンベンは、構成的権力と主権権力の間の危うい偶然的な関係に依拠した政治を構想することによって、包含/排除の境界線それ自体を無化しようとした。アガンベンの議論は、潜勢力(可能性)と現勢力(現実)との間の必然的なつながりを否定する労働価値説批判としての側面をもつており、この方向で政治教育の復権を模索することが、グローバリゼーション下における新しいシティズンシップを探求するうえでの一つの鍵となることを明らかにした。
1 0 0 0 OA 精神分析と教育 : エディプス・コンプレックスをめぐって(Colloquium 3)
- 著者
- 野平 慎二
- 出版者
- 教育思想史学会
- 雑誌
- 近代教育フォーラム (ISSN:09196560)
- 巻号頁・発行日
- vol.19, pp.15-30, 2010
物語論(Narrative Approach)によれば、物語は物事や出来事の存在と意味を構成する基本的なメカニズムであるとされる。物語をとおした自己の存在(自己物語の語り)および変容(自己物語の語り直し)はいかに可能なのか。これについて考察することが本論の第一の課題である。また今日では、「大きな物語」の終焉の後に、「小さな物語」への囚われとでも呼ぶべき現象がみられる。こうした現象の歴史的な背景を探ることが本論の第二の課題である。「小さな物語」への囚われを回避するためには、弁証法的な発達の物語を支える、物語の存在論的な次元に目を向けることが必要である。このことは、自己物語の語り直し(語りえないものの意味づけ直し)が世代間の有意味な経験の伝承となるための条件ともなる。
1 0 0 0 OA アウグスティヌスに学ぶキリスト教的愛の教えとそのリアリティ Augustine’s Insight into Christian Doctrine of Love and Its Actuality
- 著者
- 神門 しのぶ
- 出版者
- 教育思想史学会
- 雑誌
- 近代教育フォーラム (ISSN:09196560)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, pp.78, 2017 (Released:2018-09-08)
- 著者
- 北野 秋男
- 出版者
- 教育思想史学会
- 雑誌
- 近代教育フォーラム (ISSN:09196560)
- 巻号頁・発行日
- vol.24, pp.1-9, 2015-09-12 (Released:2017-08-10)
- 被引用文献数
- 1
現代アメリカの学力向上政策は、1990年頃を境に「ハイステイクス・テスト」「タフ・テスト」と呼ばれる学力テストの結果に基づく教育アカウンタビリティ政策の具現化を特徴とする。M.フーコーは、「規律・訓練のすべての装置のなかでは試験が高度に儀式化される」(フーコー,1977: 188)として、試験が生徒を規格化し、資格付与し、分類し、処罰を可能とする監視装置となることを指摘したが、今や学力テストは児童・生徒を評価・監視するだけではない。学区・学校・教師をも評価・監視する装置へと変貌している。本論文で指摘する学力テストの「暴力性(violence)」とは、学力テストの実施と結果を利用した「抑圧」「統制」「管理」という「権力性(gewalt)」を意味するものであり、それは連邦政府や州政府によってもたらされた全ての児童・生徒、学区・学校・教員に対する脅威となるものである。