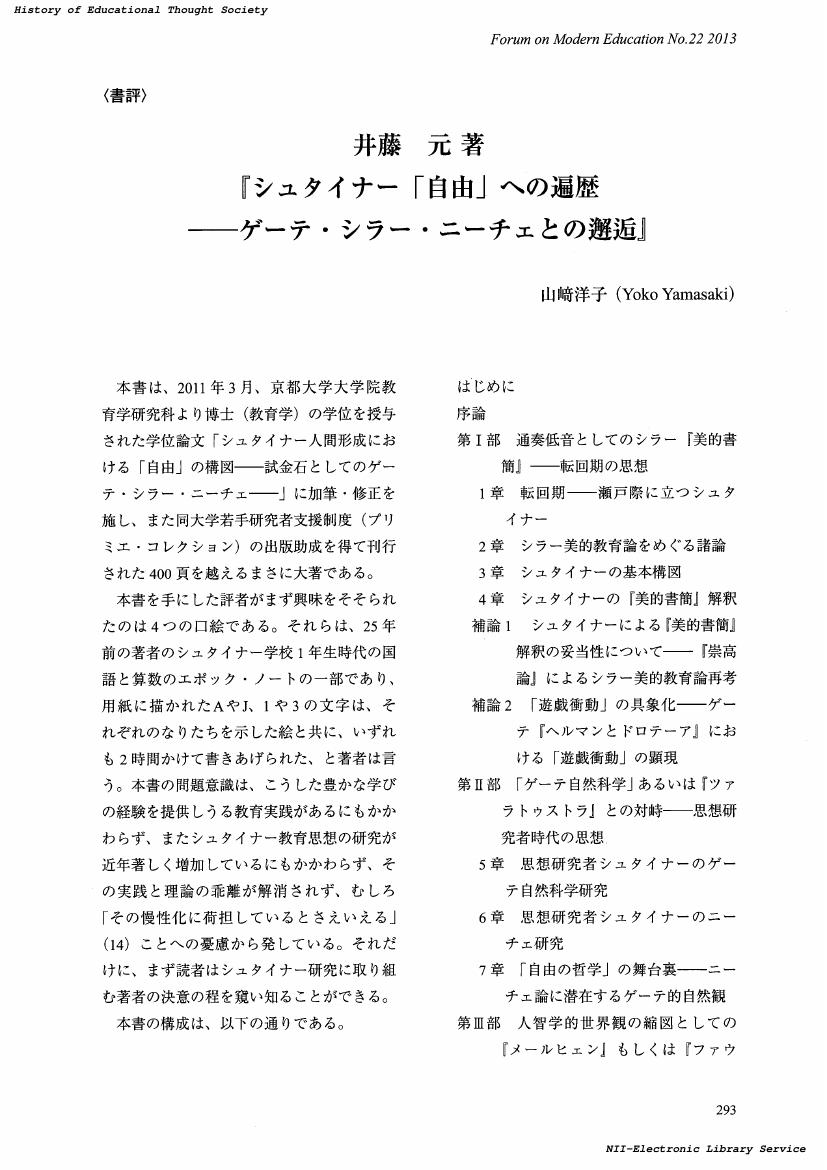- 著者
- 松浦 良充
- 出版者
- 教育思想史学会
- 雑誌
- 近代教育フォーラム (ISSN:09196560)
- 巻号頁・発行日
- vol.11, pp.109-121, 2002-12-04 (Released:2017-08-10)
「教育的関係」をめぐって、現在、相反する二つの状況が見られる。教育や人間形成環境における「関係性」の喪失や危機が叫ばれる一方で、これまで「教育的関係」が意識されなかったような、たとえば大学・高等教育などの領域において、その増殖・強化が指摘される。教育学においては、19世紀末から20世紀にかけて教育関係論という認識枠組みが成立したが、それはやがて教育的相互作用論にシフトした。しかしそれは結局「教育的関係」の喪失を追認する役割を果たし、またその危機と増殖というアンビヴァレントな状況を説明する有効な診立てを提供できていない。さらに「教え-学ぶ」という教育関係論の概念装置は、関係性の媒介項として「内容」を想定する場合に、より現実的な認識を提供することを予感させる。ただしこれについても「学び」の強調によって、相互作用論と同様の結果をもたらしている。そこから本稿は、既存の教育学や心理学の影響を受ける以前の、Learning概念の思想史的研究を展望する。
- 著者
- 伊藤 敏子
- 出版者
- 教育思想史学会
- 雑誌
- 近代教育フォーラム (ISSN:09196560)
- 巻号頁・発行日
- vol.18, pp.285-288, 2009-09-12 (Released:2017-08-10)
- 被引用文献数
- 1
1 0 0 0 OA 道徳的知と行為のアポリアに抗して-自然主義・歴史主義・共同体主義からの批判とその可能性- : 松下良平著, 『知ることの力-心情主義の道徳教育を超えて-』, 勁草書房, 2002年刊行
- 著者
- 松下 晴彦
- 出版者
- 教育思想史学会
- 雑誌
- 近代教育フォーラム (ISSN:09196560)
- 巻号頁・発行日
- vol.12, pp.241-245, 2003-09-27 (Released:2017-08-10)
- 著者
- 髙橋 舞
- 出版者
- 教育思想史学会
- 雑誌
- 近代教育フォーラム (ISSN:09196560)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, pp.127-135, 2019 (Released:2020-09-12)
- 著者
- 真壁 宏幹
- 出版者
- 教育思想史学会
- 雑誌
- 近代教育フォーラム (ISSN:09196560)
- 巻号頁・発行日
- vol.8, pp.111-124, 1999-09-25 (Released:2017-08-10)
- 著者
- 眞壁 宏幹
- 出版者
- 教育思想史学会
- 雑誌
- 近代教育フォーラム (ISSN:09196560)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, pp.67-79, 2012-10-13 (Released:2017-08-10)
本司会論文は、西村拓生会員によって示されたシュタイナーのシラー解釈を、シラー『美育書簡』の再読を通して検討し、シラーの『美育書簡』の核心が、美・芸術による「脱・像化Entbildung」の経験を通した「陶冶Bildung」にあることを示し、この陶冶プログラムが学校教育の枠を超える文化プロジェクトだったことを示す。
1 0 0 0 OA 日本社会と教育の〈いま〉 : ハイパー・メリトクラシーからハイパー教化へ
- 著者
- 本田 由紀
- 出版者
- 教育思想史学会
- 雑誌
- 近代教育フォーラム (ISSN:09196560)
- 巻号頁・発行日
- vol.27, pp.57-65, 2018 (Released:2019-09-07)
1 0 0 0 OA 再政治化と批判的教育学 : ランシエールとホネットの思想に焦点をあてて
- 著者
- 藤井 佳世
- 出版者
- 教育思想史学会
- 雑誌
- 近代教育フォーラム (ISSN:09196560)
- 巻号頁・発行日
- vol.27, pp.50-56, 2018 (Released:2019-09-07)
1 0 0 0 OA 教育思想家は「科学(Wissenschaft)」をどう考えてきたか?(コロキウム4)
- 著者
- 山内 清郎
- 出版者
- 教育思想史学会
- 雑誌
- 近代教育フォーラム (ISSN:09196560)
- 巻号頁・発行日
- vol.19, pp.45-55, 2010
本コメント論文の主要な話の筋立ては、次の四点である。第一に、人間の存在を、物語的な存在と捉えることによって、物語が人間にとってはたす機能を確認する。そして、そうした人間の有様を、仮に「物語的理性」というように呼称することにする。第二に、野平氏が物語なるものの推移を語る際に大きな参照点としたベンヤミンによる物語についての論考をあらためて検討することによって、物語なるものを歴史的な条件から論究する際のやっかいさについて若干の指摘を行なう。第三に、物語なるものの論究のやっかいさを示す傍証として、アウエルバッハ『ミメーシス-ヨーロッパ文学における現実描写』より「オデュッセウスの傷痕」を、その物語の巧みな分析手法とともに紹介する。第四に、物語(論)が射程とすべき主戦場の範囲を明らかならしめることによって、物語(論)が、今後問うていくべき問題の領野、ならびに、そのための方法論への示唆を記す。
- 著者
- 山崎 洋子
- 出版者
- 教育思想史学会
- 雑誌
- 近代教育フォーラム (ISSN:09196560)
- 巻号頁・発行日
- vol.22, pp.293-298, 2013-09-14 (Released:2017-08-10)
- 著者
- 田中 智志
- 出版者
- 教育思想史学会
- 雑誌
- 近代教育フォーラム (ISSN:09196560)
- 巻号頁・発行日
- vol.13, pp.39-48, 2004-09-18 (Released:2017-08-10)
弘田は、近代教育学がいだいてきたカント像を構成するいわば言説装置を論じている。それは「超越論的なものと経験的なもの」とのせめぎあいである。この言説装置によって喚起されるものが近代教育学に見られる「人間的なもの」への渇望である。彼は私たちの教育学研究がこの言説装置の「外」に出られないという。彼のカント論はフーコーのカント論を彼なりに読みかえたうえで構成されているが、彼のフーコー論はフーコーが拒絶したカントの人間学をフーコーの晩期思想と見なすとともに、フーコーが肯定したカントの<アクチュアリテからの批判>をフーコーの思想から消している。人間学こそフーコーの敵であり、アクチュアリテこそすべての言説装置の「外」を開く起点である。批判的で闘争的なフーコーを批判的で非闘争的なカントのなかに回収してはならない。
- 著者
- 樋口 聡
- 出版者
- 教育思想史学会
- 雑誌
- 近代教育フォーラム (ISSN:09196560)
- 巻号頁・発行日
- no.21, pp.81-89, 2012-10-13
「美と教育」再論を見据えて、シュタイナーのシラー論を考察の対象とし、特にシュタイナーの『自由の哲学』における議論を、今日の教育や人間に関する通念的理解を異化する契機と見なすことを試みた西村拓生氏のフォーラム報告論文において、西村氏自身がその試みを「あえて」シュタイナーについて語ると規定していることが、本コメント論文では着目された。なぜ「あえて」なのか。シュタイナーをめぐるいくつかの文献とともに、筆者自身が経験したシュタイナー論との関わりも振り返えられ、シュタイナーを近代教育思想研究の中にこれまでの躊躇を越えて取り込む可能性が示唆された(「あえて」と言う必要は、もはやないだろう)。西村氏が異化の契機としてシュタイナーを捉えることもさることながら、むしろシュタイナー学校での教育実践を多角的に考察する中でシュタイナーの生き方や思想が参照され研究されることに、これからのシュタイナー教育思想研究のひとまずの方向性があるのではないかという見方が提示された。
1 0 0 0 OA 17世紀教育思想の地下水脈(コメント論文,17世紀の教育思想,Forum 2)
- 著者
- 菱刈 晃夫
- 出版者
- 教育思想史学会
- 雑誌
- 近代教育フォーラム (ISSN:09196560)
- 巻号頁・発行日
- no.12, pp.73-81, 2003-09-27
相馬伸一氏の「17世紀の教育思想-その再解釈のためのいくつかのアプローチ」という刺激的な論文から、とくに実質内容の中心と捉えられるコメニウスの「類似(アナロジー)」に着目し、その思想史的背景-地下水脈-の一端を、先行する時代・ルネサンスの自然観や「医学のルター」と当時よばれたパラケルススのなかに浮き彫りにしようとするラフな試論。結果、近代教育思想が再び活力源を汲み取るべき「大地」が示唆される。最後に、派生的に、教育思想史研究のあり方についても、簡単に言及した。
- 著者
- 岡村 達雄
- 出版者
- 教育思想史学会
- 雑誌
- 近代教育フォーラム (ISSN:09196560)
- 巻号頁・発行日
- vol.10, pp.282-286, 2001-09-14 (Released:2017-08-10)
- 著者
- 菱刈 晃夫
- 出版者
- 教育思想史学会
- 雑誌
- 近代教育フォーラム (ISSN:09196560)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, pp.1-17, 2008-09-12 (Released:2017-08-10)
人間とは、はたして「理性」的動物なのか、それとも理性的「動物」なのか。理性に力点を置くか、動物に力点を置くか。教育をどう捉えて実践するかは、結局、このアクセントの違いに大きく左右されよう。西洋文明の根底にあるキリスト教による教育思想を振り返るに、「神」と繋がる理性、霊性をそなえるとされる人間が、いかに動物としての自己自身と関係しながら「人間」になれるのか、あるいは、この世を人間化、文明化、道徳化させていくのかが模索されてきた。問題は、人間に元来そなわる、理性以前の動物的なもの-感情、情感、情動、熱情、情緒、情意、そして情念など-すなわち、からだで感じる「情」と、どう関わるかである。近代教育学のベースにあるキリスト教的な教育論が、情念との関わりのなかでどのように生成してきたのか、主にルターとその周辺(エラスムスやメランヒトンなど)を手がかりに明らかにしつつ、教育思想史を振り返ってみたい。
- 著者
- 生澤 繁樹
- 出版者
- 教育思想史学会
- 雑誌
- 近代教育フォーラム (ISSN:09196560)
- 巻号頁・発行日
- no.19, pp.151-155, 2010
- 著者
- 生澤 繁樹
- 出版者
- 教育思想史学会
- 雑誌
- 近代教育フォーラム (ISSN:09196560)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, pp.131-148, 2012
プラグマティストの社会理論の基本的アイデアを「社会的な自己」のなかに見出そうとする共同体論的解釈がある。いったい自己や人間の「自然・本性」は社会的なものか、それとも原子的なものなのか。この種の問いの立て方は、私たちの政治や教育における「共同性」の成り立ちを説明するさいの初発の設定として、とても馴染みの深い主題である。と同時に、すぐれて「近代的な」問い方でもある。本論文では、それを「契約」と「経験」という二つの考察枠組みから理解したい。これらはいずれも、人間の自然や本性についての問題構制と親密であったばかりでなく、政治思想史や教育思想史において私たちの「共同性」を創出する異なる仕掛けを長らく提示しつづけてきた。この対比を通してデューイの思想を考察すると、なぜそれが共同体論的に読みなおされるのか、その論拠と課題を見渡すことができるとともに、リベラリズムとコミュニタリアニズムという現代の政治思想史における論争が明示的には語らなかったものについて光を照らすことができる。