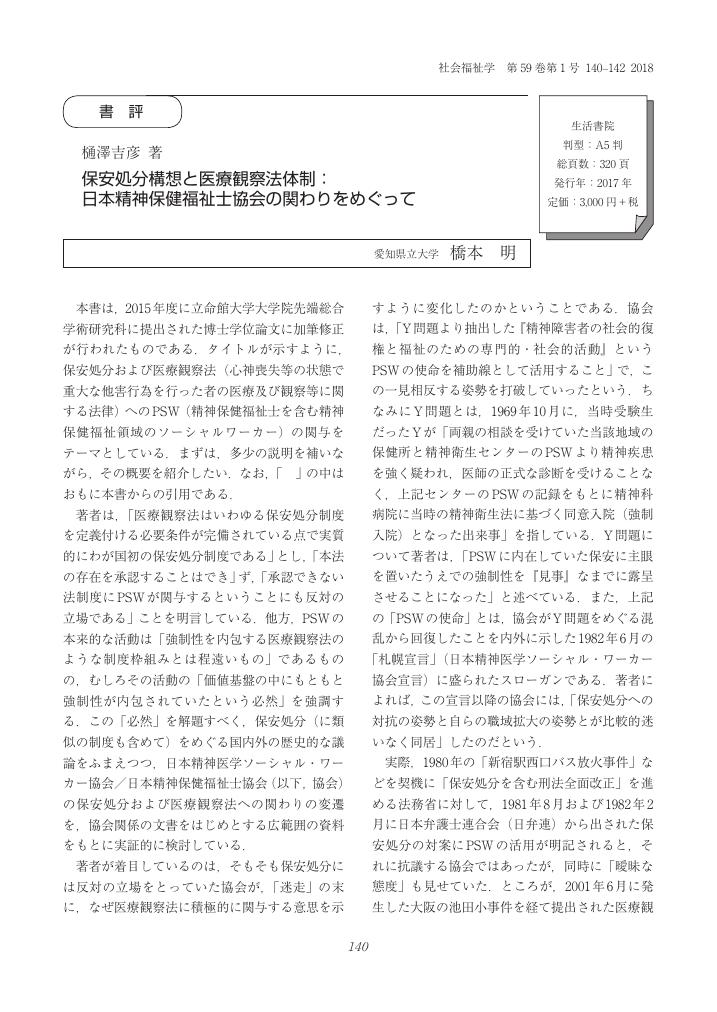1 0 0 0 OA 精神障害者の障害年金受給状況と家族要因
- 著者
- 風間 朋子
- 出版者
- 一般社団法人 日本社会福祉学会
- 雑誌
- 社会福祉学 (ISSN:09110232)
- 巻号頁・発行日
- vol.48, no.3, pp.30-41, 2007-11-30 (Released:2018-07-20)
本研究は,精神障害者の障害年金受給状況における,(1)精神障害者本人のケアを中心となって担う家族の続柄,(2)続柄別の世帯収入,の影響を明らかにすることを目的とした.全国精神障害者家族会連合会の会員2,844人から自記式質問用紙による回答を得た(有効回収率30.8%).その結果,以下のことが明らかとなった.(1)精神障害者本人の加齢に従い,ケアを担う家族の続柄が「親」から「きょうだい」へと世代交代する.(2)「きょうだい」では他の続柄と比較して障害年金受給者の割合が高い.(3)世帯収入が低いほど,障害年金受給者の割合が高い.(4)続柄と世帯収入の増減は障害年金受給状況に影響を与える.分析対象は障害年金の認知度が比較的高い集団であると推定されるが,続柄やその世帯収入により,障害年金受給状況に差が生じている.家族のもつ固有の背景を考慮し,その状況に合わせた支援施策を整備する必要があろう.
- 著者
- 樋澤 吉彦
- 出版者
- 一般社団法人 日本社会福祉学会
- 雑誌
- 社会福祉学 (ISSN:09110232)
- 巻号頁・発行日
- vol.59, no.1, pp.143, 2018-05-31 (Released:2018-06-28)
- 参考文献数
- 5
- 著者
- 橋本 明
- 出版者
- 一般社団法人 日本社会福祉学会
- 雑誌
- 社会福祉学 (ISSN:09110232)
- 巻号頁・発行日
- vol.59, no.1, pp.140-142, 2018-05-31 (Released:2018-06-28)
- 参考文献数
- 1
1 0 0 0 3.11東日本大震災と「災害弱者」
- 著者
- 戸田 典樹
- 出版者
- 一般社団法人 日本社会福祉学会
- 雑誌
- 社会福祉学 (ISSN:09110232)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, no.1, pp.178-178, 2017-05-31 (Released:2017-09-22)
1 0 0 0 韓国の社会的企業育成法の成果と課題
- 著者
- 呉 世雄
- 出版者
- 一般社団法人 日本社会福祉学会
- 雑誌
- 社会福祉学 (ISSN:09110232)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, no.2, pp.80-93, 2017-08-31 (Released:2017-09-27)
- 参考文献数
- 28
本研究は,韓国の「社会的企業育成法」の成果と課題を明らかにし,日本の社会的企業支援策に示唆を与えることを目的とする.研究方法としては,韓国の社会的企業にかかる経営実態調査および関連資料の再検討を通して現状を把握したうえで,社会的企業経営者へのインタビュー調査を行った.分析結果,育成法の成果としては,①社会的企業への関心の高まり,②自治体による支援策の活性化,③社会的弱者の雇用創出の効果,④民間企業からの協力・支援拡大の四つの大カテゴリーが挙げられた.課題としては,①社会的企業の概念の混同,②雇用の質の問題,③経営の持続可能性の弱さ,④公的支援による自律性の侵害,⑤市場秩序の混乱,⑥制度運用上の管理・監督の問題の六つの大カテゴリーが導き出された.以上の結果を踏まえ,考察では日本の社会的企業支援策への提案を行った.
1 0 0 0 民生委員を対象とした認知症が疑われる高齢者を発見した場合の地域包括支援センターへの援助要請意向とその関連要因の検討――認知症進行遅延薬に関する知識と認知症の人に対する肯定的態度に着目して――
- 著者
- 中尾 竜二 杉山 京 竹本 与志人
- 出版者
- 一般社団法人 日本社会福祉学会
- 雑誌
- 社会福祉学 (ISSN:09110232)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, no.1, pp.99-111, 2017
<p>民生委員における認知症が疑われる高齢者を発見した場合の地域包括支援センターへの援助要請意向とその関連要因を明らかにすることとした.</p><p>A県民生委員児童委員協議会に属する民生委員2,751名を対象に,属性,認知症進行遅延薬に関する知識,認知症の人に対する肯定的態度,地域包括支援センターへの援助要請意向について回答を求めた.統計解析として,まず地域包括支援センターへの援助要請意向について潜在クラス分析を用いて類型化を行った.次いで,各潜在クラスと属性等との関連性について,多項ロジットモデルを用いて検討した.</p><p>潜在クラス分析の結果,四つのクラスが抽出された.また多項ロジットモデルの結果,すべての潜在クラスに「認知症の人に対する肯定的態度」が有意な関連を示していた.</p><p>民生委員における地域包括支援センターへの援助要請意向の特徴は四つに類型化されることが明らかになった.また,地域包括支援センターへの援助要請意向を高めるためには,認知症の人に対する肯定的態度を高めることが重要である可能性が示唆された.</p>
- 著者
- 加瀬 裕子 久松 信夫 横山 順一
- 出版者
- 一般社団法人 日本社会福祉学会
- 雑誌
- 社会福祉学 (ISSN:09110232)
- 巻号頁・発行日
- vol.53, no.1, pp.3-15, 2012
認知症の行動・心理症状(Behavioural and Psychological Symptoms of Dementia ;以下,BPSD)が改善した204事例を収集し,行われた介入・対応についての記述データをカテゴリー化することで,BPSDへの効果的アプローチの構造を探索的にモデル化することを試みた.[介護側のコミュニケーションの改善][健康面への介入・対応][環境面への介入・対応][能力を維持するための課題への介入・対応][家族・介護者状況への介入・対応][事業マネジメントの改善]の6つのカテゴリーが生成された.効果が認められたBPSDの心理社会的要因へのアプローチでは,利用者の役割や社会性を強化するための「場」を調整することの重要性が示唆された.
1 0 0 0 書評 杉山 博昭 著「地方」の実践からみた日本キリスト教社会福祉
- 著者
- 梅木 真寿郎
- 出版者
- 一般社団法人 日本社会福祉学会
- 雑誌
- 社会福祉学 (ISSN:09110232)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, no.2, pp.151-154, 2016
1 0 0 0 知的障害者のスティグマ研究の国際的な動向と課題 : 文献レビュー
- 著者
- 米倉 裕希子 山口 創生
- 出版者
- 一般社団法人 日本社会福祉学会
- 雑誌
- 社会福祉学 (ISSN:09110232)
- 巻号頁・発行日
- vol.56, no.4, pp.26-36, 2016
本研究は,知的障害者のスティグマの特徴および今後の研究動向を明らかにするため,海外の研究をレビューした.PubMedで,「intellectual disability」および「stigma」をキーワードとし,2014年12月までの研究で検索された82研究のうち,関連のない研究を省いた25研究をレビューした.対象研究には,尺度研究,横断研究,介入研究が含まれており,横断研究の対象は知的障害者本人,家族,学生や市民だった.知的障害者の大半がスティグマを経験し,自尊感情や社会的比較と関連していた.家族も周囲からの差別を経験しており,被差別の経験はQOLや抑うつに影響する可能性があった,一般市民における大規模調査では短文事例と障害の認識がスティグマと関連し,介入研究では間接的な接触でも態度の改善に貢献できる可能性が示された.今後は,より効果的な介入プログラムの開発とその効果測定が望まれる.
1 0 0 0 セルフヘルプ・グループ・ユニークフェイスにみる機能の変遷について
- 著者
- 津久井 康明
- 出版者
- 一般社団法人 日本社会福祉学会
- 雑誌
- 社会福祉学 (ISSN:09110232)
- 巻号頁・発行日
- vol.55, no.3, pp.66-77, 2014
本研究では,1999年に設立されたセルフヘルプ・グループ(以下,SHG)ユニークフェイスの機能の変遷を明らかにし,SHGの機能をめぐる研究に新たな枠組みを提示することを目的とした.その際,「内へのセルフヘルプ」と「外へのセルフヘルプ」という分析枠組みを用いて,SHGユニークフェイスの活動の分析を行った.その結果,SHGユニークフェイスが,参加者の普遍的なニーズに対応する機能を前提としつつ,個別的なニーズの間のバランスを保ちながら,SHGの機能を調整していったことが明らかになった.また,SHGユニークフェイスに見られたような機能の変遷は,ほかのSHGへも適用できる可能性があることが示唆された.