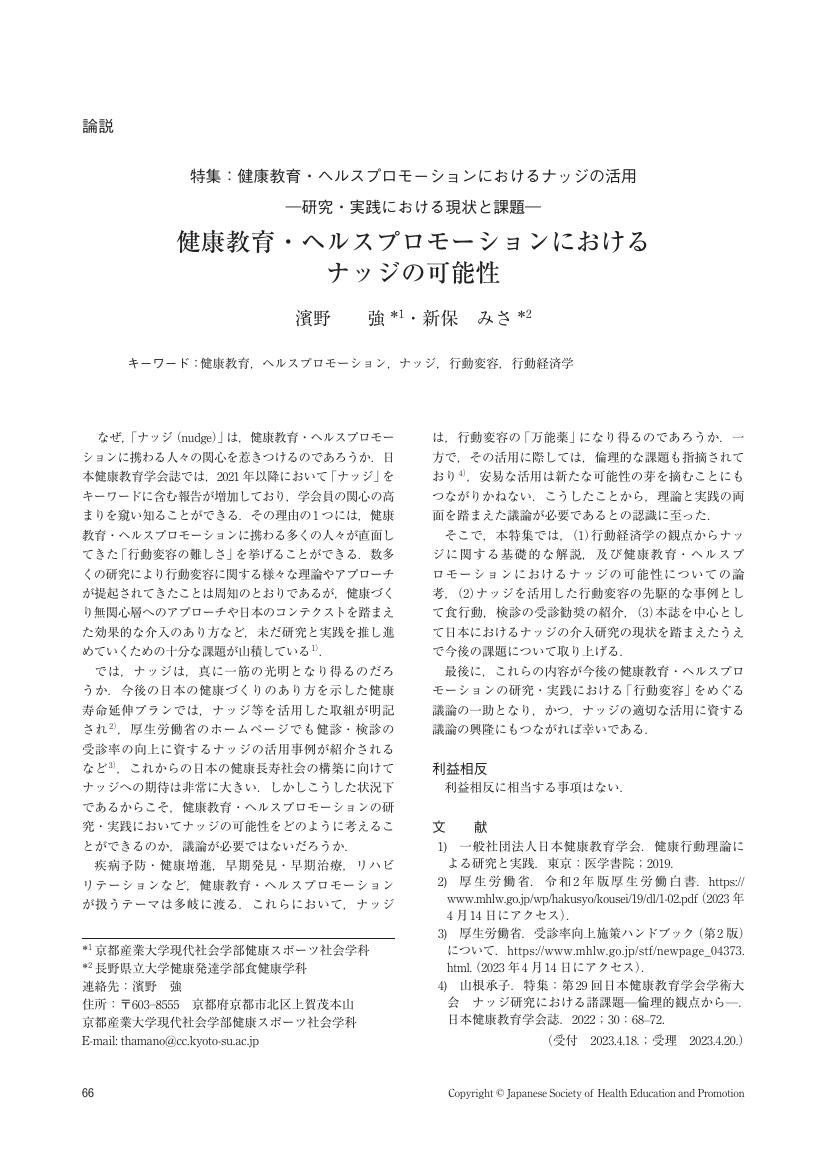18 0 0 0 OA 小学校における学級担任による給食指導
- 著者
- 新保 みさ 福岡 景奈 赤松 利恵
- 出版者
- 日本健康教育学会
- 雑誌
- 日本健康教育学会誌 (ISSN:13402560)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, no.1, pp.12-20, 2017 (Released:2017-02-28)
- 参考文献数
- 15
- 被引用文献数
- 3
目的:小学校の学級担任を対象に,学級担任が給食指導で参考にしていることを調べ,栄養教諭・学校栄養職員と相談している者の特徴を検討することを目的とした.方法:2014年7月,埼玉県A市の教育委員会を通して,市立小学校全32校の学級担任569名に横断的な質問紙調査を行った.調査項目は,給食指導を行う上で参考にしていること,給食指導で行っている取り組み,給食の喫食時間,学級全体の残菜量,属性であった.結果:解析対象者は456名で,男性143名(31.4%),平均教員経験年数(標準偏差)13.5(12.5)年だった.給食指導を行う上で参考にしていることのうち,選択した者が多かった上位3つの選択肢は「自分自身が家庭で受けた教育」(272名,59.6%),「自分自身が小学校のときに受けた給食指導」(208名,45.6%),「栄養教諭・学校栄養職員と相談」(172名,37.7%)だった.「栄養教諭・学校栄養職員と相談」を選択した者はしなかった者と比較して,女性,給食に関する校務分掌経験がある者,給食が自校式の者が多く,給食指導での取り組み個数が多かった.結論:学級担任は,自分自身が家庭や小学校で受けた教育を参考に給食指導をしている者が多かった.栄養教諭・学校栄養職員と相談している者は4割程度で,給食に関する校務分掌経験がある者や給食が自校式の者などの栄養教諭・学校栄養職員と関わる機会のある者が多かった.
- 著者
- 新保 みさ 串田 修 鈴木 志保子 中村 丁次 斎藤 トシ子
- 出版者
- 公益社団法人 日本栄養士会
- 雑誌
- 日本栄養士会雑誌 (ISSN:00136492)
- 巻号頁・発行日
- vol.65, no.6, pp.333-341, 2022 (Released:2022-06-01)
- 参考文献数
- 19
本研究では、日本栄養士会(栄養士会)の未入会者および栄養士会主催の研修会非参加者の特徴を調べることを目的に、2018年11~12月にインターネット上で横断的な自己記入式質問紙調査を行った。対象者は就業資格を必要とする15,133人だった。調査項目は属性、栄養士会入会有無と理由、栄養士会主催の研修会参加有無と理由とした。栄養士会の未入会者は入会者と比べて、年齢が低く、所有資格が栄養士のみで、最終学歴が大学、雇用形態が派遣や契約社員、勤続年数や年収が低い、勤務先が小・中学校、受託給食、保育所幼稚園等の者が多かった。未入会理由は会費が高いことや忙しい、栄養士会の活動を知らない等が多かった。研修会非参加者も参加者と比べて、未入会者と同様の特徴がみられた。研修会の非参加理由には、日程が合わないことを挙げる者が多かった。栄養士会の未入会者および研修会非参加者は年齢、雇用形態、勤続年数、年収、勤務先等に共通の特徴が見られた。
- 著者
- 串田 修 新保 みさ 鈴木 志保子 中村 丁次 斎藤 トシ子
- 出版者
- 公益社団法人 日本栄養士会
- 雑誌
- 日本栄養士会雑誌 (ISSN:00136492)
- 巻号頁・発行日
- vol.64, no.10, pp.581-588, 2021 (Released:2021-10-02)
- 参考文献数
- 33
本横断研究では、全国の管理栄養士と栄養士を対象に、基本属性、就業状況と職務満足度を把握し、両者の関連を検討することを目的とした。2018年11月にインターネット調査を実施し、就業資格を必要とする15,133人を解析対象者とした。基本属性では、性別・年齢・最終学歴・勤務地域・日本栄養士会の入会有無・研修会の参加回数を、就業状況では、所有資格・就業有無・就業資格・資格手当・優遇措置・雇用形態・実勤務先・勤務年数・年収を尋ねた。職務満足度は、5項目の尺度で評価した。尺度の得点を合計した結果、職務に満足している者は73.9%であった。職務満足度の高さには、年齢の高さ、大学等の卒業、勤務地域、日本栄養士会の入会、研修会の参加、管理栄養士の資格所有、昇給制度等の優遇措置、勤務年数や年収の多さ、勤務先が関係していた(全てp <0.05)。標本の代表性に課題があり、属性を限定した無作為抽出による追試も必要である。
1 0 0 0 OA 成人における生活習慣病のリスクを高める飲酒量と機能的・伝達的・批判的ヘルスリテラシー
- 著者
- 大内 実結 赤松 利恵 新保 みさ 小島 唯
- 出版者
- 特定非営利活動法人 日本栄養改善学会
- 雑誌
- 栄養学雑誌 (ISSN:00215147)
- 巻号頁・発行日
- vol.81, no.5, pp.202-209, 2023-10-01 (Released:2023-11-23)
- 参考文献数
- 38
【目的】飲酒に関する教育の一助となることを目指し,飲酒状況と機能的,伝達的,批判的の3つのヘルスリテラシー(以下,HL)との関連を示すことを目的とした。【方法】2020年11月実施のインターネット調査のデータを用い,20~64歳の男性3,010人,女性2,932人を対象とした。HLは,機能的,伝達的,批判的の3つのレベルごとに用いた。飲酒状況は,「非飲酒・生活習慣病のリスクを高める飲酒量(以下,高リスク量)未満」「高リスク量」に分類した。HL得点は,男女それぞれの中央値で高群と低群に分類した。HLを独立変数,飲酒状況を従属変数として,ロジスティック回帰分析により各HL高群における「高リスク量」のオッズ比を男女別に算出した。【結果】属性を調整した結果,女性では飲酒状況とレベルごとのHLに関連はみられなかったものの,HL総得点高群に高リスク量の者が少なかった (オッズ比 [95%信頼区間]:0.69 [0.54~0.88])。男性において,属性を調整しない結果では,高リスク量の者が機能的HL高群に少なく,批判的HL高群に多かったが,属性の調整により飲酒状況と各HLに関連はみられなくなった。【結論】本研究では飲酒状況とレベルごとのHLの関連を検討したが,有意な関連はみられなかった。女性では,生活習慣病のリスクを高める飲酒量の防止に向け,総合的なHLを高める重要性が示唆された。
1 0 0 0 OA 健康教育・ヘルスプロモーションにおけるナッジの可能性
- 著者
- 新保 みさ 中西 明美 會退 友美 衛藤 久美 坂本 達昭 中村 彩希
- 出版者
- 日本健康教育学会
- 雑誌
- 日本健康教育学会誌 (ISSN:13402560)
- 巻号頁・発行日
- vol.30, no.4, pp.313-318, 2022-11-30 (Released:2022-12-26)
- 参考文献数
- 14
背景:日本健康教育学会栄養教育研究会は2019年度からナッジをテーマとした活動を行っている.本稿では2021年度の活動として2022年3月26日に開催した公開学習会「第2弾!今,注目のナッジを健康行動に活用するには~ナッジと健康行動理論の関係~」について報告する.内容:学習会は3部構成で,第1部は竹林正樹氏による講義「一発でわかるナッジの基本」,第2部は栄養教育研究会からの提案「健康行動理論とナッジについて」,第3部はグループワークによる「ナッジを効かせたチラシ作り」であった.参加者は63名であった.学習会に対するアンケート(回答者数57名,回答率90%)では回答者の98%が「非常に満足した」または「まあ満足した」と回答した.満足した理由には,チラシ作りのグループワークやグループワーク後の発表に対する講師の講評などが多くあげられた.「今後もナッジを勉強し続けたいですか」という問いに,全ての回答者が「そう思う」または「少しそう思う」と回答した.結論:本学習会を通じて,参加者のナッジについての理解を深めることができた.理論と実践を含めた学習会は新たな学びを提供し,今後の学習意欲も高めたことが示唆された.
1 0 0 0 OA 管理栄養士養成課程におけるオンラインによる海外プログラムの実施と評価
- 著者
- 新保 みさ 尾関 彩 草間 かおる 中澤 弥子 笠原 賀子
- 出版者
- 特定非営利活動法人 日本栄養改善学会
- 雑誌
- 栄養学雑誌 (ISSN:00215147)
- 巻号頁・発行日
- vol.80, no.3, pp.177-184, 2022-06-01 (Released:2022-07-06)
- 参考文献数
- 10
【目的】本報告の目的は,管理栄養士養成課程におけるオンラインによる海外プログラムについて報告し,その評価を行うこととした。【活動内容】長野県立大学健康発達学部食健康学科の2年生30名に10日間のオンラインによる海外プログラムを実施した。研修先はニュージーランド(以下,NZ)で,プログラムの内容は英語,専門分野(Nutrition 1:NZの伝統菓子の講義・調理実演や調理実習,Nutrition 2:NZの管理栄養士とのセッション,Nutrition 3:栄養の基礎知識・NZの食文化や食生活指針等に関する講義),その他(学生交流など)などだった。プログラム終了後,目標達成度,国際的な視野の向上,NZの栄養・食の課題を説明できるか,海外プログラムの満足度を調査した。【活動成果】全日程に出席した者は27名(90%)だった。調査の回答者は26名(87%)で「海外の栄養士・管理栄養士の活動の現状を説明できる」という目標を達成できた・ほぼ達成できたと回答した者は23名(88%),オンラインによる海外プログラムに満足した・少し満足したと回答した者は23名(88%)だった。満足度に影響したことには現地の学生等との交流や調理実習や試食等の体験をあげた者が多かった。【今後の課題】今回実施したオンラインによる海外プログラムでは,機材や人員,時差,通信のトラブル等の課題があったが,プログラムの目標達成度や満足度は高かった。
1 0 0 0 OA 飲食店が提供する定食は「健康な食事(通称:スマートミール)」の基準に合致するか
- 著者
- 齋木 美果 新保 みさ 赤松 利恵 藤崎 香帆里
- 出版者
- 特定非営利活動法人 日本栄養改善学会
- 雑誌
- 栄養学雑誌 (ISSN:00215147)
- 巻号頁・発行日
- vol.77, no.6, pp.193-200, 2019-12-01 (Released:2020-02-06)
- 参考文献数
- 22
- 被引用文献数
- 5
【目的】東京都,神奈川県,埼玉県にある飲食店の定食が「健康な食事(通称:スマートミール)」(以降,スマートミール)の基準にどの程度適合しているか調べることを目的とした。【方法】店舗にて2食の定食の料理重量を測定し,その後栄養計算を行った。スマートミールの2段階の基準に沿って,定食を「650 kcal未満」「650 kcal以上」に分け,各々エネルギー量,食塩相当量,野菜等の重量(以降,野菜重量),エネルギー産生栄養素バランス(以降,PFC%E)の基準との適合の程度を記述統計にて検討した。【結果】25店舗の定食48食(解析対象96.0%)のうち,基準6項目全てを満たすものはなかった。「650 kcal未満」の定食(n=9,18.8%)のうち,エネルギー量の基準に適合するものは7食(77.8%),食塩相当量は6食(66.7%),野菜重量は4食(44.4%),PFC%Eのたんぱく質は4食(44.4%),脂質は1食(11.1%),炭水化物は4食(44.4%)だった。「650 kcal以上」の定食(n=39,81.3%)では,エネルギー量が12食(30.8%),食塩相当量は8食(20.5%),野菜重量は12食(30.8%),たんぱく質は22食(56.4%),脂質は9食(23.1%),炭水化物は13食(33.3%)だった。【結論】本研究で対象とした飲食店の定食でスマートミールの基準に合致するものはなかった。「650 kcal未満」の定食では,食塩相当量の基準に適合する定食が多かった。「650 kcal以上」の定食では,エネルギー量,食塩相当量に適合する定食が少なかった。いずれも,野菜重量とPFC%Eに適合する定食は少なかった。
- 著者
- 新保 みさ 角谷 雄哉 江口 泰正 中山 直子
- 出版者
- 日本健康教育学会
- 雑誌
- 日本健康教育学会誌 (ISSN:13402560)
- 巻号頁・発行日
- vol.23, no.3, pp.246-250, 2015
目的:学会セミナー「研究・実践からアドボカシー(政策提言)へ」は,アドボカシーについて学び,学会としてのアドボカシーのあり方を議論するためになされた.本報告では,講演後になされた,「研究・実践からアドボカシー(政策提言)へ」に関する総合討論の概要をまとめた.<br>内容:総合討論では,第1部の講演の内容やアドボカシーに関して,総合司会を中心に,講演者と参加者が相互に質問や意見交換を行った.主な話題としてアドボカシーへの原動力,アドボカシーの担い手,学会としてのアドボカシーのあり方に関して議論があった.講演者はこれまで関わってきたグローバル,国,自治体,企業のそれぞれのレベルにおける視点で発言をしていた.討論を通じて,日本でアドボカシーを進めるための課題として,行政機関における人材育成のあり方や大学の役割があげられた.政策を作る側からも学会としてアドボカシーを行う必要性が述べられ,今後の方向性が確認された.<br>結論:講演者と参加者の議論によって,アドボカシーはそれぞれのレベルで推進されているものの,課題があることが分かった.今後,日本健康教育学会としてのアドボカシーを推進するためには,意見を1つにまとめ,議論を重ねていく必要がある.
1 0 0 0 OA フリップチャート教材「誘惑に負けない体重管理」
- 著者
- 新保 みさ 赤松 利恵 しんぽ みさ あかまつ りえ
- 出版者
- お茶の水女子大学附属図書館(E-bookサービス)
- 巻号頁・発行日
- 2016-02-12
本教材は,成人の体重管理を目指す者を対象に,つい食べ過ぎてしまう場面において,食べ過ぎないためにどうしたらいいか,食べ過ぎてしまったらどうしたらいいかという対策を学ぶための教材です。フリップチャートは指導者がそれぞれの食べ過ぎてしまう場面,対策について説明する時に使います。ワークシートや対策シートは,学習者が自分に合った対策を考えるために使用し,誘惑日記は学習者が誘惑場面や対策についてモニタリングを行うために使います。それぞれの教材の詳しい使い方は,手引きをご参照ください。印刷方法は、次のURLをご参照ください。http://www.lib.ocha.ac.jp/e-book/list_0007a.html
- 著者
- 新保 みさ 赤松 利恵 山本 久美子 玉浦 有紀 武見 ゆかり
- 出版者
- The Japanese Society of Nutrition and Dietetics
- 雑誌
- 栄養学雑誌 (ISSN:00215147)
- 巻号頁・発行日
- vol.70, no.4, pp.244-252, 2012
- 被引用文献数
- 2
【目的】成人を対象とした体重管理の誘惑場面における対策について,ゲームを通して学習できるカード教材「ベストアドバイザーFORダイエット」を開発した。本稿では,カード教材の解説を行うとともに,保健医療従事者によるカード教材の評価を報告する。<br>【方法】2011年7月~10月に開催された市町村の保健医療従事者向けの研修会に参加した66名を対象にカード教材のゲーム式の使い方を実施した。ゲーム終了後に,質問紙を用いてゲームの感想や遊び方,体重管理の教材としての評価,属性をたずねた。また,質問紙の最後に意見や感想を自由記述で記載する欄を設けた。<br>【結果】解析対象者は62名(女性:57名,91.9%)だった。「ゲームは楽しかったですか」,「体重管理の教材として役立つと思いますか」という問いに対してそれぞれ57名(91.9%),49名(79.0%)が「とてもそう思う/そう思う」と回答した。自由記述では,指導者向け</TS><TS NAME="抄録">の教材として利用したいという意見があがった。一方で,教材や遊び方について,ルールや内容が難しいなどの改善すべき点もあがった。<br>【結論】体重管理の誘惑場面における対策に関する学習教材として,肯定的な意見が得られた。あげられた改善点をもとに,教材の見直しを行い,今後は一般成人を対象に実行可能性および教育効果について,検討をする必要がある。