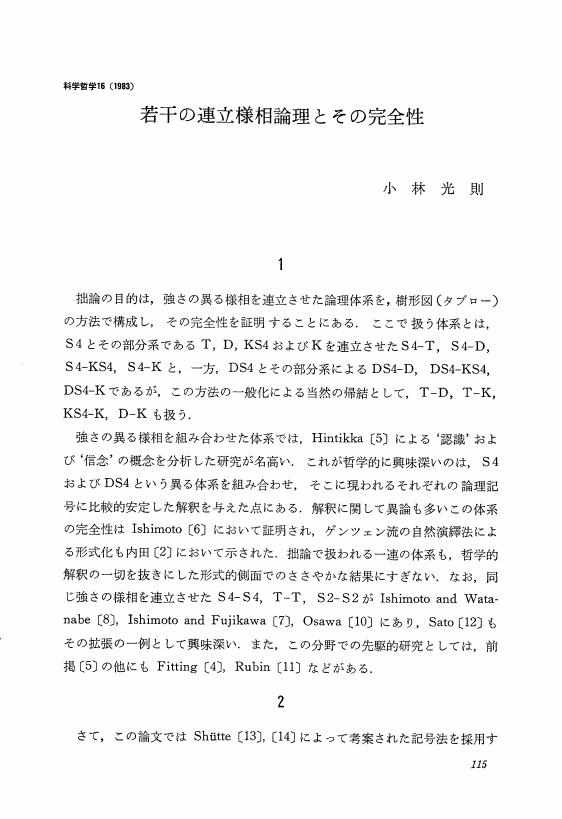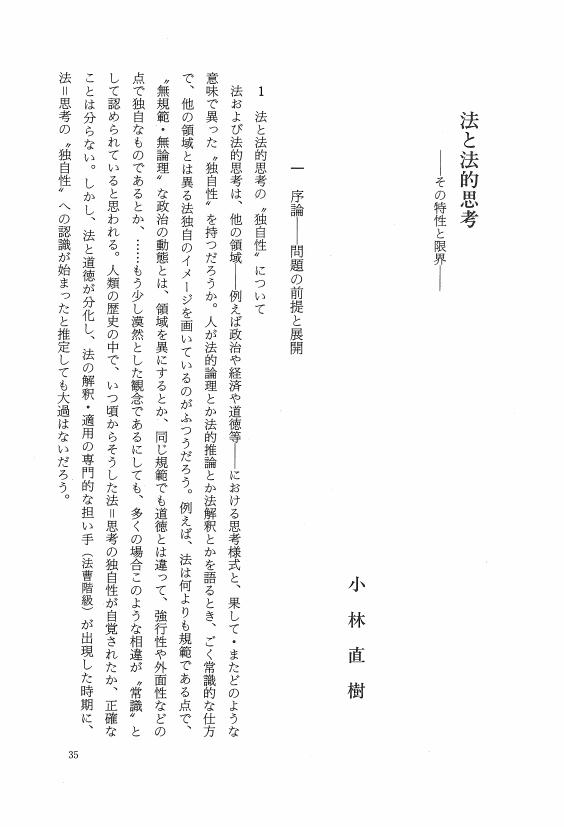1 0 0 0 OA 科学的説明と実在論
- 著者
- 小林 道夫
- 出版者
- 日本科学哲学会
- 雑誌
- 科学哲学 (ISSN:02893428)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, pp.39-51, 1993-11-20 (Released:2009-05-29)
- 参考文献数
- 18
1 0 0 0 OA 消化器外科手術における手術時手袋穿孔に関する検討 開腹手術と鏡視下手術の比較
- 著者
- 小林 美奈子 辻本 広紀 髙畑 りさ 矢口 義久 永生 高広 岡本 耕一 長谷 和生
- 出版者
- 一般社団法人 日本外科感染症学会
- 雑誌
- 日本外科感染症学会雑誌 (ISSN:13495755)
- 巻号頁・発行日
- vol.16, no.4, pp.197-202, 2019-08-31 (Released:2019-09-30)
- 参考文献数
- 16
手術時手袋の着用は,患者と医療従事者間の病原微生物の伝播経路遮断が目的である。これまでに術中に手袋損傷が起こることは諸家により報告されているが,これらの多くは開腹手術での手袋損傷である。近年,消化器外科領域において内視鏡外科手術が普及しているが,鏡視下手術での手袋損傷の検討はほとんど行われていない。そこで今回われわれは,消化器外科領域において開腹・鏡視下手術時の手袋穿孔率を比較検討した。手術時手袋1,513双,3,026枚の検討を行い,穿孔率は全体で10.9%,開腹手術11.3%,鏡視下手術10.4%であり,穿孔率に差は認められなかった(P=0.4611)。また,二重手袋着用での穿孔率は,インナー手袋5.7%,アウター手袋11.9%であり,インナーはアウターに比し有意に穿孔率が低率であった(P=0.0001)。消化器外科手術における手袋穿孔率は,鏡視下手術においても開腹手術とほぼ同率であり,血液・体液暴露予防やSSI予防の観点から鏡視下手術においても二重手袋の着用が重要であると考えられた。
1 0 0 0 OA 楽譜の論理文法
- 著者
- 小林 光則
- 出版者
- 日本科学哲学会
- 雑誌
- 科学哲学 (ISSN:02893428)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, pp.115-131, 1988-11-05 (Released:2009-05-29)
- 参考文献数
- 3
1 0 0 0 OA コンピュータ,意識,言語
- 著者
- 小林 道夫
- 出版者
- 日本科学哲学会
- 雑誌
- 科学哲学 (ISSN:02893428)
- 巻号頁・発行日
- vol.20, pp.31-46, 1987-11-05 (Released:2009-05-29)
- 参考文献数
- 20
1 0 0 0 OA 規範概念を含む真理様相論理について
- 著者
- 小林 光則
- 出版者
- 日本科学哲学会
- 雑誌
- 科学哲学 (ISSN:02893428)
- 巻号頁・発行日
- vol.18, pp.103-119, 1985-11-15 (Released:2009-05-29)
- 参考文献数
- 8
1 0 0 0 OA 若干の連立様相論理とその完全性
- 著者
- 小林 光則
- 出版者
- 日本科学哲学会
- 雑誌
- 科学哲学 (ISSN:02893428)
- 巻号頁・発行日
- vol.16, pp.115-132, 1983-11-26 (Released:2009-05-29)
- 参考文献数
- 14
1 0 0 0 OA ルイス系様相論理学の公理化について
- 著者
- 小林 光則
- 出版者
- 日本科学哲学会
- 雑誌
- 科学哲学 (ISSN:02893428)
- 巻号頁・発行日
- vol.11, pp.71-93, 1978-10-20 (Released:2009-05-29)
- 参考文献数
- 9
1 0 0 0 IR 定期傭船契約法の進展と課題
- 著者
- 小林 登
- 出版者
- 上智大學法學會
- 雑誌
- 上智法學論集 (ISSN:04477588)
- 巻号頁・発行日
- vol.64, no.1, pp.75-98, 2020-11-20
論説
1 0 0 0 OA 食品ロスの測定を通じた食料需給システムの効率性と環境負荷に関する国際比較
1 0 0 0 IR 視覚文化のグローバル化: 映画ポスターの日英比較を受けて
- 著者
- 林 佐和子
- 出版者
- 金沢大学人間社会学域経済学類社会言語学演習
- 雑誌
- 論文集:金沢大学人間社会学域経済学類社会言語学演習 (ISSN:21886350)
- 巻号頁・発行日
- no.12, pp.1-31, 2017-03-22
近年のグロ ーバル化の進行は著しく、 私たちの日常には異文化が溢れている。 言語文化・文字文化においても顕著であり、 この影響を受けて様々な伝統的文 化は変化している。 その例として、 文字文化の影響による「自然な目の動き」が存在し、 それは日本語話者と英語話者とで異なるという(熊倉, 1990)。 この目の動きの文化、 視覚文化も文明開化により統一性が失われてきていると熊倉は論じている。 本研究では、 この視覚文化に着目し、 グロ ーバル化以前と現代とでは日本語話者の視覚文化と英語話者の視覚文化には実際に変化が起きているのかをデータを用いて考察し、 どのように変化したか、 それを形作った言語 文化にはどのような変化が起きているかを明らかにする。 また、 日英のデータの比較により変化の原因は何であるかを考察した。 調査の対象として、 言語圏によって変更されることが多く各言語話者の好みを反映している視覚表現である「映画ポスター」を用いた。
1 0 0 0 OA 構造的差りと法 フェミニズムの主体像と法実践を手がかりに
- 著者
- 若林 翼
- 出版者
- 日本法哲学会
- 雑誌
- 法哲学年報 (ISSN:03872890)
- 巻号頁・発行日
- vol.2004, pp.146-153,200, 2005-09-30 (Released:2008-11-17)
- 参考文献数
- 21
The purpose of this article is to put forward the argument that the role of the law and its relevant subjects should be to dismantle the structural discrimination in the society. The theories and practices of three feminisms liberal feminism, radical feminism and postmodern feminism are compared and discussed. The liberal feminism's argument is that the female is an autonomous “chooser” and the aim of laws against gender discrimination is to basically remove obstacles for women to allow them to choose and decide by themselves. On the other hand, radical feminism believes that the role of women has been constructed and is deeply embedded in the society, especially by men, therefore their desires are also constructed. To change the structural gender discrimination which women are also part of, it is essential that women be made aware of problems through “consciousnessraising, ” and that through this feminist law should embody women's point of view and redistribute resources and privileges. Postmodern feminism, however, denies the existence of the subject and rejects the use of law to subvert the gender system. The subject is not out there, it is rather the “effect” of the coherent but coercive institution of biological sex, gender, sexual practice and desire. According to Postmodern feminism, liberal feminist law keeps the cultural norms and radical feminist law excludes women who are not typical sacrificed “women.” Considering the postmodern feminism's insight, the subject could be understood as a process to become a unique person, and that the task of law is to give adequate room to each person where she could imagine the future herself and try to be that figure. In this way, the law would subsequently lead to the erosion of the fixed binary gender system.
1 0 0 0 OA 「公私」観念の比較法史学的考察—コメント—
- 著者
- 水林 彪
- 出版者
- 日本法哲学会
- 雑誌
- 法哲学年報 (ISSN:03872890)
- 巻号頁・発行日
- vol.2000, pp.98-116, 2001-10-30 (Released:2008-11-17)
- 参考文献数
- 24
1 0 0 0 OA 「都市」と社会政策—一九世紀イギリスにおけるJ・S・ミル—
- 著者
- 村林 聖子
- 出版者
- 日本法哲学会
- 雑誌
- 法哲学年報 (ISSN:03872890)
- 巻号頁・発行日
- vol.1999, pp.7-21, 2000-10-30 (Released:2008-11-17)
- 参考文献数
- 39
1 0 0 0 OA 法の自立性について 意味論の観点から
- 著者
- 小林 公
- 出版者
- 日本法哲学会
- 雑誌
- 法哲学年報 (ISSN:03872890)
- 巻号頁・発行日
- vol.1997, pp.19-33, 1998-10-30 (Released:2009-02-12)
- 参考文献数
- 7
1 0 0 0 OA 不合理な選択としての死刑-「神々の戦い」の前に
- 著者
- 小林 和之
- 出版者
- 日本法哲学会
- 雑誌
- 法哲学年報 (ISSN:03872890)
- 巻号頁・発行日
- vol.1994, pp.171-178, 1995-10-30 (Released:2008-11-17)
- 参考文献数
- 25
1 0 0 0 OA 市場と民主主義に関する覚え書
- 著者
- 小林 公
- 出版者
- 日本法哲学会
- 雑誌
- 法哲学年報 (ISSN:03872890)
- 巻号頁・発行日
- vol.1994, pp.71-87, 1995-10-30 (Released:2008-11-17)
- 参考文献数
- 14
1 0 0 0 OA 実践的推論と『法と経済学』 法解釈と経済学の役割
- 著者
- 林田 清明
- 出版者
- 日本法哲学会
- 雑誌
- 法哲学年報 (ISSN:03872890)
- 巻号頁・発行日
- vol.1992, pp.44-59, 1993-10-30 (Released:2008-11-17)
- 参考文献数
- 15
1 0 0 0 OA 現代日本の所有問題とその歴史的文脈
- 著者
- 水林 彪
- 出版者
- 日本法哲学会
- 雑誌
- 法哲学年報 (ISSN:03872890)
- 巻号頁・発行日
- vol.1991, pp.40-57, 1992-10-30 (Released:2008-11-17)
- 参考文献数
- 22
1 0 0 0 OA 法と法的思考 その特性と限界
- 著者
- 小林 直樹
- 出版者
- 日本法哲学会
- 雑誌
- 法哲学年報 (ISSN:03872890)
- 巻号頁・発行日
- vol.1990, pp.35-54, 1991-10-30 (Released:2008-11-17)
- 参考文献数
- 2
1 0 0 0 OA 私的利益と規範の生成
- 著者
- 小林 公
- 出版者
- 日本法哲学会
- 雑誌
- 法哲学年報 (ISSN:03872890)
- 巻号頁・発行日
- vol.1987, pp.20-43, 1988-10-25 (Released:2008-11-17)
- 参考文献数
- 23