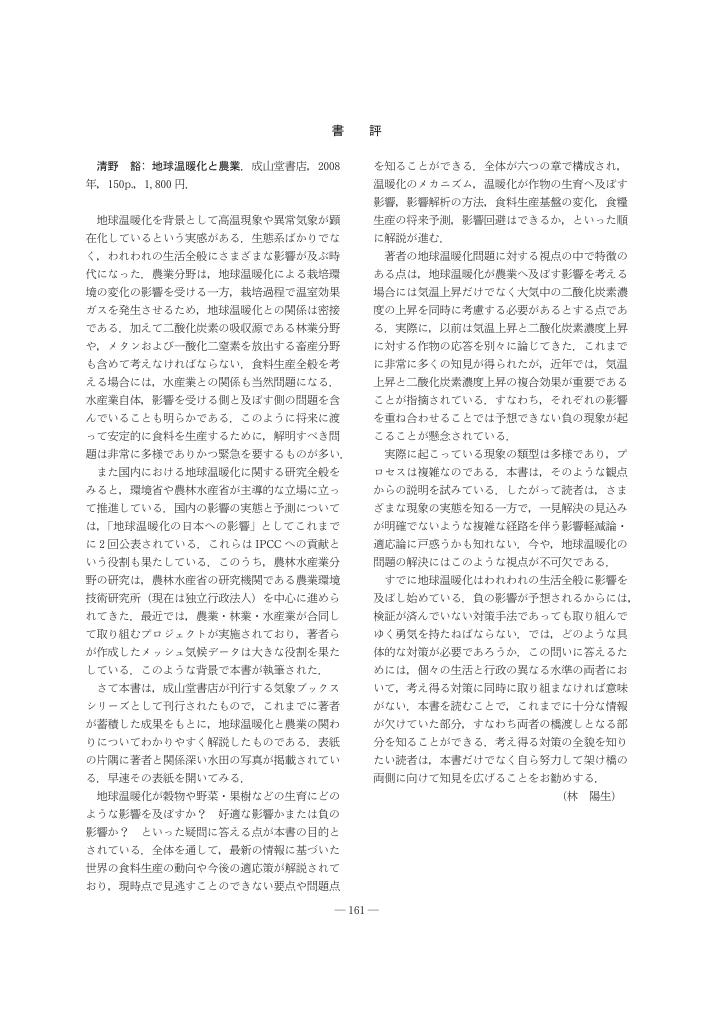1 0 0 0 OA 功利主義と効率性—不法行為法の観点から—
- 著者
- 小林 秀文
- 出版者
- 日本法哲学会
- 雑誌
- 法哲学年報 (ISSN:03872890)
- 巻号頁・発行日
- vol.1987, pp.44-60, 1988-10-25 (Released:2008-11-17)
- 参考文献数
- 13
1 0 0 0 OA 続 情報化社会における法と言語—法的効力の根拠としての組織規範論を焦点として—
- 著者
- 古林 祐二
- 出版者
- 日本法哲学会
- 雑誌
- 法哲学年報 (ISSN:03872890)
- 巻号頁・発行日
- vol.1980, pp.26-49, 1981-10-30 (Released:2008-11-17)
- 参考文献数
- 19
1 0 0 0 OA 法哲学と憲法
- 著者
- 小林 直樹
- 出版者
- 日本法哲学会
- 雑誌
- 法哲学年報 (ISSN:03872890)
- 巻号頁・発行日
- vol.1976, pp.12-26, 1977-10-30 (Released:2008-11-17)
1 0 0 0 OA 法と道徳の構造論的考察
- 著者
- 小林 直樹
- 出版者
- 日本法哲学会
- 雑誌
- 法哲学年報 (ISSN:03872890)
- 巻号頁・発行日
- vol.1957, pp.55-138, 1958-03-30 (Released:2009-02-12)
- 参考文献数
- 139
- 著者
- 林崎 涼 白井 正明
- 出版者
- 公益社団法人 日本地理学会
- 雑誌
- 地理学評論 Series A (ISSN:18834388)
- 巻号頁・発行日
- vol.88, no.4, pp.327-340, 2015-07-01 (Released:2019-10-05)
- 参考文献数
- 50
- 被引用文献数
- 2 3
石英や長石などの鉱物粒子は,光を浴びることで自身も発光する光ルミネッセンス(OSL)という性質をもつ.OSLの発光強度は放射線の被曝量に比例して増加し,露光により急減する.本研究では,アルカリ長石粒子の露光状態の違いに起因する残存OSL強度と,残存OSL強度がほぼ0,すなわち最近露光した粒子の含有率を示す露光率の変化傾向から,信濃川大河津分水路河口周辺の海岸における砂質粒子の運搬過程を推定した.その結果,分水路河口付近の野積海岸から北東に約17kmの角田浜まで,残存OSL強度の減少および露光率の増加が見られることから,この区間で北東方向へ砂質粒子が運搬されていることが推定された.一方で,野積海岸周辺では単純な変化傾向は見られず,近年の海岸侵食による残存OSL強度の大きい粒子の混入が示唆された.ごく最近の砂質粒子の運搬過程を推定する手法として,残存OSL強度と露光率は有効であり,より正確な運搬過程を把握できる可能性がある.
- 著者
- 林 上
- 出版者
- 公益社団法人 日本地理学会
- 雑誌
- 地理学評論 Series A (ISSN:18834388)
- 巻号頁・発行日
- vol.88, no.4, pp.403-405, 2015-07-01 (Released:2019-10-05)
1 0 0 0 OA 土地被覆データにもとづく疾病媒介蚊の生息分布域の分析——琵琶湖東沿岸地域を対象に——
- 著者
- 米島 万有子 中谷 友樹 渡辺 護 二瓶 直子 津田 良夫 小林 睦生
- 出版者
- 公益社団法人 日本地理学会
- 雑誌
- 地理学評論 Series A (ISSN:18834388)
- 巻号頁・発行日
- vol.88, no.2, pp.138-158, 2015-03-01 (Released:2019-10-05)
- 参考文献数
- 60
本研究では,琵琶湖東沿岸地域を対象に,国内の代表的な2種類の疾病媒介蚊(成虫)の捕集調査を実施した.そこで観測された捕集個体数の空間的変動を,偏相関最小二乗法(PLS)回帰分析に基づき調査定点周辺の土地被覆の構成(種目別面積比)と関連づけて検討した.また,得られたPLS回帰モデルを利用して,当該媒介蚊の生息分布を面的に推定した.その結果,コガタアカイエカの捕集個体数は,主に水田によって土地被覆が構成されるような農村景観の卓越する地域で多く,平野部に好適な生息場所が多く認められた.シナハマダラカ群の捕集個体数は,水域とそれに付随するヨシなどの植生から構成されるような湿地景観の卓越する地域で多く,水域周辺に好適な生息場所が存在することが判明した.こうした媒介蚊の捕集データから推定した生息分布域は,媒介蚊による吸血被害を生むリスクの分布を示すものであり,蚊媒介性感染症の流行対策に有用な地理情報と考えられる.
1 0 0 0 OA 清野 豁:地球温暖化と農業
- 著者
- 林 陽生
- 出版者
- 公益社団法人 日本地理学会
- 雑誌
- 地理学評論 Series A (ISSN:18834388)
- 巻号頁・発行日
- vol.82, no.2, pp.161a, 2009-03-01 (Released:2011-05-31)
1 0 0 0 OA 家庭内暴力(DV)と犯罪立法
- 著者
- 林 美月子
- 出版者
- 日本刑法学会
- 雑誌
- 刑法雑誌 (ISSN:00220191)
- 巻号頁・発行日
- vol.50, no.3, pp.417-427, 2011-03-10 (Released:2020-11-05)
1 0 0 0 OA 2 責任主義と責任能力
- 著者
- 林 美月子
- 出版者
- 日本刑法学会
- 雑誌
- 刑法雑誌 (ISSN:00220191)
- 巻号頁・発行日
- vol.47, no.2, pp.294-298, 2008-02-10 (Released:2020-11-05)
1 0 0 0 OA 受刑者処遇法の概要と実務に対する影響
- 著者
- 林 眞琴
- 出版者
- 日本刑法学会
- 雑誌
- 刑法雑誌 (ISSN:00220191)
- 巻号頁・発行日
- vol.46, no.3, pp.367-377, 2007-04-01 (Released:2020-11-05)
1 0 0 0 OA 高度情報化社会における地域システムの変容
- 著者
- 寺阪 昭信 若林 芳樹 中林 一樹 阿部 和俊
- 出版者
- The Association of Japanese Geographers
- 雑誌
- Geographical review of Japan, Series B (ISSN:02896001)
- 巻号頁・発行日
- vol.61, no.1, pp.159-173, 1988-05-31 (Released:2008-12-25)
- 参考文献数
- 19
- 被引用文献数
- 2 3
本論文は,情報の伝達が空間に果たしている役割を,高度情報化社会といわれている現在の日本の状況のなかで捕らえてみることにある。コンピュータ技術の発展と通信のデジタル化による新しいネットワークの形成は, 1982年の第2次通信の自由化により,ニューメディアの進展となって現れた。地域的なネットワークの例として, NTTによるINSモデルの実験は東京武蔵野・三鷹地区で1984年から行われたが,これを実用化するまでには解決すべき多くの問題があることが明らかとなった。 CATVは初期の難視聴対策から出発して,ニューメディアとして普及するにまでに至った。可視チャンネル数の増加に加えて自主放送を行うことにより,地方都市では地域活動の活性化と自治体と住民をつなぐ役割を果たし,農村地区では地域の振興に,ニュータウンや大都市域では住民への情報の供給やコミュニティーの形成に役立つ可能性を開いている。 情報化の進展にともない,企業の分散が予測されたが,東京区部,とくに都心3区への中枢管理機能はかえって集中する傾向が見られる。これはマネージメントのための情報を求める企業の立地行動によるものである。さらに,最近では東京は世界的な規模での金融市場としての重要度を高めてきたことから,外資系企業のオフィスの立地が盛んになってきている。その需要にたいしてオフィス用ビルの建設が進んでいるが,不足ぎみなので値上がりが著しい。こうして都心のビジネス地区は拡大している。 このような動向から,日本における情報の地域格差は拡大している。東京を中心とする首都圏への情報の集中は著しく,大阪を初めとする他の大都市や地方都市の比重は相対的に低下している。民間における情報化の進展や情報サービス業の発展のほかにも,郵政省のテレトピア計画や通産省のニューメディアコミュニティー構想など,政府は情報化の進展をはかっている。これらが実現すると地域社会や住民の生活を大きく変える可能性がある。このような社会の変化に対して,我が国の地理学からの研究は立ち遅れている。
1 0 0 0 OA 1978-87年における日本歴史地理学の研究動向
- 著者
- 小林 健太郎 金田 章裕
- 出版者
- The Association of Japanese Geographers
- 雑誌
- Geographical review of Japan, Series B (ISSN:02896001)
- 巻号頁・発行日
- vol.61, no.1, pp.78-98, 1988-05-31 (Released:2008-12-25)
- 参考文献数
- 143
- 被引用文献数
- 1 1
比較的実りの多かったこの10年間の日本歴史地理学の成果のうち,以下の6つのテーマについて,その動向を紹介した。 作物栽培の起源は縄文早期に,水田稲作は縄文晩期に湖るようであり,水田分布は弥生中期に本州北端にまで達し,弥生・古墳期の水田のほとんどが極めて小区画であるという従来とは大きく異なった考古学的知見が得られた。 2) 古代都市の復原研究が進み,中国と日本の都城の比較研究も行なわれて,類似点と相違点についての知見が加わった。日本における都市計画の起源にかかわる議論も行なわれた。交通路の研究も活発であり,律令期における整然とした直線状の道路計画の展開の実状が知られるに至った。これらの都市や主要施設の立地・配置とその計画における同時代の人々の空間認識についての議論も始められた。 3) 条里地割と条里呼称法とからなる条里プランが,従来の通説とは異なって, 8世紀の中頃に完成したものであることが判明し,それが古代・中世において果した役割や,広範囲に分布する条里地割をめぐる議論・分析が進んだ。古代・中世の条里地割内部やそれ以外の部分の土地利用についての研究も主要な研究テーマの一つとなった。村落の領域や形態についても研究が進展し,広範な集村化現象や散村の展開の事実も知られるに至った。 4) 中世の市場集落の分布や景観についての研究が進展したが,商品流通からみると当時は市場の有機的な階層構造が成立していなかったとの主張も行なわれた。日本歴史地理学の主要なテーマである城下町研究も進展し,特に,先駆的な戦国城下町や城下町の構造をめぐる議論が展開した。 5) 近世の藩政村と村落共同体との関係や,村落の構造に関する研究が蓄積され,労働・結婚をめぐる人口移動についての研究も発表された。従来からの新田開発研究に加え,近世農書を資料とする分析も加わった。 6) 中・近世の日本では,様々な絵図が数多く作成されたが,これらの絵図の従来からの分析に加え,これらを用いて当時の空間認識にせまろうとする研究が始められた。又,中世の説話から生活空間の深層構造にせまろうという研究も展開した。
1 0 0 0 OA 日本の流通システムの空間的パターンと近年におけるその変化
- 著者
- 林 上 日野 正輝
- 出版者
- The Association of Japanese Geographers
- 雑誌
- Geographical review of Japan, Series B (ISSN:02896001)
- 巻号頁・発行日
- vol.61, no.1, pp.120-140, 1988-05-31 (Released:2008-12-25)
- 参考文献数
- 83
- 被引用文献数
- 4 5
日本における卸売業システムの空間的パターンは,これまでずっと東京と大阪を中核都市とする二極構造によって特徴づけられてきた。しかしながら1960年代以降は,産業構造の変化と大企業本社の集中に対応しながら,卸売業取引は東京に集中するようになった。その結果,卸売業の空間的システムは単一システム構造へと変化していった。同時に,札幌,仙台,広島,福岡などの広域中心地が,それらの地域における重要な卸売業中心地になった。 戦後の経済成長にともなって輸送貨物量は驚くほど増大し,輸送手段にも格段の発達がみられた。トラック輸送の発展にともない,倉庫や食料品卸売市場などの施設のなかには都市中心部から大都市の郊外に移動するものが現われた。主要な都市の郊外に建設されたトラック・ターミナルや卸売商業団地は,卸売業施設の都心部から周辺部への移転を促進する役割を果たした。 日本の小売業システムにおける最も顕著な変化は, 1960年代の初頭以降に,スーパーマーケットやスーパーストアが全国的規模や地域的規模で急速に発展したことである。こうした店舗は,都市の階層システムを通して普及していったセルフ・サービス・システムと多店舗システムによって特徴づけられる。小売業は郊外地域で発展したため,大都市の内部では商業地域に関して対照的なパターン(郊外対都心)が生ずるようになった。 モータリゼーションは,都市階層のあらゆる段階で購買地域の構造に再編成をもたらしたもう一つの要素である。新たに発展した商業地域が自動車でやって来る消費者を吸引する一方で,既存の小規模な商業地域は厳しい競争を強いられるようになった。以前は中心地システムに対応していた購買中心地の空間的パターンは,こうした影響の下でその階層的特徴を徐々に失っていった。
1 0 0 0 OA 分家現象より觀たる北上平野北部の聚落發展型態
- 著者
- 小林 重幸
- 出版者
- 公益社団法人 日本地理学会
- 雑誌
- 地理 (ISSN:21851697)
- 巻号頁・発行日
- vol.1, no.3, pp.408-425, 1938 (Released:2010-03-19)
- 参考文献数
- 28
1 0 0 0 OA ヒュームにおける社交・会話と人間性の増幅 ―自然的徳論に関する一考察―
- 著者
- 林 誓雄
- 出版者
- 日本イギリス哲学会
- 雑誌
- イギリス哲学研究 (ISSN:03877450)
- 巻号頁・発行日
- vol.33, pp.35-50, 2010-03-20 (Released:2018-03-30)
On Humeʼs account, the scope of the natural virtues(generosity or humanity) is limited to a personʼs family and friends(“narrow circle”). Elsewhere, however, Hume admits that the scope of the natural virtues extends beyond the “narrow circle” to strangers. How, then, does the scope of the natural virtues extend beyond the “narrow circle”? In this paper, I will inquire what expands the scope of the natural virtues, and argue that the scope of the natural virtues is expanded because not only of the principle of sympathy, but also of the “society” and “conversation” in which the humanity of a person is increased and cultivated.
1 0 0 0 OA ヒューム哲学における神の信念 ―デザイン論証批判と、人間本性からの信仰論―
- 著者
- 小林 優子
- 出版者
- 日本イギリス哲学会
- 雑誌
- イギリス哲学研究 (ISSN:03877450)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, pp.69-85, 2006-03-20 (Released:2018-03-30)
- 参考文献数
- 18
David Hume is renowned for his objection to the design argument. However, in his book Dialogues Concerning Natural Religion, Philo appears to believe in God although he is against the design argument. Why does Hume allow Philo to have faith? To answer this question, I think we should not resort to the concept of natural beliefs because in Hume's other writings he explains that people can believe in God by virtue of some principles of human nature. In this paper, I answer this question by elucidating that Hume considered that a belief in God can be explained by passion, imagination, customs and education.
1 0 0 0 OA 近世スコットランド史の研究動向 ─16・17世紀の思想史を中心に─
- 著者
- 小林 麻衣子
- 出版者
- 日本イギリス哲学会
- 雑誌
- イギリス哲学研究 (ISSN:03877450)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, pp.119-125, 2006-03-20 (Released:2018-03-30)
1 0 0 0 OA ジェイムズ6世の政治思想 ―思想的コンテクストと特徴―
- 著者
- 小林 麻衣子
- 出版者
- 日本イギリス哲学会
- 雑誌
- イギリス哲学研究 (ISSN:03877450)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, pp.23-38, 2002-03-20 (Released:2018-04-25)
The political thought of James VI has always been associated witn the divine right of kingship. However, the theory of divine kingship is merely one feature of his thought. James primarily developed his ideas under the influence of political realism that he encounterea in his youth. He then incorporated various elements of religious reformers' views and Renaissance humanism into his thought for the purpose of constructing strong kingship, which could not be threatened by any other entity. In this paper, I examine the historical context that influenced the development of James' thought and the characteristics of his thought—the obedience theory, Renaissance humanism, and political realism.
1 0 0 0 OA F・ベイコン思想に於ける善について
- 著者
- 若林 明
- 出版者
- 日本イギリス哲学会
- 雑誌
- イギリス哲学研究 (ISSN:03877450)
- 巻号頁・発行日
- vol.1, pp.35-44, 1978-04-01 (Released:2018-06-25)