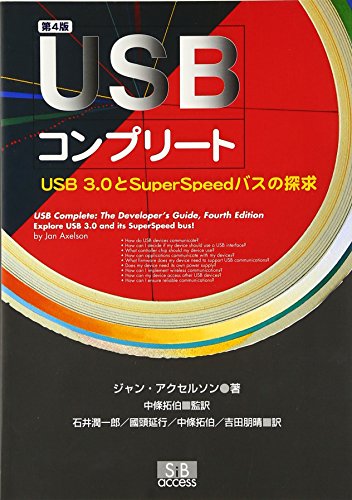- 著者
- 村中 孝司 石井 潤 宮脇 成生 鷲谷 いづみ
- 出版者
- 日本生態学会
- 雑誌
- 保全生態学研究 = Japanese journal of conservation ecology (ISSN:13424327)
- 巻号頁・発行日
- vol.10, no.1, pp.19-33, 2005-06-30
- 参考文献数
- 88
- 被引用文献数
- 21
外来生物の侵入は生物多様性を脅かす主要な要因の1つとして認識されている.日本においても, 2004年に「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」が公布され, 生態系等に係わる被害を及ぼすあるいは及ぼす可能性がある外来生物を特定外来生物として指定し, 防除などの措置を講ずることが定められている.本研究では, 同法にもとづいて指定すべき特定外来生物の検討に先立ち, 同法基本方針における「特定外来生物の選定に関する基本的事項」を維管束植物に適用して, 生物多様性を脅かす特定外来植物の候補種を選定した.これまで得られた生態学, 保全生態学およびその他の科学的知見を整理し, (1)国内外における侵略性の高さ, (2)国内における侵入面積, (3)生態系・在来種に及ぼす影響, および(4)対策事例の有無の4項目に関して, できる限り数量的に評価することにより, 108種を対策の必要性の緊急度からA-Cの3ランクに分けてリストアップした.対策緊急度の最も高いAランクには, オオブタクサAmbrosia trifida, シナダレスズメガヤEragrostis curvula, ハリエンジュRobinia pseudoacacia, アレチウリSicyos angulatus, セイタカアワダチソウSolidago altissima, オオカナダモEgeria densa, オニウシノケグサFestuca arundinacea, オオフサモMyriophyllum aquatica, コカナダモElodea nuttallii, ホテイアオイEichhornia crassipes, カモガヤDactylis glomerata, アカギBischofia javanica, 外来タンポポ種群Taraxacum spp., オオカワヂシャVeronica anagallis-aquatica, ヒメジョオンStenactis annuus, ボタンウキクサPistia stratiotesの計16種が選定された.いずれの種も生態系・在来種に及ぼす影響が顕著であり, すでに行政や地域住民が主体となり駆除対策が実施されているものである.また, オオカワヂシャを除いた15種は日本生態学会(2002)がリストアップした「日本の侵略的外来種ワースト100」に選定されており, 国内の河川における優占群落面積が大きい種が多く含まれる.それに次ぐBランクには, ハルザキヤマガラシBarbarea vulgaris, イタチハギAmorpha fruticosa, ミズヒマワリGymnocoronis spilanthoides, キショウブIris pseudacorusなど計35種が, Cランクには計57種が選定された.ここに掲載された種の中には, 現在もなお緑化用牧草, 観賞用水草などとして盛んに利用されている種が含まれている.特にAランクに選定された種については速やかに特定外来生物に指定し, 侵入・蔓延を防止するための有効な対策を強化することが必要である.
2 0 0 0 OA 超音波テレメトリーを用いた,汽水湖におけるニホンウナギの生息場所利用の把握
- 著者
- 海部 健三 竹野 遼馬 三田村 啓理 高木 淳一 市川 光太郎 脇谷 量子郎 板倉 光 石井 潤 荒井 修亮
- 出版者
- 応用生態工学会
- 雑誌
- 応用生態工学 (ISSN:13443755)
- 巻号頁・発行日
- vol.22, no.1, pp.73-82, 2019-07-28 (Released:2019-09-10)
- 参考文献数
- 28
- 被引用文献数
- 1
ニホンウナギは重要な水産資源だが,現在個体群は減少し,環境省および IUCN によって絶滅危惧種に区分されている.個体群を回復させるための対策が求められているが,その生育城である河川や沿岸域の環境をどのように回復すべきか,知見は限られている.本研究では成育場である河川や湖沼,沿岸域の環境の回復策に資することを目指し,福井県久々子湖において,超音波テレメトリー手法を利用して,ニホンウナギ 10 個体の行動を追跡した.超音波発信機を挿入した個体を放流した後,全ての個体が測位可能範囲内で測位された.明け方(4:00-6:00)および昼(6:00-18:00)に測位された個体は少なかったが,夕方(18:00-20:00)および夜(20:00-翌4:00)にはほぼ全ての個体が測位された.位置が確認された時間の長さは個体ごとに大きく異なり,最も短い個体で 0.3 時間,最も長い個体で 102.3 時間,平均は 16.5 時間であった.調査期間全体の湖岸エリア(水際から 50 m 以内)と沖エリア(水際から 50 m 以遠)の滞在時間比と面積比を個体ごとに比較した結果,6 個体で有意差が検出された.このうち 4 個体は湖岸エリアの滞在時間比が大きく,2 個体は沖エリアの滞在時間比が大きかった.湖岸エリアに滞在しなかった 1 個体を除き, 9 個体について湖岸を石積み護岸エリア,ヨシ帯エリア,コンクリート護岸エリアに分けて,各エリアの滞在時間 比と面積比を比較したところ,全ての個体で有意差が検出された.このうち 7 個体では石積み護岸エリアの滞在時間が最も長く,ヨシ帯エリアの滞在時間が最も長い個体と,コンクリート護岸エリアの滞在時間が最も長い個体が,それぞれ 1 個体ずつ見られた.湖岸を利用する個体については石積み護岸を選択する傾向が見られたが,沖および湖岸の利用は個体ごとにばらつきがあり,一定の傾向は確認されなかった.
- 著者
- 石井 潤 和田 翔子 吉岡 明良 大谷 雅人 リンゼイ リチャード 塩沢 昌 高橋 興世 鷲谷 いづみ
- 出版者
- 一般社団法人 日本生態学会
- 雑誌
- 保全生態学研究 (ISSN:13424327)
- 巻号頁・発行日
- vol.22, no.2, pp.361-370, 2017
北海道の黒松内低地帯において、ミズゴケ属植物が生育し植物の種多様性が高い湿原(来馬湿原:面積約0.9 ha)の存在が新たに確認された。地元住民を対象とした聞き取り調査および1948-2005年の空中写真の判読を行ったところ、この湿原は、1976年頃に宅地造成に伴う土地改変により部分的に土壌剥離または未舗装道路の建設がなされ、その後植生が発達して今に至ることが判明した。植生の現況を把握するためのフロラ調査では、ミズゴケ属植物としてウロコミズゴケ1種、維管束植物の在来種103種(絶滅危惧種イトモ、エゾサワスゲ、ホロムイリンドウ、ムラサキミミカキグサを含む)、外来種8種が確認された。ウロコミズゴケの分布調査の結果では、その分布は1976年の土地改変と有意な関係があり、ウロコミズゴケパッチ面積の合計は期待値と比較して、土壌剥離に伴い裸地化された場所で大きく未舗装道路だった場所で小さい傾向があった。これらの結果は、1976年の土壌剥離による裸地化が、現在のウロコミズゴケパッチを含む植生の形成に寄与している可能性を示唆している。ウロコミズゴケパッチ内外を対象とした植生調査では、オオバザサがウロコミズゴケの被度50%以上の方形区に、期待値と比べて多く出現する傾向があり、ウロコミズゴケパッチの形成とオオバザサの生育が関係している可能性が考えられる。
1 0 0 0 OA マルハナバチ一斉調査(第五報)
- 著者
- 保全生態学研究会 青木 俊明 荒木 佐智子 石井 潤 石濱 史子 板垣 智之 内山 武 大谷 雅人 掃部 康宏 川上 美穂子 菊地 智久 北本 尚子 清田 治樹 国武 陽子 柴田 賢一 柴山 弓季 正傳 大悟 陣田 浩次 高川 晋一 田中 肇 辻沢 央 中村 裕 長谷川 淳一 本城 正憲 牧野 崇司 松村 千鶴 松本 雅道 光井 淳之 三宅 康子 山崎 男土 山崎 義夫 柚木 秀雄 横山 潤 吉成 布美香 鷲谷 いづみ
- 出版者
- 一般社団法人 日本生態学会
- 雑誌
- 保全生態学研究 (ISSN:13424327)
- 巻号頁・発行日
- vol.7, no.1, pp.19-23, 2002-09-30 (Released:2018-02-09)
- 参考文献数
- 4
- 被引用文献数
- 2
- 著者
- ジャン・アクセルソン著 石井潤一郎 [ほか] 訳
- 出版者
- 星雲社 (発売)
- 巻号頁・発行日
- 2011