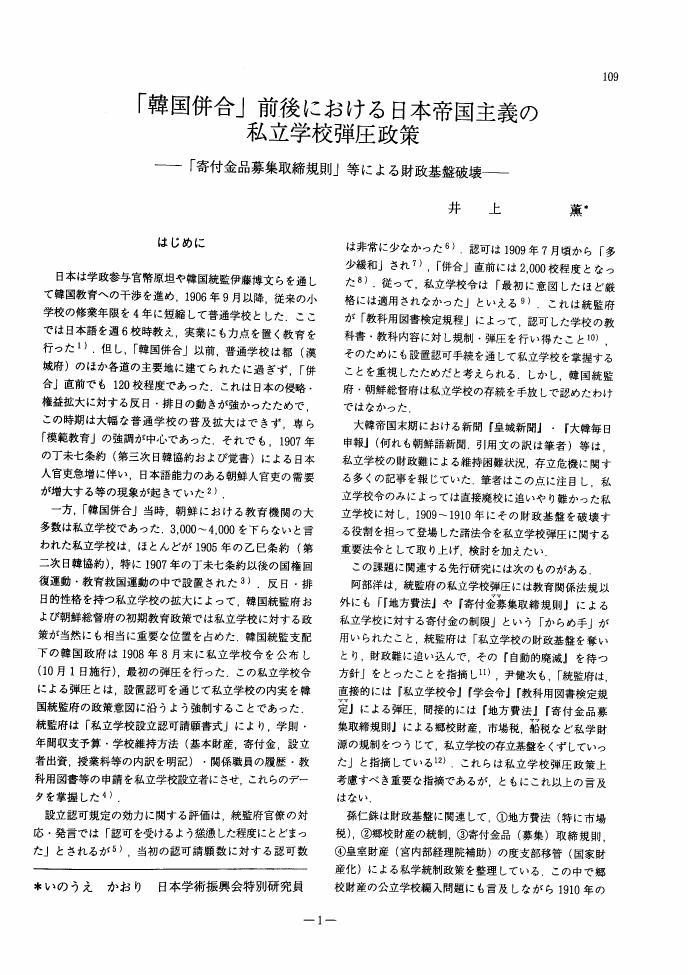- 著者
- 松田 武雄
- 出版者
- 一般社団法人日本教育学会
- 雑誌
- 教育学研究 (ISSN:03873161)
- 巻号頁・発行日
- vol.74, no.4, pp.518-529[含 英語文要旨], 2007-12
本稿は、国家的価値の浸出を抑制、制御することを睨みながら、社会教育概念の再解釈を通して社会教育におけるコミュニティ的価値の再検討を行うことを目的としている。最初に、近年注目されている社会関係資本論と社会教育を関連づけ、社会教育におけるコミュニティ的価値を再検討することの現代的意義について考察している。次に、社会関係資本と関連づけて社会教育概念の歴史的な再解釈を行うとともに、社会教育におけるコミュニティ的価値をめぐる議論を歴史的に跡づけ、問題の所在を明らかにしている。最後に、国家的価値に抗する社会教育におけるコミュニティ的価値について、社会教育概念の歴史的再解釈を踏まえて考察している。この際に、コミュニティの「共通善」や個人の善をめぐる英語圏の政治哲学の議論を、社会教育におけるコミュニティ的価値を考察するための概念装置として援用し、コミュニティ的価値の創出(相互学習)をめぐる理論的な枠組みについて検討した。
- 著者
- 広川 由子
- 出版者
- 一般社団法人日本教育学会
- 雑誌
- 教育学研究 (ISSN:03873161)
- 巻号頁・発行日
- vol.81, no.3, pp.297-309, 2014
本稿は、占領期日本における英語教育構想を新制中学校の外国語科の成立過程に焦点を当てながら明らかにすることを目的とする。占領初期の米国国務省案は、民主的な教育制度の確立要件として英語教育とその大衆化を掲げた。これがSFEの勧告となり、それをCIが具体化したことによって新制中学校に外国語科が導入された。一方、文部省は導入に消極的な姿勢を示しており、導入を決定づけた英語教育構想は、米国政府から提出されたものだったと指摘できる。
- 著者
- 川島 清吉
- 出版者
- 日本教育学会
- 雑誌
- 教育学研究 (ISSN:03873161)
- 巻号頁・発行日
- vol.38, no.2, pp.12-21, 1971-06
- 著者
- 小川 正人
- 出版者
- 一般社団法人 日本教育学会
- 雑誌
- 教育学研究 (ISSN:03873161)
- 巻号頁・発行日
- vol.80, no.3, pp.309-321, 2013
本論文は、1875年に北海道に強制的に移住させられた樺太アイヌの児童を対象として設置された小学校「対雁学校」の歴史を検討したものである。先ず同校の設立・維持に関する行政の施策をあとづけ、学校設置当初のごく一時期を除けば、行政は樺太アイヌの教育に積極的ではなかったことを明らかにした。また、児童の就学状況を捉え直すことを通して、樺太アイヌは、それまでの生活基盤から切り離された暮らしを強いられた中での余儀の無い選択として、子どもに教育を受けさせることを強く求めていたと考えられることを指摘した。樺太アイヌは、自分たちの暮らしを築くこと、そのための子どもの教育の機会と場を求めたのであり、行政がそれに応えなかったのである。
3 0 0 0 OA 近世藩学における文武課業法の成立について
- 著者
- 鈴木 博雄
- 出版者
- 一般社団法人 日本教育学会
- 雑誌
- 教育学研究 (ISSN:03873161)
- 巻号頁・発行日
- vol.38, no.4, pp.273-281, 1971-12-30 (Released:2009-01-13)
- 参考文献数
- 31
3 0 0 0 「社会化と教育」--西ドイツ教育学における議論から
- 著者
- 今井 康雄
- 出版者
- 日本教育学会
- 雑誌
- 教育学研究 (ISSN:03873161)
- 巻号頁・発行日
- vol.51, no.2, pp.p166-177, 1984-06
2 0 0 0 OA 情報教育の課題
- 著者
- 坂元 昂
- 出版者
- 一般社団法人 日本教育学会
- 雑誌
- 教育学研究 (ISSN:03873161)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, no.3, pp.229-241, 1990-09-30 (Released:2009-01-13)
- 参考文献数
- 34
- 著者
- 苫野 一徳
- 出版者
- 一般社団法人 日本教育学会
- 雑誌
- 教育学研究 (ISSN:03873161)
- 巻号頁・発行日
- vol.89, no.2, pp.325-326, 2022 (Released:2022-09-10)
2 0 0 0 OA 藤沢利喜太郎の数学教育理論の再検討 「算術」と「代数」の関連に注目して
- 著者
- 佐藤 英二
- 出版者
- 一般社団法人 日本教育学会
- 雑誌
- 教育学研究 (ISSN:03873161)
- 巻号頁・発行日
- vol.62, no.4, pp.348-357, 1995-12-30 (Released:2009-01-13)
- 参考文献数
- 34
2 0 0 0 OA 天野郁夫著『高等教育の日本的構造』
- 著者
- 舘 昭
- 出版者
- 一般社団法人 日本教育学会
- 雑誌
- 教育学研究 (ISSN:03873161)
- 巻号頁・発行日
- vol.53, no.4, pp.388-389, 1986-12-30 (Released:2009-01-13)
- 著者
- 桐村 豪文
- 出版者
- 一般社団法人 日本教育学会
- 雑誌
- 教育学研究 (ISSN:03873161)
- 巻号頁・発行日
- vol.90, no.1, pp.25-37, 2023 (Released:2023-06-20)
- 参考文献数
- 42
フィリップスは、エビデンスに基づく政策と実践の推進をめぐって対立する立場の全体像を、「硬い心」の立場と「軟らかい心」の立場を両極にもつ連続体として捉えている。本稿が着目するのは、その連続体の中間に位置する「より柔軟」な立場である。その立場は、昨今の科学哲学の知見を踏まえ、因果関係の概念をINUS条件として捉え、ローカルな文脈を重視するアプローチを展開する。しかしそのアプローチも不確実性の問題に直面し、価値判断の必要性に回帰する。
2 0 0 0 OA 大学を選択する論理とジェンダー
- 著者
- 知念 渉
- 出版者
- 一般社団法人 日本教育学会
- 雑誌
- 教育学研究 (ISSN:03873161)
- 巻号頁・発行日
- vol.89, no.4, pp.552-564, 2022 (Released:2023-04-25)
- 参考文献数
- 23
大学ランクや学部学科の専攻における男女差を分析した従来の研究は、大学ランクと専攻を別々に分析してきた。しかし、大学ランクや専攻、浪人という選択などの多様な変数を同時に考慮しなければ、大学進学とジェンダーの関係性はみえてこないのではないか。そこで本稿では多重対応分析を用いて、それらの変数間の「関係の網」を再構築する。その結果、人々の「合理的な選択」を促してジェンダー不平等を持続させる制度的文脈が明らかになる。
- 著者
- 井上 薫
- 出版者
- 一般社団法人 日本教育学会
- 雑誌
- 教育学研究 (ISSN:03873161)
- 巻号頁・発行日
- vol.63, no.2, pp.109-118, 1996-06-30 (Released:2009-01-13)
- 参考文献数
- 67
2 0 0 0 OA 義務教育における無償制の発展過程
- 著者
- 伊藤 秀夫 松井 一麿 下村 哲夫 角替 弘志 沢井 昭男 桑原 敏明
- 出版者
- 一般社団法人 日本教育学会
- 雑誌
- 教育学研究 (ISSN:03873161)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, no.3, pp.196-208, 1962-09-30 (Released:2009-01-13)
- 参考文献数
- 86
2 0 0 0 OA 『文部省年報』就学率再検討学齢児童はどのくらいいたか
- 著者
- 土方 苑子
- 出版者
- 一般社団法人 日本教育学会
- 雑誌
- 教育学研究 (ISSN:03873161)
- 巻号頁・発行日
- vol.54, no.4, pp.361-370, 1987-12-30 (Released:2009-01-13)
- 参考文献数
- 44
- 被引用文献数
- 1
2 0 0 0 OA 夜間中学問題を通して学校を考える
- 著者
- 田中 勝文
- 出版者
- 一般社団法人 日本教育学会
- 雑誌
- 教育学研究 (ISSN:03873161)
- 巻号頁・発行日
- vol.45, no.2, pp.107-117, 1978 (Released:2009-01-13)
- 参考文献数
- 18
- 著者
- 天野 郁夫
- 出版者
- 一般社団法人 日本教育学会
- 雑誌
- 教育学研究 (ISSN:03873161)
- 巻号頁・発行日
- vol.76, no.2, pp.172-184, 2009-06-30 (Released:2017-11-28)
高等教育システムはいま、世界的な変動期を迎えている。日本もその例外ではない。そのシステム変動の基本的な構造と方向性を分析する上で、最も説得的な理論とされているのは、アメリカの社会学者マーチン・トロウの「歴史・構造理論」である。「エリートからマス、ユニバーサルへ」の段階移行で知られるこの理論は、ヨーロッパ、それにアメリカ高等教育の発展の歴史的な経験をもとに、一般化されたものである。本論文の目的は、日本の経験を事例に、その比較高等教育システム論としてのトロウ理論の妥当性を検証することにある。日本を、ヨーロッパ・アメリカと対比させた本論文での分析は、この移行理論の基本的な妥当性を裏付けるものである。しかし同時に、その移行過程の分析は、「エリートからマス、そしてユニバーサルへ」の段階移行に、単一の道を想定することの妥当性に疑問を提示するものである。移行の過程について、アメリカ、ヨーロッパ、そして日本に代表される東アジアという、3つの道を想定することによって、この理論はさらに説得性を増し、実り多いものになるはずである。
2 0 0 0 OA シュタイナーの教育方法論の特質 発達観との関係を中心として
- 著者
- 吉田 武男
- 出版者
- 一般社団法人 日本教育学会
- 雑誌
- 教育学研究 (ISSN:03873161)
- 巻号頁・発行日
- vol.54, no.2, pp.156-165, 1987-06-30 (Released:2009-01-13)
- 参考文献数
- 43
2 0 0 0 OA 『教養』研究の現状と課題—学校化された教養を問うために—
- 著者
- 綾井 桜子
- 出版者
- 一般社団法人 日本教育学会
- 雑誌
- 教育学研究 (ISSN:03873161)
- 巻号頁・発行日
- vol.82, no.1, pp.65-72, 2015 (Released:2016-05-19)
2 0 0 0 OA 「身体感性論」という新しい哲学プロジェクトと教育
- 著者
- 樋口 聡
- 出版者
- 一般社団法人 日本教育学会
- 雑誌
- 教育学研究 (ISSN:03873161)
- 巻号頁・発行日
- vol.87, no.3, pp.391-399, 2020 (Released:2021-01-09)