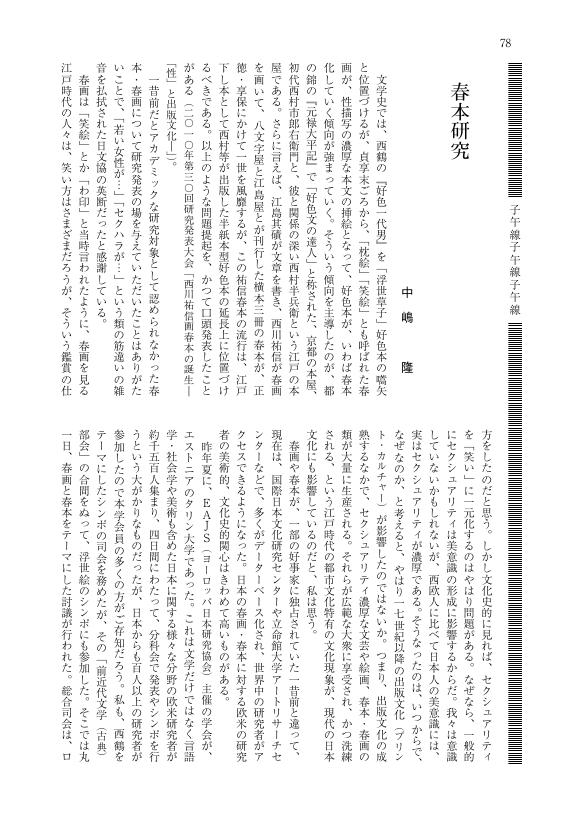1 0 0 0 OA 物語の語り・読み手の言葉
- 著者
- 橋本 博孝
- 出版者
- 日本文学協会
- 雑誌
- 日本文学 (ISSN:03869903)
- 巻号頁・発行日
- vol.60, no.8, pp.43-51, 2011-08-10 (Released:2017-05-19)
言葉の内部には均質に概念が詰まっているのではない。担い手ごとに固有の核がある。その固有であるべき言葉の核を統制しようとするかのごとき動きが、現在の小学校国語科の授業に見られる。物語の授業においてこの傾向を打ち破るには、物語がどう語られているかという次元での文脈を、子どもたちとともに築くことから始めなければならない。登場人物とできごとではなく、語りの次元で作品と向かい合う、という問題意識から出発すると、「ごんぎつね」で問われるべきは、ごんと兵十の物語ではなくなる。ごんと兵十の物語を語る「わたし」をこそ読まなければいけない。そのことは「ごんぎつね」の構造を解き明かすことにつながる。
1 0 0 0 OA 神話と歴史 : 大物主神をめぐって(<特集>神話の世界)
- 著者
- 土橋 寛
- 出版者
- 日本文学協会
- 雑誌
- 日本文学 (ISSN:03869903)
- 巻号頁・発行日
- vol.22, no.8, pp.1-9, 1973-08-10 (Released:2017-08-01)
1 0 0 0 小島勗論ノート
- 著者
- 前田 角蔵
- 出版者
- 日本文学協会
- 雑誌
- 日本文学 (ISSN:03869903)
- 巻号頁・発行日
- vol.30, no.7, pp.98-114, 1981
- 著者
- 青柳 隆志
- 出版者
- 日本文学協会
- 雑誌
- 日本文学 (ISSN:03869903)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, no.6, pp.56-57, 2009
1 0 0 0 OA 黒田三郎詩集『ひとりの女に』(読む)
- 著者
- 宮崎 真素美
- 出版者
- 日本文学協会
- 雑誌
- 日本文学 (ISSN:03869903)
- 巻号頁・発行日
- vol.41, no.8, pp.64-68, 1992-08-10 (Released:2017-08-01)
- 著者
- 角谷 有一
- 出版者
- 日本文学協会
- 雑誌
- 日本文学 (ISSN:03869903)
- 巻号頁・発行日
- vol.53, no.3, pp.1-12, 2004
作品のことばに撃たれ、その「ことばの仕組み」が、自分のとらわれている世界を揺さぶり、瓦解させていくような文学作品の「読み」を教室の一斉授業の中でつくり出すことができないか。今回、村上春樹の『七番目の男』を取り上げて、その<語り>の構造を読むことを通じて目指したのも、そういうことだった。授業として決してうまくいったとは言えない今回の実践から、作品の深みへ誘う「読み」の授業づくりのヒントをつかもうとしたのが、今回の報告である。
- 著者
- 中原 香苗
- 出版者
- 日本文学協会
- 雑誌
- 日本文学 (ISSN:03869903)
- 巻号頁・発行日
- vol.64, no.10, pp.62-66, 2015-10
- 著者
- 篠原 進
- 出版者
- 日本文学協会
- 雑誌
- 日本文学 (ISSN:03869903)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, no.10, pp.84-85, 2008
1 0 0 0 表現の国学 : 賀茂真淵から橘守部まで
- 著者
- 風間 誠史
- 出版者
- 日本文学協会
- 雑誌
- 日本文学 (ISSN:03869903)
- 巻号頁・発行日
- vol.48, no.2, pp.1-11, 1999
国学とは歌文の表現をめぐるなにごとかであった、という視点から真淵以後の国学と歌文の流れを俯瞰しようと試みた。真淵国学は、中世以来の雅(古典規範)を相対化することによって、十八世紀後半に多種多様な歌文を生み出す契機となった。そしてその延長において、雅という規範や美意識は意義を失い、近代の始まりを招来した。それはまた同時に、歌文の創作と学問との乖離をも決定的にした。
1 0 0 0 野生の論理/治病の論理:―― 〈瘧〉治療の一呪符から ――
- 著者
- 北條 勝貴
- 出版者
- 日本文学協会
- 雑誌
- 日本文学 (ISSN:03869903)
- 巻号頁・発行日
- vol.62, no.5, pp.39-54, 2013
<p>平城京二条大路側溝から出土した治瘧の呪符木簡は、定説的には唐・孫思?撰の医書『千金翼方』に基づき、列島固有の文脈も加味して作成されたと考えられている。しかし、同種の呪言は八世紀に至るまでの複数の中医書に散見し、『千金翼方』より上記の木簡に近い表現を持つものもある。その淵源を遡ってみると、前漢・王充撰『論衡』に引かれる『山海経』にまで辿り着く。鬼門を守る神が疫鬼を虎に喰わせるという辟邪の文章は、やがて儺の呪言として展開してゆくが、その過程で、山林修行で培われた医薬・呪術の知識・方法、洪水と疫病の流行による世界の破滅/更新を説く神呪経の言説を含み込んでゆくことになる。そうして成立した短い呪言の一語一語には、その直接意味するところ以上に、豊かで複雑な自然環境/人間の関わりをうかがうことができるのである。</p>
- 著者
- 田中 榮一
- 出版者
- 日本文学協会
- 雑誌
- 日本文学 (ISSN:03869903)
- 巻号頁・発行日
- vol.33, no.8, pp.25-39, 1984-08-10 (Released:2017-08-01)
国語教育の一環としての、文学教育における「読み」や教材研究・教材分析はどうあったらより妥当であるのかという観点に立ち、その一例として、かつてかならずしも妥当な扱われ方をしなかった「野ばら」(小川未明)に即して、その読み・分析について私見をこころみてみた。そこにおいて、その作品の有する特質に即した読みや分析をほどこすことが大切であること、それにより、見落しがちな新たな意味の発見や、より深くより妥当な読み(学習)の成立が期待できること、作者や周辺の資料の援用も時によっては必要であり効果を挙げうること、等にふれた。
1 0 0 0 OA 仏舎利相承説と〈家〉 : 十三世紀の歴史叙述(<特集>中世文学と〈家〉)
- 著者
- 大橋 直義
- 出版者
- 日本文学協会
- 雑誌
- 日本文学 (ISSN:03869903)
- 巻号頁・発行日
- vol.52, no.7, pp.34-43, 2003-07-10 (Released:2017-08-01)
『玉葉』建久三年四月八日条に記された鳥羽宝蔵宝珠の相承系譜は先学の指摘するように、その後も三宝院流という宗教空間内の秘事口説として存在し続けた。しかし、一方で、鳥羽宝蔵の宝珠という本来の意味を離れ、十三世紀の舎利相承系譜に借用されてゆく。これらの相承説の変容・展開の位相を検討することにより、九条家・大乗院や承久の乱以後の天皇家など、様々なかたちの〈家〉の存続・財産保全・追善供養を保証するという現実的な意味をになった歴史叙述として仮構される様相について考察する。
1 0 0 0 横光利一と神道思想 : 『旅愁』の古神道について
- 著者
- 森 かをる
- 出版者
- 日本文学協会
- 雑誌
- 日本文学 (ISSN:03869903)
- 巻号頁・発行日
- vol.46, no.9, pp.45-52, 1997
横光利一は、国体観念の徹底を目的とした大政翼賛会が採用した禊を通じて、『旅愁』に古神道のモチーフを構想する契機をつかんだ。筧克彦の神道説の発見は、他の神道説も複合しての古神道の造形をもたらしたのみでなく、小説の構想にもかかわる点で意味が大きい。同化主義を本質とする筧の神道思想の受容によって構築されたのが、『旅愁』第四篇を中心とした、古神道がカトリックを包摂する神道的世界である。
1 0 0 0 OA 釈教歌の方法と文体
- 著者
- 平野 多恵
- 出版者
- 日本文学協会
- 雑誌
- 日本文学 (ISSN:03869903)
- 巻号頁・発行日
- vol.63, no.7, pp.21-34, 2014-07-10 (Released:2019-07-20)
釈教歌が盛行しはじめる平安時代中期から、釈教歌には二つの文体があった。一つは、漢訳仏典を和語に翻訳して詠むことで、もう一つは漢語による仏教語をそのまま詠み込むことである。前者は経典の内容を詠む法文歌に見られる。当初は経典内容の叙述に詠み手の解釈や心情を加えた二元的構造の歌が多かったが、後に四季の叙景歌や恋歌そのものへと変化した。後者は僧侶の法縁歌・述懐歌に特徴的で、伝教大師や弘法大師などの高僧の伝承歌を始発とする。和語の使用を原則とする和歌が仏教語を許容したのは、当時の和歌が翻訳不可能な仏教語の力を必要としたからだろう。
1 0 0 0 浦島説話の異郷 : 富・長寿・悦楽の国(<特集>故郷と異郷)
- 著者
- 石原 昭平
- 出版者
- 日本文学協会
- 雑誌
- 日本文学 (ISSN:03869903)
- 巻号頁・発行日
- vol.23, no.9, pp.57-64, 1974
- 著者
- 吉野 樹紀
- 出版者
- 日本文学協会
- 雑誌
- 日本文学 (ISSN:03869903)
- 巻号頁・発行日
- vol.48, no.8, pp.1-10, 1999-08-10 (Released:2017-08-01)
筒井康隆の『夢の検閲官』について、「反転」という視点から、その言葉のしくみについて論述した。反転とは、途中まである一つの読みに寄り添っていた読者の読みが、ある時を境に反転させられることをいう。それは、筋の展開や、構造としてあるのではなく、表層の構造を支えている言葉のしくみに織り込まれている。その言葉のしくみに着目して読むことが、文学を教室で読むことにとって重要な課題なのである。
1 0 0 0 OA 春本研究
- 著者
- 中嶋 隆
- 出版者
- 日本文学協会
- 雑誌
- 日本文学 (ISSN:03869903)
- 巻号頁・発行日
- vol.61, no.10, pp.78-79, 2012-10-10 (Released:2017-12-29)
- 著者
- 金井 景子
- 出版者
- 日本文学協会
- 雑誌
- 日本文学 (ISSN:03869903)
- 巻号頁・発行日
- vol.42, no.11, pp.38-46, 1993-11-10 (Released:2017-08-01)
明治三十年代初頭に蒔かれた写生文の種は『ホトトギス』と共に成長して、大正・昭和と、綴り方運動など、人が文を書く原初の欲動と密接に繋がりながら多様な結実を見た。明治三八年一月号の『ホトトギス』は漱石の「吾輩は猫である」と子規の「仰臥漫録」が掲載された号である。本稿ではこれを一つの分水嶺と考え、ここにいたる同誌の写生文実践の内実を、日記というジャンルが果たした役割を焦点化しつつ辿る。
1 0 0 0 OA 禿童異聞考 : 「童謡」と平清盛像象形の関係
- 著者
- 柳瀬 喜代志
- 出版者
- 日本文学協会
- 雑誌
- 日本文学 (ISSN:03869903)
- 巻号頁・発行日
- vol.46, no.5, pp.25-34, 1997-05-10 (Released:2017-08-01)
覚一本系の『平家物語』巻第一「禿髪」に平清盛の専横政治の象徴として書かれていた「三百人」の「禿髪」の童子のことが、広本系の延慶本『平家物語』第一本「清盛繁昌之事」や古活字本『源平盛衰記』巻一では王莽の「童謡」の故事と重ねて語られている。この「禿髪」をめぐる物語の改変は、当時の注釈学の方法に倣って清盛の野心を解明して見せ、かつ「談義」と呼ばれる講義様式をそのままに語りの構成に取り込んだと見られる。そして清盛に皇位を簒奪する企望があったことを表して、新清盛像を提出している。
1 0 0 0 OA 目的意識論への行程 : 大正十五年の青野季吉(<特集>プロレタリア文学)
- 著者
- 関口 安義
- 出版者
- 日本文学協会
- 雑誌
- 日本文学 (ISSN:03869903)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, no.6, pp.1-11, 1982-06-10 (Released:2017-08-01)
1926 was a memorable year for Aono Suekichi. Having resolved to withdraw from political activity in order to devote himself to literary criticism, he found himself a man of the times. He produced a flurry of articles and was drawn into a number of debates, the most important being, of course, that concerning goal-consciousness. This argument was to linger on into 1927. Other than this much-publicized debate, Suekichi experienced two others in the course of 1926. One involved Hirotsu Kazuo, and the other, Masamune Hakucho. Both of these debates provide useful material for understanding the Aono Suekichi of 1926, the Aono Suekichi, that is, who proclaimed the theory of goal-consciousness. This essay attempts to trace the development of this theory by examining the two less-known debates.