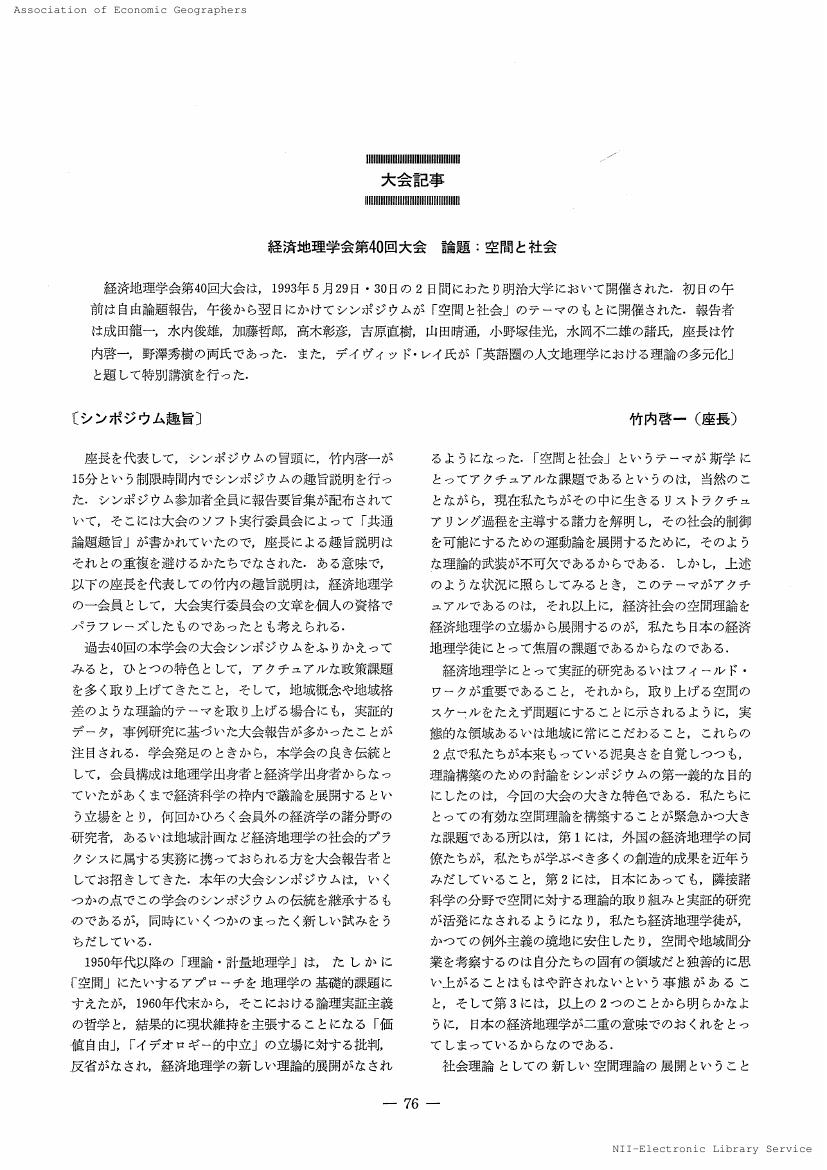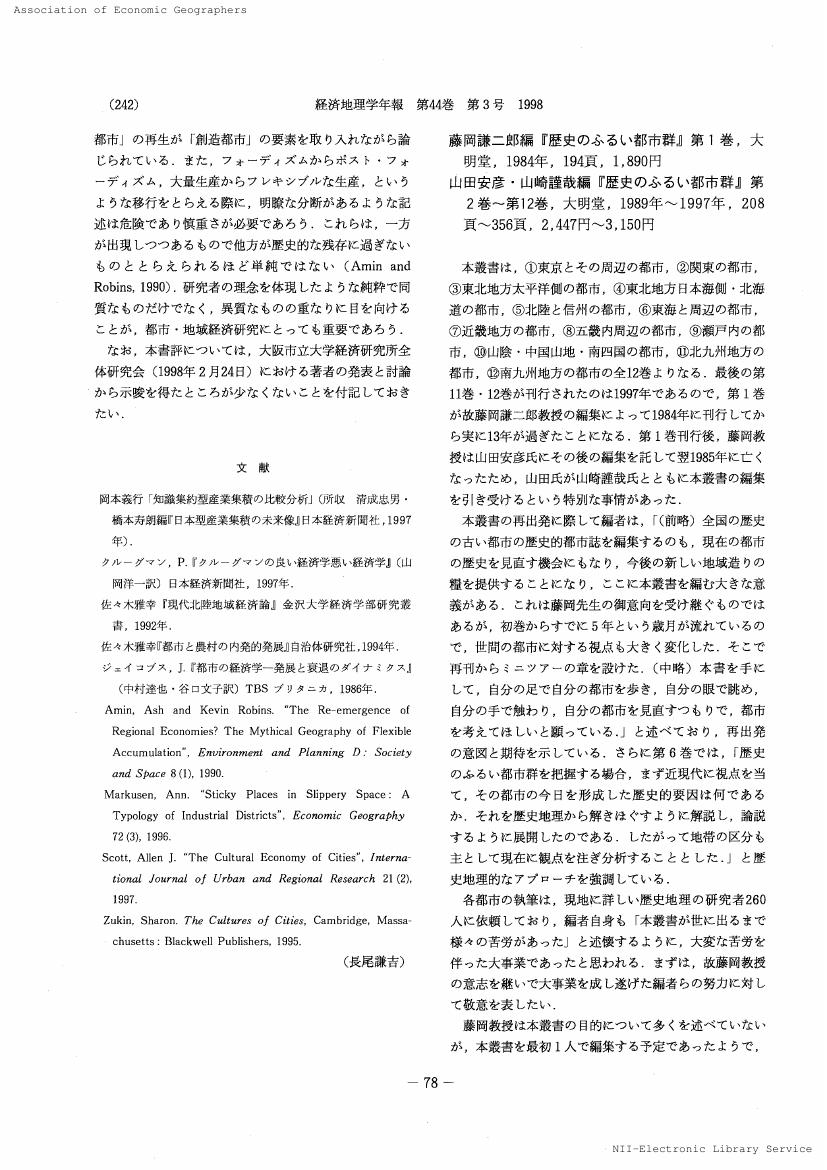1 0 0 0 OA アジアにおける梅干し開発輸入の展開とそのメカニズム
- 著者
- 則藤 孝志
- 出版者
- 経済地理学会
- 雑誌
- 経済地理学年報 (ISSN:00045683)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, no.2, pp.100-117, 2012-06-30 (Released:2017-05-19)
本稿では,梅干し開発輸入の展開とそのメカニズムを,加工業者の企業行動とそれを規定する諸要因の分析から明らかにした.その際,複数の要因=歯車がかみ合いながら開発輸入をめぐるダイナミックな構造変化が起こる仕組みを開発輸入メカニズムと捉え,とくに1990年代に起こった台湾から中国への産地移動に着目した.梅干し開発輸入の地理的パターンは,1960年代から1980年代までの日本-台湾から1990年代以降の日本-中国へとシフトしてきたが,その背景にはアジアの経済発展があった.そのなかで,日本の加工業者は開発輸入をめぐる多様な企業行動を展開してきた.台湾中心期(1962年〜1980年代)には,栽培・加工の技術指導や資材提供,産地開拓がみられ,中国転換・拡大期(1990年代〜2000年代前半)には,新たに直接投資を通じた加工場の設立や調製品輸入の導入がみられた.一方,輸入減少期(2000年代後半)には開発輸入からの撤退が相次ぐなか,差別化商品の開発や品質管理システムの導入など「量的指向型」から「品質指向型」へと企業行動の転換が図られている.このような企業行動の展開は,アジアの経済発展や日本の市場動向などの経済的要因に加えて,言語の共通性や信頼の度合い,政治的対立の有無などの文化的・政治的要因にも規定されていた.とくに1990年代における中国での開発輸入を主導したのは台湾系加工業者であり,そこでは日台中の加工業者間の「文化的・政治的距離」が大きな影響を及ぼしていた.
1 0 0 0 OA 東京圏における保育士不足がもたらした地方圏の保育労働市場への影響
- 著者
- 甲斐 智大
- 出版者
- The Japan Association of Economic Geography
- 雑誌
- 経済地理学年報 (ISSN:00045683)
- 巻号頁・発行日
- vol.67, no.3, pp.149-171, 2021-09-30 (Released:2022-09-30)
- 参考文献数
- 45
- 被引用文献数
- 1
本稿では,求人票に記載された新卒保育士の待遇と地方養成校出身の新卒保育士の就職動向を分析し,保育士養成校のもつ,保育労働力供給源としての役割について考察した. これまで各保育所は自宅からの通勤を前提として新卒保育士を募集してきた.東京圏を中心に保育ニーズが拡大するなかで,東京圏の法人は保育士の待遇を改善し,地方圏へと採用エリアを拡大させた.その結果,宮城県では東京圏への労働力の流出が顕在化し,それに歯止めをかけるべく宮城県での保育士に対する待遇は向上し,宮城県の保育士の就職先の選択肢は拡大した.他方,青森県へも東京圏法人の参入がみられるものの,自治体の財政難を背景に青森県では保育士の待遇改善が難しい状況におかれている.そのため,青森県の保育労働市場はインフォーマルな調整によって下支えされており,相対的に待遇の良い東京圏への保育労働力の流出が増加している.その結果,地元で安定して働ける職業として認識されてきた保育士として学生を就職させることを一つの魅力と位置付けて,学生募集をしてきた青森県の保育士養成校への入学者は減少傾向にある. このように,近年,東北地方の養成校は,保育士が不足する東京圏にも保育士を供給する機能を有しつつある.この機能は縁辺地域でより拡大しており,結果的に地方の保育士養成校の保育士供給機能の低下が懸念されていることが明らかとなった.
1 0 0 0 OA 経済地理学会第40回 (1993年度) 大会 論題 : 空間と社会
- 出版者
- 経済地理学会
- 雑誌
- 経済地理学年報 (ISSN:00045683)
- 巻号頁・発行日
- vol.40, no.1, pp.76-96, 1994-03-31 (Released:2017-05-19)
1 0 0 0 OA 人文学的アーバニズムとしての中心市街地再生
- 著者
- 武者 忠彦
- 出版者
- The Japan Association of Economic Geography
- 雑誌
- 経済地理学年報 (ISSN:00045683)
- 巻号頁・発行日
- vol.66, no.4, pp.337-351, 2020-12-30 (Released:2021-12-30)
- 参考文献数
- 51
地方都市における中心市街地の再生は長年の政策課題であるが,行政主導の計画や事業の多くが機能不全に陥る一方で,近年は小規模で漸進的に都市を改良していく「計画的ではない再生」の動きが注目されている.こうした変化を「工学的アーバニズム」から「人文学的アーバニズム」へのシフトとして解釈することが本稿の目的である.工学的アーバニズムとは,都市は予測・制御が可能なものであるという認識の下で,全国標準化された計画や事業を集権的な行政システムによって進めるという考え方や手法のことである.それを可能にしたのは,近代都市像の社会的共有と都市化という時代背景であった.これによって,中心市街地再生は近代化,活性化,集約化というテーマで政策的に進められてきたが,工学的アーバニズムの限界が明らかになった現在では,都市形成のメカニズムの複雑さを前提に,個々の主体が試行錯誤しながら漸進的に都市を改良し,結果的に都市の文脈が形成されていくという人文学的アーバニズムの重要性が高まっている.現在の地方都市が直面する「都市のスポンジ化」も,人文学的アーバニズムとして読み解くことで,都市形態学的な説明よりも深い洞察が得られることが期待される.そうしたアプローチは「中心市街地再生の人文学」を構想することにもつながるだろう.
1 0 0 0 OA 政治経済学的人口地理学の可能性
- 著者
- 中澤 高志
- 出版者
- The Japan Association of Economic Geography
- 雑誌
- 経済地理学年報 (ISSN:00045683)
- 巻号頁・発行日
- vol.64, no.3, pp.165-180, 2018-09-30 (Released:2019-09-30)
- 参考文献数
- 48
- 被引用文献数
- 1
低出生力や高齢化といった現代日本の人口学的諸問題は,東京一極集中や限界集落化といった地理学的諸問題と不可分である.つまり,最重要の政策課題は,人口と地理が結びつく領域にこそ存在する.人口地理学は,これまでも現状分析の面から人口政策に寄与してきたが,人口政策にまつわる理念やイデオロギーに関する議論とは距離を置いてきた.本稿では,欧米における新たな人口地理学の潮流を意識しながら,新書『縮小ニッポンの衝撃』の批判的検討を手掛かりに,政治経済学的人口地理学の可能性について模索する.地図は,住民の主体的意思決定に役立つツールである反面,客観性を装い,政策主体の意図に沿うように住民を説得するメディアとしても使われる.このことは,GIS論争やスマートシティに関する議論とも関連する.そもそも,データを収集する営み自体が客観的ではありえず,何らかの理想状態を想定して行われている.日本において人口減少への対策が論じられる場合,移民の受け入れ拡大が検討されない場合が多い.そのことは,日本人とは誰かという問いや,エスノセントリズムに関する議論などと結びつく.『縮小ニッポンの衝撃』からは,著者らが低所得の地方圏出身者を他者化していることが垣間見える.このことは,経済や財政への貢献度という一次元において,人々を序列化しようとするポリティクスの表れである.価値中立な地理的量としての人口概念こそ,再検討されるべきである.
- 著者
- 前田 陽次郎
- 出版者
- 経済地理学会
- 雑誌
- 経済地理学年報 (ISSN:00045683)
- 巻号頁・発行日
- vol.61, no.1, pp.94-95, 2015-03-30 (Released:2017-05-19)
1 0 0 0 OA 台湾の地理学会と地理学教室
- 出版者
- 経済地理学会
- 雑誌
- 経済地理学年報 (ISSN:00045683)
- 巻号頁・発行日
- vol.14, no.2, pp.59-61, 1968-11-30 (Released:2017-05-19)
- 著者
- 奥田 義雄
- 出版者
- 経済地理学会
- 雑誌
- 経済地理学年報 (ISSN:00045683)
- 巻号頁・発行日
- vol.4, pp.14-28, 1958
1 0 0 0 OA 名古屋市における女性の就業構造と通勤行動
- 著者
- 神谷 浩夫
- 出版者
- 経済地理学会
- 雑誌
- 経済地理学年報 (ISSN:00045683)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, no.4, pp.247-258, 1983-12-20 (Released:2017-05-19)
- 被引用文献数
- 4
- 著者
- 根田 克彦
- 出版者
- The Japan Association of Economic Geography
- 雑誌
- 経済地理学年報 (ISSN:00045683)
- 巻号頁・発行日
- vol.62, no.4, pp.405-408, 2016-12-30 (Released:2017-12-30)
- 著者
- 森川 洋
- 出版者
- 経済地理学会
- 雑誌
- 経済地理学年報 (ISSN:00045683)
- 巻号頁・発行日
- vol.44, no.3, pp.242-245, 1998-09-30 (Released:2017-05-19)
- 著者
- 登別地域大会実行委員会
- 出版者
- 経済地理学会
- 雑誌
- 経済地理学年報 (ISSN:00045683)
- 巻号頁・発行日
- vol.66, no.4, pp.352-357, 2020
<p> 2019年10月26日(土) ・27日(日) の両日,経済地理学会登別地域大会を開催した.26日は,登別温泉第一滝本館を会場に,シンポジウム「道内観光地の将来展望―交通体系の変化を見据えて―」を行い,学会関係者や地元自治体関係者など45名が参加した.開会の趣旨を説明した後,登別現地からの報告や新幹線延伸と地域への影響に関する報告,他地域の事例としてニセコの観光実態に関する報告が行われた.その後,今後の登別観光のあり方などについて,活発な討議が行われた.シンポジウム後は,そのまま第一滝本館での懇親会・宿泊とし,翌27日は,登別市と白老町において,論点に関わる観光拠点のエクスカーションを実施した.24名の参加であり,各施設での担当者からの解説と活発な議論が行われた.</p>
- 著者
- 金森 正郎
- 出版者
- 経済地理学会
- 雑誌
- 経済地理学年報 (ISSN:00045683)
- 巻号頁・発行日
- vol.60, no.4, pp.348-349, 2014-12-30 (Released:2017-05-19)
1 0 0 0 OA ドイツにおける郡の現状と改革計画
- 著者
- 森川 洋
- 出版者
- 経済地理学会
- 雑誌
- 経済地理学年報 (ISSN:00045683)
- 巻号頁・発行日
- vol.53, no.1, pp.119-134, 2007-03-30 (Released:2017-05-19)
郡制度を欠くわが国では町村と市は対等に扱われるため,財政能力の低い町村は地方交付税の削減の中で,「平成の大合併」に組み込まれざるを得なかった.これに対して,郡の機能的支援によって特別市と対等の立場に立つドイツの市町村は,これまで市町村連合を形成しながらも,小規模市町村が自立し,「市民に身近な政治」を維持してきた.しかし今日,市町村の郡納付金や州からの基準交付金に依存する郡の財政は,州からの任務委託の増大によって著しく悪化してきた.各州では郡の機能改革が計画され,メクレンブルク・フォアポメルン州のように,郡の地域改革に着手しているところもある.
- 著者
- 孫 艶
- 出版者
- 経済地理学会
- 雑誌
- 経済地理学年報 (ISSN:00045683)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, no.3, 2012
1 0 0 0 中心市街地活性化におけるまちづくり会社の役割と課題
- 著者
- 甲斐田 晴子
- 出版者
- 経済地理学会
- 雑誌
- 経済地理学年報 (ISSN:00045683)
- 巻号頁・発行日
- vol.62, no.2, pp.141-150, 2016
1 0 0 0 支店経済都市・福岡の変容
- 著者
- 小栁 真二
- 出版者
- 経済地理学会
- 雑誌
- 経済地理学年報 (ISSN:00045683)
- 巻号頁・発行日
- vol.64, no.4, pp.303-318, 2018
<p> 札幌市・仙台市・広島市・福岡市の4市は,三大都市圏に次ぐ居住・経済・政治の機能集積を有し,地方ブロックの中心的地位にある地方中枢都市として,しばしば一括して扱われてきた.しかしながら近年の社会・経済指標によれば,福岡市は他の3市と比べて顕著な集積を示し,この群から抜け出しつつある. <BR> 本稿ではまず,福岡市の成長が顕著な人口について,その主な増加要因である国内の人口移動に着目して分析した.福岡市における就職期の転入超過は4市のなかで最も大きく,就職期に大きい東京圏への転出超過が縮小傾向にある.このような人口移動を支える要因として,所得機会の存在に加え,居住地としての魅力の高さが重要と考えられる. <BR> 支店経済と並び福岡市の経済的中心性を特徴づけてきた商業機能については,九州新幹線博多~鹿児島中央間全線開業を契機に大型商業施設の出店が続いているにもかかわらず,その広域中心性は低下している可能性がある.代わりに,近年顕著な伸びを示しているのがMICEや訪日外国人の受け入れなど集客機能であり,市経済の新たな牽引役となることが期待されている. <BR> さらに,支店経済からの脱却を目標に,福岡市ではスタートアップ企業の支援に力を入れている.ただし,取り組みは端緒についたばかりであり,将来の市経済の牽引役となる企業が現れるか,また規模拡大時にも福岡市に立地し続けるかは,現時点では未知数である.</p>
1 0 0 0 地方鉄道第三セクター化の課題 : ひたちなか海浜鉄道の事例
- 著者
- 土谷 敏治
- 出版者
- 経済地理学会
- 雑誌
- 経済地理学年報 (ISSN:00045683)
- 巻号頁・発行日
- vol.59, no.1, pp.111-135, 2013
本稿では,地方鉄道が第三セクター化される際の課題や問題点について,ひたちなか海浜鉄道を事例として検討した.具体的には,利用者に対して,乗降駅と乗車券の種類を特定した旅客流動調査を実施するとともに,属性,利用目的・利用頻度などの特色,同鉄道に対する評価について,利用者アンケート調査を実施した.また,市民の認識・評価については,市域全体を対象に市民アンケート調査を実施した.その結果,同鉄道は,勝田・那珂湊間の利用者が全利用者の半数程度を占め,とくに勝田乗降客の半数以上はJR線乗り継ぎ利用者で,その最大の目的地が水戸であることから,JR線をはじめとする地域の交通機関の連携が必要である.とくに,施設などハード面だけでなく,運行ダイヤや運賃制度などソフト面も含めた連携が重要であり,ヨーロッパにみられる運輸連合の導入が将来的な課題である.利用の中心は,沿線居住者や沿線に立地する高校への通学者で,それら利用者の利便性向上が重要であるが,土・休日を中心に相当数の観光客の利用がみられ,地方鉄道にとっては観光利用促進も経営上の課題である.市民の評価では,沿線と沿線以外で地域差はあるものの,財政的支援,今後の存続ともに市民の支持がえられていることが明らかになった.その背景には,広報紙や一般紙を通じた市民に対する行政の積極的な広報活動があり,その継続が求められる.このようなひたちなか市の事例は,公共交通機関の存廃問題を抱える多くの地域で参考になるだろう.
1 0 0 0 Post COVID-19に向けた東北の観光戦略
- 著者
- 山田 浩久 宮原 育子 櫛引 素夫 林 玉恵 山口 泰史 初澤 敏生
- 出版者
- 経済地理学会
- 雑誌
- 経済地理学年報 (ISSN:00045683)
- 巻号頁・発行日
- vol.66, no.3, pp.237-247, 2020
<p> 本稿は,2020年8月8日の13:30~15:00に「Post COVID-19に向けた東北の観光戦略」をテーマにオンラインで開催された北東支部例会の報告である.参加者は北海道から九州まで,非学会員を含めて41名を数えた.広域からの参加が認められたことは,Post COVID-19に対する関心が地域を選ばないことの現れであると思われるが,それを支部例会で議論することができたのはオンライン開催のメリットである.会場では,東北地方を対象にして,震災復興事業とCOVID-19対策の両立,国と県の施策のずれ,航空機と新幹線への影響に関する報告があった後,東北地方のインバウンド旅行に大きな影響力を持つ台湾の観光情勢について報告がなされ,総合討論において活発な意見交換が行われた.</p>
- 著者
- ト部 勝彦
- 出版者
- 経済地理学会
- 雑誌
- 経済地理学年報 (ISSN:00045683)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, no.3, pp.207-225, 1990
- 被引用文献数
- 1