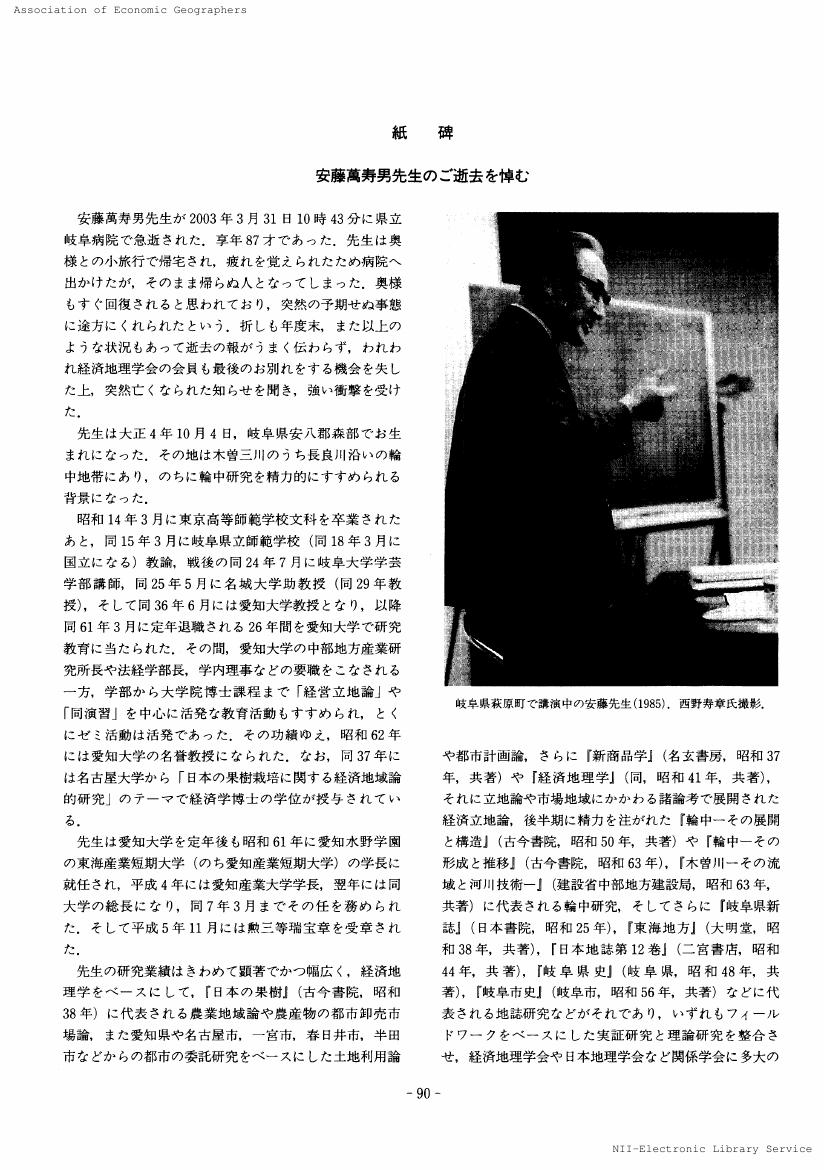- 著者
- 立見 淳哉
- 出版者
- 経済地理学会
- 雑誌
- 経済地理学年報 (ISSN:00045683)
- 巻号頁・発行日
- vol.53, no.4, pp.369-393, 2007
イノベーティブ・ミリュー論と「生産の世界」論という代表的な2つの集積理論が,どのような点で共通し,どのような点で異なっているのか,コンヴァンシオン経済学(EC)を中心とする制度経済学の潮流との関連で考察した.これらの集積理論はいずれも,より現実的な人間像に近いといえる手続合理性の仮定を前提し,不確実性をはじめとする「純粋な市場論理」の不完全性を乗り越えるような効果を有している.これらの効果は,アクターの認知プロセスと深くかかわるものである.「生産の世界」論では,近年の認知科学の発展が取り入れられており,経済調整に果たす物質的事物の役割が考慮されている.2つの集積理論のこうした基本的な共通性にもかかわらず,当然ながら異なる点も存在する.集団学習にかかわるような産業集積の動態分析にとっては,「生産の世界」論のほうがより周到な構成をとっている.可能世界,テスト,事物の導入,等々といった概念の導入によって,評価モデルと呼びうるような慣行(コンヴアンシオン)のもとで,製品品質を含む慣行的規則の生成・変容が論じられている.とはいえ,評価モデルの変容や,集団学習過程における空間的近接性の役割は自明ではない.今後,近年の認知科学やECの展開をふまえて,空間的近接性と集団学習の論理を理論的・実証的に明らかにしていくことが求められる.
- 著者
- 中部地域大会実行委員会
- 出版者
- 経済地理学会
- 雑誌
- 経済地理学年報 (ISSN:00045683)
- 巻号頁・発行日
- vol.52, no.1, pp.36-44, 2006
2005年度の経済地理学会中部地域大会は10月30,31日の両日,経済地理学会が主催し,名古屋地理学会の共催,中部大学人文学部歴史地理学科の後援で中部大学人文学部を会場として開催された.30日の午前中は中部支部の例会として産業,都市,交通,人材,行政の5つの分野にわたって5人の一般発表があった.いずれも午後のシンポジウム「21世紀・中部圏のビジョンを語る-豊かで魅力ある地域をめざして-」にかかわらせた発表であった.シンポジウムではまずコーデイネーターの中藤がシンポジウムの趣旨と視点を述べた後,矢田会長の基調講演「自立圏域連帯型国土構想」があり,そのあと5人のパネリストによるパネルディスカッションが行われた.このシンポジウムには会員,学生,一般市民など130人あまりが参加した.31日は「中部圏の産業基盤と中部国際空港」のテーマで巡検が行われ,37人が参加した.晴天に恵まれ,巡検としては最高の天気であった.なお,大会を開催するにあたって実行委員会が組織され,主として一般発表とシンポジウムは中部大学の関係者で,巡検は名古屋地理学会の関係者が担当した.
1 0 0 0 OA 過疎地域における交通現象と交通機関の機能 : 島根県邑智郡を事例にして
- 著者
- 北島 修
- 出版者
- 経済地理学会
- 雑誌
- 経済地理学年報 (ISSN:00045683)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, no.3, pp.217-234, 1982-09-20 (Released:2017-05-19)
- 著者
- 栗原 尚子
- 出版者
- 経済地理学会
- 雑誌
- 経済地理学年報 (ISSN:00045683)
- 巻号頁・発行日
- vol.24, no.3, pp.p80-83, 1978
- 著者
- 加茂 浩靖
- 出版者
- 経済地理学会
- 雑誌
- 経済地理学年報 (ISSN:00045683)
- 巻号頁・発行日
- vol.44, no.2, pp.93-115, 1998-05-31
- 被引用文献数
- 2
本研究の目的は, 労働市場特性の地域性をもとに, わが国における労働市場の地域構造を把握することにある. このため全国を452の職安管轄区域に区分した単位地域について, (1)有効求人倍率, 雇用保険受給率, 1人当たり製造業賃金, 一般求職者の県外就職率の4つの指標を用いてその地域的パターンを示し, (2)クラスター分析を用いてその類型化を試みた. また分析に際しては, 職安管轄区域の都市的中心性および中心・周辺関係を重視した. その結果, (1)1985年の分析から, 職安管轄区域は, 賃金水準が相対的に高位にある関東地方と西日本の太平洋ベルト地帯, 労働市場の状態が劣悪な国土の縁辺部, この両者の間に広域的に展開し, 有効求人倍率において比較的良好な状態にある地域, の3つの地域に分類されること, (2)1985年と1993年を比較すると, 国土の縁辺部において労働市場状態の改善が顕著であったこと, また, 都市的中心性の低い地区においても労働市場状態の改善傾向が確認され, この変化によって, 労働市場特性の都市的中心性階層間の格差が縮小したこと, (3)1人当たり製造業賃金については, 中心地帯で高く, 周辺地帯で低いという地域性にほとんど変化がみられなかったこと, (4)1985年と1993年を通じて, 県庁所在地区は, それぞれの県のなかでも比較的良好な労働市場状態を示すこと, などが明らかになった.
- 著者
- 竹中 克行
- 出版者
- 経済地理学会
- 雑誌
- 経済地理学年報 (ISSN:00045683)
- 巻号頁・発行日
- vol.55, no.1, pp.65-83, 2009-03-30
- 被引用文献数
- 1
世界有数のワイン生産国スペインは,1980年代以降,EU(EC)共通農業政策による生産制限や新大陸産ワインとの競争といった新たな状況の中で,高品質化と製品の差別化による販路拡大を模索してきた.本稿では,そうしたワイン産業の質的転換に地理的呼称制度が果たした役割について,小規模な原産地呼称が多数成立したカタルーニャ自治州の場合に即して検討した.まず,地理的呼称制度の中で,呼称保護や品質管理といった保証の側面に焦点を当て,同自治州の12の原産地呼称に関する分析を行った結果,産地のイメージや風味の違いを競争資源とする付加価値の創出に一定の効果を与えたことが明らかになった.他方,地理的呼称制度による生産地域画定は,大規模生産者の事業展開にとってはしばしば制約要因となるので,そうした規制の側面についても,代表的な大手生産者を事例として分析した.その結果,大規模生産者は,保証・規制のレベルを異にする地理的呼称の複数のカテゴリを併用したり,複数の原産地呼称に生産拠点をつくるなどの方法で,生産地域画定による縛りを巧みに回避しつつ,付加価値の向上にかかわる地理的呼称制度の利点をいかしていることが判明した.
1 0 0 0 OA 安藤萬寿男先生のご逝去を悼む
- 著者
- 藤田 佳久
- 出版者
- 経済地理学会
- 雑誌
- 経済地理学年報 (ISSN:00045683)
- 巻号頁・発行日
- vol.50, no.4, pp.378-379, 2004-12-30 (Released:2017-05-19)
1 0 0 0 OA 追悼 故 江澤譲爾 前会長
- 出版者
- 経済地理学会
- 雑誌
- 経済地理学年報 (ISSN:00045683)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, no.1, pp.77-78, 1975-05-18 (Released:2017-05-19)
- 著者
- 田中 耕市
- 出版者
- 経済地理学会
- 雑誌
- 経済地理学年報 (ISSN:00045683)
- 巻号頁・発行日
- vol.55, no.1, pp.33-48, 2009
- 被引用文献数
- 1
モータリゼーションに伴う公共交通機関の衰退によって,日本の中山間地域では自家用車を運転しない高齢者の生活利便性が著しく悪化している.おりしも,2001年の補助制度改変と2002年の規制緩和によって,交通事業への参入と撤退の自由度が高まったため,不採算地域における交通サービスの維持方法が問題となっている.本研究では,中山間地域における公共交通が抱える問題を明らかにして,今後の地域交通手段のあり方について考察した.特に,中山間地域の多くがこれまで依存してきた乗合バスと,それに対する代替交通手段に注目した.近年は,自家用車を運転する高齢者の割合も高くなりつつある一方で,高齢者の交通死亡事故も急増しており,公共交通機関の維持が必要である.規制緩和直後の乗合バスの廃止路線数は予想されたほどではなかったが,JRバスグループを中心に中山間地域からの事業撤退が展開された.また,補助制度の変更に伴って,市町村内で完結する路線の撤退が相次いだ.乗合バス路線の廃止後には,自治体補助によるコミュニティバスやコミュニティ乗合タクシー等が運行されることも多かった,しかし,コミュニティバス以外にも,デマンド型交通や有償ボランティア輸送等の代替交通の可能性もあり,中山間地域ゆえの地域特性を考慮したうえでの選択が必要である.自治体の財政は逼迫していることもあり,代替交通は効率的な運営が求められ,運行システムの構築が肝要である.その際には,住民へ提供する交通サービスのシビル・ミニマムをどこまでに設定すべきかの自治体判断も深く関連する.自治体は事前に地域住民のニーズとその特性を把握する必要がある一方で,地域住民も自ら代替交通の計画段階から参画することが,代替交通サービスの成功への鍵となる.しかし,将来的には,人口密度のさらなる低下から,交通サービスのシビル・ミニマムに関する問題の再燃は避けられない.各自治体と無住化危惧集落の住民との相互理解が重要である.
1 0 0 0 林業への新規就労とその対応 : 岐阜県加子母村森林組合の事例より
- 著者
- 中川 秀一
- 出版者
- 経済地理学会
- 雑誌
- 経済地理学年報 (ISSN:00045683)
- 巻号頁・発行日
- vol.42, no.2, pp.79-100, 1996
- 被引用文献数
- 1
林業就業者の減少, 高齢化が進む中で, 森林の管理を誰が行っていくのか, という問題に対する展望は示されてこなかった. こうした中で, 近年, 都市部で生活していた人々の間に, 山村に移住し林業に携わる人々があらわれはじめ, 注目を集めている. 本研究は, 岐阜県加子母村森林組合の事例から, 林業事業体側の対応と新規就労者の林業および山村の生活への適応について検討し, 今後の定着可能性につぃて考察した. 加子母村森林組合は, 村有林作業班の統合を経て, 「東濃桧」販売収益の増大を財政基盤に, 通年雇用・完全月給制による直営作業班を実現した. しかし, こうした雇用条件改善は村内労働者からは敬遠され, 名古屋大都市圏を中心とする都市部出身者によって新たな作業班が編成された. 新規就労者はいづれも20〜30歳代半ばで, 独身者または幼少の子供のいる世帯主である. 両者の新規就労の要因, 林業観には差異が認められ, とくに後者は新規就労の動機として農村生活への希求を挙げる傾向が強い. しかし, 近所付き合いなど農村生活の困難を感じ, 現職に慎重になっているのはむしろ後者であり, 前者は現在の職業に楽観的である. 全般的に彼らの林業技術習得は着々と進んでおり, 林業技術者としての展開は期待される. しかし, ライフサイクルの進展にともなう, 子供の教育機会, 結婚問題など, 山村問題一般への対応に迫られることが予想され, 地域に定着した労働力とみなすのは早計である. 林業労働力としてこうした新規就労を位置づけるためには, むしろ, 彼らの流動性を包含できるような, 地域間労働力移動を前提とするシステムが必要であろう.
世界の食料経済が新たな局面を迎える中で,食料貿易は近年増加している.それは特にアジアの消費の拡大にもよるものである.アジアの大国でもある中国は,特に近年のめざましい経済成長の中で,農産物の大生産国であると同時に,大食料消費国でもある.南米から北米,アフリカからヨーロッパという食料貿易の研究は,世界システム論的な視点あるいはコモディティチェーン(商品連鎖)といったアプローチにより行われてきた.しかし,中国の食料流通に関する研究は少なく,これ抜きには東アジアの食料貿易の理解は難しい.これらのアプローチの東アジアヘの適用を検討する上で,この巨大な国の国内の流通システムの研究は不可欠である.以上のような観点から本論では,中国の青果物供給体系を明らかにすることを試みる.その際,研究事例として北京はもとより中国でも最大級の卸売市場である大鐘寺青果物卸売市場を取り上げ,3月と9月の入荷状況を検討した.両月を設定したのは,3月は多くの野菜が端境期を迎える一方,9月は出荷が最盛期を迎える時期に相当するからである.使用した資料は「大鐘寺農副産品批発(卸売)市場蔬菜水果上市行情及産地月報表」「大鐘寺農副産品批発(卸売)市場月成交量統計表」である.「月報表」では各品目ごとの入荷産地が,「統計表」では各品目ごとの取引額,取引量,最高値,最安値を含む単価がそれぞれ示されている.以上の資料を用いて具体的に北京市に入荷する青果物がどの地域からどのような形態で輸送されているのかを明らかにし,このような青果物の入荷圏がどのように形成されてきたのかなどにも言及するとともに,わが国の青果物流動との比較も行った.その結果,青果物の入荷パターンには季節的な違いが認められた.多くの農産物が出荷の最盛期を迎える9月には,同市場への入荷は北京市近郊,華北地域に集中したが,端境期となる3月には遠く華中・華南方面からも入荷が認められた.その際,単価の高いものほど遠隔から,安いものほど近郊から入荷するという傾向が確認できた.総じて,季節的な変動が認められるものの,端境期には中国全土をカバーするような北京市への青果物供給システムがすでに構築されているといえる.その背景には中国国内の経済格差が影響していることが考えられる.特に,北京の購買力の高さがこのような全国的な体系の構築において重要な役割を果たしたと考えられる.その意味では北京で豊かな消費を享受する者は,日本や米国などの消費者と同じであり,従来コモディティチェーンのアプローチなどで取り上げられた生産地と消費地の格差の問題と同様の問題が中国国内にも当てはめられる.今回確認されたのと同様の全国的な青果物供給体系を早くに構築した日本との比較では,両者の性格の違いが浮き彫りになった.また,東アジアの食料供給という観点からは,中国のもつ,供給者としての側面のみならず,強力な購買力を持ち,時に広大なスケールでの供給圏を構築しうる消費者としての側面が重要であることが確認された.これは欧米諸国への供給者として注目されたアフリカや南米の国々とは大きく異なる点であり,東アジアの食料流通を考える上での極めてユニークな特徴である.
- 著者
- 菊地 達夫
- 出版者
- 経済地理学会
- 雑誌
- 経済地理学年報 (ISSN:00045683)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, no.4, pp.299-308, 2012
北海道は,明治以降,中央政府の主導によって,地域開拓政策,地域開発政策を展開してきた.戦前の地域開拓政策では,食料生産,地下資源開発を中心に産業立地を形成してきた.他方,製造業を中心とした工業立地では,道外大規模資本による鉄鋼業や製紙業の立地,道内小規模資本による食品加工業,木材加工業の立地がみられた,戦後では,太平洋ベルト地帯が形成されると,工業立地の分散のため,大規模な地域開発政策が計画された.北海道の場合,苫小牧東部地域開発計画が展開した.しかしながら,苫小牧東部地域開発計画をはじめとする道内工業団地は,思うような企業誘致ができなかったところが多い.そうした中,同時期に展開した石狩湾新港地域開発計画では,地域環境や地域資源の活用を重視した企業誘致を行い,一定の企業立地に達している.工業立地の場合,その中心は食品加工業や木材加工業であった.それに加え,近年,リサイクル系企業や環境・エネルギー系企業の立地が,急速にすすみつつある.また,東日本大震災の影響が,皮肉にも,それら企業立地の追い風になっている.第7期北海道総合開発計画,札幌臨海小樽・石狩地域の基本計画の内容では,誘致する企業立地の推進として,食品加工業,リサイクル系企業,環境・エネルギー系企業などの業種が示されている.いずれも,地域環境や地域資源の活用を重視する業種内容である.そのため,石狩湾新港地域は,それら企業立地の先駆的な役割を果たしている.
1 0 0 0 全国陸上輸送体系における貨物流動パターン
- 著者
- 野尻 亘
- 出版者
- 経済地理学会
- 雑誌
- 経済地理学年報 (ISSN:00045683)
- 巻号頁・発行日
- vol.39, no.2, pp.136-154, 1993
- 被引用文献数
- 1
本稿の目的は, 1980年の運輸省の地域貨物流動調査のデータを因子分析等を用いて分析し, 全国陸上輸送体系である鉄道コンテナと路線トラックの貨物流動の空間的構造を明らかにし, それらについて各々の輸送手段の特性との関連から考察を加えることにある. クロス集計によれば, 双方の輸送手段ともに東京・大阪・愛知・福岡・北海道に発着が集中している. しかし路線トラックの方がコンテナよりも発着地ともに分散傾向にある. 最大流直接連結法によって, コンテナでは東京・大阪・北海道・福岡を中心とする広域的な流動が, 路線トラックでは東京が東日本全体の, 大阪が西日本全体の発着の中心となっている2大構造が明らかとなった. さらにRモード因子分析の結果を総合すれば一層興味深い流動パターンが現れた. コンテナの場合, 東京と全国間, 大阪と東北・関東・四国・九州間, 北海道から関東・東海・近畿間, 福岡と東京・大阪間という流動パターンが認められた. 路線トラックの場合には, 東京と南東北・関東甲信越および近畿間, 大阪と関東・近畿・中国・四国・九州間, 愛知と近畿・東海・北陸・関東間, 福岡と九州各県間, 宮城と東京および東北各県間, 広島と大阪および中国各県間, 北海道内といった流動パターンが認められた. Rモードの因子得点をクラスター分析した結果,コンテナでは東京・大阪・愛知・北海道が, 路線トラックでは東京・大阪・愛知が各々重要な発送の中心地であると認められた. 路線トラックは各広域拠点都市を中心としたブロック域内の輸送が中心であるのに対して鉄道コンテナはトラックよりも長距離の広域拠点都市間の輸送を補完するものとして機能している. しかし本研究では貨物流動に因子分析を適用することについての問題点も浮かび上がった. そのため物流に関する研究とも関連させながら内外の方法論について展望し検討を加えた.
1 0 0 0 OA 経済地理学における生態学的認識論と2つの「埋め込み」(<特集>経済地理学の本質を考える)
- 著者
- 中澤 高志
- 出版者
- 経済地理学会
- 雑誌
- 経済地理学年報 (ISSN:00045683)
- 巻号頁・発行日
- vol.59, no.4, pp.468-488, 2013-12-30 (Released:2017-05-19)
本稿では,経済地理学における関係論的視点重視の潮流を生態学的認識論の高まりと捉えた.ブラーシュは生態学を範に採り,科学としての人文地理学の樹立を目指したが,対象を自然的・物的関係に自己限定し,主体と社会環境との相互作用や一般的・普遍的な関係の探求を他分野にゆだねる結果となった.地域構造論は,ブラーシュの「地的有機体」と同様の認識論に立脚しながらも,地域的分業体系の骨格をなす産業配置の側から,経済循環の空間的まとまりである経済地域の生成を説明する枠組みを示した.しかし,現代の経済地理を分析するうえでは限界があり,空間的組織化論の発展によってそれを乗り越えることが期待される.「埋め込み」の概念的な検討に際しては,「グラノベッター的埋め込み」と「ポランニー的埋め込み」を峻別すべきである.前者の浸透によって,主体の行為を社会的文脈の中で関係論的に捉える研究は蓄積されたが,一般的・普遍的関係を把握するための方法論的探究が置き去りにされている感がある.その難点を克服するためには,「ポランニー的埋め込み」の議論を摂取して,一般的・普遍的関係に迫りうる分析視角の確立を目指すべきである.以上を踏まえ,労働市場のマクロな分析視角として,労働力需給の空間的ミスマッチ,時間的ミスマッチ,スキルミスマッチの地理的・歴史的変化の把握と,これらミスマッチの制度的克服の解明を提起し,若干の実証的検討を行った.
- 著者
- 西原 純
- 出版者
- 経済地理学会
- 雑誌
- 経済地理学年報 (ISSN:00045683)
- 巻号頁・発行日
- vol.55, no.2, pp.168-175, 2009
- 被引用文献数
- 1
2008年11月1日(土)に経済地理学会中部支部11月例会として,標記のシンポジウムを中部大学名古屋キャンパスにて開催した.地理学だけでなく地方財政学や社会学の研究者を含めた8人の報告者と61名の参加を得た.平成の大合併の目的,合併のあり方,庁舎の方式や地域内分権制度,山間地域・離島地域での広域な自治体の運営,地域の担い手・組織などについて,合併後の行政実情と問題を報告・討論し,そこから解決すべき課題を共有して,課題の解決に迫った.
1 0 0 0 OA 山梨県富士吉田織物産地における機屋の経営革新と企業間ネットワークの形成
- 著者
- 小俣 秀雄
- 出版者
- 経済地理学会
- 雑誌
- 経済地理学年報 (ISSN:00045683)
- 巻号頁・発行日
- vol.59, no.1, pp.88-110, 2013-03-30 (Released:2017-05-19)
本稿は,新製品開発によって経営革新を成し遂げた機屋と産地との相互の関係に注目して,山梨県富士吉田織物産地の革新性について検討することにより,産地の持続的なあり方を展望することを目的とした.本稿で新製品開発による経営革新の事例として取り上げたM機屋は,生産手段を持たずに,デザイン企画機能に特化して製品の提案を行う「テーブル機屋」という形態である.M機屋による新製品開発とそれによる経営革新には,企業独自の努力や論理が強く作用しているが,M機屋の要求に対応できる産地内の外注業者の技術レベルやそれらの業者の空間的近接も重要な成功要因であった.また,新製品が開発されるプロセスにおいて,外注業者のグレードアップや技術的範囲の拡大も見られた.これらのことから,個別機屋の新製品開発は産地と個別機屋に相互効果を及ぼすことが明らかとなった.現在の富士吉田産地においては,政府の施策を直接的契機として,性格を異にする企業の共同化が複数興っており,M機屋はこれらの企業間ネットワーク同士の結節点をなしている.かくして富士吉田産地では重層的・広域的で複雑な企業間ネットワーク構造により,M機屋の経営革新に関するノウハウの,他の機屋への伝播を促すソフトな仕組みが形成されつつある.これを産地全体のなかで位置づけると,従来の下請け的な構造のなかに,企業間の水平的ネットワークによって自立的な経営を目指す部門が生成しつつあり,二重構造的である.このような二重構造の深化は,富士吉田織物産地の持続的な在り方の1つの方向であるといえる.
- 著者
- 坪本 裕之
- 出版者
- 経済地理学会
- 雑誌
- 経済地理学年報 (ISSN:00045683)
- 巻号頁・発行日
- vol.53, no.5, pp.461-477, 2007-12-30
- 被引用文献数
- 1
本研究は,1990年代以降の,大規模再開発が進められている東京中心部におけるオフィス業務の変化と企業再構築,そしてそれらが反映されると考えられる新しいオフィス形態の導入が,都心とそれを含む大都市圏空間にもたらす影響について考察した.事例として,バブル経済崩壊後に急成長を遂げた経営コンサルティング企業に代表される知識基盤産業のオフィス構築活動を検討し,新しいオフィスの形態とそれを支える要素について考察した.米国に親会社をもつ旧会計事務所系経営コンサルティング企業では,1990年代前半に企業再構築の柱として,情報共有を目的とした情報化の推進とチーム制の導入,能力主義的業績評価をはじめとする人的資源管理(Human Resource management)の刷新が行われ,それに伴って,コンサルタントの執務するスペースにフリーアドレスが導入され改良されていった.フリーアドレスでは,コンサルタントはあらかじめ決められた席を持たず,必要があるごとに自由に席を決める.この新たなオフィスの形態を導入した結果,コンサルタントの大量採用が進む一方で,従業員一人当たりが占有する床面積とそれにかかるコストは大幅に縮小され,利用目的の再考と効率的なオフィススペースの活用が試みられた.さらにモバイルオフィスの導入によってコンサルタントの業務はフットルースとなり,フリーアドレスはオフィスから都市空間に拡張された.そして,オフィスとその外部の都市空間はワークプレイス(workplace)として統一的に扱われるようになりつつある.1990年代初頭にサテライトオフィスを開設した企業では,経営コンサルティング企業と同様に情報技術の利用と人的資源管理の刷新を行った結果,郊外に設けられた施設型分散オフィスの利用価値が低下している.一方,その核として位置づけられる中心部のオフィスは,チームプロジェクトの結節点としての機能が強化されつつ,顧客との関係強化においては,ワークプレイスそれ自身が含まれる不可視的な商品を具現化するショールームとしての機能が重視され,顧客企業本社からの近接性が高く,2000年代に入って再開発が進行しオフィス床の供給が増加した中央業務地区(CBD)での立地が強化されている.こうした動向は,オフィスがその内部における情報流やオフィス組織,そしてそれらを有機的に結びつけようとする企業活動が反映された土地利用形態であることを示している.事例として挙げた,情報へのアクセスの均質性が実現されたフリーアドレスと,それが外部に拡張してできるワークプレイスは,業務の遂行とサービスの付加価値の向上に必要とされる協同作業,言い換えればチーム構成員の相互補完を前提とした業務空間である.しかし,この補完性はオフィス形態を支えてきた潜在的な本質であり,ワークプレイスが構築されるに伴って表出したに過ぎない.既往の都市内部レベルのオフィス研究においては,対面接触の情報通信手段による代替性が基本的な概念として強調され,それが不可能な情報交換の手段として対面接触が位置づけられて都心の集積が評価されたが,今後の都市内部および大都市圏レベルのオフィス研究においては,オフィス業務の持つ補完性の考慮がより重要となろう.都市内部の業務地域を,機能的空間として考察してきた都市地理学の有用性は,この点の考慮にあるといっても過言ではない.
1 0 0 0 地方銀行の県外店舗網の展開と資金移動
- 著者
- 千葉 立也
- 出版者
- 経済地理学会
- 雑誌
- 経済地理学年報 (ISSN:00045683)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, no.4, pp.257-269, 1981-02-28