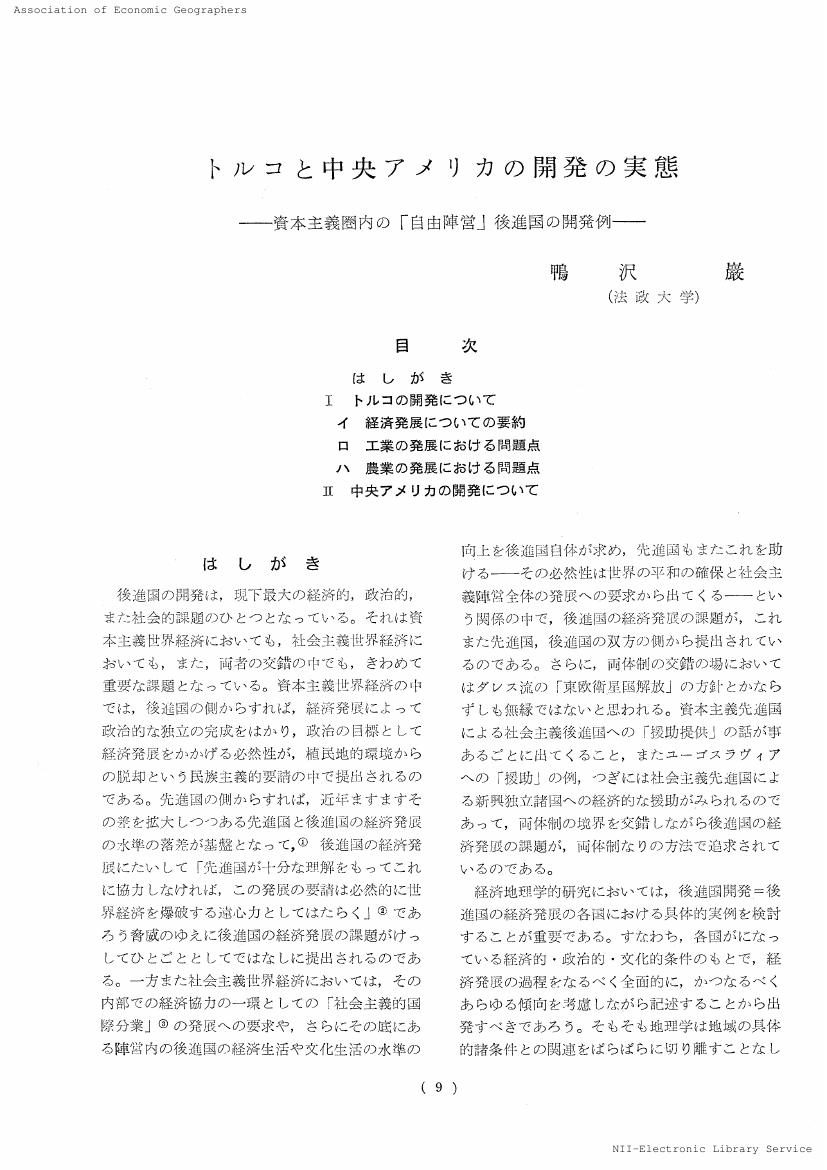1 0 0 0 OA 花き園芸における主産地形成の展開 : 花き生産配置との関連において
- 著者
- 太田 理子
- 出版者
- 経済地理学会
- 雑誌
- 経済地理学年報 (ISSN:00045683)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, no.4, pp.244-262, 1980-02-29 (Released:2017-05-19)
1 0 0 0 OA 地方中核都市の郊外における人口高齢化と住宅地の持続可能性 : 福岡市の事例
- 著者
- 長沼 佐枝 荒井 良雄 江崎 雄治
- 出版者
- 経済地理学会
- 雑誌
- 経済地理学年報 (ISSN:00045683)
- 巻号頁・発行日
- vol.54, no.4, pp.310-326, 2008-12-30 (Released:2017-05-19)
- 被引用文献数
- 3
1970年代以降,地方中核都市は急成長を遂げ,現在も人口が増加し続けている.それに伴い深刻な住宅不足に陥ったが,大都市圏のように一定期間に集中した人口増加は経験していない.したがって,地方中核都市の郊外では,同じ年齢層の住民が多数入居せざるを得なかった大都市圏の郊外とは,異なる人口高齢化の様相を示す可能性がある.本稿では福岡市を事例に,地方中核都市の郊外においても,大都市圏と同様のメカニズムで高齢化が進むか否かを実証的に検討する.また人口維持の面から住宅地の持続可能性について考察を行う.福岡市の高齢化は2000年には都心において進んでいたが,2015年には郊外において急速に進行すると予測される.中でも高齢化の進行が著しいのが,1970年代に丘陵を切り開いて造られた,縁辺部の住宅地である.ここでは,第二世代の地区外転出が進んでいることに加え,離家した第二世代が第一世代の近隣に戻ってくる可能性が低いことも確認された.このような住宅地に,新たな住民が大量に転入するとは考え難いだめ,いずれ高齢化が進むと考えられる.また福岡の事例からみて,地方中核都市の郊外においても,第一世代の定住による加齢と第二世代の地区外転出により,地区の人口高齢化が進むという大都市圏と同様のメカニズムが顕在化する可能性が高い.さらに,こういった住宅地は,地区内の土地の勾配や公共交通の利便性に問題があることから,大都市圏,あるいは地方都市の平地上の住宅地と比べて,第一世代が単独で生活できる期間が短くなる可能性がある.
1 0 0 0 年齢階級別人口移動からみたわが国都市システムにおける大都市の現状
- 著者
- 森川 洋
- 出版者
- 経済地理学会
- 雑誌
- 経済地理学年報 (ISSN:00045683)
- 巻号頁・発行日
- vol.66, no.2, pp.177-188, 2020
<p> 国勢調査(2015年) を用いて,主として大都市の年齢階級別人口移動を分析した結果,東京特別区を除く5大都市もそれぞれ関係圏をもつとともに,全国の主要都市から若年人口を吸引し,東京特別区に対して人口を供給する「吸水ポンプ」の役目を果たすことが確認された.5大都市に属する横浜市,京都市,神戸市も広い関係圏をもち,比較的多くの地方都市から人口を吸引するもので,単なる衛星都市ではない.また5 大都市と広域中心都市(福岡市 ,仙台市,札幌市)は東京特別区に大量の若年人口を供給するほぼ同一階層の都市といえる.東京特別区では全国から大量の若年人口を吸引しており,その他の年齢階級人口は排出しても,人口の一極集中が是正される方向にはない.</p>
- 著者
- 安倉 良二
- 出版者
- 経済地理学会
- 雑誌
- 経済地理学年報 (ISSN:00045683)
- 巻号頁・発行日
- vol.53, no.2, pp.173-197, 2007
- 被引用文献数
- 1
本研究は,地方中小都市における中心商店街の再生について,愛媛県今治市の仲間型組織である「今治商店街おかみさん会」(以下,今治おかみさん会)を事例に選び,その設立背景となる商業環境の変化と活動実態の分析から考察を進めた.高度経済成長期に工業の好況を背景に隆盛を極めた今治市の中心商店街は,1990年代後半以降,大店法の運用緩和に伴う郊外地域での大規模な商業集積の形成としまなみ海道開通の影響を受け,その衰退が決定的となった.今治商工会議所,今治市役所,今治商店街協同組合は大規模な再開発構想や空店舗対策など,様々な再生策を打ち立てたが,その多くは不調に終わり,中心商店街の再生は行き詰まりをみせていた.このような状況からの打開策として,松山市で女性による商店街のまちづくりに関する実践を知った今治市役所商工労政課の提案を受けて2000年11月に設立されたのが今治おかみさん会である.今治おかみさん会は,既存の商店街組織である今治商店街協同組合とは独立しており,話題性の高い共同事業を独自で継続的に展開することで中心商店街の再生に寄与する組織のひとつとなっている.しかし,行政からの補助金削減と会員店舗の減少により,今治おかみさん会の運営は厳しい状況にある.今治市の事例からは,商業活動の衰退が進む地方中小都市の中心商店街では,規模の縮小を前提に,既存の枠にとらわれない仲間型組織が再生の一翼を担う可能性をもつことが明らかになった.
1 0 0 0 OA 現代日本の古紙・鉄屑リサイクルシステム : 静脈産業立地論序説
- 著者
- 外川 健一
- 出版者
- 経済地理学会
- 雑誌
- 経済地理学年報 (ISSN:00045683)
- 巻号頁・発行日
- vol.40, no.3, pp.241-255, 1994-09-30 (Released:2017-05-19)
- 被引用文献数
- 1
本稿では日本におけるリサイクルの現状を, 特に古紙と鉄屑を事例に考察した. 古紙卸売業の立地は, 人口及び出版・印刷業が集中している首都圏のシェアが大きい. 鉄屑卸売業の立地は古紙に比べて, 西日本のシェアが高いが, これは「再生業」たる電炉メーカーの立地に大きく起因している. 製紙工場の立地展開は, 一貫して木材資源を求めてのものであったが, 将来的に古紙を原料とする「古紙」立地の可能性は小さい. これに反し電炉の立地は, 現在も鉄屑の発生しやすい都市・工業地帯の周辺に集中している. 再生原料の空間移動に関しては, 新聞古紙に相当の広域移動が観察でき, 段ボール古紙の方は, 幾分移動が限定されている. また鉄屑は古紙の場合に比べて域内で消費されている. ところで廃棄物問題が顕在化している今出再生資源や廃棄物の空間移動を的確に把握したうえでの「国土」の適切な利用方法の検討が, 重要な課題であるといえよう.
- 著者
- 清水 希容子
- 出版者
- 経済地理学会
- 雑誌
- 経済地理学年報 (ISSN:00045683)
- 巻号頁・発行日
- vol.52, no.2, pp.96-97, 2006
1 0 0 0 OA わが国産業機械工業の立地 : 市場構造と生産物ポテンシャルの考察
- 著者
- 宮坂 正治
- 出版者
- 経済地理学会
- 雑誌
- 経済地理学年報 (ISSN:00045683)
- 巻号頁・発行日
- vol.9, pp.1-17, 1964-03-31 (Released:2017-05-19)
- 被引用文献数
- 1
1 0 0 0 OA 和歌山県南部川村における梅生産・加工の展開
- 著者
- 荒木 一覗
- 出版者
- 経済地理学会
- 雑誌
- 経済地理学年報 (ISSN:00045683)
- 巻号頁・発行日
- vol.39, no.2, pp.155-173, 1993-05-31 (Released:2017-05-19)
- 被引用文献数
- 5
本研究は,規模の拡大や都市へのアクセス, 労働力の高齢化などで大きな制約のある営農条件不利地域を対象に, そこでの農業存続の新たな可能性を解明することを試みた. その際, 一部に認められる自立的農業経営地域の存立メカニズムを検討することに力点を置いた. また, 農民の組織化, 加工業など農外部門との関わり, 農業の国際化との関わりの検討も重視した. 対象としたのは, 和歌山県日高郡南部川村の梅生産と加工である. 研究の成果は次の通りである. 第1にこの地域の梅栽培の発展過程を考察し, 全国的な梅産地への成長に至るこの地域の特質を検討した. 結果, 梅干需要の伸びが梅加工業の集積した当地の梅産地としての成長に有利に作用したと考えられる. 第2に, 村内の梅栽培農家の経営形態を1年間の労働力配分を重視して分析したところ, 安定した収益を挙げる梅栽培を柱とした複合経営により自立的な農業経営が達成されていることが明らかになった. 第3に, 梅栽培農家の安定した収益を保証するメカニズムを加工業者に着目して検討した. その結果, 2次加工部門を域内に取り込むことや台湾産の梅干を輸入することで成長してきた加工業者の存在が梅の生産者価格の高付加価値化と安定において重要であることが明らかになった. 一方, 生産農家,加工業者の双方において労働者の不足と高齢化が, また流通部門では海外産品の高騰がともに問題点として指摘された.
1 0 0 0 メガ・イベント研究からオリンピック研究へ:―地理学的主題の探求―
- 著者
- 成瀬 厚
- 出版者
- 経済地理学会
- 雑誌
- 経済地理学年報 (ISSN:00045683)
- 巻号頁・発行日
- vol.66, no.1, pp.3-28, 2020
<p> 本稿は,英語圏におけるオリンピック研究を整理したものである.本稿で取り上げたオリンピック研究の多くは,上位分野であるメガ・イベント研究に位置づけることができ,学際的な観光研究から発したこの分野には都市社会学や地理学の貢献が大きかった.オリンピックという複雑で大規模なイベントの性質上,本稿では多様な研究分野を扱っているが,オリンピック研究における都市研究を含む広義の地理学的な主題を探求するのが本稿の目的である. <BR> IIIでは初期のイベント研究における社会的インパクトの分類―経済,観光,物理的,社会・文化的,心理的,政治的―に従って,多様な分野におけるオリンピック研究を概観した.IVでは地理学的主題をもった研究に焦点を合わせ,オリンピック都市,グローバル都市間競争,都市(再)開発,レガシー・環境・持続可能性,市民権と住民参加という分類で整理した. <BR> 地理学者によるオリンピック研究は2000年前後から,過去の開催都市を概観する形で,それ以降盛り上がりをみせる地理的主題を持つオリンピック研究を牽引したといえる.当初から国際的なイベントであった近代オリンピック競技大会は,今日において大会招致がグローバル都市間競争の一端となり,大会関連開発は新自由主義的な都市政策の下で官民連携によって行われている.さまざまな問題を抱え,オリンピックはどこに向かうのだろうか.</p>
1 0 0 0 OA 「行動の科学としての地理学」をめぐって
- 著者
- 大貝 健二
- 出版者
- 経済地理学会
- 雑誌
- 経済地理学年報 (ISSN:00045683)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, no.4, pp.309-323, 2012-12-30 (Released:2017-05-19)
- 被引用文献数
- 1
経済のグローバル化や,少子高齢化の進行に伴い,国内地域経済の疲弊が進んでいる.そのなかで農商工連携,6次産業化など地域資源を活用した地域経済の活性化を目指す取り組みが展開されてきている.本稿で取り上げる北海道・十勝地域は,国内最大の小麦生産地であるが,その大部分は国内消費地へと移出されていることから,地域内で生産,加工,消費の連関は希薄であった.しかし,近年は,農業生産者,中小企業者などの地域の経済主体により,十勝で生産された小麦を地域内で加工し消費する,地域内経済循環を構築する取り組みが広まりつつある,同時に,十勝地域では,「農」や「食」をキーワードに,地域資源を活用した地域産業振興策が積極的に展開されている.そこで,本稿では,地域の経済主体による経済循環を構築する取り組みを明らかにするとともに,地方自治体による地域産業振興施策の展開にも注目している.
- 著者
- 岡部 遊志
- 出版者
- 経済地理学会
- 雑誌
- 経済地理学年報 (ISSN:00045683)
- 巻号頁・発行日
- vol.61, no.2, pp.101-120, 2015
フランスにおいては地方分権が進むとともに,地域政策の担い手として「地域圏」の役割が重要になってきている.その重点政策の1つがフランス版のクラスター政策である「競争力の極」政策である.クラスター政策に関しては,その空間的なスケールとガバナンスのありようが問われているが,これらの点を踏まえて本稿では,フランスのミディ・ピレネー地域圏を対象地域にして,「競争力の極」政策が地域の産業集積と政府間関係に果たした役割を明らかにする.フランス南西部のミディ・ピレネー地域圏は,航空宇宙産業が集積するトゥールーズを中心都市としつつも,全体としては農村的で,周辺的な低成長地域として位置づけられてきた.2005年からの「競争力の極」政策により,当地域圏では,西隣のアキテーヌ地域圏と連携しつつ,「アエロスパース・ヴァレー」の名の下で,航空宇宙産業の国際競争力強化が目指されてきた。こうした政策の結果,既存の航空宇宙産業集積とIT産業との融合が図られるなど,研究開発機能の強化が促進された.資金面での中央政府の役割は低下しているものの,産業特性やガバナンスの観点からは,依然として影響力は強い.また,R&Dを促進するために「戦略分野」が設定されているが,これを空間的な観点から分析すると,広域的な連携がなされている一方で,中心都市トゥールーズの中心性が強化される傾向がみられた.
1 0 0 0 OA 合理化による石炭資源の放棄 : 常磐炭田の例
- 著者
- 矢田 俊文
- 出版者
- 経済地理学会
- 雑誌
- 経済地理学年報 (ISSN:00045683)
- 巻号頁・発行日
- vol.13, no.1, pp.1-19, 1967-04-01 (Released:2017-05-19)
- 著者
- 安倉 良二
- 出版者
- 経済地理学会
- 雑誌
- 経済地理学年報 (ISSN:00045683)
- 巻号頁・発行日
- vol.53, no.2, pp.173-197, 2007-06-30 (Released:2017-05-19)
- 被引用文献数
- 5
本研究は,地方中小都市における中心商店街の再生について,愛媛県今治市の仲間型組織である「今治商店街おかみさん会」(以下,今治おかみさん会)を事例に選び,その設立背景となる商業環境の変化と活動実態の分析から考察を進めた.高度経済成長期に工業の好況を背景に隆盛を極めた今治市の中心商店街は,1990年代後半以降,大店法の運用緩和に伴う郊外地域での大規模な商業集積の形成としまなみ海道開通の影響を受け,その衰退が決定的となった.今治商工会議所,今治市役所,今治商店街協同組合は大規模な再開発構想や空店舗対策など,様々な再生策を打ち立てたが,その多くは不調に終わり,中心商店街の再生は行き詰まりをみせていた.このような状況からの打開策として,松山市で女性による商店街のまちづくりに関する実践を知った今治市役所商工労政課の提案を受けて2000年11月に設立されたのが今治おかみさん会である.今治おかみさん会は,既存の商店街組織である今治商店街協同組合とは独立しており,話題性の高い共同事業を独自で継続的に展開することで中心商店街の再生に寄与する組織のひとつとなっている.しかし,行政からの補助金削減と会員店舗の減少により,今治おかみさん会の運営は厳しい状況にある.今治市の事例からは,商業活動の衰退が進む地方中小都市の中心商店街では,規模の縮小を前提に,既存の枠にとらわれない仲間型組織が再生の一翼を担う可能性をもつことが明らかになった.
1 0 0 0 但馬漁業の展開とその流通構造
- 著者
- 田中 豊治
- 出版者
- 経済地理学会
- 雑誌
- 経済地理学年報 (ISSN:00045683)
- 巻号頁・発行日
- vol.18, no.2, pp.40-61, 1973
1 0 0 0 OA シンガポールの工業化
- 著者
- 巖 勝雄
- 出版者
- 経済地理学会
- 雑誌
- 経済地理学年報 (ISSN:00045683)
- 巻号頁・発行日
- vol.18, no.2, pp.62-75, 1973-01-25 (Released:2017-05-19)
1 0 0 0 OA 但馬漁業の展開とその流通構造
- 著者
- 田中 豊治
- 出版者
- 経済地理学会
- 雑誌
- 経済地理学年報 (ISSN:00045683)
- 巻号頁・発行日
- vol.18, no.2, pp.40-61, 1973-01-25 (Released:2017-05-19)
1 0 0 0 OA 物質代謝論アプローチとエコロジー経済学
- 著者
- 外川 健一
- 出版者
- 経済地理学会
- 雑誌
- 経済地理学年報 (ISSN:00045683)
- 巻号頁・発行日
- vol.39, no.3, pp.207-220, 1993-09-30 (Released:2017-05-19)
本論文ではまず, 環境経済学の確立に向けた代表的アプローチの1つである, 物質代謝論アプワーチについての考察を行なった. 人間の経済活動をも含む, 広い意味での生命活動が, 「人間と自然のあいだの物質代謝」を媒介として行なわれているという事実を重視・認識し, 環境経済学の理論を構築しようというのが, このアプワーチの本質である. そのうえで筆者は, 基本的に「人間と自然のあいだの物質代謝」を, 人間の経済活動を主とした生命活動が大きく作用している, エコーシステム内の物質及びエネルギーの代謝と捉えることとした, 次に, 経済学における環境問題・資源問題の文献としてマルサス, ジェヴォンズ, ジョージェスク=レーゲンの業績を, 特に「規制原理」と「増殖原理」という観点から考察した. そのうえで, 現在環境問題解決のため, 大きな期待がかけられている「リサイクル」について, その本来の意味と限界とを指摘した. さらに, コルビーによる地球環境管理をめぐる5つのパラダイムを紹介し, 現在発展途上にあるエコロジー経済学の形成と展望に関して, 若干のコメントを述べた. そのうえで, とくにマルサスに起源を持つ, 「規制原理」と「増殖原理」との相互作用を通じてみられる社会・経済の発展をみる視角に, 新古典派やマルクス経済学の業績を組みいれて考察するというパラダイムの模索も, 有益なものであると指摘した. 最後に, 人間と自然のあいだの物質代謝の攪乱は, 具体的には地域において展開されていることを考えれば, 物質代謝論アプローチには, 産業立地や地域構造の把握が不可欠であることを強調した.
1 0 0 0 OA トルコと中央アメリカの開発の実態 : 資本主義圏内の「自由陣営」後進国の開発例
- 著者
- 鴨沢 巖
- 出版者
- 経済地理学会
- 雑誌
- 経済地理学年報 (ISSN:00045683)
- 巻号頁・発行日
- vol.5, pp.9-26, 1959-04-25 (Released:2017-05-19)
1 0 0 0 OA 三陸常磐地域における資本制漁業の発達
- 著者
- 田中 豊治
- 出版者
- 経済地理学会
- 雑誌
- 経済地理学年報 (ISSN:00045683)
- 巻号頁・発行日
- vol.7, pp.11-23, 1961-05-25 (Released:2017-05-19)