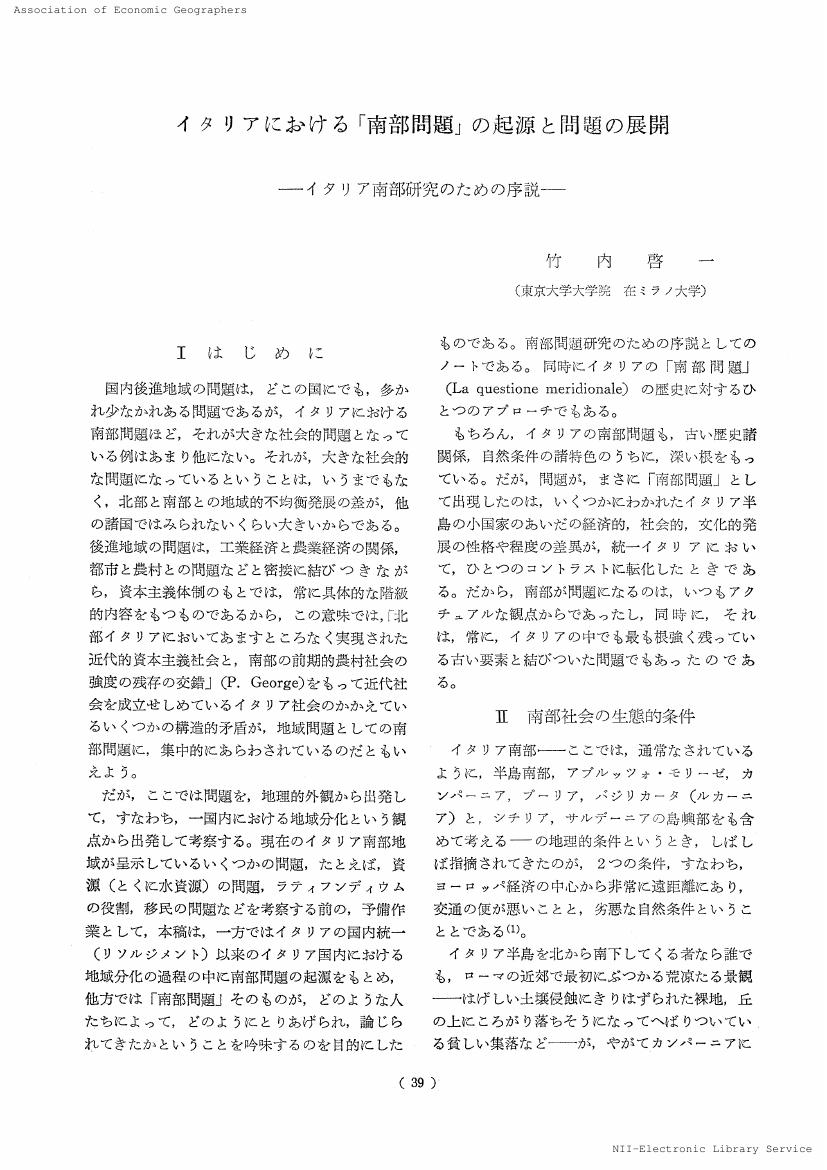2 0 0 0 OA イタリアにおける「南部問題」の起源と問題の展開 : イタリア南部研究のための序説
- 著者
- 竹内 啓一
- 出版者
- 経済地理学会
- 雑誌
- 経済地理学年報 (ISSN:00045683)
- 巻号頁・発行日
- vol.7, pp.39-55, 1961-05-25 (Released:2017-05-19)
- 被引用文献数
- 1
2 0 0 0 OA インバウンドの拡大と地方公共団体の情報発信
- 著者
- 亀山 嘉大 侯 鵬娜
- 出版者
- The Japan Association of Economic Geography
- 雑誌
- 経済地理学年報 (ISSN:00045683)
- 巻号頁・発行日
- vol.62, no.3, pp.191-209, 2016-09-30 (Released:2017-09-30)
- 参考文献数
- 31
- 被引用文献数
- 4
本稿は,中四国・九州地域の地方公共団体( 16県5政令指定都市) の調査をもとに,地方公共団体の情報発信を端緒としたシティプロモーションがインバウンドとどのような関係にあるのかを探り,その意義を地域の視点から議論したものである. 観光の情報発信は,シティプロモーションという(地域にとって) 公共財・サービスになるので,市場の失敗による過小供給の抑制のために,地方公共団体が役割を担うことは合理的である.また,観光の情報発信は,旅行者の購買プロセスと関連付けて理解できる. これらをもとに,地方公共団体の情報発信を端緒としたシティプロモーションをPhase a) 発地における交流や経験を介した着地側の情報発信,Phase b) インターネット媒体を介した着地側の情報発信,Phase c) 着地における交流や経験を介した着地側の情報発信,Phase d) 従来型の国際交流事業に基づく着地側の情報発信の4局面に分類した上で,SWOT分析によって調査結果を整理した.地方公共団体の施策は,Phase a) やPhase d) で違いがあり,SWOT分析の内部環境の強みであるPhase a) で海外事務所を展開したり,職員を海外の地方政府へ派遣したりし,さらに,SWOT分析の外部環境の機会であるPhase d) で20~30年に及ぶ国際交流を展開している.地方公共団体の情報発信を端緒としたシティプロモーションは,旅行先の魅力を高め,旅行先の言語の障壁や安全安心といった心理的な障壁を低減(軽減) し,サーチコストをともなう旅行者の手間隙の軽減を通じて,輸送費を低減させ,インバウンドの誘致に影響を与えているものと考えられる.
2 0 0 0 OA 「資源論」の新構想へ向けての課題 : 書評に代えての覚え書(フォーラム)
- 著者
- 石井 素介
- 出版者
- 経済地理学会
- 雑誌
- 経済地理学年報 (ISSN:00045683)
- 巻号頁・発行日
- vol.60, no.1, pp.37-46, 2014-03-30 (Released:2017-05-19)
- 被引用文献数
- 2
「資源」概念の多義・曖昧性をそのままにしての乱用状態に警告を発し,資源問題をめぐる討議に論理的整序のための立脚点をもたらす意味で,敗戦直後期の日本政府内に置かれていた資源委員会(調査会)における「資源」概念の醸成・確立過程を跡付けて再評価すると共に,基礎情報学分野における「情報」概念の検証状況,ならびに筆者自身の病床体験を参考としつつ,「生命体が自然物の中に認知し付与した有用性の意味作用(significance)」のことを「生命体資源」と呼んで,これを資源概念の諸次元の中の基本的原点をなすものと規定する.この基本をなす資源論視角から,その後時代と共に派生してきた異次元の資源論である「政治経済資源」や「地域社会資源」等の各資源論視角について,関係技術面の役割の問題を含めて,生命体資源という原点視角に照らしての若干の再検討課題を提起するものである.
- 著者
- 梶原 健嗣
- 出版者
- 経済地理学会
- 雑誌
- 経済地理学年報 (ISSN:00045683)
- 巻号頁・発行日
- vol.64, no.2, pp.113-120, 2018
<p> 日本の治水計画は,河川整備基本方針で長期的なグランドデザインを定め,河川整備計画で,今後20~30年間の具体的な計画を定める.この中で,核となるのは治水計画の想定洪水=基本高水とそのピーク流量(基本高水流量)である. <BR> この基本高水流量の決定に際し,決定的な影響力を持っているのが貯留関数法という「治水の科学」である.しかし,その算定では過大な流量が導き出される恐れがある.あるいは,治水計画に事業計画が対応せず,「半永久的に未完の治水計画」になる場合もある. <BR> では,そうした河川で水害が起きた際に,河川の管理瑕疵は問われるのか.水害訴訟は,本来は,被害者救済とともに行政の瑕疵・責任を検証しうる制度として期待されたはずである.しかし,初の最高裁判断となった大東水害訴訟判決により,この期待は機能不全となってしまっている.大東基準として確立した法理に照らせば,「過大な基本高水」の下では,河川管理責任はブラックボックス化しかねないのである.</p>
2 0 0 0 OA 大都市圏経済と経済格差 : 研究課題と政策課題(<特集>地域格差の経済地理学)
- 著者
- 長尾 謙吉
- 出版者
- 経済地理学会
- 雑誌
- 経済地理学年報 (ISSN:00045683)
- 巻号頁・発行日
- vol.59, no.1, pp.44-56, 2013-03-30 (Released:2017-05-19)
- 被引用文献数
- 3
本稿では,大都市圏の経済活動と経済格差について,6つの論点から研究課題と政策課題を整理し研究動向を踏まえつつ批判的検討を加えた.第1は,格差,不平等,貧困という概念の整理と研究意義についてであり,貧困のみを重視せず格差研究との両輪が必要であることを主張した.第2は,社会的格差と空間的視角についてであり,反映論的な都市・地域研究の問題点を指摘し,弁証法的な観点を取り込む重要性を述べた.第3は,大都市圏の社会的分極化をめぐり,日本の大都市圏についても分極化の観点だけでなく専門職化など多面的な接近が必要なことを論じた.第4は,就業,所得,消費の大都市圏内における格差についてであり,包括的指標として所得の重要性は認めつつも,就業,所得,再分配,消費という経済循環の諸側面をより意識する必要性を述べた.また,アメリカ合衆国のように社会的かつ地理的な分極化あるいは分断化が進むのか展望した.第5に,所得格差と資産格差との関わりを取り上げた.日本において分極化が明瞭でないのはなぜか,資産の側面から問題を提起した.第6は,経済格差との関わりからみた大都市圏経済の再編の方向性について展望した.
2 0 0 0 OA 大企業の本社からみた日本の主要都市
- 著者
- 阿部 和俊
- 出版者
- The Japan Association of Economic Geography
- 雑誌
- 経済地理学年報 (ISSN:00045683)
- 巻号頁・発行日
- vol.63, no.4, pp.335-342, 2017-12-30 (Released:2018-12-30)
- 参考文献数
- 6
- 被引用文献数
- 1
本論は大企業の本社を指標として日本の主要都市を検討し,とくに大阪について焦点をあてるものである.上場企業を大企業とみなして, 登記上の本社数をみると1950~2015年の間,東京の本社数比率は40~50%を占め,大阪は14~15%である.しかし,2010年と2015年では,東京の比率は43.9%であるのに対して,大阪の比率は2010年では12.6%,2015 年では11.8%にまで低下した.複数本社制に注目し,第2本社の方を実質的な本社と考えると2015年では,東京の本社数比率は全企業の50.7%にまで上昇し,大阪は9.8%にまで低下する.さらに本社数に従業者数でウエイトをかけると大阪の値は1960年では東京の54.4%だったが,2015年では9.1%にまで低下する.
2 0 0 0 福島県商業まちづくりと東日本大震災
- 著者
- 山川 充夫
- 出版者
- 経済地理学会
- 雑誌
- 経済地理学年報 (ISSN:00045683)
- 巻号頁・発行日
- vol.62, no.2, pp.130-140, 2016
<p> 福島県商業まちづくり条例は,売場面積6,000 m<sup>2 </sup>以上をもつ大規模小売店舗を「特定」し,その新設立地に関しては郊外での抑制と中心市街地への誘導を行うという土地利用の視点からコンパクトなまちづくりを推進することを目的として,2006年に制定された.この条例は翌年の改正まちづくり三法の制定に大きな影響を与えただけでなく,地方の道県に対して同種の条例あるいはガイドラインの制定を促進した.そして福島県条例は,実際に郊外における特定大型店の新規立地を抑制し,消費者買物行動が郊外から中心商業地に転換する効果を発揮してきている.<BR> 2011年3月,東日本大震災と原子力災害が岩手県・宮城県・福島県の太平洋沿岸地域を襲った.被災地では被災者や避難者の日常生活を支えることを大義とし,商業拠点形成が居住地再編の要として位置付けられ,国の圧倒的な支援を受けて,復興が進められている.しかしそこではコンパクトなまちづくりが謳われているが,その実態は大型店を中核とする市街地整備が進められ,従前の商店街とは異なった商業集積が再生されつつある.特にいわき市小名浜地区では津波被害を契機とし,港湾地区の土地利用の変更をしてまで,巨大なショッピングセンターが誘致されることになっており,ショック・ドクトリンのもとで県条例は空洞化の危機に直面している.</p>
2 0 0 0 OA 食品のローカル性と産地振興 : 虚構としての牛肉の地域ブランド(<特集>食と地域振興)
- 著者
- 高柳 長直
- 出版者
- 経済地理学会
- 雑誌
- 経済地理学年報 (ISSN:00045683)
- 巻号頁・発行日
- vol.53, no.1, pp.61-77, 2007-03-30 (Released:2017-05-19)
- 被引用文献数
- 4
近年,地域ブランドが社会的に着目されている.とりわけ,農産物や食品では,ブランドの呼称に地名を利用し,産地を強調するものが多数みられるようになった.本稿では,牛肉を事例として,農産物や食品に込められるローカル性の意味について考察するとともに,地域ブランドを利用して産地振興を図る際の方向性について議論を行った.地域性をアピールした牛肉が市場で大量に流通するようになったが,牛の品種・血統や飼料の地域的差異は縮小し,牛肉の品質は均一化しつつある.そもそも,繁殖と肥育が地域分業で営まれ,市場で流通している地域ブランド牛肉には,産地内で生まれたものと産地外で生まれたものとが混在している.また,ブランドは必ずしも品質を保証しておらず,呼称の混乱もみられるほどである.したがって,牛肉の商品自体に付随するローカル性は縮小し,「地域」ブランドは虚構であるといわざるを得ない.牛肉産地における振興の方向性としては,3つのことがあげられる.第1に,ローカル性の喪失には目をつむり,地域ブランドの示す空間範囲を拡大することである.弱小ブランドの産地としては,既存のフードシステムで競争する限り,流通量を増やして,少しでも認知度を高める必要がある.第2に,ローカル性を徹底的に追求していくことである.希少性のある品種を飼養したり,飼料や飼育方法などで,他産地との差別化を図っていく.第3に,牛肉のローカル性が虚構であることを,利用していくということである.現代の日本では,食品の可食部分だけを消費しているのではなく,むしろ食品に付随する情報を消費している.食品に物語性を付加することで,消費者の需要喚起を図っていく戦略が考えられる.
2 0 0 0 OA 日本勤労者住宅協会と地域住宅生協による住宅供給のシステムとその展開
- 著者
- 長谷川 達也
- 出版者
- 経済地理学会
- 雑誌
- 経済地理学年報 (ISSN:00045683)
- 巻号頁・発行日
- vol.48, no.3, pp.238-252, 2002 (Released:2017-05-19)
- 被引用文献数
- 1
本稿では,日本勤労者住宅協会(勤住協)と地域住宅生協の設立過程,住宅供給および住宅地開発の展開とその特徴を全国,地域レベルから明らかにした.1961年のILO勧告を受け,労働者住宅自主建設運動は協同組合によるサード・アーム方式による住宅供給主体の確立を目指したが,結局特殊法人である勤住協が公的機関として設立されるにとどまったことで,勤住協と地域住宅生協という異なった組織形態が併存したなか,住宅供給が行われることになった.動注協による住宅供給システムは,住宅金融公庫をはじめとする融資を得て地域住宅生協等に住宅地開発を委託するもので,これまで全国各地に100,000戸を超える住宅を供給した。近年,勤住協による住宅供給は減少傾向にあり,地域住宅生協等でもその経営体力の格差が拡大しつつある.大阪労働者住宅生活協同組合を事例とした,地域住宅生協による住宅地開発の特徴は,生協が独自に資金を調達した事業が少なく,ほとんどが勤住協の委託事業であり,また小規模開発で供給量も少ないことがあげられる.地域住宅生協による住宅供給システムは,一般公募が原則となる勤住協事業が大半をしめることから,協同組合としての機能が発揮できないこと,住宅購入時に加入した組合員の継続性の問題などを抱えている.1990年代以降本格化した特殊法人見直しにおいて,勤住協は住宅供給主体としての在り方について議論されてきたが,2001年12月に民営化が決定したことで,今後新たな方向性が模索されていくことになる.
- 著者
- 半澤 誠司
- 出版者
- 経済地理学会
- 雑誌
- 経済地理学年報 (ISSN:00045683)
- 巻号頁・発行日
- vol.47, no.4, pp.56-70, 2001-12-31 (Released:2017-05-19)
- 被引用文献数
- 3
本稿の目的は, 日本のアニメーション産業の特性を把握し, その集積要因を検討することにある.アニメーション産業は, 知識集約的な特徴を持つ, いわゆるコンテンツ産業の一つとみなされることが多いが, 実際の制作工程をみるとむしろ労働集約的な製造業としての側面が強い.作品周期が短く市場予測が難しい上に, 短期間での制作が求められるテレビシリーズアニメーションの開始によって, 1960年代に制作会社の垂直分割が進展し, 各工程に特化した中小零細企業が多数乱立するようになった.この結果として, 各制作会社間の物流と情報交換の利便性を図るために, 産業集積が生まれた.受発注関係はほとんどが東京都内で完結し, その取引内容は工程間で特色の違いがみられる.すなわち, 上位工程に位置する制作会社はさまざまな工程を持ち, 多くの企業から受注を受け, 外注比率も高いのに対し, 下位工程に位置する制作会社は一部工程に専門化し, 受注先が少なく, 外注比率が低い.1990年代におけるグローバル化の進展とデジタル化によって, 分散傾向も一部ではみられるが, アニメーション産業では取引先の能力把握と信頼性の構築が重視され, 人的繋がりから仕事が生じている面が強いので, それを生み出す場としての東京の重要性は大きくは変わらないと考えられる.
2 0 0 0 OA 明治期〜第二次大戦前における金融網の地域的展開過程 : 「五大銀行」を中心として
- 著者
- 吉津 直樹
- 出版者
- 経済地理学会
- 雑誌
- 経済地理学年報 (ISSN:00045683)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, no.2, pp.57-77, 1980-09-25 (Released:2017-05-19)
- 被引用文献数
- 1
2 0 0 0 神奈川県中西部における余暇活動の空間的展開
- 著者
- 落合 康浩
- 出版者
- 経済地理学会
- 雑誌
- 経済地理学年報 (ISSN:00045683)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, no.3, pp.245-265, 1991-09-30
- 被引用文献数
- 4
余暇活動は, 生活時間の中における重要性と活動の多様性から, 行動地理学において人間の行動空間を分析するためには有効な指標と考えられるが, その研究事例は少ない. そこで本稿では, 神奈川県中西部の三地区において実施したアンケート調査の結果をもとに, 住民の余暇活動空間の拡がりとその構造を考察した. 移動をともなって行われる余暇活動は, 活動に要する時間によって, 「平日型」「週末型」「期末型」の3タイプに分類される. 平日型余暇活動は, 活動に費やされる時間が短く, 移動時間も極力短縮される. したがって, その対象地は, 日常生活の空間である居住地もしくは勤務地の周辺に選択される. 対象地の選択される空間の拡がりは活動種目によって異なるほか, 活動者の属性に影響され, 女性よりも男性の, また自営業者よりも通勤者の活動空間が広くなる. 週末型余暇活動は日帰りで行われる活動で, 対象地には恒常的に選択されるものと, 恒常的には選択されることのないものとがある. 恒常的に選択される対象地は居住地から30〜40分以内の空間に拡がり, 非恒常的な対象地は, 日帰りの限界である居住地から3時間までの空間の中に選択される. また, 恒常的に選択される対象地は郊外よりも都市内部での活動に多く, 主として居住地を通る主要な鉄道沿いに選択され, 東京・横浜方面により多く選択される. 非恒常的な対象地は, 東京・横浜から居住地の方向に拡がる空間により多く選択される傾向にある. 活動者の居住地が異なることによって, 対象地の選択パターンには差異が認められ, 対象地の選択される空間の拡がりには活動者の職業・勤務地が影響する. 期末型余暇活動は, 活動種目では週末型に類似するが, 宿泊をともなう活動のため費やされる時間が長く, その対象地が選択される空間は週末型余暇活動の空間をこえて拡がる.
- 著者
- 中村 剛治郎
- 出版者
- 経済地理学会
- 雑誌
- 経済地理学年報 (ISSN:00045683)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, no.4, pp.275-298, 2012-12-30 (Released:2017-05-19)
- 被引用文献数
- 1
現代においては,既存の経済活動を維持することが難しくなり,経済発展を牽引する革新的な経済活動を創出すること,そのための制度的な環境を準備することが重要になっている.結果としての経済地理を描くだけでなく,経済発展のための制度的環境を創り出して,経済と地理の新しい結びつきを生みだすことが,経済地理研究の現代的課題になっている.筆者は,経済と地理の間に,経済発展のための制度的環境としての地域(地域社会・文化・政治・環境・経済)という概念を入れて,地域における諸アクターの関係性の蓄積が作りだす地域の制度や制度的構造が経済発展にどのような影響を与えるか,それらを部分的に変えようとする制度的設計,地域的制度的仕掛けが新たな経済発展の経路を拓けるかを検討する方法が必要と考える.筆者は地域政治経済学的アプローチを,主体重視の発展論的で動態的な比較地域制度アプローチとして展開しつつある.本稿は,この視点から,筆者のこれまでの事例研究のうちのいくつかを整理し直して紹介し,現代の経済地理あるいは地域経済の抱える構造的問題と政策研究の課題を明らかにしようとするものである.はじめに,筆者の動態的比較地域制度アプローチに言及した上で,内発的発展という地域の論理をもちえずに外発的成長の国民的論理に翻弄された山間地域,地域の論理をもちながら国民的論理に組み込まれた大都市地域,国民的制度構造のもとで独自の内発的発展をしてきた地方都市,東京一極集中の問題性,外発的成長から内発的知識経済に変わった米国の都市,辺境の分工場経済から内発的知識経済に発展した北欧の都市を取り上げ,最後に震災復興の地域産業政策に言及する.
2 0 0 0 福岡県黒木町における共同製茶の変容
- 著者
- 片岡 義晴
- 出版者
- 経済地理学会
- 雑誌
- 経済地理学年報 (ISSN:00045683)
- 巻号頁・発行日
- vol.39, no.4, pp.297-317, 1993-12-31
本稿は, 高級茶とされる玉露の主産地構造の変容を, 福岡県黒木町の集落共同製茶を事例として, そこで顕在化している問題点の検討によって明らかにすることを目的とする. 1970年代後半以降, 茶価格が低迷する中で, これまで形成されてきた主産地は変容をせまられ, 茶生産農家の対応は分化し, 同時にこれまでの主産地化を一方で支えてきた共同製茶も変化せざるをえなくなっている. まず第1に, これまで玉露生産の基盤となってきた摘採労働力が不足し, 農家はせん茶生産に移行せざるをえなくなっている. しかしせん茶拡大にはある程度の面積規模が必要とされるが, 山間地に位置する同町では規模拡大が可能な農家と, 不可能な農家が生まれ, さらに茶価格の低迷によって農家経営は分化している. そのタイプは, 茶拡大型, 他作目移行型, 停滞型, 兼業依存強化型, 老齢化衰退型に分類できる. 第2に, こうした分化が, せん茶生産移行と機械摘採の一般化, 茶樹品種の統一化などとあいまって, 加工期間の短期化と大量化をもたらし, これまで玉露加工を前提とした共同製茶工場設備との矛盾を生み, 分化しつつある農家間の利害対立は激化している. こうした中で小規模農家の一部は農業部門維持をあきらめ共同製茶から脱退し, また茶拡大農家の一部も生産拡大をより確実にするため, 集落の農家により構成される共同製茶から脱退し, 従来の集落共同製茶は分解していった. 第3に, しかし加工労働力不足とその高齢化によって, 残存農家による共同製茶維持も困難になりつつある. とはいえ, 茶拡大型農家にとっても茶専業で農業経営可能な面積規模はなく, 大半の農家にとっては, 共同製茶工場は農家経営上欠くことのできない存在である. こうした分化した農家が共同製茶を必要とすればするほど, 共同製茶工場の矛盾はそれだけ大きくならざるをえなくなっている.
2 0 0 0 OA ハーヴェイ著 : 地理学における説明
- 著者
- 杉浦 芳夫
- 出版者
- 経済地理学会
- 雑誌
- 経済地理学年報 (ISSN:00045683)
- 巻号頁・発行日
- vol.19, no.2, pp.100-103, 1974-01-25 (Released:2017-05-19)
2 0 0 0 OA 電気機械工場の地方分散と地域的生産体系 : 宮城県・熊本県の実態調査事例の分析を中心に
- 著者
- 山口 不二雄
- 出版者
- 経済地理学会
- 雑誌
- 経済地理学年報 (ISSN:00045683)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, no.1, pp.38-59, 1982-03-31 (Released:2017-05-19)
- 被引用文献数
- 4
2 0 0 0 コンビニエンス・チェーンの発展と全国的普及過程に関する一考察
- 著者
- 土屋 純
- 出版者
- 経済地理学会
- 雑誌
- 経済地理学年報 (ISSN:00045683)
- 巻号頁・発行日
- vol.46, no.1, pp.22-42, 2000-03-31
- 被引用文献数
- 6
近年, コンビニエンス・ストア(以下, CVSと略)は, 物販だけでなく様々なサービスを供給する代理店として各方面の業界から注目されている.このような注目を受けるのは, CVSが全国的に広がり, かつ消費者に近接して分布しており, さらに情報・配送システムによってネットワーク化されているからである.しかし, CVSの地位的展開を考察した従来の研究は, ミクロスケールで行われたものが中心であり, 全国スケールで検討したものは少ない.そこで本研究では, CVSチェーンの全国展開パターンを検討し, CVSチェーンの発展とCVSの全国的普及過程との関わりについて考察した. 日本のCVS業界は上位集中化が進んでおり, 上位チェーンによる店舗展開がCVS全体の普及に大きく関わっている.よって本研究では, 出店戦略が特徴的な代表チェーン(セブンイレブン, ローソン, ファミリーマート, セイコーマート)を取り上げ, 全国展開のパターンについて検討した.その結果, 全国展開パターンとして, (1)大都市圏からの虫食い的展開, (2)拠点的展開, (3)エリアフランチャイズ方式, (4)特約店の支援の4つを指摘できた.しかし, これらのパターンには, 配送システムへの初期投資を円滑に回収する, あるいは運営コストを低レベルで押さえるという共通の要因が関わっており, ドミナントエリア(密度の高い店舗網)の形成という点で共通していた. このようなCVSチェーンによる全国展開によって, CVSの全国的分布には地域間, 都市階層間の偏在が形成されていることが明らかとなった.さらに, JITを前提としたルート配送が必要なことから, 都市遠隔山村, 半島部や離島へのCVS普及が進んでいないことも明らかとなった.
- 著者
- 小川 勇樹
- 出版者
- 経済地理学会
- 雑誌
- 経済地理学年報 (ISSN:00045683)
- 巻号頁・発行日
- vol.61, no.1, pp.92-93, 2015-03-30 (Released:2017-05-19)
2 0 0 0 OA 戦後わが国における政策主導型みかん産地の崩壊とその要因 : 大分県東国東郡国東町を事例に
- 著者
- 川久保 篤志
- 出版者
- 経済地理学会
- 雑誌
- 経済地理学年報 (ISSN:00045683)
- 巻号頁・発行日
- vol.46, no.3, pp.246-265, 2000-09-30 (Released:2017-05-19)
第2次対戦後わが国のみかん農業は, 1961年の農業基本法の下で選択的拡大部門の1つに位置づけられ, 生産・流通面で多大な政策的補助を受けながら大きく発展した.この結果, 特に九州地方では政策主導型の新興みかん産地が数多く形成されたが, これらの多くは1972年以降のみかん価格低迷下で激化した産地間競争で敗退し, 産地は縮小・崩壊の傾向にある.そこで本稿では, パイロット事業の実施によって大産地が形成された大分県国東町を事例に政策主導型産地の崩壊要因の分析を試みた.その結果, パイロット事業の実施経過の分析からは, (1)事業の着工が1969年と価格低迷期の直前であったため, 事業参加農家がみかん農業の高収益期を経験できなかったこと, (2)造成面積482haもの大規模な事業に見合うだけのニーズが地元農家になかったにもかかわらず事業が推進されたこと, (3)造成農地には土壌・地形・日照の面で栽培に不適な部分が多く含まれていたこと, の3点が明らかとなった.また, みかん栽培の中心集落における農家経営の分析からは, (1)みかん栽培の歴史が浅く, 先祖から伝わる独自の栽培技術等がなかったため, 産地間競争の激化に際して, 品質の向上に基づく高価格販売も土地生産性の向上によるコストダウンも実現することができなかったこと, (2)後継者世代が他産業へ就業したため農業労働力が高齢化していき, みかん園の管理ができなくなったこと, (3)パイロット事業で購入した農地への執着心が弱く, 負債額もそれほど大きなものではなかったこと, の3点が明らかとなった.
2 0 0 0 外国人の生活空間行動 : 東京大都市地域の就学生
- 著者
- 清水 昌人
- 出版者
- 経済地理学会
- 雑誌
- 経済地理学年報 (ISSN:00045683)
- 巻号頁・発行日
- vol.43, no.1, pp.59-71, 1997-03-31
- 被引用文献数
- 2
本稿では, 近年注目されている来日外国人の居住の問題を, 生活空間の観点から把握するため, 外国人就学生の日常行動についてその空間的側面を検討した. アンケート調査の結果から, 以下の点が明らかになった. (1)彼らの主要活動場所である学校・アルバイト先・住居は, 平均して各々30分程度の時間距離にある. これらの位置関係は彼らの日常生活の時間配分・空間行動を規定する. (2)住居周辺で過ごす時間が長くても, 居住地域に対する積極的な関心が生まれるとは限らない. (3)彼らの交遊関係は, その主要な部分が学校の友人との付き合いで占められる. (4)友人関係が住居周辺で形成される場合でも, そのことが地域に対する興味・関心に結びつくわけではない. また「セグリゲーション」の状態について予察を行い, 中国籍者と韓国籍者では活動空間が異なること, 中国籍者が社会関係の面で日本人からより「凝離」しているのは時空間収支が不利なためであること, などの可能性を示唆した.