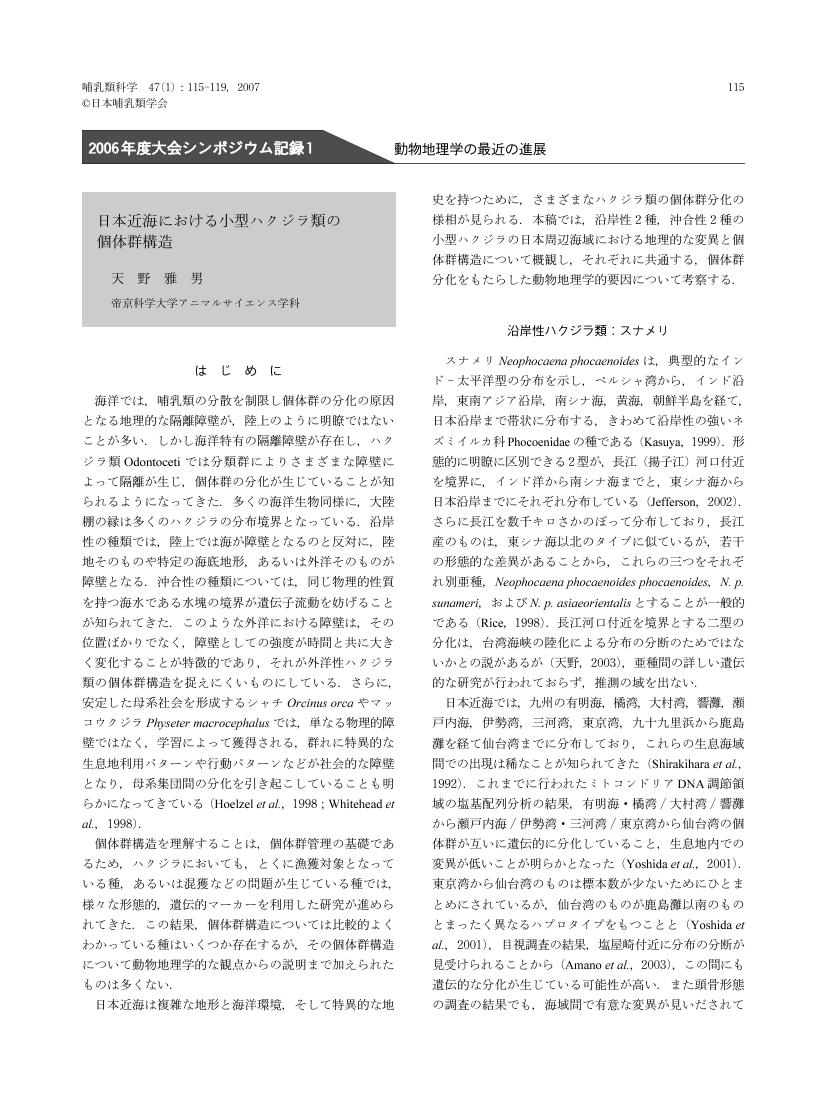1 0 0 0 OA 山梨県東部のテンの食性の季節変化と占有率-順位曲線による表現の試み
- 著者
- 箕輪 篤志 下岡 ゆき子 高槻 成紀
- 出版者
- 日本哺乳類学会
- 雑誌
- 哺乳類科学 (ISSN:0385437X)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, no.1, pp.1-8, 2017 (Released:2017-07-11)
- 参考文献数
- 21
- 被引用文献数
- 4
山梨県東部の上野原市郊外に生息するホンドテンMartes melampus melampus(以下,テン)の食性は明瞭な季節変化を示した.平均占有率は,春には哺乳類33.0%,昆虫類29.1%で,動物質が全体の60%以上を占めた.夏には昆虫類が占める割合に大きな変化はなかったが,哺乳類は4.7%に減少した.一方,植物質は増加し,ヤマグワMorus australis,コウゾBroussonetia kazinoki,サクラ類(Cerdus属とPadus属を含む)などの果実・種子が全体の58.8%を占めた.秋にはこの傾向がさらに強まり,ミズキCornus controversa,クマノミズキCornus macrophylla,ムクノキAphananthe aspera,エノキCeltis sinensis,アケビ属Akebiaなどの果実(46.4%),種子(34.1%)が全体の80.5%を占めた.冬も果実・種子は重要であった(合計67.6%).これらのことから,上野原市のテンの食性は,果実を中心とし,春には哺乳類,夏には昆虫類も食べるという一般的なテンの食性の季節変化を示すことが確認された.ただし,以下のような点は本調査地に特徴的であった;1)春に葉と昆虫類も利用すること,2)秋に甲殻類も利用すること,3)秋に利用する果実の中に,他の多くの調査地でよくテンが利用するサルナシActinidia argutaがほとんど検出されないこと.占有率-順位曲線は,ある食物品目の糞ごとの占有率を上位から下位に配する.これにより,同じ平均値であっても一部の占有率が大きくて他が小さいか,全体に平均値に近い値をとったかなどの内容を表現することができる.今回の結果をこれで表現すると,1)夏,秋,冬の果実・種子のように多くの試料が高い値をとって低順位になると急に減少する,多くのテン個体にとって重要度の高い食物品目,2)春の哺乳類や春,夏の昆虫類のように直線的に減少する,占有率に偏りのない食物品目,3)春の支持組織や果実・種子,秋の甲殻類や昆虫類,冬の昆虫類や葉のように,一部の試料だけが高い値をとり,多くの試料は低い値になる食物品目の3パターンがあることが示された.これには食物の供給状態やテンの選択性などが関連することを議論した.
1 0 0 0 胃内容物からみた北アルプス南部産ニホンカモシカの食性
- 著者
- 宮尾 嶽雄
- 出版者
- 日本哺乳類学会
- 雑誌
- 哺乳動物学雑誌: The Journal of the Mammalogical Society of Japan (ISSN:05460670)
- 巻号頁・発行日
- vol.6, no.5, pp.199-209, 1976
- 被引用文献数
- 1
1967年5月より1975年5月までの間に, 中央アルプス (木曽山脈) および北アルプス南部で発見されたニホンカモシカ12頭の死体について, その胃内容物から食植物の種類を同定した。発見地点の海抜高度は1, 100~2, 000m, 死亡時期は秋 (10・11月) , 積雪期 (2~4月) , 早春 (3~5月) にわたっている。<BR>12個体の剖検例から, 胃内に発見された食植物は, 常緑針葉樹2科7種, 落葉広葉樹6科6種, 常緑広葉樹1科4種, 草本7科9種の総計16科26種になる (Table 1) 。これらを死亡時の季節別にみるとTable2およびTable3の如くになる。秋には9種で広葉樹が多く, 針葉樹は1種にすぎない。積雪期には8種の植物が食べられているが, 針葉樹が圧倒的に多い。早春になると食植物の種類は急増して18種となり, 草本の食べられる割合が多くなる。<BR>参考までに, 夏期に食痕によって確認されたニホンカモシカの食植物はTable4およびTable5の如く, 種類数はひじょうに多く, しかも草本が主な食物になることがわかる。<BR>すなわち, ニホンカモシカの食物としては, 秋に常緑広葉樹, 積雪期に針葉樹, 春から夏には草本が重要なものとなる。これを要するに, ニホンカモシカは, 新鮮な緑葉を求める動物なのである。<BR>したがって, ニホンカモシカの食生活は, 積雪期にきわめて厳しいものとなる。そのため, 山地森林の広域皆伐は, ニホンカモシカの生活を成り立たなくさせ, その結果, ヒノキなどの植林地に, ニホンカモシカによる食害が発生する。植林地への食害は, 環境破壊に対するニホンカモシカの無言の抗議行動であり, それはまた, 人間の生息環境悪化に対する警告でもある点を認識しなければならない。<BR>合成樹脂製品の断片2点が胃内にみられた1例もある。ニホンカモシカの死体は, ツキノワグマによって食い荒らされていることが多い。
1 0 0 0 OA フェロモンと繁殖
- 著者
- 林 進
- 出版者
- 日本哺乳類学会
- 雑誌
- 哺乳類科学 (ISSN:0385437X)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, no.1, pp.1_11-16, 1986 (Released:2008-10-01)
1 0 0 0 OA 日本モンキーセンター研究部とりつぶし事件の背景
- 著者
- 水原 洋城
- 出版者
- 日本哺乳類学会
- 雑誌
- 哺乳類科学 (ISSN:0385437X)
- 巻号頁・発行日
- vol.16, no.1, pp.1_79-82, 1976 (Released:2008-12-17)
1 0 0 0 エゾヤチネズミの個体群動態解析
- 著者
- 藤巻 裕蔵
- 出版者
- 日本哺乳類学会
- 雑誌
- 哺乳類科学 (ISSN:0385437X)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, no.2, pp.33-42, 1975
1 0 0 0 ネズミ類の消化器系の進化(I)
- 著者
- エヌ・エヌ・ヴオロンツオフ著 藤巻裕蔵·畑礼子訳
- 出版者
- 日本哺乳類学会
- 雑誌
- 哺乳類科学 (ISSN:0385437X)
- 巻号頁・発行日
- vol.12, no.1, pp.54-63, 1972
- 著者
- G.Fプロムレイ著 藤巻裕蔵·新妻昭夫訳
- 出版者
- 日本哺乳類学会
- 雑誌
- 哺乳類科学 (ISSN:0385437X)
- 巻号頁・発行日
- vol.12, no.2, pp.45-46, 1972
1 0 0 0 ヒメネズミの齢査定と成長
- 著者
- 藤巻 裕蔵
- 出版者
- 日本哺乳類学会
- 雑誌
- 哺乳類科学 (ISSN:0385437X)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, no.1, pp.26-29, 1977
1 0 0 0 ヒメネズミの繁殖活動
- 著者
- 藤巻 裕蔵
- 出版者
- 日本哺乳類学会
- 雑誌
- 哺乳動物学雑誌: The Journal of the Mammalogical Society of Japan (ISSN:05460670)
- 巻号頁・発行日
- vol.4, no.3, pp.74-80, 1969
- 被引用文献数
- 1
1960年3刀から1961年11月まで札幌市藻岩山の天然林でヒメネズミを採集し, これらを臼歯の磨滅状態によって越冬個体と当年個体とにわけて, 繁殖活動の季節的変化を調べ次の結果を得た。<BR>1.繁殖期は, 1960年には4~9月, 1961年には3~8月であった。<BR>2.繁殖期間中越冬個体が主として繁殖する。当年個体のうち早く生まれ, 体重も越冬個体に近くなったようなものは繁殖活動を行なう。しかし繁殖能力は低く, 個体群の増大には重要な意義を持たない。
1 0 0 0 九州における2000年以降のクマ類の目撃事例
- 著者
- 栗原 智昭
- 出版者
- 日本哺乳類学会
- 雑誌
- 哺乳類科学 (ISSN:0385437X)
- 巻号頁・発行日
- vol.50, no.2, pp.187-193, 2010-12-30
- 参考文献数
- 25
九州のツキノワグマ<i>Ursus thibetanus</i>個体群は絶滅した可能性が高いという意見がある一方で,地元での目撃情報は少なくない.2000年5月から2010年4月の10年間に得られた目撃情報の中から,7つの判断基準に基づき信頼性が高いと判断されるものを抽出したところ,祖母山系宮崎県側での6件のべ8頭の目撃情報がこれに該当した.クマ類である可能性は,極めて高い3例,十分高い1例,高い2例であった.これらの証言のみから目撃された動物をツキノワグマと断定することはできないが,野生のクマ類の生息が強く示唆された.<br>
1 0 0 0 OA 日本近海における小型ハクジラ類の個体群構造
- 著者
- 天野 雅男
- 出版者
- 日本哺乳類学会
- 雑誌
- 哺乳類科学 (ISSN:0385437X)
- 巻号頁・発行日
- vol.47, no.1, pp.115-119, 2007 (Released:2007-08-21)
- 参考文献数
- 43
1 0 0 0 北海道網走郡大空町で確認されたヒメヒナコウモリの出産哺育コロニー
- 著者
- 近藤 憲久 福井 大 倉野 翔史 黒澤 春樹
- 出版者
- 日本哺乳類学会
- 雑誌
- 哺乳類科学 (ISSN:0385437X)
- 巻号頁・発行日
- vol.52, no.1, pp.63-70, 2012-06-30
- 参考文献数
- 36
- 被引用文献数
- 1
北海道網走郡大空町にある旧大成小学校体育館で,コウモリの出産哺育コロニーが発見された.本コロニーを形成する個体の捕獲を行い,外部形態を精査したところ,乳頭が2対あることからヒメヒナコウモリと同定した.また,8月以降にコロニー周辺で拾得された2個体のコウモリについても,外部並びに頭骨計測値からヒメヒナコウモリと同定した.5回にわたる捕獲調査の結果,本種は6月下旬~7月上旬に出産し,8月上旬には幼獣が飛翔を始めていた.本コロニーを形成する雌成獣は約60頭であった.8月以降は,成獣はほとんどいなくなり,幼獣が大部分(96%)を占めていた.飛翔時の音声構造は,FM-QCF型であり,ピーク周波数の平均値は26.1 kHzであったが,FM成分とQCF成分の比率は飛翔環境によって大きく変化していた.ヒメヒナコウモリのねぐらおよび出産哺育個体群は国内初記録であり,今回の発見により,本種の国内における繁殖・定着が明らかになった.<br>
<p>エチゴモグラ<i>Mogera etigo</i>は,新潟県の越後平野にのみ生息する日本固有種である.本種は,生息域が局所的であり,人為的な生息地改変や,競合種であるアズマモグラ<i>M. imaizumii</i>との種間競争の影響により,分布域の縮小が懸念されている.過去の研究において,エチゴモグラの主要分布域の一部であり,その分布変化の最前線と考えられてきた新潟市江南区および五泉市の2地域で,エチゴモグラの分布後退が懸念されているが,最近の分布状況は明らかではない.本研究では,モグラのトンネルサイズを計測することで,これら2地域におけるエチゴモグラとアズマモグラの分布状況の調査を行った.その結果,新潟市江南区では,アズマモグラのトンネルが新たに確認され,エチゴモグラと同所的に生息していることも明らかとなった.過去の分布状況と比較すると,同地区におけるエチゴモグラの分布域は縮小している可能性が示唆された.一方で五泉市ではアズマモグラが優占し,局地的に単独でエチゴモグラのトンネルがみられる区域と,2種が同所的に生息する区域が確認された.五泉市における2種の分布状況は,過去のものと比較して大きな変化はみられなかったが,今後の土地利用の変化によっては,局在化したエチゴモグラの生息地は消失することも懸念される.</p>
1 0 0 0 OA ニホンジカは音声で何を伝えているか?
- 著者
- 山中 正美
- 出版者
- 日本哺乳類学会
- 雑誌
- 哺乳類科学 (ISSN:0385437X)
- 巻号頁・発行日
- vol.35, no.1, pp.65-70, 1995 (Released:2008-07-30)
1 0 0 0 OA 第30回シンポジウム記録,「家畜化」概念はホミニゼーションにどこまで適応できるか
- 著者
- 江原 昭善
- 出版者
- 日本哺乳類学会
- 雑誌
- 哺乳類科学 (ISSN:0385437X)
- 巻号頁・発行日
- vol.27, no.1and2, pp.1and2_37-42, 1987 (Released:2008-10-01)
1 0 0 0 OA エゾヤチネズミの齢査定と成長
- 著者
- 阿部 永
- 出版者
- 日本哺乳類学会
- 雑誌
- 哺乳類科学 (ISSN:0385437X)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, no.1, pp.1_39-42, 1977 (Released:2008-12-17)
1 0 0 0 OA A malformed sperm whale with two nostrils
- 著者
- Masaki Yasuaki
- 出版者
- 日本哺乳類学会
- 雑誌
- 哺乳動物学雑誌: The Journal of the Mammalogical Society of Japan (ISSN:05460670)
- 巻号頁・発行日
- vol.4, no.4-6, pp.147-149, 1969-12-30 (Released:2015-05-19)
- 参考文献数
- 5
1 0 0 0 GPSテレメトリーの測位成功率及び測位精度の評価
- 著者
- 宇野 裕之 玉田 克巳 平川 浩文 赤松 里香
- 出版者
- 日本哺乳類学会
- 雑誌
- 哺乳類科学 (ISSN:0385437X)
- 巻号頁・発行日
- vol.42, no.2, pp.129-137, 2002-12-30
- 参考文献数
- 16
- 被引用文献数
- 3
2001年9月から12月に北海道東部地域において,2種類のGPS (Global Positioning System)首輪(テロニクス社:TGW-400/GPS/SOB 及びテレヴィルト社:G01-01011)の測位成功率及び測位精度の検証を行った.測位成功率の試験は4つの植生タイプ(落葉広葉樹林,針広混交林,針葉樹人工林,開放環境)及び3つの地形(谷,尾根,斜面)ごとに実施した.テロニクス社製の測位成功率は全ての環境下で97%以上であり,植生や地形の影響は受けなかった.テレヴィルト社製の成功率は83%以上であったが,林冠被度が高くなると成功率が低下した.測位精度試験の結果,誤差距離(accuracy)は,テロニクス社製を用いて4つ以上の衛星から電波を受けた場合(三次元座標)1.5~3.5m,テレヴィルト社製を用いた三次元座標の場合4.2m,3つの衛星から電波を受けた場合(二次元座標)15.6m であった.三次元座標の場合,全測位点の95%は半径30m の円内に入ることが判った.アカシカ(Cervus elaphus)を用いた飼育個体試験の結果,行動は測位成功率には影響しなかった.GPSテレメトリーは野生動物の季節移動や生息地利用を明らかにする上で有効な手法であると考えられた.