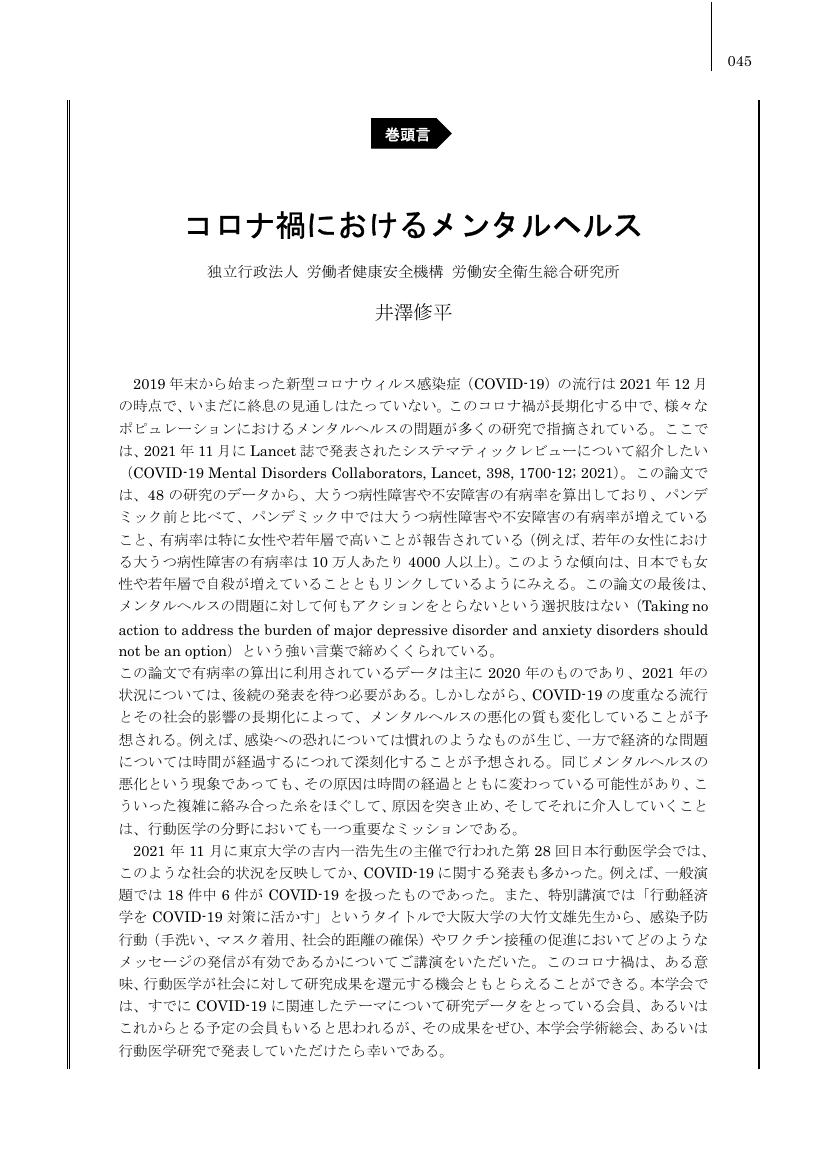48 0 0 0 OA 行動的QOL : 「行動的健康」へのプロアクティブな援助
- 著者
- 望月 昭
- 出版者
- 日本行動医学会
- 雑誌
- 行動医学研究 (ISSN:13416790)
- 巻号頁・発行日
- vol.7, no.1, pp.8-17, 2001 (Released:2014-07-03)
- 参考文献数
- 30
- 被引用文献数
- 3 9
重度の知的障害を持つ個人にみられる多くの行動的症状、例えば強度行動障害、の原因をたどると、それはしばしば当該の個人の障害性 (impairment) によるものではなく、個人と環境との相互作用によるものである場合がある。そのようなケースでは、問題行動のみに注目して対症療法的なリアクティブなトリートメントを行うのではなく、正の強化で維持される個人の行動の選択肢を拡大するプロアクティブなトリートメント (Foxx, 1996) が採用される必要がある。当論文では、筆者は「行動的QOL」という概念を提出する。それは、個人の生活の質を正の強化で維持される行動の選択に関する方法と量で測定するものである。行動的QOLは、個人の生活の質に関する2つの側面を同時に持つ。すなわち、環境的側面と個人的満足の側面である。他のQOLの測定においては、前者は環境の設定や配置の改善によって測定され、後者は一般的に個人に対する質問によって測定されてきたが、それらはそれぞれ別個に行われてきた。行動的QOLは、個人の行動によって測定され、そこでは個人は環境を自ら選び取り、またその満足度の度合いをその選ばれた環境との相互作用 (=行動) として示すものである。行動的QOLは、3つのレベルに分類することができる : 第一のものは、ある状況で、選択はできないが正の強化で維持される行動が個人に準備されているもの、第二のものは、個人にいくつかの選択肢が準備され、それを選択することができるというもの、そして第三のものは、個人が既存の選択肢を拒否して新しい選択肢を要求できるものである。この論文の後半では、重度の知的障害を持つ個人における「選択決定」の簡単なレビューと、筆者らのグループによる2つのケーススタディを紹介する。それはいずれも、何らかの問題行動を持つ個人に対する、選択決定を含んだプロアクティブなトリートメントを、行動QOLの拡大のミッションのもとで展開したものである。最初のケーススタディは、重度の知的障害を持つ個人において上記した行動的QOLの第三のレベルの確立が可能かを検証したものである (Nozaki& Mochizuki, 1995)。実験では、どのように、既存の選択肢に対する「NO」を表明する選択肢を設定することができ、またそうしたトリートメントが、対象者の行動問題、すなわち聴覚障害の兆候や極端な活動性の低さ、に対して効果を持つかが検討された。第二のケーススタディでは、殆ど行動の選択肢が与えらていなかった施設環境において、強度の行動障害を示す成人に対して行われたものである (望月ら、1999)。この第二の研究は、筆者らと施設職員との「共同相談モデル」(Ervin, et al., 1998) であり、(a) 職員間での行動的QOLの概念の共有化、(b) 施設の日常場面における、正の強化の機会の設定や選択場面の設定、という作業からなっている。これらの研究の結果、重度の障害を持つ個人でも行動の選択肢を選ぶことができること、そしてそうしたトリートメントを通じて問題行動が減じることが示された。行動的QOLは、個人の選択決定 (=自己決定) を中心としたヒューマンサービスの新たな哲学と方法論を必要とする。この考え方は、他者の決定を過不足なく援助するための学際的方法を含むものである。この作業に適したひとつのパラダイムは行動分析であろう。
15 0 0 0 OA 過敏性腸症候群における アレキシサイミア傾向の影響
- 著者
- 鹿野 理子
- 出版者
- 日本行動医学会
- 雑誌
- 行動医学研究 (ISSN:13416790)
- 巻号頁・発行日
- vol.22, no.2, pp.65-70, 2016 (Released:2017-06-23)
アレキシサイミア(失感情症)は、シフネオスが古典的心身症患者の臨床観察から、心身症患者にみられる性格特性として提唱した概念である。アレキシサイミア傾向者は、情動の認識や表現ができず、情動を介したコミュニケーションが不得手で、情動体験を言語などの象徴化機能を通じて表現できない。そのため、しばしば心理療法が成立せずに治療が難渋する。アレキシサイミアの問題は情動制御の困難さにあるとされ、心身症のみならず、様々な精神疾患、死亡率や心臓死率にも関連することが報告されたが、情動制御が身体症状に関連するメカニズムは十分に解明されてはいない。過敏性腸症候群は、器質的所見がないものの、便通異常に伴う腹痛を慢性的に示す症候群で、ストレスがその発症や症状の増悪に影響する。最もよく見られる典型的な心身症のひとつである。過敏性腸症候群においてもアレキシサイミア傾向との関連が報告されている。アレキシサイミアでは特に陰性感情を調整することができずに、陰性情動に伴う身体的過覚醒の状態、自律神経系、および神経内分泌反応が亢進し、それらが身体症状の発症、および増悪因子となると推測されている。これまでのアレキシサイミア研究では、疫学研究はアレキシサイミアと心身症を含む様々な疾患群との関連を示し、神経生理学的研究、および脳科学研究はアレキシサイミアの特徴をこの仮説を支持する形で提示している。しかしながら、特に多くの神経生理学的研究では臨床症状を呈さない健常者でのアレキシサイミア傾向が高いものを対象としており、情動が身体症状に影響するメカニズムを解明するにあたり、疾患群での検討が必要である。本総説では、これまでのアレキシサイミアと過敏性腸症候群の関連を検討した先行研究を総括し、自験例を示し、過敏性腸症候群の脳腸相関の病態へのアレキシサイミア傾向の影響を考察する。
7 0 0 0 OA 人はなぜ薬物依存症になるのか
- 著者
- 松本 俊彦
- 出版者
- 日本行動医学会
- 雑誌
- 行動医学研究 (ISSN:13416790)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, no.2, pp.94-99, 2020 (Released:2021-05-09)
7 0 0 0 OA QOL評価研究の歴史と展望
- 著者
- 下妻 晃二郎
- 出版者
- 日本行動医学会
- 雑誌
- 行動医学研究 (ISSN:13416790)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, no.1, pp.4-7, 2015 (Released:2015-04-16)
- 参考文献数
- 6
- 被引用文献数
- 9
QOL評価においては、QOLが複数の要素から構成される「多次元」的概念であることと、「主観」を評価・測定することに意義がある。QOL評価尺度は目的別に主に2種類ある。一つは健康状態を詳しく調べる「プロファイル型尺度」で、もう一つは、医療経済評価で使われる「価値付け型尺度」である。プロファイル型尺度で測定した結果は臨床現場へ、価値付け型尺度で測定した結果は社会における医療資源配分の指標として役立つ。PRO(Patient-Reported Outcome)という言葉が最近よく使われるようになってきたが、QOLとは概念や階層が若干異なり、それを理解することで両方を上手に併用・使い分けを行うことが大切である。QOL尺度開発の歴史は、まず1946年のWHO憲章の健康の定義から始まるが、その後1948年に開発されたKarnofskyのPerformance Status(KPS)では、まだ「主観」の測定が大事であるという考えはおそらくなかった。QOLという用語が一般に知られるようになったのは、米国では1970–80年代とされる。1990年代に入ると数多くのQOL測定尺度が主に欧米で開発された。2001年に日本では国際QOL研究学会が開催され、500名以上の研究者が参集したが、その後日本で質が高い議論ができる場が少なかったため、2011年にQOL/PRO研究会が設立された。QOL/PRO評価研究の課題としては、測定の信頼性の向上や得られたデータの臨床的解釈に関する方法論の確立、そして、特に価値付け型尺度が使われる医療経済評価の研究においては、倫理的・社会的課題の解決が重要事項である。信頼性と妥当性が高いQOL/PRO評価法の開発は、行動医学へも多くの貢献ができると期待される。
7 0 0 0 OA QOL評価研究と行動医学 —レスポンスシフトの視点から—
- 著者
- 鈴鴨 よしみ
- 出版者
- 日本行動医学会
- 雑誌
- 行動医学研究 (ISSN:13416790)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, no.1, pp.12-16, 2015 (Released:2015-04-16)
- 参考文献数
- 15
- 被引用文献数
- 1
医療のアウトカムとして患者のQOLを測定・評価することは、1980年代から様々な分野で実施されてきた。研究の進展に伴い評価における課題も浮き彫りになったが、その一つがレスポンスシフトである。レスポンスシフト(response shift)は患者が報告するアウトカム(Patient-reported outcomes: PRO)に特異的な現象である。自分の健康状態を自己評価する際に、我々は自己内部にある基準を参照して判断するが、この内部基準が変化する現象をレスポンスシフトと呼ぶ。レスポンスシフトは、内的基準の変化(recalibration)、価値の変化(reprioritization)、意味の変化(reconceptualization)の3つに分類される。治療介入効果の検証のために介入前後でPROを測定し比較することはしばしば行われるが、このような経時的比較は、同じものさしで測定すること(基準が変わらないこと)を前提としている。しかし、健康変化や介入によってこれまでに体験したことのない状態を体験すると、自己評価の基準が変わってしまうことがある。この現象が起きると、本人が良くなったと自己評価していたとしてもPROスコアには変化が現れない、またはその逆に、本人は変化していないと感じていてもスコアには差が現れるという現象が生じ、介入の効果が過大・過小評価されてしまう。そのため、レスポンスシフトを検出し考慮したうえで介入効果を評価する統計的手法が検討されてきた。一方、レスポンスシフトは、環境の変化への適応として捉えることもできる。慢性疾患や障害の存在にも関わらず利益や成長を見出すことは、負の影響を軽減するための認知的戦略である。この視点において、レスポンスシフトはバイアスや交絡因子というよりは、それ自体が重要な健康指標であり介入のゴールであると考えることができる。QOL評価研究で培われたレスポンスシフトの検出手法を、行動医学における心理的適応の検出・評価研究に適用することで、さらなる知見が得られる可能性がある。
6 0 0 0 OA 行動変容テクニックの標準化に関する国際的な動向について
- 著者
- 石川 善樹
- 出版者
- 日本行動医学会
- 雑誌
- 行動医学研究 (ISSN:13416790)
- 巻号頁・発行日
- vol.20, no.2, pp.41-46, 2014 (Released:2014-11-20)
- 参考文献数
- 20
- 被引用文献数
- 2
疫学研究などの成果により、健康に寄与する行動が明らかにされ、科学的知見の整理が進められてきた。また、行動科学や健康心理学などの観点から、それら健康行動の決定要因が特定され、これまで様々な行動モデルが提案されてきた。しかし、健康行動のメカニズム解明が進む一方、具体的にどのような介入を行えば実際に行動が変容するのかという点は、21世紀における医学・公衆衛生学上の課題として残されている。行動変容を狙いとした介入は、複雑ないくつもの要素から構成され、またそれら要素は互いに相互作用し合っている。それ故、介入の再現性や臨床現場での適用性、さらにはシステマティックレビューを通じた知見の統合を困難にしていることが指摘されている。CONSORT(Consolidated Standards of Reporting Trials: 臨床試験報告に関する統合基準)は、ランダム化比較試験(randomized controlled trial: RCT)の報告の質を改善することを狙いとした国際標準のガイドラインである。その中では、運動や食生活などの健康行動の改善を目的とした非薬理学的治療においても、介入プロセスや内容について詳細な報告を行うことが求められている。しかしながら、具体的にどのように介入プロセスや内容を記述すればよいのか、CONSORTで定められているガイドラインは存在しない。そこで近年、介入内容を客観的で、再現性があり、かつそれ以上還元のできない行動変容テクニックに分類する試みが国際的に行われている。その成果として、たとえば身体活動、食生活、禁煙、飲酒、性感染症予防分野などで、効果的な行動変容テクニックが特定され始めている。また2013年には、Annals of Behavioral Medicine誌上にて、国際的なコンセンサスのとられた93に及ぶ行動変容テクニックの分類表が公表されている。本稿では今後の医学教育における行動科学のカリキュラム作成における基礎資料の提供を狙いとし、どのような考え方・手法に基づいて行動変容テクニックの標準化が進められているのか、近年の国際的な動向を展望することを目的とする。
- 著者
- 宮崎 貴久子
- 出版者
- 日本行動医学会
- 雑誌
- 行動医学研究 (ISSN:13416790)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, no.1, pp.8-11, 2015 (Released:2015-04-16)
- 参考文献数
- 20
- 被引用文献数
- 1
QOL(Quality of life)は患者立脚型アウトカム(Patient reported outcome: PRO)の一つとして、患者から直接得られた、患者の主観による生活の質あるいは生命の質に関する評価である。1980年代以降、QOLを計量心理学的あるいは科学的に測る目的でさまざまな尺度(質問票)が開発された。それぞれの疾患特有の症状に着目した疾患特異尺度と、広く一般の人々から患者にまで共通した項目で測定する包括的尺度がある。それらは、集団を対象として計測され、結果は統計学的な分析を経てからはじめて結果が公表される。一方で、臨床的にQOL評価を活用したいという要望も生じ、それに対応すべく臨床における最小重要差の算定を目指したのが、MID(Minimally important difference)調査研究である。尺度は、対象となる集団のQOLを正確に測る物差しであることに加えて、測定結果の差の臨床的意味を説明し、治療方法の意思決定に資する情報を提供し、臨床行動に示唆を与えることまでが期待されるようになった。背景に、がんや生活習慣病、慢性疾患の増加により、治療成績や延命だけでなく、病気と共に生活していく患者のQOLを考慮した医療も必要とされるようになったことがある。QOLを考慮する必要性と共に、患者の健康に関する情報をいかに科学的に妥当性と信頼性を保ち計測するかという目的で、健康関連の質問票を作成する手順評価のためのチェックリスト(COnsensus-based Standards for the selection of health Measurement INstruments: COSMIN)が開発された。COSIMINチェックリストの項目には、妥当性・信頼性の検証とともに、得られた結果の説明力の一項目としてMIDが取り上げられている。尺度を開発する時点ですでに、尺度を用いた調査の臨床的な意味を考える必要が示唆されている。MIDの算定方法は、大きく、統計学的分布によるdistribution-based methodと、外部の基準とQOLスコアの差の関係性によるanchor-based methodの2つがある。それぞれの算定方法には特徴がある。より臨床的意味を問うには、悪化と改善の方向性で異なる算定値が提示されるanchor-based methodであると言われている。MIDは臨床におけるQOL評価の活用に有用ではあるが、検討課題もあることに留意したい。特に、調査の状況設定については注意が必要である。また、統計学的観点からは、個人間での変化量が、そのまま群間での変化量としてよいのかという課題が提示されている。患者のQOL維持・向上を目指して、QOL/PRO評価結果を臨床にいかに使用するか、そのためにはどのような方略があるのかについて、さらなる検討と議論を深める必要がある。
5 0 0 0 OA コンピテンシー基盤型と問題解決型アプローチ:公衆衛生大学院の社会行動科学教育
- 著者
- 福田 吉治
- 出版者
- 日本行動医学会
- 雑誌
- 行動医学研究 (ISSN:13416790)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, no.2, pp.71-73, 2021 (Released:2022-01-23)
5 0 0 0 OA 将来構想委員会による日本行動医学会の学会活性化案と若手の会の設立
- 著者
- 津野 香奈美
- 出版者
- 日本行動医学会
- 雑誌
- 行動医学研究 (ISSN:13416790)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, no.2, pp.78-83, 2021 (Released:2022-01-23)
5 0 0 0 OA コロナ禍におけるメンタルヘルス
- 著者
- 井澤 修平
- 出版者
- 日本行動医学会
- 雑誌
- 行動医学研究 (ISSN:13416790)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, no.2, pp.45-1, 2021 (Released:2022-01-23)
5 0 0 0 OA 日常生活場面における セルフコンパッション行動の測定法の開発
- 著者
- 内田 太朗 Takahashi Toru 仁田 雄介 熊野 宏昭
- 出版者
- 日本行動医学会
- 雑誌
- 行動医学研究 (ISSN:13416790)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, pp.24-34, 2020 (Released:2020-06-07)
セルフコンパッション(Self-compassion:SC)とは、苦痛の緩和のために慈しみをもって自分に接することであ る。SC特性は、精神的健康と関連があることが、様々な調査研究で明らかにされてきた。しかしながら、先行研究において、SC は特性あるいは状態として測定されてきたため、SCが日常生活場面で具体的にどのように実行されているかは不明である。また、実 際の日常生活場面におけるSCをアセスメントするツールがないため、臨床現場などにおいて、SCに対する介入効果を十分に検討す ることができない。これらの問題を解決するための方法の1つに、SCを特性や状態としてではなく、具体的な行動として測定するこ とが考えられる。そこで、本研究では、臨床行動分析の機能的アセスメントの枠組みに基づき、行動の形態および行動の結果の2 つの観点からSC行動を測定する方法を開発し、その妥当性を検討することを目的とした。大学生および大学院生31名を対象とし、 日常生活場面における、SC行動を測定する質問項目を用いて、携帯端末を用いた調査を実施した。SC行動の形態(項目は「自分 自身をなだめる」「優しさをもって自分に接する」「苦痛を緩和しようとする」「セルフヴァリデーションをする」)および行動の結果(項 目は「落ち着きの増加」「自分への優しさの増加」「苦痛の緩和」「自己批判の減少」)をそれぞれ説明変数とし、状態SC、状態 well-being、アクセプタンスをそれぞれ目的変数としたマルチレベル単回帰分析を行った。分析の結果、SC行動の形態の項目「自 分自身をなだめる」、「優しさをもって自分に接する」、「苦痛を緩和しようとする」は、状態SCの高さを有意に予測した。また、SC行 動の結果の項目「落ち着きの増加」、「自分への優しさの増加」、「苦痛の緩和」は、状態SCの高さを有意に予測し、「自己批判の 減少」は、状態SCの高さを有意傾向で予測した。これらの結果から,本研究で作成したSC行動を測定するおおよその項目は、妥 当であることが示唆された。SC行動の形態の項目「自分自身をなだめる」は、状態well-beingの高さを有意傾向で予測し、SC行 動の結果の項目「苦痛の緩和」は状態well-beingの高さを有意に予測した。しかし、それら以外のSC行動の形態および結果の項 目は、状態well-beingの高さを有意に予測しなかった。これらの結果から、SC行動後の60分以内における状態well-beingは増加 しない可能性がある。今後の研究では、SC行動がその後のwell-beingを増加させるかどうかをより詳細に検討するために、SC行 動と(1)本研究で測定されなかった状態well-beingの要素との関連性を検討、(2)60分以降あるいは1日全体の状態well-being との関連性を検討、(3)well-being特性との関連性を検討することが必要である。SC行動の形態の項目「自分自身をなだめる」、 「優しさをもって自分に接する」、「苦痛を緩和しようとする」は、アクセプタンスの高さを有意に予測した。また、SC行動の結果の項 目「自分への優しさの増加」「自己批判の減少」は、アクセプタンスの高さを有意に予測し、「落ち着きの増加」は、アクセプタンスの高さを有意傾向で予測した。これらの結果から,SC行動の種類によって,アクセプタンスの高さを予測する程度が異なることが示 された。本研究の限界点として、SC行動の先行条件および確立操作を検討できなかったことが挙げられる。今後の研究で、どの ような文脈下でSC行動が生起しやすいのかを検討することや、ルールなどを含めた確立操作がSC行動の生起に与える影響を検討 することが望まれる。そうすることにより、SC行動を生起・維持させる変数に関する知見が蓄積され、機能的アセスメントの枠組 みからSC行動をより詳細に捉えることが可能となると考えられる。
4 0 0 0 OA 睡眠時間は主観的健康観及び精神神経免疫学的反応と関連する
- 著者
- 岡村 尚昌 津田 彰 矢島 潤平 堀内 聡 松石 豊次郎
- 出版者
- 日本行動医学会
- 雑誌
- 行動医学研究 (ISSN:13416790)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, no.1, pp.33-40, 2010 (Released:2014-07-03)
- 参考文献数
- 28
大学生の睡眠時間と心身の健康との関連性を明らかにするために、GHQ-28による主観的評定と精神神経免疫学的(PNI)反応[3-methoxy-4-hydroxyphenylglychol(MHPG)含有量、免疫グロブリン(Ig)A抗体産生量]を用いた客観的評価から、睡眠時間の長さによって、心身のストレスの自覚とノルアドレナリン神経系と免疫系の活性がどのように異なるのか検討した。研究参加の同意が得られた健康な大学生205名(男性110名、女性95名、年齢18.6±1.0)を対象に睡眠時間を調査し、最適睡眠時間群(AS:Adequate Sleep)(6〜8時間睡眠)を35名、短時間睡眠群(SS: short sleep)(5時間以下の睡眠)33名と長時間睡眠群(LS: long sleep)(9時間以上の睡眠)28名をそれぞれ抽出した。講義時に、集団一斉法にてGHQ-28への記入を求め、PNI反応を測定するために唾液の採取を行った.LS群のGHQ-28得点は、「社会的活動障害」および「うつ傾向」下位尺度でAS群とSS群に比較して有意に高値であった。一方、SS群はASに比較して「身体症状」下位尺度得点が有意に高かった。SS群の唾液中free-MHPGは、AS群と異ならなかったが、LS群に比較して有意に高く、s-IgAは有意に低かった。ロジスティック回帰分析の結果は、中等度以上の「身体的症状」、「社会的活動障害」と「うつ傾向」症状が短時間もしくは長時間睡眠と有意に関連していることを明らかにした。以上の知見から、6〜8時間睡眠が最も心身の健康と関連していることが示された。また、睡眠時間いかんによって唾液を指標にして得られたPNI反応が異なったことは、今後、大学生のストレス関連疾患の予防や健康増進活動のために、睡眠の重要性を示す客観的証拠となると考える。
4 0 0 0 OA Detached Mindfulnessの測定:注意制御と距離化を考慮した検討
- 著者
- 今井 正司 熊野 宏昭
- 出版者
- 日本行動医学会
- 雑誌
- 行動医学研究 (ISSN:13416790)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, no.2, pp.106-114, 2021 (Released:2022-01-23)
4 0 0 0 OA ストレス関連精神疾患とエピジェネティクス
- 著者
- 松澤 大輔
- 出版者
- 日本行動医学会
- 雑誌
- 行動医学研究 (ISSN:13416790)
- 巻号頁・発行日
- vol.22, no.2, pp.57-64, 2016 (Released:2017-06-23)
遺伝子DNAが出生後も環境と生体との相互作用によるエピジェネティックな修飾を受けて発現調節されることが注目されている。DNAメチル化はその一つであり、脳内神経細胞のDNAメチル化も様々な外部刺激により後天的に変化がもたらされる。近年では精神疾患においてもその影響を示唆する研究が相次いでいるが、不安や恐怖の記憶が症状に関わるストレス関連精神疾患ではエピジェネティックな現象の関与について現在でも知見が少ない。本稿では、ストレス関連精神疾患で発症脆弱性や治療抵抗性を示す背景としてのDNAメチル化の関与を、筆者の教室で得られた結果を紹介しながら論じたい。精神疾患におけるエピジェネティックな機構は、ストレス応答の変化など獲得した行動の次世代への継承にも役割を果たしている可能性もあり、今後の研究結果の蓄積が待たれている。
4 0 0 0 OA タイプA行動パターンとストレス反応
- 著者
- 佐藤 豪
- 出版者
- 日本行動医学会
- 雑誌
- 行動医学研究 (ISSN:13416790)
- 巻号頁・発行日
- vol.3, no.1, pp.8-15, 1996 (Released:2014-07-03)
- 参考文献数
- 39
タイプA行動パターンは、冠動脈疾患の発症の原因となる行動様式として、近年広く知られるようになった。本論文ではタイプA行動パターンと冠動脈疾患を結びつける要因としてストレスとそれに対する心理・生理的反応との関連について検討することを目的とする。タイプA者は自己価値が様々な外的要因によって変動しやすいものと感じているために、絶えず自尊心についての危機感を持っている。またタイプA行動パターンの形成には信頼性の乏しい対人関係や、幼少期における両親の達成努力に重きを置いた養育態度が寄与しているものと考えられる。タイプA者はタイプB者よりも自らが直面したストレスを過大に評価し、より危機的状況ととらえやすい傾向を持ち、そのためにストレスに対して能動的対処を行おうとすることが示されている。このような対処行動中にはタイプA者はタイプB者に比べて交感神経系の興奮の増大、内分泌学的反応性の昂進、また心理的ストレス反応の増大を示すことが明らかとなっている。交感神経系の興奮の持続は、循環器系、内分泌学的な機能の異常を引き起こし、冠動脈疾患の発症に寄与しているものと考えられる。またタイプA行動パターンが末梢のβアドレナリン系の反応抑制によって減少するという研究から、末梢の反応性もタイプA行動パターンの形成に寄与している可能性が示されてきた。さらに中枢性のドーパミン作動系機能とJenkins Activity Surveyの検査成績からタイプA行動パターンにはアレキシサイミア的特徴があることが示唆された。さらにドーパミン作動系機能の歪みと幼少期における両親との分離体験の関連性を示す研究からタイプAの形成過程には幼少期の心理的体験が関与しており、それがドーパミン作動系機能などの心理・神経・内分泌機能の歪みを起こし、タイプAの形成に関与する可能性を示唆した。本論文では、タイプA行動パターンの性質の解明のためには心理・神経・内分泌学的研究と、心理・社会的研究の両方が必要であることを示した。
4 0 0 0 OA 職業性ストレスと心血管リスク
- 著者
- 服部 朝美 宗像 正徳
- 出版者
- 日本行動医学会
- 雑誌
- 行動医学研究 (ISSN:13416790)
- 巻号頁・発行日
- vol.22, no.2, pp.71-75, 2016 (Released:2017-06-23)
少子高齢化に伴い、日本では労働人口が減少していく。労働人口の維持は国の存立に関わる問題であり、国家を維持するために、国民はより長く働くことが求められるようになる。一方、加齢に伴い、心血管リスクは上昇することから、高齢労働者の健康を守るために、より綿密な心血管リスク管理が必要となる。高血圧は日本人の脳・心臓疾患発症に寄与する最も重要なリスク因子であり、2010年の国民・栄養調査によると、30歳以上の男性で60%、女性で45%が高血圧と考えられる。しかしながら、血圧のコントロール率は、過去30年間、改善傾向にあるものの、男性で30%、女性で40%程度に留まっているのが現状である(高血圧治療ガイドライン2014)。一方、職業性のストレスは健康障害と関連することが示されており、特に血圧の上昇に対する影響については多くのエビデンスが蓄積されてきた。これまでの報告から、職業性のストレスは特に職場血圧の上昇と強く関連し、この関連は女性よりも男性でみられること、さらには、脳・心臓疾患発症とも関連することがわかっている。長時間労働についても心血管リスクを上昇させるとの報告があるが、両者の関連は、仕事のやりがいや裁量権といった要因によって緩衝をうける可能性がある。加齢に伴い、ストレス等に対する血圧反応が亢進する可能性があり、高齢労働者の血圧管理を考慮するうえで、量的、質的労働ストレスの考慮は重要となろう。健康で長く働いてもらうためには、十分な心血管リスク管理とストレスマネジメントの両者に配慮する必要がある。
4 0 0 0 OA 入眠障害と入眠時の対処行動の関連
- 著者
- 宗澤 岳史 山本 隆一郎 根建 金男 野村 忍
- 出版者
- 日本行動医学会
- 雑誌
- 行動医学研究 (ISSN:13416790)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, no.1, pp.8-15, 2011 (Released:2014-07-03)
- 参考文献数
- 20
本研究は、入眠障害と入眠時の対処行動の関連を検討したものである。研究1では、入眠時の対処行動を因子分析によって分類した。分類された因子は第1因子“認知活動抑制”、第2因子“非入眠行動”、第3因子“認知活動活性”と解釈された。研究2では大学生355名を対象に、対処行動と入眠時認知活動、入眠障害の程度の関連を検討した。その結果、全て対処行動は入眠時認知活動と入眠障害の程度と正の相関を示した。また、パス解析の結果、入眠障害に至る2つの経路が示された。一つは、認知的対処が入眠時認知活動と有意な関連を示す間接的なパスであり、もう一つは、行動的対処が入眠障害の程度と有意な関連を示す直接的なパスであった。本研究結果から、入眠時の不適切な対処行動は入眠障害に対して不適切な影響を有することが確認された。今後は、不適切な対処行動の除去と代わりとなる対処方略の導入を用いた入眠障害に対する認知行動療法の開発が期待される。