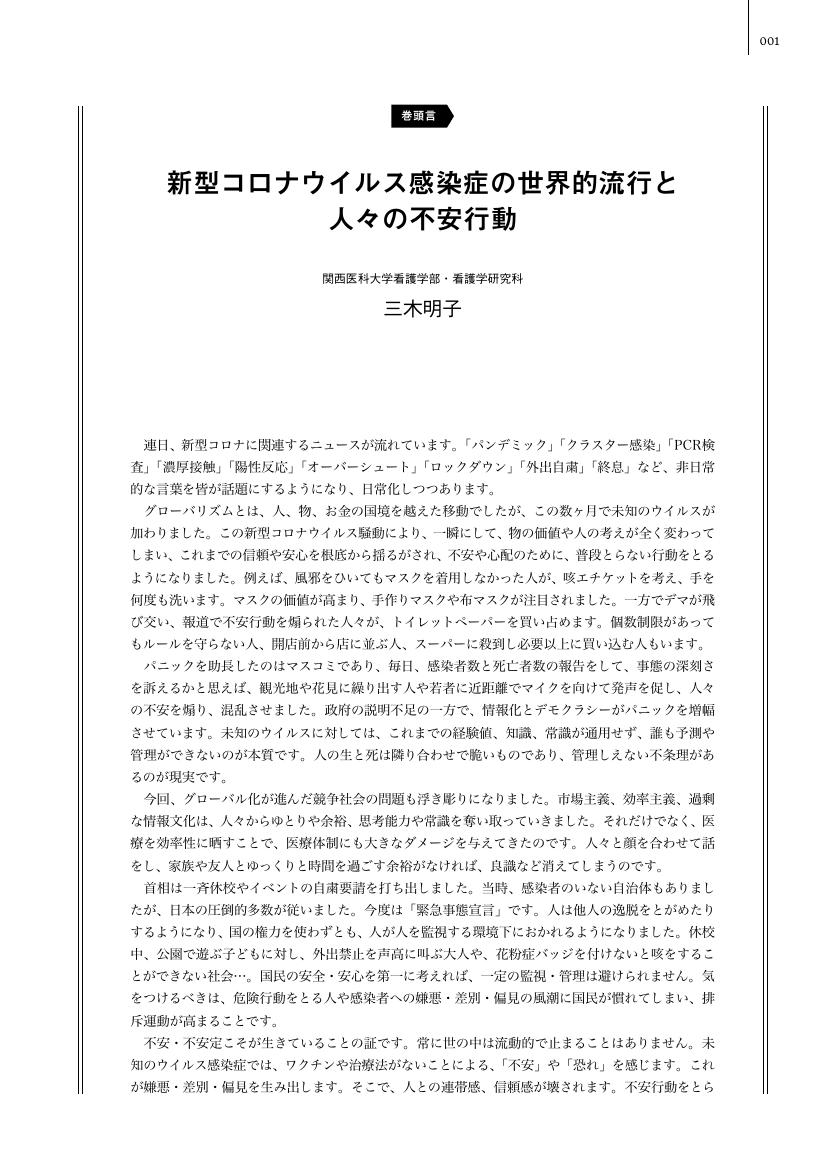1 0 0 0 行動変容テクニックの標準化に関する国際的な動向について
- 著者
- 石川 善樹
- 出版者
- 日本行動医学会
- 雑誌
- 行動医学研究 (ISSN:13416790)
- 巻号頁・発行日
- vol.20, no.2, pp.41-46, 2014
疫学研究などの成果により、健康に寄与する行動が明らかにされ、科学的知見の整理が進められてきた。また、行動科学や健康心理学などの観点から、それら健康行動の決定要因が特定され、これまで様々な行動モデルが提案されてきた。しかし、健康行動のメカニズム解明が進む一方、具体的にどのような介入を行えば実際に行動が変容するのかという点は、21世紀における医学・公衆衛生学上の課題として残されている。行動変容を狙いとした介入は、複雑ないくつもの要素から構成され、またそれら要素は互いに相互作用し合っている。それ故、介入の再現性や臨床現場での適用性、さらにはシステマティックレビューを通じた知見の統合を困難にしていることが指摘されている。CONSORT(Consolidated Standards of Reporting Trials: 臨床試験報告に関する統合基準)は、ランダム化比較試験(randomized controlled trial: RCT)の報告の質を改善することを狙いとした国際標準のガイドラインである。その中では、運動や食生活などの健康行動の改善を目的とした非薬理学的治療においても、介入プロセスや内容について詳細な報告を行うことが求められている。しかしながら、具体的にどのように介入プロセスや内容を記述すればよいのか、CONSORTで定められているガイドラインは存在しない。そこで近年、介入内容を客観的で、再現性があり、かつそれ以上還元のできない行動変容テクニックに分類する試みが国際的に行われている。その成果として、たとえば身体活動、食生活、禁煙、飲酒、性感染症予防分野などで、効果的な行動変容テクニックが特定され始めている。また2013年には、Annals of Behavioral Medicine誌上にて、国際的なコンセンサスのとられた93に及ぶ行動変容テクニックの分類表が公表されている。本稿では今後の医学教育における行動科学のカリキュラム作成における基礎資料の提供を狙いとし、どのような考え方・手法に基づいて行動変容テクニックの標準化が進められているのか、近年の国際的な動向を展望することを目的とする。
- 著者
- 行動医学コアカリキュラム作成ワーキンググループ 中尾 睦宏 中山 健夫 端詰 勝敬 吉内 一浩 堤 明純 石川 善樹 乾 明夫 井上 茂 島津 明人 諏訪 茂樹 津田 彰 坪井 康次
- 出版者
- 日本行動医学会
- 雑誌
- 行動医学研究 (ISSN:13416790)
- 巻号頁・発行日
- vol.20, no.2, pp.63-68, 2014
行動科学について、医学生が卒業時に求められるコンピテンシーを明らかにすることを目的として、デルファイ法による調査を行った。日本行動医学会教育研修委員会の下に設置されたワーキンググループで、行動科学(行動医学)に関して、医学生が卒業時までに身につけておきたいと思われる知識や技術(コンピテンシー項目)のリストアップを行い、日本行動医学会評議員111名に対して、2ラウンドのデルファイ様式のオンライン調査に参加を呼びかけた。電子メールによる呼びかけに対し26名が参加した。参加者のうち、17名は心理学、5名は臨床、2名は看護、5名は社会医学のバックグラウンドを有していた(一部重複あり)。8名は大学医学部での講義の受け持ちを持っており、教育歴は平均11年であった。2回の調査で「説明もしくは概説できる」と集約されたコンピテンシー項目は、ストレスとコーピング、動機付け、行動療法、認知行動療法、利用者-医療者関係、医療者関係、クオリティ オブ ライフ、ソーシャルサポート、セルフ・エフィカシー、刺激統制、リラクセーション法、アドヒアランス、服薬行動、傾聴技法および質問技法であった。「知っている必要あり」と集約されたコンピテンシー項目は、情報処理の自動化、ローカスオブコントロール、ティーチング、社会的認知、性行動、エンパワーメントであった。回答数は少ないものの、専門家からの意見として得られた今回の所見は、我が国の医学部における行動医学のカリキュラムを開発するにあたって参考になると考えられる。
1 0 0 0 OA 高齢者における運動セルフ・エフィカシーの情報源および運動変容ステージとの関連
- 著者
- 前場 康介 竹中 晃二
- 出版者
- 日本行動医学会
- 雑誌
- 行動医学研究 (ISSN:13416790)
- 巻号頁・発行日
- vol.18, no.1, pp.12-18, 2012 (Released:2014-07-03)
- 参考文献数
- 25
- 被引用文献数
- 3
本研究では、高齢者における運動セルフ・エフィカシー(Self-efficacy; SE)に影響する4つの情報源および運動変容ステージとの関連について検討し、各変容ステージにおける情報源の特徴を明らかにすることを目的とした。60歳以上の高齢者を対象とした質問紙調査を実施し、合計365名(男性166名、女性199名:平均年齢74.21歳)の回答が分析対象となった。質問紙の内容は、①基本属性、②運動SEの情報源、③運動SE、および④運動変容ステージ、をそれぞれ測定するものであった。分析の結果、定期的な運動習慣を有する高齢者は192名(52.6%)であり、運動SEの情報源における合計得点、および運動SE得点は変容ステージが進行するにつれて高まっていくことが明らかになった。さらに、運動SEの各情報源も同様に、変容ステージが進行するにつれてそれらの得点も漸増する傾向にあることが示された。本研究から得られた知見に従うことで、高齢者を対象とした運動介入においてより効果的な方略を提案することが可能となる。
1 0 0 0 OA 座り行動と睡眠障害:系統的レビューとメタ分析
- 著者
- 中村 志津香
- 出版者
- 日本行動医学会
- 雑誌
- 行動医学研究 (ISSN:13416790)
- 巻号頁・発行日
- vol.23, no.2, pp.111-112, 2018 (Released:2018-06-29)
1 0 0 0 OA 一過性のウォーキングに伴う感情の変化とウォーキングに伴う感情を規定する認知的要因
- 著者
- 荒井 弘和 堤 俊彦
- 出版者
- 日本行動医学会
- 雑誌
- 行動医学研究 (ISSN:13416790)
- 巻号頁・発行日
- vol.13, no.1, pp.6-13, 2007 (Released:2014-07-03)
- 参考文献数
- 30
- 被引用文献数
- 1
本研究の目的は、一過性のウォーキング実施時間が感情の変化に与える影響、およびウォーキングに伴う感情を規定する認知的要因について検討することであった。本研究の対象者は、大学1年生82名であった。対象者は、15分間ウォーキング群または30分間ウォーキング群に割り付けられた。ウォーキング前後の感情の測定には、運動場面専用の感情尺度であるWaseda Affect Scale of Exercise and Durable Activity(WASEDA)およびFeeling Scale(FS)を用いた。さらに、ウォーキングに伴う感情を規定する「自分自身の身体に注目すること」および「汗」という2つの連合的要因と「いっしょに運動する人」および「まわりの景色」という2つの分離的要因からなる認知的要因が準備された。本研究は、2(群)×2(時間)の対象者間・内混合要因計画である。対象者はウォーキング前後にWASEDAとFSの評価を行った。対象者はさらに、ウォーキング後に、ウォーキング中の主観的運動強度(RPE)と、ウォーキングに伴う感情を規定する認知的要因の評価を行った。ウォーキングによる感情の変化とウォーキングに伴う感情を規定する認知的要因の評価は、ウォーキングの実施時間(15分間または30分間)によって異ならなかった。また、両方の群において、「いっしょに運動する人」および「まわりの景色」という分離的要因が、ウォーキング後の感情を説明していることが示された。そのため、ウォーキング時に、連合的要因に注意を向ける方略(連合的方略)よりも、分離的要因に注意を向ける方略(分離的方略)を用いることによって、ウォーキング後の感情が好ましくなる可能性がある。。
1 0 0 0 OA 集団のデータ解析-考え方と実際-
- 著者
- 桑原 恵介
- 出版者
- 日本行動医学会
- 雑誌
- 行動医学研究 (ISSN:13416790)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, no.2, pp.189-196, 2020 (Released:2021-05-09)
1 0 0 0 OA 新生児の母親に対する乳児の睡眠形成についての簡便な親教育
- 著者
- 羽山 順子 足達 淑子 津田 彰
- 出版者
- 日本行動医学会
- 雑誌
- 行動医学研究 (ISSN:13416790)
- 巻号頁・発行日
- vol.16, no.1, pp.21-30, 2010 (Released:2014-07-03)
- 参考文献数
- 33
- 被引用文献数
- 1
[研究背景]寝渋り、夜泣きのような乳幼児の睡眠問題は、母親の睡眠と健康に悪影響を及ぼす。児の睡眠問題は、就床時および夜間覚醒時の児に対する適切な対応を親に教育することで予防できるとの報告がある。先行研究において、筆者らは生後4ヵ月の乳児を持つ母親を対象に児の睡眠問題予防を目的とした教育介入を実施した。しかし教育の効果は限定的であり、4ヵ月より早い月齢である新生児の親に対する教育が、児の睡眠問題の予防にはより有用であると考えられた。 [目的]先行研究の結果を踏まえ、本研究は、新生児の母親に対して行った児の睡眠問題予防教育が、母親の養育行動と児の睡眠問題予防に及ぼす効果を、その後の4ヵ月児健康診査で比較して検討した。 [方法]対象は教育群46名と教育をしなかった比較群30名であった。教育では、乳幼児の睡眠問題予防のため望ましい養育行動について説明した小冊子を、地域の新生児訪問時に助産師が母親に配布した。評価した行動は1)児の睡眠に関連した親の養育行動(望ましい養育行動13項目、望ましくない養育行動3項目)、2)児の睡眠と睡眠問題、3)母親の睡眠と健康問題であった。 [結果]教育の結果、教育群の母親は、児の夜間覚醒時に「すぐには触らず様子をみる」という望ましい養育行動が比較群より高率に見られた(教育群:比較群=48.9%:23.3%,p<0.05)。さらに望ましい養育行動の合計数は比較群よりも多く(教育群:比較群=4.4:3.3,p<0.01)、望ましくない養育行動の合計数は少なかった(教育群:比較群=1.3:1.7,p<0.05)。また、教育群の母子は就床時刻が規則正しい者の割合が高く、母親は頭痛を感じる者の割合が低かった(教育群:比較群=2.3%:20.0%,p<0.05)。 [考察]以上の結果から、小冊子を用いて児の就床覚醒時刻を規則正しくするための養育行動を教育したことは、教育群の児における就床時刻の規則性促進に影響したと考えた。また、児の就床時刻が規則正しいことは教育群の母親における就床時刻の規則性を促し、母親の頭痛の減少につながった可能性があると考えた。 一方、児の睡眠問題では群間差が見られず、新生児の母親への教育介入が、4ヵ月児の母親への教育よりも児の睡眠問題の予防に有用とした本研究の仮説は支持されなかった。この理由として、①予防効果の検証時期が生後4ヶ月では早過ぎた可能性、②今回用いたような簡素な介入の効果検証にはサンプル数(76名)が小さ過ぎた可能性、③本研究における教育法が、必ずしも児の睡眠に問題意識を有してはいない母親には不十分であった可能性が考えられた。従って、新生児の母親に対しては、本研究の教育方法では不十分で、情報の提供の仕方などに一段の工夫の余地があると考えた。 他地域も含めたより多数の対象者における比較試験を行うこと、睡眠日誌などで睡眠指標の精度を高める必要がある。 [結論]4ヵ月より早い月齢での親教育が児の睡眠問題の予防にはより有用であるとの仮説は支持されなかった。しかし、本研究における教育介入の結果、限定的ではあるが児の睡眠に関連する養育行動および母子の睡眠習慣に効果が認められた。また、母子の睡眠習慣の改善は、母親の健康問題の改善に貢献する可能性があることが示された。
1 0 0 0 OA 実践:統計解析超入門~無料で誰でも簡単に~
- 著者
- 高橋 則晃 中尾 睦宏
- 出版者
- 日本行動医学会
- 雑誌
- 行動医学研究 (ISSN:13416790)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, no.2, pp.176-181, 2020 (Released:2021-05-09)
1 0 0 0 OA 行動医学と動機づけ面接
- 著者
- 竹内 武昭
- 出版者
- 日本行動医学会
- 雑誌
- 行動医学研究 (ISSN:13416790)
- 巻号頁・発行日
- vol.24, no.2, pp.61, 2019 (Released:2019-10-03)
1 0 0 0 OA 東日本大震災被災者・避難者の健康増進
- 著者
- 本谷 亮
- 出版者
- 日本行動医学会
- 雑誌
- 行動医学研究 (ISSN:13416790)
- 巻号頁・発行日
- vol.19, no.2, pp.68-74, 2013 (Released:2013-10-31)
- 参考文献数
- 11
- 被引用文献数
- 8
東日本大震災の被災者・避難者の多くは、心身両面においてさまざまな健康問題を抱えている。健康問題の例としては、PTSD症状の出現、抑うつ、不安、焦燥、怒りの増加、睡眠障害、血圧上昇、アルコール依存症、生活習慣病、あるなどがあげられる。震災がもたらしたこのような健康問題は、震災直後の急性期のみならず、中長期においても大きな問題となっており、被災者に対する継続的なアプローチが必要である。今回の震災では、津波や原発事故のために、強制的に避難をせざるをえず、震災後、住環境が大きく変化した者も多い。動かないことで全身の心身機能が低下する“生活不活発病(廃用症候群)”も、避難している高齢者を中心に散見され、心身の健康問題の悪循環を生んでいる。加えて被災三県の中でも放射線の影響が懸念されている福島県では、住民の屋外活動の減少や食品摂取の過剰制限など、放射線不安が要因で引き起こされている健康問題への対応も課題の一つとなっている。被災者・避難者の抱える健康問題に関しては、ハイリスク者の早期発見、早期支援を行うことが重要である。また、ハイリスク者や対応困難者に対しては、医師、看護師、保健師、心理士など多職種がチームとなって連携したアプローチをすることが不可欠であり、支援に臨床心理学的視点や行動医学的視点が必要となることもある。そして、被災者・避難者の健康増進を考える際には、個々人に対するアプローチに加えて、地域やコミュニティーに対するアプローチも非常に重要であり、いかに地域やコミュニティーを取り込んだアプローチができるかが長期におよぶ被災者・避難者の健康増進のカギとなる。
1 0 0 0 OA 行動の提示による集団の認知
- 著者
- 増田 豊
- 出版者
- 日本行動医学会
- 雑誌
- 行動医学研究 (ISSN:13416790)
- 巻号頁・発行日
- vol.4, no.1, pp.30-32, 1997 (Released:2014-07-03)
- 参考文献数
- 2
筆者は、37歳男性の精神分裂病患者の行動変容を観察した。この患者は強度の思考障害はなかったが、入院当初から治療者の様々な精神療法的な介入にもかかわらず拒薬が著しかった。そこでスタッフがこの患者を除く同室の患者全員に、その病室内で同時に服薬するように指導していったところ、指導後3週間でその拒薬患者も自ら服薬するようになった。この症例について筆者は以下のように考察した。1) この患者は同一時刻に同一の病室で服薬するという行動の提示によって集団を認知した。2) 自らこの集団に帰属したことにより、この患者は服薬という行動をとるようになった。3) 具体的な行動の提示による集団の認知と集団帰属好性は、この患者のみならず、ヒトの集団に関わる根本的なありようであろう。
- 著者
- 津田 茂子 田中 芳幸 津田 彰
- 出版者
- 日本行動医学会
- 雑誌
- 行動医学研究 (ISSN:13416790)
- 巻号頁・発行日
- vol.10, no.2, pp.81-92, 2004
- 被引用文献数
- 2
妊娠後期 (妊娠36週以降) の妊婦79名 (平均年齢30.0歳、19~41歳) を対象として、妊娠後期の心理的健康感と出産後のマタニティブルーズとの関連性を調べるとともに、マタニティブルーズに及ぼす産科的要因 (母体合併症の有無、出産経験、新生児の状態、分娩時の異常) と世帯形態、年齢などの影響を検討した。妊婦の心理的健康感は自記式のWHO Subjective Well-being Inventory (SUBI)、すなわち「心の健康度」と「心の疲労度の少なさ」の2つの下位尺度から構成された質問紙によって測定し、マタニティブルーズはSteinのマタニティブルーズ自己質問表によって出産後5日目に評価した。<br>SUBIの標準化された得点区分に従えば、対象者の妊娠後期の心理的健康感は、心の健康度と心の疲労度の少なさ、いずれも高く自覚されていた。臨床上、マタニティブルーズと判定されるマタニティブルーズ高得点者 (8点以上) は16.2%であり、先行研究と比較すると、若干低い発症率であった。出産後5日目のマタニティブルーズ症状は妊娠後期の心理的健康感と有意な負の相関を示した。すなわち、妊娠後期の心の健康度が高いほど、マタニティブルーズの全症状と4つの下位症状 (情動易変性、抑うつ感、精神運動制止、自律神経系症状) は軽度であり、同様に、心の疲労度が少ないほどこれらマタニティブルーズの症状も少なかった。また、マタニティブルーズ症状と関連する産科的要因として、年齢の高さ、母体合併症、新生児の異常などが示された。さらに、心の健康度と心の疲労度の少なさの関数として、マタニティブルーズ症状得点は有意もしくは有意傾向をもって減少した。重回帰分析の結果は、出産後5日目のマタニティブルーズを予測するSUBI下位尺度項目として、身体的不健康感の少なさ、近親者の支え、社会的な支え、達成感、人生に対する失望感の少なさなどが、説明変数として有意であることを明らかにした。さらに、ロジスティック回帰分析の結果より、臨床的なマタニティブルーズの発症を予測する要因は妊娠後期の心の疲労度の少なさであることが示された。<br>これらの知見より、出産後のマタニティブルーズの影響を軽減するための方策として、妊娠後期の心理的健康感、とりわけ心の疲労度を少なくすることが重要であること、さらに、管理する必要のある産科的要因として母体合併症の有無や新生児の異常が明示され、介入の方向性が明確になった。
1 0 0 0 OA 睡眠時無呼吸症候群とうつ病 ~両者の関連性を検討する~
- 著者
- 池上 あずさ
- 出版者
- 日本行動医学会
- 雑誌
- 行動医学研究 (ISSN:13416790)
- 巻号頁・発行日
- vol.23, no.2, pp.58-62, 2018 (Released:2018-06-29)
閉塞性睡眠時無呼吸(以下OSA)とうつ病が同じ患者に並存することがある。PSG検査による解析では、OSAは 睡眠中の上気道の閉塞による無呼吸などの呼吸イベントから覚醒反応を生じたための睡眠構築不良(すなわち不眠)がその病態の本質であり、その結果、日中の眠気、倦怠感や集中力低下、認知機能の低下に加えてうつ症状も引き起こす。OSAとうつ病の合併については、ヨーロッパ五か国の延べ18980人の一般人口を対象とした調査でOSAの17.6%にうつ病がみられたとのOhayonらの報告をはじめとして、合併率が7~63%と幅が広い。これは、OSAに対する合併をDSM-Ⅳに基づいたうつ病の診断ではなく、うつの重症度を見る問診票で評価したものなどであったためと考えられた。しかし、ランダムに選択された個人の長期的な2つの大規模疫学研究ではどちらも年齢、BMI、アルコールや血圧、心血管疾患などの交絡因子を検討したうえでOSAのうつ病発症の調整オッズ比を、Peppardらは1.8倍、Chenらは2.18倍と報告しており、OSAとうつ病発症の間の密接な関係を示唆している。OSAとうつ病の重症度については、8論文で直接の関連性を肯定し、9論文は否定していた。しかし、眠気とうつ病の重症度、さらには低酸素血症とうつ病の重症度については関連性を認めていた。橋爪らは、OSAにうつ病を合併している患者8名に対してCPAP療法によるうつ病の治療効果を検討し、Beck Depression Inventry(BDI)とHamilton Depression Scale( HDS)両方のうつ症状のスケールで改善したと報告した。自験例であるが、他院でうつ病として治療中に当院を紹介され、PSGにてOSAと診断された20名(男性12名、女性8名)についてOSA治療後の経過を追跡した。OSA診断前には、全例抗うつ剤や抗不安薬あるいは睡眠導入剤を投与されていた。20例中14名にCPAP療法を導入し、継続できた12例中7例においてうつ症状と不眠の改善により服用中の薬物を減量ないしは中止することができた。口腔内歯科装置で治療された2例中1例は同様に不眠が改善した。一方、中長時間作用型のベンゾジアゼピン(以下BZ)系睡眠導入剤多剤服用例においては、無呼吸低呼吸指数(AHI)と覚醒反応指数(ArI)の間に大きな乖離があり、無呼吸・低呼吸時に覚醒反応を認めない症例も散見された。OSAのうつ症状発現のメカニズムは複雑であり、今後の研究成果が期待されるが、遺伝的要因、肥満と心血管危険因子を背景に頻回な覚醒反応を伴う睡眠の分断化、間欠的低酸素血症とそれによる炎症性サイトカイン、睡眠・覚醒機構に影響するセロトニンやノルアドレナリン、γ―アミノ酪酸(GABA)などの阻害性及び興奮性神経伝達物質が潜在的に関与し、眠気のレベルや本人の病前性格、社会的なストレスなどが複合的に合わさって形成されると考えられる。従って、CPAPを使用しても昼間の眠気が強いOSA患者は、うつ病の合併を考慮すべきであろう。うつ病患者の場合、抗うつ剤の影響で肥満となり、OSAを悪化させる一方で不眠に対して使用したBZ系薬剤によりOSAがマスクされるという状況も考えられる。つまり、治療に反応しないうつ病においては、OSA合併を常に念頭に置く必要がある。OSAとうつ病は、両者がそれぞれに対して潜在的危険因子になり得ると考えられる。
1 0 0 0 OA 模擬エレベーター内における音楽と同乗者の存在が女性搭乗者の不安に与える影響
- 著者
- 鈴木 智草 宇津木 成介
- 出版者
- 日本行動医学会
- 雑誌
- 行動医学研究 (ISSN:13416790)
- 巻号頁・発行日
- vol.16, no.1, pp.1-11, 2010 (Released:2014-07-03)
- 参考文献数
- 22
本研究では、公共閉所空間としてエレベーター室内を想定し、そこにおける音楽の有無と男子同乗者の有無が女子実験参加者の主観的不安と心拍数および居心地感に与える影響を測定した。実験1では、実験参加者の意思で自由にエレベーターから出られる状況を設定した(高自由度条件)。その結果、音楽の影響は見られなかったが、居心地感に対する同乗者の影響が見られた。実験2では、5分間エレベーターに入っていなければならないという、低自由度条件で実験を行ったところ、音楽によって心拍数の増大が抑制された。実験3では同乗者条件、音楽条件に加えて、状況の自由度の条件を設定した。その結果、高自由条件では、音楽が実験参加者の不安を低減させ、同乗者の存在は居心地を低下させた。低自由度条件では、同乗者の存在によって実験参加者の居心地は上昇し、また音楽は心拍数の増大を抑制した。これらの結果から、BGMには女性搭乗者の不安や居心地を改善する作用のあることが認められたが、その作用は同乗者の存在および状況の自由度によって異なっていた。
1 0 0 0 OA 新型コロナウイルス感染症の世界的流行と 人々の不安行動
- 著者
- 三木 明子
- 出版者
- 日本行動医学会
- 雑誌
- 行動医学研究 (ISSN:13416790)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, pp.1-2, 2020 (Released:2020-06-07)
1 0 0 0 OA がん検診受診率向上のための行動変容アプローチ
- 著者
- 平井 啓
- 出版者
- 日本行動医学会
- 雑誌
- 行動医学研究 (ISSN:13416790)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, no.2, pp.57-62, 2015 (Released:2015-11-19)
- 参考文献数
- 12
- 被引用文献数
- 1
日本の乳がん検診の受診率は極めて低く、さらに系統的ながん検診受診率対策が十分に行われていなかった。そこで、乳がん検診(マンモグラフィー検査)に関して、トランスセオレティカルモデル・計画的行動理論などの行動変容の理論と方法を用いて、行動変容モデルを作成し、モデル内の変数を用いた対象者セグメンテーションを行い、さらに異なるセグメント毎に心理的特性を考慮したメッセージを作成し、それらを送り分けるテイラード介入を実施し、コントロール群との実際の受診率の違いを無作為化比較試験によって検討した。641名の女性に対する調査の結果、目標意図・実行意図・がん脅威などの心理的変数からなる行動変容モデルが開発された。このモデルに基づいた対象者セグメンテーションが行われ、その妥当性が示された。3つのセグメント毎に開発されたメッセージを送り分けるテイラード介入を1,859名の女性を対象とした地域介入研究において実施した。その結果、テイラード介入群(19.9%)とコントロール群(5.8%、Odds ratio 95%信頼区間: 2.67–6.06)、さらにコントロール群と3つのセグメントの間で受診率に有意な違いがあることが明らかとなった。これらの研究から、行動変容モデルに従って対象者をセグメントに分け、そのセグメントがどのような心理的特性を持った人たちによって構成されているかを精緻に調べ、それに対応したメッセージとデザインを開発するという一連の方法は、効果的な行動変容を実現するためにはとても有効な方法であるのではないかと思われる。
1 0 0 0 OA 病棟看護師における感情労働とワーク・エンゲイジメントおよびストレス反応との関連
- 著者
- 加賀田 聡子 井上 彰臣 窪田 和巳 島津 明人
- 出版者
- 日本行動医学会
- 雑誌
- 行動医学研究 (ISSN:13416790)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, no.2, pp.83-90, 2015 (Released:2015-11-19)
- 参考文献数
- 39
看護師を対象に、感情労働による心理学的影響を調べた近年の先行研究では、感情労働がバーンアウト/抑うつの悪化や職務満足感の向上に影響を与えることが着目されている。しかし、日本の看護師を対象に感情労働の心理学的側面に着目した先行研究は少なく、感情労働を要素別に分類し、ワーク・エンゲイジメントやストレス反応との関連を検証した研究は、我々の知る限り見当たらない。そこで本研究では、日本の看護師を対象に「看護師の感情労働測定尺度:ELIN」を用いて感情労働の要素を詳細に測定し、これらの各要素とワーク・エンゲイジメント、心理的ストレス反応および身体的ストレス反応との関連を検討することを目的とした。関東圏内の1つの総合病院に勤務する女性病棟看護師306名を対象に、感情労働(ELIN:「探索的理解」、「ケアの表現」、「深層適応」、「表層適応」、「表出抑制」の5下位尺度からなる)、ワーク・エンゲイジメント(The Japanese Short Version of the Utrecht Work Engagement Scale:UWES-J短縮版による)、心理的ストレス反応および身体的ストレス反応(職業性ストレス簡易調査票:BJSQによる)、個人属性(年齢、診療科、同居者の有無)に関する質問項目を含めた自記式質問紙を用いて調査を実施した(調査期間:2011年8~9月)。分析は、感情労働とワーク・エンゲイジメント、心理的ストレス反応および身体的ストレス反応との関連を検討するため、感情労働の各下位尺度を独立変数、ワーク・エンゲイジメント、心理的ストレス反応および身体的ストレス反応を従属変数、個人属性を調整因子とした重回帰分析を実施した。重回帰分析の結果、感情労働の構成要素の一つである「探索的理解」とワーク・エンゲイジメントとの間に正の関連が、「表出抑制」とワーク・エンゲイジメントとの間に負の関連が認められた。また、感情労働の構成要素の一つである「深層適応」と心理的ストレス反応および身体的ストレス反応との間に正の関連が認められた。これらの結果から、「探索的理解」を高め、「表出抑制」や「深層適応」を低減させるようなアプローチによって、看護師が自身の感情をコントロールしながらも、心身の健康を保持・増進するために有効な可能性が示唆された。
1 0 0 0 OA 一過性の有酸素運動が唾液中コルチゾールの分泌に与える影響に関する予備的検討
- 著者
- 荒井 弘和 岡 浩一朗 竹中 晃二
- 出版者
- 日本行動医学会
- 雑誌
- 行動医学研究 (ISSN:13416790)
- 巻号頁・発行日
- vol.14, no.1, pp.30-35, 2009 (Released:2014-07-03)
- 参考文献数
- 26
現在、運動心理学において、精神神経免疫学に関する測定指標に注目が集まっている。そこで、本研究の目的は、一過性の有酸素運動が唾液中コルチゾール分泌に与える影響を予備的に検討することとした。本研究では、10名の対象者(平均年齢24.50±2.68歳;男性5名/女性5名)が招集され、(1) 自転車エルゴメータを用いた中等度の強度による20分間のサイクリングを行う条件と、(2) 20分間の読書を行うコントロール条件という、2つのカウンタ・バランスされた実験条件を行った。全ての対象者は、インフォームド・コンセントシートに署名した。唾液中のコルチゾール濃度は、各実験条件の前後に測定され、唾液中のコルチゾール濃度は、放射免疫測定法(radioimmunoassay: RIA)によって分析された。本研究は、2(条件:運動/コントロール)×2(時間:前/後)の対象者内要因計画である。繰り返しのある分散分析は、条件の主効果、時間の主効果、および交互作用を示さなかった。結論として、本研究では、一過性の有酸素運動はコルチゾール濃度を変化させない可能性が示された。
1 0 0 0 OA 冠動脈疾患と社会経済的要因 —メカニズムと予防の視点から—
- 著者
- 坪井 宏仁 近藤 克則 金子 宏 山本 纊子
- 出版者
- 日本行動医学会
- 雑誌
- 行動医学研究 (ISSN:13416790)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, no.1, pp.1-7, 2011 (Released:2014-07-03)
- 参考文献数
- 46
心疾患は、本邦では悪性新生物に次ぐ死因の第2位を占め、その多くが「冠動脈疾患(coronary heart disease, CHD)」である。CHDのリスクファクターとして、高血圧・高脂血症・糖尿病など生活習慣に基づくものが一般に知られているが、心理的・社会的・経済的因子も無視できない。多くの欧米諸国では長年にわたり心疾患が死因の第1位であるため、その原因と予防に関する研究も多く、CHDと心理的社会的因子や社会経済的因子に関する研究結果が多く得られている。わが国でもライフスタイルの変化により動脈硬化病変がさらに増加し、CHD罹患率やそれによる死亡率の上昇することが予測される。その予防において、個人の生活習慣以外にCHDの重要なリスクファクターである社会経済的要因を把握することも重要であろう。わが国は、高度成長時代を経て平等と言われる社会を築いてきたが、1990年代後半以降は個人間の社会経済的格差が広がっている。その変化の長短は視点によって異なるところであろうが、社会経済的格差が健康に影響を及ぼすのであれば、格差の変革が疾病予防にもつながるはずである。そこで本稿では、CHDと社会経済的状況(socioeconomic status, SES)の関係について、まず両者の関係を述べ、次に両者をつなぐメカニズムを主に心理社会的側面から触れ、最後にCHD予防の可能性を社会的側面から考察した。CHDは、冠動脈壁に経年的に形成される内膜の肥厚病変とその破裂により発生し、原因は酸化・炎症や交感神経系の亢進などである。一方、SESは収入・教育歴・職業(職の有無、職場での立場も含む)などから成り、さまざまな経路でCHDに影響すると考えられる。健康行動はSESによって差があり、高SES層ほど健康によい行動を取る傾向にある。その差が、健康増進資源・医療へのアクセスの違いにつながり、CHDの発症および予後に影響する。次に、心理社会的経路であるが、この経路では、心理的・社会的特性の差異が自律神経・内分泌・免疫系を介してCHDの成因に影響する。低SES層には、慢性ストレスやライフイベントが多く、抑うつ傾向・怒り・攻撃性・社会的孤立などが認められる一方、高SES層ではコントロール感や自己実現感が高い。このような差違が、視床下部-下垂体-副腎皮質(hypothalamic-pituitary-adrenal, HPA)系または交感神経-副腎髄質(sympathetic-adrenal-medullar, SAM)系を介し、炎症・酸化・血糖の上昇・交感神経系の亢進に影響し、長年の間にCHDイベントのリスクが高まる。また、両親および幼少期のSESが、HPA系およびSAM系の反応を脆弱にしたり、成人後の行動的・心理社会的リスクファクター(喫煙・運動不足・攻撃性・職場での緊張・不健康な心理状態など)に影響を与え、CHDに影響を及ぼす可能性も示唆されている。さて、CHDの予防は、生活習慣予防として特定健康診査・特定保健指導により個人および職場レベルで2008年より行われている。しかしSESとCHDの関連性を考慮すると、社会レベルでの予防策も必要であろう。WHOは、健康を決定する社会的要因として「社会経済環境」「物理環境」「個人の特性と行動」を挙げている。このうち、社会経済環境を整備することがCHD予防につがなる可能性を示した。教育による介入、社会保障制度の整備、人生の節目でのサポートなどが有効であろうことが海外の研究で示されている。SESを改善しCHDを予防する戦略には、エビデンスに基づいた社会疫学的研究が必要であろう。