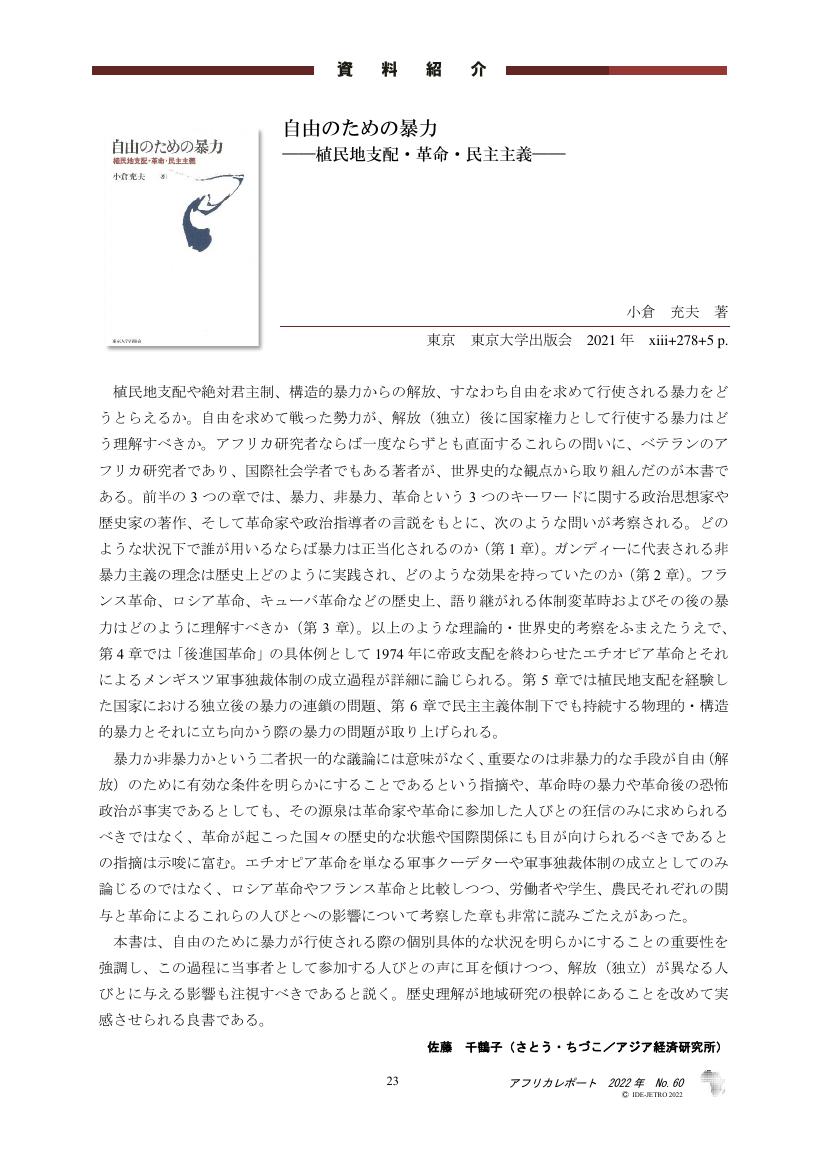1 0 0 0 OA イラン核交渉:国際政治にみる言説の不合理性
- 著者
- Yakov M. Rabkin
- 出版者
- 独立行政法人 日本貿易振興機構アジア経済研究所
- 雑誌
- 中東レビュー (ISSN:21884595)
- 巻号頁・発行日
- vol.4, pp.23-34, 2017 (Released:2019-11-12)
本稿は2年間の交渉の末昨年7月に漸く合意に至ったイラン核交渉について、その背景にあって強力に交渉の帰趨を支配してきた国際政治の構造的な要因に着目し、それがイラン問題に留まらず広く現在の国際関係を歴史的に規定してきたことに注意を喚起しようとするものである。2013年以降のイラン核開発疑惑をめぐる交渉の実質的な主役である米国は、この交渉について国家安全保障上の「深刻な懸念」を表明するイスラエルの説得に腐心してきた。だがここでイスラエルの懸念の主な根拠がアフマディネジャード大統領(当時)の「イスラエルを地図上から消す」発言であること、この発言の真意についてあいまいな部分が残るにもかかわらず、イスラエル側がネタニエフ首相を中心にこれに固執し続けてきたことはきわめて特異なことであると言わなければならない。その背景にはオスロ合意の空洞化と軌を一にするイスラエルの国内政治の極端な右傾化、1979年の革命以後のイランを全否定して「反近代化(De-modernization)」のサイクルに落とし込もうとする一部の根強い潮流(それは皮肉にも隣国のイラクにおいて実現した)、さらに旧来からの「西欧VSアジア」の差別的構造を維持しようとする強力な力が否定しようもなく働いていると見るべきであろう。この最後の点について筆者は第二次大戦中のマンハッタン計画に言及し、当時のルーズベルト米大統領がいずれにしても西欧側にあったナチス・ドイツへの原爆の投下を躊躇する一方で、これを引継いだトルーマン大統領はその外部にあった日本に対して2度の原爆投下をためらわなかったという事実を指摘する。こうした事例に象徴される不平等な関係が現在でも絶えず繰り返されている事実は、イラン核合意の性格を公平に理解し今後の展開を見通すうえで不可欠な前提である。(文責・鈴木 均)
1 0 0 0 OA イスラエル経済:グローバル化と「起業国家」 第Ⅰ部:ネオリベラリズムとグローバル化
- 著者
- 清水 学
- 出版者
- 独立行政法人 日本貿易振興機構アジア経済研究所
- 雑誌
- 中東レビュー (ISSN:21884595)
- 巻号頁・発行日
- vol.4, pp.42-53, 2017 (Released:2019-11-12)
With its geopolitical implications, Israel’s presence in the Middle East is conspicuous. Over the last two decades, Israel has rapidly expanded its sphere of influence to other parts of the world through economic transactions. Its dramatic development has been supported by its economic globalisation and high-tech industry. Israel currently belongs with the developed economies as a member state of the OECD, with a per-capita income of US$ 35,000, and is often referred to as a “success story” that other countries can draw lessons from for their own economic development.Part One attempts to analyse the factors, mainly related to economic policies, which contributed to the paradigm shift in Israel’s development strategy from the Zionist socialistic ideology to the neoliberal globalising policy orientation. The turning point was the economic reform introduced in 1985, which enabled the Bank of Israel to play an independent and leading role in monetary and fiscal policies against the rampant hyperinflation at the time. However, it should be noted that the reform package was a co-product of Israel and the US administration, supported by financial assistance attached to the reform. For the US, an economically stabilized Israel was an essential strategic asset against the Soviet Union. Since then, various reforms were introduced gradually, such as liberalisation of the labour market, privatisation, liberalisation of the financial market, and capital transfers. However, the voluminous favourable grant from the US was essential in absorbing balance of payment constraints and various social tensions through the transition period. Therefore, Israel’s transition to a neoliberal globalised economy was not a model that could be easily imported by other developing countries in the region.
1 0 0 0 OA 総論(1): 2014年の中東地域/総論(2): 中東地域との経済関係の深化に向けて
- 著者
- 鈴木 均 岡田 江平 石黒 大岳 土屋 一樹 ダルウィッシュ ホサム 池田 明史 渡邊 祥子 内藤 正典
- 出版者
- 独立行政法人 日本貿易振興機構アジア経済研究所
- 雑誌
- 中東レビュー (ISSN:21884595)
- 巻号頁・発行日
- vol.2, pp.2-42, 2015 (Released:2019-12-07)
- 参考文献数
- 13
1 0 0 0 OA エジプトにおける体制維持戦略と外交政策
- 著者
- Housam Darwisheh
- 出版者
- 独立行政法人 日本貿易振興機構アジア経済研究所
- 雑誌
- 中東レビュー (ISSN:21884595)
- 巻号頁・発行日
- vol.2, pp.43-64, 2015 (Released:2019-12-07)
エジプトではムバーラク大統領の国内政策と域内におけるエジプトの影響力低迷が引き金となって、2011年1月25日に抗議運動起こった。抗議運動はエジプト全土に拡がり、18日間の民衆的な反体制運動によってムバーラクは軍に見捨てられ、失脚に追い込まれた。この民衆蜂起によって警察は街頭から撤退し、シナイ半島の警察署は焼き放たれ、ムバーラクが率いていた国民民主党の建物や国内治安機関の本部は襲撃され、国家機関が数ヶ月にもわたって機能不全となり、ムバーラク体制の崩壊は国内的な混乱を招くこととなった。振り返れば、エジプトでの政治的大変動は社会的な革命へと展開することはできなかった。その理由は独裁体制からの移行を先導できる組織化された反体制勢力が存在しなかったためである。民衆による抗議運動は一時的に体制を転覆できても旧体制のエリートを分裂させることはできず、軍の影響下にある体制の復活を防ぐこともできなかった。2011年以降のエジプトは現在まで混乱状態に陥ったままであるが、1カ月に及ぶエジプト軍最高評議会(SCAF)の暫定統治、エジプト史上初の自由な大統領選挙によって選出された文民大統領のムルスィーによる一年余りの統治、そして2013年7月の軍事クーデターによって権力の座に就いたスィースィーの統治といった過程で、民衆蜂起がエジプトの外交関係に及ぼした影響はごく僅かであった。本稿は、現在のエジプトの外交政策が2011年の革命にほとんど影響を受けていないのはなぜか、またエジプトの統治者たちが政権の正統性、体制の強化および政治的な安定性を確保し、国内的な課題に対処するための戦略をいかに策定しているのかを説明することを試みる。本稿での主張は、ムバーラク以降のエジプトが体制の強化と保全のために外交政策を進めており、国内的な混乱によって地域内アクターへの依存度が高まっていることである。
- 著者
- 福田 安志
- 出版者
- 独立行政法人 日本貿易振興機構アジア経済研究所
- 雑誌
- 中東レビュー (ISSN:21884595)
- 巻号頁・発行日
- vol.2, pp.65-79, 2015 (Released:2019-12-07)
The Basic Law of Governance in Saudi Arabia stipulates that the king of Saudi Arabia has absolute power in the government of Saudi Arabia. However, after King Abdullah’s accession to the throne in 2005, his political powers were limited because of the presence of the so-called Sudeiri Seven, the powerful royal group that consists of the seven sons of King Abdel-Aziz’s purported favorite wife, Sheikha Hussa bin Ahmad Sudeiri.The death of the crown prince Sultan in 2011 followed by the death of the next crown prince Naif in 2012, both members of the Sudeiri Seven, weakened the power of the Sudeiri Seven. As a result, King Abdullah’s power had increased greatly compared to that of the Sudeiri Seven. Also, the sons of King Abdullah, who occupied prominent governmental posts, were acquiring strong influence in the regime.The death of King Abdullah in January 2015 and Salman’s accession to the throne caused changes to the ruling regime in Saudi Arabia. King Salman appointed Prince Muqrin as crown prince and deputy premier, and Prince Muhammad b. Naif as deputy crown prince. King Salman also appointed his son Muhammad b. Salman as defence minister and head of the royal court. Finally, King Salman issued a royal order on January 29 to reshuffle his cabinet and dismiss the governors of the Riyadh and Makka.
1 0 0 0 OA 左から右へ: イスラエルの政治的な長期傾向
- 著者
- Yakov M. Rabkin
- 出版者
- 独立行政法人 日本貿易振興機構アジア経済研究所
- 雑誌
- 中東レビュー (ISSN:21884595)
- 巻号頁・発行日
- vol.2, pp.80-102, 2015 (Released:2019-12-07)
- 参考文献数
- 90
第二次大戦時に大量のユダヤ人避難民を受け入れたイスラエルは、1946年の建国時には共産主義的な社会改革思想に基づくキブツ運動などの左翼的思潮を国家建設の支柱にしていたが、その後の政治過程のなかで一貫して右傾化の方向をたどり、現在では国際的にみても最も保守的な軍事主義的思想傾向が国民のあいだで広く共有され、国内のアラブ系住民の経済的従属が永く固定化するに至った。現在のイスラエル国家を思想的にも実体経済的にも支えている基本的な理念は、建国時のそれとは全く対極的な新保守主義とグローバル化された「新自由主義」的な資本主義であり、それは当然ながら国内における安価な労働力としてのアラブ系住民の存在を所与の前提条件として組み込んでいる。これは具体的にどのような経緯によるものであり、またイスラエル国家のどのような性格から導き出されるものなのか。本論稿では政治的シオニズムがイスラエル建国後から現在までにたどってきた思想的な系譜を改めて確認し、現在のイスラエルが国際的に置かれている特異な立場とその背後にある諸要因を説明する。
1 0 0 0 OA 米国ユダヤ人の対イスラエル観の変化と新しいロビー組織J STREETの活動
- 著者
- 立山 良司
- 出版者
- 独立行政法人 日本貿易振興機構アジア経済研究所
- 雑誌
- 中東レビュー (ISSN:21884595)
- 巻号頁・発行日
- vol.2, pp.103-121, 2015 (Released:2019-12-07)
- 参考文献数
- 47
The American Jewish community as a whole still remains very much supportive of Israel’s policies. Most American mainstream Jewish organizations and their leaders have hardly criticized Israel’s position regarding the occupation, settlements, and the peace process. But over the last ten years or so, different views and opinions have become more visible in the American Jewish community, as represented by J Street, a “pro-Israel and pro-peace” lobby. What has brought about this diversification in the American Jewish community over their attitude toward Israel’s policies?Many opinion surveys indicate that younger American Jews have become more critical of Israel’s policies with regard to the Palestine question and the peace process. This may be attributed to a shift in identity among young American Jews. Older American Jews tend to see Israel as democratic, progressive and peace-seeking, etc. In addition, they perceive Israel as a safe haven for Jews. But younger Jews draw from memories and impressions scene in recent events, such as the First and Second Intifada, and the military confrontations with Palestinian groups based in Gaza, all of which are perceived as morally and politically more complex than the wars Israel fought between 1948 and 1974.Communities in the Jewish diaspora try to influence the policies of their homeland in order to protect their identity and sets of values. While the American Jewish community is still strongly committed to liberal democratic values, its counterpart in Israel has leaned toward the political right and toward ethno-religious nationalism. The diffusion of identities and sets of values in both communities may bring about further shifts in the relations between the two communities.
1 0 0 0 OA ハッジ・サイヤーフ:世界歴訪による自己形成
- 著者
- Ali Ferdowsi
- 出版者
- 独立行政法人 日本貿易振興機構アジア経済研究所
- 雑誌
- 中東レビュー (ISSN:21884595)
- 巻号頁・発行日
- vol.2, pp.122-137, 2015 (Released:2019-12-07)
ハッジ・サイヤーフ(1836-1925年)は広く19世紀中葉の欧米を見聞した旅行家であり、またイラン人として最初にアメリカ合衆国の市民権を得た人物である。彼がその生涯で訪れた国や地域は順にコーカサス地方、イスタンブール、ヨーロッパ諸国、米国、日本、中国、シンガポール、ビルマ、インドなどに及ぶ。またメッカは9度巡礼しており、エジプトも数度訪れている。だが彼の本領は単なる世界旅行者というよりも、彼が卓越した旅行記作家だったところにある。本論は前半においてサイヤーフの生涯を改めて簡潔に紹介し、後半部では彼の記録から典型的な事例を4つほど引用してその個性的な自己認識と自己形成を跡付ける。それは総じて非ヨーロッパ系のアジア出身者として西欧的な「市民」概念とどう対峙し、それを自らの属性として血肉化したかを具体的に物語っている。これを読むとハッジ・サイヤーフは欧米の一流の政治家・知識人と交流を持っていたことが理解される。またサイヤーフは当時の著名な汎イスラミスト、ジャマール・アッディーン・アフガーニー(1838/9-97年)とも親交があった。最後に筆者はサイヤーフが明治維新直後の1875年に日本(横浜)を半年ほど訪れ、ハッジ・アブドッラー・ブーシェフリーなる人物と邂逅したことを紹介している。上記4番目の事例はサイヤーフが日本を訪れる直前インタビュー記事だという。(文責・鈴木均)
1 0 0 0 OA エジプトにおける軍の経済活動 ―スィースィー体制での役割―
- 著者
- 土屋 一樹
- 出版者
- 独立行政法人 日本貿易振興機構アジア経済研究所
- 雑誌
- 中東レビュー (ISSN:21884595)
- 巻号頁・発行日
- vol.2, pp.157-168, 2015 (Released:2019-12-07)
- 参考文献数
- 18
Since the second transition period started July 2013, the Egyptian armed forces have once again played a critical role in building a new political system. Although the Supreme Council of the Armed Forces (SCAF) had not come to the front this time, it controlled the transition process and succeeded in keeping the privileges of the military in both political and economic fields.This paper focuses on the economic role of the military under the regime of Abdel Fattah el-Sisi. Large scale economic activity of the military started in the mid-1970s. The military expanded its grip on the domestic economy and became one of the largest producers in Egyptian civil industry. In addition to controlling a huge business empire, the military under the Sisi administration is an entity supportive of national development goals. As the backer of the current regime, the armed forces have taken on a new responsibility as a central role player in economic development.
1 0 0 0 OA 総論: 2015年の中東地域
- 著者
- 鈴木 均 池田 明史 土屋 一樹 ダルウィッシュ ホサム 渡邊 祥子 猪口 相
- 出版者
- 独立行政法人 日本貿易振興機構アジア経済研究所
- 雑誌
- 中東レビュー (ISSN:21884595)
- 巻号頁・発行日
- vol.3, pp.2-32, 2016 (Released:2019-12-03)
1 0 0 0 OA 中東政治の変容とイスラーム主義の限界
- 著者
- 鈴木 均 内藤 正典 渡邊 祥子 ダルウィッシュ ホサム 石黒 大岳 齋藤 純 土屋 一樹
- 出版者
- 独立行政法人 日本貿易振興機構アジア経済研究所
- 雑誌
- 中東レビュー (ISSN:21884595)
- 巻号頁・発行日
- vol.1, pp.3-26, 2014 (Released:2019-12-21)
- 参考文献数
- 6
1 0 0 0 OA ポスト・アラブの春と日本の中東政策
- 著者
- Yukiko Miyagi
- 出版者
- 独立行政法人 日本貿易振興機構アジア経済研究所
- 雑誌
- 中東レビュー (ISSN:21884595)
- 巻号頁・発行日
- vol.1, pp.27-45, 2014 (Released:2019-12-21)
- 参考文献数
- 38
本稿は、中東における問題や紛争に対する日本の政策を考察し、中長期的な視野に立った日本の国益追求のためにはどのような選択肢が考えられるかを論じる。そのために、イランの核開発問題とシリアの市民戦争をケースとしてとりあげる。戦後の日本は中東での問題や紛争に対して、地域内諸国およびアメリカとの関係を同時に維持するために、双方の均衡を図る政策を打ち出してきたが、冷戦後には米国寄りの傾向が多く見られた。現在中東では、アラブの春の展望は不透明な部分が多い。日本は中東との関係において、問題や紛争の性質によっては負の遺産を抱える欧米とは一線を画した独自の政策とアプローチを打ち出すことが、中東資源国との関係の強化と拡大や中東市場の発展と安定には望ましいと考える。また同時に、今後の米国の中東における国益の変化が考えられることも要因ととらえ、本稿は冷戦期にみられたような、より均衡のとれた立場を打ち出し、より広い概念をもとに基づいた効果的なソフトパワーの行使を提唱する。
1 0 0 0 OA ロウハーニー大統領の登場から核協議の進展へ ―米国オバマ政権の対イラン外交の転換と日本―
- 著者
- 鈴木 均
- 出版者
- 独立行政法人 日本貿易振興機構アジア経済研究所
- 雑誌
- 中東レビュー (ISSN:21884595)
- 巻号頁・発行日
- vol.1, pp.46-61, 2014 (Released:2019-12-21)
- 参考文献数
- 29
The recent rapprochement between Iran and the United States after Hassan Rouhani was elected president in June 2013 may represent an important geopolitical shift that would alter the politics of the Middle East. The main purpose of this paper is to evaluate this political shift, examine whether the interim nuclear agreement between Iran and the United States would lead to some structural shifts in the Middle East, and analyze to what extent this change can be sustainable for both sides.The main Part of this paper is divided into three sections. The first section examines in detail the process of Iran’s Presidential election in June 2013, especially the sudden change of atmosphere which took place just three days before election day. The second section is devoted to analyzing the Obama administration’s shift to diplomacy with Iran. And the third section treats the on-going nuclear negotiations between Iran and P5+1, which is expected to reach a comprehensive solution.The paper argues that the dramatic shift in the US policy toward Iran is not limited to the bilateral relationships between the US and Iran, but it is related to several key issues in the Middle East, in particular to those in Syria, Iraq and Afghanistan. This changing process in Iranian politics and the path to diplomacy is profitable for Japanese national interest, and that Japan should also contribute to Iran’s return to the international community.
1 0 0 0 OA シリア問題とレバノン――2011~2013年
- 著者
- Massoud Daher
- 出版者
- 独立行政法人 日本貿易振興機構アジア経済研究所
- 雑誌
- 中東レビュー (ISSN:21884595)
- 巻号頁・発行日
- vol.1, pp.62-75, 2014 (Released:2019-12-21)
2011年に発生したアラブ世界での民衆蜂起は、市民としてのアラブ人が近代的で民主的な国家を建設しようとする努力であった。その意味でアラブ民衆蜂起が発生した主な原因はもっぱら国内要因であり、そこに地域的、国際的な介入が加わったのである。アラブ民衆蜂起はシリアでは内戦に発展し、その影響は現在周辺国にも及んでいる。シリアが内戦に至った要因を理解するためには、シリアとそれを取り巻く現状を理解するだけでなく,シリアという国家が持つ歴史、なかでもフランス委任統治期の分断統治政策の失敗、ハーフィズ・アサドによる独裁体制の構築と継続、イスラエルによる干渉といったシリア現代史の影響を検討することが重要である。シリア内戦はレバノン、ヨルダン、トルコなどの周辺国にも少なからぬ影響を与えている。シリア難民の流出は、レバノンとヨルダンにとって社会と経済の負荷となっている。またシリア国内の分断と混乱は、レバノンの国内宗派対立をも先鋭化させた。他方でシリア内戦が長期化するにともない、イスラエルによるシリアとレバノンへの干渉が懸念されるようになっている。シリア内戦およびそれに対するイスラエルの対応は、結果的にレバノンへの大きな圧力となった。今後レバノンが主権国家としての安定的な地位を維持するためには、シリア内戦への政治的な関与を避け,国内各勢力の融和および各勢力の協調による国家運営を進めることがこれまで以上に必要である。
1 0 0 0 OA 湾岸およびインド洋地域の安全保障と日本
- 著者
- 石黒 大岳
- 出版者
- 独立行政法人 日本貿易振興機構アジア経済研究所
- 雑誌
- 中東レビュー (ISSN:21884595)
- 巻号頁・発行日
- vol.1, pp.76-91, 2014 (Released:2019-12-21)
- 参考文献数
- 18
In this paper, first we look back at the activities of the JMSDF in the Indian Ocean and the Gulf for the past 10-20 years from the view-point of contributions to security in the regions, and Japan's defence and diplomatic policies. In addition we would like to consider the situation that Japan has currently been placed in, or the primary factors of the change of power balance caused by China's foreign expansion and US gradual troop reductions, and economic conditions and energy supply problems after the earthquake disaster, as well as the returning of the LDP Administration. Each of these affects Japan's defence and diplomatic policies, and Japanese approach to Gulf countries is to be precisely understood in this context.For Japan, the importance of relationships with Gulf countries will surely increase in the foreseeable future. However the immediate addition of the JMSDF's force in the Indian Ocean and the Gulf Region is difficult. So Japan's role in regional security will probably be depending on the licensing of technology to India and Gulf countries, plus the construction of collaborative systems devoted to the training and support of highly proficient personnel . China will have a competitive relationship with Japan over access to the energy supply sources and the markets in Gulf countries, and it will be necessary to employ such systems for the purpose of international trust building and preventing of any free-ride.
1 0 0 0 OA 「アラブの春」後の移行期過程 ─帰結を分ける諸要因―
- 著者
- 池内 恵
- 出版者
- 独立行政法人 日本貿易振興機構アジア経済研究所
- 雑誌
- 中東レビュー (ISSN:21884595)
- 巻号頁・発行日
- vol.1, pp.92-126, 2014 (Released:2019-12-21)
Diverging outcomes are unfolding in the post-Arab Uprising countries’ transitional processes. In January 2014, Tunisia successfully adopted a new constitution based on a consensus of the opposing political parties and factions. In contrast, Egypt abolished one constitution and hastily instituted another in a time span of slightly more than a year. Yemen has announced the final document of the National Dialogue Conference in the same month. Libyans finally voted for the long awaited and disputed elections of the Constitutional Drafting Committee in February 2014.The paper picks up three factors which seem to be influential in determining the modality of transitional political process in the four Post-Arab spring countries. The first is the initial conditions of the transitional politics.. Differences in the way the previous regimes collapsed are analyzed to illuminate the continuity and break of the ruling institutions and state apparatus. The second factor is the type of the interim government. In line with Shain and Linz typology, provisional, power-sharing, caretaker, and international interim government models are applied to clarify the types of interim governments in each four countries’ different phases in transitional politics. The third is the “rules of the game,” particularly those pertaining to the constitutional process. Who set what kind of rules and how are to be considered in each of four countries and possible influences of each set of the rules of the game to the diverging results of the transitional politics are considered.
- 著者
- 児玉 由佳
- 出版者
- 独立行政法人 日本貿易振興機構アジア経済研究所
- 雑誌
- アフリカレポート (ISSN:09115552)
- 巻号頁・発行日
- vol.60, pp.40, 2022-09-01 (Released:2022-09-01)
1 0 0 0 OA 任期半ばに達したウルグアイのラカジェ・ポウ政権-右派連合の中間評価
- 著者
- 中沢 知史
- 出版者
- 独立行政法人 日本貿易振興機構アジア経済研究所
- 雑誌
- ラテンアメリカ・レポート (ISSN:09103317)
- 巻号頁・発行日
- vol.39, no.1, pp.32-45, 2022 (Released:2022-07-31)
- 参考文献数
- 25
ウルグアイで2020年3月に成立したラカジェ・ポウ大統領率いる右派連合政権は、2019年大統領選挙決選投票において5党による選挙協力を行って勝利して以降、安定して政権を運営している。本稿では、任期半ばにさしかかるラカジェ・ポウ政権について、2019年選挙の過程から2022年3月27日実施の国民投票までを記述し、その施政の中間評価を行う。まず第1節では、右派連合政権の成立過程を辿る。つぎに第2節では、ラカジェ・ポウ政権最初の政策を、労働組合との関係、コロナ対策、対外関係、治安政策、そして緊急法の制定に分けて概括する。そして第3節では、任期前半における最大の政治イベントとなった国民投票について、最大の争点となった治安問題の観点から述べ、結果を分析する。最後に、国民投票結果を受けた任期後半および次期大統領選の展望について述べる。本稿を通じて、これまで先行研究で指摘されてきたウルグアイ有権者の投票行動と似た傾向が観察され、高度に制度化された政党政治が堅持されていることを示す。
1 0 0 0 OA チリにおける近年の政治社会変動とボリッチ政権-代表制の危機という視点から
- 著者
- 三浦 航太
- 出版者
- 独立行政法人 日本貿易振興機構アジア経済研究所
- 雑誌
- ラテンアメリカ・レポート (ISSN:09103317)
- 巻号頁・発行日
- vol.39, no.1, pp.1-17, 2022 (Released:2022-07-31)
- 参考文献数
- 9
2021年12月に行われたチリの大統領選挙の結果、急進左派連合のガブリエル・ボリッチが勝利し、1990年の民主化以来初めてとなる、左右二大連合に属さない勢力による政権が誕生した。本稿では、代表制の危機という視点から、2010年代のチリの政治社会変動、新しい政治勢力が台頭した2021年選挙、今後のボリッチ政権の課題について考察することを目的とする。チリは、既存の左右二大連合政治に対する不信を起点に、投票率の低下、抗議行動の活発化、2019年のチリ史上最大級の抗議行動「社会の暴発」を経験してきた。さらに近年では、代表制の危機の表れとしてポピュリズム的性格をもった政治勢力の出現もみられ、新しい政治構図のもとで2021年大統領・議会選挙が行われた。ボリッチ新政権には、新自由主義からの転換という大きな目標があるが、その目標の実現のためには、いまだ解消されない代表制の危機という課題にも同時に取り組むことが求められている。
- 著者
- 佐藤 千鶴子
- 出版者
- 独立行政法人 日本貿易振興機構アジア経済研究所
- 雑誌
- アフリカレポート (ISSN:09115552)
- 巻号頁・発行日
- vol.60, pp.23, 2022-02-26 (Released:2022-02-26)