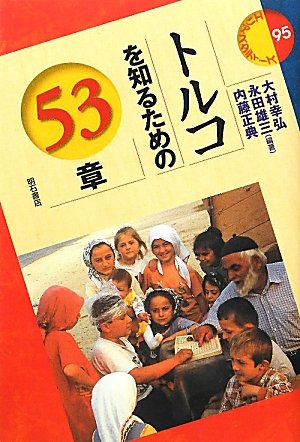- 著者
- 内藤 正典
- 出版者
- 公益社団法人 日本地理学会
- 雑誌
- 地理学評論 (ISSN:02896001)
- 巻号頁・発行日
- vol.60, no.2, pp.134-163, 1987
- 被引用文献数
- 1
クフレイン村は,ダマスカスの近郊に広がるオアシスの東端,シリア沙漠との境に位置する人口約1,600人の農村である.年間降水量100mmのこの村では,灌漑による夏季の疏菜と降雨による冬季の小麦栽培がおこなわれてきた.しかし1960年代以降,灌漑用水の不足と農地改革による経営規模の縮小とによって農家経営は行き詰まり,耕作放棄が進んでいる.この傾向は,オアシスの東半分を占めるステップ地帯の諸村に共通にみられる.数千年にわたって,都市民に食糧を供給してきた灌漑農業の歴史は,独立後の40年というわずかな問に崩壊の危機を迎えた.危機を招来した直接の原因は,首都への人口集中に伴う周辺農村の急速な都市化と,経済効果の伴わない農地改革の2点にある.そしてこれらの問題は,国家統合のために不可欠の政策が実現される過程で顕在化した.オスマン帝国時代から都市権力の中枢にあった名望家地主層の追放,およびマイノリティー・グループによるセクタリアニズムの解消という2つの政策がそれである.本稿は,2つの国家統合政策が,その実現過程で,近郊農村をどのように空間的に編成し,結果として農村の崩壊をもたらしたのかを分析した.第1の政策は,エジプトとの連合が成立した1958年に農地改革を実施し,名望家地主を追放することよって実現した.しかし農地改革は,都市権力の交代の副産物にすぎなかった.その後1963年のバアス革命をへて,1970年まで続く政権抗争では,-社会主義を標榜するバアス党内の権力抗争であったにもかかわらず-農民が革命の主体となることはなかった.1970年に成立した地方山村出身のアラウィー派政権も,農民組合員に対する特権の供与を通じて,上からの組織化を進めているが,農村全体の基盤整備には消極的である.第2のセクタリアニズムの解消は,アラウィー派政権の樹立によって一層困難となった.国家権力の中枢が位置する首都で,多数を占めるスンニー派住民に対抗するために,少数民族・宗派集団のオアシス農村への定住は黙認されている.このため,水需要の増大から灌漑用水は極度に不足し,既存の灌漑設備はオアシス内への集落の展開によって破壊された.農地改革によって村落の社会・経済構造が一変し,しかも灌漑農業の限界地に位置するクフレイン村では,権力による空間編成の過程で発生したさまざまな矛盾が,最も明示的なかたちで農村自体の存立を脅かすことになったのである.
5 0 0 0 OA <論説>地誌の終焉
- 著者
- 内藤 正典
- 出版者
- 法政大学地理学会
- 雑誌
- 法政地理 = JOURNAL of THE GEOGRAPHICAL SOCIETY OF HOSEI UNIVERSITY (ISSN:09125728)
- 巻号頁・発行日
- vol.22, pp.32-43, 1994-03-24
3 0 0 0 OA ダマスカス・オアシス,クフレイン村の崩壊
- 著者
- 内藤 正典
- 出版者
- The Association of Japanese Geographers
- 雑誌
- Geographical review of Japan, Series B (ISSN:02896001)
- 巻号頁・発行日
- vol.60, no.2, pp.134-163, 1987-12-30 (Released:2008-12-25)
- 参考文献数
- 47
- 被引用文献数
- 1 1
クフレイン村は,ダマスカスの近郊に広がるオアシスの東端,シリア沙漠との境に位置する人口約1,600人の農村である.年間降水量100mmのこの村では,灌漑による夏季の疏菜と降雨による冬季の小麦栽培がおこなわれてきた.しかし1960年代以降,灌漑用水の不足と農地改革による経営規模の縮小とによって農家経営は行き詰まり,耕作放棄が進んでいる.この傾向は,オアシスの東半分を占めるステップ地帯の諸村に共通にみられる.数千年にわたって,都市民に食糧を供給してきた灌漑農業の歴史は,独立後の40年というわずかな問に崩壊の危機を迎えた.危機を招来した直接の原因は,首都への人口集中に伴う周辺農村の急速な都市化と,経済効果の伴わない農地改革の2点にある.そしてこれらの問題は,国家統合のために不可欠の政策が実現される過程で顕在化した.オスマン帝国時代から都市権力の中枢にあった名望家地主層の追放,およびマイノリティー・グループによるセクタリアニズムの解消という2つの政策がそれである.本稿は,2つの国家統合政策が,その実現過程で,近郊農村をどのように空間的に編成し,結果として農村の崩壊をもたらしたのかを分析した.第1の政策は,エジプトとの連合が成立した1958年に農地改革を実施し,名望家地主を追放することよって実現した.しかし農地改革は,都市権力の交代の副産物にすぎなかった.その後1963年のバアス革命をへて,1970年まで続く政権抗争では,-社会主義を標榜するバアス党内の権力抗争であったにもかかわらず-農民が革命の主体となることはなかった.1970年に成立した地方山村出身のアラウィー派政権も,農民組合員に対する特権の供与を通じて,上からの組織化を進めているが,農村全体の基盤整備には消極的である.第2のセクタリアニズムの解消は,アラウィー派政権の樹立によって一層困難となった.国家権力の中枢が位置する首都で,多数を占めるスンニー派住民に対抗するために,少数民族・宗派集団のオアシス農村への定住は黙認されている.このため,水需要の増大から灌漑用水は極度に不足し,既存の灌漑設備はオアシス内への集落の展開によって破壊された.農地改革によって村落の社会・経済構造が一変し,しかも灌漑農業の限界地に位置するクフレイン村では,権力による空間編成の過程で発生したさまざまな矛盾が,最も明示的なかたちで農村自体の存立を脅かすことになったのである.
3 0 0 0 トルコからドイツへの出稼ぎ移民の社会・文化変容に関する研究
- 著者
- 内藤 正典 チョルズ ジョシュクン 間 寧 足立 典子 足立 信彦 林 徹 関 啓子 矢澤 修次郎 CORUZ Coskun ジョシュクン チョルズ ショシュクン チョルズ ルーシェン ケレシュ CEVAT Geray RUSEN Keles
- 出版者
- 一橋大学
- 雑誌
- 国際学術研究
- 巻号頁・発行日
- 1994
本研究は、過去30年以上にわたって、ドイツを始めとする西ヨーロッパ諸国に移民してきたトルコ人を対象に、彼らがヨーロッパに生活する上で直面する社会的・文化的諸問題とは何であるのかを明らかにした。本研究の成果として特筆すべき点は、移民を受け入れてきたホスト社会(あるいは国家)が発見した移民問題と移民自身が発見した移民問題との間には、重大な認識上の差異が存在することを実証的に明らかにしたことにある。トイツにおいて、トルコ系移民の存在が移民問題として認識されたのは、1973年の第一次石油危機以降のことであり、そこでは、移民人口の増大が、雇用を圧迫するという経済的問題と同時に、異質な民族の増加が文化的同質性を損なうのではないかという文化的問題とが指摘されてきた。他方、トルコ系移民の側は、ホスト社会からの疎外及び出自の文化の維持とホスト社会への統合のあいだのジレンマが主たる問題として認識されていた。この両者の乖離の要因を探究することが、第二年度及び最終年度の主要な課題となった。その結果、ホスト社会側と移民側との争点は、ホスト国の形成原理にまで深化していることが明らかとなった。ドイツの場合、国民(Volk)の定義に、血統主義的要素を採用しており、血統上のドイツ国民と単に国籍を有するドイツ国民という二つの国民が混在することが最大の争点となっているが、ドイツの研究者及び移民政策立案者も、この点を争点と認識することを回避していることが明らかとなった。このような状況下では、移民の文化継承に関して、移民自らホスト社会への統合を忌避しイスラーム復興運動に参加するなど、異文化間の融合は進まず、むしろ乖離しつつあるという興味深い結果を得た。さらに、研究を深化させるために、本研究では、ドイツ以外のヨーロッパ諸国に居住するトルコ系移民をめぐる問題との比較検討を行った。フランスでは、トイツのような血統主義的国民概念が存在せず、国民のステイタスを得ることも比較的容易である。しかし、フランス共和国の主要な構成原理である政教分離原則(ライシテ)に対して、ムスリム移民のなかには強く反発する勢力がある。社会システムにいたるまでイスラームに従うことを求められるムスリム社会と信仰を個人の領域にとどめることを求めるフランス共和国の理念との相克が問題として表出するのである。この現象は、移民を個人として統合することを理念とするフランスとムスリムであり、トルコ人であることの帰属意識を維持する移民側との統合への意識の差に起因するものと考えられる。即ち、共和国理念への服従を強いるフランス社会の構成原理が、それに異論を唱える移民とのあいだで衝突しているのであり、そこでは宗教が主要な争点となっていることが明らかになった。さらに、本研究では多文化主義の実践において先進的とされるオランダとドイツとの比較研究を実施した。オランダの場合は、制度的に移民の統合を阻害する要因がほとんど存在しないことから、トルコ系移民の場合も、比較的ホスト社会への統合が進展している。しかし、オランダの採る多極共存型民主主義のモデルは、移民が独自の文化を維持することを容認する。そのため、麻薬や家族の崩壊など、オランダ社会に存在する先進国の病理に対して、ムスリム・トルコ系移民は強く反発し、むしろ自らホスト社会との断絶を図り、イスラーム復興運動に傾倒していく傾向が認められる。以上のように、ドイツ、フランス、オランダの比較研究を通じて、いずれの事例も、トルコ系移民のホスト社会への統合は、各国の異なる構成原理に関する争点が明示されてきたことによって、困難となっていることが明らかにされた。本研究は、多民族・多文化化が事実として進行している西ヨーロッパ諸国において、現実には、異なる宗教(イスラーム)や異なる民族・文化との共生を忌避する論理が、きわめて深いレベルに存在し、かつ今日の政治・経済においてもなお、それらが表出しうるものであることを明らかにすることに成功した。
1 0 0 0 トルコを知るための53章
- 著者
- 大村幸弘 永田雄三 内藤正典編著
- 出版者
- 明石書店
- 巻号頁・発行日
- 2012
1 0 0 0 OA 総論(1): 2014年の中東地域/総論(2): 中東地域との経済関係の深化に向けて
- 著者
- 鈴木 均 岡田 江平 石黒 大岳 土屋 一樹 ダルウィッシュ ホサム 池田 明史 渡邊 祥子 内藤 正典
- 出版者
- 独立行政法人 日本貿易振興機構アジア経済研究所
- 雑誌
- 中東レビュー (ISSN:21884595)
- 巻号頁・発行日
- vol.2, pp.2-42, 2015 (Released:2019-12-07)
- 参考文献数
- 13
1 0 0 0 OA 中東政治の変容とイスラーム主義の限界
- 著者
- 鈴木 均 内藤 正典 渡邊 祥子 ダルウィッシュ ホサム 石黒 大岳 齋藤 純 土屋 一樹
- 出版者
- 独立行政法人 日本貿易振興機構アジア経済研究所
- 雑誌
- 中東レビュー (ISSN:21884595)
- 巻号頁・発行日
- vol.1, pp.3-26, 2014 (Released:2019-12-21)
- 参考文献数
- 6
1 0 0 0 OA 多文化・多民族共生のための研究視角
- 著者
- 内藤 正典
- 出版者
- 公益社団法人 日本地理学会
- 雑誌
- 地理学評論 Ser. A (ISSN:00167444)
- 巻号頁・発行日
- vol.70, no.11, pp.749-766, 1997-11-01 (Released:2008-12-25)
- 参考文献数
- 14
- 被引用文献数
- 1 2
本稿は山本健見による筆者の著書への批判に反論することを通じて,多民族・多文化の共生をめぐる諸問題に対する研究視角を検討したものである.冷戦体制の崩壊とともに,イスラムとイスラム社会を共産主義に代わる新たな脅威とする言説が西欧諸国に蔓延している.しかし,多くのムスリム移民が定住している西ヨーロッパ諸国において,この言説は多文化の共生を危機に陥れる危険をはらんでいる.宗教や民族の相違が直ちに対立や紛争をもたらすとする言説の問題点とは何であるのか.移民自身からの異議申立ては何を争点としているのか.異文化との共存をめぐるマスメディアの功罪とは何か.そして,移民によって国家の基本原理が問われていることをどのように評価すべきか.本稿では,ドイツにおけるトルコ人移民の問題を通して,これらの課題を検討する際に必要な視角を具体的に提示した.
1 0 0 0 IR 多文化・多民族共生のための研究視角
- 著者
- 内藤 正典
- 出版者
- 学術雑誌目次速報データベース由来
- 雑誌
- 地理学評論. Ser. A (ISSN:00167444)
- 巻号頁・発行日
- vol.70, no.11, pp.749-766, 1997-11
- 被引用文献数
- 1
本稿は山本健見による筆者の著書への批判に反論することを通じて,多民族・多文化の共生をめぐる諸問題に対する研究視角を検討したものである.冷戦体制の崩壊とともに,イスラムとイスラム社会を共産主義に代わる新たな脅威とする言説が西欧諸国に蔓延している.しかし,多くのムスリム移民が定住している西ヨーロッパ諸国において,この言説は多文化の共生を危機に陥れる危険をはらんでいる.宗教や民族の相違が直ちに対立や紛争をもたらすとする言説の問題点とは何であるのか.移民自身からの異議申立ては何を争点としているのか.異文化との共存をめぐるマスメディアの功罪とは何か.そして,移民によって国家の基本原理が問われていることをどのように評価すべきか.本稿では,ドイツにおけるトルコ人移民の問題を通して,これらの課題を検討する際に必要な視角を具体的に提示した.
1 0 0 0 東西南北 アフガニスタンの和解と平和構築
- 著者
- 内藤 正典
- 出版者
- 渋沢栄一記念財団
- 雑誌
- 青淵 (ISSN:09123210)
- 巻号頁・発行日
- no.766, pp.16-18, 2013-01
1 0 0 0 OA 中東における紛争予防に関する学際的研究の構築
中東の紛争では、中東の内外からの外部勢力の介入が紛争の長期化をもたらす実態が明らかになった。また、紛争防止策として、(1)国家再建時にすべての勢力をそのプロセスに包含すること、(2)イスラーム社会組織が果たす社会サービスの分配機能への着目、(3)難民や避難民の保護と共生のしくみを域内で構築すること、(4)民主化への移行期は、治安・雇用の創出・市民社会の政治参加への拡大などの課題への舵取りが紛争の再燃防止になること、などが挙げられる。
1 0 0 0 中東とソ連の都市問題とエスニシティの比較研究
- 著者
- 山内 昌之 ERGENC Ozer KHALIKOV A.K GRAHAM Willi ERCAN Yavuz DUMONT Paul QUELQUEJAY C ALTSTADT Aud PAKSOY Hasan 福田 安志 内藤 正典 新井 政美 小松 久男 栗生沢 猛夫 坂本 勉 WILLIAM Grah PAUL Dumont CHANTAL Quel AUDREY Altst HASAN Paksoy
- 出版者
- 東京大学
- 雑誌
- 国際学術研究
- 巻号頁・発行日
- 1989
この共同研究が目指したものは、中東とソ連における都市とエスニシティの在り方を比較検討しながら、近現代の急速な都市化にともなう環境、人間と社会との関係、個人と集団の社会意識の変容を総合的、多角的に解明しようとするところにあった。当該地域におけるエスニシティの多様性と連続性を考慮するとき、これは、集団間の反目、矛盾が先鋭で具体的な形をとって現われてくる都市という生活の場においてエスニシティの問題を検討することであり、またエスニシティ、民族、宗教問題を媒介変数としてトランスナショナルな視角から都市の在り方と変容を検討することでもあった。本共同研究の参加者は以上の問題意識を踏まえ、まず第1に、タシケント、モスクワ等のソ連の都市と、イスタンブ-ル、テヘラン、カイロ、エルサレム等の中東の都市において現地調査を行なった。これらの諸都市での調査においては現地人研究者の協力を得た上で、都市問題の現状とエスニシティを異にする住民相互間の衝突、反目の具体的事例をつぶさに観察した。また現地調査と平行して、現地人研究者との間で意見の交換を行ない、当該地域での研究状況の把握、現地人研究者との交流に努め、さらに必要な資料の収集にも当たった。第2に、ソ連、中東世界での都市化にともなうエスニシティ、民族、宗教問題を分析した。モスクワ国家による都市カザンへの支配の実態を検証し、また経済開発によるソ連中央アジアでの居住条件の変化と、エスニシティ・グル-プの変容についての相関関係を検討した。さらにイスラエルにおいては、ソ連からのユダヤ人移民にともなうユダヤ都市の拡大・拡散による、アラブ人とユダヤ人の文化接触の問題を取り上げた。次いで都市を基盤とした民族主義イデオロギ-の形成・展開の側面についても検討を加えた。トルコにおけるトルコ民族主義の展開過程とその周辺トルコ系地域への影響を、歴史的事実を踏まえつつ分析した。同時にソ連中央アジアにおける非ロシア系民族の間での民族意識の形成過程を検証し、イスラ-ムや、アルメニア正教、ギリシャ正教の復興が民族的アイデンティティに及ぼす影響を検討した。またアゼルバイジャンでの文学活動が民族意識の形成に与えた影響を分析した。これらの事例研究によって、中東とソ連における都市問題とエスニシティをめぐる問題の相関関係を明らかにし、また都市化にともなう社会意識の変容を解明することに努めた。第3に、経済と都市間ネットワ-クの側面から都市のエスニシティの問題を検討した。アレッポの都市経済におけるアルメニア人、クルド人の役割を検討した。またドイツへのトルコ人労働移民の問題を取り上げ、出稼ぎ者、帰還者双方が引き起こす都市問題が、二地域の関係の中で明らかにされた。さらにイラン諸都市とイスタンブ-ルの間の絨毯交易に従事していたアゼルバイジャン人に注目しながら、当該地域におけるエスニシティと都市経済、都市間の関係を把握した。アラビア半島諸都市における通商活動も取り上げ、アラブ世界の都市間通商ネットワ-クにおけるインド人、ペルシャ人の役割を分析した。次いでイランや中央アジアからのメッカ巡礼を分析することを通し、宗教的側面からも都市間ネットワ-クの検討を行なった。これらの研究により、当該地域における経済と宗教を軸とする都市間ネットワ-クとエスニシティの連続性を明らかにすることに努めた。第4に、総合的、多角的研究の必要性から都市とエスニシティ問題の持つ普遍的な性格に着目し、研究交流の空間的幅を広げ、中東、ソ連の現地研究者はもちろんのこと欧米諸国の研究者との間でも共同研究や比較研究を行なった。さらにストラスブ-ルにおいて日本とフランスの研究者を中心に、ソ連と中東の民族問題に関する国際シンポジウムを開催するなど、これまでの研究成果に基づいた研究者相互間の交流を推進した。この共同研究は、湾岸危機やソ連邦の解体など当該地域をめるぐる急激な変動の渦中に実施されたにもかかわらず、比較の手法を用い都市という場におけるエスニシティの問題を解明し、都市の在り方と変容を明らかにする上で大きな成果をあげることができたと確信している。