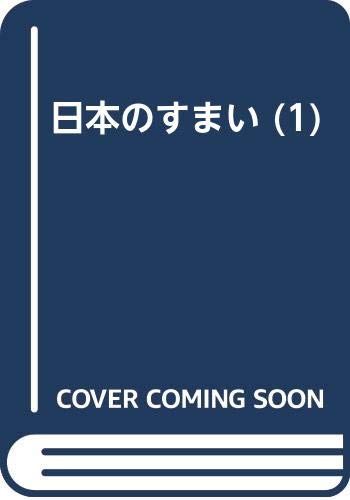- 著者
- 椎名 秀一朗 寺谷 卓馬 小尾 俊太郎 佐藤 新平 小池 幸宏 段 佳之 赤松 雅俊 藤島 知則 吉田 英雄 加藤 直也 今井 康雄 今村 雅俊 浜村 啓介 白鳥 康史 小俣 政男
- 出版者
- The Japan Society of Hepatology
- 雑誌
- 肝臓 (ISSN:04514203)
- 巻号頁・発行日
- vol.41, no.1, pp.24-30, 2000-01-25
- 被引用文献数
- 27 24
経皮的ラジオ波焼灼療法は, 病変に挿入した電極の周囲をラジオ波により誘電加熱し, 肝腫瘍を壊死させる新しい治療法である. 我々は, Radionics社のcool-tip型電極を用い, 肝細胞癌30例61病変を治療した. 病変の存在部位等を理由に経皮的ラジオ波焼灼療法を断念した例はなかった. 効果判定のために施行したCTでは, 治療を行った病変は最終的にはすべて造影されなくなり, 完全壊死に陥ったと評価された. Cool-tip型電極を用いた経皮的ラジオ波焼灼療法は, 経皮的局所療法で治療されてきたほとんどの症例に施行可能であり, 経皮的エタノール注入療法や経皮的マイクロ波凝固療法と比べ, 治療セッション数を少なくし入院期間を短縮できるものと考えられた. 近い将来, 肝癌治療の主流になると思われる.
2 0 0 0 IR 米国著作権法におけるオンライン送信 : 頒布権との関係を中心に
- 著者
- 鳥澤 孝之
- 出版者
- 筑波法政学会
- 雑誌
- 筑波法政 (ISSN:03886220)
- 巻号頁・発行日
- no.53, pp.137-151, 2012-09
- 著者
- 鳥澤 孝之
- 出版者
- 日本知的財産協会
- 雑誌
- 知財管理 (ISSN:1340847X)
- 巻号頁・発行日
- vol.61, no.12, pp.1805-1814, 2011-12
デジタル化・ネットワーク化による技術の進展は、著作物の流通を著しく促進していることから、著作権制度に大きな影響を与えている。特にコンテンツの利用においては、ビデオカセット、DVDなどのパッケージソフトウェア、電子書籍等について著作権保護を図ると同時に、公益性の観点から著作権者の排他的権利を制限することが必要になる。「その2」では、わが国の著作権制限規定の適用の状況について考察し、著作権制度の今後の課題について提言する。
2 0 0 0 IR 著作物の頒布及び上映における著作権制度の課題(その1)コンテンツの著作権保護
- 著者
- 鳥澤 孝之
- 出版者
- 日本知的財産協会
- 雑誌
- 知財管理 (ISSN:1340847X)
- 巻号頁・発行日
- vol.61, no.11, pp.1651-1671, 2011-11
デジタル化・ネットワーク化による技術の進展は、著作物の流通を著しく促進していることから、著作権制度に大きな影響を与えている。特にコンテンツの利用においては、ビデオカセット、DVDなどのパッケージソフトウェア、電子書籍等について著作権保護を図ると同時に、公益性の観点から著作権者の排他的権利を制限することが必要になる。「その1」では、わが国の著作権制度について、映画の著作物などのコンテンツを中心に、著作物の頒布と上映に係る権利の変遷や、条約、外国法との比較などを通して考察する。
2 0 0 0 OA 大学図書館の研究支援
- 著者
- 加藤 信哉
- 巻号頁・発行日
- 2013-08-08
平成25年度日本薬学図書館協議会研究集会 於:愛知学院大学楠元キャンパス 2013/8/8
2 0 0 0 OA 佐賀県暴徒征討報告書
- 出版者
- [製作者不明]
- 巻号頁・発行日
- 1874
2 0 0 0 IR 経済システム分析の予備概念
- 著者
- 神武 庸四郎
- 出版者
- 一橋大学
- 雑誌
- 経済学研究 (ISSN:04534751)
- 巻号頁・発行日
- no.47, pp.147-200, 2005
2 0 0 0 IR 社会的な場とコミュニケーション構造
- 著者
- 神武 庸四郎
- 出版者
- 一橋大学
- 雑誌
- 一橋論叢 (ISSN:00182818)
- 巻号頁・発行日
- vol.131, no.6, pp.535-553, 2004-06-01
2 0 0 0 IR 歴史の構造
- 著者
- 神武 庸四郎
- 出版者
- 一橋大学
- 雑誌
- 一橋大学研究年報. 経済学研究 (ISSN:04534751)
- 巻号頁・発行日
- vol.42, pp.3-42, 2000-10-10
- 著者
- Kamitake Yoshiro
- 出版者
- 一橋大学
- 雑誌
- Hitotsubashi journal of economics (ISSN:0018280X)
- 巻号頁・発行日
- vol.50, no.2, pp.75-86, 2009-12
In the creation of a new nomenclature for economic systems theory, Nicklas Luhmann's sociological conceptualism may sometimes perform a heuristic role. In particular, the concepts of 'autopoiesis system' and 'observation of observations' can be extremely useful for the analysis of a far-reaching constellation of various economic concepts. This study develops the elementary terminology of metaeconomics and economic systems theory, and emphasizes the significance of the 'observation of observations'. In most cases when several fundamental concepts need to be logically constructed, the corresponding mathematical symbols and notions may often be utilized as the means for representing their formal functions. Amongst others, 'category' is the most important, because it can formalize the structure of economic systems and meta-observations from the viewpoint of logical foundations.
- 著者
- 神武 庸四郎
- 出版者
- 一橋大学
- 雑誌
- Hitotsubashi journal of economics (ISSN:0018280X)
- 巻号頁・発行日
- vol.49, no.2, pp.133-147, 2008-12
In preparing theoretical tools to analyze economic systems we need several fundamental concepts that are often applied in various scientific investigations outside economic studies. Amongst others, the concept of autopoiesis, which was introduced by Niklas Luhmann into his sociological systems theory, is the most important in constructing a theoretical model to explain the working of economic systems. An autopoietic system may be regarded as the functional core by which other elementary concepts such as homeostasis, machinery, corporate system and social entropy can be logically connected. In conclusion, all economic systems are contained in distinct social systems of autopoietic character and incorporated with them as a subsystem or partially independent system.
2 0 0 0 IR 大河内暁男「産業革命期経営史研究」
- 著者
- 神武 庸四郎
- 出版者
- 岩波書店
- 雑誌
- 経済研究 (ISSN:00229733)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, no.4, pp.p381-383, 1980-10
- 著者
- 神武 庸四郎
- 出版者
- 公益財団法人史学会
- 雑誌
- 史學雜誌 (ISSN:00182478)
- 巻号頁・発行日
- vol.97, no.9, 1988-09-20
2 0 0 0 貧困と社会病理 : 暴力,自殺
- 著者
- 川野 健治
- 出版者
- 一般社団法人日本発達心理学会
- 雑誌
- 発達心理学研究 (ISSN:09159029)
- 巻号頁・発行日
- vol.23, no.4, pp.395-403, 2012-12-20
本稿の目的は,暴力と自殺を通して貧困について考えることである。ただし,社会的排除を強めることになりかねないので,暴力と自殺の共通性を仮定することには慎重でありたい。貧困は,アノミー論や内的衝動論が示すように,個体の暴力発生の確率を高める側面をもっている。しかし,そればかりではなく,児童虐待,配偶者間暴力,犯罪の側面からみると,暴力の方向性に影響を与えている可能性がある。一方,自殺については,景気変動との関係は指摘されており,理論的な説明も試みられている。しかし,社会経済状況やそれに基づく社会資源の不足を指標とした貧困と自殺関連行動との関係性についての実証的研究では,一貫した結果は得られていない。暴力と自殺を通して見出される貧困の特徴とは,解消すべき内的な心理状態を生み出すものであり,その発露に対する防御因子,たとえば家族との適切な交流とか,支援・サービスの利用とか,安定した住環境とか,教育の機会を剥奪するものであった。しかし,逆にいえば,貧困に注目することで,暴力や自殺の発生を規則的に把握することができる。ニッチとしての貧困という視点からの研究を進めることで,これらの社会病理を管理する手がかりを得られるのではないだろうか。
- 著者
- 橋本 高志良 堀場 匠一朗 江藤 正通 津邑 公暁 松尾 啓志
- 雑誌
- 情報処理学会論文誌コンピューティングシステム(ACS) (ISSN:18827829)
- 巻号頁・発行日
- vol.6, no.4, pp.58-71, 2013-10-30
マルチコア環境では,一般的にロックを用いて共有変数へのアクセスを調停する.しかし,ロックには並列性の低下やデッドロックの発生などの問題があるため,これに代わる並行性制御機構としてトランザクショナル・メモリが提案されている.この機構においては,アクセス競合が発生しない限りトランザクションが投機的に実行されるため,一般にロックよりも並列性が向上する.しかし,Read-after-Readアクセスが発生した際に投機実行を継続した場合,その後に発生するストールが完全に無駄となる場合がある.本稿では,このような問題を引き起こすRead-after-Readアクセスを検出し,それに関与するトランザクションをあえて逐次実行することで,全体性能を向上させる手法を提案する.シミュレーションによる評価の結果,提案手法により16スレッド並列実行時において最大53.6%,平均15.6%の高速化が得られることを確認した.
2 0 0 0 OA “Human Rights”と“droits de l'homme”の含意をめぐって
- 著者
- 樋口 陽一
- 出版者
- 日本学士院
- 雑誌
- 日本學士院紀要 (ISSN:03880036)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, no.2, pp.47-63, 2002 (Released:2007-06-22)
Quant au terme de“droits de l'homme”, notion clé du constitutionnalisme contemporain, it faut bien distinguer entre les deux. Les droits de l'homme lato sensu peuvent se définir comme une revendication, regardée légitime, pour la possibilité de mener une vie d'une façon humaine. Le terme anglais Human Rights aurait d'ailleurs cette résonnance. Or, queue est la façon humaine de mener une vie? La réponse dépendrait du contenu de l'adjectif “humain”, et elle serait nécessairement variable d'une culture à l'autre. À l'extrême, être tout dévoué à la communauté à laquelle on appartient, pourrait être regardé comme la manière la plus “humaine”de vivre dans telle ou telle société.S'agissant des droits de l'homme stricto sensu, ils présupposeraient, comme titulaire des droits, l'individu“doppelfrei”, libéré à la fois de l'oppression et de la protection des corps statutaire et féodal. Les droits de l'homme, entendus dans ce sens strict, sont les produits historiques de la modernité individualiste d'origine occidentale. Ile ne peuvent pas être dissociés de la notion de l'individu qui se décide et qui assume la conséquence de sa propre décision, tandis que les droits de l'homme lato sensu pourraient s'adapter à une conception plus on moms communautariste.Les droits de l'homme stricto sensu exige ainsi une manière de vivre qui semblerait, du point de vue de certaines cultures, être plutôt“inhumaine”. Même au sein de la zone culturelle occidentale, la croyance en la vertue de l'individu se trouve de moins en moins certain, et la tentation même à la démission de l'individu risque de se propager (“Escape from Freedom”).Ainsi, un sceptisme à l'égard de la notion de l'homme titulaire des droits de l'homme stricto sensu fermente, depuis des decennies, dans le milieu intellectuel. L'accusation est lancée surtout del apart du femminisme et du multiculturalisme d' après laquelle la notion même des droits de l'homme serait anachronique et dépassée.Tout en respectant la pluralité des cultures en général, comment défendre le noyau essentiel des droits de l'homme, la liberté reconnue à chacune et à chacun de choisir sa propre identité? La culture des droits de l'homme peut se concilier avec l'exigence légitime de la pluralité des cultures, tant que ces dernières acceptent ce noyau dur. Or, il ya bien des cultures qui refusent, au nom de leur tradition ou de leur identité collective, la prémisse même d'une coexistence avec la culture des droits de l'homme. Le véritable enjeu émerge ainsi.
2 0 0 0 OA 福井県丹生郡城崎村要覧
- 出版者
- 城崎村
- 巻号頁・発行日
- vol.大正2年, 1914