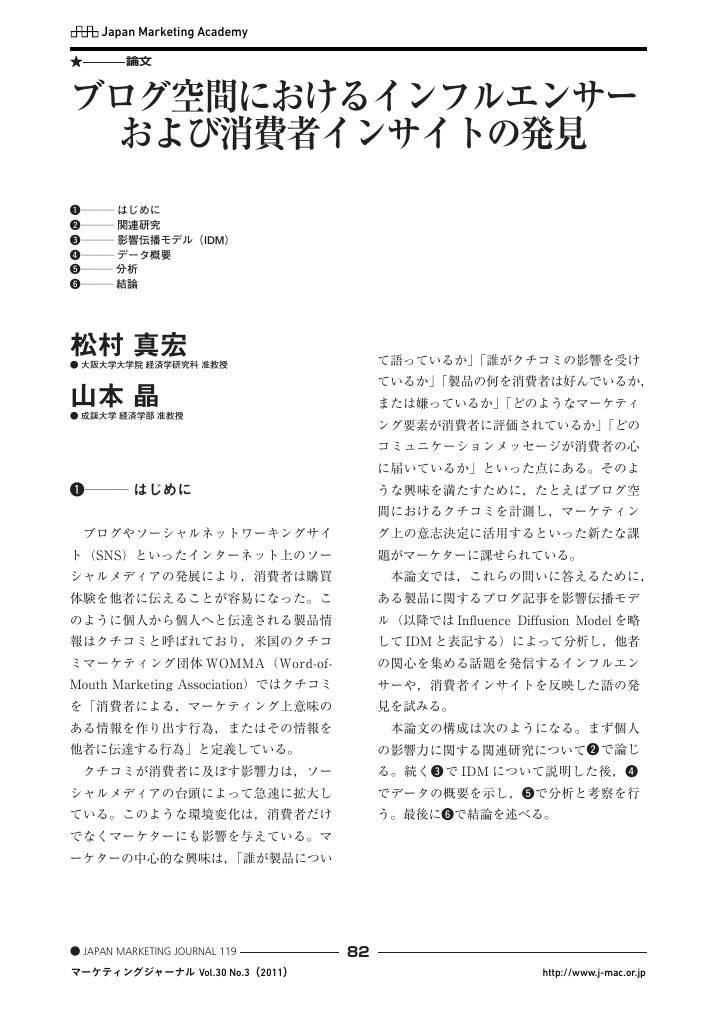2 0 0 0 OA 全身入浴またはシャワー浴の入浴習慣がその後のHSP入浴法に及ぼす影響
- 著者
- 伊藤 要子 石澤 太市 多田井 幸揮 綱川 光男
- 出版者
- 一般財団法人 日本健康開発財団
- 雑誌
- 日本健康開発雑誌 (ISSN:2432602X)
- 巻号頁・発行日
- pp.202142G03, (Released:2020-08-19)
- 参考文献数
- 29
背景・目的 我々は、より健康的な入浴法を目指し、Heat shock protein 70 (HSP70)を日常の入浴で高めるHSP入浴法を確立してきた。しかし、生活意識の変化から入浴をシャワーで済ませる機会が増えている。本研究では、日常の入浴として全身入浴またはシャワー浴を行っている人に入浴による温熱刺激を与え、HSP70、体力指数および気分プロフィール検査などの主観評価への影響について比較し、HSP入浴法を検討した。方法 健常男性11名を日常の入浴法として40℃ 10分の全身入浴群とシャワー浴群に分け、5日間の日常入浴後に試験入浴として40℃ 15分の全身入浴と保温を実施し、体温(舌下温度)を測定した。また、試験入浴前、1日後、2日後にHSP70発現量、体力指数および気分プロフィール検査、気分・感覚状態のアンケートを実施した。結果 全身入浴群において、試験入浴中の体温はシャワー浴群に比し有意に上昇し、HSP70は試験入浴前に比し有意に上昇した。また、疲労感や筋肉痛はシャワー浴群に比し有意に軽減し、気分プロフィール検査POMSの混乱は日常入浴前に比し有意に低下した。考察 全身入浴を継続することで、温熱刺激に対する感受性が高まり、HSP70の有意な上昇、疲労感の軽減、気分状態を良好にし、心身の健康に良い影響を及ぼすことが示唆された。また、日常の全身入浴の継続後の試験入浴40℃ 15分入浴は、従来のHSP入浴法である40℃ 20分の入浴時間を5分短縮する、新しいHSP入浴法となり得るものと思われた。
2 0 0 0 OA 新学部設立の顛末準備室教員の視点から
- 著者
- 笹嶋 宗彦
- 出版者
- 日本知能情報ファジィ学会
- 雑誌
- 知能と情報 (ISSN:13477986)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, no.2, pp.39-42, 2019-04-15 (Released:2021-04-15)
- 参考文献数
- 2
2 0 0 0 アミューズメント産業
- 著者
- アミューズメント産業出版 [編]
- 出版者
- アミューズメント産業出版
- 巻号頁・発行日
- vol.27(8), no.319, 1998-07
2 0 0 0 OA リアルタイム音楽情景記述システム:サビ区間検出手法
- 著者
- 後藤 真孝
- 雑誌
- 情報処理学会研究報告音楽情報科学(MUS)
- 巻号頁・発行日
- vol.2002, no.100(2002-MUS-047), pp.27-34, 2002-10-25
本稿では、ポピュラー音楽の音響信号に対して、サビの区間の一覧を求める手法を提案する。従来、楽曲の音響信号中に何度も出現するサビのどこか一箇所を、指定した長さだけ切り出して提示する研究はあったが、サビ区間の開始点と終了点はわからず、サビの転調も扱えなかった。本手法は、様々な繰り返し区間の相互関係を調べることで、楽曲中で繰り返されるすべてのサビ区間を網羅的に検出し、それらの開始点と終了点を推定できる。また、転調後でも繰り返しと判断できる類似度を導入することで、転調を伴うサビも検出できる。この検出結果は、リアルタイム音楽情景記述システムにおける大局的な記述に相当する。RWC研究用音楽データベース100曲を用いて本手法を評価したところ、80曲のサビが検出できた。
2 0 0 0 OA 先史日本における貨幣の展開
- 著者
- 村上 麻佑子
- 出版者
- 日本思想史研究会
- 雑誌
- 年報日本思想史 = NENPO NIHON SHISOSHI (THE ANNUAL OF JAPANESE INTELLECTUAL HISTORY) (ISSN:13472992)
- 巻号頁・発行日
- no.17, pp.1-14, 2018-03-27
2 0 0 0 OA 神代正語常磐草 : 3巻
- 著者
- 細田富延 [著]
- 巻号頁・発行日
- vol.[1], 1827
2 0 0 0 OA 鵲と扁鵲 : 魏志倭人伝鳥考
- 著者
- 犬飼 和雄
- 出版者
- 法政大学社会学部学会
- 雑誌
- 社会労働研究 = 社会労働研究 (ISSN:02874210)
- 巻号頁・発行日
- vol.39, no.1, pp.26-41, 1992-07
2 0 0 0 OA ワクシニアウイルス・ベクター -ワクシニアウイルスの分子生物学と新型ワクチンの開発-
2 0 0 0 新解国語辞典
- 著者
- 金田一京助, 佐伯梅友 編
- 出版者
- 小学館
- 巻号頁・発行日
- 1960
2 0 0 0 新国語辞典
- 著者
- 石井庄司, 小西甚一 編
- 出版者
- 大修館書店
- 巻号頁・発行日
- 1963
2 0 0 0 OA 50周年記念シンポジウム―2 ∼神経学・半世紀の進歩∼ 世界からみた日本神経学会の半世紀
- 著者
- 木村 淳
- 出版者
- 日本神経学会
- 雑誌
- 臨床神経学 (ISSN:0009918X)
- 巻号頁・発行日
- vol.49, no.11, pp.737-740, 2009 (Released:2009-12-28)
- 参考文献数
- 7
The Japanese Society of Neurology, founded in 1960, suffered an initial set back internationally primarily because of the language barrier. It gained a quick, and justifiable recognition after the 12th World Congress of Neurology held in Kyoto (1981), and now enjoys an indisputable reputation in the field of neuroscience. Clinical neurophysiology lead the world from the inception with the early formation of study group in 1951 as the predecessor of the current Japanese Society of Clinical Neurophysiology. In both fields, however, clinical training has fallen behind research achievements with limited resources and a shortage of teaching staff. On the occasion of 50th anniversary of our society, we must seek the sovereignty of neurology as an independent discipline as advocated by the World Federation of Neurology. We must also participate in global affairs with confidence despite a perceived language barrier to promote neurology world wide.
2 0 0 0 OA ブログ空間におけるインフルエンサーおよび消費者インサイトの発見
- 著者
- 松村 真宏 山本 晶
- 出版者
- 日本マーケティング学会
- 雑誌
- マーケティングジャーナル (ISSN:03897265)
- 巻号頁・発行日
- vol.30, no.3, pp.82-94, 2011-01-10 (Released:2021-03-04)
- 参考文献数
- 29
- 被引用文献数
- 2
2 0 0 0 OA 記念講演 神経学に魅せられて:若い世代への期待
- 著者
- 木村 淳
- 出版者
- 日本神経学会
- 雑誌
- 臨床神経学 (ISSN:0009918X)
- 巻号頁・発行日
- vol.48, no.11, pp.792-797, 2008 (Released:2009-01-15)
- 参考文献数
- 6
- 被引用文献数
- 1 1
日本神経学会は1960年に設立されましたが,当時神経学を学べる施設は,東大,新潟大,九大などに限られていました.僕は,のちに京大総長を務められた平沢興先生の錐体外路系に関する解剖講義に憧れてこの道を志し,インターン修了後すぐ渡米しましたが,1)神経系が人体のもっとも重要な,人間が人間たるゆえんである脳の機能を主要な対象としていること,2)複雑難解にもかかわらず理路整然とした学問で,解剖学の知識に基づいて病巣の局在が可能であること,3)新しい領域で,将来への展望が明るいことなどにも強く魅かれました.半世紀近くを経た今も思いは同じですが,これに加えて分子生物学をはじめとする神経科学分野の目覚しい発展により,病態の確立のみならず以前は対症療法に甘んじていた多くの疾患にも新しい治療法が続々と開発され,4)患者の治る神経内科,が神経学の新たな魅力となり,これは僕達のスローガンでもあります.神経学の国内外の進歩にともない,この分野を目指す若い先生方への期待は日増しに大きくなってきました.わが国の神経学は僕がアイオワ滞在中に飛躍的な発展を遂げ,これに貢献された多くの先達が新しい世代に求めるところは,先生方の個人的な経験を踏まえ,千差万別かと思います.この機会に日米で神経学を学んだ者の一人として,僕の次世代への期待を纏めますと,1)国際的な視野で仕事をする,2)診断に役立つ新しい技術を開発する,3)臨床に直結する基礎研究を展開する,そしてそのすべてを集結して4)患者の治る神経内科をめざすことです.いずれも実現可能な目標ですが,いうはやすく,おこなうは難しの部類です.とくに,実力に見合った国際的な評価を確立するのはわれわれがもっとも不得手とするところで,僕自身の体験でも,海外の学会活動で欧米の学者と互角にわたり合うのはかなり難しく,常に意識的な努力が必要と実感しています.国際学会での論争で,実力は伯仲しているのにいつもこちらに分が悪いのは,主に発表態度の差によるものと考えられます.我が国は儒教の影響もあり,古くから「知るを知らざるとなすは尚なり」の考えが根強く,10を知って1を語るのが良いとされます.その逆にアメリカ人は,幼稚園での「Show And Tell」を手始めに,中学校で習う「Five Paragraph Essay」で鍛え上げられ,1を知って10を語る輩が多いようです.また,日本人は完璧主義ですから,とちっても平気な欧米人とはちがいアドリブの発表が苦手です.英語でも上手く話せなければ,我は黙して語らずと達観している人もありますが,外国語ですからBrokenでも当たり前です.僕の国際性の定義は,1)実力をつけて,あとは対等と自信をもつ,2)知ってることはどんどんいう,3)失敗しても愛嬌と思って気にしない,4)英語は意味がわかればよいので,あえて流暢に喋ろうとしない,ことです.若い先生方がこれからの国際舞台でますます活躍されることを願って止みません.