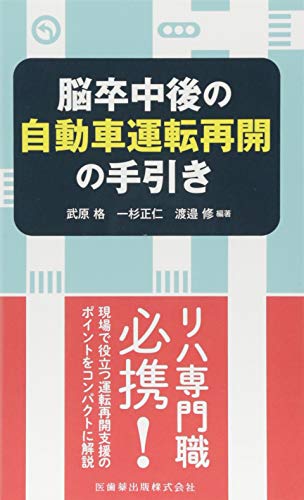1 0 0 0 OA 異状死体からの眼球摘出をめぐる法的・倫理的問題点について
- 著者
- 一杉 正仁 木戸 雅人 川戸 仁 横山 朋子 黒須 明 長井 敏明 徳留 省悟
- 出版者
- 日本生命倫理学会
- 雑誌
- 生命倫理 (ISSN:13434063)
- 巻号頁・発行日
- vol.14, no.1, pp.135-138, 2004-09-17 (Released:2017-04-27)
- 参考文献数
- 7
異状死体からの眼球摘出例をもとに、法的および倫理的問題を検討した。角膜移植実施のためには、眼球提供者の死体血を採取して、適応基準検査を実施することが必要となる。異状死体では、法医解剖終了後の採血が困難であるため、事前の血液採取が必要である。そのためには、死因究明の目的で採取した血液を使用するか、あるいは解剖時に採血をする必要がある。異状死体からの眼球摘出および諸検査をすみやかに行うために、本問題について幅広い理解が必要であり、かつ、司法当局、一般臨床医、異状死体の検案や解剖に携わる医師が密接に連絡を取り合うことが重要である。
1 0 0 0 OA 交通環境における自転車の走行状況と交通事故発生要因について
- 著者
- 松井 靖浩 及川 昌子 一杉 正仁
- 出版者
- 一般社団法人 日本交通科学学会
- 雑誌
- 日本交通科学学会誌 (ISSN:21883874)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, no.3, pp.11-19, 2016 (Released:2018-03-01)
- 参考文献数
- 9
都市部における自転車の走行状況を明確にすることで、交通事故発生メカニズムを解明し、交通安全対策を行うための基礎資料に資することを目的とする。本稿では、最初に朝の通勤時間帯に信号機のない交差点における自転車乗員の行動特性を分析した。その結果、自転車の交差点進入時の平均走行速度は3.09m/sであった。また、進行方向に向かって道路中央より左側と道路の左路側帯を走行する自転車乗員が86%を占め、多くの自転車が道路の左側を走行していることが分かった。ただし、この交差点の左角には建物があり、交差道路を行き交う車両、自転車、歩行者が自転車乗員には死角となり、交差点進入直前まで認識が困難な環境であった。このように、道路の左側を走行する自転車がある程度の走行速度を保ち、安全確認をせずに交差点に進入する自転車乗員の行為は、とくに走行音を伴わない電気自動車や自転車が接近した場合、出会頭による車両等との衝突事故の起因になり得ることが予想される。次に、車両に搭載したドライブレコーダより取得できるニアミスデータを用い、車両と自転車との接近状況を分析した。車両と自転車との接近状況について、死亡事故とニアミスを調査した結果、いずれの事象も車両が直進し、前方を自転車が横断する事例が最も多い傾向にあった。本結果から、ニアミスデータは事故状況を把握する上で活用可能であると考えられる。そこで、ニアミス事象において車両が直進し自転車が横断するケースに着目し、衝突予測時間(TTC)を算出した。その結果、建物や車両などの物陰から自転車が飛び出す場合のTTCは、障害物なしの状態で飛び出す場合のTTCと比べ有意に短いことが判明した。これら2つの結果より、自転車乗員、車両運転者共に建物などの障害物により見通しが悪く、相手を認識できない場合、出会い頭での交通事故に至る可能性が極めて高くなることが推察される。今後、本分析結果に基づき、自転車専用のカーブミラー等の新規設置により視界が改善されることが望まれる。さらに、自転車検知型被害軽減装置の開発や保護性能評価手法において、本分析結果が反映されることが期待される。
1 0 0 0 OA タクシー運転者における健康起因事故の予防対策についての実態調査
- 著者
- 一杉 正仁 山内 忍 長谷川 桃子 高相 真鈴 深山 源太 小関 剛
- 出版者
- 一般社団法人 日本交通科学学会
- 雑誌
- 日本交通科学学会誌 (ISSN:21883874)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, no.2, pp.50-57, 2016 (Released:2018-03-01)
- 参考文献数
- 11
- 被引用文献数
- 1
職業運転者における健康起因事故予防のために行うべき指導および啓発内容を具体的に明らかにするために、栃木県タクシー協会に所属する全タクシー運転者2,156人を対象に、無記名自記式のアンケート調査を実施した。844人から調査用紙が返送され(回収率は39.1%)、平均年齢は60.7歳であった。所属事業所の保有車両台数は30台未満(中小規模)が60.4%、30台以上が39.6%(大規模)であった。乗務前に体調が悪くても運転したことがある人は有効回答の28.5%であり、この割合は大規模事業所の運転者で有意に高かった。運転した理由として、運転に支障がないと判断したこと(59.0%)、収入が下がること(57.9%)が多かった。運転中に体調が悪くなったことがある人は有効回答の32.6%であり、その時、会社に申告して運転をやめた人が55.3%、しばらく休んでから運転を続けた人が26.5%、そのまま運転を続けた人が14.6%を占めた。体調が悪い時は運転を控えるよう指導された人は有効回答の76.0%、体調が悪い時に言い出しやすい職場環境であると回答した人は83.9%であり、いずれも事業所の規模による差は認められなかった。また、自身の健康と運転について、会社でしっかり管理してほしいと回答した人が34.0%を占め、27.2%の人がより頻回の健康診断受診を希望していた。健康起因事故の背景と予防の重要性が会社の規模によらずタクシー業界に十分浸透していないこと、厳しい労働環境がタクシー事業所全体に共通しているため、健康起因事故の予防を推進する経済的余裕がないことが分かった。健康起因事故を予防できるように、運転者自身が体調不良によるリスクを認識し、健康管理に対する意識の持ち方・知識を高めていくこと、これを事業所がサポートするシステムを構築することが重要である。
1 0 0 0 OA 失語症患者の自動車運転再開支援
- 著者
- 奥野 隆司 井上 拓也 吉田 希 仲野 剛由 西岡 拓未 石黒 望 一杉 正仁
- 出版者
- 一般社団法人 日本交通科学学会
- 雑誌
- 日本交通科学学会誌 (ISSN:21883874)
- 巻号頁・発行日
- vol.18, no.1, pp.24-31, 2018 (Released:2019-12-21)
- 参考文献数
- 18
失語症患者において自動車運転再開に必要な言語能力を明らかにすること、失語症患者に対する効果的な運転支援策を明らかにすることを目的に、脳卒中後の失語症患者で運転再開に至った6症例を検討した。失語症の検査として、Standard Language Test of Aphasia(SLTA)を実施した。神経心理学的検査として、Mini Mental State Examination(MMSE)、Trail Making Test(TMT)-AおよびB、Kohs立方体組み合わせテストを実施した。運転の評価・訓練には、簡易ドライビングシミュレーター(DS)を用いた。SLTAにおいて文字認識・理解は全6人で良好であった。一方、6人全員が減点されたのは「口頭命令に従う」・「語の列挙」であった。神経心理学的検査では、MMSEで基準値を下回った者が3人、TMT-Bを完遂できなかった者が1人であった。DSでは、訓練当初から運転能力にほぼ問題のなかった者が3人、訓練当初は運転能力に問題はあったものの徐々に改善がみられた者が3人であった。失語症の検査で文字認識・理解の程度を把握することは重要である。そして、失語症患者では、神経心理学的検査だけで運転再開の可否を判断することは困難であり、DSを用いた運転評価及び訓練が有用であった。失語症患者では、神経心理学的検査や文字認識・理解の程度を評価したうえで、DSを用いた運転能力の評価と訓練を継続的に実施することが重要である。
1 0 0 0 OA 運転管理に必要な疾病・薬剤の知識
- 著者
- 一杉 正仁
- 出版者
- 公益財団法人大原記念労働科学研究所
- 雑誌
- 労働科学 (ISSN:0022443X)
- 巻号頁・発行日
- vol.87, no.6, pp.240-247, 2011 (Released:2013-07-25)
- 参考文献数
- 21
- 被引用文献数
- 4
運転中の急激な体調変化によって運転操作に支障をきたし,結果的に事故につながることがある。運転中にひとたび体調変化が生じると,ほとんどの例で適切な回避行動がとられず,事故につながる。社会の安全や自身の健康を確保するためにも,運転中に軽微な体調不良を自覚した際には,積極的に自動車運転を中止する必要がある。薬剤を内服することで,原疾患のコントロールを良好に保つことは運転中の疾病発症を予防するうえで重要であるが,その際には運転に支障がない薬剤が選択されるべきである。各事業所で運転中の体調変化を予防する取り組み,あるいは体調変化が生じても事故に至らないようにする工夫が必要である。(図3)
- 著者
- 馬塲 美年子 一杉 正仁 相磯 貞和
- 出版者
- 一般社団法人 日本てんかん学会
- 雑誌
- てんかん研究 (ISSN:09120890)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, no.1, pp.8-18, 2013 (Released:2013-07-16)
- 参考文献数
- 12
- 被引用文献数
- 2
近年、てんかん発作に起因した事故が散見されるが、その背景と刑事責任について検討した。対象は1966年から2011年に発生し、運転者のてんかん発作が原因とされた死傷事故22例である。2002年に道路交通法が改正され、てんかんの既往があっても条件を満たせば自動車運転免許が取得できるようになったが、対象例中に免許更新時にてんかんの既往を申告した運転手はいなかった。起訴されたのは17例(77.3%)で、不起訴は5例(22.7%)であった。起訴された17例中、有罪は14例(82.4%)、無罪は3例(17.6%)であったが、近年、量刑は重くなる傾向であった。多くの運転手は、医師から自動車運転を控えるように指導されていながらも、運転を続けていた。てんかん患者の運転適性が正確に判断されるようなシステムが必要である。また、てんかん患者に対して自動車運転の適否を適切に指導できるよう、医師への啓蒙が必要と考えられた。
1 0 0 0 OA 2010年に栃木県で実施された法医解剖において遺体から検出された昆虫類について
- 著者
- 桐木 雅史 千種 雄一 一杉 正仁 黒須 明 徳留 省悟
- 出版者
- 日本衛生動物学会
- 雑誌
- 日本衛生動物学会全国大会要旨抄録集 第63回日本衛生動物学会大会
- 巻号頁・発行日
- pp.67, 2011 (Released:2014-12-26)
法医解剖において遺体から採取された生物を同定し解析することで有用な情報が得られる場合があることが知られている。本学では、主として栃木県で発見された遺体を対象として法医解剖を実施している。2010年に実施された法医解剖228件のうち35件(15.4%)において、遺体から検出された昆虫が熱帯病寄生虫病室に持ち込まれた。概要をまとめ、考察を加えて報告する。 月別では1年を通して1~10件/月あり、8月をピークとして6~9月に多かった。虫種はハエ類が多く、35件中33件で幼虫が見られ、他の2件でも卵または蛹が確認された。ハエの種類としてはクロバエ科(Calliphoridae)が29件、ニクバエ科(Sarcophagidae)が14件で確認された。また、1月に発見された遺体からはチーズバエ科幼虫が検出された。 ハエ類以外に、甲虫類が5件で検出されている。カツオブシムシ類、シデムシ類がそれぞれ2件で見つかり、1件でゴミムシ類、ハサミムシ類、ヒラタムシ上科が見られた。 ヒラタムシ上科の幼虫は橈骨の骨髄腔内から検出された。この幼虫は形態からヒラタムシ上科の球角群に属することがわかった。このグループには動物死体の骨髄腔内に侵入することが報告されているケシキスイ科(Nitidulidae)が含まれる。演者らは寒冷期に発見された白骨死体の骨髄腔からチーズバエ科の幼虫を検出し、昨年の本学会で発表している。通常法医解剖において、生物の検索は体表に留まるが、本事例から骨の内部も法医昆虫学的な検索の対象となり得ることがあらためて示唆された。
1 0 0 0 OA 白骨死体大腿骨頭内からのハエ幼虫検出事例
- 著者
- 桐木 雅史 一杉 正仁 千種 雄一 黒須 明 徳留 省悟
- 出版者
- The Japan Society of Medical Entomology and Zoology
- 雑誌
- 衛生動物 (ISSN:04247086)
- 巻号頁・発行日
- vol.61, no.2, pp.115-119, 2010-06-15 (Released:2011-01-07)
- 参考文献数
- 28
- 被引用文献数
- 3 5
某年12月下旬に栃木県中部の山林内で白骨化した遺体が発見された.法医解剖において,右大腿骨の大腿骨頭内から数十匹の虫体を検出した.採取した虫体は活発に動き,しばしば跳躍した.本虫はチーズバエ科(Diptera: Piophilidae)の3齢幼虫と同定された.本科は広く世界に分布し,日本には5種が報告されている.幼虫は動物の腐肉などの動物性蛋白質を好む種が多く,動物の死骸や骨に発生することが観察されている.本虫の骨内への侵入経路としては脈管孔が考えられる.孔径1 mm以上の脈管孔も多数あり,本科の幼虫のみならず,微小な生物であれば容易に侵入できると考えられる.遺体から検出される生物を解析することで死後時間の推定などの有用な情報が得られることがある.本事例から,体表や軟部組織のみならず,骨の内部も法医昆虫学的な検索の対象となり得ることが示唆された.
1 0 0 0 脳卒中後の自動車運転再開の手引き
- 著者
- 武原格 一杉正仁 渡邉修編著
- 出版者
- 医歯薬出版
- 巻号頁・発行日
- 2017
1 0 0 0 OA マークミスの発生率が高い試験問題とは
- 著者
- 一杉 正仁 菅谷 仁 平林 秀樹 妹尾 正 下田 和孝 田所 望 古田 裕明
- 出版者
- 獨協医科大学
- 雑誌
- Dokkyo journal of medical sciences (ISSN:03855023)
- 巻号頁・発行日
- vol.35, no.3, pp.175-178, 2008-10-25
- 被引用文献数
- 1
マークミスが生じやすい試験問題を明らかにするために,同一受験生を対象に,問題の種類や解答肢数の違いといった質的な変化あるいは問題数の変化がマークミスの発生頻度におよぼす影響を検討した.医学部6年生が4パターンの試験(530問,複択問題6.8 %;1130問,複択問題2.0 %;530問,複択問題11.8%;530問,複択問題57.2%)を受験し,それぞれにおけるマークミスの発生頻度を調査した.問題数が約2倍になっても,複択問題のしめる割合が低下するとともに,1人当たりのマークミス発生率は有意に低下した.問題形式および問題数が同じ場合,複択問題のしめる割合が4.8倍に増加すると,1人あたりのマークミス発生率は2倍に増加した.問題数を増加させるより,複択問題のしめる割合を増加させた方が,マークミスを誘発しやすいことがわかった.したがって,今後は複択問題のしめる割合を増加させた試験問題を利用して,マークミスの予防対策を講じることが有効と考える.
1 0 0 0 OA “エコノミークラス症候群”から“旅行者血栓症”へ
- 著者
- 一杉 正仁
- 出版者
- 特定非営利活動法人 日本バイオレオロジー学会
- 雑誌
- 日本バイオレオロジー学会誌 (ISSN:09134778)
- 巻号頁・発行日
- vol.16, no.1, pp.32-33, 2002-03-30 (Released:2012-09-24)
- 参考文献数
- 4
1 0 0 0 IR 試験におけるヒューマンエラーの予防対策について
- 著者
- 一杉 正仁 菅谷 仁 平林 秀樹 妹尾 正 上田 秀一 下田 和孝 田所 望 古田 裕明 Masahito Hitotsugi Hitoshi Sugaya Hideki Hirabayashi Tadashi Seno Shuichi Ueda Kazutaka Shimoda Nozomu Tadokoro Hiroaki Furuta 獨協医科大学国試教育センター 獨協医科大学国試教育センター 獨協医科大学国試教育センター 獨協医科大学国試教育センター 獨協医科大学国試教育センター 獨協医科大学国試教育センター 獨協医科大学国試教育センター 獨協医科大学国試教育センター Medical Education Center for National Examination Dokkyo Medical University School of Medicine Medical Education Center for National Examination Dokkyo Medical University School of Medicine Medical Education Center for National Examination Dokkyo Medical University School of Medicine Medical Education Center for National Examination Dokkyo Medical University School of Medicine Medical Education Center for National Examination Dokkyo Medical University School of Medicine Medical Education Center for National Examination Dokkyo Medical University School of Medicine Medical Education Center for National Examination Dokkyo Medical University School of Medicine Medical Education Center for National Examination Dokkyo Medical University School of Medicine
- 雑誌
- Dokkyo journal of medical sciences (ISSN:03855023)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, no.2, pp.77-81, 2010-07-25
試験におけるヒューマンエラーの実態を明らかにし,予防教育の効果を検証するために,医師国家試験模擬試験を利用して受験生がおかすヒューマンエラーを包括的に調査解析した.医学部6年生が2回の医師国家試験模擬試験を受験し,自己採点結果と,マークシートによる機械的採点結果を対比した.2回の試験を通じて,受験生1人が1回の試験で平均1.4個のエラーをおかしていた.エラーの分類別頻度では,2肢選択すべきところを1肢しか選択しなかったエラーが49.1%,1肢選択すべきところを2肢以上選択したエラーが31.6%,選択したものと異なる記号をマークしたエラーが10.5%と続いた.全ての受験者(全受験者)と,2回の試験に参加した受験者(2回受験者)に大別してエラーの発生頻度,エラーの内容について比較した.2 回受験者は,1人当たりがおかすエラー数および2問以上のエラーをおかす人の割合ともに2回目の試験で有意に減少していた. これは,受験者自らがエラーの実態に気付き,そして適切な助言のもとに注意を払って試験に臨んだ結果と思われる.試験におけるヒューマンエラーの実態を明らかにし,それを最小限にくい止める対策は,単に医師国家試験における失点防止だけでなく,ミスをおかしてもそれに気付き,問題解決ができるようなerror tolerantの考え方を養う上でも重要と思われる.We analyzed inadvertent human errors made by 6thgrade medical students during two trial examinations madeup of 500 multiple-choice questions where either one or twocorrect answers were required. Forty and 39 students, respectively,took the two examinations. Students averaged1.4 errors each during the examinations. Most errors( 80.7%) involved selecting the wrong number among the answeroptions( i.e. when a two option selection was required,only one option was selected). The students who had takenboth examinations made significantly less errors in the latterexamination than the former. Furthermore, the prevalenceof students who had made more than one inadvertenterror was significantly lower among students who tookboth examinations. We showed the effectiveness of interventionregarding inadvertent errors during 500 multiplechoicequestion examinations and of educating the studentsabout preventive measures. These results might have auseful application to improved safety promotions based onerror-tolerant theories.
平成17年度に行った動物実験結果および平成18年度に行った妊婦衝突試験用ダミーを用いたスレッド試験結果を総合的に解析した。その結果、妊婦が時速30km/h以下の追突事故に遭遇した際、腰部にかかる外力のみでは、胎児の予後に悪影響をおよぼすというエビデンスは得られなかった。さらに、追突事故に遭遇した前席乗員は、反動で腹部を車室内部に強打することがわかった。したがって、妊婦乗員のシートベルト着用効果を考えるうえでは、この腹部にかかる外力を低減させることが重要であると結論づけた。シートベルト着用で、追突時における腹部とステアリングとの二次衝突をある程度予防し、子宮内圧の変化を低減できることがわかった。しかし、負荷された加速度が大きいか、あるいは乗車位置がハンドルと近い場合に、シートベルトを着用してもある程度の外力が腹部へ作用することが明らかになった。そこで、さらなる積極的予防策として、緊急ベルト引き締め装置を追突事故時に作動させるシステムを考案した。その結果、比較的高速度の追突事故遭遇時には、子宮内圧をさらに低減させ、胎児保護に効果的であることが示唆された。また、低速度(約13km/h)の正面衝突事故をモデルしたスレッド試験を行ったところ、シートベルト着用時には、子宮内圧の上昇を35〜45%に軽減できることがわかった。したがって、シートベルトの着用は、追突および正面衝突時の妊婦子宮内圧上昇を抑制するうえで有効であった。妊婦のシートベルト着用について社会的議論がされているなか、われわれはシートベルト着用が胎児保護に有効である科学的根拠を明らかにした。本研究成果の一部は新聞、テレビ等でも紹介されたが、これら成果を積極的に公表し、一般の方に正しい知識を啓蒙している。