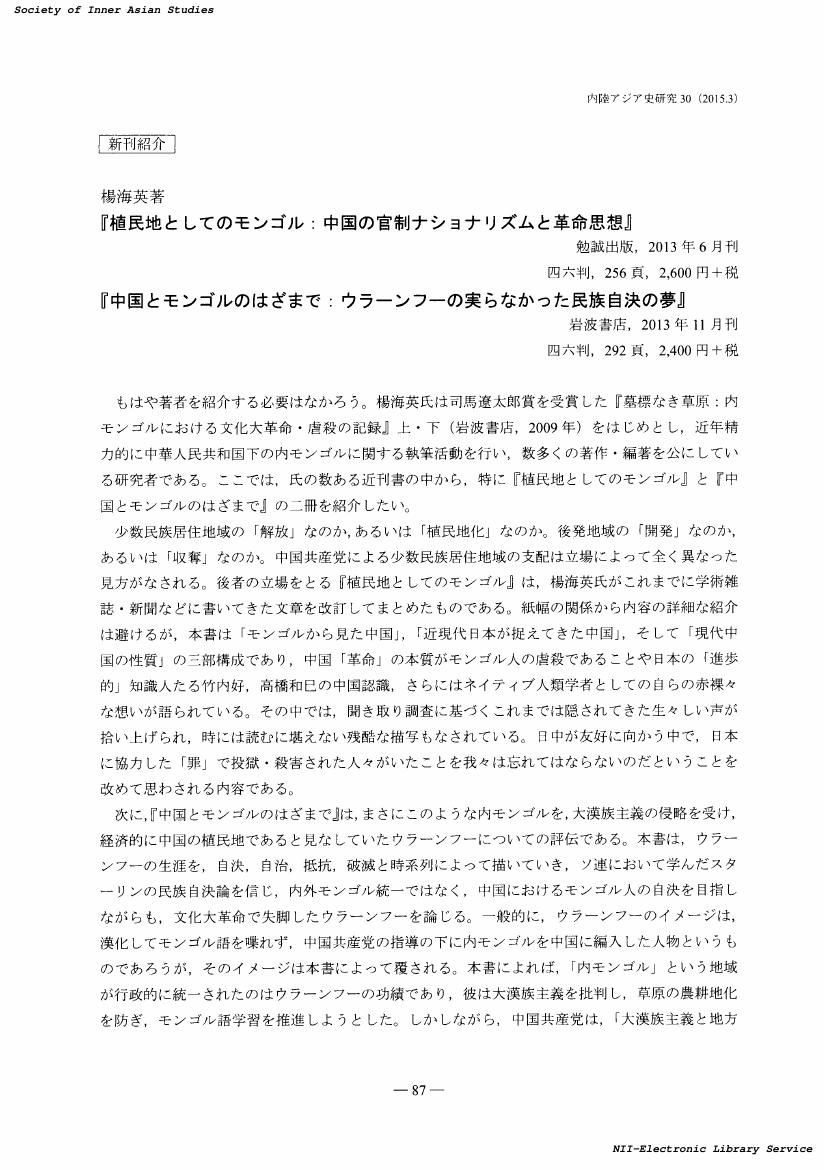1 0 0 0 OA 擬人化キャラクターのデザインについての研究
- 著者
- トウ サンサン
- 出版者
- 一般社団法人 日本デザイン学会
- 雑誌
- 日本デザイン学会研究発表大会概要集 日本デザイン学会 第69回研究発表大会
- 巻号頁・発行日
- pp.322, 2022 (Released:2022-08-30)
擬人化とは、人以外のものに対して人としての性質・特徴を与える比喩の表現方法である。現在、よく知られている擬人化作品はほとんど二次元愛好者向けであり、二次元文化愛好者以外は興味を持てないという問題点がある。本研究では、癒し系キャラクターの大衆に受け入れられやすい特徴を分析し、擬人化キャラクターデザインの要素として適用することを目的とし、人々の擬人化キャラクターに対する好みの傾向について考察した。その結果、人々が擬人化キャラクターに対しての好みは、モチーフの種類(動物・植物・ものなど)、作品の種類(キャラクターが何に使われているか)によって異なった。従って統一的な基準で判断してはいけないことがわかった。これからも再度調査を行い、一番人気のある形、もしくは人々の好みの傾向を左右するポイントが把握できるようになることを期待している。
1 0 0 0 OA 肥満猫における脂質代謝変動
- 著者
- 小宮 拓巳 生野 佐織 左向 敏紀
- 出版者
- 日本ペット栄養学会
- 雑誌
- ペット栄養学会誌 (ISSN:13443763)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, no.Suppl, pp.suppl_32-suppl_33, 2022-06-30 (Released:2022-08-31)
肥満猫の血清を用い、リポ蛋白質コレステロール分画を測定した結果、健常猫の数値と同程度であり、猫では肥満であってもT-CHOの上昇は認められず、リポ蛋白質コレステロール分画は変化しないことが分かった。一方、肥満ではないがT-CHOが高値を示した検体では、LDLが高値を示し、さらに肝または腎数値が上昇していたことから、リポ蛋白質コレステロール分画の変動は、他の疾患と関係している可能性が示唆された。
1 0 0 0 OA 透析患者におけるインドキシル硫酸の動態
- 著者
- 丹羽 利充 小沢 裕子 前田 憲志 柴田 昌雄
- 出版者
- 社団法人 日本透析医学会
- 雑誌
- 日本透析療法学会雑誌 (ISSN:09115889)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, no.10, pp.951-956, 1988-10-28 (Released:2010-03-16)
- 参考文献数
- 18
- 被引用文献数
- 1
慢性血液透析患者血液中に蛋白結合して著明に増加しているインドキシル硫酸の高速液体クロマトグラフィー (HPLC) を用いた簡便な定量法の確立を試みた. 血清10μlをinternal-surface reversed-phase (ISRP) カラムを装着したHPLCにより分析した. 溶出ピークを乾固後, 二次イオンマススペクトロメトリー (SIMS) により測定したところ, 分子量が213と分かり, また, UVスペクトル, HPLCの保持時間もインドキシル硫酸と一致した. 蛋白結合型インドキシル硫酸の血清濃度を, 血清の除蛋白を必要とせずにHPLCにより短時間に容易に測定することが可能となった.透析患者80名の透析前および透析後の総インドキシル硫酸および遊離型インドキシル硫酸の血清中濃度をISRP-HPLCにより測定し, 各臨床検査値との相関関係を検討した. 透析前総インドキシル硫酸は平均32.6μg/mlと正常者の平均0.50μg/mlに比較して著明に増加していた. 透析後のインドキシル硫酸は平均25.7μg/mlであった. 透析前のインドキシル硫酸濃度は透析年数, 透析前血清クレアチニン, β2-ミクログロブリン濃度と弱いが有意に正相関した. インドキシル硫酸の蛋白 (アルブミン) 結合率は透析前89%, 透析後84%であった.インドキシル硫酸の薬物-アルブミン結合への阻害作用を平衡透析法により検討した. インドキシル硫酸はサリチル酸のアルブミン結合を用量依存性に阻害した. また, 透析患者の血清中にアルブミンと結合して著明に増加している3-carboxy-4-methyl-5-propyl-2-furanpropionic acidはインドキシル硫酸のアルブミン結合を用量依存性に抑制した.インドキシル硫酸は血中では大部分がアルブミンと結合しており血液透析により除去されにくく, 透析患者の血清中に薬物結合阻害因子として著明に蓄積していた.
- 著者
- 李 昭衡
- 出版者
- 日本比較政治学会
- 雑誌
- 比較政治研究 (ISSN:21890552)
- 巻号頁・発行日
- vol.8, pp.1-23, 2022 (Released:2022-02-09)
- 参考文献数
- 129
Over the last few years, Japanese prefectural assemblies have issued a considerable of resolutions concerning North Korea, but those numbers vary across the Japanese 47 prefectural assemblies. This paper attempts to explain the varied number by presence of civic groups in each prefecture. The assessment of the impact of civic groups on local assemblies is undertaken by using original panel data on the 47 prefectures from 1993 to 2018. The panel data analysis empirically shows that grassroots activism exerts significant influence on and facilitates the adoption of resolutions by local legislative bodies and supports the model’s predictions for legislative production.
- 著者
- 安田 英峻
- 出版者
- 日本比較政治学会
- 雑誌
- 比較政治研究 (ISSN:21890552)
- 巻号頁・発行日
- vol.7, pp.21-36, 2021 (Released:2021-04-16)
- 参考文献数
- 66
本稿は、ポスト・サッチャー時代におけるイギリスの保守党政治がどのような展開を見せているかを分析するため、メイジャー政権(1990~1997)を取り上げる。メイジャー政権に関する先行研究では、サッチャー政権が招いた社会的・経済的格差を始めとした負の遺産に対し、新たな政策路線を提起できなかったという評価が根強い。本稿はこの理解に修正を加えることを目的にしている。本稿では、メイジャー政権下の保守党が提起した新たな政治理念に注目し、それが国内政策の展開に与えた影響を考察する。分析の結果、当時の党知識人が提起した「市民的保守主義」の理念が、公共サービスの質的改善を目的とする「市民憲章」において反映されていたことが明らかとなった。本稿は、サッチャリズムに代わる新たな政策路線として、メイジャー政権は地方自治体やその関連組織である学校、病院、行政などのコミュニティ活性化を進める理念を打ち出し、実際の国内政策において展開したことを明らかにした。
- 著者
- 新川 匠郎
- 出版者
- 日本比較政治学会
- 雑誌
- 比較政治研究 (ISSN:21890552)
- 巻号頁・発行日
- vol.7, pp.37-56, 2021 (Released:2021-08-31)
- 参考文献数
- 55
本論は、なぜ西欧諸国内で異なるメディアの特徴が生じるのかという問いに対して、政権のアカウンタビリティの異なる実践に注目して考察を加えるものである。これまでのメディアシステムの国際比較では類型学的な関心が強く、メディアシステム形成については多く議論されてこなかった。アカウンタビリティ研究では政党を中心に比較分析が重ねられており、メディアとの関係については十分な検討が進められていない。こうしたメディアシステム研究とアカウンタビリティ研究の相互補完を目指し、本論は西欧諸国における政権のアカウンタビリティと社会アカウンタビリティを行使するメディアの関係について、多様性と複雑さを捉える質的比較分析(QCA)から探っていく。この分析からは、政権のアカウンタビリティを支える政治制度は国別のメディアシステム形成の各種パターンで中核的要素になることを確認する。また、その政治制度が機能不全に陥ると、それは分極的なメディアシステムの助長につながるとも提起する。この結果からは有権者を補助するメディアの特徴が浮き彫りになる一方、それは政権のアカウンタビリティ欠如により異なる役割を果たすようになることも示唆される。
- 著者
- 尹 海圓
- 出版者
- 日本比較政治学会
- 雑誌
- 比較政治研究 (ISSN:21890552)
- 巻号頁・発行日
- vol.7, pp.1-20, 2021 (Released:2021-02-27)
- 参考文献数
- 70
本研究はテクノポリス政策の決定過程における日韓政府の対照的な方針転換、つまり、日本の地理的集中から分散への転換と、韓国の地理的集中から分散、再び集中への回帰という現象を説明するために次の仮説を提示する。経済分野において政治家と有権者がクライエンテリスティックな関係を結ぶ日本では、政策に伴う雇用保障の効果が特殊利益とみなされ、産業政策の支援対象は分散し福祉政策化する傾向が強い。一方、日本に比べ相対的にプログラマティックな関係に基づく韓国では、雇用保障が一般利益と見なされる時期を除き、産業政策の支援対象は集中する傾向が強い。テクノポリス政策は両国ともに当初は産業政策として構想されたが、日本では、本政策による雇用保障を特殊利益とみなした政治家の介入により、支援対象は分散し福祉政策的な効果が強まった。韓国でも、当時一般利益と見なされた雇用保障に対応する中で一時期支援対象が分散するが、経済成長が再び一般利益として重視されるにつれ、支援対象は集中し産業政策的な効果が強くなった。
1 0 0 0 OA 彙報
- 出版者
- 内陸アジア史学会
- 雑誌
- 内陸アジア史研究 (ISSN:09118993)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, pp.246-256, 2016-03-31 (Released:2017-05-26)
1 0 0 0 OA The manuscript 'F' of Sir-a Tuγuǰi
- 著者
- Kápolnás Olivér
- 出版者
- Society of Inner Asian Studies
- 雑誌
- 内陸アジア史研究 (ISSN:09118993)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, pp.165-174, 2016-03-31 (Released:2017-05-26)
- 著者
- 上村 明
- 出版者
- 内陸アジア史学会
- 雑誌
- 内陸アジア史研究 (ISSN:09118993)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, pp.119-143, 2016-03-31 (Released:2017-05-26)
In June 1930, over 430 Altai-Urianhai families moved across the Altai Mountains to Xinjiang, China. This "escape" triggered a chain of cross-border movements going out of Mongolia, initially in the region of western Mongolia and then spreading all along the border areas close to China. Altai-Urianhai's reports presented at the national congress meetings, as well as maps they produced and submitted to the governments, show that their territory had shrunk due to Kazakh domination of the region and unfavorable governmental policies. They stated that their motherland was the Chingel River to the west of the Altai Mountains, pleading for the government to return it to them. Furthermore, the government of the People's Republic of Mongolia, which was undertaking nation-state building, had started to introduce the school-education system and the conscription system. The Altai-Urianhai people considered not only those systems but also the government to be those of "Halha's", "red", and therefore "evil". In this context, they did not "escape" from their motherland, but rather returned to their homeland. Those suffering in other areas of Mongolia took the incident to be an "escape from the motherland" or a "form of resistance" rather than a "return home". In other words, they "de-contextualized" the incident from Altai-Urianhais' historical contexts, and "re-contextualized" it into their own positions in the situation of that time. Thus developed the mass refugee movements in the early 1930s in Mongolia.
1 0 0 0 OA 近代"モンゴル","東三省"における戸口調査資料について : 東アジア地域の戸口調査事業展開のなかで(公開講演・研究発表要旨,2014(平成26)年度内陸アジア史学会大会記事,彙報)
- 著者
- 中見 立夫
- 出版者
- 内陸アジア史学会
- 雑誌
- 内陸アジア史研究 (ISSN:09118993)
- 巻号頁・発行日
- vol.30, pp.121-122, 2015-03-31 (Released:2017-10-10)
- 著者
- 菅原 純
- 出版者
- 内陸アジア史学会
- 雑誌
- 内陸アジア史研究 (ISSN:09118993)
- 巻号頁・発行日
- vol.30, pp.120-121, 2015-03-31 (Released:2017-10-10)
1 0 0 0 OA 編集後記
- 出版者
- 内陸アジア史学会
- 雑誌
- 内陸アジア史研究 (ISSN:09118993)
- 巻号頁・発行日
- vol.30, pp.App1, 2015-03-31 (Released:2017-10-10)
- 著者
- 前野 利衣
- 出版者
- 内陸アジア史学会
- 雑誌
- 内陸アジア史研究 (ISSN:09118993)
- 巻号頁・発行日
- vol.30, pp.118-119, 2015-03-31 (Released:2017-10-10)
- 著者
- 吉田 順一
- 出版者
- 内陸アジア史学会
- 雑誌
- 内陸アジア史研究 (ISSN:09118993)
- 巻号頁・発行日
- vol.30, pp.122-123, 2015-03-31 (Released:2017-10-10)
- 著者
- 呉 國聖
- 出版者
- 内陸アジア史学会
- 雑誌
- 内陸アジア史研究 (ISSN:09118993)
- 巻号頁・発行日
- vol.30, pp.119-120, 2015-03-31 (Released:2017-10-10)
- 著者
- 橘 誠
- 出版者
- 内陸アジア史学会
- 雑誌
- 内陸アジア史研究 (ISSN:09118993)
- 巻号頁・発行日
- vol.30, pp.87-88, 2015-03-31 (Released:2017-10-10)
- 著者
- 植田 暁
- 出版者
- 内陸アジア史学会
- 雑誌
- 内陸アジア史研究 (ISSN:09118993)
- 巻号頁・発行日
- vol.30, pp.89-90, 2015-03-31 (Released:2017-10-10)