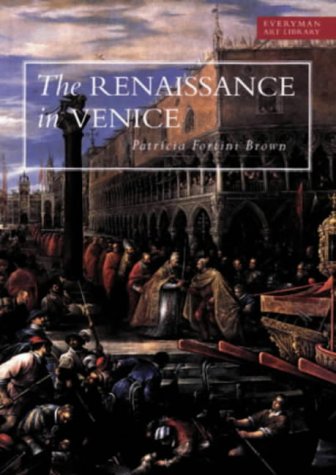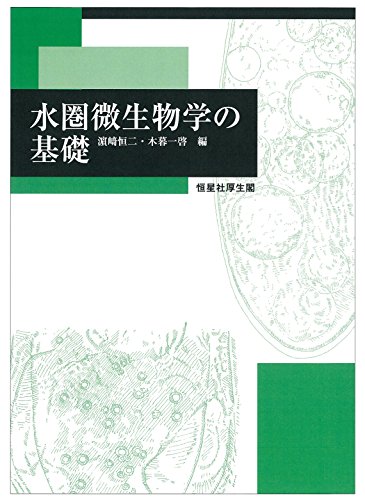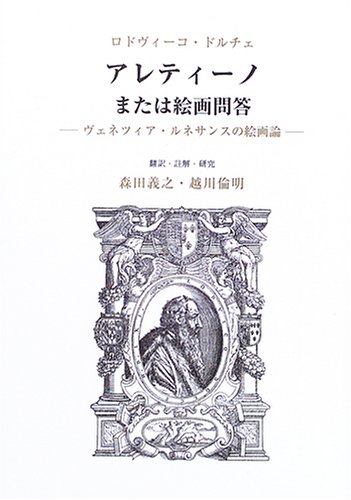- 著者
- Patricia Fortini Brown
- 出版者
- Weidenfeld & Nicolson
- 巻号頁・発行日
- 1997
1 0 0 0 エル・グレコとヴァザーリ(1)初期男性裸体素描の再検討を中心に
- 著者
- 松井 美智子
- 出版者
- 東北学院大学学術研究会
- 雑誌
- 東北学院大学教養学部論集 (ISSN:18803423)
- 巻号頁・発行日
- no.166, pp.33-59, 2013-12
1 0 0 0 渡邉美樹の快答乱麻(其の1・新連載)
- 著者
- 渡邉 美樹
- 出版者
- 日経BP社
- 雑誌
- 日経ビジネスassocie (ISSN:13472844)
- 巻号頁・発行日
- vol.7, no.10, pp.54-56, 2008-05-06
なぜ夢が持てないのか。その理由は30歳であろうが、中学1年生であろうが、何ら変わりません。自分のことにしか興味がないからです。マザーEテレサは「愛の反対は無関心」と言いました。極言すれば、夢がないという人には、他者への愛がないのです。 そういう人には「いいじゃないですか。あなたの人生、しょせん、そんなものですよね」というのが一つの答えですが、いかがですか。
1 0 0 0 時間の束をひもといて : 追悼土屋健治
- 著者
- 『土屋健治追悼集』刊行会編集
- 出版者
- 『土屋健治追悼集』刊行会
- 巻号頁・発行日
- 1996
1 0 0 0 中選挙区制における候補者の選挙行動と得票の地域的分布
- 著者
- 水崎 節文 森 裕城
- 出版者
- Japanese Association of Electoral Studies
- 雑誌
- 選挙研究 (ISSN:09123512)
- 巻号頁・発行日
- vol.10, pp.16-31,123, 1995
The multimember constituency system of the Japanese House of Representatives adopted in 1925 has lasted up to the present time, with the exception of a general election in 1946. This system is unique in the world and has influenced the electoral behavior of candidates as well as voters in Japan. It is inevitable that candidates from the same party are in competition.<br>One remarkable characteristic of the election results at the district level is that votes obtained by an individual candidate show a tendency to concentrate into the particular area. To examine the regional distribution of votes, we use the RS index and the DS index which was devised by Mizusaki, and trace the scores in the general elections from 1958 to 1993. The computed values have been decreasing year by year, but in some rural districts both indices show still very high scores.<br>The phenomenon of the concentration of votes in a particular area in a district has been considered as a reflection of premodern electoral behavior. Although this view cannot be denied in this paper, we try to explain the phenomenon in a different way. We would like to show that the spatial competitions aomng the plural candidates from the same party can be interpreted as a rational behavior with the strategy to win elections.
1 0 0 0 特集3 正月はブロードバンド三昧
- 著者
- 原 隆
- 出版者
- 日経BP社
- 雑誌
- 日経パソコン (ISSN:02879506)
- 巻号頁・発行日
- no.448, pp.108-115, 2004-01-05
芸能人の隠し芸大会、ドラマやバラエティ番組のNG集、プロ野球の珍プレイ好プレイ集など、おせち料理同様、お正月のテレビ番組にもそろそろ飽きてきたのでは。今年のお正月は趣向を変えてブロードバンドコンテンツを楽しんでみてはいかがだろう。パソコンにはテレビのようにチャンネルや放送時間の制限はない。無数の番組がいつでも楽しめる。
1 0 0 0 世論調査から出口調査に比重移る:選挙報道10年の変化
- 著者
- 井芹 浩文
- 出版者
- Japanese Association of Electoral Studies
- 雑誌
- 選挙研究 (ISSN:09123512)
- 巻号頁・発行日
- vol.20, pp.61-62, 2005
- 著者
- Aoki Toshiaki Satoh Makoto Tani Mitsuhiro Yatake Kenro Kishi Tomoji
- 出版者
- 北陸先端科学技術大学院大学先端科学技術研究科情報科学系
- 雑誌
- Research report (School of Information Science, Graduate School of Advanced Science and Technology, Japan Advanced Institute of Science and Technology) (ISSN:09187553)
- 巻号頁・発行日
- vol.IS-RR-2016-002, pp.1-11, 2016-05-23
The safety and reliability of automotive systems are becoming a big concern in our daily life. Recently, a functional safety standard which specializes in automotive systems has been proposed by the ISO. In addition, electrical throttle systems have been inspected by NHTSA and NASA due to the unintended acceleration problems of Toyota’s cars. In light of such recent circumstances, we are researching practical applications of formal methods to ensure the high quality of automotive operating systems. An operating system which we focus on is the one conforming to the OSEK/VDX standard. This paper shows a case study where model checking is applied to a commercial automotive operating system. In this case study, the model checking is combined with testing in order to efficiently and effectively verify it. As a result, we acquired the confidence that the quality of the operating system is very high.
1 0 0 0 The theatres of George Devine
- 著者
- Irving Wardle
- 出版者
- Cape
- 巻号頁・発行日
- 1978
1 0 0 0 水圏微生物学の基礎
- 著者
- 濵崎恒二 木暮一啓編
- 出版者
- 恒星社厚生閣
- 巻号頁・発行日
- 2015
1 0 0 0 アレティーノまたは絵画問答 : ヴェネツィア・ルネサンスの絵画論
- 著者
- ロドヴィーコ・ドルチェ [著] 森田義之 越川倫明翻訳・註解・研究
- 出版者
- 中央公論美術出版
- 巻号頁・発行日
- 2006
1 0 0 0 神の王国と人間の都市 : 中世からルネサンスへ
- 著者
- 中山公男佐々木英也責任編集
- 出版者
- 日本放送出版協会
- 巻号頁・発行日
- 1985
1 0 0 0 ヴェネツィアの宴
- 著者
- 樺山紘一 森田義之責任編集 森田義之 [ほか] 執筆
- 出版者
- 講談社
- 巻号頁・発行日
- 1992
1 0 0 0 OA (書評)中村裕一著「唐代制勅研究」
- 著者
- 金子 修一
- 出版者
- 法制史学会
- 雑誌
- 法制史研究 (ISSN:04412508)
- 巻号頁・発行日
- vol.1992, no.42, pp.265-271, 1993-03-30 (Released:2009-11-16)
1 0 0 0 OA 死生観形成に関する調査 : 看護学生と大学生の比較
- 著者
- 糸島 陽子
- 出版者
- 京都市立看護短期大学
- 雑誌
- 京都市立看護短期大学紀要 (ISSN:02861097)
- 巻号頁・発行日
- vol.30, pp.141-147, 2005-09-01
- 被引用文献数
- 1
本研究は,看護学生と大学生の死生観形成要因を比較し,今後の看護教育における死生観育成について検討することを目的とした。その結果,1.自我同一性の形成時期と死生観尺度得点においては,看護学生・大学生間で差はみられなかった。 2.各年代で<生>と<死>を考える授業は,学生の死生観形成に影響を与えることが期待できる。3.死別経験をした学生は,死はすべての終わりではなく,生きている人間の間で生き続けていくなどの【不死感・死後の世界観】を形成する傾向がみられた。4.看護学生は,死別経験の有無に限らず,看護教育の特性により,生きるということは運命であるなどの【人智を超えた生命観(人間の力の及ばない生死に関すること)】が形成される傾向がみられた。以上のことから,看護教育において,看護学生が終末期看護や死別経験をした時々に生じる感情を大切にし,意識化させながら,ひとりひとりが,一人称・二人称・三人称の<生>と<死>の意味を円環させ考える教育は,死生観を育んでいく上で重要である。
1 0 0 0 愛媛県の山城谷式アクセント : 音声実現と「式」の対立
- 著者
- 吉田 健二
- 出版者
- アクセント史資料研究会
- 雑誌
- 論集
- 巻号頁・発行日
- no.11, pp.177-197, 2015