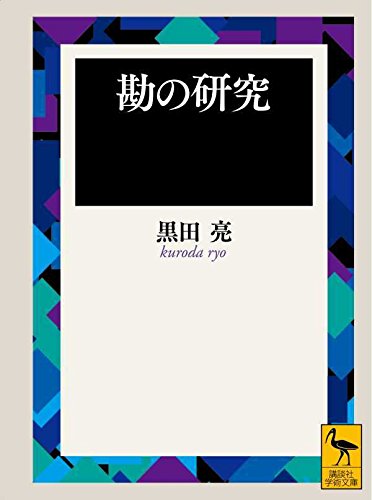1 0 0 0 城戸幡太郎著 「心理學史 (上)」
- 著者
- 黒田 亮
- 出版者
- The Japanese Psychological Association
- 雑誌
- 心理学研究 (ISSN:00215236)
- 巻号頁・発行日
- vol.12, no.2, pp.81-83, 1937
1 0 0 0 猿の生活から
- 著者
- 黒田 亮
- 出版者
- The Japanese Psychological Association
- 雑誌
- 心理学研究 (ISSN:00215236)
- 巻号頁・発行日
- vol.1, no.6, pp.934-960, 1926
- 被引用文献数
- 1
1 0 0 0 雜録:生き物雜録/日日ぐさ(1)/自文鳥人工育雛
- 著者
- 黒田 亮 葉山 正 松島 亀之助
- 出版者
- The Japanese Society for Animal Psychology
- 雑誌
- 動物心理 (ISSN:18836275)
- 巻号頁・発行日
- vol.1, no.2, pp.22-35, 1934
1 0 0 0 爬蟲類に於ける聽覺の研究
- 著者
- 黒田 亮
- 出版者
- The Japanese Psychological Association
- 雑誌
- 心理研究 (ISSN:18841066)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, no.147, pp.268-281, 1924
1 0 0 0 高等學校の心理學科に關する私見
- 著者
- 黒田 亮
- 出版者
- The Japanese Psychological Association
- 雑誌
- 心理研究 (ISSN:18841066)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, no.123, pp.188-193, 1922
1 0 0 0 情緒に伴ふ身體的變化の局所性に就いて
- 著者
- 黒田 亮
- 出版者
- The Japanese Psychological Association
- 雑誌
- 心理学研究 (ISSN:00215236)
- 巻号頁・発行日
- vol.9, no.5, pp.891-900, 1934
When any emotion reaches to a high degree of intensity there takes place a sense of graze in a certain locality over the external surface of our body. The sense of graze is in quality something like a feeling experienced when we, in a bath, receive on the abdominal region a surge caused by moving our hand. It is rough and devoids of compactness, it is felt near the surface of our skin, being never taken for visceral disturbance which usually appears deep in the visceral cavity. In looking down from height, we are aware of the sense at the calf of our legs the same instant when we experience danger. The author calls this a calf phenomenon.<BR>In the negative emotions, for instance of fear or dread, it is felt at the back, but in case of positive emotion of joy on the other hand it is localized on the ventral side, especially on the chest. While the sense is static in the calf phenomenon, it is dynamic in nature in intense fear or joy, that is it runs a certain distance with a certain speed; the speed seems to increase in accordance with the increase of their intensity. It closely resembles a sense of touch and is clearly distinguished from visceral or organic sensation by its superficial, at least somatic origin. The fact that it disappears as soon as the emotion concerned looses its intensity or comes to disappeare shows that it is essential bodily changes subjectively experienced in intense emotions.<BR>Though at present its physiological nature is not clear enough, we are prone to accept Cannon's thalamic theory in so far as it is of somatic kind, shallowly seated and has no direct connection of with excitations visceral organs. The James-Lange theory is not consistent with the existence of the sense of graze essential to emotions.<BR>The sense is differently localized in different qualities of emotions, in general the positive emotions on the ventral side and the negative on the dorsal one. This fact is biologically of significance because the positive emotions have to do with situations favorable and acceptable and the negative ones on the other hand with those unfavorable and rejected to an organism.(The author)
1 0 0 0 再び高等學校の心理學教授に就いて
- 著者
- 黒田 亮
- 出版者
- The Japanese Psychological Association
- 雑誌
- 心理研究 (ISSN:18841066)
- 巻号頁・発行日
- vol.27, no.161, pp.375-384, 1925
1 0 0 0 アリマキの行動特にその對光反應に就いて
- 著者
- 黒田 亮
- 出版者
- The Japanese Psychological Association
- 雑誌
- 心理研究 (ISSN:18841066)
- 巻号頁・発行日
- vol.19, no.109, pp.30-34, 1921
1 0 0 0 二歳兒の距離知覺に就いて
- 著者
- 黒田 亮
- 出版者
- The Japanese Psychological Association
- 雑誌
- 心理学研究 (ISSN:00215236)
- 巻号頁・発行日
- vol.1, no.1, pp.69-80, 1926
- 被引用文献数
- 1
1 0 0 0 心理学史・心理学論
- 著者
- 「心理学史・心理学論」刊行会編集
- 出版者
- 「心理学史・心理学論」刊行会
- 巻号頁・発行日
- 1999
1 0 0 0 大阪樟蔭女子大学人間科学研究紀要
- 著者
- 大阪樟蔭女子大学学術研究会 [編集]
- 出版者
- 大阪樟蔭女子大学人間科学部学術研究会
- 巻号頁・発行日
- 2002
1 0 0 0 心の世界 : 心理學入門
1 0 0 0 OA <資料>哺乳びんの消毒方法と母親の認識
- 著者
- 若松由佳子/川原瑞代/渡辺久美/島内千恵子/菅沼ひろ子/串間秀子 ワカマツユカコ/カワハラミズヨ/ワタナベクミ/シマウチチエコ/スガヌマヒロコ/クシマヒデコ WAKAMASTUYukako/KAWAHARAMizuyo/WATANABEKumi/SHIMAUCHIChieko/SUGANUMAHiroko/KUSHIMAHideko
- 雑誌
- 宮崎県立看護大学研究紀要 = Journal of Miyazaki Prefectural Nursing University
- 巻号頁・発行日
- vol.1, no.2, pp.92-97, 2000-12
近年の児の栄養方法の推移をみると母乳栄養の割合が上昇してきているが, 半数以上は哺乳びんを用いる育児が行われている。そこで, 今回哺乳びんの消毒方法がどのように行われているかを明らかにすることを目的に調査を行った。すなわち, 乳児を養育している母親108名を対象として, 哺乳びんの消毒方法の実施の実態とそれらに対する認識について調査した。その結果, 生後1ヶ月の時点での哺乳びん使用者は55名で, 哺乳びんの消毒方法は, 「次亜塩素酸ナトリウムでの消毒」が25名, 「煮沸消毒」が22名, 次いで「電子レンジでの消毒」が9名であった。消毒方法を選択するのに影響を受けた情報源では「テレビ・新聞等の広告」と「出産した施設での専門家の指導」が同数の14名, 次いで「家族」が13名でほぼ同数程度と多く, その他には「育児書」や「雑誌」などが情報源になっていた。消毒方法別にみると, 次亜塩素酸ナトリウム消毒実施者は, 「テレビ・新聞などの広告」が多く, 煮沸消毒実施者は, 「出産した施設での指導」が多かった。消毒方法についての認識は, 「清潔なものを使いたい」という人が多い一方で, 「手間がかかる」「いつまで必要か」「このような消毒や洗浄で子どもに安全か疑問」などの疑問も同時にみられた。更に, 哺乳びんの消毒を必要と考える期間についても, 6ヶ月から12ヶ月と答えた人が約60%を占めたが, 6ヶ月以下もみられ一定していなかった。これらの結果から, 哺乳びんの消毒については, 方法の選択や実施法やその時期に戸惑いがみられることがわかった。従って, 乳児の免疫学的及び, 細菌学的特徴も考慮に入れた消毒方法についての検討と情報提供が必要であり, 母親と指導する側の認識についても考慮しながら, 有効な保健指導を行う必要があることが示唆された。