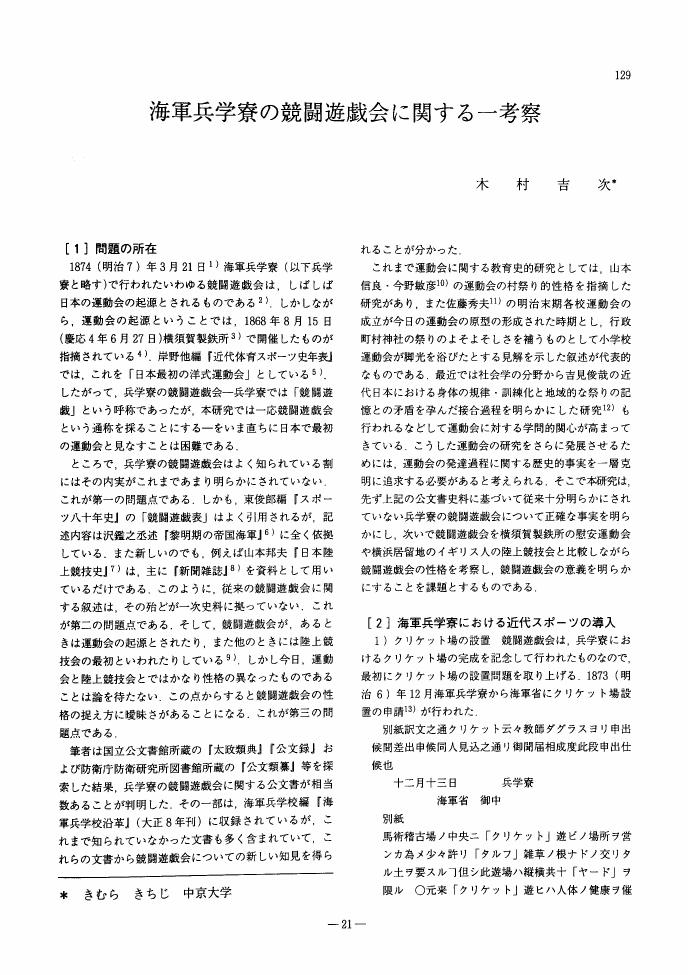- 著者
- 小林 良清
- 出版者
- 日本公衆衛生学会
- 雑誌
- 日本公衆衛生雑誌 (ISSN:05461766)
- 巻号頁・発行日
- vol.65, no.10, pp.615-620, 2018-10-15 (Released:2018-10-31)
- 参考文献数
- 11
目的 2015年の都道府県別生命表において長野県男性の平均寿命が滋賀県男性の平均寿命に準じて全国2位に後退したが,20歳以上の平均余命がいずれも全国1位であることから,20歳未満の年齢層における死亡率が2位後退に大きく影響していると考え,既存の統計資料等を活用してその状況を明らかにする。方法 政府統計から都道府県別生命表を入手し,長野県,滋賀県,全国における男性のそれぞれの年齢別死亡率を確認した。そして,平均寿命の計算式を作成し,仮の年齢別死亡率における長野県男性の平均寿命を試算した。さらに,長野県の衛生統計から男性の年齢階級別死因別死亡数を入手し,死因の状況を確認した。結果 2015年長野県男性の年齢別死亡率は,9歳から13歳において2010年長野県男性の年齢別死亡率より2倍以上高く,9歳から14歳において2015年滋賀県男性の年齢別死亡率より2倍以上高くなっていた。そして,平均寿命の計算式を用い,9歳から13歳における2015年長野県男性の年齢別死亡率が2010年長野県男性の年齢別死亡率と同じだったと仮定して平均寿命を試算すると81.77885歳となり,2015年滋賀県男性で試算される平均寿命81.77882歳を上回った。また,9歳から14歳における2015年長野県男性の年齢別死亡率が2010年長野県男性の年齢別死亡率と同じだったと仮定すると,平均寿命が81.78154歳となった。10歳から14歳において2015年長野県男性の死亡数は,2010年長野県男性の死亡数に比べて2.4倍に増えており,死因別死亡数がわかっている2014年から2015年を2010年と比較すると,「傷病および死亡の外因」に含まれるもの,含まれないものがともに増えていた。結論 平均寿命は,すべての年齢の死亡状況が反映された一つの数字であり,その値から課題を抽出するためには年齢に着目した分析が不可欠である。今回の分析により,2015年長野県男性の平均寿命が2015年滋賀県男性の平均寿命に準じて全国2位に後退したのは,10代前半の死亡数・率の増加が大きく影響していたものと推測された。
2 0 0 0 OA 自殺予防におけるフランクルのロゴセラピーの意義
- 著者
- 大谷 正人 OTANI Masato
- 出版者
- 三重大学教育学部
- 雑誌
- 三重大学教育学部研究紀要, 自然科学・人文科学・社会科学・教育科学 (ISSN:18802419)
- 巻号頁・発行日
- vol.66, pp.13-20, 2015-03-31
自殺予防の精神療法を行う際には、自殺者の9割以上に存在する精神疾患の治療、十分な時間をかけた傾聴、希死念慮の一時性の確認、周囲の人々との絆の回復への支援などが臨床上主要な課題となる。自殺予防の根拠となり得るセラピーの一つとして、フランクルのロゴセラピーがある。フランクルのロゴセラピーは、人々が人生の意味を見出すことを援助することがその本質であるが、自殺防止に役立つ様々な視点も存在している。それは、創造価値、体験価値、態度価値という生きる意味を確認すること、未来への視点をどのような時でも持ち続けること、「生きることから何かを期待できるか」ではなく、「生きることが私たちから何を期待しているか」という自己中心的世界観から世界中心的世界観への変換の必要性、苦悩のもつ意義の確認、愛する者への思いにより救済され得ること、そして自己超越による永遠性という視点である。自殺予防に関わる者にとって、フランクルのロゴセラピーは大きな示唆を与え続けている。
2 0 0 0 IR 規範性の要件 : 近親交配回避からインセスト・タブーへ?
- 著者
- 浜本 満
- 出版者
- 九州大学大学院人間環境学研究院教育学部門
- 雑誌
- 大学院教育学研究紀要 (ISSN:13451677)
- 巻号頁・発行日
- no.20, pp.1-22, 2018
In this paper I start retracing the history of anthropological approaches to incest taboo, though I regard the so-called incest problem as a kind of pseudo problem. Incest Taboo was first given an exaggerated theoretical importance in the context of 19th century evolutionist anthropology, as a key institution which enabled human society to depart from pristine promiscuity, and has been considered to be a sole institution found universally all over the world, despite frequent indications that it is actually not that universal. What might be truly universal is the tendency to be found among other mammals and primates to avoid inbreeding, and not incest prohibition itself. There even exist societies which lack a rule to forbid incest as such (although such societies actually show almost no cases of incest), and even among many societies with some rule of incest prohibition, contents of the rule, attitudes towards its transgression, kinds of punishment (from death penalty and ostracism to more lenient forms including mild admonishment and ridicule, as far as the total absence of any punishment) widely vary for each society. However, the universal tendency to evade inbreeding and those rules of prohibition were often confused, and as a result, the fiction of the universality of the prohibition has largely remained intact. It follows the very question how to explain the universal Inset Taboo was the empty question in which the object to be explained was actually absent. Westermarck's hypothesis, which explains the universal tendency of avoiding inbreeding, that close association in early childhood later develops an aversion to their sexual relations, took the limelight again in the latter half of the 20th century, and as the evidence accumulates to prove it, new waves of argument to attempt to explain the universality of the incest prohibition by this "Westermarck effect" have become popular, both in anthropology and other related fields. I would like to show how and why these new attempt to explain incest taboo will turn out to be a failure, and through its examination and refutation, I hope I could throw new light on the nature of rules, what is their proper function, what human mental capacity to be required in order to understand and live by rules.
2 0 0 0 図書館法成立史資料
- 著者
- 裏田武夫, 小川剛 編
- 出版者
- 日本図書館協会
- 巻号頁・発行日
- 1968
2 0 0 0 OA 国際社会におけるアナーキー、周辺、介入 : 植民地統治と平和構築
- 著者
- 五十嵐 元道
- 出版者
- 北海道大学大学院法学研究科
- 雑誌
- 北大法学論集 (ISSN:03855953)
- 巻号頁・発行日
- vol.65, no.1, pp.180-157, 2014-05-30
2 0 0 0 「第7回日韓西洋中世史研究集会」に参加して
2 0 0 0 OA 攝津名所圖會
- 著者
- 秋里籬嶌 著述
- 出版者
- 森本太助 [ほか4名]
- 巻号頁・発行日
- vol.[8], 1798
2 0 0 0 戦後における無理心中の実態
- 著者
- 姫岡 勤
- 出版者
- 社会学研究会
- 雑誌
- ソシオロジ (ISSN:05841380)
- 巻号頁・発行日
- vol.11, no.1, pp.11-26, 1964
2 0 0 0 OA 海軍兵学寮の競闘遊戯会に関する一考察
- 著者
- 木村 吉次
- 出版者
- 一般社団法人 日本教育学会
- 雑誌
- 教育学研究 (ISSN:03873161)
- 巻号頁・発行日
- vol.63, no.2, pp.129-138, 1996-06-30 (Released:2009-01-13)
- 参考文献数
- 54
2 0 0 0 OA 徴用工員の教育問題
- 著者
- 工業青年教育研究会 編
- 出版者
- 国民工業学院
- 巻号頁・発行日
- 1942
2 0 0 0 OA 東条一堂『四十四音論』及び岡本保孝『四十四音論弁誤』について
- 著者
- 田中 草大
- 出版者
- 東京大学大学院人文社会系研究科国語研究室
- 雑誌
- 日本語学論集 (ISSN:18800947)
- 巻号頁・発行日
- vol.7, pp.28-54, 2011-03-24
2 0 0 0 OA 日本文典 : 中学教程
- 著者
- 中等学科教授法研究会 著
- 出版者
- 中等学科教授法研究会
- 巻号頁・発行日
- 1897
2 0 0 0 OA オピオイド投与時の嘔気予防としてのハロペリドール, 塩酸ヒドロキシジン併用の有用性
- 著者
- 金石 圭祐 松尾 直樹 余宮 きのみ
- 出版者
- 日本緩和医療学会
- 雑誌
- Palliative Care Research (ISSN:18805302)
- 巻号頁・発行日
- vol.1, no.1, pp.101-108, 2006 (Released:2006-03-31)
- 参考文献数
- 18
- 被引用文献数
- 1
オピオイド投与時において嘔気の出現はしばしば問題となる副作用のひとつである. 今回オピオイド持続投与の際の嘔気予防としてハロペリドール単独投与群と塩酸ヒドロキシジン, ハロペリドールの併用投与群各50名に関し, 嘔気の出現率等についてretrospectiveな調査を行った. 持続投与開始後の嘔気の出現率はハロペリドール単独投与群(34%)と塩酸ヒドロキシジン併用投与群(10%)間で有意差を認めた. 多変量解析の結果では嘔気の危険因子として, 治療開始前の嘔気, イレウス, 塩酸ヒドロキシジン併用の有無が抽出された. また両群間のモルヒネ投与症例のみを検討しても, 嘔気の出現率はハロペリドール単独投与群(32.5%)と塩酸ヒドロキシジン併用投与群(4.5%)間で有意差を認めた. オピオイド持続投与時の嘔気予防にハロペリドール・塩酸ヒドロキシジン併用が有効である可能性が示唆された.
2 0 0 0 OA オランダにおける国民投票制度の導入・実施・廃止
- 著者
- 越田崇夫
- 出版者
- 国立国会図書館
- 雑誌
- レファレンス (ISSN:1349208X)
- 巻号頁・発行日
- no.823, 2019-08
2 0 0 0 OA Effects of decontextualized tsunami disaster education: A case study of schools in Acapulco, Mexico
- 著者
- Genta Nakano María Teresa Ramírez-Herrera Néstor Corona
- 出版者
- Japan Society for Natural Disaster Science
- 雑誌
- Journal of Natural Disaster Science (ISSN:03884090)
- 巻号頁・発行日
- vol.39, no.2, pp.19-33, 2019 (Released:2019-05-13)
- 参考文献数
- 37
- 被引用文献数
- 2
Disaster risk reduction education is provided through external support at schools. Most educational programs evaluate the level of knowledge transfer. However, the particular context of school is not considered, even though it prescribes the understanding of students. In this study, tsunami education was provided by a non-Mexican NGO at two schools in Acapulco, Mexico, and questionnaire surveys were conducted. The surveys identified that students were more interested in obtaining knowledge than learning action for their self-protection. This tendency in motivation was generated by the school context: the school teaches decontextualized knowledge despite the need to contextualize disaster education in daily life. This disparity caused a gap in the communication between the NGO members and the students. Therefore, it is important that disaster education programs remove students from the school context and place them in the context of daily life. More localized content could help remove students from the context of school. This study argues that the effectiveness of disaster education is influenced by the context in which students learn, and the findings suggest that educational practices should be designed on the basis of the context of the learners.
2 0 0 0 IR 西王母と桃の関係性 : 不死の薬と仙桃・蟠桃
- 著者
- 若林 歩
- 出版者
- 日本女子大学国語国文学会
- 雑誌
- 国文目白 (ISSN:03898644)
- 巻号頁・発行日
- no.51, pp.103-112, 2012-02
2 0 0 0 アルフォンソ十世賢王の七部法典 : 逐文対訳試案、その道程と訳注
- 著者
- 相澤正雄 青砥清一試訳
- 出版者
- 相澤正雄
- 巻号頁・発行日
- 2010