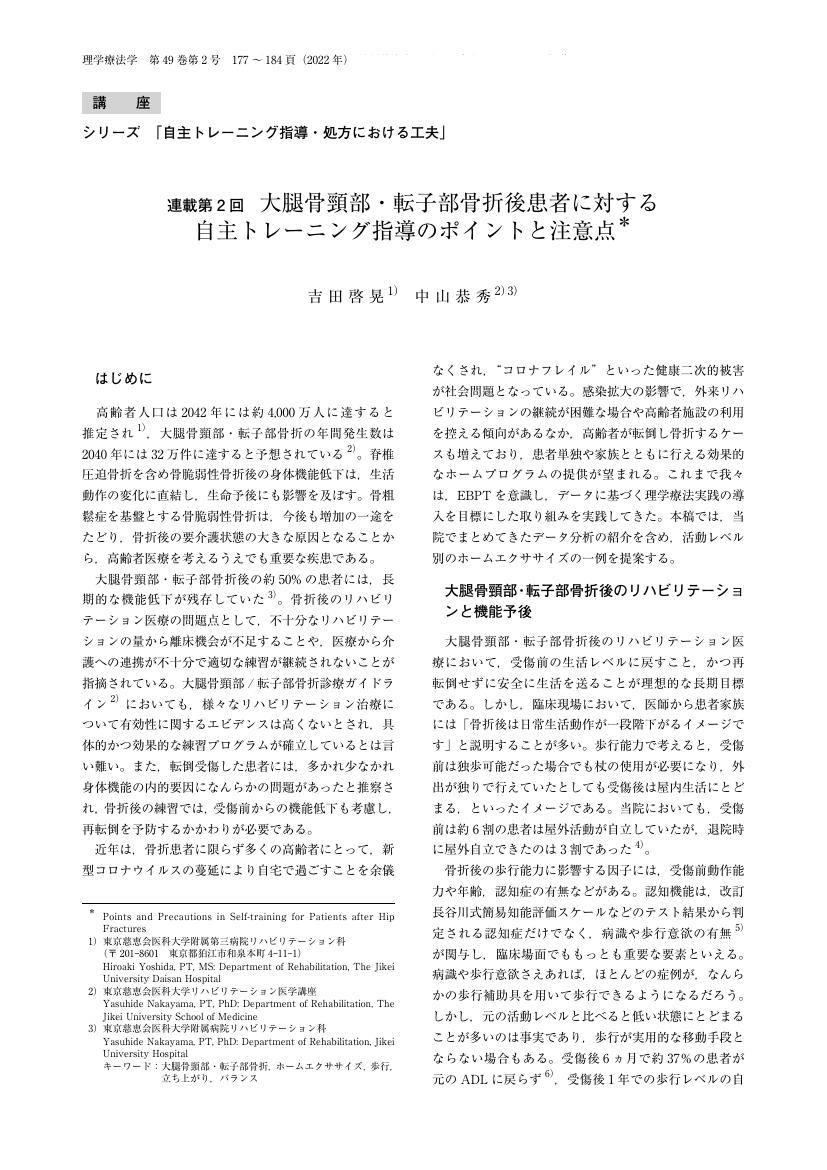29 0 0 0 OA 大腿骨頸部・転子部骨折後患者に対する自主トレーニング指導のポイントと注意点
- 著者
- 吉田 啓晃 中山 恭秀
- 出版者
- 一般社団法人日本理学療法学会連合
- 雑誌
- 理学療法学 (ISSN:02893770)
- 巻号頁・発行日
- vol.49, no.2, pp.177-184, 2022 (Released:2022-04-20)
- 参考文献数
- 35
3 0 0 0 OA 靴下着脱動作時の体幹柔軟性に関する評価方法の検討
- 著者
- 中島 卓三 木下 一雄 伊東 知佳 吉田 啓晃 金子 友里 樋口 謙次 中山 恭秀 安保 雅博
- 出版者
- 公益社団法人 日本理学療法士協会
- 雑誌
- 理学療法学Supplement Vol.39 Suppl. No.2 (第47回日本理学療法学術大会 抄録集)
- 巻号頁・発行日
- pp.Cb0737, 2012 (Released:2012-08-10)
【目的】 我々は人工股関節全置換術(以下THA)後の靴下着脱動作に関与する機能的因子について検討している。靴下着脱動作は上肢・体幹・下肢の全身の複合的な関節運動であり、先行研究では靴下着脱動作における体幹の柔軟性の影響を明らかにすることが課題であった。THA患者の靴下着脱には脱臼防止のために股関節を屈曲・外転・外旋で行う長座位開排法(以下 長座位法)と端座位開排法(以下 端座位法)があるが、両法における脊柱の分節的可動性の違いを明らかにした報告はない。本研究の目的は、THA患者での検討の予備研究として、健常成人を対象に、靴下着脱肢位の違いによる脊柱の分節的可動を明らかにするとともに、靴下着脱時の脊柱分節性をより反映しうる評価方法を検討することである。【方法】 対象は健常男性20名(平均年齢31.6±6.3歳,身長172.4±4.6cm,体重65.8±7.0kg)、靴下着脱方法は長座位法・端座位法の2肢位で行った。体幹柔軟性の評価は一般的に使用されている長座位体前屈(以下 LD)と、今回新たな評価方法として下肢後面筋の影響を排除した端座位で膝・股関節屈曲90度、腕組みの状態から骨盤を後傾し体幹を屈曲させ肩峰と大転子を近づけるよう口頭指示して行う方法(SF)で評価した。測定にはスパイナルマウス(Index社製)を使用し、長座位法・端座位法・LD・SFの4肢位について、Th1~Th12までの上下椎体間が成す角度の総和を胸椎彎曲角、L1~L5までの上下椎体間が成す角度の総和を腰椎彎曲角、仙骨と鉛直線が成す角度を仙骨傾斜角として計測した。脊柱後彎(屈曲)および仙骨前傾は正、脊柱前彎(伸展)および仙骨後傾は負で表記した。長座位法・LDは安静長座位との差を、端座位法・SFは安静端座位との差を算出した。統計処理にはSPSS(ver19)を使用し、長座位法と端座位法およびLDとSFの相違を確認するためにWilcoxonの符号付き順位和検定を用い、靴下着脱動作それぞれとLD・SFとの関連にはSpearmanの順位相関係数を求め検討した。【説明と同意】 本研究は、当大学倫理委員会の承認を得て、ヘルシンキ宣言に則り施行した。【結果】 各測定値の平均は胸椎彎曲角(長座位法:端座位法:LD:SF=37.65±23.54度:44.45±8.89度:47.10±31.40度:64.55±18.03度)、腰椎彎曲角(41.00±9.44度:32.25±7.77度:44.80±13.71度:36.75±6.74度)、仙骨傾斜角(-18.30±5.00度:-16.75±9.04度:-5.45±10.84度:-19.20±7.33度)であった。長座位法と端座位法の違いでは腰椎彎曲角・仙骨傾斜角で有意差が認められ(p<0.01)、LD とSFの違いでは全ての項目で有意差が認められた(胸椎彎曲角・仙骨傾斜角:p<0.01、腰椎彎曲角:p<0.05)。また長座位法とLD・SFの関係では、LDの仙骨傾斜角(rs=0.77、p<0.01)で相関を認められた。端座位法とLD・SFの関連性では、SFの腰椎彎曲角(rs=0.72、p<0.01)・仙骨傾斜角(rs=0.52、p<0.05)で相関を認めた。【考察】 着脱肢位の違いによる脊柱の分節性では腰椎彎曲角・仙骨傾斜角が異なっており、下部体幹の分節性に違いがみられた。宮崎ら(2010)は、LDはSLRを代表とするハムストリングスや股関節の柔軟性を反映し、脊柱の柔軟性まで反映し難いと報告している。今回の結果からも長座位法は下肢の柔軟性の影響により、腰椎の後彎・仙骨の後傾の可動性が必要であると考えた。しかし、THA患者の場合では腰椎前彎、股関節屈曲制限を呈することが多いため、胸椎の後彎やその他の部位での代償が必要であると考えられた。一方、体幹柔軟性の評価方法の比較ではLDとSFは胸椎・腰椎・骨盤すべてにおいて異なった分節性であることが確認された。また、長座位法とLDの仙骨傾斜角で相関を認め、端座位法とSFの腰椎彎曲角・仙骨傾斜角で相関を認めた。LDは下肢の柔軟性の影響により仙骨の分節性を反映する評価方法であると考えられた。一方、SFに関しては端座位での腰椎・仙骨の分節性を反映し得る体幹柔軟性の評価方法であると考えられた。しかし、いずれの結果も健常人での比較であるため、股関節やその他の部位による多様の運動方略を持ち合わせていると考えられる。今後は股関節や腰椎の可動制限を認めるTHA患者を対象として測定を行い、着脱肢位の違いによる体幹分節性の違いを明らかにし、体幹の柔軟性を反映しうる簡便な評価方法を検討していきたい。【理学療法学研究としての意義】 体幹柔軟性評価としてLDとSFは脊柱分節性に違いがあった。靴下着脱肢位の違いによって、その評価方法は使い分ける必要があると考えられた。
2 0 0 0 OA 学会版徒手筋力検査法の開発
1 0 0 0 OA 廃用症候群患者における血液データと身体機能の関係
- 著者
- 五十嵐 祐介 中山 恭秀 中村 智恵子 平山 次彦
- 出版者
- 社団法人 日本理学療法士協会関東甲信越ブロック協議会
- 雑誌
- 関東甲信越ブロック理学療法士学会 第31回関東甲信越ブロック理学療法士学会 (ISSN:09169946)
- 巻号頁・発行日
- pp.101, 2012 (Released:2012-11-07)
【目的】廃用症候群は原疾患や症状がさまざまであり、身体機能の特徴や傾向は捉えにくい。過去の報告では、院内での疾患分類や臥床による各機能の生理的変化など数多くされているが、血液データと身体機能の検討をした報告は少ない。当院では廃用症候群における評価表を作成し、廃用症候群と診断された全症例に対し評価表を使用している。そこで、今回は当病院にて使用している廃用症候群評価表にて得られたデータを使用し、血液データと身体機能を後方視的に検討することを目的とする。【方法】対象は当院入院中にてリハビリテーション科に依頼のあった患者のうち廃用症候群と診断された患者67名(男性40名、女性27名)。評価表より年齢、臥床日数(入院時からPT開始時までの日数)、血液データ(TP、Alb、Na、Cl、K、CRP、WBC、RBC、Hb)、Barthel Index(以下:BI)、Ability Basic Movement Scale(以下:ABMS)、入院前の日常生活自立度を抽出した。解析は入院前の日常生活自立度において入院前の身体機能が屋内自立以上(A2以上)の群と屋内介助(B1以下)の2群に分け、2群間における年齢、臥床日数、各血液データ、BI、ABMSの値を対応の無いt検定にて比較した。なお、本研究はヘルシンキ宣言に則りデータの取り扱いに十分注意し抽出、解析を行った。【結果】入院前屋内動作自立群51名(平均年齢80.37±9.3歳、平均臥床日数18±20.7日、平均BI値43.5±27.6、平均ABMS値21.4±7.15)、入院前屋内動作介助群16名(平均年齢81.8±8.5歳、平均臥床日数10.94±10.5日、平均BI値13.4±13.9、平均ABMS値13.4±4.07)となり、BIにおける入浴以外の全項目、ABMS全項目及び血液データではWBCにのみそれぞれ有意差が見られた(p<.01)。【考察】今回の結果より入院以前に屋内生活が自立していた患者は、介助を要していた患者と比べ、PT介入時における基本動作能力及びADL能力において有意な差が見られた。また、血液データよりWBCにのみ有意な差が見られた。WBCは感染等に対する免疫反応の指標として使用されることが多いが有意差が見られたことより、身体機能と何らかの繋がりがある可能性が考えられる。しかし、今回の結果では原疾患や治療方法などの分類を行っていないため、具体的な考察を行うまでには至らなかった。このため、今後は疾患分類や治療法による身体機能への影響について再度検討していきたい。【まとめ】入院前の自立度の違いにより、入院後に廃用症候群と診断された患者の血液データはWBCのみに有意差がみられた。
- 著者
- 藤田 裕子 来住野 健二 木山 厚 五十嵐 祐介 中山 恭秀
- 出版者
- 公益社団法人 日本理学療法士協会
- 雑誌
- 理学療法学Supplement
- 巻号頁・発行日
- vol.2011, pp.Ab0659, 2012
【はじめに、目的】 Four Square Step Test(以下FSST)は2002年にDiteらによって考案された評価法であり、先行研究より信頼性と妥当性が検討され、臨床的なバランス評価に有用と示されている。また、健常者や脳卒中、骨関節疾患を対象とする疾患別のバランス評価としての有用性や、他の臨床的バランス評価との比較によりTimed"up and go"Test(以下TUG)と有意な相関関係が示されている。FSSTの臨床評価指標としての位置づけは他のバランス評価との比較が中心であり、実際にどのような要素が含まれていて、何を反映させている評価指標であるかは明らかにされていない。また、FSSTはテスト方法から前後左右への重心移動やまたぎ動作、後進歩行が必要と考えられ、その要素のひとつである足圧中心(以下COP)の移動が動作に反映しているのではないかと考える。しかし、パフォーマンス動作からバランスを評価できるとされているTUGやFunctional reach test(以下FRT)は、COPの軌跡や動揺を客観的に評価できる重心動揺計を用いた研究により、それぞれのテストがもつ特性や要素の検討がなされているが、FSSTの検討は見当たらない。そこで今回バランスを、静的バランス、支持基底面を変化させずにCOPを支持基底面に保持させる動的バランス、支持基底面を変化させることでCOPを支持基底面に保持する動的バランスの3つに分け、FSSTと関連性を比較することとした。それぞれのバランスの指標として、静的バランスの指標を、姿勢安定度評価指標(Index of postural stability:以下IPS)、支持基底面を変化させない動的バランスの指標をX方向とY方向の平均姿勢動揺速度(以下動揺速度)、支持基底面を変化させる動的バランスの指標を動的バランスの要素を含むTUGの3つとした。【方法】 対象は健常成人17名(男性9名、女性8名、平均年齢は27.5±4.1歳、平均身長166.2±8.1cm)であった。FSSTはDiteらによる方法を基に、TUGはPodsiodleらによる方法で測定し、練習のあと2回の計測を行い、それぞれの2回の平均値を採用した。また、重心動揺計の計測は裸足で行い、両足踵間距離は10cmとし、視線は2m先の指標を注視させ、上肢を体側に下垂させた。IPSを静的バランスの指標とし、安静立位保持の測定で得られた平均動揺速度(cm/s)を、支持基底面を変化させない動的バランスの指標とした。重心動揺計はアニマ社製GS-3000を使用しサンプリング周期50msにて計測した。解析指標としてはFSSTとTUG、IPS及び動揺速度の計4項目とした。各指標間の関係性を調べるためにそれぞれの指標において正規性の検定を行い、正規分布を確認した後、Pearsonの積率相関係数を求めた。危険率5%未満を有意水準とした。【倫理的配慮、説明と同意】 対象者にはヘルシンキ宣言に則り研究の目的と方法を説明し、同意を得た。【結果】 今回、測定結果の平均値は、FSSTは7.03±0.9秒、TUGは6.17±0.69秒、IPSは1.63±0.27、動揺速度は0.49±0.16cm/sであった。また、FSSTと各評価間の相関係数は、IPSはr=0.275、TUGはr=0.489、動揺速度はr=-0.145を示した。TUGと動揺速度はr=-0.241、IPSはr=0.475となり、動揺速度とIPSはr=-0.794となった。この内で有意な相間関係を示したものは、FSSTとTUG、IPSと動揺間で有意な相関関係を示した。【考察】 本研究においてTUGとFSSTの相関関係が示されたことは先行研究と同等の結果となったが、TUGと動揺速度の指標間では相関関係が見られなかったことは先行研究と異なる結果となった。FSSTは跨ぎ動作、重心移動、後進動作などの要素をもち、TUGは立ち座り、歩行、方向転換の要素をもっているのではないかと考えられる。また今回、健常者を対象としてFSSTの測定を行ったが、静的バランスとの関係性は認められず、動的バランスであるTUGとの関係性が示された。しかしFSSTとTUGの相関関係があるにも関わらず、要素が大きく異なっている。このことから、臨床において、これら2つの評価方法がパフォーマンスを行うことで動的バランスを評価する指標でも、独立したバランス指標となりうることができるのではないかと考える。とくにTUGには跨ぎ動作や後進歩行が含まれていないため、FSSTではこれらの要素を反映している可能性が考えられる。一方で先行研究より、TUGは高齢者を対象として、動揺速度との関連性があるとされている。今回は対象者が健常者のみの測定であったため、今後FSSTにおいて対象者を健常者以外の高齢者や疾患別に重心動揺計の計測を行い、さらに検討していく必要性があると考える。【理学療法学研究としての意義】 本研究や先行研究と合わせてFSSTとTUGは動的バランス評価として関連性があるのではないかと考えられる。今後はFSSTの要素をさらに検討していくことで、TUGとは異なった要素を含むバランス指標として臨床的に有用な指標となり得る可能性があるのではないかと考える。
1 0 0 0 OA 高信頼性・高性能をそなえた二輪用次世代制御弁式鉛蓄電池 : GYZ20L形電池の開発
- 著者
- 中山恭秀
- 出版者
- ジーエス・ユアサコーポレーション
- 雑誌
- GS Yuasa technical report (ISSN:13497618)
- 巻号頁・発行日
- vol.5, no.2, 2008-12-25
- 著者
- 川井 謙太朗 中山 恭秀 吉田 啓晃 宮野 佐年
- 出版者
- 公益社団法人 日本理学療法士協会
- 雑誌
- 理学療法学Supplement
- 巻号頁・発行日
- vol.2005, pp.A0799, 2006
【目的】肩甲胸郭関節は肩関節において、最も中枢部に位置する重要な関節である。腱板機能の重要性は知られているが、腱板が機能するためには基盤となる肩甲胸郭関節の安定性が重要である。また、肩甲胸郭関節は安定化機構に加えて、上肢運動連鎖として機能する重要な関節である。肩甲上腕関節に関与する主要筋力と握力との関連性については、廣瀬らにより報告されているが、肩甲胸郭関節に関与する筋群(前鋸筋・菱形筋・僧帽筋など)との関連性については、一切報告なされていない。そこで、Hand-held Dynamometer(以下HHD)を使用し、肩甲胸郭関節に主に関与する筋群を計測し、握力との関連性を検討することを目的とした。尚、事前に検者内信頼性に優れた検査であることを確認した。<BR>【方法】当大学倫理委員会の承諾を得て、十分に研究の目的を説明した後、実験に対し同意を得た教職員を対象とした。健常女性20歳代~60歳代の各年代20名ずつ、計100名(200肩)、利き手が右手の人とした。測定項目はMMTに基づき、肩甲骨外転と上方回旋、肩甲骨内転、肩甲骨下制と内転、肩甲骨内転と下方回旋の4動作とした。抵抗を加える部位、HHDの測定パットの位置は、MMTの段階5の徒手抵抗位置と同様とし、break testとした。握力は、握力計(松宮医科精器製作所HAND DYNAMO METER KIRO)を使用し、足幅を肩幅に開いた立位、体側垂下式にて測定した。尚、左右各々3回の平均値を採用した。<BR>【結果】握力と肩甲胸郭関節に主に関与する筋力との相関関係をPearsonの積率相関係数(p<0.001)にて求めた結果、全ての動作において、握力と正の相関が認められた。肩甲骨外転と上方回旋(右:r=0.63 左:r=0.61)、肩甲骨内転(右:r=0.38左:r=0.36)、肩甲骨下制と内転(右:r=0.33 左:r=0.31)、肩甲骨内転と下方回旋(右:r=0.35 左:r=0.39)。肩甲骨外転と上方回旋に関しては、握力と有意な正の相関が認められた。<BR>【考察】本研究では、握力と全ての筋力との間に正の相関が認められたことより、握力から肩甲胸郭関節に主に関与する筋力が予測できることが確認された。また、肩甲骨外転と上方回旋筋群のみに有意な正の相関が認められた。廣瀬らは、握力と肩甲上腕関節に関与する主要筋力との関係を調べ、肩関節屈筋群のみに有意な相関が認められたと報告している。肩関節屈曲時の計測において肩甲胸郭関節は、前鋸筋の作用により肩甲骨を胸郭に固定させ安定性を高めている。勿論、僧帽筋・菱形筋などの筋群も安定性向上のため機能しているが、前鋸筋に比べると弱い。つまり、廣瀬らの計測した肩関節屈筋群と、本研究の肩甲骨外転と上方回旋筋群(前鋸筋など)は同様の動作で測定するため、類似した結果が得られたと考える。
- 著者
- 吉田 啓晃 木下 一雄 平野 和宏 中山 恭秀 角田 亘 安保 雅博 河合 良訓
- 出版者
- 公益社団法人 日本理学療法士協会
- 雑誌
- 理学療法学Supplement
- 巻号頁・発行日
- vol.2008, pp.A3P3040, 2009
【目的】<BR>人工股関節全置換術症例は、下衣更衣動作や靴下着脱動作の獲得に難渋することが多い.その際、股関節屈曲・外転・外旋の複合的な可動域の拡大が求められる.臨床経験上、このような動作時に大転子後面の痛みを訴える場合があるが、我々が渉猟しえた範囲では、疼痛因子を検証した報告は見当たらない.今回、股関節の局所解剖を行い、股関節後面とくに股関節深層外旋筋の構造を観察した.股関節屈曲・外転・外旋運動において、外旋筋の一つである大腿方形筋の伸張が制限因子となりうるという興味深い知見を得たので報告する.<BR>【対象と方法】<BR>東京慈恵会医科大学解剖学講座の解剖実習用献体2体4肢(78歳男性、84歳女性)を対象とした.ホルマリン固定した遺体の表皮及び結合組織、脈管系、表層筋を除去し、深層外旋筋と呼ばれる梨状筋、上・下双子筋、大腿方形筋、内・外閉鎖筋筋と関節包を剖出した後、大腿骨は骨幹部1/2で切断した.遺体は観察側を上にして側臥位に固定し、股関節を他動的に屈曲、外転、外旋させた時の外旋筋群の伸張の程度を観察した.尚、肉眼で観察する限りでは4関節ともに股関節の変形は認められなかった.<BR>【結果】<BR>股関節中間位(解剖学的肢位)からの外旋に伴い深層外旋筋群はすべて弛緩した.一方、屈曲に伴い梨状筋及び大腿方形筋が伸張され、外転に伴い梨状筋、上・下双子筋、内閉鎖筋は弛緩するが大腿方形筋、外閉鎖筋は伸張された.複合的な運動では、屈曲位からの外転では梨状筋や上・下双子筋、内閉鎖筋は弛緩するが、大腿方形筋は伸張され、さらに外旋が加わると大腿方形筋は最大限に伸張され、筋線維が切れる程であった.とくに大腿方形筋を上下部の二等分した場合の下部の線維で顕著であった.<BR>【考察】<BR>骨盤と大腿骨の相対的な位置関係と筋の走行により、股関節に関する筋の作用や筋による関節運動制御は多様に変化する.解剖学書での筋の作用より、解剖学的肢位からの屈曲は梨状筋・内閉鎖筋・大腿方形筋が、また外転は大腿方形筋と外閉鎖筋が関節運動を制御すると考えられる.その中で屈曲・外転ともに制御するのは大腿方形筋であり、屈曲と外転の複合的な運動では大腿方形筋が伸張されたという今回の結果を裏付ける.さらに屈曲・外転位からの外旋では、外旋筋とされる大腿方形筋が伸張された.外転位からの外旋は、大転子後面を背側から尾側に向ける運動であり、大腿方形筋の停止部を遠ざけるため、とくに大腿方形筋の下部線維が伸張されたと考えられる.<BR>変形性股関節症による人工股関節全置換術症例では、手術の展開において大腿方形筋は温存されることが多いが、術中操作により過度のストレスがかかり、術後の関節運動時に大転子後面に痛みが生じることも予想される.今後は術中の様子も含めて、関節運動時の疼痛因子を検討する必要がある.
- 著者
- 藤田 吾郎 大髙 愛子 浦島 崇 中村 高良 中山 恭秀 小林 一成 安保 雅博
- 出版者
- 日本理学療法士学会
- 雑誌
- 理学療法学 (ISSN:02893770)
- 巻号頁・発行日
- pp.11724, (Released:2020-05-21)
- 参考文献数
- 36
【目的】先天性心疾患術後遠隔期の学童期から青年期の患者と健常者の健康関連QOL(以下,HRQOL)を比較し,HRQOL と運動耐容能や身体活動状況との関係を検討する。【方法】対象は先天性心疾患患者22 例と健常者22 例。HRQOL,運動耐容能,身体活動水準,運動習慣を評価し,両群のHRQOL の比較と,各指標との関連を分析した。【結果】HRQOL 尺度のうち,先天性心疾患群の身体的幸福感(以下,PW)が有意に低かった(p <0.05)。先天性心疾患群において,PW と嫌気性代謝閾値の間に相関を認めたが(rs = 0.472,p <0.05),最高酸素摂取量にはなかった。また身体活動水準とPW の間には相関があり(rs = 0.504,p <0.05),運動習慣のある先天性心疾患患者は習慣がない患者に比べてPW が高かった(p < 0.05)。【結論】先天性心疾患患者のHRQOL は嫌気性代謝閾値レベルの運動耐容能や身体活動状況と関連がある。
1 0 0 0 決定木による急性期脳卒中患者の転帰予測モデルの作成
- 著者
- 林 友則 保木本 崇弘 樋口 謙次 中村 高良 木山 厚 堀 順 来住野 健二 中山 恭秀
- 出版者
- 社団法人 日本理学療法士協会関東甲信越ブロック協議会
- 雑誌
- 関東甲信越ブロック理学療法士学会 (ISSN:09169946)
- 巻号頁・発行日
- vol.38, pp.P-9, 2020
<p>【目的】急性期の脳卒中診療において、早期から退院の可否や転院の必要性などに関しての転帰予測が求められる機会は多い。現在までの脳卒中転帰予測に関する報告の中で、急性期の転帰予測をフローチャート形式にて示した報告は少ない。そこで本研究では、決定木分析を用いて初回理学療法評価から転帰予測モデルを作成することを目的とした。</p><p>【方法】対象は2012年7月から2015年4月までに当大学附属4病院に入院し理学療法が開始された脳梗塞,脳内出血患者496名とした。開始日が発症当日または発症後1週間以上経過している対象59例を除いた438例(男性315 例,女性123例,年齢69.3±13.0歳)を対象とし、退院群163名と転院群275名の2群に分類した。理学療法開始日数、NIHSS、GCS、上田式12段階片麻痺機能検査(以下、12グレード法)、ABMS各項目、年齢、病態(脳梗塞、脳出血)、性別、就労の有無、キーパーソンの有無、同居家族の有無、家屋環境をカルテおよび評価表より収集した。それらを独立変数として、退院、転院を従属変数とした決定木分析を実施した。統計解析ソフトはRを使用した。</p><p>【倫理的配慮】本研究は当大学倫理委員会の承認を得た上で、ヘルシンキ宣言に遵守して行った。</p><p>【結果】退院に関しては、NIHSSが3未満である場合(85 %)、そして、NIHSSが3以上であっても、12グレード法が9以上かつABMSの立ち上がりが2以上の場合(69 %)が退院となる決定木が得られた。転院に関してはNIHSSが3以上、12グレード法が9未満の場合(81%)と、NIHSSが3以上、12グレード法が9未満かつABMSの立ち上がりが2未満の場合(64%)が転院となる決定木が得られた。</p><p>【考察】退院の転帰予測には、NIHSSの点数に加え、分離運動の可否、立ち上がりの安静度が影響していると考える。今回の決定木による転帰予測モデルは、急性期の脳卒中診療において臨床的な判断基準を示すことが可能であり、転帰予測に有効であると考えられる。</p>
1 0 0 0 OA 前方リーチ動作中の非運動肢側肩甲帯の運動特性
- 著者
- 梅森 拓磨 中山 恭秀 安保 雅博
- 出版者
- 日本保健科学学会
- 雑誌
- 日本保健科学学会誌 (ISSN:18800211)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, no.4, pp.201-207, 2019 (Released:2019-10-05)
- 参考文献数
- 18
目的:前方リーチ動作における下部体幹の運動は,姿勢制御のために肩関節屈曲運動に先行して,運動を行う反対側に体幹側屈運動が起こると言われている.一方で,運動を行なっていない側の鎖骨,肩甲骨からなる肩甲帯を含む上部体幹の動きについての報告は渉猟した限り認めない.今回,健常成人男性の前方リーチ動作ではリーチ動作を行なっていない側の肩甲帯がどのように動いているかを解析し,その結果をもとに,運動を行なっていない側の肩甲帯の動きについて,体幹運動の影響の違い,および利き手と非利き手による違いを姿勢制御の観点から検討することである. 方法:右利き健常男性6 名(年齢平均27.8 ± 2.5 歳)の前方リーチ動作時の非運動肢肩甲帯挙上角度を三次元動作解析装置にて測定した.各組み合わせ(利き手・近位条件,非利き手・近位条件,利き手・遠位条件,非利き手・遠位条件)について,フリードマン検定を用いて統計解析を行った. 結果:到達時では,非利き手・遠位条件群に,最大角度では利き手・遠位条件群にそれぞれ有意差を認めた. 考察:非運動肢肩甲帯を用いて姿勢評価定量的に行える可能性があること,また,損傷側や運動麻痺側が利き手か非利き手かによって,到達する上肢機能のレベルが異なることが示唆された.
1 0 0 0 OA 変形性膝関節症患者におけるH/Q比とlateral thrustの関係
- 著者
- 五十嵐 祐介 平野 和宏 鈴木 壽彦 田中 真希 石川 明菜 姉崎 由佳 樋口 謙次 中山 恭秀 安保 雅博
- 出版者
- 公益社団法人 日本理学療法士協会
- 雑誌
- 理学療法学Supplement Vol.40 Suppl. No.2 (第48回日本理学療法学術大会 抄録集)
- 巻号頁・発行日
- pp.48100131, 2013 (Released:2013-06-20)
【目的】変形性膝関節症(以下膝OA)は整形外科疾患において代表的な疾患であり、関節軟骨の変性や骨棘形成など様々な臨床症状を呈する。膝OAの増悪には多くの因子が関与しており、主に肥満や膝関節の安定性、膝関節屈曲及び伸展筋力、膝関節のアライメント、歩行時におけるlateral thrustなどとされている。一方、膝OAの進行予防に関する因子として、膝OA患者の歩行や階段昇降などの動作時に膝関節屈曲筋力と伸展筋力の比であるH/Q (ハムストリングス/大腿四頭筋)比を筋電図で検討した結果、各筋のバランスが膝OA進行予防に重要であるとの指摘がされている。しかし、膝OAの増悪因子と考えられるlateral thrustと膝関節屈曲筋力、伸展筋力のバランスを表すH/Q比との関連を検討した報告は見当たらない。そこで今回、当大学附属4病院にて共通で使用している人工膝関節全置換術患者に対する評価表から、術前評価のデータを使用し、後方視的にlateral thrustとH/Q比との関係を検討することとした。【方法】対象は2010年4月から2012年8月までに当大学附属4病院において膝OA患者で人工膝関節全置換術の術前評価を実施した199肢(男性:33肢、女性:166肢、平均年齢74.1±7.3歳)とした。測定下肢は手術予定側及び非手術予定側に関わらず膝OAの診断がされている下肢とした。筋力の測定はHand-Held Dynamomater (ANIMA社製μ-tas)を使用し、端座位時に膝関節屈曲60°の姿勢で膝関節伸展と屈曲が計測できるよう専用の測定台を作成し、ベルトにて下肢を測定台に固定した状態で伸展と屈曲を各々2回測定した。測定値は2回測定したうち最大値を下腿長にてトルク換算し体重で除した値を使用した。また、lateral thrustの有無は各担当理学療法士が歩行観察により評価した。統計学的処理はlateral thrust有群(以下LT有群)と無群(以下LT無群)の2群に分け屈曲筋力、伸展筋力、H/Q比をそれぞれ対応のないt検定にて比較した。【倫理的配慮】本研究は、当大学倫理審査委員会の承諾を得て施行した。【結果】LT有群95肢(男性:22肢、女性:73肢、平均年齢74.1±7.4歳、平均伸展筋力99.9±42.2Nm/kg、平均屈曲筋力30.1±15.83Nm/kg、平均H/Q比0.34±0.23)、LT無群104肢(男性:11肢、女性:93肢、平均年齢74.5±6.5歳、平均伸展筋力95.5±47.9 Nm/kg、平均屈曲筋力35.4±21.5 Nm/kg、平均H/Q比0.44±0.38)となり、屈曲筋力とH/Q比において2群間に有意差を認めた(p<.05)。【考察】LT有群は、LT無群と比較し屈曲筋力及びH/Q比にて有意に低値を示した。lateral thrustに対し筋力の要因を検討したものでは、大腿四頭筋の最大筋力値が高いほどlateral thrustが出現しにくいという報告や、一方で大腿四頭筋の最大筋力値はlateral thrustの出現に関与しないという報告もあり、筋力の観点からは統一した見解は未だ示されていない。今回の結果にて有意差は認められなかったが伸展筋力ではLT有群の平均値がLT無群よりも高値であったことや、屈曲筋力にて有意差が認められたことは先行研究と同様の傾向を示すものはなく、lateral thrustを単一の筋力のみで検討するには難しいのではないかと考える。本研究でlateral thrustとH/Q比において有意差が認められたことより、各筋力の最大値以外にも比による筋力のバランスという観点も重要であり、lateral thrustが出現している膝OA患者に対するトレーニングとして、最大筋力のみでなく主動作筋と拮抗筋のバランスを考慮したアプローチも重要であると考える。今後はlateral thrustとH/Q比の関係を更に検討するために、歩行時における各筋の活動状態やlateral thrustの程度、立脚期における膝関節内反モーメントなどの評価にて考察を深めていきたい。【理学療法学研究としての意義】本研究の結果より、最大筋力でのH/Q比がlateral thrustの出現に関与する一因である可能性が示唆され、理学療法研究として意義のあることと考える。今後、更に考察を深めていくことでlateral thrust の制動に効果的なH/Q比の検討につなげていきたい。
- 著者
- 木下 一雄 中島 卓三 吉田 啓晃 樋口 謙次 中山 恭秀 安保 雅博
- 出版者
- 公益社団法人 日本理学療法士協会
- 雑誌
- 理学療法学Supplement
- 巻号頁・発行日
- vol.2012, pp.48100456, 2013
【はじめに、目的】我々はこれまで後方進入法による人工股関節全置換術(以下THA)後早期(退院時)における靴下着脱動作に関与する因子の検討を行ってきた。そこで本研究においてはTHA後5か月における靴下着脱動作の可否に関与する股関節の可動域を検討し、術前後の各時期における具体的な目標値を提示することを目的とした。【方法】対象は2010年の4月から2012年3月までに本学附属病院にてTHAを施行した110例116股(男性23例、女性87例 平均年齢60.9±10.8歳)で、膝あるいは足関節可動域が日本整形外科学会と日本リハビリテーション医学会が定める参考関節可動域に満たない症例は除外した。疾患の内訳は変形性股関節症85股、大腿骨頭壊死31股である。調査項目は術前、退院時(術後平均22.7±7.0日)、術後2か月時、術後5か月時の股関節屈曲、外旋、外転可動域、踵引き寄せ距離(%)(対側下肢上を開排しながら踵を移動させた時の内外果中央から踵までの距離/対側上前腸骨棘から内外果中央までの距離×100)と術後5か月時の端座位での開排法による靴下着脱の可否をカルテより後方視的に収集した。靴下着脱可否の条件は端座位にて背もたれを使用せずに着脱可能な場合を可能とし、それ以外のものを不可能とした。統計学的処理はロジスティック回帰分析を用いて目的変数を術後5か月時における靴下着脱の可否とし、説明変数を各時期における股関節屈曲、外旋、外転可動域、踵引き寄せ距離とした。有意水準はいずれも危険率5%未満とし、有意性が認められた因子に関してROC曲線を用いて目標値を算出した。【倫理的配慮、説明と同意】本研究はヘルシンキ宣言に基づき実施した。また本研究は当大学倫理審査委員会の承認を受けて施行し、患者への説明と同意を得た上で測定を行った。【結果】 術後5か月時の靴下着脱の可否は可能群103股、不可能群は13股であった。術後5か月時の靴下着脱の可否に関与する因子として、術前では股関節外旋と踵引き寄せ距離が抽出され、外旋のオッズ比(95%信頼区間)は1.124(1.037-1.219)、踵引き寄せ距離は1.045(1.000-1.092)、判別的中率は93.1%であった。それぞれの目標値、感度、特異度、曲線下面積は、外旋では25°、76.7%、92.3%、0.912で、踵引き寄せ距離は40.4%、84.5%、76.9%、0.856であった。退院時、術後2か月時、術後5か月時においては踵引き寄せ距離が因子として抽出され、退院時のオッズ比(95%信頼区間)、判別的中率は1.054(1.012-1.097)、91.4%、術後2か月時は1.092(1.008-1.183)、89.6%、術後5か月時は1.094(1.007-1.189)、91.3%であった。各時期の目標値、感度、特異度、曲線下面積は、退院時では40.4%、88.3%、61.5%、0.814であり、術後2か月時は50.0%、93.2%、61.5%、0.842で、術後5か月時では61.0%、80.1%、92.3%、0.892であった。【考察】我々の靴下着脱動作に関する先行研究は、術後早期における長座位での靴下着脱動作に関与する因子の検討であった。退院後の生活環境やリハビリ継続期間を考慮すると、実用性のある端座位での靴下着脱動作を継続期間中に獲得するための機能的因子を明確にすることが必要であった。先行研究では術前に靴下着脱が困難なものが退院時に着脱可能となるには外旋可動域が必要であった。今回の結果からも術前では股関節の変形により可動域制限がある場合でも股関節の外旋により代償して靴下着脱が可能となることが術後5か月の着脱動作能力に必要であると考えられる。また、術後5か月の靴下着脱を可能とするための機能的な改善目標として踵引き寄せ距離が抽出された。臨床的に術後の股関節可動域は概ね改善するが、疼痛や習慣的な動作姿勢の影響により改善経過は多様である。また、靴下着脱動作は股関節から足関節までの下肢全体を使った複合関節による動作である。このことから術後では単一方向の可動域を目標とするだけではなく、総合的、複合的な可動域の改善目標により着脱能力の獲得を目指すべきであると考える。具体的には術後2か月までに対側の膝蓋骨上まで踵を引き寄せられることが望ましいと考える。今後は踵引き寄せ距離に影響する軟部組織の柔軟性や疼痛の評価を行い、踵引き寄せ距離を改善するためのアプローチに関しても検討していきたい。\t【理学療法学研究としての意義】本研究により各時期の具体的な目標値が明確になり、術後5か月時までの経時的な改善指標となり得る。これにより術前後の患者指導の効率化や質の向上が図られると考える。
1 0 0 0 OA THA後の靴下着脱動作に関与する因子の検討
- 著者
- 木下 一雄 伊東 知佳 中島 卓三 吉田 啓晃 金子 友里 樋口 謙次 中山 恭秀 大谷 卓也 安保 雅博
- 出版者
- 公益社団法人 日本理学療法士協会
- 雑誌
- 理学療法学Supplement Vol.39 Suppl. No.2 (第47回日本理学療法学術大会 抄録集)
- 巻号頁・発行日
- pp.Cb1369, 2012 (Released:2012-08-10)
【はじめに、目的】 我々はこれまで後方進入法による人工股関節全置換術(THA)後の長座位および端座位における靴下着脱動作に関する研究を行ってきた。その先行研究においては靴下着脱能力と関係のある股関節屈曲、外転、外旋可動域、踵引き寄せ距離や体幹の前屈可動性の検討を重ねてきた。しかし、靴下着脱動作は四肢、体幹の複合的な関節運動であるため、少なからず罹患側の状態や術歴、加齢による関節可動域の低下などの影響を受けると考えられる。そこで本研究では、退院時の靴下着脱動作に関与する体幹および股関節可動域以外の因子を検討し、術後指導の一助とすることを目的とした。【方法】 対象は2010年の4月から2011年8月に本学附属病院にてTHAを施行した228例234股(男性54例、女性174例 平均年齢64.2±10.9歳)である。疾患の内訳は変形性股関節症192例、大腿骨頭壊死36例である。調査項目は年齢、身長、体重、罹患側(片側か両側)、術歴(初回THAか再置換)、術前の靴下着脱の可否、足関節背屈制限の有無、膝関節屈曲制限の有無をカルテより後方視的に収集した。術前の靴下着脱の可否の条件は長座位または端座位にて背もたれを使用せずに着脱可能な場合を可能とし、不可能をそれ以外の者とした。足関節背屈、膝関節屈曲可動域は標準可動域未満を制限ありとした。統計学的処理はロジスティック回帰分析を用いて目的変数を退院時における長座位または端座位での靴下着脱の可否とし、説明変数を年齢、BMI、罹患側(片側か両側)、術歴(初回THAか再置換)、術前の靴下着脱の可否とした。有意水準はいずれも危険率5%未満とした。【倫理的配慮、説明と同意】 本研究においてはヘルシンキ宣言に基づき、患者への説明と同意を得た上で測定を行った。測定データをカルテより後方視的に収集し、個人名が特定できないようにデータ処理した。【結果】 まず、長座位では、退院時の靴下着脱可能群は130例、不可能群は114例であった。可能群の平均年齢は62.8±10.6歳、不可能群は65.7±10.9歳であり、可能群の平均BMIは23.4±4.0、不可能群は24.1±3.8であった。可能群の罹患側は、片側70例、両側60例、不可能群は片側例、両側例は各57例であり、術歴は可能群の初回THAは102例、再置換は28例、不可能群の初回THAは101例、再置換は13例であった。術前の靴下着脱の可否は、可能群のうち術前着脱可能な者は74例、術前着脱不可能が56例であり、不可能群のうち術前着脱可能な者は24例、不可能な者は90例であった。また、可能群の足関節背屈制限は4例、不可能群は3例であり、可能群の膝関節屈曲制限は3例、不可能群は15例であった。一方、端座位では、退院時の靴下着脱可能群は110例、不可能群は134例であった。平均年齢は可能群62.2±10.9歳、不可能群65.8±10.7歳、可能群の平均BMIは23.2±4.1、不可能群は24.1±3.6であった。罹患側に関しては、可能群の片側59例、両側51例、不可能群は片側69例、両側65例であった。術歴に関しては可能群の初回THAは84例、再置換は26例、不可能群では初回THAは112例、再置換は22例であった。術前の靴下着脱の可否に関しては、可能群では79例が術前の着脱が可能、31例が着脱不可能であり、不可能群は術前の着脱可能な者は34例、不可能な者は100例であった。可能群の足関節背屈制限は3例、不可能群は4例であり、可能群の膝関節屈曲制限は2例、不可能群は16例であった。統計処理の結果、長座位での靴下着脱因子は術前の靴下着脱の可否が抽出され、端座位での靴下着脱因子には術前の靴下着脱の可否と年齢が抽出された。(p<0.01)。【考察】 本研究においては退院時における靴下着脱動作に関与する体幹および股関節可動域以外の因子を検討した。先行研究では本研究と同様に術前の着脱の可否が術後の可否に関与しているという報告があるが、いずれも症例数が少ない研究であった。本研究の結果より術前の着脱の可否は術後早期における着脱の可否に関与しており、術前患者指導の必要性を示唆するものである。端座位着脱における年齢の影響に関しては、加齢または長期の疾病期間に伴う関節可動域の低下、あるいは着脱時の筋力的な要因が考えられる。今後は症例数を増やして詳細な因子分析を行いながら、縦断的な検討も加えていきたい。【理学療法学研究としての意義】 THAを施行する症例は術前より手を足先に伸ばすような生活動作が制限され、術後もその制限は残存することが多い。本研究により靴下着脱動作に関与する因子を明らかにすることで術前後の患者指導の効率化や質の向上が図られると考える。
1 0 0 0 OA 斜面板上立位姿勢保持が立位・歩行に及ぼす作用と理学療法への応用
- 著者
- 中山 恭秀
- 巻号頁・発行日
- 2012
筑波大学博士 (リハビリテーション科学) 学位論文・平成24年3月23日授与 (甲第6180号)