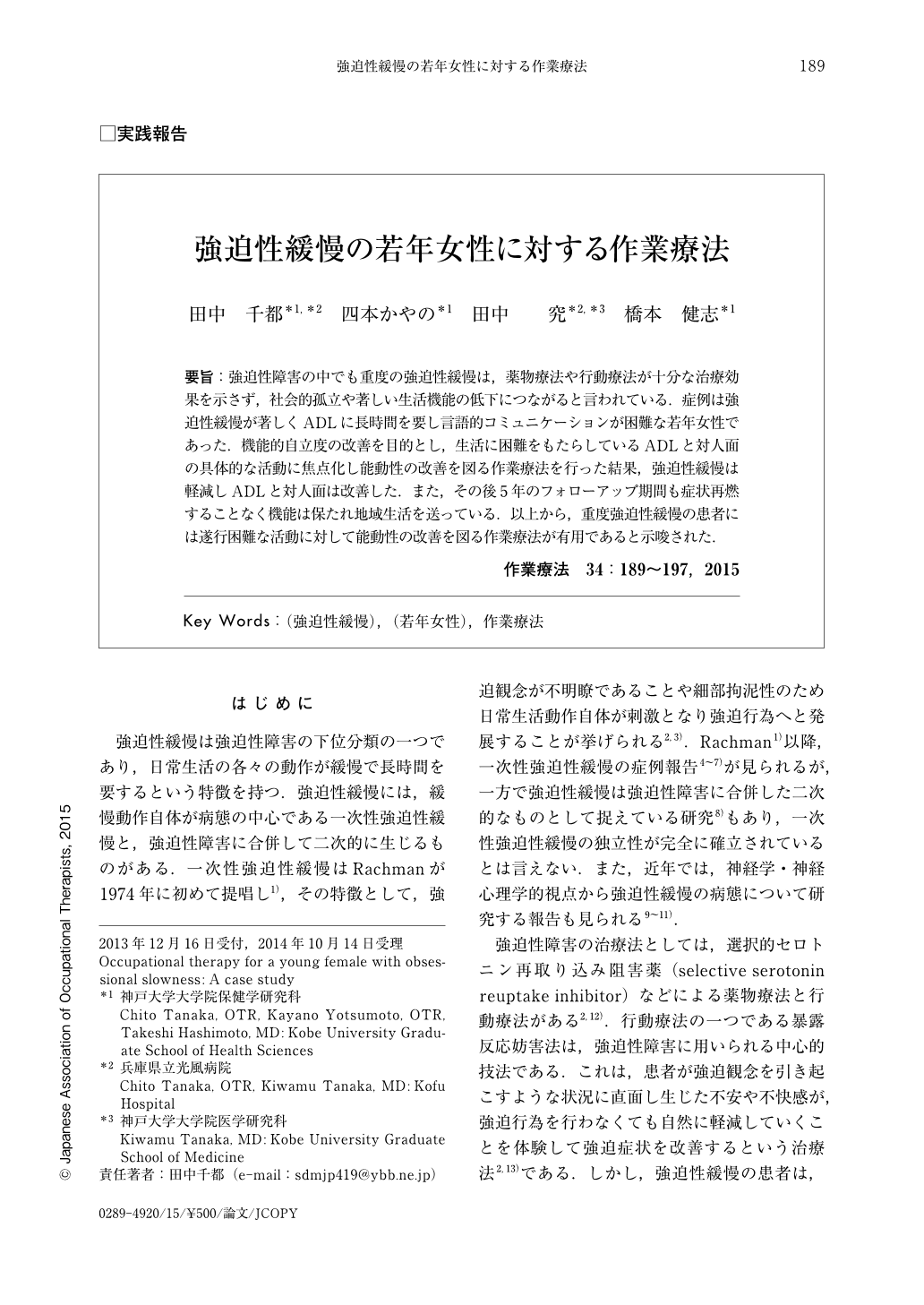54 0 0 0 OA 福島第一原子力発電所で採取された放射性廃棄物中のPd-107分析法の開発
23 0 0 0 OA 福島第一原子力発電所の滞留水への放射性核種放出
- 著者
- 西原 健司 山岸 功 安田 健一郎 石森 健一郎 田中 究 久野 剛彦 稲田 聡 後藤 雄一
- 出版者
- Atomic Energy Society of Japan
- 雑誌
- 日本原子力学会和文論文誌 (ISSN:13472879)
- 巻号頁・発行日
- pp.1202060058, (Released:2012-02-08)
- 参考文献数
- 15
- 被引用文献数
- 29 35
After the severe accident in the Fukushima-1 nuclear power plant, a large amount of contaminated stagnant water has been produced in turbine buildings and surrounding areas. This rapid communication reports the calculation of the radionuclide inventory in the core, the collection of the measured inventory in the stagnant water, and the estimation of the radionuclide release ratios from the core to the stagnant water. The present evaluation is based on data obtained before June 3, 2011. It was revealed that the release ratios of tritium, iodine and cesium were several tens of percent, while those of strontium and barium were smaller by one or two orders of magnitude. These release ratios of the Fukushima accident were equivalent to those of the TMI-2 accident.
18 0 0 0 OA 福島第一原子力発電所の滞留水への放射性核種放出
- 著者
- 西原 健司 山岸 功 安田 健一郎 石森 健一郎 田中 究 久野 剛彦 稲田 聡 後藤 雄一
- 出版者
- Atomic Energy Society of Japan
- 雑誌
- 日本原子力学会和文論文誌 (ISSN:13472879)
- 巻号頁・発行日
- vol.11, no.1, pp.13-19, 2012 (Released:2012-02-15)
- 参考文献数
- 15
- 被引用文献数
- 30 35
After the severe accident in the Fukushima-1 nuclear power plant, a large amount of contaminated stagnant water has been produced in turbine buildings and surrounding areas. This rapid communication reports the calculation of the radionuclide inventory in the core, the collection of the measured inventory in the stagnant water, and the estimation of the radionuclide release ratios from the core to the stagnant water. The present evaluation is based on data obtained before June 3, 2011. It was revealed that the release ratios of tritium, iodine and cesium were several tens of percent, while those of strontium and barium were smaller by one or two orders of magnitude. These release ratios of the Fukushima accident were equivalent to those of the TMI-2 accident.
10 0 0 0 解離性障害における幻聴についての精神病理学的考察
- 著者
- 田中 究
- 出版者
- 神戸大学
- 雑誌
- 神戸大学医学部紀要 (ISSN:00756431)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, no.3, pp.337-350, 1997-03
幻覚,特に幻聴は,通常,分裂病を中心に精神病症状の病理を典型的に現すとされているが,外傷後ストレス障害,境界性人格障害,身体化障害,あるいは解離性同一性障害をはじめとする解離性障害など,神経症圏の疾患にみられることもまれではない。シュナイダーの一級症状による鑑別では分裂病とこれらの神経症性の疾患が誤診されることがある。しかし,かれらの幻聴を観察すると知覚性が高く意味性に乏しいこと,幻聴の他者を世界内に位置づけ得ることで分裂病性の幻聴から区別することができる。こうした神経症性の幻聴は観察によれば聴覚性のフラッシュパック,想像上の友人によるもの,交代人格によるものの三種類に分類され,これらの鑑別が診断に結びつく。しかし,これには注意深い観察と面接を要する。また,幻聴を有する神経症圏内の患者には健忘,離人症,現実感喪失,同一性の混乱や変容といった解離症状が認められる。これは心的外傷,小児期の虐待の後遺障害と考えられる。幻聴はこの解離に関係しており,幻聴を持つ神経症患者においては解離症状を疑い,その背景にある心的外傷に注目することが治療の端緒になる。またこうした幻聴には薬物がほとんど無効で治療の中心は精神療法である。
8 0 0 0 OA 子ども虐待とケア
- 著者
- 田中 究
- 出版者
- 一般社団法人 日本児童青年精神医学会
- 雑誌
- 児童青年精神医学とその近接領域 (ISSN:02890968)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, no.5, pp.705-718, 2016-11-01 (Released:2017-05-17)
- 参考文献数
- 73
近代になって子ども虐待は民間福祉機関や個人によって気付かれ, 子どもの保護が始められ, それを公的機関, 司法が支援してきた。しかし, そのことで市民社会からは見えにくくなっていた。Kempら(1962)の「殴打された子の症候群(Battered Child Syndrome)」の報告は, 子ども虐待対応の枠組みを, 福祉モデルから医療モデルに変化させた。こうして, 子ども虐待は再発見されたのである。虐待された子どもの現す特異な行動は, 心的トラウマの症状として診断され, 社会病理ばかりではなく養育者の精神病理が虐待の要因として捉えられるようになった。その上で, 子どもの心的トラウマを評価し, 治療することの知見や研究が積み重ねられ, 治療技法が考案されている。さらに, 基本的なアタッチメントへの理解がすすみ, アタッチメントの再構築についても議論されるようになった。こうした治療的な関与には医療だけではなく, 福祉, 保健, 教育, 司法がそれぞれ相補的な役割を果たし, 協働していくことが一層重要である。
2 0 0 0 OA 心的外傷との関連からみた精神分裂病患者の解離症状
- 著者
- 宋 建華 福島 春子 胡桃澤 伸 田中 究
- 出版者
- 神戸大学
- 雑誌
- 神戸大学医学部紀要 (ISSN:00756431)
- 巻号頁・発行日
- vol.61, no.4, pp.145-177, 2001-03-31
- 被引用文献数
- 1
精神分裂病患者で成育歴に心的外傷体験を持つものは少なくないが, このような患者には精神分裂病固有の症状に加え, 心的外傷に起源をもっと考えられる症状を認めることがある。著者らは, 神戸大学精神神経科外来に通院する90名の精神分裂病患者に対して, 解離症状質問票 (Dissociation Questionnaire ; DIS-Q) および解離体験尺度 (Dissociative Experience Scale ; DES) を用いて, 心的外傷に関連した症状とその頻度を調査し, 検討した。さらに簡易精神症状評価尺度 (Brief Psychiatric Rating Scale ; BPRS) を用いて解離と精神症状の関連について調査した。この結果, 精神分裂病患者においても, 健常群や他疾患群と同様に解離傾性を認めた。高解離群では精神分裂病の発症年齢が有意に低く, 心的外傷後ストレス障害にみられる症状を認めた。また, 心的外傷を有する群は解離傾性が高く, 心的外傷のない群より, 離人感, 現実感喪失および行動, 思考, 感情の制御不全が生じやすく, 心的外傷のない群では情動の平板化, 感情緊張の低下, 感受性や興味, 関心の欠如といったいわゆる陰性症状が優位に見られた。また, DESとDIS-Qは強い相関を認め, 精神分裂病の解離傾性を解析するのにDISQはDESと同様, 有用な検査法であることが示された。現象的に精神分裂病症状の中に心的外傷起源の幻聴 (解離性フラッシュバック) が含まれ, 言語的あるいは非言語的な刺激, 特定の状況, それにともなう感情を想起したときに, 思路障害が生じる場合があることを示し, 精神病理学的な検討を試み, 心的外傷を考慮した精神分裂病治療が必要であることを述べた。
2 0 0 0 児童養護施設入所児の精神医学的評価とその治療に関する研究
被虐待児童の評価として、既に十分に確立している精神疾患概念(診断基準)を用いて評価し、被虐待児童の精神症状、心理的影響について、その成育史上の特徴との関連を明らかにすることは有用であると考えられ、調査を実施した。本調査は兵庫県児童擁護連絡協議会および神戸市養護施設連盟に加盟する児童養護施設(28施設)において行ったものである。その結果、児童養護施設には高率に被虐待児が入所しており、また何らかの精神症状、精神疾患を持つものも高率におり、児童養護施設はもはや生活施設としてではなく、療育・治療の施設としての位置づけがなされなくてはならない状況であった。また、2施設においては悉皆調査を行い、児童の精神医学的診断を質問紙法(子ども用面接(ChIPS))でおこない、加えて児童の観察および診察および事例検討を通して精神科医および小児科医、臨床心理士が評価を行った。また、この評価と生活状況、養育環境および虐待体験の有無、虐待の種類などについて検討し、統計学的解析を行った。この結果、児童養護施設入所時のうち被虐待児の割合は70%認め、何らかの精神症状を持つ児童が74.7%認めた。その内訳は反応性愛着障害35%、注意欠陥多動性障害23%、反抗挑戦性障害28%、行為障害28%、全般性不安障害16%、気分変調・抑うつ状態16%、遺尿(夜尿)18%、解離症状24%、感情コントロール不全16%、知的障害19%などを認めた。さらに、乳児院を経て入所した児童は、反応性愛着障害、注意欠陥多動性障害、反抗挑戦性障害で有意に多かった。これらの児童への治療は、身体医学的治療(薬物療法)および精神医学的治療を医師らがあたり、心理学的治療(遊戯療法、芸術療法、認知行動療法、など)は臨床心理士等に業務依頼し、経時的にこれらの症状評価を行った。研究協力者として加藤寛氏(兵庫県こころのケア研究所研究部長)、井上雅彦氏兵庫教育大学発達心理臨床研究センター准教授)に評価、治療等へのご協力を頂いた。
2 0 0 0 阪神・淡路大震災被災地区精神科入院者調査
- 著者
- 麻生 克郎 太田 正幸 長尾 卓夫 岩尾 俊一郎 田中 究
- 雑誌
- 精神神經學雜誌 = Psychiatria et neurologia Japonica (ISSN:00332658)
- 巻号頁・発行日
- vol.98, no.10, pp.751-757, 1996-10-25
- 参考文献数
- 5
- 被引用文献数
- 1
1 0 0 0 強迫性緩慢の若年女性に対する作業療法
要旨:強迫性障害の中でも重度の強迫性緩慢は,薬物療法や行動療法が十分な治療効果を示さず,社会的孤立や著しい生活機能の低下につながると言われている.症例は強迫性緩慢が著しくADLに長時間を要し言語的コミュニケーションが困難な若年女性であった.機能的自立度の改善を目的とし,生活に困難をもたらしているADLと対人面の具体的な活動に焦点化し能動性の改善を図る作業療法を行った結果,強迫性緩慢は軽減しADLと対人面は改善した.また,その後5年のフォローアップ期間も症状再燃することなく機能は保たれ地域生活を送っている.以上から,重度強迫性緩慢の患者には遂行困難な活動に対して能動性の改善を図る作業療法が有用であると示唆された.
- 著者
- 西原 健司 山岸 功 安田 健一郎 石森 健一郎 田中 究 久野 剛彦 稲田 聡 後藤 雄一
- 出版者
- Atomic Energy Society of Japan
- 雑誌
- 日本原子力学会和文論文誌 (ISSN:13472879)
- 巻号頁・発行日
- vol.11, no.3, pp.247, 2012 (Released:2012-08-15)
日本原子力学会和文論文誌 Vol. 11, No. 1 (2012), pp.13-19 著者の申し出により,14–16頁の Table 4, 7(1/2), 7(2/2)に誤りがありましたので,PDFの通り訂正いたします。
1 0 0 0 虐待と解離性障害
- 著者
- 田中 究
- 出版者
- 日本児童青年精神医学会
- 雑誌
- 児童青年精神医学とその近接領域 (ISSN:02890968)
- 巻号頁・発行日
- vol.46, no.5, pp.511-516, 2005-11-01
- 被引用文献数
- 1