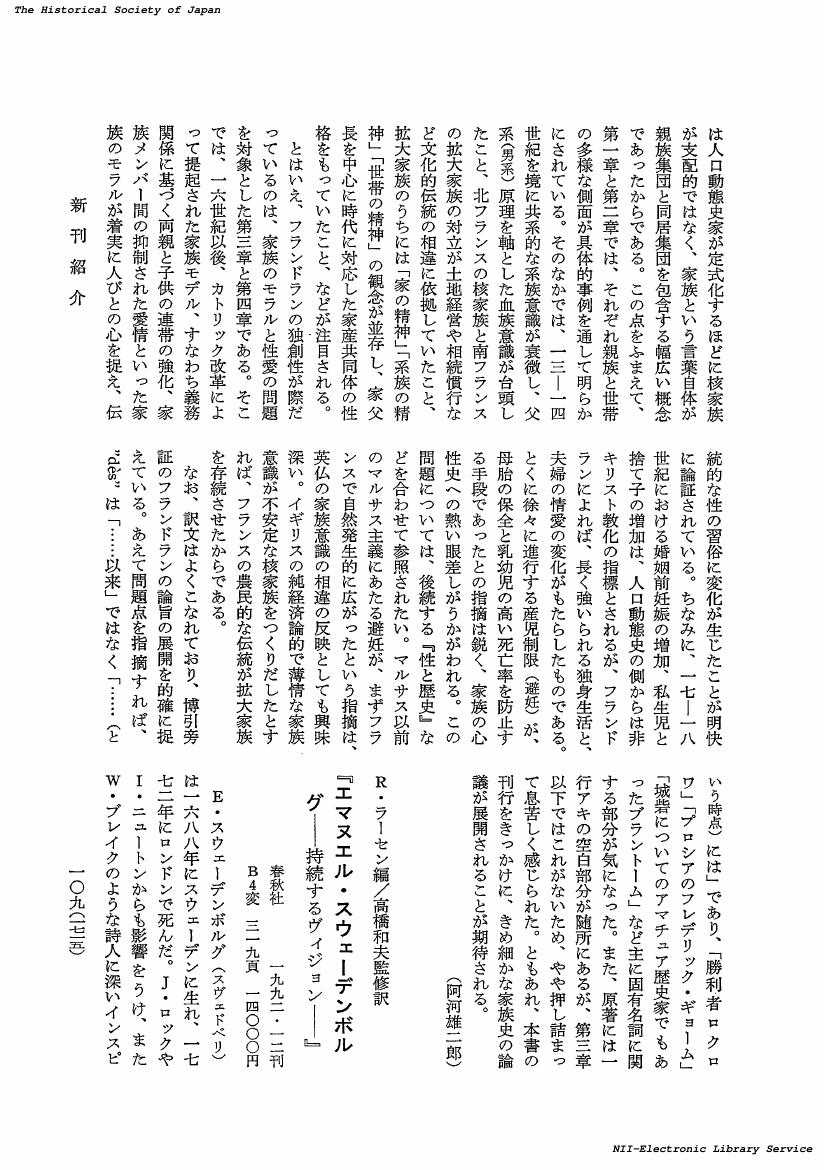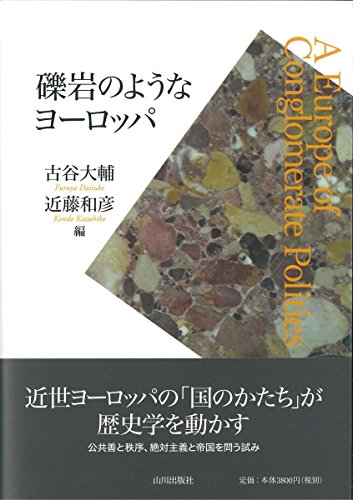50 0 0 0 OA ジャコバン主義の再検討:「王のいる共和政」の国際比較研究
本研究は、「王のいる共和政」の国際比較を通じて、近代ヨーロッパ共和主義の再検討を行った。この結果、ハンガリー、ドイツ、ポーランド、スウェーデン、オーストリアにおいて、「王のいる共和政」というジャコバン思想と運動が存在したことを解明した。さらに、これらの地域における「王のいる共和政」論の源流を、16世紀の政治的人文主義(political humanism)による古代ローマ共和政の近世的再解釈に見出した。加えて、この思想が啓蒙絶対王政を正当化するための主導的原理として機能したことを実証した。このようにして、この原理が1790年代の中・東欧において広範に拡大することになったのである。
7 0 0 0 IR 註釈『イギリス史10講』(上) : または柴田史学との対話
- 著者
- 近藤 和彦
- 出版者
- 立正大学大学院文学研究科
- 雑誌
- 立正大学大学院紀要 = Bulletin of the Graduate School of Humanities and Sociology, Rissho University (ISSN:09112960)
- 巻号頁・発行日
- no.30, pp.71-87, 2014
5 0 0 0 OA 註釈『イギリス史10講』(下の2)―または柴田史学との対話―
- 著者
- 近藤 和彦
- 出版者
- 立正大学大学院文学研究科
- 雑誌
- 大学院紀要 = Bulletin of the Graduate School of Humanities and Sociology Rissho University (ISSN:09112960)
- 巻号頁・発行日
- no.36, pp.1-14, 2020-03-31
- 著者
- 近藤 和彦
- 出版者
- 公益財団法人 史学会
- 雑誌
- 史学雑誌 (ISSN:00182478)
- 巻号頁・発行日
- vol.87, no.7, pp.1191-1192, 1978-07-20 (Released:2017-10-05)
2 0 0 0 IR 註釈『イギリス史10講』(中)または柴田史学との対話
- 著者
- 近藤 和彦
- 出版者
- 立正大学大学院文学研究科
- 雑誌
- 立正大学大学院紀要 = Bulletin of the Graduate School of Humanities and Sociology, Rissho University (ISSN:09112960)
- 巻号頁・発行日
- no.32, pp.13-25, 2016
- 著者
- 近藤 和彦
- 出版者
- 立正大学史学会
- 雑誌
- 立正史学 (ISSN:03868966)
- 巻号頁・発行日
- no.113, pp.25-41, 2013
1 0 0 0 OA 史学会公開シンポジウム「天皇像の歴史を考える」コメント
- 著者
- 近藤 和彦
- 出版者
- 公益財団法人 史学会
- 雑誌
- 史学雑誌 (ISSN:00182478)
- 巻号頁・発行日
- vol.129, no.10, pp.76-84, 2020 (Released:2021-12-01)
天皇像の歴史を君主(monarch)の歴史の共通性において、また特異性において理解したい。ちなみに西洋史で、両大戦間の諸学問をふまえて君主制の研究が進展したのは1970年代からである。2つの面からコメントする。 A 広く君主制(monarchy)の正当性の要件を考えると、①凱旋将軍、紛議を裁く立法者、神を仲立ちする預言者・司祭といったカリスマ、②そうしたカリスマの継承・相続、③神意を証す聖職者集団による塗油・戴冠の式にある。このうち②の実際は、有力者の推挙・合意によるか(→ 選挙君主)、血統によるか(→ 世襲君主)の両極の中間にあるのが普通である。イギリス近現代史においても1688~89年の名誉革命戦争、1936年エドワード8世の王位継承危機のいずれにおいても、血統原則に選挙(群臣の選み)が接ぎ木された。天皇の継承史にも抗争や廃位があったが、万世一系というフィクションに男子の継体という male chauvinism が加わったのは近代の造作である。 B 近世・近代日本の主権者が欧語でどう表現されたかも大きな問題である。1613年、イギリス国王ジェイムズが the high and mightie Monarch, the Emperour of Japan に宛てた親書を、日本側では将軍(大御所)が処理し、ときの公式外交作法により「源家康」名で返書した。幕末維新期にはミカド、大君などの欧語訳には混迷があり、明治初期の模索と折衝をへて、ようやく1873~75年に外交文書における主権者名が「天皇」、His Majesty the Emperor of Japan と定まった。NED(のちのOED)をふくむすべての影響力ある辞書はこの明治政府の定訳に従順である。じつは emperor / imperator は主権者にふさわしい名称かもしれないが、そもそも血統という含意はないので、万世一系をとなえる天皇の訳語としては違和感がぬぐえない。とはいえ、世界的に19世紀は多数の「皇帝」が造作された権威主義の時代でもあった。
- 著者
- 中村 悟之 近藤 和彦 三重野 哲
- 出版者
- 一般社団法人 日本物理学会
- 雑誌
- 日本物理学会講演概要集
- 巻号頁・発行日
- vol.71, pp.594, 2016
<p>本実験は、宇宙空間における小惑星衝突を想定したモデル実験である。高速飛翔体の衝突時に発生する高温プルーム内の分子回転温度や黒体温度を測定することにより、実際の小惑星衝突での分子形成の様子を解明することを目的としている。高速飛翔体にはポリカーボネイト弾を使用し、標的には鉄と水とヘキサンを、充填気体には窒素を用いた。衝突後の高温ガス中にはCN分子が多く含まれ、その発光からCN分子回転温度の特性を調べた。また、同時に、黒体輻射温度も測定した。</p>
- 著者
- 近藤 和彦
- 出版者
- 公益財団法人 史学会
- 雑誌
- 史学雑誌 (ISSN:00182478)
- 巻号頁・発行日
- vol.97, no.3, pp.321-357,423-42, 1988
Manchester in the eighteenth century has been associated with the coming of the industrial revolution. Certainly it would become one of the leading centres of the capitalist world economy in the nineteenth century, but it was still 'one of the greatest mere villages in England', famous for its textile trade, with a population of some twenty thousand, in the age of Defoe and Walpole. More significantly for the purpose of this paper the parish of Manchester was in the diocese of Chester, a part of the country notorious for party strife and as 'disaffected'. The collegiate parish church was a stronghold of high church clergymen, while the parish contained a sizeable cluster of dissenters (mainly presbyterians) which amounted to 422 families out of 3201, i.e. more than 13% of the whole and more than twice the national average of 6.2%. My analysis in this paper is focused first on the clerical quarrels within the collegiate church of Manchester from 1718 to 1728. Samuel Peploe (1668-1752), who had proved his spirit against the Jacobites in 1715 as vicar of Preston, was promoted by the whig government warden of Manchester in 1718 (and then bishop of Chester in 1726). He would have to face hard years in dealing with the high churchmen and non-jurors in the church and the parish. Secondly the workhouse project and the opposition in the town are analysed from 1729 to 1731. John Byrom (1692-1763), a high churchman of letters and stenographer, was one of the most active opponents of the scheme. His correspondence, diaries and poems, together with parliamentary and other sources, reveal a good deal of the hitherto hidden social alignments of the Mancunians and clarify other often misrepresented circumstances. Factious rivalry infected the town, and such public projects as an incorporated workhouse were doomed to failure by the opposition of high churchmen (tories), who feared that the alliance of low churchmen and dissenters (whigs) might dominate not only the incorporated trust, but also the administration and finance of the town. The intended bill for the workhouse became an issue of party politics in Parliament, and was defeated in April 1731 by an alliance of tories and whig opposition members. Byrom's return to Manchester on 10 June (the Pretender's birthday) was welcomed at the collegiate church, where Peploe remained beset as warden. The sources I rest upon are both local and central, unpublished and published, v. notes. I have edited the most relevant documents relating to the workhouse issue in the Bulletin of the Faculty of Letters, Nagoya University, vol.33 (1987). The article containing the selected documents is abbreviated as WH, and referred to on page 45 (note 4).
- 著者
- 近藤 和彦
- 出版者
- 績文堂出版
- 雑誌
- 歴史学研究 = Journal of historical studies (ISSN:03869237)
- 巻号頁・発行日
- no.1000, pp.24-31, 2020-09
- 著者
- 近藤 和彦
- 出版者
- 公益財団法人 史学会
- 雑誌
- 史学雑誌 (ISSN:00182478)
- 巻号頁・発行日
- vol.102, no.9, pp.1715-1716, 1993-09-20 (Released:2017-11-29)
1 0 0 0 OA 岸田 紀著『ジョン・ウェズリ研究』
- 著者
- 近藤 和彦
- 出版者
- 公益財団法人 史学会
- 雑誌
- 史学雑誌 (ISSN:00182478)
- 巻号頁・発行日
- vol.86, no.11, pp.1646-1653, 1977-11-20 (Released:2017-10-05)
1 0 0 0 礫岩のようなヨーロッパ
- 著者
- 古谷大輔 近藤和彦編
- 出版者
- 山川出版社
- 巻号頁・発行日
- 2016
- 著者
- 近藤 和彦
- 出版者
- 公益財団法人 史学会
- 雑誌
- 史学雑誌 (ISSN:00182478)
- 巻号頁・発行日
- vol.100, no.9, pp.1640-1641, 1991-09-20 (Released:2017-11-29)
1 0 0 0 OA インタビュー:近藤和彦教授ロング・インタビュー
- 著者
- 近藤 和彦 クリオ編集部 後藤 はる美 伊藤 剛史 辻本 諭
- 出版者
- 東京大学大学院人文社会系研究科西洋史学研究室「クリオの会」
- 雑誌
- クリオ = Clio : a journal of European studies
- 巻号頁・発行日
- vol.25, pp.1-48, 2011
1 0 0 0 修正主義をこえて(史学会第一〇〇回記念大会講演要旨)
- 著者
- 近藤 和彦
- 出版者
- 公益財団法人史学会
- 雑誌
- 史學雜誌 (ISSN:00182478)
- 巻号頁・発行日
- vol.111, no.12, pp.1986-1988, 2002-12-20
1 0 0 0 OA 近世ヨーロッパ周縁世界における複合的国家編成の比較研究
- 著者
- 近藤 和彦 石井 康之 伊藤 浩司 沼口 寛次
- 出版者
- 日本作物学会
- 雑誌
- 日本作物学会九州支部会報 (ISSN:02853507)
- 巻号頁・発行日
- no.60, pp.50-53, 1994-03-11
- 被引用文献数
- 1
春播き(4月5日播種)および秋播き(1O月1日播種)のベントグラスにおいて,冬期の乾物生長に対する生長調節剤処理の影響について検討した。生長抑制剤バウンティ散布区(B区),蒸散抑制剤ミドリテール散布区(M区)および対照区(C区)を設け,B区は11月中旬に1回のみ,M区は11月中旬より2週間間隔で,春播きは計8回,秋播きは計上0回処理した。地上部乾物重は,処理後4週間目ではB区が最も小さかったが,春播きでは2月11日以降,秋播きでは1月7日以降B区の地上部重が他の2区よりも大きくなった。秋播きの刈株乾物重および葉身重比率は,B区が一貫して他の2区よりも有意に大きかった。茎数は,生長抑制剤処理により増加し,その処理の影響は秋播きの方が大きいことが示された。これは処理開始時までの茎数が,秋播きでは少なく,茎数増加期に相当していたことによると推察された。したがって,地上部重の区間差は、主に茎数の差によっていた。クロロフィル濃度は宇B区の値が他の2区より高く維持された。M区の生長経過はC区に比べて優ることはなかった。以上により,冬期における生長の抑制と葉身の退色を緩和するには,秋における生長抑制剤の散布は有効であると推察された。