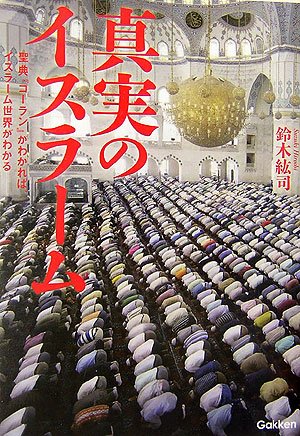96 0 0 0 OA 耳鼻咽喉科領域における針灸治療 その1鼻咽頭症候群
- 著者
- 鈴木 紘
- 出版者
- 公益社団法人 全日本鍼灸学会
- 雑誌
- 日本鍼灸治療学会誌 (ISSN:05461367)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, no.3, pp.74-78, 1980-07-15 (Released:2011-05-30)
- 参考文献数
- 5
Method.1. The treatment was given to 23 patients.2. In order to relieve stiffness in the shoulders and the nape, acupuncture was administered at the following points: BL-10, GB-20, GB-12, TH-17, GB-21, TH-14, BL-11, BL-38, GV-20, GV-12, LI-4, LI-10, HT-7, KI-3, TH-4, GB-41 etc.3. On the shoulders and the nape, stationary insertion was administered was given for 15 minutes.Results.1. Effective results were obtained in 12 cases. Therefore, 52 percent of all patients responded well to the treatment.2. In my last report for the 24th Congress it was 60 percent for 45 patients suffering from the same syndrome. Together with those reported in the previous paper, the results obtained there suggest that favorable results were obtained in 57% of the 68 patients complaining of epipharyugeal syndrome.4. This kind of disease or syndrome almost always has its onset from May to August. This was true in 70 percent of all patients.5. Occupational breakdown showed most of the made patients to be white collar workers and female patients to be housewives.Conclusion.Stiffness is intimately related with diseases. For this reason it may be very important to give treatment to the shoulders and the nape together with the later nape.
1 0 0 0 偽ニュース:誰が信じ,広めるのか?
偽ニュースは,社会に与える影響が極めて大きいにも関わらず,その受容と伝達の背景にある認知過程の検討が十分に行われていない。本研究では,1) 実証的信念との関連が指摘されている,認知的内省性,パターン錯覚,擬人観等の個人の認知特性が,同様に偽ニュースの受容と関連するかどうか,2) 文化伝達の領域で提唱されている最小反直観性(MCI) 説が偽ニュースの受容と伝達に対しても適用可能か,同様に信念の文化伝達への関与が指摘されている,3) 権威に対する信頼,議論に対する適切な理解,主張者の信念-行動間の一致が偽ニュースの伝達にも関与するかどうかという3つの観点から検討を行う。
宗教的推論は、直感的システムと熟慮的システムを仮定する二重過程理論では前者によって行われると想定されてきた。しかし、日本人においては熟慮的システムと結びついていることが示されている。本研究では、この違いを、東洋人は、カルマを熟慮的に受け入れている(カルマ仮説)、あるいは熟慮的思考と直感的迷信を弁証法的に受け入れている (弁証法的共存仮説) 可能性と想定する。日・仏・英において、認知的負荷によって熟慮的システムを抑制する実験、熟慮的思考を測定する質問紙と宗教的信念の質問紙の相関を検討する実験、熟慮的な判断と直感的な宗教的モラル推論の弁証的共存を測定する実験を実施し、両仮説を検証する。
1 0 0 0 栃木県内コナラ林の採取用落葉と表層土壌の放射性セシウムの経年変化
<p>リターフォールは、森林生態系の林冠から林床への放射性セシウム(RCs)の移行媒体、腐葉土製造の原料であるが、両者を関連づける情報は少ない。本研究は、福島第一原発事故後の栃木県のRCs初期沈着量の違う3ヶ所のコナラ林において、リターフォール、林床堆積有機物層(A<sub>0</sub>)および土層(A)のRCs濃度の7年間の変化、樹上生枝葉との比較、将来の腐葉土製造再開の可能性を考察した。リターフォール内の葉のRCs濃度は、事故直後はRCs初期沈着量の順に低くなったが、いずれの場所も林床のA<sub>0</sub>層濃度と比べ低かった。これはRCs初期沈着量に応じて林冠でのRCs沈着量が増加したが、事故当時コナラは展葉前で直接林床に降下沈着したためである。コナラ樹上枝葉のRCs濃度の季節変化(2015)は、当年枝葉は開葉直後の4月、5月が最も高く、その後はともに減少し、落葉期は葉で減少、当年枝は上昇した。以上の結果は開葉落葉に伴う枝葉のRCsの移行が枝内で限定していることを示唆する。将来的な腐葉土製造再開の可能性を知るためのA<sub>0</sub>層中のRCs濃度の減衰曲線は負の指数関数で近似され、初期沈着量の違いに応じて暫定許容値(400Bq/Kg)を超える期間が延長すると予測される。</p>
- 著者
- 鈴木 紘一 小尾 和洋 北洞 哲治 横田 曄 森 忠敬 宇都宮 利善 桐原 陽一
- 出版者
- Japanese Society of National Medical Services
- 雑誌
- 医療 (ISSN:00211699)
- 巻号頁・発行日
- vol.38, no.2, pp.152-157, 1984
抗生物質起因性偽膜性大腸炎の成因として, 腸内嫌気性菌であるClostridium difficileの産生する毒素が重視されている. 同菌の検出及び毒素産生能を検索しえた症例を呈示し, 主として合成ペニシリンによる急性出血性大腸炎との対比検討を行つた. 症例は47才女性. 化膿性子宮内膜炎にて子宮内容掻爬術を施行後, FOM, ABPC, CEX, CETなどの抗生物質を持続的に投与中, 腹痛, 下痢, 粘血便, 裏急後重を来した. 大腸内視鏡検査にて直腸より下行結腸にかけて大小様々の黄白色を呈する偽膜と炎症性粘膜を認め, 糞便よりC. difficileを検出した. 同菌の培養濾液及び糞便濾液につき細胞傷害試験及び血管透過性因子をみる家兎腸管ループ試験, 皮内反応を行い毒素の存在を証明した. C. difficileは炎症消退後の固型便より再び検出されたが毒素産生能はみられなかつた. 急性出血性大腸炎とは異なる病態であり, 両疾患の相違につき言及した.
1 0 0 0 蛋白質分解-新しいモディフアイアー蛋白質による制御
特定領域研究「蛋白質分解-新しいモディファイアー蛋白質による制御-」(平成12年度〜平成16年度)が終了したので、その成果をとりまとめ、研究成果報告書を文部科学省に提出した。本研究のテーマとした細胞内の主要な蛋白分解システムであるユビキチン・プロテアソームシステム研究とオートファゴソーム・リソソームシステム研究は、研究期間の5年間に大きな進展が見られた。ユビキチン・プロテアソームシステム研究では、このシステムが広く生物・生命現象に関わることが定説となった時点で、一昨年ユビキチンの基質蛋白質への結合反応の発見についてノーベル化学賞が贈られた。本特定領域研究で得られた成果は、その後のこの領域の生物医学的研究の発展に、極めて大きな貢献をした。また、日本発信の研究であるオートファジー研究では、本特定領域研究チームの研究成果は世界最先端を行っており、平成17年度においても世界に注目される成果が出されている。研究成果報告書の提出に加えて、この特定領域研究で得られた研究成果を社会の方々に広く知っていただき、より理解を深めていただくという趣旨で公開講座を平成17年12月24日に順天堂大学有山記念講堂で行った。「いきいきとした細胞、そして健康を保ために」というタイトルで、副題を「タンパク質分解の重要性」とし、5人の演者から世界トップレベルの研究内容をわかりやすく、面白く話していただいた。最後に5人の演者が登壇し、パネルディスカッションを行ったが、150人ぐらいの出席者の中から、次々と質問が出され、討論時間の30分はあっという間に終わった。細胞の中で蛋白質がつくられた後なぜ壊されなければならないか、蛋白質の分解が健康維持や病気の原因・進行にどう関与しているのかという疑問に対する科学的な説明は、かなり理解していただいたように思えた。蛋白質分解の研究領域が益々発展することを祈念する。
1 0 0 0 食品成分による生体防御の機作
本研究では、食品成分の生体防御系に対する作用を、免疫応答系とそれ以外の作用を介した系で解析した。免疫応答系に関するものでは、無菌およびSPFマウスのパイエル板のTおよびB細胞について、フローサイトメトリーを行ない、消化管が免疫細胞分化の場として重要な役割を果していることを証明した。また代表的な牛乳アレルゲンであるαsl-カゼインを免疫したマウスより、Lytー2^+サプレッサ-T細胞をクローン化することに成功した。食品成分の自己免疫疾患におよぼす影響を検討した結果、低カロリー食がBWF_4マウスにおける自己免疫疾患の治療に効果のあることを立証した。さらに食品によるアレルギーの制御を目的として、患者に造血因子GCSFを投与すると、好中球数が増加することを明らかにした。また、生体の防御ポテンシャルを増強する目的で、ハイブリドーマを検定細胞として、食品中に抗体産生を促進する成分を検索し、卵黄リポタンパク質、スキムミルク、ラクトフェリンなどにその効果のあることを明らかにした。つぎに、好中球、マクロファージなどの白血球の局部浸潤を調べる方法を用い、植物性食品を中心に、免疫賦活作用を持つ成分を検索し、キノコ類、緑黄野菜類にその活性のあることを明らかにした。一部にはインターフェロン誘導活性がみられた。免疫系以外による生体防御では次のような成果が得られている。セノバイオティクス(有機人工成分)の解毒、排泄に必須である肝薬物代謝物質の誘導に食餌タンパク質の量、質が大きく影響することを明らかにした。また生体防御において重要な役割を果たしているビフィズス菌の増殖因子であるβーDフコシルグルコースを酵素的に合成した。さらに、生体防御系に重要な役割を果たしているカルシウムプロテアーゼについて、その構造と機能について分子生物学的研究が行なわれた。さらに、消化管に分布する免疫細胞の組織化学的特徴を解明した。