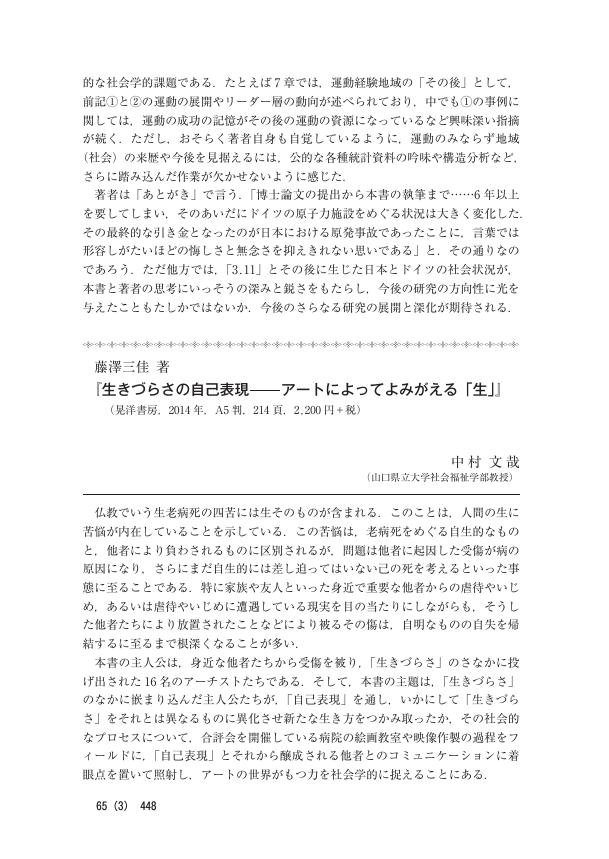1 0 0 0 宗教市場理論の射程 : 世俗化論争の新たな一局面
- 著者
- 沼尻 正之
- 出版者
- 日本社会学会
- 雑誌
- 社会学評論 (ISSN:00215414)
- 巻号頁・発行日
- vol.53, no.2, pp.230-246, 2002-09-30
本稿は, 近年ロドニー・スタークらアメリカの宗教社会学者たちにより提唱されている, 従来の世俗化論争の枠組を越えた, 新たな宗教社会学理論, およびその理論的基礎に基づいて展開されている宗教市場理論について検証することを目的としている.以下ではまずはじめに, 彼らが反世俗化論を唱える際の理論的根拠に関して, 宗教の定義の問題, 剥奪理論との関係についての議論を取り上げて論じる.次に, 彼らによる宗教変動の理論を, 宗教集団の類型論 (チャーチ・セクト・カルト), 宗教・呪術・科学の三者の関係についての議論, 宗教変動の三要素 (世俗化・リバイバル・宗教的刷新) を取り上げて説明する.その上で更に, 彼らの宗教市場理論について検討する.合理的選択理論などを基礎とする, この宗教市場モデルは, 一般の市場の場合と同様に宗教も, 多元主義的状況でその活発さを増すという考え方に基づくものであるが, この視点をとることで, 現代社会における伝統宗教の盛衰や, カルト的新宗教の台頭状況などが, どのように整合的に説明できるかを示す.最後に, こうした理論の持ついくつかの問題点を挙げ, それらを克服するために今後どのような課題があるのかを考察することで, 彼らの理論の持つ射程を明らかにしたい.
- 著者
- 阿藤 誠
- 出版者
- 日本社会学会
- 雑誌
- 社会学評論 (ISSN:00215414)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, no.4, pp.91-97, 1981-03-31
In the recent issue of this Journal, Mr.Yoshiki Kikuchi wrote about the rapid fertility decline since 1973 in Japan. He implied in it that the recent low fertility in Japan, measured by total fertility rates, reflected the decrease in birth intention of the average married couple toward less than two children. Based on the assumption that fertility behavior of Japanese women changed fundamentally in 1970's, he attempted population projections in which he assumed women would have only 1. 5 children on average in the future Japan.<BR>In my judgement, such argument is totally unwarranted. There has been no significant change in the legal status and the extent of actual prevalence of birth control measures in around early 1970's. In this respect Japanese situation is completely different from the Western countries where the diffusion of modern contraceptive methods and the liberalization of induced abortion presumably contributed to the recent fertility decline there.<BR>No evidence has shown that Japanese married couples have changed their fertility dramatically toward less than two children. Mean number of children ever born for 1955-1965 marriage cohorts were almost invariably about 2.2 and the total intended number of children was also 2.2 on average for more recent marriage cohorts.<BR>Although such social and economic changes as industrialization, urbanization, the rising aspirations for living, and the rise of educational level, may have been conducive to the long-run low fertility in Japan, they cannot explain the recent abrupt decline in period fertility rates. Also, there has been no significant change in married women's status either within or out of home.<BR>The major reason for the recent decline in period fertility rates is the simultaneous rise in the mean age at marriage for both sexes since 1973, which is, in turn, not only due to the abrupt shrinkage of the size of younger age cohorts in the marriage market after the "baby boom" cohort, but also due to the recent rise in the proportion of women entering colleges. Fragmentary data seem to indicate that marital fertility itself has declined recently, but this should be interpreted not as the decline in completed fertility but as the temporal decline due to the spacing of childbearing.
1 0 0 0 OA 園井ゆり著『里親制度の家族社会学――養育家族の可能性』
- 著者
- 和泉 広恵
- 出版者
- 日本社会学会
- 雑誌
- 社会学評論 (ISSN:00215414)
- 巻号頁・発行日
- vol.65, no.4, pp.616-618, 2015 (Released:2016-03-31)
1 0 0 0 OA 映像の共有と諸権利
- 著者
- 内田 順子
- 出版者
- 日本社会学会
- 雑誌
- 社会学評論 (ISSN:00215414)
- 巻号頁・発行日
- vol.65, no.4, pp.504-520, 2015 (Released:2016-03-31)
- 参考文献数
- 23
本稿は, 国立歴史民俗博物館が実施している民俗研究のための映像制作を事例として, 「映像を保存・活用する」際の諸課題について考察するものである. 長期的な展望をもって映像を制作し, 保存し, 活用するには, メディア変換などの技術的な問題, 著作権・肖像権などの法的問題, アーカイブの構築などの映像を共有するしくみに関する問題などを解決していく必要がある. 民俗研究を目的として制作された映像は, 研究者と, 研究対象となる地域の人びととの協働によってつくられるものであるため, その協働の関係性は, 映像そのものに色濃く反映される. そのような映像を保存・活用する際には, 著作権・肖像権に関する一般的な検討とは別に, 倫理的な問題として検討しなければならない事柄がある. その点が, 一般的な映像の保存・活用と異なるところである.
- 著者
- 北島 義和
- 出版者
- 日本社会学会
- 雑誌
- 社会学評論 (ISSN:00215414)
- 巻号頁・発行日
- vol.66, no.3, pp.395-411, 2015
1 0 0 0 君主のスペクタクルの知覚様式 : 20世紀初期の日本の事例から
- 著者
- 右田 裕規
- 出版者
- 日本社会学会
- 雑誌
- 社会学評論 (ISSN:00215414)
- 巻号頁・発行日
- vol.66, no.3, pp.379-394, 2015
- 著者
- 安達 智史
- 出版者
- 日本社会学会
- 雑誌
- 社会学評論 (ISSN:00215414)
- 巻号頁・発行日
- vol.66, no.3, pp.346-363, 2015
- 著者
- 三原 武司
- 出版者
- 日本社会学会
- 雑誌
- 社会学評論 (ISSN:00215414)
- 巻号頁・発行日
- vol.66, no.3, pp.364-378, 2015
1 0 0 0 OA 国家のリスケーリングと都市のガバナンス
- 著者
- 丸山 真央
- 出版者
- 日本社会学会
- 雑誌
- 社会学評論 (ISSN:00215414)
- 巻号頁・発行日
- vol.62, no.4, pp.476-488, 2012-03-31 (Released:2013-11-22)
- 参考文献数
- 47
2000年代以降, 都市研究で「国家のリスケーリング」論が影響力をもつようになっている. これは, グローバルやリージョナルな経済・政治統合が進むなかで国家諸機構の機能や影響力がその地理的スケール上の編成を変化させることに注目し, 都市やそのガバナンスの変化との関連を明らかにするものである. 「都市」は, 従来の都市研究でしばしば所与の空間的単位とみなされてきたが, 「地理的スケール上の編成の変化 (リスケーリング)」という発想を採り入れることで, それが資本や国家のスケール的編成と相互規定的に生産される地理的スケールのひとつであり, それゆえ今日, 「都市」というスケールをどう定義するかということそれ自体が「スケールの政治」の争点になっていることが明らかになる. 本稿では, この視角による都市研究の基本的な問題構制と成果を整理し, グローバル化とネオリベラリズムのもとでの都市ガバナンスの変化を捉えるのに有益であることを示す. そのうえで「平成の大合併」をめぐる地方都市の事例の簡単な分析を行う. 基礎自治体の合併は, 既存の「地域/都市」スケールのガバナンスを担う政治行政機構を再編して, 新たな「地域/都市」スケールでガバナンスを組織しなおす「国家のリスケーリング」のひとつだが, 事例分析から, 日本でこれがどのような政治経済的な力学で進められたのかを明らかにする. あわせてこの視角による都市研究の課題を引き出し整理する.
1 0 0 0 OA 早瀬利雄・馬場明男編 現代アメリカ社会学
- 著者
- 阿閉 吉男
- 出版者
- 日本社会学会
- 雑誌
- 社会学評論 (ISSN:00215414)
- 巻号頁・発行日
- vol.5, no.1, pp.109-111, 1954-10-20 (Released:2009-11-11)
- 著者
- 上藤 文湖
- 出版者
- 日本社会学会
- 雑誌
- 社会学評論 (ISSN:00215414)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, no.2, pp.369-384, 2006-09-30
ドイツでは移民法成立に向け, 数年にわたり外国人の社会への統合が論じられるなか, たびたび〈多文化社会〉が論争となってきた.多文化社会を現実として肯定し外国人の統合を推進するのか, これを幻想として否定するのか.論争はこうした二重性をもっている.1980年以降ベルリンでは, 国家レベルに先行して文化的多様化が進行し, 外国人の包摂への取り組みとドイツ社会の変革を志向する政策が進んでいった.そして1989年以前には, 〈多文化社会〉はその現実が争われ, 東西ドイツの分断という政治的状況が, 現実としての〈多文化社会〉に対する肯定と否定双方を生んでいった.しかし東西ドイツが統合し大量の難民を受け入れた1990年以降, 現実として多文化が受容されはじめる.そして1998年の〈多文化社会〉論争では, 〈指導文化〉とされるドイツ文化と多文化の関係が論じられたが, 文化的多様性に対する一定の承認のもと, 文化的多様性の認知としての〈多文化社会〉から, どのような成員がどのような共通の基盤のもとで社会を形成するのかを問う〈多文化社会〉へと, その議論が変化したのである.ベルリンにおける〈多文化社会〉をめぐる議論は, 外国人によって社会が問われ変化していくことを示している.都市における〈多文化社会〉をめぐる葛藤は, 都市という空間の中で外国人と社会との関係が構築されていくプロセスの中に位置づけられる.
- 著者
- 佐藤 成基
- 出版者
- 日本社会学会
- 雑誌
- 社会学評論 (ISSN:00215414)
- 巻号頁・発行日
- vol.60, no.3, pp.348-363, 2009-12-31
- 被引用文献数
- 1
1990年代以後,欧米先進諸国の移民統合政策が変化してきている.それまでの「デニズンシップ」や「多文化主義」に傾斜した政策が後退し,「統合」という概念により重点が置かれるようになっている.それは一見,「グローバル化」時代のトレンドと矛盾するように見える.本稿は,このような最近の変化を,19世紀以来の国民国家形成とグローバルな移民の拡大との歴史的な連関関係のなかで考察してみる.国民国家は,19世紀以来200年間のグローバルな変容のなかで形成/再形成され,またグローバルに波及してきた.そのようななかで国民国家は,移民を包摂・排除しながらその制度とアイデンティティを構築してきた.本稿は,その歴史的過程を明らかにしたうえで,最近の欧米先進諸国の「市民的」な移民統合政策への変化が,「異質」なエスノ文化的背景をもった移民系住民を包摂するかたちで国民国家を再編成しようとする,新たな「ネーション・ビルディング」への模索であるということを主張する.最後に,こうした最近の欧米先進諸国における変化から日本の状況を簡単に検討する.
- 著者
- 山本 薫子
- 出版者
- 日本社会学会
- 雑誌
- 社会学評論 (ISSN:00215414)
- 巻号頁・発行日
- vol.65, no.3, pp.450-451, 2014 (Released:2015-12-31)
1 0 0 0 OA 藤澤三佳著『生きづらさの自己表現――アートによってよみがえる「生」』
- 著者
- 中村 文哉
- 出版者
- 日本社会学会
- 雑誌
- 社会学評論 (ISSN:00215414)
- 巻号頁・発行日
- vol.65, no.3, pp.448-450, 2014 (Released:2015-12-31)
1 0 0 0 OA 連帯と承認をめぐる理念の生成と変容
- 著者
- 伊藤 美登里
- 出版者
- 日本社会学会
- 雑誌
- 社会学評論 (ISSN:00215414)
- 巻号頁・発行日
- vol.65, no.3, pp.409-425, 2014 (Released:2015-12-31)
- 参考文献数
- 26
U.ベックは, ローカル次元において連帯と承認を作り出す仕組みとして市民労働という政策理念を提案した. この理念が現実社会との関連でいかに変容したか, 他方で社会においてはいかなる変化がもたらされているか, これらを考察することが本稿の目的である.研究の結果次のようなことが判明した. 市民労働の政策理念は, 政策的実践に移される過程で, ある部分が市民参加に, 別の部分が市民労働という名のワークフェア政策としてのモデル事業に採用され, 分裂していった. 現在の市民労働と市民参加は, ベックの市民労働の構成要素をそれぞれ部分的に継承しつつ, 中間集団や福祉国家の機能を部分的に代替している. 政策的実践としての市民労働と市民参加の存在は, 「家事労働」「市民参加」「ケア活動」といった概念の境界を流動化したが, 「職業労働」概念の境界は相対的に強固なままである.ベックの市民労働には, 元来, 社会変革の意図が含まれていた. すなわち, この政策理念は, 職業労働と市民参加と家事労働やケア活動の境界を流動化し, それらの活動すべてを包括するような方向, すなわち労働概念の意味変容へ向かうことを意図して提案された試みであった. しかし, 現状においては, そもそもの批判対象であった職業労働の構造を強化する政策にこの市民労働の名称が使われている. 他方, 市民参加においては, 部分的にではあるが, 市民労働の政策理念が生かされ一定の成果をあげている.
1 0 0 0 OA 公共圏論のパースペクティブの刷新
- 著者
- 兼子 諭
- 出版者
- 日本社会学会
- 雑誌
- 社会学評論 (ISSN:00215414)
- 巻号頁・発行日
- vol.65, no.3, pp.360-373, 2014 (Released:2015-12-31)
- 参考文献数
- 50
本稿は, アレグザンダーの「市民圏」論の検討によって, 公共圏論の理論的な刷新を図ることを目的とする.公共圏論に大きな影響を及ぼすハーバーマスは, 公共圏を公論形成の領域と規定する点ではマクロ的な観点を保持する. だが, 直接的な対話による了解を志向する討議を公共圏におけるコミュニケーションのモデルとすることから, 民主的社会における市民の意思形成とマクロレベルでの政治プロセスの接続という点で理論的困難を抱えている.これに対してアレグザンダーは「市民圏」概念を提唱する. 彼は, 市民圏におけるコミュニケーションを, 討議から, 感情的な共感に訴えることでオーディエンスからの承認を求めるパフォーマンスに代替することを主張する. 彼に従えば, 基本的なコミュニケーションをパフォーマンスとして捉えることこそが, 民主的社会における公共圏のより適切な理論化につながる.理論的課題は多く, 公共圏におけるコミュニケーションがスペクタクルとして上演されることを肯定するだけという評価もあるかもしれない. だが, アレグザンダーの市民圏論が, 現代の民主的社会と公共圏の関係に対する新たな洞察を可能にすると, 筆者は主張したい.
1 0 0 0 OA 世界社会学会議横浜大会を振り返る
- 著者
- 長谷川 公一
- 出版者
- 日本社会学会
- 雑誌
- 社会学評論 (ISSN:00215414)
- 巻号頁・発行日
- vol.65, no.3, pp.308-316, 2014 (Released:2015-12-31)
- 参考文献数
- 5
第18回世界社会学会議は, 2014年7月13日から19日まで, 横浜市のパシフィコ横浜を会場に開催され, 無事終了した. 国際社会学会の世界社会学会議 (World Congress of Sociology) は4年に1度開催される社会学界最大の学術イベントである. 本稿では, 組織委員会委員長というホスト国側の責任者の立場からこの会議の経過と意義を振り返り, 本大会の成果を今後に引き継ぐための課題を提起したい.1960年代以来, 長い間先送りされてきた世界社会学会議の開催がなぜ2014年大会の招致というかたちで実現したのか, その背景は何だったのか. 開催都市に横浜を選んだのはなぜか. 組織委員会をどのように構成したのか. 世界社会学会議横浜大会は, これまでの世界社会学会議と比べてどのような特徴をもつのか. 組織委員会として, 組織委員長として, どのような課題に直面し, 腐心したのか. 横浜大会の成果と意義は何か. 横浜大会はどのような意味で「成功」といえるのか. 横浜大会の成果を, 研究者個々人が, また日本社会学会がどのように継承していくべきかを考察する. 日本の社会学の国際化・国際発信の重要なワンステップではあるが, 横浜大会は決してゴールではない. 日本社会学会は, 日本の社会学の国際的な発信を, 引き続き組織的にバックアップしていくべきである.
- 著者
- 植田 今日子
- 出版者
- 日本社会学会
- 雑誌
- 社会学評論 (ISSN:00215414)
- 巻号頁・発行日
- vol.55, no.1, pp.33-50, 2004-06-30
近年の公共事業見直しのうごきと自然環境への意識の高まりから, 川辺川ダム (熊本県) はその必要性を厳しく問われる公共事業である.頭地地区を含めた五木村, 相良村 (一部) はこれまで36年間, 大挙離村や地域社会内部での対立を経験しながら水没予定地域としてありつづけてきた.五木村は現在ダムの「早期着工」を訴える立場にある.なぜ周囲で声高に事業の必要性が問われる中, 自らをさんざん苦しめてきたダムの早期着手を訴えなければならないのだろうか.本稿では, 水没予定地である五木村頭地地区でのフィールドワークをもとに, ダム計画に対して3つの異なる立場をとってきた五木村の水没3団体が, いかにして自らの団体を他団体と差異化しつつ, 「早期着工」という総意を成立させているのかを明らかにすることで, 「早期着工」表明の論理に近づくことを目的とした.<BR>これまで, 公共事業によって損害を被るはずの人びとが事業の早期着手を訴えるということは, 自己利益の最大化として功利主義的に捉えられることが多かった.しかし「早期着工」の意思表明には, 公共事業が生活の場における諸関係にもたらしてしまう意味を克服しようとする遂行的意味があった.それは, 世帯ごとの意思決定を配慮・尊重するがゆえに, むらがむらとして成立しないという状況において実践された, むらの生成という言遂行的な意志表明であった.
1 0 0 0 田野大輔著『愛と欲望のナチズム』
- 著者
- 沼尻 正之
- 出版者
- The Japan Sociological Society
- 雑誌
- 社会学評論 (ISSN:00215414)
- 巻号頁・発行日
- vol.64, no.4, pp.733-734, 2013
- 著者
- 赤枝 香奈子
- 出版者
- 日本社会学会
- 雑誌
- 社会学評論 (ISSN:00215414)
- 巻号頁・発行日
- vol.56, no.1, pp.129-146, 2005-06-30
同性間の親密な関係は, しばしば「同性愛/友情」という二項対立的な図式によって解釈される.しかし女性同士の親密性については, 従来, その分類が曖昧であるとされ, 同性愛と友情が連続的であるのみならず, 母性愛とも連続性をもつものとみなされてきた.<BR>公的領域と私的領域の分離に基づく近代社会において, 親密性は私的領域に属する事柄とされる.そして性・愛・結婚を三位一体とする「ロマンティック・ラブ・イデオロギー」によって, 私的領域は形成されてきたと言われる.しかし, 母性愛と女性同士の友情や愛情は, 必ずしも親和的ではなかった.それはロマンティック・ラブの核心に位置するとされる, 生殖から解放された「自由に塑型できるセクシュアリティ」 (A.ギデンズ) を志向するかどうかという違いに端的に表される.近代日本の女学校において見られた女性同士の親密な関係は, しばしば「安全な」友情か「危険な」同性愛に分断され論じられてきたが, 現在から振り返った場合, 彼女たちの親密な関係は, まさしくロマンティック・ラブの実践であったといえる.そのような親密性は, 女学校において実践される限りは, 健全な成長の一段階としてみなされたが, ひとたび女学校の外へ出ると, 「異常」のレッテルを貼られ, 「母」とは対照的に位置づけられ, スティグマ化された独身女性の表象である「老嬢」と結びつけられ, 貶められた.