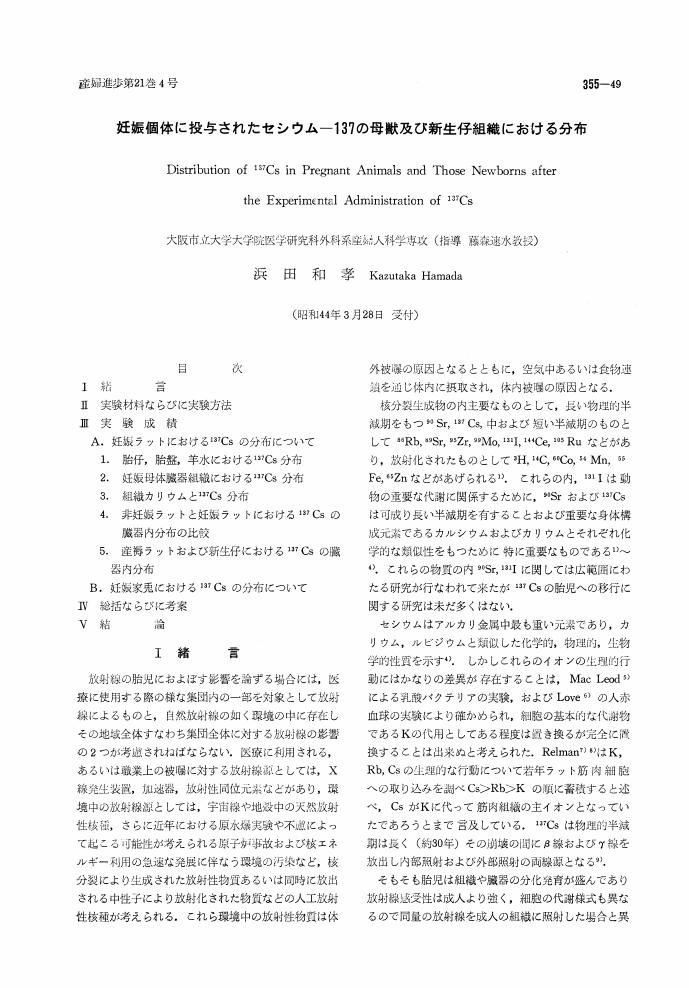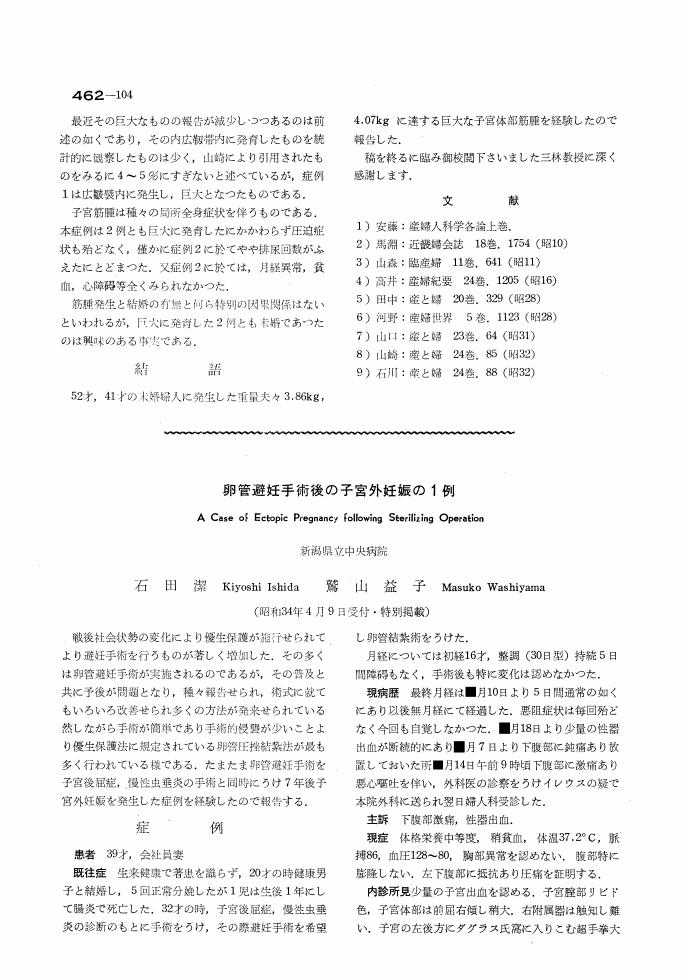2 0 0 0 妊娠中のアルコール摂取に関する最近の話題
- 著者
- 冨松 拓治
- 出版者
- 近畿産科婦人科学会
- 雑誌
- 産婦人科の進歩 (ISSN:03708446)
- 巻号頁・発行日
- vol.68, no.2, pp.137-139, 2016 (Released:2016-06-29)
- 参考文献数
- 5
2 0 0 0 子宮筋腫の経過観察中に筋腫内に子宮肉腫を発症した1例
- 著者
- 川島 直逸 河原 俊介 安堂 有希子 羽田野 悠子 三瀬 有香 芦原 隆仁 吉岡 信也 若狭 朋子
- 出版者
- 近畿産科婦人科学会
- 雑誌
- 産婦人科の進歩 (ISSN:03708446)
- 巻号頁・発行日
- vol.66, no.3, pp.290-295, 2014
子宮肉腫は全子宮悪性腫瘍の約5%とまれな腫瘍で,その画像所見が多彩であることなどから術前診断は一般的に困難とされ,子宮筋腫との鑑別診断には苦慮することが多い.今回,子宮筋腫の経過観察中に子宮平滑筋肉腫を発症した1例を経験したため報告する.症例は51歳,1経妊1経産.健診にて子宮筋腫を指摘されたため,当科紹介受診となる.経腟超音波検査・MRIにて子宮体部筋層内に径6cm大の腫瘤を認め,子宮筋腫と診断し定期的な経過観察とした.初診の約2年後より不正性器出血が出現した.超音波検査では,腫瘍の増大傾向は認めなかったが,腫瘍の一部に高輝度領域が出現していたので,子宮筋腫の変性を疑った.その後も不正性器出血が続くためGnRHアゴニスト療法を開始したが,開始4カ月後の超音波検査にて,腫瘍は径9cm大と増大し高輝度領域も拡大していた.血液検査では腫瘍マーカーやLDHなどは正常値で,子宮内膜細胞診も陰性であった.MRIでは,子宮体部の腫瘍は径10cm大に増大し,T2強調像で不均一な高信号を呈し,また腫瘍の一部で強い造影効果を認め,子宮肉腫が疑われた.CT検査では両側肺野に多発転移病巣が疑われた.子宮肉腫の臨床診断で,腹式子宮全摘術および両側付属器摘出術を施行した.摘出標本の病理所見では,子宮体部の同一腫瘍内に平滑筋腫組織と平滑筋肉腫組織が存在し,かつ両者は混在するように接しており,子宮筋腫の悪性転化もしくは既存の子宮筋腫の近傍より平滑筋肉腫が発生したと推察された.子宮平滑筋肉腫IVB期の最終診断で,術後化学療法を施行中である.子宮筋腫の取り扱いにあたっては,診断時の子宮平滑筋肉腫との鑑別のみならず,まれではあるが経過観察中にも子宮平滑筋肉腫発症の可能性を考慮することが必要と思われた.〔産婦の進歩66(3):290-295,2014(平成26年8月)〕
2 0 0 0 子宮筋腫により急性尿閉をきたした10例
- 著者
- 西沢 美奈子 徳山 治 深山 雅人 川村 直樹
- 出版者
- 近畿産科婦人科学会
- 雑誌
- 産婦人科の進歩 (ISSN:03708446)
- 巻号頁・発行日
- vol.66, no.2, pp.148-154, 2014
女性の尿閉は10万人あたり7人と報告されており,とくに婦人科疾患によるものはまれとされている.子宮筋腫はその原因疾患に含まれるが,腫大子宮による尿路系圧迫に伴う症状としては頻尿が比較的多く認められるものの,尿閉をきたすものはまれである.これまでに1~3例の症例報告はみられるが,まとまった症例数での系統的解析が行われた報告はない.今回,われわれは子宮筋腫が原因と思われる急性尿閉を発症した10例を経験したので,その臨床背景,発症時の状況,病態について診療録をもとに後方視的に検討した.対象は,2006年4月から2012年3月までの6年間に当院子宮筋腫外来を受診した2032例の患者のうち,急性尿閉をきたした10例(0.49%)である.年齢は38~51歳,子宮の大きさは妊娠12~21週相当,3例が頸部筋腫を有し,7例は体部筋腫のみであった.いずれの症例も尿閉は膀胱に尿が充満しているときに発症しており,起床時にみられることが多く,確認できた残尿量は175~1600mlであった.導尿後は尿閉が継続してみられることはなく,膀胱充満時に腫大子宮体部が上方あるいは後方へ変位し,その結果,尿道の変位・延長,後方からの子宮頸部の尿道圧迫などが生じて一過性尿閉が出現したものと推測された.子宮筋腫が原因と思われる尿閉の既往がある場合,原則外科的介入の適応とされるが,眠前の多量水分摂取を控えたり,膀胱に尿が充満しすぎないよう注意することなど生活習慣を指導することで,その後尿閉を繰り返さず経過する場合が多い.したがって,とくにまもなく閉経を迎える年代では1度の急性尿閉のエピソードは外科的介入の絶対適応ではないものと考えられた.〔産婦の進歩66(2): 148-154,2014 (平成26年5月)〕
2 0 0 0 胎児型奇形腫
- 著者
- 林 美佳 神田 隆善 佐藤 直美 岩井 恵美 棟方 哲
- 出版者
- 近畿産科婦人科学会
- 雑誌
- 産婦人科の進歩 (ISSN:03708446)
- 巻号頁・発行日
- vol.60, no.3, pp.229-234, 2008
成熟嚢胞性奇形腫は外胚葉,中胚葉,内胚葉の成分を有し,卵巣良性腫瘍のうちでもっとも一般的な疾患である.しかし,その1型である胎児型奇形腫は非常にまれな疾患であり,文献的にも本例を含め28例の報告しかない.われわれは成熟嚢胞性奇形腫の診断で手術を施行したが,手術後に胎児型奇形腫と診断された症例を経験したので報告する.症例は22歳の未妊婦で月経過少を主訴に外来を受診した.初診時超音波画像で径2.0cm大の卵巣腫瘍を認めた.成熟嚢胞性奇形腫と卵巣機能不全の診断で3ヵ月毎に経過観察およびホルモン療法を施行していた.4年間で腫瘍が径5.0cm大としだいに増大し,さらにその3ヵ月後径7.0cm大と急激に増大してきたため腹腔鏡手術を施行した.摘出標本は径5.0cm×7.0cm大の嚢胞性腫瘤で,内部に充実性部分を有していた.充実性部分は頭部,体幹,四肢様構造をもち胎児に類似していた.組織学的には脳,脊椎,皮膚,毛髪,歯牙,骨,気管,消化管さらに骨格筋などを認めた.胎児型奇形腫の診断で現在外来で経過観察中である.また胎児型奇形腫と類似した形態を示す封入奇形腫,卵巣妊娠との相違点,胎児型奇形腫の発生についても文献的考察を加えた.〔産婦の進歩60(3):229-234,2008(平成20年8月)〕
- 著者
- 加藤 徹 山本 麻未 笠間 周平 伊藤 善啓 池田 ゆうき 坂根 理矢 鍔本 浩志 芳川 浩男 澤井 英明
- 出版者
- 近畿産科婦人科学会
- 雑誌
- 産婦人科の進歩 (ISSN:03708446)
- 巻号頁・発行日
- vol.65, no.2, pp.161-167, 2013
抗NMDA受容体脳炎は,若年女性に好発する非ヘルペス性辺縁系脳炎の1つで,卵巣奇形腫関連傍腫瘍性脳炎である.今回われわれは卵巣成熟嚢胞性奇形腫を有する抗NMDA受容体脳炎の再発症例を経験した.症例は35歳で,20歳のときに原因不明の脳炎を発症し,約2カ月間の入院の既往歴があった.その後26歳で妊娠した際に卵巣成熟嚢胞性奇形腫と診断され,妊娠中に腹式左卵巣嚢腫摘出術が施行された.それ以降は健常に過ごしていたが,今回突然の発熱と精神症状を発症した.その後,意識障害を認め脳炎が疑われたため,当院へ紹介となった.当院神経内科へ入院後にけいれん重積発作を起こし,気管内挿管されICU入室となった.入院時に施行したCTで骨盤内に卵巣腫瘍が指摘された.抗NMDA受容体脳炎が疑われ当科へ紹介となり,緊急で腹式両側付属器切除術を施行した.摘出標本の病理診断は成熟嚢胞性奇形腫であった.手術後は昏睡状態が続いたが約1カ月後に開眼し,その後徐々に意識状態は改善し,入院から116日目に独歩で退院となった.入院時に採取した血液と髄液の検体より抗NMDA受容体抗体を検出し,診断確定に至った.退院後は外来において経過観察中で脳炎の再発は認めていない.卵巣成熟嚢胞性奇形腫は頻度の高い疾患であるが,このような疾患を引き起こすこともあり,卵巣奇形腫の症例では詳細な既往歴の聴取で過去の脳炎や,中枢神経に関した既往歴の有無を確認することが重要である.〔産婦の進歩65(2):161-167,2013(平成25年5月)〕
2 0 0 0 OA 妊娠個体に投与されたセシウム-137の母獣及び新生仔組織における分布
- 著者
- 浜田 和孝
- 出版者
- 近畿産科婦人科学会
- 雑誌
- 産婦人科の進歩 (ISSN:03708446)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, no.4, pp.355-367, 1969-07-01 (Released:2011-10-11)
- 参考文献数
- 48
- 著者
- 後山 尚久 新谷 雅史 本庄 英雄 HRTの今後のあり方検討委員会
- 出版者
- 近畿産科婦人科学会
- 雑誌
- 産婦人科の進歩 (ISSN:03708446)
- 巻号頁・発行日
- vol.55, no.4, pp.373-387, 2003 (Released:2003-12-24)
- 参考文献数
- 53
- 被引用文献数
- 1
米国国立衛生研究所により一般閉経女性を対象としたホルモン補充療法の大規模前向き臨床試験であるWomen's Health Initiative (WHI) Hormone Programの一部のプロトコールが,乳癌の発生率があらかじめ設定していたリスクを超えたとの理由で,2002年7月の中間集計後にそれ以上の試験継続を中止すると発表された.この報道はわが国でも報道されたために今後のホルモン補充療法の実施に関しては,実際に診療を担当する医師と受療者となる中高年女性の本療法への認識や考え方を調査し,今後の更年期医療の方向性を考えるための情報を得る必要があると思われた. そこで,近畿産科婦人科学会内分泌・生殖研究部会が中心となり,近畿全体での産婦人科医師へのアンケート調査を行うことで,本報道が及ぼした実際の医療現場への影響とホルモン補充療法の捉え方,意識などを検討した.対象は近畿圏で医療を行っている産婦人科医師で,1800名に対しアンケート調査を行った.420名から回答があり,回収率は23.3% (420/1800)であった. 1.アンケート回収率の低さ(23.3%)は産婦人科医師のHRTに対する関心の低さを反映していると思われるが,アンケート回答者の多く(76.6%)は報道内容をよく知っていることがわかった. 2.本報道内容は日本の更年期医療にそのまま適応できないと考えている医師が69.7%であり,その理由として「わが国の乳癌,心臓病の発症リスクが米国と異なる」という意見が3割強に認められた.一方,日本の更年期医療現場にも適応できると30.3%の医師が考えており,すでに32.7%がみずからの診療姿勢や対応を具体的に変える行動をとっていた. 3.WHI報道への医師の最初の印象として,「危険なので患者に勧める治療法ではない」と考えたのは21.4%にすぎず,「自分としてはすぐにやめる」という考えを示したのは5.0%(将来的に徐々にやめる:11.0%)の医師にとどまった. 4.このままHRTを続ける医師が40.2%であったが,このうち血管運動神経障害様症状や性交障害などの限られた症状や疾患のみに適応するとの答えが54.3%に認められた. 5.今後のHRT実施に際しては,そのbenefitの説明とともに,過半数の医師が「乳癌,子宮内膜癌,血栓症などの危険性に関する情報(乳癌:76.0%)を伝えてinformed consentをすべきと考えていることが判明した. 以上より,日本の産婦人科医師はHRTへの関心が必ずしも高くないが,HRTを実施している医師は冷静にWHI報道を受け止め,一部迅速な対応がみられる.6割の医師がこれからのHRT実施についてなんらかの工夫を模索しており,HRTのrisk and benefitをよく理解し,患者へのriskを含めた十分な説明が必要であることを自覚しており,このことから本報道はわが国のHRTの状況あるいは更年期医療そのものに大きな影響を及ぼすものではないと考えられた. 今後,わが国でのHRTの有用性と危険性に関する臨床研究が必要であり,エストロゲン欠乏性疾患の発症予防をend-pointとしたevidenceを集積しての新たなガイドラインの作成が望まれる.〔産婦の進歩55(4):373-387,2003(平成15年11月)〕
1 0 0 0 OA 卵管避妊手術後の子宮外妊娠の1例
- 著者
- 上田 康夫 丸尾 原義 足高 善彦 本田 由佳 深山 知子
- 出版者
- 近畿産科婦人科学会
- 雑誌
- 産婦人科の進歩 (ISSN:03708446)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, no.2, pp.121-130, 2005 (Released:2005-06-30)
- 参考文献数
- 15
- 被引用文献数
- 1
【研究目的】1988年以降15年間における本院での母体体重,出生体重の変遷を調査することにより,母体体重増加基準に関する現行日産婦基準の再評価を行った. 【研究方法】1988年1月から2002年12月の間に兵庫県立柏原病院で管理した妊婦3310例を対象とした.これらの妊婦を非妊時Body Mass Index(BMI)によってやせ(BMI<18),標準(18-24),肥満(>24)の3つの体型群に分類し母体体重増加量別に低出生体重児(<2.5kg),巨大児(≧4kg),Light for dates(LFD),Heavy for dates(HFD)および妊娠中毒症(高血圧主徴のみで浮腫,蛋白尿を除外)の発生率を検討するとともに,各体型群での至適体重増加量を考案した.さらに現行の至適増加基準と今回得られた基準の両者を用いて全妊婦を増加過剰,至適,過少の3群に分け,年代別の各群への分布を検討した. 【結果】全体型妊婦での母体体重増加量は1988年の12.0±3.7kg(mean±SD)から2002年の10.0±3.9kgに,一方出生体重も3114±414gから3040±384gに減少し,この傾向はとくに肥満群で著明で,同群での低出生体重児発症も増加した.母体至適体重増加量の検討では,対照とした標準群中7~10kgの母体体重増加群に比べ,やせ群中10kg未満の母体体重増加群での出生体重は減少し,逆に>14kg群ではHFD,妊娠中毒症が増加した.標準群では<7kg群でLFD,低出生体重児が有意に多かったが,13kg以上の群では逆に巨大児,HFDの発症が有意に高く妊娠中毒症の発症率も体重増加につれて増加した.肥満群では>7kg群でHFDと巨大児の発症率が有意に高かった.以上の結果より,やせ群10~14kg,標準群7~13kg,肥満群<7kgという新しい基準域が求められた.現行日産婦体重増加基準による分布において各群とも至適域に入る妊婦は少なく,やせ群では体重増加過少,標準・肥満群では体重増加過剰が多数を占めた. 【考察】1988年以来15年間に母体体重増加量と出生体重はともに明らかな減少傾向を示したものの,現行日産婦基準からは標準,肥満群におけるいっそうの体重抑制の必要性が示唆された.しかし,現行基準における至適域の決定には妊娠中毒症─妊娠浮腫の関与が大きく,結果として妊娠浮腫による体重増加過剰例の存在が各群至適域の上限値を引き下げていた可能性がある.今後本邦での妊娠中毒症分類の変更に応じた新しい至適体重増加基準が広く議論されることが期待される.〔産婦の進歩57(2):121-130,2005(平成17年5月)〕
- 著者
- 上田 康夫 丸尾 原義 足高 善彦 深山 知子 本田 由佳 中林 正雄
- 出版者
- 近畿産科婦人科学会
- 雑誌
- 産婦人科の進歩 (ISSN:03708446)
- 巻号頁・発行日
- vol.56, no.3, pp.275-286, 2004 (Released:2004-09-30)
- 参考文献数
- 27
- 被引用文献数
- 1
【目的】正常および妊娠中毒症母体の妊娠経過に伴う体脂肪(Fat Mass:FM),体水分(Total Body Water:TBW)の動態を生体インピーダンス法(bioelectrical impedance analysis:BIA)に胎児部分重量補正を加えた妊婦体成分測定系によって明らかにしようとした. 【方法】兵庫県立柏原病院で管理した妊婦358例を対象とし,1)妊娠6週から16週までの正常妊婦66例,2)妊娠末期から産褥期の正常妊婦44例,3)非妊時体型(やせ:BMI<18,標準:18~24,肥満:>24)と妊娠期間中の全体重増加量によって区分された正常および妊娠中毒症関連疾患妊婦290例である.これらの妊婦は健診時に体脂肪計(タニタTBF-410)による両足間インピーダンス測定を行い,FM,TBWを算出した. 【成績】妊娠6週から16週までの体重変化はFMおよびTBWと有意な正相関を示し,FM,TBWの体重に対する比率は前者が57%,後者が29%を示した.正常妊婦での母体体重およびTBW増加が妊娠期間を通じてほぼ一定であったのに反し,そのFMの増加勾配は妊娠前半期に著明で後半期には明らかに抑制された.とくに肥満体重増加不良群でのFMは非妊時レベル以下に下降した(肥満<7kg:1.0±2.1kg).妊娠中の体重増加はTBWよりFMとの相関性が高かったが,産褥1ヵ月間の体重減少は逆にTBWの減少に起因するものであった.一方,中毒症関連疾患のうち中毒症重症(高血圧主徴,純粋型)におけるFMは初期より明らかに減少し36週には-2.6±3.2kgと対照2.8±1.8kgに比べて有意に低値であり,中毒症軽症や妊娠浮腫と対照的であった.他方, TBWは4群とも36週には対照より高値であり,とくに妊娠浮腫重症では6.6±2.4kgと明らかな高値を示し,とくに妊娠浮腫群では体重との相関が高かった.一方,二次元座標系による分析では妊娠浮腫,中毒症軽症が第1象限内を推移し末期には正常>10kg群にオーバーラップしたのに反し,妊娠浮腫重症は後期にTBWが急増し第1象限をY軸方向へ推移した.他方中毒症重症は初期より第4象限を左上方に偏倚した.また,妊娠36週でのFM,TBW増加量による分類によると妊娠浮腫軽症はFM過少-TBW過剰群を除いた8群間に広く分布したのに反し,妊娠浮腫重症はFM過少/正常-TBW過剰群に,中毒症軽症はFM過剰-TBW正常/過剰群に分布した.他方中毒症重症はFM過少-TBW正常/過剰群に局在した.他方,妊娠浮腫軽症と診断した例のうち実際にTBW過剰であったものは37%であった. 【結論】本測定系の応用によって母体体重変化をFMとTBWの2つに分けて把握することが日常診療の場で可能になり,妊娠浮腫軽症という診断自体の不確実性が明らかになった.一方,中毒症重症ではFMの著明な減少とTBWの相反的な増加が特徴的であり,これには同症で観察されるインスリン抵抗性の高まりが関与する可能性が考えられた.さらに,本症ではFM,TBW両者の相反的な変化が相殺されるために母体体重に明らかな変化の現れないことが推測され,従来の体重のみを指標とした妊婦管理の限界がうかがわれた.いずれにしても臨床的にもっとも問題となる中毒症重症の体成分変化が,この妊婦体成分診断法によって妊娠の比較的早期から他の中毒症群と区別しうるという事実は,本法が中毒症の予知,病態診断を考えるうえできわめて重要なものになる可能性を示唆するものと考えられた.〔産婦の進歩56(3):275-286,2004(平成16年8月)〕
- 著者
- 大仲 恵 越山 雅文 上田 匡 山西 優紀夫 浮田 真吾 菱川 賢志 奈倉 道和 金 共子 廣瀬 雅哉 小笹 宏
- 出版者
- 近畿産科婦人科学会
- 雑誌
- 産婦人科の進歩 (ISSN:03708446)
- 巻号頁・発行日
- vol.63, no.2, pp.88-93, 2011 (Released:2011-06-27)
- 参考文献数
- 9
taxane系薬剤2剤にてアナフィラキシー(薬剤有害事象grade3~4)が出た2例を報告する.症例1は63歳の卵巣癌IIIc期.卵巣癌の手術後,paclitaxel-carboplatin (TC) 療法としてpaclitaxelの2回目投与を行った際,開始4分で血圧低下・呼吸困難・意識消失(有害事象grade4) が出現したため,気道を確保しながら酸素投与を開始すると同時に,コハク酸メチルプレドニゾロンナトリウムの急速点滴,エピネフリンの反復投与の治療を行った.48分後には意識は回復し,呼吸症状・血圧も平常値に戻った.TC療法は中止とし,後にcyclophosphamide-adriamycin-cisplatin (CAP)療法(4コース),cisplatin/irinotecan療法(2コース)を施行した.さらに,docetaxel-carboplatin (DC)療法としてdocetaxelを投与したが,投与開始5分後に呼吸困難(有害事象grade3) が出現したため中止となった.症例2は42歳の卵巣癌IIIc期.術後,初回のpaclitaxel投与開始3分後に呼吸症状(有害事象grade2) が発症し中止となった.その後docetaxelを投与したが,やはり投与開始後5分に重度の呼吸困難(有害事象grade3)が出現したが同様の応急処置で軽快した.paclitaxel投与にて薬剤過敏症状が出現した患者に対してdocetaxelを投与する場合には,同様の過敏症再発を念頭に慎重な管理が必要であると考えられた.〔産婦の進歩63(2):88-93,2011(平成23年5月)〕
1 0 0 0 止血に難渋した帝王切開後の腹壁血腫の1例
- 著者
- 柴田 梓沙 濱田 真一 島 佳奈子 智多 昌哉 大西 洋子 山嵜 正人 村田 雄二
- 出版者
- 近畿産科婦人科学会
- 雑誌
- 産婦人科の進歩 (ISSN:03708446)
- 巻号頁・発行日
- vol.73, no.3, pp.218-224, 2021 (Released:2021-08-07)
- 参考文献数
- 31
妊娠女性の高齢化に伴い子宮筋腫合併妊娠や癒着胎盤は増加傾向にあり,両者の合併で方針に苦慮することがある.今回われわれは,子宮体部前壁下部筋腫に加え帝王切開瘢痕部を覆う前壁付着胎盤で癒着が疑われる症例を経験した.前壁付着の前置胎盤に準じ子宮底部横切開による帝王切開術を選択し,良好な経過を得たので報告する.症例は37歳,7妊3産,3回の初期中絶既往があり,第1子は妊娠32週前期破水経腟分娩,第2子は妊娠39週経腟分娩,第3・4子は妊娠33週双胎妊娠前期破水にて緊急帝王切開分娩であった.今回は自然妊娠であった.初期より子宮体部前壁下部に10 cm大の変性筋腫,子宮後壁に5 cm大の筋腫を認め,妊娠16週で当院に紹介された.胎盤は帝王切開瘢痕部を覆うように子宮前壁全体に付着していた.妊娠後期のMRI検査にて癒着胎盤の可能性も示唆されたため,周術期の出血のリスクや子宮を温存した場合の出血・感染のリスク,今後変性筋腫に対し子宮摘出が必要になる可能性を説明し,明確な挙児希望がなかったため本人・家族の同意を得て子宮底部横切開による帝王切開術および子宮摘出を行う方針とした.妊娠37週4日に硬膜外麻酔および腰椎麻酔下に尿管ステントカテーテル留置後,帝王切開術を実施した.児は2880g男児,Apgar score 8/9であった.胎盤を遺残させたまま筋層を仮縫合した後,腟上部切断術を行った.術中出血量は750 ml,手術時間は1時間24分であった.術後経過も良好で,術後7日目に母児ともに退院となった.胎盤病理では癒着胎盤を示す明らかな所見は認めなかった.子宮体部前壁下部筋腫合併妊娠では通常の子宮下節切開が困難で児の娩出に難渋することがある.本症例では子宮全摘を前提に子宮底部横切開による帝王切開術を行った.子宮底部横切開は,胎盤前壁付着の体部前壁下部筋腫症例にも応用ができると考えられる.〔産婦の進歩73(3):218-224,2021(令和3年8月)〕
1 0 0 0 OA 子宮内膜癌における基底膜の免疫組織学的研究
- 著者
- 小畑 孝四郎 井上 芳樹
- 出版者
- 近畿産科婦人科学会
- 雑誌
- 産婦人科の進歩 (ISSN:03708446)
- 巻号頁・発行日
- vol.44, no.2, pp.143-156, 1992-03-01 (Released:2011-07-05)
- 参考文献数
- 31
- 被引用文献数
- 1
Immunohistochemical studies were performed on type IV collagen and laminin in endometrial adenocarcinomas to relate the localization of basement membrane components to tumor invasion and metastasis. Paraffin sections were prepared from formalin-fixed specimens of 58 endometrial carcinomas. Immunohistochemical staining was performed with primary mouse anti-human type IV collagen antibody or rabbit anti-human laminin antibody and by the ABC method. DNA ploidy analysis was added in 29 cases. Staing for type IV collagen was found in 37.1 ± 19.6% of well differenciated adenocarcinomas, 28.7±16.1% of moderately differenciated lesions, and 18.6±7.8% of poorly differenciated lesions. The respective percentages for laminin were 36.3±17.4%, 28.9±18.6%, and 22.8±17.1%. In metastatic lymph node, positive staining was similar to that in primary leisions. DNA aneuploid lesions showed less staining for laminin. Tumor cells had cytoplasmic laminin in 7 cases and it was rarely seen in the basement membrane. Six of those tumors were G2 or G3 and six had DNA aneuploid. Five of those patients died of primary disease and four of intraperitoneal recurrence.The features of the basement membrane in tumors may reflect construction rather than destruction by cancer cells.
1 0 0 0 OA 過多月経例における月経血量の測定と子宮腔内異常
- 著者
- 井本 広済 奥田 喜代司 佐伯 理男 岡崎 審 猪木 千春 杉本 修
- 出版者
- 近畿産科婦人科学会
- 雑誌
- 産婦人科の進歩 (ISSN:03708446)
- 巻号頁・発行日
- vol.44, no.5, pp.482-485, 1992-09-01 (Released:2011-07-05)
- 参考文献数
- 8
There is a conciderable incidence of out-clinic patients who complained of hypermenorrhea (10 %). Menstrual blood loss was measured by alkali hematine method and uterine abnormalities were examined by ultrasonography and hysteroscopy in the 18 patients who complained of hypermenorrehea. Only eight patients had a mean menstrual blood loss of over 60ml and anemia. The other 10 patients whose menstrual blood loss was less than 60ml, had no severe anemia. These results suggest that over 60ml of menstrual blood loss should be abnormal as objective hypermenorrhea. The number of used pads was not correlated with menstrual blood loss. In the eight patients with objective hypermenorrhea, uterine myomas were found in four patients and endometrial polyp was found in one patient by hysteroscopic and ultrasonographic examination. However, in two patients out of eight, no organic, endocrinological and blood coagulation cause of hypermenorrhea was found.
1 0 0 0 産痛制御とその周辺 (分娩における自然主義に対する批判)
- 著者
- 山村 博三
- 出版者
- 近畿産科婦人科学会
- 雑誌
- 産婦人科の進歩 (ISSN:03708446)
- 巻号頁・発行日
- vol.22, no.4, pp.270-271, 1970
- 著者
- 水野 潤二 椹木 勇 江藤 勝磨 日下 尚機 江原 収
- 出版者
- 近畿産科婦人科学会
- 雑誌
- 産婦人科の進歩 (ISSN:03708446)
- 巻号頁・発行日
- vol.24, no.4, pp.286-298, 1972
1953年Morrisによって指摘された精巣性女性化症候群testicular feminization syndromeのcomplete formでseminomaを伴ったまれな1例を経験した. すなわち43才の主婦で下腹部腫瘤感を主訴として来院し, 本症と診断, 開腹により右側性腺は新生児頭大の未分化胚細胞腫(20×10×10cm, 840g)であり, 左側は, 胡桃大の睾丸(精子形成像はなく, Leydig細胞増生)と栂指頭大の嚢胞(輸精管)を認め, これらを摘出した. 両親はいとこ結婚と言われ, 8人の同胞のうち男女各1人は幼時死亡, 他の5人はいずれも女性で, 結婚しているが, 長姉および患者は児を得ていない. 術後尿中17KSは著減し, 腟スメアの各係数にはかなりのエストロゲン効果がみられるなど, 順調に経過している.
1 0 0 0 子宮剔除並びに卵管結紮後に於ける諸種内分泌腺の組織学的研究
- 著者
- 吉岡 毅
- 出版者
- 近畿産科婦人科学会
- 雑誌
- 産婦人科の進歩 (ISSN:03708446)
- 巻号頁・発行日
- vol.11, no.1, pp.19-31, 1959