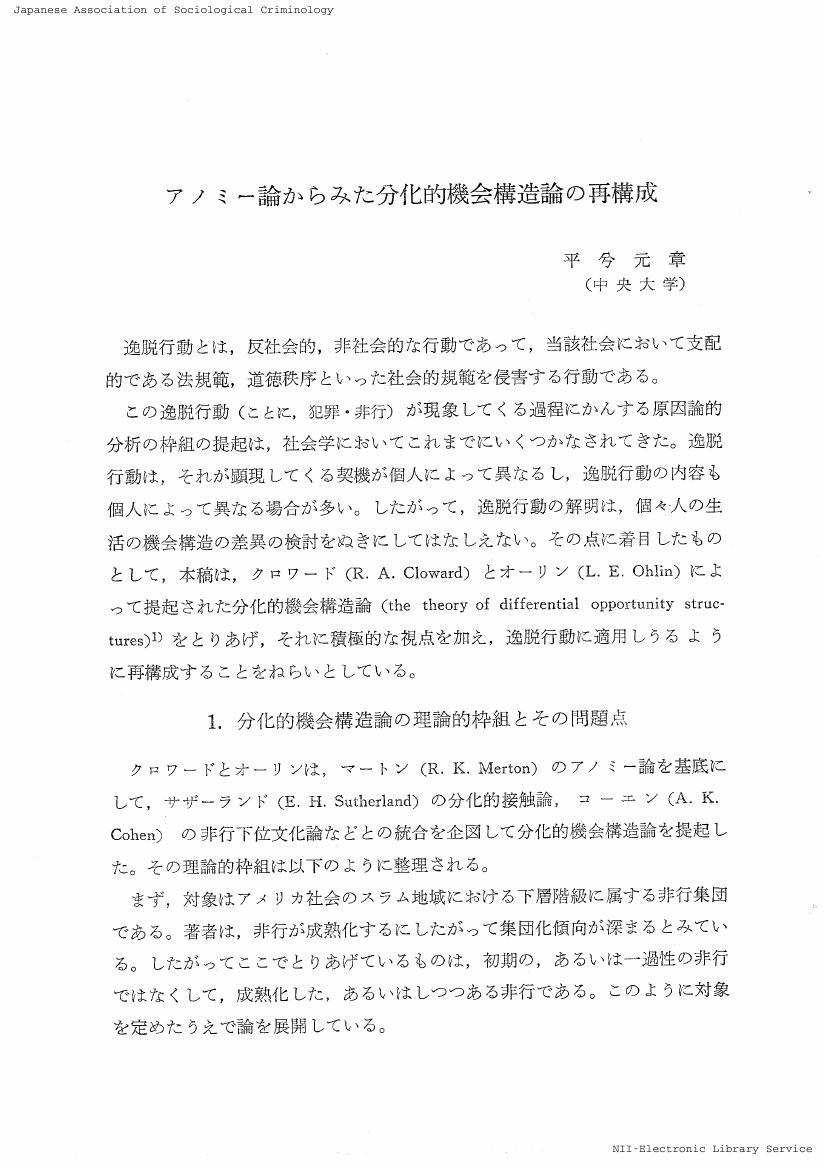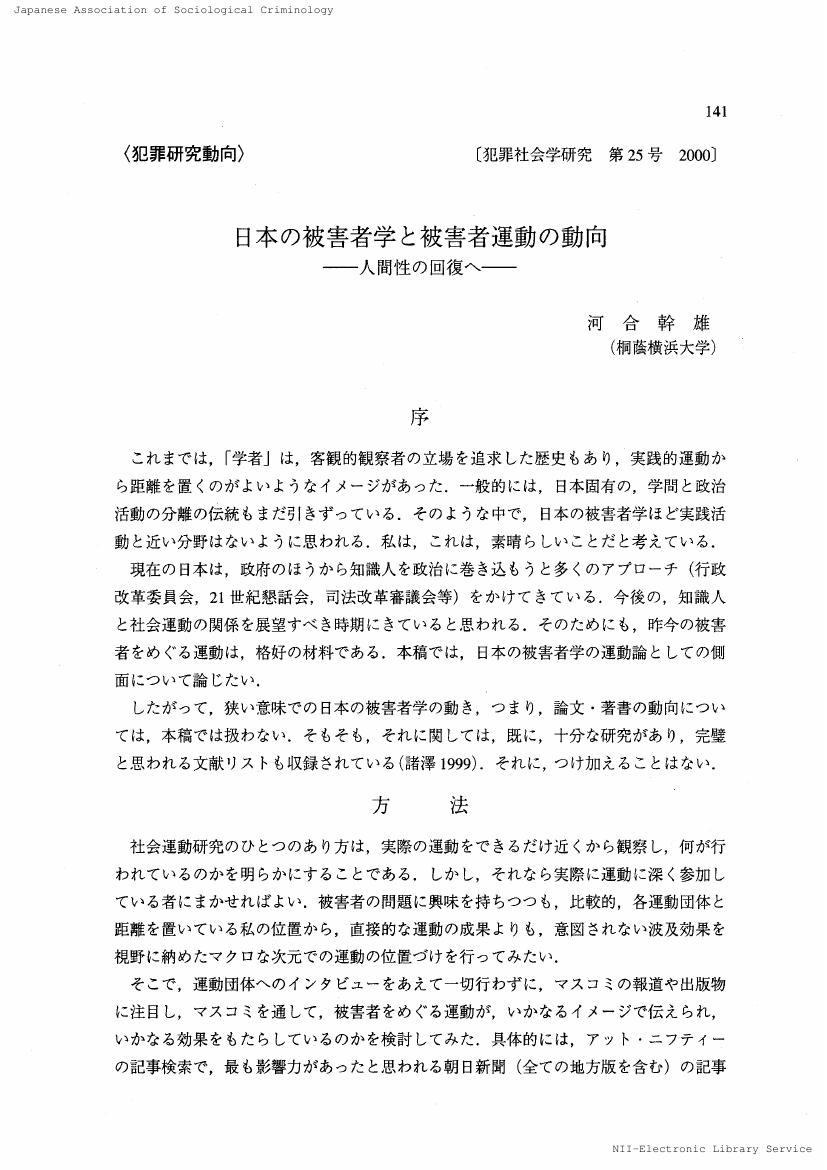1 0 0 0 OA 刑事司法と福祉の連携に関する現状と課題について (課題研究 刑事司法と福祉の連携の在り方-犯罪行為者の社会復帰支援の現状と課題) 長崎県地域生活定着センターの"実践"から見えてきたもの
- 著者
- 伊豆丸 剛史
- 出版者
- 日本犯罪社会学会
- 雑誌
- 犯罪社会学研究 (ISSN:0386460X)
- 巻号頁・発行日
- vol.39, pp.24-36, 2014-10-18 (Released:2017-03-31)
長崎県地域生活定着支援センターでは,主たる業務である矯正施設を退所する障がい者・高齢者への福祉的支援だけではなく,捜査・公判段階にある障がい者・高齢者に対する福祉的支援にも積極的に取り組んできた.その理由は,ひとえに矯正施設退所者を支えるシステムだけではなく,矯正施設に至る前のより早い段階,即ち刑事司法手続上の捜査・公判段階から福祉的介入がなされるシステムも同時並行的に構築していかなければ,社会的弱者を犯罪へ至らしめる負の連鎖は,真の意味で断ち切ることができないのではないかと実感したからである.こうした問題意識から,長崎県地域生活定着支援センターでは,社会福祉法人南高愛隣会等と協働し,平成23年度から調査研究事業に基づく様々な司法と福祉のモデル的実践を積み重ねてきた.また,その一環として,平成25年度には定着支援センター内に「司法福祉支援センター」をモデル的に開設し,被疑者・被告人に特化した支援も実践してきた.本稿では,これらの取り組みから見えてきた捜査・公判段階からの障がい者・高齢者支援における成果や課題について述べるとともに,司法と福祉の狭間を紡いでいくために,これまで交わることのなかった様々な機関が互いを知り,深めあうことでの「イノベーション」の必要性を説く.
1 0 0 0 OA <敵>は新自由主義なのか? (課題研究 貧困と犯罪・非行)
- 著者
- 芹沢 一也
- 出版者
- 日本犯罪社会学会
- 雑誌
- 犯罪社会学研究 (ISSN:0386460X)
- 巻号頁・発行日
- vol.35, pp.87-98, 2010-10-01 (Released:2017-03-30)
犯罪や貧困の処遇において,監視や排除,厳罰化など,日本でもアメリカのように抑圧的な手段が強化されているといわれる.そして,このような状況に批判的な論者は,その原因として新自由主義をあげ,それへの敵対と対抗を唱えている.だがはたして,日本に新自由主義的な統治が出現しているといえるのか?本稿は1970年代以来の日本社会の構造的な変容を踏まえながら,90年代以降に起こったのは,新自由主義への統治原理の転換ではなく,日本型安定社会のたんなる崩壊だということを示す.その上で,そうした文脈にある日本の貧困や犯罪処遇の変容について,新自由主義批判を展開することは的外れであるだけでなく,看過しえない危険性をともなうことを主張する.問題は安定社会に代わる社会構想の不在なのであって,今後,社会保障や社会復帰政策を構想する上で不可欠なのは,経済的リソースの配分をめぐって国家と市場との関係性を冷静に思考することである.そのためには,小泉構造改革の誤った総括によって根づいた市場不信と,自民党の利益政治批判によって広まった政治不信をともに払拭する必要がある.
- 著者
- 平井 秀幸
- 出版者
- 日本犯罪社会学会
- 雑誌
- 犯罪社会学研究 (ISSN:0386460X)
- 巻号頁・発行日
- vol.41, pp.26-46, 2016
理論犯罪学の伝統的理解では,規律から管理へと犯罪統制トレンドが変化するなかで,リスクは犯 罪者処遇ではなく犯罪予防やリスク人口層の管理と結びつくようになっているとされる.しかし,そ うした理解は経験的・理論的に見て必ずしも妥当なものではない.エビデンスに基づく犯罪者処遇の 上昇に伴って,認知行動療法のようなリスクモデルの犯罪者処遇がグローバルな拡がりを見せており, それは新自由主義的合理性に基づくリスク回避型自己の責任化実践として作動しつつある.とはいえ, 近年ではリスクモデルの犯罪者処遇と並行して,レジリエンスを鍵概念のひとつとする新たな犯罪者 処遇が現れはじめてもいる.リスクモデルにおいて回避・対処すべき再犯リスクとみなされた困難状 況(不確実性)は,レジリエンス原則のもとでは前進・成長のチャンスとして積極的に受けとめられ, 元犯罪者は不確実性受容型自己として責任化される.慎慮主義的なリスク回避型自己とアントレプレ ナー的な不確実性受容型自己は,共に新自由主義を支える主体像としてポスト・リスクモデルの犯罪 者処遇のなかで共存し得るものかもしれない.新時代の犯罪者処遇研究には,「リスクと犯罪者処遇」 という従来の枠組を超えた新たな問題設定と,それに基づく経験的・批判的研究の更なる蓄積が求め られている.
- 著者
- 小長井 賀與
- 出版者
- 日本犯罪社会学会
- 雑誌
- 犯罪社会学研究 (ISSN:0386460X)
- 巻号頁・発行日
- vol.34, pp.95-113, 2009-10-20 (Released:2017-03-30)
本稿では,社会的排除論に立脚した新しい犯罪者処遇方法の原型をイギリスに求め,背景,理念,方法,意義及び事例を概観し,「更生中心主義か,リスク管理及び正義の実現か」という二項対立を止揚した新しい処遇モデルとして,理論的に整理した.イギリスでは,「福祉国家」建設が破たんしたとされる1980年代以降は,保守党政権によって新自由主義に立脚する国家運営が行われた.犯罪対策においては,犯罪の責任を専ら個人に求め,厳罰化が進められた.しかし,1997年に労働党政権へ移行した後は,経済の発展と国民の福利が両立する「福祉社会」建設が模索されるようになり,政府は,社会的排除論に立脚して,種々の社会政策を行ってきた.社会的排除論では,個人的要因ではなく社会構造的な要因によって,社会に参加できない一群の人々が出現するとする.犯罪対策においても,2001年以降は犯罪の社会的要因を公的に認め,犯罪を行った者を含めすべての市民に社会参加の機会を平等に保障することで,犯罪リスクを減じようとする政策を行うようになった.すなわち,政府は,官・民・公のパートナーシップの枠組みを用いて犯罪者を地域社会に再統合する政策を行い,さらに,刑事司法を社会的包摂政策及び社会保障政策に繋げ,より大きなフィールドの中で犯罪者を「7つの経路」から包括的に「地域で生活する者」としてエンパワーすることを目指してきた.「7つの経路」とは,実証研究に基づく犯因性ニーズであり,再犯を予防する手立てでもある.このようなイギリスの犯罪者処遇モデルは,シティズンシップに基づく人間観や,市民に社会参加の機会を保障することが社会や国家の責務であるとする社会観に負うところが大きい.あるべき社会や市民を示す概念を構築し切れていない日本では,残念ながら自国に相応しい犯罪者処遇モデルも形成しづらい状況にある.それでも日本はイギリスの経験から学び,いくつかの方策を導入することができる.特に,犯罪者の更生と社会参加が地域社会の安全に寄与するとし,自治体や市民セクターとのパートナーシップを用いて犯罪者を社会に再統合する方法は示唆に富む.
1 0 0 0 OA アノミー論からみた分化的機会構造論の再構成
- 著者
- 平兮 元章
- 出版者
- 日本犯罪社会学会
- 雑誌
- 犯罪社会学研究 (ISSN:0386460X)
- 巻号頁・発行日
- vol.1, pp.204-219, 1976 (Released:2017-02-01)
1 0 0 0 少年犯罪と精神疾患の関係の語られ方:戦後の新聞報道の分析を通じて
- 著者
- 赤羽 由起夫
- 出版者
- 日本犯罪社会学会
- 雑誌
- 犯罪社会学研究 (ISSN:0386460X)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, pp.104-118, 2012
本論の目的は,少年犯罪と精神疾患の関係の語られ方の内容とその歴史的な変遷の分析を通じて,1990年代以降の少年犯罪の医療化の特徴を明らかにすることである.そのために本論が分析資料として用いるのは,終戦から現在までの『朝日新聞』,『毎日新聞』,『読売新聞』の縮刷版から選出した精神疾患に言及のある少年犯罪の記事,および精神疾患についての記事である.分析の結果,明らかになった知見は,次の三点である.第一に,終戦から1970年代までに少年犯罪と関係づけられて語られた主な精神疾患には,精神分裂病,精神病質,精神薄弱,ノイローゼがある.第二に,1990年代以降に少年犯罪と関係づけられて語られた主な精神疾患には,行為障害と発達障害がある.第三に,1990年代以降の少年犯罪の医療化の背景には,第一に,精神疾患が指摘されやすい「普通の子」による少年犯罪が社会問題化したことと,第二に,教育問題までも包含する精神疾患として行為障害と発達障害の概念が登場したことがあげられる.
- 著者
- 中島 隆信
- 出版者
- 日本犯罪社会学会
- 雑誌
- 犯罪社会学研究 (ISSN:0386460X)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, pp.42-61, 2011-10-31 (Released:2017-03-30)
経済学が他分野にあれこれ口を出して引っかき回すことを「経済学帝国主義」という.しかし,刑事政策に関しては,経済学による「侵略」はこれまで日本ではあまりされてこなかった.その理由としては,犯罪を費用・便益の視点から分析することへの強い抵抗感があげられよう.しかし,刑事犯罪は裁判で有罪となった人間を刑務所に入れればそれで片が付くわけではない.犯罪には,取り調べ費用,裁判費用,施設収容費用がかかり,さらに社会復帰ができなければまた同じ費用が何度でもかかることになる.経済学的視点がすべてに優先するとはいえないが,経済のインセンティブ構造に明らかに反したり,費用・便益の観点からきわめて非効率だったりする社会政策は,いずれは国民の支持を失い,破綻に追い込まれるだろう.本論文は,近年進みつつある厳罰化,刑事裁判,矯正,そして更生保護にまつわる現在の日本の制度設計について,経済学的視点から検討を加えることにしたい.
- 著者
- 菊池 武剋
- 出版者
- 日本犯罪社会学会
- 雑誌
- 犯罪社会学研究 (ISSN:0386460X)
- 巻号頁・発行日
- vol.9, pp.56-67, 1984 (Released:2017-03-30)
Fujita (1982) argues that delinquencies committed by Japanese Koreans begin in their early adolescence and that environmental factors characterizing Korean sub-society in Japan are responsible for the delinquencies. (Fujita mentions such "environmental factors" as low socioeconomic status of Korean families.) But can we explain delinquencies of Japanes (Koreans only in terms of such "environmental factors"? This paper examines this causal issue on the basis of case studies. A close examination of the social organization of Korean people ir Japan as a "minority group" reveals that it consists of numerous subgroups which are heterogeneous with regard to such characteristics as nationality, socioeconomic status, and generation. Our case studies of Korean delinquents indicate that their self-identity as Koreans varies according to the types of subgroups to which they belong. Levine's (1977) "Typology of Stranger Relationship" gives us a clue to explore the social roles of the Korean adolescents in Japan and their bearings on their delinquencies. The two axes of his typology are "Stranger's Interest in Host Community" and "Host's Response to Strangers". Although Levine's typology is useful in classifying Korean people's "interest in host community", it dose not include a category for the typical response of Japanese to Korean ; i. e., "negative stereotyping" (Wagatsuma, 1981). "Negative stereotyping" is crucial in shaping Korean adolescents' selfidentity as marginal men. It is also crucial in determining scioeconomic status and social marginality of Koreans in Japan. The first conclusion of this paper is that construction of a more elaborate typology about types of marginality of Koreans is crucial in understanding causal mechanism underlying delinquencies of Japanese Koreans. Another conclusion of this paper is that we have to employ a phenomenological approach in understanding and analyzing individual cases. The approach will enable us to explore effects of the strain factors which have been said to be characteristic of Korean delinquents in Japan. If we can synthesize the typological studies and case studies, we will be able to elaborate a theory about deviant behaviors of minority peoples in general.
1 0 0 0 OA 脳科学・神経科学の進歩と少年司法
- 著者
- 上野 正雄
- 出版者
- 日本犯罪社会学会
- 雑誌
- 犯罪社会学研究 (ISSN:0386460X)
- 巻号頁・発行日
- vol.42, pp.65-71, 2017 (Released:2018-10-31)
少年法は保護処分すなわち教育によって少年を更生させようとする.しかし,近時の少年法を巡る 動きを見ると少年の責任を追及するという姿勢が強くなってきている.その背景には,少年を可塑性 が高いという点で質的に成人と異なる存在と見るか(子ども観),少年と成人の連続性を重視して本質 的な相違はないと見るか(小さな大人観),法対象者の見方の違いがある.このような中で,近時の脳 科学・神経科学の進歩は,衝動的行動を抑制する前頭前皮質の成熟は20代後半まで緩徐に進行するが, 感情をつかさどる大脳辺縁系は10歳頃に始まる思春期に成熟が促進され,この両者の成熟速度の不均 衡のため,10代の若者は危険な行動に走りがちだが,一方で環境に素早く適応することができる,と いう知見をもたらした.これは「子ども」観が拠って立つ科学的根拠の一つとなる.反面,非行少年 に対する責任を追及するという方策は,少年の更生とそれによる社会の安全確保にとって望ましいも のではないことになる.その上で,「子ども」観の徹底という点から,少年法上のいくつかの制度につ いてどのように解釈し,運用することが適切なのかを検討する.
1 0 0 0 OA ポスト・リスクモデルの犯罪者処遇へ? (課題研究:犯罪社会学におけるリスク社会論の意義)
- 著者
- 平井 秀幸
- 出版者
- 日本犯罪社会学会
- 雑誌
- 犯罪社会学研究 (ISSN:0386460X)
- 巻号頁・発行日
- vol.41, pp.26-46, 2016 (Released:2017-10-31)
理論犯罪学の伝統的理解では,規律から管理へと犯罪統制トレンドが変化するなかで,リスクは犯 罪者処遇ではなく犯罪予防やリスク人口層の管理と結びつくようになっているとされる.しかし,そ うした理解は経験的・理論的に見て必ずしも妥当なものではない.エビデンスに基づく犯罪者処遇の 上昇に伴って,認知行動療法のようなリスクモデルの犯罪者処遇がグローバルな拡がりを見せており, それは新自由主義的合理性に基づくリスク回避型自己の責任化実践として作動しつつある.とはいえ, 近年ではリスクモデルの犯罪者処遇と並行して,レジリエンスを鍵概念のひとつとする新たな犯罪者 処遇が現れはじめてもいる.リスクモデルにおいて回避・対処すべき再犯リスクとみなされた困難状 況(不確実性)は,レジリエンス原則のもとでは前進・成長のチャンスとして積極的に受けとめられ, 元犯罪者は不確実性受容型自己として責任化される.慎慮主義的なリスク回避型自己とアントレプレ ナー的な不確実性受容型自己は,共に新自由主義を支える主体像としてポスト・リスクモデルの犯罪 者処遇のなかで共存し得るものかもしれない.新時代の犯罪者処遇研究には,「リスクと犯罪者処遇」 という従来の枠組を超えた新たな問題設定と,それに基づく経験的・批判的研究の更なる蓄積が求め られている.
1 0 0 0 OA 脳科学・神経科学と少年の刑事責任
- 著者
- 本庄 武
- 出版者
- 日本犯罪社会学会
- 雑誌
- 犯罪社会学研究 (ISSN:0386460X)
- 巻号頁・発行日
- vol.42, pp.33-49, 2017 (Released:2018-10-31)
少年の刑事責任の低減を示す脳科学の知見は,アメリカの判例に積極的に取り入れられ,少年に対 する死刑の廃止や仮釈放のない終身刑の大幅な制限をもたらしている.この背景には,法学者と科学 者の活発な共同研究,大規模な共同研究を支援する体制,経験科学の知見を司法に導入することに対 する裁判所の寛容な姿勢があると考えられる.脳科学の知見は,現在各州で少年に対する厳罰化を抑 制する立法を後押ししており,将来的に,少年に対する刑事処分全体ひいては少年司法全体の改革を もたらす可能性がある.脳科学は,少年司法の基盤をパレンス・パトリエに基づく慈悲の精神から, 意思決定能力の未成熟さという科学的な知見に移行させ,少年犯罪者を成人から区別して取り扱うと いう発想を強固にする.重大犯罪においても,少年の刑事責任の低減に見合った処分のあり方が求め られる.現在までのところ,脳科学は青年期に関する発達心理学の知見を補強するという慎重な用い られ方をしており,その限りで弊害は乏しい.日本の少年司法も脳科学の知見を取り入れるべきであ ろう.
- 著者
- 土井 隆義
- 出版者
- 日本犯罪社会学会
- 雑誌
- 犯罪社会学研究 (ISSN:0386460X)
- 巻号頁・発行日
- vol.41, pp.10-25, 2016 (Released:2017-10-31)
ハイモダニティの時代を迎えている今日の日本社会では,あらゆる局面で再帰的なメカニズムが作動するようになっている.個々人の日常生活においても,社会的な流動性が高まった結果,リスクに対して鋭敏な感覚が育まれるようになっている.しかし,流動化が与える影響は,若年層と高齢層とで大きく異なっている.そのため,そこから生じるリスク感覚も,各年齢層によって大きく異なっている.したがって,その差異は,逸脱行動に対する個々人の心理的な距離感にも反映している.本論は,このような観点から,21世紀以降の我が国において,若年層の一般刑法犯の検挙人員が低下傾向を示しているという事実と,高齢層のそれが高留まりの傾向を示しているという事実の,それぞれの背後に潜んでいる社会的要因の差異について解明を試みる.
1 0 0 0 OA 暴力団員と累犯(<特集>累犯をめぐる諸問題)
- 著者
- 星野 周弘
- 出版者
- 日本犯罪社会学会
- 雑誌
- 犯罪社会学研究 (ISSN:0386460X)
- 巻号頁・発行日
- vol.5, pp.42-63, 1980 (Released:2017-03-09)
- 著者
- 土井 政和
- 出版者
- 日本犯罪社会学会
- 雑誌
- 犯罪社会学研究 (ISSN:0386460X)
- 巻号頁・発行日
- vol.39, pp.67-81, 2014-10-18 (Released:2017-03-31)
本稿は,まず,更生保護法施行前後における保護観察実務の変化の存否とその背景について述べたのち,刑事司法と福祉との連携が進行していく中で,保護観察の将来の方向性はいかにあるべきかについて言及する.次に,刑事司法と福祉との連携を促進し,対象者の社会復帰支援を強化する福祉の側からの試みが現在どのような課題に直面し,また,刑事司法制度にどのような課題を提起しているかについて検討する.本稿では,検察庁への社会福祉士の配置及び保護観察所による更生緊急保護事前調整モデルの二つを取り上げる.特に更生緊急保護事前調整モデルは二つ可能性をもつ.一つは,対象者が保護観察所に赴いてから手続をとる現在の更生緊急保護制度における時間的制約を解消し,早期に福祉に繋ぐことを可能にすること,もう一つは,対象者の選択に関し,被疑者段階にある対象者に対して綿密な情状調査が一種の「起訴猶予前調査」として行われ,更生緊急保護実施後の経過が良好でない場合は再起するという運用をもたらす可能性があることである.近年,再犯防止を目的として諸施策の試行が拡大しているが,再犯防止概念は本人支援と社会防衛の両者を内包しており,その用い方によっては,視点が本人支援から社会防衛へと容易に転換しうるものであることから,福祉の刑事司法化をもたらさないためにも,福祉は刑事司法との関係において対等性・独立性を失わないようにしなければならない.
1 0 0 0 OA 法社会学的犯罪社会学の研究動向
- 著者
- 所 一彦
- 出版者
- 日本犯罪社会学会
- 雑誌
- 犯罪社会学研究 (ISSN:0386460X)
- 巻号頁・発行日
- vol.3, pp.189-192, 1978 (Released:2017-02-18)
1 0 0 0 OA ストーカー行為をめぐる最近の動向について
- 著者
- 宮園 久栄
- 出版者
- 日本犯罪社会学会
- 雑誌
- 犯罪社会学研究 (ISSN:0386460X)
- 巻号頁・発行日
- vol.40, pp.129-134, 2015-10-30 (Released:2017-04-30)
1 0 0 0 OA 日本の被害者学と被害者運動の動向
- 著者
- 河合 幹雄
- 出版者
- 日本犯罪社会学会
- 雑誌
- 犯罪社会学研究 (ISSN:0386460X)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, pp.141-147, 2000 (Released:2017-03-30)
- 著者
- 浜井 浩一
- 出版者
- 日本犯罪社会学会
- 雑誌
- 犯罪社会学研究 (ISSN:0386460X)
- 巻号頁・発行日
- vol.32, pp.8-26, 2007-10-20 (Released:2017-03-30)
近時,日本では,凶悪犯罪の増加など治安の悪化が大きな社会問題として取り上げられている.マスコミは,凶悪犯罪が起こるたびに,認知件数や検挙率といった警察統計を取り上げて危機感をつのらせる.しかし,認知件数は,犯罪指標の一つではあるが,警察に事件が届けられ,警察が犯罪として認知したものを計上した行政機関の受理統計であり,犯罪発生をそのまま反映したものではない.本稿では,最初に犯罪被害調査の特徴を概観した後に,筆者が平成16年度の科学研究費補助金(基盤研究B「治安・犯罪対策の科学的根拠となる犯罪統計(日本版犯罪被害調査)の開発」)の交付を受けて2006年に実施した犯罪被害調査の結果を報告する.まず,犯罪被害率について過去に行われたICVSの結果等とも比較し,犯罪被害調査から見た日本の犯罪情勢について報告し,さらに,犯罪被害調査の妥当性・信頼性を確認する意昧から,調査方法による回収率・回答パターンの変化,更には回収率が低下することによる調査結果への影響に焦点を当てた報告を行う.本犯罪被害調査では,調査対象者(サンプル)を二つのグループに分け,一つのグループについては,従来から日本の世論調査等でよく用いられている訪問面接方式によって調査を実施し,もう一つのグループについては訪問留置き方式によって調査を実施した.これは,近時,個人情報に対する国民の意識の高まり等によって,世論調査・社会調査の実施環境が著しく悪化し,調査の回答率が低下したことに加えて,調査実施に対する苦情も増大しつつある現実を踏まえ,調査方法による回収率等への影響を調べるためのものである.さらに,回収率の低下が調査の信頼性にどのような影響を与えるのかを検討するため,無回答者に対して,質問項目を絞った簡易質問紙を郵便で送付する追跡(二次)調査を実施し,その結果を訪問調査の結果と比較した.
1 0 0 0 OA 「事件」の構成過程における警察のワーク
- 著者
- 今井 聖
- 出版者
- 日本犯罪社会学会
- 雑誌
- 犯罪社会学研究 (ISSN:0386460X)
- 巻号頁・発行日
- vol.42, pp.121-138, 2017 (Released:2018-10-31)
本稿の目的は,駅構内での女性への痴漢被疑者に対して行われた警察のワークを,「ワークのエスノ メソドロジー研究」の立場から考察することである.本稿では,被疑者を警察署に任意同行するため の説得と,警察署での実質的な事情聴取という2つのワークを分析する. これらの警察のワークは,警察官と被疑者との会話的やりとりを通して遂行される.従来研究にお いて,「ストリートレベルの官僚」としての警察官による裁量の行使が指摘されていたが,実際の会話 的相互行為に基づいた研究は十分取り組まれてこなかった. 本稿では,ある実際の「痴漢事件」において,交番および警察署で行われた,警察官と被疑者によ る会話的やりとりを分析し,それにより達成される警察のワークを記述する. 分析からは,主として次の2点が示される.第一に,交番警察が被疑者を任意同行する際に,被疑 者にとっての必要性を強調することで「説得」を行っていること.第二に,警察署警察が,被疑者と 痴漢被害を訴える女性の同行者との間の相互行為を推断的に記述していることである.以上の分析知 見を踏まえ,警察のワークが被疑者に困難な「現実」をもたらし得るものであったことを指摘する.
- 著者
- 今井 聖
- 出版者
- 日本犯罪社会学会
- 雑誌
- 犯罪社会学研究 (ISSN:0386460X)
- 巻号頁・発行日
- vol.42, pp.121-138, 2017
本稿の目的は,駅構内での女性への痴漢被疑者に対して行われた警察のワークを,「ワークのエスノ メソドロジー研究」の立場から考察することである.本稿では,被疑者を警察署に任意同行するため の説得と,警察署での実質的な事情聴取という2つのワークを分析する. これらの警察のワークは,警察官と被疑者との会話的やりとりを通して遂行される.従来研究にお いて,「ストリートレベルの官僚」としての警察官による裁量の行使が指摘されていたが,実際の会話 的相互行為に基づいた研究は十分取り組まれてこなかった. 本稿では,ある実際の「痴漢事件」において,交番および警察署で行われた,警察官と被疑者によ る会話的やりとりを分析し,それにより達成される警察のワークを記述する. 分析からは,主として次の2点が示される.第一に,交番警察が被疑者を任意同行する際に,被疑 者にとっての必要性を強調することで「説得」を行っていること.第二に,警察署警察が,被疑者と 痴漢被害を訴える女性の同行者との間の相互行為を推断的に記述していることである.以上の分析知 見を踏まえ,警察のワークが被疑者に困難な「現実」をもたらし得るものであったことを指摘する.