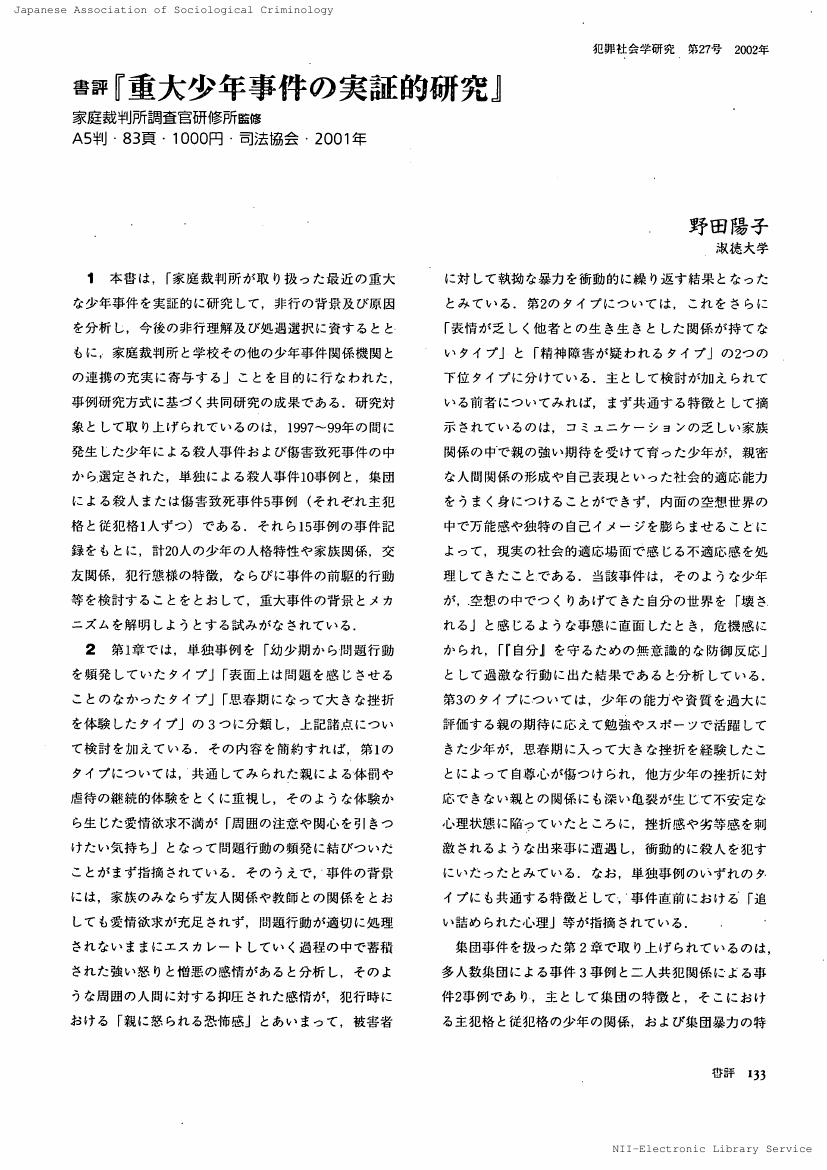2 0 0 0 OA グッドライフモデルと犯罪・非行からの立ち直り
- 著者
- 相澤 育郎
- 出版者
- 日本犯罪社会学会
- 雑誌
- 犯罪社会学研究 (ISSN:0386460X)
- 巻号頁・発行日
- vol.44, pp.11-29, 2019-10-20 (Released:2022-04-26)
グッドライフモデルとは,2000年代の初頭より,ニュージーランドの心理学者トニー・ウォードらによって提唱された,犯罪者処遇・更生に関する理論的枠組みである.本稿の目的は,これに関連する文献をレビューすることにより,その全体像の解明と評価を行い,そして日本の犯罪者処遇政策への示唆を得ることである.グッドライフモデルは当初から,リスク管理的アプローチをモデルに組み入れることを意図していた.それは,犯罪者処遇・更生理論にとって重要な再犯の予防(リスクの管理)と本人の福利(グッドライフの促進)を両立させる理論的挑戦である.またグッドライフモデルの発想による処遇は,人間の尊厳と人権,刑罰と更生,そして処遇と処遇者の倫理に基づいている.そこでは,刑事司法に関与するすべてのステークホルダーを重視する関係的刑罰理論が重要な位置を占めている.そしてグッドライフモデルにはエビデンスが不十分であるとの批判もなされるが,これを支える前提と実務に焦点を当てた評価研究は,徐々に積み重ねられている.結論として,グッドライフモデルには,その折衷主義的な性格ゆえの課題も残されているが,日本の犯罪者処遇実務に取り入れられるべきである.
2 0 0 0 OA 犯罪研究動向:触法精神障害者の処遇に関する研究動向
- 著者
- 城下 裕二
- 出版者
- 日本犯罪社会学会
- 雑誌
- 犯罪社会学研究 (ISSN:0386460X)
- 巻号頁・発行日
- vol.45, pp.131-139, 2020-11-20 (Released:2022-04-26)
2 0 0 0 OA 犯罪研究動向 女性の暴力被害に関する調査
2 0 0 0 OA 北欧における犯罪研究の特徴
- 著者
- 細井 洋子
- 出版者
- 日本犯罪社会学会
- 雑誌
- 犯罪社会学研究 (ISSN:0386460X)
- 巻号頁・発行日
- vol.9, pp.203-215, 1984 (Released:2017-03-30)
2 0 0 0 OA フィンランドにおける性犯罪対策 刑法改正と性犯罪受刑者処遇
- 著者
- 齋藤 実
- 出版者
- 日本犯罪社会学会
- 雑誌
- 犯罪社会学研究 (ISSN:0386460X)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, pp.134-147, 2006-10-18 (Released:2017-03-30)
わが国において,幼女を狙った性犯罪が相次いで起こり,社会に深刻な問題を投げかけている.そのため,俄かに,性犯罪対策のあり方についての議論がなされているが,現在,議論の中心の1つは,いかに効果的な性犯罪者処遇を行い,再犯を防止するかという点にある.再犯防止のために,諸外国の性犯罪対策の状況を知ることは,わが国で効果的な性犯罪者対策をするために不可欠の要素であろう.本稿では,諸外国の中でも,今まであまり紹介されることのなかった,フィンランドの性犯罪対策について紹介していく.フィンランドにおける積極的な性犯罪対策の歴史は古くはないものの,近年一定の効果をあげているといわれる.フィンランドでは,具体的な性犯罪対策として,刑法改正と性犯罪者処遇を性犯罪対策の二本柱としている.そこで,本稿では,フィンランドの性犯罪対策を紹介し,これらのわが国の導入の可能性を検討した.
2 0 0 0 OA 刑罰理論と社会機能の相互関係(<特集>社会と刑罰)
- 著者
- 平場 安治
- 出版者
- 日本犯罪社会学会
- 雑誌
- 犯罪社会学研究 (ISSN:0386460X)
- 巻号頁・発行日
- vol.2, pp.40-57, 1977 (Released:2017-02-01)
- 著者
- 安達 光治
- 出版者
- 日本犯罪社会学会
- 雑誌
- 犯罪社会学研究 (ISSN:0386460X)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, pp.7-21, 2006-10-18 (Released:2017-03-30)
「生活安全条例」は,現在では,多くの都道府県ないしは市町村で制定されており,また,この種の条例制定の促進は,政府の政策でもある.「生活安全条例」は内容面から次のように分類できる.すなわち,(1)地域の生活安全活動の理念を提示するもの,(2)学校,道路,公園,集合住宅等の設計において防犯の観点による行政や警察の積極的関与を規定するとともに,暴力犯罪や侵入窃盗などの前段階の行為を処罰するもの,(3)生活安全と生活環境の美化を融合させたもの,である.このような条例制定の狙いは,地域住民の防犯活動への積極的関与を促し,地域社会の犯罪抑止機能を回復することにある.条例は,地域住民の防犯に関する具体的なニーズに基づき,地域住民の主体性を前提とした民主的なプロセスを通して制定,展開されなければ,実効性を持ち得ない.そして,「生活安全条例」を機軸とした自主防犯活動には,住民自身による権力的な視点からの自己監視というリスクが潜んでいる.このようなリスクは,遍在性を有しており,またその存在に気づきにくいという意味で「リスク社会」に特徴的なものと考えられる.
2 0 0 0 OA 心理学化される現実と犯罪社会学
- 著者
- 土井 隆義
- 出版者
- 日本犯罪社会学会
- 雑誌
- 犯罪社会学研究 (ISSN:0386460X)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, pp.182-198, 2001 (Released:2017-03-30)
- 被引用文献数
- 1
2 0 0 0 OA 脳科学化する社会と少年観
- 著者
- 赤羽 由起夫
- 出版者
- 日本犯罪社会学会
- 雑誌
- 犯罪社会学研究 (ISSN:0386460X)
- 巻号頁・発行日
- vol.42, pp.19-32, 2017 (Released:2018-10-31)
本論文の目的は,脳科学と少年観の関係について,社会学的にどのように捉えたらよいかを考察す ることである. 現代の日本では,脳科学の知識や技術の広がりが,さまざまな影響を社会に及ぼしている.ここで は,脳科学の知識や技術が社会に普及し,影響を及ぼしていく過程を「社会の脳科学化」と呼ぶ.本 論文では,社会の脳科学化が脳科学と少年観の関係にもたらす影響について議論する.議論の結果は, 以下の5点にまとめられる. 第1に,脳科学と少年観の関係を捉えるためには,あらゆる脳科学の使用法を考慮する必要がある. 第2に,社会の脳科学化を促進する社会的文脈としては,新自由主義的な主体像の浸透が有力な仮説 の1つである.第3に,少年に対する処罰と教育の関係については,なにが社会化すべき能力とみな され,どのくらいその能力の発達可能性があるとみなされているのかを見る必要がある.第4に,少 年に対する治療と教育の関係については,なにが逸脱とみなされ,どのように脳科学の知見が使用さ れるのかを見る必要がある.第5に,少年に対する事前統制と事後統制の関係については,それらの 重点の変化を見る必要がある.
- 著者
- 野田 陽子
- 出版者
- 日本犯罪社会学会
- 雑誌
- 犯罪社会学研究 (ISSN:0386460X)
- 巻号頁・発行日
- vol.27, pp.133-135, 2002-10-26 (Released:2017-03-30)
2 0 0 0 高齢犯罪者対策と法的対応のあり方
- 著者
- 星 周一郎
- 出版者
- 日本犯罪社会学会
- 雑誌
- 犯罪社会学研究 (ISSN:0386460X)
- 巻号頁・発行日
- vol.43, pp.57-70, 2018
<p>未曾有の高齢社会化に伴い,高齢犯罪者に関わる犯罪現象が変化するとともに,その対応のあり方についても新たな検討が求められる.増加の著しい高齢者万引きに関しては,その多くが比較的軽微な事案であるため,刑事司法制度が予定する犯罪者処遇がほとんどなされない一方,その犯行動機,犯行原因に対応する形で,医療,福祉との間での有機的な連携の必要性がある.しかしながら,それ以上に当該行為の未然防止が重要である.そのためには,生体認証システム付防犯カメラシステムの利用や問題を抱えた高齢者の情報などの個人情報の取扱いについて,社会一般の理解を踏まえた上で,プライバシー保護とのバランスを図った枠組みの整備が求められる.他方で,近年になって社会の耳目を集めることの多い「介護疲れ殺人」については,裁判員裁判が開始されて以降,「懲役3年・執行猶予5年」という量刑が下されることが多くなっている.しかし,当該被告人の再犯可能性がほとんど認められない事案が多いことを考えると,執行猶予の期間量定の意義に関して理論的な再検討が求められると同時に,当該者の支援のあり方についても,従来の刑事司法の枠組みを超えた対応の必要がある.</p>
- 著者
- 水藤 昌彦
- 出版者
- 日本犯罪社会学会
- 雑誌
- 犯罪社会学研究 (ISSN:0386460X)
- 巻号頁・発行日
- vol.41, pp.47-61, 2016 (Released:2017-10-31)
- 被引用文献数
- 1
本稿の目的は,2000年代半ばから開始され,現在も活発化を続けている刑事司法と福祉の連携によ る非行・犯罪をした人への対応を題材として,福祉機関の側からみたリスクとセキュリティ(安全の 保証策)に関する課題を検討することである.本稿では,まず刑事司法と福祉による連携の現状と特 徴を確認する.次に,このような刑事司法と福祉の連携が開始された契機,ならびに刑事司法と福祉 のそれぞれからみた連携の目的について検討する.続いて,福祉機関の認識するリスクとセキュリティ について考察する.刑事司法と連携する福祉機関によって認識されると考えられるリスクには,①支 援対象者による再犯のリスク,②支援者としての法的責任を問われるリスク,③他の支援機関との関 係が悪化したり,社会的評価が傷つくリスク,④福祉機関の他利用者,利用者家族との関係を悪化さ せるリスクの4つがあると考えられる.これらのリスクに対するセキュリティは,支援対象者の再犯 防止を過度に強調したり,サービスから排除したりすることにつながる可能性がある.福祉が刑事司 法に対して対等性・自立性を確保していくためには,自らの認識するリスクに対するセキュリティが 福祉の司法化という新たなリスクへつながる可能性をはらんだものである点について自覚することが 求められる.
- 著者
- 浜井 浩一
- 出版者
- 日本犯罪社会学会
- 雑誌
- 犯罪社会学研究 (ISSN:0386460X)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, pp.4-9, 2004-10-18 (Released:2017-03-30)
2 0 0 0 OA 日本の人口変動と犯罪 : 1950〜2000年(II 自由論文)
- 著者
- 松本 良夫
- 出版者
- 日本犯罪社会学会
- 雑誌
- 犯罪社会学研究 (ISSN:0386460X)
- 巻号頁・発行日
- no.31, pp.101-115, 2006-10-18
日本の人口事情は,少子・高齢化に向けて急速に変化している.本論文は20世紀後半期における日本人口の年齢構成と犯罪情勢との関連について検討したものである.6つの罪種(殺人,強盗,傷害,強姦,窃盗および詐欺)に関して,6つの年齢層(10代・20代・30代・40代・50代・60歳以上),6つの年次(1950,60,70,80,90,2000年)の(A)被検挙者出現率および(B)寄与度(Cスコア)が分析された.(A)各罪種の被検挙者出現率は,年齢軸・時代軸で構成された「社会変動地図」で表示した.(B)各年齢層の犯行寄与度(当該年齢層の被検挙者の構成比/当該年齢層の人口割合)は,折線グラフで表示した.以下の結果が得られた.1)1950・60年には,20代のCスコアは,ほとんどの罪種において高率であった.2)1970年以降,10代のCスコアが特に傷害,窃盗で上昇し,90年以降は強盗のCスコアも上昇した.3)近年,中・高年齢層のCスコアが,殺人,強盗,傷害および窃盗で,わずかながら上昇している.
2 0 0 0 OA 刑罰に関する社会心理学的考察(<特集>社会と刑罰)
- 著者
- 高橋 良彰
- 出版者
- 日本犯罪社会学会
- 雑誌
- 犯罪社会学研究 (ISSN:0386460X)
- 巻号頁・発行日
- vol.2, pp.21-39, 1977 (Released:2017-02-01)
2 0 0 0 OA 声かけなどの不審者遭遇情報と性犯罪の時空間的近接性の分析
- 著者
- 菊池 城治 雨宮 護 島田 貴仁 齊藤 知範 原田 豊
- 出版者
- 日本犯罪社会学会
- 雑誌
- 犯罪社会学研究 (ISSN:0386460X)
- 巻号頁・発行日
- no.34, pp.151-163, 2009-10-20
警察や一般市民の間で,声かけなどのいわゆる不審者遭遇情報は,より重篤な性犯罪などの前兆事案として捉えられているものの,実証的な研究はこれまでなされてきていない.本研究では,犯罪学における近接反復被害の分析手法を応用し,声かけなどの不審者遭遇情報とその後の性犯罪発生との時空間的近接性を検証する.A都道府県警察における3年間の不審者遭遇情報(1,396件)と屋外での性犯罪(599件)の認知データを地理情報システム(GIS)とシミュレーション手法を用いて時空間的に解析したところ,声かけなどの不審者遭遇情報と性犯罪は時間的にも空間的にも近接して発生していることが分かった.具体的には,声かけなどの不審者遭遇情報発生後,少なくとも1ヶ月にわたって発生地点から1kmの範囲において性犯罪の発生件数が有意に高いことが示された.この結果に基づいて,本研究の限界を踏まえつつ,実証データに基づく警察活動への考察を行う.
2 0 0 0 OA 「加害者の家族」としての自己との距離化とその社会的機序 体験の語り得なさに注目して
- 著者
- 高橋 康史
- 出版者
- 日本犯罪社会学会
- 雑誌
- 犯罪社会学研究 (ISSN:0386460X)
- 巻号頁・発行日
- vol.40, pp.100-114, 2015-10-30 (Released:2017-04-30)
本稿の目的は,犯罪者を家族にもつ人びとが,いかにして自己の体験を語るようになるのかを描き出し,彼/彼女らが実践するスティグマ対処の手段の1つとしての役割距離とそのメカニズムを明らかにすることである.したがって,犯罪者を家族にもつ人びとへの支援に関する研究と異なる視点から,彼/彼女らの経験に接近する.具体的には,これまでの研究で議論されていない犯罪者を家族にもつ人びとの体験の語り得なさを乗り越える過程を捉えることを目指し,彼/彼女らの語りを事例として役割距離の観点から検討した.その結果,彼/彼女らは,加害者の家族として自己を振る舞えるようになるというスティグマの受容を経ることで,沈黙の状態から脱却していたことが明らかになった.彼/彼女らは,異質な他者や同じ属性をもたない他者との同質性の発見や,同じ属性をもたない他者との関係性を通じた自己の内にある普通さの想起によって,加害者の家族としての自己との距離化を実践し,スティグマが自己の役割の一部でしかないことを自覚していた.以上のことから,彼/彼女らの「回復」において,同じ属性をもたない他者との出会いや相互作用が重要な意味をもつことがわかる.
2 0 0 0 OA 声かけなどの不審者遭遇情報と性犯罪の時空間的近接性の分析
- 著者
- 菊池 城治 雨宮 護 島田 貴仁 齊藤 知範 原田 豊
- 出版者
- 日本犯罪社会学会
- 雑誌
- 犯罪社会学研究 (ISSN:0386460X)
- 巻号頁・発行日
- vol.34, pp.151-163, 2009-10-20 (Released:2017-03-30)
警察や一般市民の間で,声かけなどのいわゆる不審者遭遇情報は,より重篤な性犯罪などの前兆事案として捉えられているものの,実証的な研究はこれまでなされてきていない.本研究では,犯罪学における近接反復被害の分析手法を応用し,声かけなどの不審者遭遇情報とその後の性犯罪発生との時空間的近接性を検証する.A都道府県警察における3年間の不審者遭遇情報(1,396件)と屋外での性犯罪(599件)の認知データを地理情報システム(GIS)とシミュレーション手法を用いて時空間的に解析したところ,声かけなどの不審者遭遇情報と性犯罪は時間的にも空間的にも近接して発生していることが分かった.具体的には,声かけなどの不審者遭遇情報発生後,少なくとも1ヶ月にわたって発生地点から1kmの範囲において性犯罪の発生件数が有意に高いことが示された.この結果に基づいて,本研究の限界を踏まえつつ,実証データに基づく警察活動への考察を行う.
- 著者
- 宮澤 節生
- 出版者
- 日本犯罪社会学会
- 雑誌
- 犯罪社会学研究 (ISSN:0386460X)
- 巻号頁・発行日
- vol.38, pp.7-35, 2013-10-15 (Released:2017-03-31)
- 被引用文献数
- 1
本稿の課題は,2003年以後のデータによって,(1)いくつかの外国について犯罪発生率と厳罰化の動向を検討し,(2)外国の研究者が2003年以後の日本の状況をどのように理解しているかを検討し,さらに(3)日本の刑事政策の近年の状況を私なりに検討することにある.(1)については,(1)主要犯罪全体についても,殺人事犯についても,フランス,ドイツ,イギリス,アメリカという主要先進国において発生率が共通に低下していること,(2)犯罪発生率低下の要因はアメリカについて最もよく検討されており,「警察力の増強」と「厳罰化による刑務所人口の増加」が主要原因として指摘されているが,カナダなど犯罪発生率が安定的に低い国々にはそのような要因が存在しないので,明確な結論は得られていないこと,(3)厳罰化政策がとられた国々では政策転換をめざす運動が展開されているが,その影響はまだ見られないことなどを明らかにした.(2)については,2000年以前の日本は犯罪発生率が例外的に低い先進国として関心を集めていたが,その後の発生率の増減に対しては研究関心が見られず,存在するのは,近年の厳罰化をポピュリズム刑事政策として理解する立場に対する批判であることを示し,それに対して反批判を行った.(3)については,新聞論調,犯罪被害者団体の活動,立法・法改正,死刑判決・死刑執行などの状況を検討して,いまなおポピュリズム刑事政策と性格付けうることを主張し,ありうる批判に対して反批判を試みた.
2 0 0 0 OA 「症候群」としての児童虐待と「代理人によるミュンヒハウゼン症候群」
- 著者
- 南部 さおり
- 出版者
- 日本犯罪社会学会
- 雑誌
- 犯罪社会学研究 (ISSN:0386460X)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, pp.96-111, 2004-10-18 (Released:2017-03-30)
「代理人によるミュンヒハウゼン症候群」(MSBP)は,「(1)親あるいは親代わりの人物によって偽装された児童の疾患,(2)その児童は医学的検査や治療に差し出され,それは通常,絶え間なく,しばしば複合的な医療手続をもたらしている,(3)その加害者は自分が子どもの病気の原因であることを否認する,(4)子どもが加害者から分離されると,急性症状や病気のサインは消失する」の4つの基準を満たす用語として広く一般的に用いられている医学的概念である(Meadow 1995).しかし,提唱者であるメードゥ自身が認めるように,この基準は特異性に欠け,医師やソーシャル・ワーカー,司法関係者たちに混乱を生み出した.本稿は,医学的「症候群」としてのMSBP概念の特性と意義,同証拠が事実認定に与える影響を考察し,MSBPの概念がいかなる意義を持つべきかを明らかにする.MSBP概念は,発見が困難な虐待を発見するためのツールとして用いられることに最大の意義が存する.刑事事実認定においてMSBP証拠は,不可解に見える現象に対する医学的アプローチとして参照可能であるが,それはあくまでも「症候群」証拠にすぎず,その性質上,犯罪事実の認定に際しての「決定的証拠」とはなし難いものである.