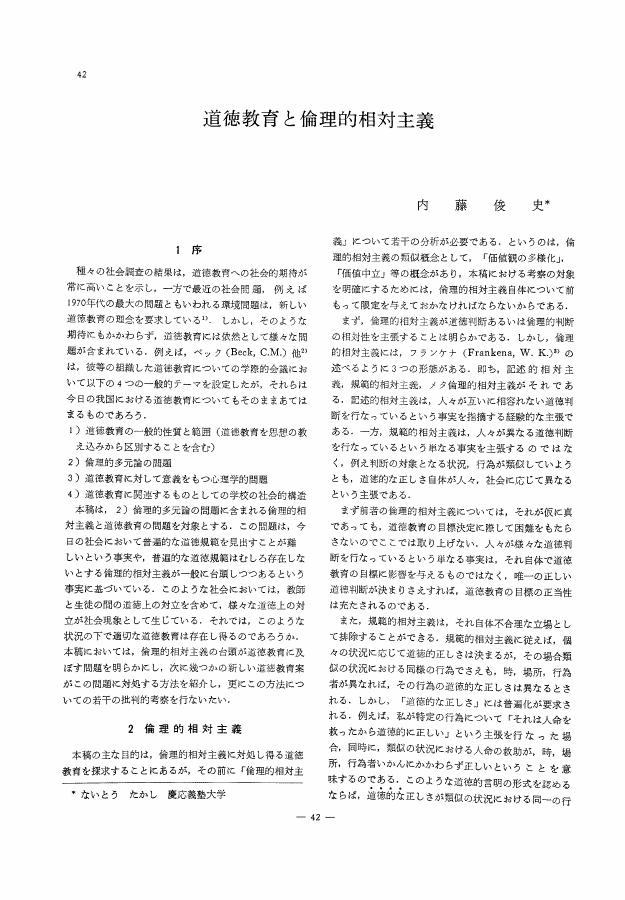- 著者
- 平井 悠介
- 出版者
- 一般社団法人日本教育学会
- 雑誌
- 教育学研究 (ISSN:03873161)
- 巻号頁・発行日
- vol.74, no.4, pp.530-541, 2007-12
1990年代のアメリカ合衆国において、リベラル派の政治哲学者の間でシティズンシップ概念が注目を集めている。本稿の目的は、市民のアイデンティティや行為のあり方に焦点を当てる90年代のシティズンシップ論および市民教育論の展開の意義を、リベラル派の市民教育理論における「討議的転回」との関連のもと探究することである。探究に際し、本稿では討議的転回後のリベラル派の市民教育理論にみられる二つの立場からの議論(<討議を民主主義的意思決定の手段とみなす議論>と<討議を市民教育の手段とみなす議論>)の分析を行う。前者の立場のマセードおよびゴールストンの議論と、後者の立場のカランとガットマンの議論とを対比し、後者の議論で重視されている、批判的かつ自律的に思考する能力の育成と相互尊重という市民的徳の涵養が、人々のアイデンティティの多様性を尊重する国家的統合にとって必要とされることを示していく。
1 0 0 0 OA 北東ユーラシア・北太平洋諸国の大学改革 : 国際性と地域性の視点から
- 著者
- 竹田 正直 所 伸一 シャリーモフ ピョートル ウィルソン ケビン ボンダレンコ オリガ
- 出版者
- 一般社団法人日本教育学会
- 雑誌
- 教育學研究 (ISSN:03873161)
- 巻号頁・発行日
- vol.66, no.1, pp.86-87, 1999-03-30
1 0 0 0 関東農村における寺子屋の一性格とその歴史的背景
- 著者
- 利根 啓三郎
- 出版者
- 日本教育学会
- 雑誌
- 教育学研究 (ISSN:03873161)
- 巻号頁・発行日
- vol.40, no.3, pp.43-53, 1973-09
1 0 0 0 寛政期寺子屋の1事例研究--伊勢国「寿硯堂」を中心にして
- 著者
- 梅村 佳代
- 出版者
- 日本教育学会
- 雑誌
- 教育学研究 (ISSN:03873161)
- 巻号頁・発行日
- vol.53, no.2, pp.p151-160, 1986-06
1 0 0 0 OA カベルによるエマソンの再解釈 : 道徳的完成主義にみられる教育の哲学
- 著者
- 齋藤 直子
- 出版者
- 一般社団法人日本教育学会
- 雑誌
- 教育學研究 (ISSN:03873161)
- 巻号頁・発行日
- vol.68, no.3, pp.296-305, 2001-09-30
1 0 0 0 OA 地方分権の推進と公教育概念の変容
- 著者
- 大桃 敏行
- 出版者
- 一般社団法人日本教育学会
- 雑誌
- 教育學研究 (ISSN:03873161)
- 巻号頁・発行日
- vol.67, no.3, pp.291-301, 2000-09-30
地方分権の推進が今日の大きな改革課題の一つになっている。小論の目的は行政の地方分権化と公教育概念の変容について次の三つの視点から考察することにある。第一は、今次の地方分権に向けた改革が中央から地方への権限の移動だけでなく、行政のあり方の変革を迫っていることである。現代国家において、行政は立法府の政策を忠実に実施するだけの機関ではない。むしろ、政策形成において重要な役割を担うとともに、その執行においては広範な裁量権を有している。このことは行政自体が政策のための価値の選択・序列化に深く関わっていることを意味し、今次の改革は地方段階における行政のより開かれた制度の設立を求めるものである。このことは官僚制の緩衝装置の弱体化をもたらし、親や住民への説明責任、彼(女)らへの応答責任を高めることを教職に求めることになろう。第二は、地方分権が規制緩和や公共サービスの民営化といった政府機能の縮小に向けた潮流と密接に関わって進められていることである。教育の領域において、規制緩和や民営化はまず生涯学習において進められ、次に学校教育にも導入されてきた。このような変革は、主に国家に依拠した公教育概念から、国家、私企業、ボランティア団体など多様なセクターが教育機会の供給に関わる「公教育」概念への変容をもたらすことになろう。この地方分権化と政府機能の縮小という二つの大きな改革潮流が交差するとき、公共セクターが教育においてどのような役割をどの程度までどのように担うべきかを決定する重い責任が、各自治体の住民の手に置かれることになる。第三は、教育の地方分権化を進めていくうえで独自の課題が存在することである。行財政機構の地方分権化が多様性をもたらすことは明らかであるが、別言すれば、それは自治体間の公共サービスの不平等を意味する。この「多様性」を正当化する一つの論拠が、意思決定を行うものがその結果に責任を負うべきであるという自治論である。しかし、教育の場合、公共サービスの意思決定者(大人)とその受給者(子ども)が異なるために、これは妥当な原理とはならない。さらに、大人の間での参加民主主義の実現と将来の民主的シチズンシップの育成とは同義でない。学校の主要な目的が将来の市民の育成にあるのなら、地方分権化自体は教育改革の目的にはなり得ない。地方レベルでの参加型の意思決定システムに向けた改革が学びの場の変革に実際にいかなる影響を持ちうるのかが問われなければならない。この点の考察を欠いた参加賛美論は危うい。歴史的に見れば、教育行政の専門化と等しい教育機会の保障のための国家関与は、参加と自助の地方自治の制限に依拠して求められた。
- 著者
- 上地 完治
- 出版者
- 一般社団法人 日本教育学会
- 雑誌
- 教育学研究 (ISSN:03873161)
- 巻号頁・発行日
- vol.77, no.4, pp.387-389, 2010
1 0 0 0 OA 野村芳兵衛の一人称の語りとその変容 : 実践記録の記述を中心に
- 著者
- 浅井 幸子
- 出版者
- 一般社団法人日本教育学会
- 雑誌
- 教育學研究 (ISSN:03873161)
- 巻号頁・発行日
- vol.66, no.2, pp.183-192, 1999-06-30
本論文は、大正期に「新教育」の実験学校として設立された池袋児童の村小学校における野村芳兵衛の教育の展開の過程を、彼の一人称の語りの様式の変容に着目して叙述することを目的としている。野村の試みの特徴は、教育の意味と関係の変革が、彼の教師としてのアイデンティティの解体と再編を通して行われ、「私」という一人称を主語とする語りにおいて鮮明に表現された点にある。彼は、明治時代に確立した「教育」と「教師」の役割に懐疑を抱き、ラディカルに「自由」を提唱し「教育」の制度と秩序の破壊を企図した「池袋児童の村」の教師となっている。その際、彼の中心課題として表現され、彼の探究の出発点となっていたのは、「教育」でも「児童」でもなく、「私」の救済と模索であった。野村の教育の展開過程を、彼の一人称の語り、とりわけ実践記録の叙述に着目して叙述することを通し、本論文では以下3点を指摘している。第一に、1924-25年頃に成立した野村自身を「私」、子どもを固有名またはイニシャルで表記する物語的な記述の様式に、「教師-児童」の役割的な関係に対して「私-あなた」の関係と呼びうる野村と子どもとの関係が現出していること。野村が最初に子どもを名前で表記した際、そこでは教師が子どもを見る、教師が子どもに問うという教育において一般的な視線と言語の関係が逆転し無効化していた。彼は教育を語る言葉を一旦喪失するが、その後「私」と固有名の子どもが登場する実践記録の記述を通し、子どもとの「私-あなた」の関係において教師としてのアイデンティティを再構築している。また同時に教育を、目的に向かう活動としてではなく、その具体的な関係において既に成立し,でいる一回性を持つ実践として見い出していた。第二に、野村が1925-26年頃に構想したカリキュラムが、子どもの学習経験の意味と関係を重層的に表現し構成していたこと。彼は、教師と子ども、子どもと子どもの固有の関係を、それぞれの「個」の世界の鑑賞として表現し、学習の社会的な意味を構成している。そしてもう一方では、とりわけ「教科目」の再編において、子どもの経験を学問あるいは芸術の活動として意味づけていた。彼のカリキュラムは、制度的な教育の計画というよりも、学習経験の関係と意味のネットワークとして成立している。第三に、1930年以降に再構成された野村のカリキュラムが、「協働自治」を一元的な原理とすることによって、学校を組織化し教育の関係を「協働」へと定型化していたこと。カリキュラムの変化に先立って、野村の使用する一人称は「私」から「吾々」へと変化し、彼の子どもとの経験の叙述が激減している。彼は「社会」へと眼を向けた一方、彼自身と子どもの固有性への視線を衰退させていた。その結果、「池袋児童の村」は、「ハウスシステム」と呼ばれる子どもの班組織、校歌、校旗等の導入を通して、機能的かつ象徴的な組織へと再編されている。
1 0 0 0 OA ハンス・リヒャートとプロイセン中等学校改革
- 著者
- 小峰 総一郎
- 出版者
- 一般社団法人 日本教育学会
- 雑誌
- 教育学研究 (ISSN:03873161)
- 巻号頁・発行日
- vol.63, no.4, pp.404-413, 1996-12-30 (Released:2009-01-13)
- 参考文献数
- 84
- 著者
- 新谷 周平
- 出版者
- 一般社団法人日本教育学会
- 雑誌
- 教育學研究 (ISSN:03873161)
- 巻号頁・発行日
- vol.73, no.4, pp.470-481, 2006-12-29
本稿の目的は、フリーター・ニートの批判言説および選択の意味解釈を通じて、教育学研究、政策・実践の課題を明らかにすることにある。ニート批判は、社会の不安を抑え込む差異化欲求の表れと解釈することができるが、それを根底から変革するよりは、政策・実践へと転換されるプロセスに影響を与えることの方が現実的でありまた必要である。ニート選択は、確かに客観的には構造要因の影響が大きいが、消費文化への接触や労働の拒否を通じた社会への抵抗という実存レベルの解釈が可能であり、その先に道具的・経済的利益に接続する方策が求められる。キャリア教育政策や機会平等論から導かれる政策は、計画性や上昇移動を基準とする単一の生き方・働き方のモデルを設定するが、それは過剰な同化とあきらめを介した格差拡大を生じさせる可能性が高い。それとは異なる生き方・働き方のモデルを設定し、そのために必要なスキル・認識枠組みを政策・実践に取り入れる必要がある。
- 著者
- 坂本 辰朗
- 出版者
- 一般社団法人日本教育学会
- 雑誌
- 教育學研究 (ISSN:03873161)
- 巻号頁・発行日
- vol.75, no.3, pp.311-312, 2008-09-30
- 著者
- 金井 香里
- 出版者
- 一般社団法人日本教育学会
- 雑誌
- 教育學研究 (ISSN:03873161)
- 巻号頁・発行日
- vol.68, no.2, pp.181-191, 2001-06-30
1 0 0 0 教育におけるケアリング
- 著者
- 渋谷 真樹
- 出版者
- 一般社団法人日本教育学会
- 雑誌
- 教育学研究 (ISSN:03873161)
- 巻号頁・発行日
- vol.74, no.3, pp.372-374, 2007-09
- 著者
- 中村 夕衣
- 出版者
- 一般社団法人日本教育学会
- 雑誌
- 教育学研究 (ISSN:03873161)
- 巻号頁・発行日
- vol.75, no.1, pp.1-12[含 英語文要旨], 2008-03
本稿では、『アメリカン・マインドの閉塞』の著者として知られるアラン・ブルームの大学論について考察する。これまでブルームの大学論は、保守主義の立場から展開される西欧中心主義的な議論、あるいは過去の大学文化を取り戻そうとする懐古主義的な議論と見なされ、批判されることが多かった。本稿では、そうした諸批判を検討しつつ、ブルームの大学論がポストモダンを経た現在でも意義深いものであることを明らかにする。彼の描く大学の歴史は、中世に起源をもつとされる通説とは異なり、近代、とくに啓蒙主義以降の「哲学」との関連で展開されている。近代に誕生した「大学」は、啓蒙主義の企ての限界が露呈するなかで解体を余儀なくされた。啓蒙主義の限界がどこにあり、またその後の大学はどのような歩みを経て現代に辿り着いたのか。独自の哲学史観のうえで展開されるブルームの大学論を読み解き、「哲学の場としての大学」の可能性を模索する。
- 著者
- 今井 康雄
- 出版者
- 一般社団法人日本教育学会
- 雑誌
- 教育學研究 (ISSN:03873161)
- 巻号頁・発行日
- vol.73, no.2, pp.98-109, 2006-06-30
ウィトゲンシュタインの後期哲学は、反表象主義の主要な典拠となっており、教育学においても、「情報化」の要請に対応した、「力」を重視する現代的な教育論の傾向にそって解釈がなされている。これに対して本稿が試みるのは、ウィトゲンシュタインの後期哲学を、「力」を重視する教育論の基盤を掘り崩すような哲学として解釈することである。ウィトゲンシュタインは、反表象主義の立場を徹底することによって、一方で教えることの不確実性を明らかにするとともに、他方では、この不確実性を回避するために教育論が通常子供の心のなかに想定している「力」の観念を解体する。その結果、教育は極めて脆弱な営みとして現れることになる。ウィトゲンシュタインは、その小学校教師時代、こうした教育の脆弱さに実際に直面していたと推測できる。しかし『哲学探究』のなかには、教育の脆弱さを克服する可能性が、理解されていないものを理解可能なものにおいて示すという「事例」のメディア的構造として示唆されてもいるのである。
1 0 0 0 OA 多文化教育における教師の役割
- 著者
- 矢野 泉
- 出版者
- 一般社団法人 日本教育学会
- 雑誌
- 教育学研究 (ISSN:03873161)
- 巻号頁・発行日
- vol.61, no.3, pp.262-270, 1994-09-30 (Released:2009-01-13)
- 参考文献数
- 32
1 0 0 0 OA 道徳教育と倫理的相対主義
- 著者
- 内藤 俊史
- 出版者
- 一般社団法人 日本教育学会
- 雑誌
- 教育学研究 (ISSN:03873161)
- 巻号頁・発行日
- vol.46, no.1, pp.42-52, 1979-03-30 (Released:2009-01-13)
- 参考文献数
- 25
1 0 0 0 OA 郷土文化と教育
- 著者
- 務臺 理作
- 出版者
- 一般社団法人 日本教育学会
- 雑誌
- 教育学研究 (ISSN:03873161)
- 巻号頁・発行日
- vol.7, no.10, pp.1066-1088, 1939 (Released:2009-01-13)
1 0 0 0 OA ジョホノットの教育学と東京師範学校の1879年改革-教員養成教育課程の分析と考察-
- 著者
- 水原 克敏
- 出版者
- 一般社団法人 日本教育学会
- 雑誌
- 教育学研究 (ISSN:03873161)
- 巻号頁・発行日
- vol.48, no.2, pp.154-164, 1981-06-30 (Released:2009-01-13)
- 参考文献数
- 71