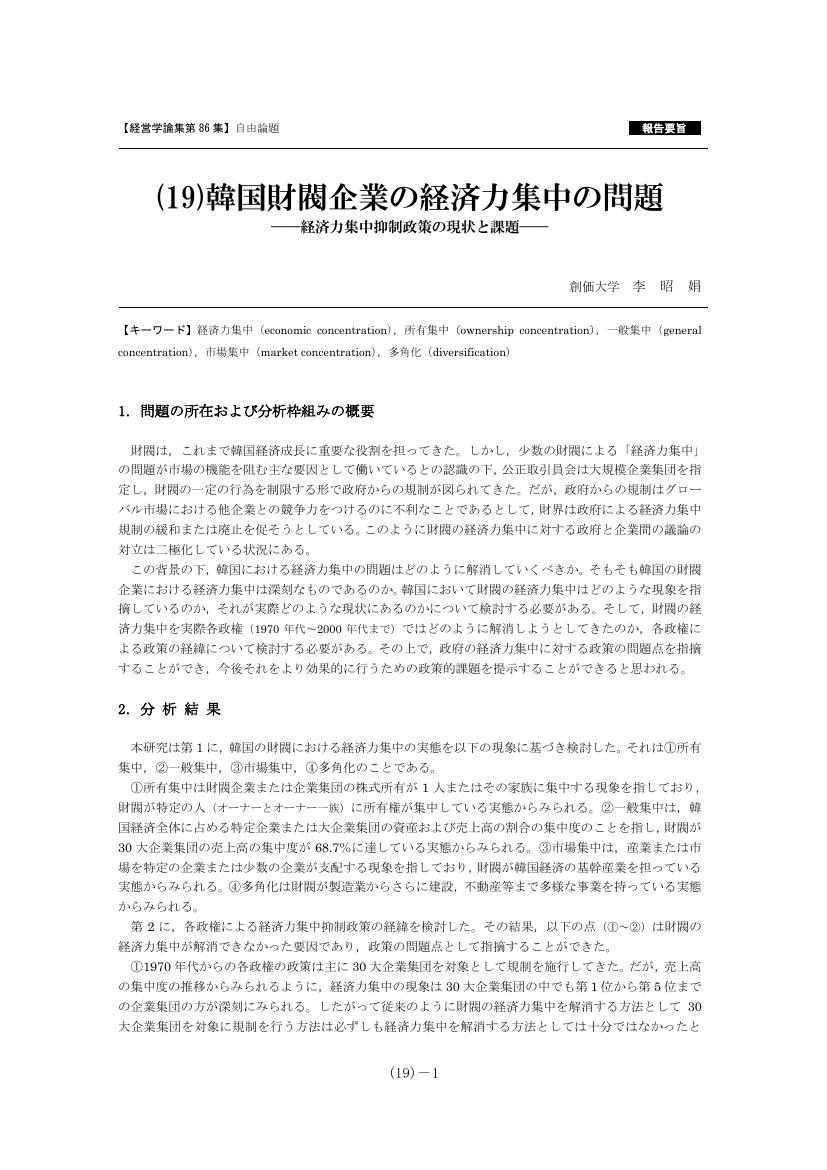38 0 0 0 OA 株式会社の歴史・理論・課題
- 著者
- 勝部 伸夫
- 出版者
- 日本経営学会
- 雑誌
- 經營學論集 第86集 株式会社の本質を問う-21世紀の企業像 (ISSN:24322237)
- 巻号頁・発行日
- pp.14-21, 2016 (Released:2017-03-23)
株式会社は資本集中という機能をフルに発揮して巨大化し,今や社会に不可欠な制度となった。では専門経営者に率いられた巨大株式会社は誰のために,どのように動かされるのか。また大企業はどのようにチェックされるのか。これはコーポレート・ガバナンスの問題であるが,それは実際には,経営者資本主義から株主資本主義への転換を推進するものとして登場した。すなわち資本主義の危機が進行する中,グローバリゼーションの進展と新自由主義思想の台頭を背景として,株主利益の最優先が声高に叫ばれ,国もそれを法制度改革等の面からサポートする流れが加速した。しかし,会社は株主のものだ,と言って済ますことはできない。株主の責任,株式会社の責任が問われる事態が進行しており,改めて株式会社とは何であり,その本質はどこにあるかを根本から問い直す必要が出てきていると言えよう。
4 0 0 0 OA (01)中国の大企業における主要株主の変化と国有資産管理の現状
- 著者
- 西村 晋
- 出版者
- 日本経営学会
- 雑誌
- 經營學論集 第89集 日本的経営の現在─日本的経営の何を残し,何を変えるか─ (ISSN:24322237)
- 巻号頁・発行日
- pp.F1-1-F1-8, 2019 (Released:2019-09-26)
中国の上場企業の株式所有構造の最大の特徴は,筆頭株主の株式所有比率が非常に高い傾向がみられる事である。特に,大企業では国有持株会社を介して政府に迂回所有されているケースが典型的である。政府が上場企業を迂回所有する仕組みは国有資産管理制度の中心的な仕組みの一つである。国有企業に対して民間や外資の持株比率を高め,国有持株会社の持株比率を低下させる改革である混合所有制改革が,2013年に決定され,2018年現在も改革の途上にある。改革の進展度合いにはかなりのバラつきがある。中央レベルの国有企業を見てみると,宝山鋼鉄やシノペックなどの重工業系の巨大企業では,未上場子会社に対して複数の民間投資家から出資を招く程度の改革にとどまっている。国有持株会社の支配権を維持しつつ複数の提携相手の民間企業に株式を分散できたケースとしては,チャイナユニコムを挙げることができる。しかしながら,今回の改革で,支配株主と中小株主との利害の対立という中国企業のガバナンスの基本的な構図が変化する訳ではない。
4 0 0 0 OA (14)ウォール街の現在 ──ダークプールによる超頻度取引(HFT)の問題点──
- 著者
- 矢澤 健太郎
- 出版者
- 日本経営学会
- 雑誌
- 經營學論集 第87集 日本の経営学90年の内省と構想【日本経営学会90周年記念特集】 (ISSN:24322237)
- 巻号頁・発行日
- pp.F14-1-F14-8, 2017 (Released:2019-09-26)
本稿は,ニューヨークにある世界一の金融街である「ウォール街(ウォール・ストリート)の現在」を問題として,パターン認識の技術を駆使したクオンツたちのステルス・モデルを,筆者自身の問題としていかに応用し,博士号を取得しても研究職に従事しない「ポスドク問題」に対する筆者自身の考えを述べたものである。 2010年のフラッシュ・クラッシュはクオンツ危機とも呼ばれ,アルゴリズムの異常検知によって危機が生じた。クオンツのモデルは極秘情報として一切公表されないが,極秘であったはずにも関わらず多数のモデルが同時連続的にクラッシュを起こしたという2010年の出来事から,いかなる問題と教訓を読み解くか。筆者は,クオンツ・モデルで駆使されたパターン認識の技術を推測・熟考し,この発展的応用が新しいビジネス創造を生み出すと考え,それは実験室や研究室の垣根を跳び越えた「ポスドク問題」への解決にもつながると思い,筆者自身の考えを述べた。
3 0 0 0 OA 経済の金融化とファンドによる企業支配
- 著者
- 三和 裕美子
- 出版者
- 日本経営学会
- 雑誌
- 經營學論集 第86集 株式会社の本質を問う-21世紀の企業像 (ISSN:24322237)
- 巻号頁・発行日
- pp.86-95, 2016 (Released:2017-03-23)
現代資本主義においては,経済活動を通して生み出された富は,生産手段に投下されるよりも,金融市場に向かい,国債,株式,デリバティブ市場の急速な取引技術の革新によって,さらに取引残高が増加する。この結果,大規模な資金を運用する年金基金,投資信託などの機関投資家,富裕層の資産運用を主に行うヘッジファンドなどの行動が金融市場や企業に及ぼす影響が大きくなり,「もの言う株主」などとして注目を集めるようになった。また,今日企業を支配するファンドも出現し,取引先に対する関係保持や新規市場開拓,技術革新,労使関係等に無関心,あるいはそれらを軽視し,ときには法令遵守にも留意しないという最低限のコーポレート・ガバナンスさえ機能しない状況を生み出している。現代社会におけるファンドの影響力は投資先企業にとどまらず,企業支配や国家にまで及んでいる。本稿では,経済の金融化との関連でファンドの企業支配の実態と問題点を明らかにし,現代株式会社への影響を考える。
2 0 0 0 OA 経営学の学問性を問う ──研究対象の多様化から考える──
- 著者
- 澤野 雅彦
- 出版者
- 日本経営学会
- 雑誌
- 經營學論集 第84集 経営学の学問性を問う (ISSN:24322237)
- 巻号頁・発行日
- pp.22-29, 2014 (Released:2019-09-27)
かつて経営学は,メーカーを中心に研究を展開してきたが,近年,産業構造の転換に対応して研究対象を次々多様化し,さまざまな議論を行うようになってきている。もともと,経済学のようにディシプリンが明確な学問ではないだけに,その分,学問性が怪しくなってきているのも確かである。本研究では,経営学成立の経緯を考えることで,経営学の性質を検討して,「コンビナートモデル」と「自動車モデル」の2つの経営学を抽出したが,いずれも,直傭制が成立する20世紀型システムに適合的であることが明らかである。ところが,21世紀に入る頃から,産業構造の転換により,派遣・請負つまり,間接雇用が増えはじめ,経営学が成立する基盤そのものが揺らいでいる。そのため,脱構築なくしては経営学の学問性は疑わしいものとなるであろう。
2 0 0 0 OA (1)経営と芸術:ピーター・ドラッカー理論の根源を求め
- 著者
- 村山 元英
- 出版者
- 日本経営学会
- 雑誌
- 經營學論集 第83集 新しい資本主義と企業経営 (ISSN:24322237)
- 巻号頁・発行日
- pp.F1-1-F1-6, 2013 (Released:2019-09-26)
2 0 0 0 OA (19)韓国財閥企業の経済力集中の問題 ──経済力集中抑制政策の現状と課題──
- 著者
- 李 昭娟
- 出版者
- 日本経営学会
- 雑誌
- 經營學論集 第86集 株式会社の本質を問う-21世紀の企業像 (ISSN:24322237)
- 巻号頁・発行日
- pp.F19-1-F19-2, 2016 (Released:2019-10-01)
- 著者
- 松尾 健治
- 出版者
- 日本経営学会
- 雑誌
- 經營學論集 第89集 日本的経営の現在─日本的経営の何を残し,何を変えるか─ (ISSN:24322237)
- 巻号頁・発行日
- pp.F45-1-F45-8, 2019 (Released:2019-09-26)
本研究の目的は,「レトリカル・ヒストリー(rhetorical history)」についての近年の研究蓄積の状況を検討したうえで,意図せざる結果や失敗のメカニズムといった論点が従来見過ごされてきたことを示し,今後の研究に向けた展望を提示することである。レトリカル・ヒストリーは「企業の重要なステークホルダーを管理するための説得戦略として過去を戦略的に用いること」と定義され,正当性の確保,あるいは組織アイデンティティや組織のレピュテーションの管理といった目的で実践される。しかしながら既存研究では,意図せざる結果,とりわけ失敗に関する研究蓄積が欠けていた。その理由としては,当事者が協力を忌避しがちであることや,歴史を物語る際の聴き手の反作用についての考慮が不十分であるといったことが考えられる。本稿ではこうした問題意識に基づいたうえで,今後,意図せざる結果や失敗についての研究を蓄積していく上で必要な方法論に関する考察を行う。
2 0 0 0 OA (28)イノベーションによる生命倫理の変容プロセス
- 著者
- 尾田 基
- 出版者
- 日本経営学会
- 雑誌
- 經營學論集 第89集 日本的経営の現在─日本的経営の何を残し,何を変えるか─ (ISSN:24322237)
- 巻号頁・発行日
- pp.F28-1-F28-2, 2019 (Released:2019-09-26)
- 著者
- 福原 康司 間嶋 崇 堀野 賢一郎
- 出版者
- 日本経営学会
- 雑誌
- 經營學論集 第89集 日本的経営の現在─日本的経営の何を残し,何を変えるか─ (ISSN:24322237)
- 巻号頁・発行日
- pp.F15-1-F15-9, 2019 (Released:2019-09-26)
本稿は,専修大学が実施しているリーダーシップ開発に関するプログラム(専修リーダーシップ開発プログラム)の有効性と課題を定量的・定性的に検討することを目的とする。同プログラムは,リーダーシップ能力の養成を目指し,学部横断的に実施している課外プログラムである。同プログラムでは,その質の向上のため,学習転移の議論を意識し,実践文脈の提供やリフレクションの多様な促しなど試行錯誤を繰り返してきた。しかし,定量的な調査の結果,人間関係構築力の向上において効果が見られたものの,リフレクション能力の向上という点で本プログラムの脆弱性が判明した。さらに,定性的な調査を通じ,グループ・リフレクションの機会の適切な提供などがこの問題の解決の糸口になろうことが俄かに分かってきた。
2 0 0 0 OA (10)マネジメントの視点からのテレワークの分析
- 著者
- 安達 房子
- 出版者
- 日本経営学会
- 雑誌
- 經營學論集 第89集 日本的経営の現在─日本的経営の何を残し,何を変えるか─ (ISSN:24322237)
- 巻号頁・発行日
- pp.F10-1-F10-7, 2019 (Released:2019-09-26)
テレワークとは,パソコンに代表されるコンピュータとインターネットを使って,空間的・時間的な制約を克服した働き方である。テレワークには,在宅勤務,モバイル勤務,サテライトオフィスや自社オフィスなどを使った勤務形態などがある。本稿ではテレワークを,企業と雇用関係をもつ労働者の働き方という狭義の意味でとらえている。 このようなテレワークを組織マネジメントの視点から分析する視点として,本稿ではバーナード=サイモン理論を基礎にしつつ,その研究成果を受け継いできた情報処理アプローチを整理し,意味形成アプローチを展開している。本稿では,安達(2016)『ICTを活用した組織変革』を踏まえて,共通認識・共感・共有ビジョンと組織文化の関係について論及した。
2 0 0 0 OA 株式会社の本質
- 著者
- 中條 秀治
- 出版者
- 日本経営学会
- 雑誌
- 經營學論集 第86集 株式会社の本質を問う-21世紀の企業像 (ISSN:24322237)
- 巻号頁・発行日
- pp.29-36, 2016 (Released:2017-03-23)
本報告の論点の第1は,中世キリスト教に由来するcorpus mysticum(神秘体)という概念が株式会社の本質に深くかかわるという主張である。ここではカントロビッチの『王の二つの体』という著作で展開されるcorpus mysticumが社会制度に援用される歴史的展開を概観し,corpus mysticumという概念が教会から国家へと援用され,やがて各種の永続性を志向する団体に伝播する経緯を確認する。 第2の論点は,会社観には二つの流れが存在するという主張である。一つはcompany という用語で示される「共にパンを食べる仲間」としての「人的会社」の流れであり,もう一つはcorpus mysticumという人間以外の観念体を立ち上げるcorporationという用語で示される「物的会社」の流れである。 大塚久雄の『株式会社発生史』を批判的に検討すると,ソキエタス(societas)の中心人物に匿名的に投資する分散型コンメンダ(commenda)と「会社そのもの」に投資する集中型コンメンダの二つのパターンがあることは明白である。大塚はこの両者を共にマグナ・ソキエタス(magna societas)として同じものとして扱うが,この二つのマグナ・ソキエタスは性格の異なる会社観として捉えられるべきものである。この考えを推し進めれば複線型の株式会社発生史となる。つまり,一つはソキエタスの性格を残したcompanyへの流れであり,これは合名会社・合資会社につながる。他は「会社それ自体」がcorpus mysticum として法人化するcorporation,つまり株式会社への流れである。
2 0 0 0 行動科学的意思決定論の展開(新しい企業・経営像と経営学)
- 著者
- 松行 康夫
- 出版者
- 日本経営学会
- 雑誌
- 經營學論集 (ISSN:24322237)
- 巻号頁・発行日
- vol.63, pp.209-213, 1993
1 0 0 0 OA 【報告者】:イノベーションと企業不祥事 ──企業活動の光と影──
- 著者
- 谷口 勇仁
- 出版者
- 日本経営学会
- 雑誌
- 經營學論集 第79集 日本企業のイノベーション (ISSN:24322237)
- 巻号頁・発行日
- pp.119-131, 2009 (Released:2019-09-25)
1 0 0 0 OA 非営利組織としての病院経営の方向 ──医療制度,病院価値,BSC を手掛かりに──
- 著者
- 髙橋 淑郎
- 出版者
- 日本経営学会
- 雑誌
- 經營學論集 第88集 公共性と効率性のマネジメント─これからの経営学─ (ISSN:24322237)
- 巻号頁・発行日
- pp.6-15, 2018 (Released:2019-06-17)
- 被引用文献数
- 1
本稿は,わが国で非営利組織としての病院経営を,私的病院の経営を中心にして,これまでの先達の研究成果を踏まえ,わが国の医療制度の特徴を確認し,さらに先進諸国の医療における患者や医療サービス提供者の変化を明らかにした。その上で,医療における医療価値研究から病院価値研究への動きを把握し,現在および将来に向けて医療経営で,バランスト・スコアカード(BSC)およびその発展形であるSustainable BSC(SBSC)の有用性を論理的に示した。すなわち,SBSCは,持続可能性コンセプトの3つの次元すべてを,その戦略的重要度に応じて統合するBSCであることを示したことで,BSCからSBSCへの病院経営の方向を示した。これらの議論より,本稿で議論した病院価値を理解し把握した病院経営者が医師であれ,非医師であれ,払底している現状を確認し,戦略経営実践の枠組みが作れる,リーダーシップを持った人材の育成が急務であることを示した。
1 0 0 0 OA (02)2つの限定合理性
- 著者
- 米川 清
- 出版者
- 日本経営学会
- 雑誌
- 經營學論集 第86集 株式会社の本質を問う-21世紀の企業像 (ISSN:24322237)
- 巻号頁・発行日
- pp.F2-1-F2-8, 2016 (Released:2019-10-01)
サイモンとトゥベルスキー=カーネマンの「限定合理性」へのアプローチの決定的相違点を明らかにする。また,トゥベルスキー自身も,当初,合理的選択からのシステム的逸脱に対する新古典派的説明を,「見当外れの弁護人」と酷評した。歳月は流れ,トゥベルスキー=カーネマンは,やがて主流派の効用概念の補正の側に宗旨替えをする。完全合理的なはずの人間が犯すエラー研究が標準理論の修正へと向かった時,「限定合理性」の主張は,主流派の思弁的な領域に埋没した。現在,2つの「限定合理性」が存在するが,サイモンの側に立ち,トゥベルスキー=カーネマンの「限定合理性」に批判的検討を加える。
- 著者
- 風間 信隆
- 出版者
- 日本経営学会
- 雑誌
- 經營學論集 第86集 株式会社の本質を問う-21世紀の企業像 (ISSN:24322237)
- 巻号頁・発行日
- pp.F25-1-F25-9, 2016 (Released:2019-10-01)
ドイツでは「共同決定」制度の法制化により,利害多元的統治モデルが制度化されている。しかし,1990年代後半以降,EU統合とグローバル化の急速な展開,伝統的安定株主の「消滅」と外国人機関投資家の圧力,さらには「新自由主義」的思潮の下での「株主価値重視経営」の喧伝の下で,「協調型資本主義」の「終焉」とまで主張されてきた。同時に,この時期,ドイツ固有の企業統治システムを維持するドイツ企業も存在したが,なかでも欧州最大の自動車会社に躍進したフォルクスワーゲン社はポルシェ・ピエヒ一族の過半数所有という形で資本市場からの圧力を遮断し,「長期連帯主義」に依拠した伝統的企業統治を維持してきた。しかし,2015年9月に発覚したVWディーゼルエンジン排ガス規制不正スキャンダルは,巨額のリコール・損害賠償費用,ブランド価値の棄損等,大きな打撃を受けている。本稿は,まず特に2000年代以降のVWの多元的企業統治の経路依存的進化の具体的在り様をたどるとともに,このインサイダー型企業統治構造が有する,克服すべき課題も明らかにする。
1 0 0 0 OA 日本企業復活とダイナミック・ケイパビリティ
- 著者
- 菊澤 研宗
- 出版者
- 日本経営学会
- 雑誌
- 經營學論集 第87集 日本の経営学90年の内省と構想【日本経営学会90周年記念特集】 (ISSN:24322237)
- 巻号頁・発行日
- pp.42-49, 2017 (Released:2019-09-26)
かつて世界で輝いていた日本企業は,変化の速いグローバルな環境に適応できず,現在,凋落している。なぜか。これまでさまざまな原因が指摘されてきたが,本論文では,今日,多くの日本企業が誤った新古典派的な資本主義理論とオーディナリー・ケイパビリティにもとづく経営を展開している点に注目する。何よりも,日本企業復活にとって必要なのは,正しいシュムペーター流の資本主義理論とデイビット・ティースによって展開されているダイナミック・ケイパビリティにもとづく経営であることを説明する。
1 0 0 0 OA (23)制度の死角と意図せぬ不正 ──食品表示等問題の検証──
- 著者
- 水村 典弘
- 出版者
- 日本経営学会
- 雑誌
- 經營學論集 第85集 日本的ものづくり経営パラダイムを超えて (ISSN:24322237)
- 巻号頁・発行日
- pp.F23-1-F23-10, 2015 (Released:2019-09-25)
企業倫理の基盤となる制度の実効性を高めるためには,意図せぬ不正に走る人の心理現象と心理プロセスを分析して,倫理諸制度の基本設計や運用の一部に修正パッチを当てるか,さもなければ制度の全体を抜本的に見直す必要がある。では,なぜ人は無自覚的に不正を働き,時として悪事に手を染めるのか。現場で起きた「倫理の失敗」の数々を検証し,組織人の意図せぬ不正とその背後要因にスポットライトを当てて概括的な整理を試みたのが「行動ビジネス倫理」である。本稿は,ビジネス倫理学の領域で推奨される「倫理的な意思決定に向けたフレームワーク」とその脆弱性に焦点を当てた「行動ビジネス倫理」の分析視覚を明らかにしたうえで,2013年10月に株式会社阪急阪神ホテルズで発覚したメニュー表示問題の詳細について,関連省庁や「阪急阪神ホテルズにおけるメニュー表示の適正化に関する第三者委員会」が公表した調査報告書をもとに検証する。
1 0 0 0 OA 【報告書】:イノベーション研究の分析視角と課題
- 著者
- 軽部 大
- 出版者
- 日本経営学会
- 雑誌
- 經營學論集 第79集 日本企業のイノベーション (ISSN:24322237)
- 巻号頁・発行日
- pp.17-29, 2009 (Released:2019-09-25)