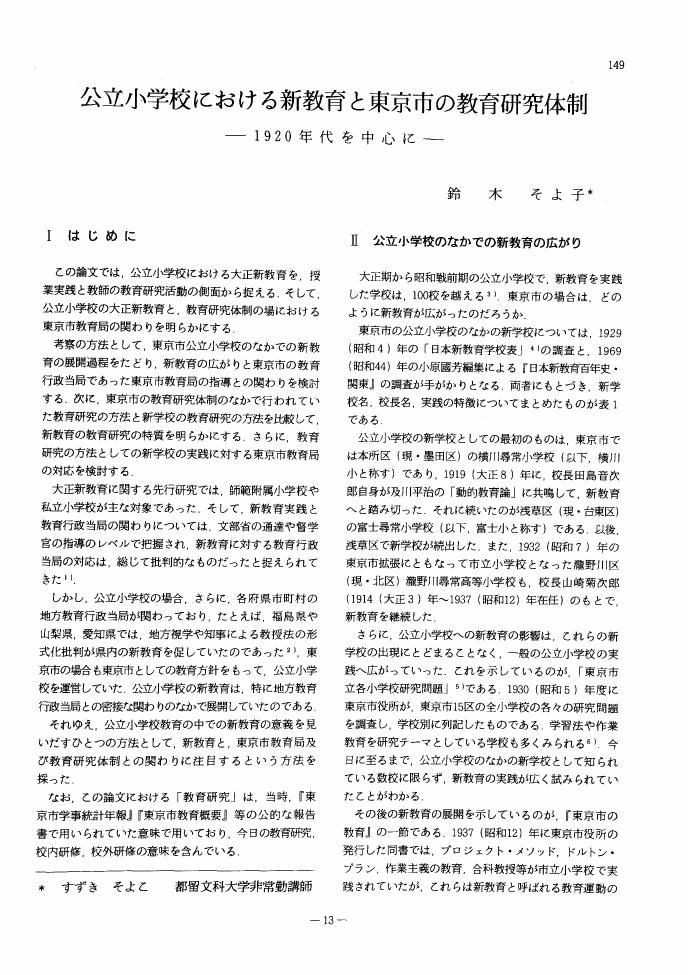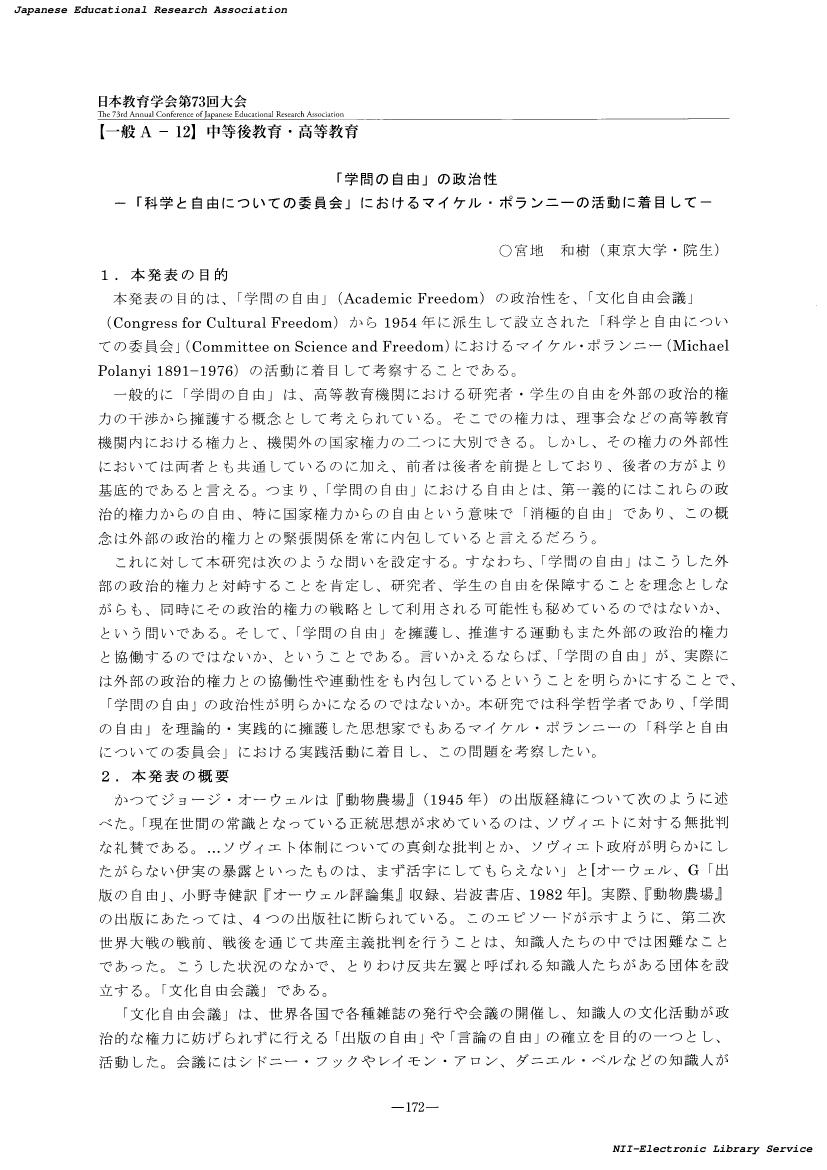1 0 0 0 子どもの人権と児童の権利条約問題
- 著者
- 喜多 明人
- 出版者
- 一般社団法人 日本教育学会
- 雑誌
- 日本教育学会大會研究発表要項
- 巻号頁・発行日
- vol.39, 1980
1 0 0 0 「学校準備」としての子育て
- 著者
- 前馬 優策 野﨑 友花 志田 未来 志水 宏吉
- 出版者
- 一般社団法人 日本教育学会
- 雑誌
- 日本教育学会大會研究発表要項
- 巻号頁・発行日
- vol.75, pp.360-361, 2017
- 著者
- 原 圭寛
- 出版者
- 一般社団法人 日本教育学会
- 雑誌
- 日本教育学会大會研究発表要項
- 巻号頁・発行日
- vol.73, pp.168-169, 2014
- 著者
- 緩利 誠 二井 紀美子
- 出版者
- 一般社団法人 日本教育学会
- 雑誌
- 日本教育学会大會研究発表要項 (ISSN:2433071X)
- 巻号頁・発行日
- vol.69, pp.390-391, 2010-08-13 (Released:2018-04-20)
1 0 0 0 OA テレビを利用した環境教育の推進に関する実証的研究・その1
- 著者
- 高橋 勉 山本 恒夫 清水 義昭 榊原 康男 石川 友一 本田 聆吉 須賀 昇
- 出版者
- 一般社団法人 日本教育学会
- 雑誌
- 日本教育学会大會研究発表要項 (ISSN:2433071X)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, pp.52-53, 1978-08-29 (Released:2018-04-20)
1 0 0 0 OA 公立小学校における新教育と東京市の教育研究体制1920年代を中心に
- 著者
- 鈴木 そよ子
- 出版者
- 一般社団法人 日本教育学会
- 雑誌
- 教育学研究 (ISSN:03873161)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, no.2, pp.149-158, 1990-06-30 (Released:2009-01-13)
- 参考文献数
- 36
1 0 0 0 OA 大学改革と教養教育 : 再創造と保障への視点 (<特集>教養の解体と再構築)
- 著者
- 寺崎 昌男
- 出版者
- 一般社団法人 日本教育学会
- 雑誌
- 教育学研究 (ISSN:03873161)
- 巻号頁・発行日
- vol.66, no.4, pp.386-394, 1999-12-30 (Released:2007-12-27)
教養教育のカリキュラムを開発・発展させることこそ、日本の大学が当面している最も緊張な課題である。筆者は、東京大学教育学部長、立教大学全学共通カリキュラム運営センター部長としての経験を踏まえ、学士課程教育における教養教育の創造とその維持に関する所見を記す。 1) 大学の学士課程教育の新しい教育目標を設定することが、重要である。日本の大学人と社会は、現代の人類が当面している課題ならびに将来の世界が当面する諸課題に対して洞察力と感受性を持つ、しかも専門学の教育を受けた若者を育てることを、大学教育の目標に選ぶべきである。学士課程教育の目標は「教養ある専門人の育成」にあるという伝統的理解は、変えられなければならない。すなわち、日本の大学は、リベラル・アーツ教育機関であると考えなければならない。 2) この目標を達成するためには、新しいカリキュラムを編成するべきである。そのカリキュラムは、第一に環境問題、第二に人権に関する理論、第三に生命に関する思想、第三に宇宙に関する知見である。半世紀前、アメリカから一般教育が輸入されてきた当時、これらの四つの知的分野は、若い世代に必要な教養とは考えられていなかった。しかし、現在、これら四つの知的分野は、現代世界の人類の課題を理解するのに不可欠の知的分野すなわち現代のリベラル・アーツを成すものと考えられる。 3) この数年間、日本各地の大学で教授法やカリキュラム構成について多くの改善・創造の努力が払われている。だが重要なことは、教養教育のカリキュラムを創造し運営するしっかりした、権限有る、永続的な組織が作られることである。そのような組織こそ、カリキュラムの永続的な改革、すなわち真の意味での大学改革に不可欠なものである。だが残念なことに、多くの国立大学は、硬直した内部組織に妨げられて、このような組織を作ることに失敗しているように思われる。 筆者は、かつて勤務していた立教大学の教養教育運営組織の例を紹介しつつ、教養教育を成功させる鍵は、大学の教育スタッフが意識変革をするか否かにかかっていると主張する。すなわち「自分は学部教授会に所属している、しかし全く同じ意味で教養教育に責任を持つ組織にも所属している」と考えることが大切であり、それこそが、大学改革に連なるカリキュラム改革に成功するための鍵である、というのが筆者の結論である。
1 0 0 0 OA 教育ママゴン度の実態に関する調査研究
- 著者
- 古川 隆
- 出版者
- 一般社団法人 日本教育学会
- 雑誌
- 日本教育学会大會研究発表要項 (ISSN:2433071X)
- 巻号頁・発行日
- vol.39, pp.26, 1980-08-22 (Released:2018-04-20)
1 0 0 0 OA 阿部彰著『教育関係法令目録並びに索引』(昭和編 I, II, III)
- 著者
- 神田 修
- 出版者
- 一般社団法人 日本教育学会
- 雑誌
- 教育学研究 (ISSN:03873161)
- 巻号頁・発行日
- vol.56, no.4, pp.364-365, 1989-12-30 (Released:2009-01-13)
- 著者
- 佐々木 正人
- 出版者
- 一般社団法人 日本教育学会
- 雑誌
- 教育学研究 (ISSN:03873161)
- 巻号頁・発行日
- vol.64, no.3, pp.317-326, 1997-09-30 (Released:2007-12-27)
筆者らは参加観察とインタビューで重度の視覚障害者のナヴィゲーションについての情報について検討している。たとえば、通路が交差するところでの独特な音響的構造によって通路の転換点を知覚することができる。また足裏の接触感の連続によってルートの延長を知覚できる。盲人も、視覚に障害がない者も、このように環境に偏在し、埋め込まれている情報によってナヴィゲーションが可能になっているが、伝統的な盲人の認知研究ではこのような環境に存在する情報については無視してきた。その理由は一つの光学理論にある。ルネッサンス以来、西欧の視覚理論は、イメージが視覚の原因であると考えられてきた。デカルトは幾何光学の方法で、眼球の後ろに外界と類似した像が映っているとするこの考え方をしりぞけ、視覚の像理論を否定した。彼は、像に変えて、視覚刺激に由来する微小な運動が視覚の原因であるとした。彼の転換によって視覚の理論は無意味な運動刺激を解釈する「心」という機構を必要とすることになった。このような光学の「記号化」が、特殊な盲人という問題を登場させた。それは無意味な刺激と意味深い情報との関係という問題であり、制限された刺激が盲人の思考にどのような問題を引き起こすのかという問題であった。この文脈では盲人の問題は非常に狭く設定された。アメリカの心理学者ギプソンは、物理的エネルギーとしての光と、視覚刺激としての光と、視覚情報としての光を区別した。彼はその生態光学によって、環境に存在する視覚の情報としての包囲光を問題にした。放射光が多重に反響した状態である照明が環境には満ちている、この照明光はすべての観察点を包囲する光の基礎となる。この光は環境の表面の構造に依存しており、知覚の情報となる。構造化した包囲光がナヴィゲーションをガイドする。図1には弱視の女性の事例を示した。環境に意味の存在を認める生態光学を基礎とすることで、盲人の認知の研究は、デカルト光学の設定した境界をこえることができ、この問題への多元的理解に接近することができる。
- 著者
- 赤堀 孝
- 出版者
- 一般社団法人 日本教育学会
- 雑誌
- 教育学研究 (ISSN:03873161)
- 巻号頁・発行日
- vol.19, no.1, pp.71-75, 1952
1 0 0 0 学校はなぜ学校となったのか
- 著者
- リートケ マックス 山内 芳文 長尾 十三二
- 出版者
- 一般社団法人 日本教育学会
- 雑誌
- 教育学研究 (ISSN:03873161)
- 巻号頁・発行日
- vol.56, no.2, pp.174-183, 1989
1 0 0 0 OA 郷土科と地域社会学校
- 著者
- 佐藤 正夫
- 出版者
- 一般社団法人 日本教育学会
- 雑誌
- 教育学研究 (ISSN:03873161)
- 巻号頁・発行日
- vol.18, no.2, pp.47-58,69, 1950 (Released:2009-01-13)
- 著者
- 榊 達雄
- 出版者
- 一般社団法人 日本教育学会
- 雑誌
- 日本教育学会大會研究発表要項
- 巻号頁・発行日
- vol.24, 1965
- 著者
- 高橋 誠
- 出版者
- 一般社団法人 日本教育学会
- 雑誌
- 日本教育学会大會研究発表要項
- 巻号頁・発行日
- vol.47, 1988
- 出版者
- 一般社団法人 日本教育学会
- 雑誌
- 教育学研究 (ISSN:03873161)
- 巻号頁・発行日
- vol.84, no.1, pp.61-68, 2017
- 著者
- 宮地 和樹
- 出版者
- 一般社団法人 日本教育学会
- 雑誌
- 日本教育学会大會研究発表要項 (ISSN:2433071X)
- 巻号頁・発行日
- vol.73, pp.172-173, 2014-08-21 (Released:2018-04-20)
- 著者
- 山田 恵吾
- 出版者
- 一般社団法人 日本教育学会
- 雑誌
- 教育学研究 (ISSN:03873161)
- 巻号頁・発行日
- vol.66, no.4, pp.443-453, 1999-12-30 (Released:2007-12-27)
本稿は、1926年(大正15)年地方官官制改正への千葉県労務当局の対応を通して「自由教育」に対する統制策を検討するものである。 従来、この時期の初等教育実践に関しては、いわゆる「大正自由教育」の展開として師範学校附属小学校や私立校における新しい実践の試みと、それに対する文部省側の政治的抑圧という観点から検討がなされてきており、児童の自発的学習に配慮した教育実践とその研究・運動が体制側に否定されていく過程として捉えられてきている。一方、地域レベルでの初等教育実践の展開については、いくつかの成果が認められるものの、十分検討されることのないまま対立的構図、及び「大正デモクラシー」から「ファシズム」へという歴史的文脈の中に解消される傾向にあったといえる。 そこで本稿では、地域における初等教育のありようを地方政治や地方行政の動向との関わりから捉えなおすことに積極的意義を認め、1920年代に千葉県労務当局が推進した「自由教育」に対する統制策に焦点を当てることにした。とりわけ、1926(大正15)年地方官官制改正(郡役所廃止や学務部設置)が教育行政体制に如何なる変容をもたらし、またそれが「自由教育」への統制策にどう結実していくのかを検討した。その結果、次の点が明らかになった。すなわち、(1)この時期の教育行政の専門家を背景として、(2)1926年地方官官制改正、とりわけ郡役所廃止に伴う公立校の監督指導体制の確立の要請、さらに(3)郡指導監督下の不統一な教育状況に対する県の姿勢を厳しく質した県会の圧力等を諸要因として、県は「自由教育」に対する「統制」を図ったことが明らかとなった。その「統制」とは具体的に千葉県師範学校附属小学校の「自由教育」の模範としての存在感を低下させるとともに、教育実践の新たな基準の創出=「小学校教育改善要項」の制定を通じて、県下公立校の統制を図ることであった。後者では、特に「自由教育」が附小と基本的条件の異なる公立校で実践されることによって生ずる様々な問題を「改善」することを意味していた。一方、「小学校教育改善要項」の基本理念として設定された「教育の郷土化」は、その後、文部省の推進する郷土教育に呼応しつつ、郷土教育展覧会を開催するなど県主導の下に具体化が図られていく。つまり、県の教育行政の自立性は、中央の政策を強化する方向で機能を果たすことになるのである。こうして1920年代の新しい教育実践の試みは、その独自の活動性を後退させるとともに、次第に行政機構内に収斂されていったのである。
- 著者
- 白石 崇人
- 出版者
- 一般社団法人 日本教育学会
- 雑誌
- 教育学研究 (ISSN:03873161)
- 巻号頁・発行日
- vol.82, no.1, pp.132-134, 2014 (Released:2016-05-19)
1 0 0 0 OA 鄭 在哲 著 佐野 通夫 訳 『日帝時代の韓国教育史 日帝の対韓国植民地教育政策史』
- 著者
- 佐藤 由美
- 出版者
- 一般社団法人 日本教育学会
- 雑誌
- 教育学研究 (ISSN:03873161)
- 巻号頁・発行日
- vol.82, no.1, pp.147-150, 2014 (Released:2016-05-19)