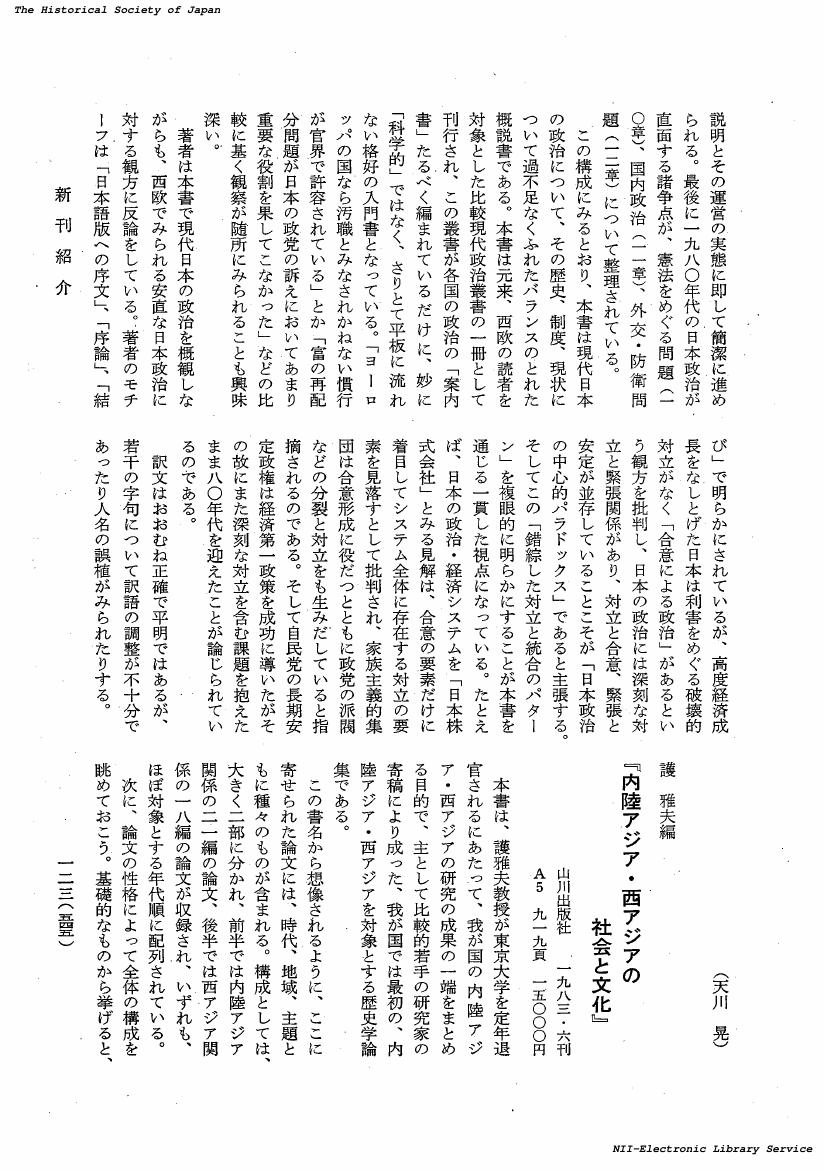2 0 0 0 OA 戦国期本願寺教団の構造
- 著者
- 神田 千里
- 出版者
- 公益財団法人 史学会
- 雑誌
- 史学雑誌 (ISSN:00182478)
- 巻号頁・発行日
- vol.104, no.4, pp.461-495,626, 1995-04-20 (Released:2017-11-30)
The aim of this article is to shed some light upon the background of the ikkoikki (一向一揆) uprisings which took place in the Sengoku period. The author takes notice of one feature of the structure of the sect, in contrast to the previous research that has only observed the characteristics of the social class of its members. In the first place, the Hohganji-Shusu (本願寺宗主, chief priest of Honganji temple) could not be shusu Without the recognition of the Honganji family, its vassals, and the Monto (門徒, disciples). The author points out that this recognition prevailed among the bushi (武士, warrior) classes at that time. Secondly, the author analyzes gosho (御書) and goinsho (御印書) to show that the orders issued by shusu were accepted by the monto only after consultation among all the members. Therefore the sect was managed according to an agreement between the shusu and monto. Finally, the author points out the fact that this union of shusu and monto was closely concerned with both the doctrine preached by Honganji and the hope of monto to be born again in the pure land: thus, the mechanism of the uprising.
- 著者
- 柳橋 博之
- 出版者
- 公益財団法人 史学会
- 雑誌
- 史学雑誌 (ISSN:00182478)
- 巻号頁・発行日
- vol.93, no.4, pp.545-546, 1984-04-20 (Released:2017-11-29)
2 0 0 0 OA 坂井秀夫著『イギリス外交の源流-小ピットの体制像-』
- 著者
- 青木 康
- 出版者
- 公益財団法人 史学会
- 雑誌
- 史学雑誌 (ISSN:00182478)
- 巻号頁・発行日
- vol.93, no.1, pp.99-105, 1984-01-20 (Released:2017-11-29)
- 著者
- 近藤 和彦
- 出版者
- 公益財団法人 史学会
- 雑誌
- 史学雑誌 (ISSN:00182478)
- 巻号頁・発行日
- vol.87, no.7, pp.1191-1192, 1978-07-20 (Released:2017-10-05)
2 0 0 0 土一揆像の再検討
- 著者
- 神田 千里
- 出版者
- 公益財団法人 史学会
- 雑誌
- 史学雑誌 (ISSN:00182478)
- 巻号頁・発行日
- vol.110, no.3, pp.410-435, 2001
Regarding the debate over whether tsuchi-ikki (土一揆) was part of the peasants' class struggle, Y. Inagaki criticized the researches regarded it as such a struggle, arguing that it was carried out by warriors, agents of landlords, or wealthy peasants and thus could not be looked upon as a political struggle. Inagaki's argument has been opposed by not a few scholars to date. At present, the balance of evidence seems to support the argument that tsuchi-ikki was part of the peasants' class struggle. Especially strong support has been provided by the researches on tokusei (徳政, annulling loan contracts) by K. Seta, H. Kasamatsu, and S. Katsumata, which has proved that tokusei demanded by tsuchi-ikki were based on the idea of the land possession common to the residents of villages at that time. On the other hand, it has come to be known that both the unity of peasants based on the village and the idea of the land possession common to villagers in the medieval Japan still prevailed in later premodern times. This brings the author to think that tsuchi-ikki cannot be completely explained only by the two elements in the previous debate, because the term disappears from the documentations by the end of the sixteenth century. The author, therfore, rexamines whether the unity of peasants based on the village is the definitive element of tsuchi-ikki, looking at the connection between daimyo, landlords, warriors and tsuchi-ikki, in order to throw some light upon the aspects that still remain unexplained.
2 0 0 0 OA 秦漢時代の人的結合と国家 『嶽麓書院藏秦簡』を手掛かりに
- 著者
- 椎名 一雄
- 出版者
- 公益財団法人 史学会
- 雑誌
- 史学雑誌 (ISSN:00182478)
- 巻号頁・発行日
- vol.130, no.8, pp.1-36, 2021 (Released:2022-08-20)
秦漢時代を対象とする歴史研究において、郷里社会における人的結合を究明することは、当該時代の特質を描きだすとともに秦漢国家形成論にもつながる重要な課題である。従来の主な議論では、任侠や爵制あるいは血縁や地縁が着目されてきた。本稿では、諸研究の成果を踏まえ、出土文献や編纂史料を分析し、犯罪者およびその犯罪者を救わんとする者の関係を構築する原理を明らかにして、秦の統一国家形成と関連づけた議論を行う。 第一章では、『睡虎地秦墓竹簡』『嶽麓書院藏秦簡』『二年律令』に抄録される法律条文から、犯罪者およびその犯罪者を救わんとする者の関係を確認し、親属と「所知」二つの人的関係を指摘する。また、犯罪者およびその親属と「所知」には強い人的結合が存在したことも確認する。 第二章では、国家が法律条文において、危機に瀕した者を救済する資格を、その親属と「所知」のみに認めていたことを指摘する。その上で、『嶽麓』で親属と「所知」を並記する構造が、『墨子』にもみえることを確認する。 第三章では、墨家の影響を受ける『呂氏春秋』や任侠を称賛する司馬父子による『史記』から、命を賭して報恩に至る人的結合に、「知」が不可欠な要素と認識されていたことを確認する。その上で『嶽麓』には、秦墨や任侠的風潮の色濃い地域への秦の進出が影響していたことを指摘する。 第四章では、秦の法律文書には、「知」にもとづく関係を国家の支配に利用する施策が内包されていたことを確認する。また、その「知縁」とも呼ぶべき人々と親属で構成される小型の集団を、国家が社会の基盤として認識していたことを指摘する。 秦の東方や南方地域の郷里社会には、親属と任侠的習俗にもとづいた「知縁」で構成される小型の集団が存在した。秦はその小型の集団を維持・再生産する施策を通し支配の正当性を獲得し、その構成員や郷里社会の維持や再生産にまで及ぶ支配構造を構築していたことを論じる。
2 0 0 0 OA 暴力の歴史の描写を目指して 中近世ドイツ犯罪史研究における動向から
- 著者
- 齋藤 敬之
- 出版者
- 公益財団法人 史学会
- 雑誌
- 史学雑誌 (ISSN:00182478)
- 巻号頁・発行日
- vol.130, no.2, pp.37-57, 2021 (Released:2022-02-20)
1990年代初頭からドイツ歴史学の中で活況を見せる歴史犯罪研究は、中近世における傷害や殺人などの暴力をはじめとする犯罪の社会史を論じている。その系譜は、ドイツ社会史研究の盛り上がりや、人類学にも接近した「新しい文化史」の台頭といった、1970年代以降の歴史学の趨勢に位置づけられる。G・シュヴェアホフやM・ディンゲス、J・アイバッハといった研究者は、犯罪社会学の概念やP・ブルデューの名誉や男性性に関する見方を積極的に摂取することで、N・エリアスの文明化論でしばしばネガティヴに描写されてきた前近代の暴力を文化史的に捉え直した。すなわち、とくに男性間での名誉をめぐる揉め事に、中傷や挑発の言動に端を発して最終的に身体的な実力行使に至るというエスカレートの規則性や儀礼化を見出すことで、感情や攻撃欲の無制限の発露、非文明的な行為としての暴力像を退けた。こうした理解はその後の研究に受け継がれつつも、P・シュスターやP・ヴェットマン=ユングブルートらは暴力と名誉の関係をより緩やかに捉えており、さらに近世の決闘の諸相を検討したU・ルートヴィヒや19-20世紀ベルンにおける暴力犯罪を分析したM・コティエーは男性の名誉と結びついた暴力を一種のゲーム、つまり自己目的化したコミュニケーション形態と理解することで、暴力の感情的次元を改めて視野に収めている。 本稿での整理から導かれる今後の課題として、18世紀フランクフルトの犯罪を分析したアイバッハの研究を決闘研究や感情史研究と接続させ、19世紀まで射程に入れて暴力の形態や行動様式、認識の変化をたどるとともに、名誉を守る必要性と暴力による負傷や命の危険との間に葛藤を抱いていたのかといった点を問うことが有意義である。このような暴力の社会的位置づけの検討を通じて、「端境期(ザッテルツァイト)」と呼ばれる18世紀から19世紀の時代的特質の解明にも貢献できると思われる。
2 0 0 0 OA 明治中・後期の皇室財政 制度と実態
- 著者
- 加藤 祐介
- 出版者
- 公益財団法人 史学会
- 雑誌
- 史学雑誌 (ISSN:00182478)
- 巻号頁・発行日
- vol.130, no.4, pp.64-92, 2021 (Released:2022-04-20)
本稿は、明治中・後期(1888~1912年)における皇室財政の制度と実態について、基礎的な検討を行うものである。 1888~1893年度においては緊縮財政路線がとられた。一方、この時期の宮内省内蔵頭の杉孫七郎は、平常の財政運営に関しても伊藤博文の指導力に依存する傾向があり、また主に元老によって構成される皇室経済会議が皇室財政を監督する体制を支持していた。 1894年度以降、皇室財政は次第に膨張へと転じていく。そうした中で内蔵頭の渡辺千秋は、御料地経営の収益を組み込んだ統一的な財政制度の確立や、借入金の完済などを提起した。また渡辺は、杉内蔵頭の時代とは異なり、平常の財政運営に関しては、宮内省は自ら問題を処理する能力=専門性を備えつつあると認識していた。 1903年以降、帝室制度調査局において皇室法の検討が活発化していった。同局および宮内省内での検討を経て、1910年に皇室財産令が、1912年に皇室会計令が制定・公布された。皇室財産令によって、皇室経済会議は宮相の「諮詢機関」である帝室経済会議へと縮小再編され、宮内省の専門分化が進展した。また皇室会計令によって、御料地経営の収益を組み込んだ統一的な財政制度が確立した。 一方で、田中光顕(宮相)・渡辺体制下の宮内省は、財政基盤強化のためのアドホックな資金獲得に走るところがあった。日清戦争賠償金の皇室財政への編入(1898年)や国庫支出の皇室費の増額(1910年)はその典型である。宮内省は、前者によって借入金の完済に成功し、後者によって日露戦後の財政逼迫に対処したが、こうした対応は議会(国民)との間に一定の緊張を生じさせた。こうした明治中・後期における宮内省の対応のあり方は、議会(国民)との間の緊張を回避するという志向が明確に見られた1920年代のそれとは、大きく異なっている。
- 著者
- 安酸 香織
- 出版者
- 公益財団法人 史学会
- 雑誌
- 史学雑誌 (ISSN:00182478)
- 巻号頁・発行日
- vol.129, no.11, pp.1-33, 2020 (Released:2021-11-20)
近世ヨーロッパ史研究では、ここ半世紀のあいだに近代化論から離れ、近世国家の特質をめぐる議論を展開してきた。この傾向は、近世アルザス史研究にも、フランス絶対王政の新たな理解に基づく再考を促した。しかし、一七世紀のアルザス譲渡以降についてフランスとの関係にのみ注目し、神聖ローマ帝国とのつながりを度外視するならば、同地域の秩序を根本的に理解することはできない。近年では両関係が考慮されつつあるが、いまだ事例研究の数は少なく、まして体系的な研究には至っていない。それゆえ本稿では、アルザス最大勢力であるシュトラースブルク司教の訴訟を事例とし、帝国、王国、アルザスの諸権力を視野に入れて同地域の秩序を描き出すことを試みた。 具体的には、第一章にて近世アルザス史を概観し、第二章にて前述の訴訟を分析し、第三章にてアルザス周辺の紛争と解決における特質を浮かび上がらせた。特質として、以下三点を指摘できる。第一に、アルザス地域諸権力は、フランス王が創設したアルザス最高評定院を、紛争解決の唯一の手段ではなく、選択肢の一つとみなしていた。第二に、彼らは神聖ローマ皇帝とフランス王の双方の封臣として、多様な紛争解決手段を利用できた。しかし第三に、手段の複数性は、裁判所間、さらには皇帝とフランス王のより大きな紛争を引き起こす危険性を孕んでいた。彼らがこの危険を避け、当事者間の示談を試みたことは、多様な選択肢の一時的な放棄を意味したが、しかし結果として彼らの自立性を高めることにもなった。 本稿では、フランスの主権確立や州の統一という従来のアルザス史像とは対照的に、また新旧制度の併存という近年の理解を発展させて、地域的・国家的枠組みを越えた柔軟な紛争解決に基づくアルザスの秩序を明らかにした。この成果は、近世ヨーロッパの政治秩序を、国家間の勢力関係や近世国家論とは異なるかたちで描き出す可能性を秘めている。
2 0 0 0 OA 消費論からみた中世菅浦
- 著者
- 橋本 道範
- 出版者
- 公益財団法人 史学会
- 雑誌
- 史学雑誌 (ISSN:00182478)
- 巻号頁・発行日
- vol.129, no.6, pp.32-48, 2020 (Released:2021-09-09)
本稿は、環境史的視野をもった消費論、環境史的消費論を構築するために、中世の近江国菅浦における産物の消費実態の考察から、生業の構造とその変化を解明したものである。 網野善彦が「湖の民」と述べたように、菅浦については内水面を対象とした二つの生業、漁撈と水運に従事したムラというイメージが流布している。しかし、まず近世菅浦研究がそのイメージを一新し、中世菅浦研究もそれに続こうとしている。それは、アブラギリ生産など、「集落とその背後などの陽当たりのよい傾斜地」を対象とした生業の重要性を提起したものと総括できる。 建武二年(一三三五)に進上を誓約したとされる供御、コイ、ムギ、ビワ、ダイズのうち、コイが長禄元年(一四五八)には代銭納化されていたのに対し、ビワは禁裏に献上され、都市領主社会内部でも分配されていた。十五世紀の王権と都市領主にとっては、菅浦はビワの名産地という位置づけであった。 一方、琵琶湖地域内での贈答をみると、菅浦産コイの贈答も確認できるものの、もっぱら菅浦から贈答されるのはビワとコウジであった。いずれも「集落とその背後などの陽当たりのよい傾斜地」の産物である。ここで注目したいのは、反対に菅浦へと贈答されるもののなかに、琵琶湖産淡水魚のフナ・ウグイ・アユがみえることで、もし菅浦の主たる生業が漁撈であれば贈答されるとは考えにくい。地域内の消費実態からも中世菅浦の生業の重心が、内水面ではなく、「集落とその背後などの陽当たりのよい傾斜地」に置かれていた可能性は高い。 中世菅浦は、多様な生業を複合的に組み合わせて生存していたが、消費論はこうした複合する生業を羅列的に明らかにするだけでなく、それらの首都や地域における価値づけなど、階層的構造とその変化を解明する可能性を秘めている。その上で、この構造と自然条件との関係が解明できれば、地域環境史にも貢献できると考える。
2 0 0 0 OA 古代中世の葬送と女性 参列参会を中心として
- 著者
- 島津 毅
- 出版者
- 公益財団法人 史学会
- 雑誌
- 史学雑誌 (ISSN:00182478)
- 巻号頁・発行日
- vol.129, no.1, pp.1-36, 2020 (Released:2021-09-02)
古代中世の葬送において女性がどう関わっていたのか。これまで葬送史研究、および女性史研究でも検討されたことはなく、両者の歴史的な関係を解明する必要性があった。 そこで本稿は、八世紀から十六世紀までの葬送事例を通して、女性における葬送への参列参会の実態と歴史的な変化を検討し、その背景を葬送の性格と女性の位置という二側面から考察した。 まず十三世紀半ばまででは、次のようなことを指摘した。一に、葬送が凶事とされたため、身体を保護する必要性から幼女や妊婦は葬送の参列もできなかった。二に、女官・女房や女性親族は、故人を愛しみ遺体に触れることも可能であった。しかし、九世紀中頃から女性が公的な社会から疎外されていくなか、女性親族が会的側面をもつ葬送への参列や葬所への参会が行われなくなる。一方女官・女房は、公的立場をもった女性として、職務の一環から参列参会していた。三に、皇后・中宮はさらにその身位がもつ制約から、夫であった天皇や上皇の葬送にも参列参会できなかった。 そして、十三世紀後半以降では次のようなことを指摘した。十二世紀以降、父祖経歴の官職を嫡系が継承していく中世的な「家」の成立により、女性の位置関係にも変化が現れた。一方、禅律系寺院が境内に荼毘所・墓地を構えたことから葬所が「結縁の場」となる。こうして十三世紀後半を期に、公家・武家などの葬送では寺院で葬送が完結して葬列がなくなり、女性親族が葬所へ参会し始めるようになる。ところが十四世紀以降、后も立てられず、女房が妻妾として天皇に仕え、娘の皇女は尼となっていた。天皇家のこうした特異な状況によって、葬列が組まれ続け、平安時代以来の形態を残す天皇・上皇の葬送にも、妻妾が参列して娘とともに荼毘に参会するようになっていた。 以上のように古代中世の女性と葬送の位置関係には、九世紀半ばと十三世紀半ばの二度の画期があったことを解明した。
2 0 0 0 OA ミュンヘンヴィラーのネクロロギウム
- 著者
- 関口 武彦
- 出版者
- 公益財団法人 史学会
- 雑誌
- 史学雑誌 (ISSN:00182478)
- 巻号頁・発行日
- vol.89, no.4, pp.453-486,547-54, 1980-04-20 (Released:2017-10-05)
The purpose of this study is to clarify a tremendous role the reformed monasticism played during the formation of feudal society through the aid of a necrology of the Cluniac priory, Munchenwiler, that is the most extensive of all the medieval necrologies. We have reached the following conclusions : 1)Necrology was a monastic register for mutual intercession of the monks. In the High Middle Ages, almost all the Benedictine monks were elevated to priesthood and they formed a privileged group consisting of men of prayer (oratores). 2)The monks' raison d'etre was to intercede for lay patrons. They were enrolled in Cluny's Book of Life (Liber Vitae) and commemorated in the elaborate and extended Cluniac liturgy. 3)Reformed monasticism became an accelarating element of the downfall of the Carolingian monarchy. Through the contract of precaria with monastic establishments, there arose increasingly two separate classes, that is, warriors (bellatores) and peasants (laboratores). Furthermore the cooperation of new nobility and reformed monasticism brought about the disintegration of territories of the old monasteries (Saint-Germain-des-Pres, Saint Bertin and Saint Denis etc. ...) and undermined the administrative unit of the Carolingian Empire, namely, pagus (=dioecesis). 4)The emergence of new corps d'Elite, namely, a body of men of prayer came to secularize the traditional sacredness of the king. In France, the secular and spiritual power had been actually separated by the first half of the eleventh century. This de facto distinction between the secular (temporalia) and religious power (spiritualia), we might say, decided the character of the French Investiture Controversy.
- 著者
- 大川 裕子
- 出版者
- 公益財団法人 史学会
- 雑誌
- 史学雑誌 (ISSN:00182478)
- 巻号頁・発行日
- vol.118, no.11, pp.2019-2020, 2009-11-20 (Released:2017-12-01)
2 0 0 0 明治皇室典範の制定と元老院議官:皇室の自律性をめぐる制度構想
- 著者
- 原科 颯
- 出版者
- 公益財団法人 史学会
- 雑誌
- 史学雑誌 (ISSN:00182478)
- 巻号頁・発行日
- vol.129, no.4, pp.30-54, 2020
明治22(1889)年に制定された(明治)皇室典範(以下、典範)は、皇位継承や皇族など皇室に関する重要事項を定めた。本稿は、従来等閑視されてきた元老院議官の制定への関与に着目した上で、典範によって規定された皇室の自律性を明らかにするものである。<br> 典範草案の多くは、柳原前光や尾崎三良など、近世朝廷関係者で三条実美を人脈的結節点とする元老院議官によって作成・協議された。それらは、井上毅の意見とは異なり、天皇の皇族に対する監督権(以下、皇族監督権)を尊重しながら、皇位継承順序・摂政就任順序の変更などは元老院へ諮詢されねばならないとした。背景には、皇室の自律性確保や元老院の権限強化といった志向がうかがえる。<br> しかしながら制定を主導した伊藤博文は、皇族監督権を容認する一方、皇位継承順序の変更については、皇室の政治からの独立性を担保すべく、元老院のみならず内閣への諮詢も否定した。こののち柳原は、伊藤・井上に対し、起草作業の主導権をめぐる対抗意識や政治的闘争心を強めるに至った。<br> その後、典範諮詢案の枢密院会議では、永世皇族制が採択されたものの、皇族の婚姻や懲戒などに関しては、宮内大臣の副署や皇族会議ないし枢密顧問官への諮詢を要すとしつつ、天皇の皇族監督権が広く認められた。<br> かくして典範の制定は、憲法のそれとは対照的に、草案の広範な回付や伊藤への対抗意識を伴った。この間、柳原ら議官は一貫して上院の皇室事項への関与を重視したが、伊藤は内閣・議会いずれの関与も斥けた。しかしながら両者は、先行研究では看過されてきたが、皇位継承を除く皇室事項について天皇の意思を尊重する点では概ね一致したといえる。即ち典範は、皇室の自律性を確保すべく、皇室の政治からの独立性(消極的自律性)を保障した上で、皇室事項は原則として、天皇をはじめ宮内大臣・皇族会議・枢密顧問官の意思で決定・運営されるとしたのである(積極的自律性)。
2 0 0 0 OA 中世前期京都朝廷と天人相関説 : 日本中世<国家>試論
- 著者
- 下村 周太郎
- 出版者
- 公益財団法人 史学会
- 雑誌
- 史学雑誌 (ISSN:00182478)
- 巻号頁・発行日
- vol.121, no.6, pp.1084-1110, 2012-06-20 (Released:2017-12-01)
Within the recent research done on the Japanese medieval state, a debate has arisen over how to evaluate the Kamakura Bakufu in contrast to the imperial court in Kyoto. If we try to relocate the problem somewhat differently, we end up fundamentally focusing on the question of what is the meaning of "state" in medieval Japan. The present article focuses on contemporary ideology and extraordinary events from the analytical perspective of the relativization of the modern nation-state, in order to trace indicators and characteristic features of the "state" within the Japanese medieval world, within the context of the time-space continuum of premodern East Asia. In concrete terms, the author takes up the political ideology of correlating divine will with human action (tenjin 天人) in connection with extraordinary events, a set of beliefs which originated in China then spread throughout the regions on its periphery, as the ideology developed in Kyoto aristocratic society during the early medieval period, which is a given factor when trying to place the Kamakura Bakufu within context of the state at that time. This tenjin ideology involved understanding the origins of extraordinary events, both favorable and disastrous, as stemming from divine judgement towards corresponding good or bad political governance. What the author terms the "tenjin correlation" can therefore be identified as the fundamental necessary condition for aristocratic organizations responsible for political action and therefore for those political entities of the premodern East Asian world which we conceptualize as "states". Although the research to date has tended to undervalue and de-emphasize the importance of the "tenjin correlation" in the workings of the imperial court in early medieval Kyoto, the author is able to verify the continuing existence of an ideology of causality based on the "tenjin correlation," in particular with respect to extraordinary natural phenomena. That is to say, the idea of such phenomena as crucial events being a characteristic feature of the medieval world is the key to evaluating the early medieval Kyoto imperial court as a "state" within the time-space continuum of premodern East Asia. On the basis of such ideology, the various political responses that were selected and implemented on the occasion of extraordinary natural events can be understood structurally as composed of invocation (exorcism) and public acts of benevolence. The author concludes that the medieval Japanese "state" model can be understood in terms of extraordinary natural events, etc. being ultimately judged as divine punishment for immoral, mistaken political governance on the part of the ruler, and also as a political entity composed of rulers and their counselors responding to the will of heaven with two kinds of human action, acts of expiation and public displays of benevolence. It is within this context that the situation of the Kamakura Bakufu and medieval social structure should be placed.
2 0 0 0 OA 嶋崎 昌著『隋唐時代の東トゥルキスタン研究-高昌国史研究を中心として-』
- 著者
- 堀 直
- 出版者
- 公益財団法人 史学会
- 雑誌
- 史学雑誌 (ISSN:00182478)
- 巻号頁・発行日
- vol.86, no.12, pp.1741-1748, 1977-12-20 (Released:2017-10-05)
- 著者
- 高野 太輔
- 出版者
- 公益財団法人 史学会
- 雑誌
- 史学雑誌 (ISSN:00182478)
- 巻号頁・発行日
- vol.105, no.3, pp.307-331, 1996
2 0 0 0 OA ウマイヤ朝期イラク地方における軍事体制の形成と変容 : シリヤ軍の東方進出問題をめぐって
- 著者
- 高野 太輔
- 出版者
- 公益財団法人 史学会
- 雑誌
- 史学雑誌 (ISSN:00182478)
- 巻号頁・発行日
- vol.105, no.3, pp.307-331, 1996-03-20 (Released:2017-11-30)
- 著者
- 河上 麻由子
- 出版者
- 公益財団法人 史学会
- 雑誌
- 史学雑誌 (ISSN:00182478)
- 巻号頁・発行日
- vol.117, no.12, pp.2047-2082, 2008-12-20 (Released:2017-12-01)
This article examines memorials (上表文) sent to the Southern dynasties that display a strong Buddhist influence. Its first chapter focuses on the analysis of the memorials sent to the Song and the Liang Dynasties from the Shizi 師子 Kingdom and the Tian-zhu-jia-pi-li 天竺迦〓黎 and Zhong-tian-zhu 中天竺 Kingdoms, which have been considered the same kingdom, but despite the common name Tian-zhu 天竺, they should not be regarded as the same. In addition, it is difficult to confirm that tribute sent in the name of the Shizi Kingdom in 527 was really sent by that kingdom. Chapter 2 discusses the circumstances under which the memorials sent to the Song and Nanqi Dynasties correspond to those sent to the Liang Dynasty and concludes that the former were composed by Buddhist monks who moved between the Nanhai 南海 Kingdoms and China, in such places as Funan 扶南. Moreover, the author argues that during the reign of Liang Dynasty Emperor Wu, correspondence was sent out expressing the emperor's wish to receive Buddhist-worded memorials, which forced neighboring kingdoms to consult older memorials preserved in a place presumably Funan. Given this background, Chapter 3 examines the relationship between the Southern dynasties and those kingdoms which sent Buddhist-influenced memorials, concluding that the traditional tribute relationship (册封 or 除授) was not formed between the Southern dynasties and those kingdoms, with only one exception during the Song era. This is because their memorials presumed a different relationship, between the Chinese emperor as bodhisattvas who provide guidance in popular worship and the kingdoms, as described in the Buddhist scripture about the relationship between Ashoka the Great and the kingdoms on his periphery. Within such a scenario, the traditional emperor-subject tribute relationship was considered inappropriate. Considering the situation of the Southern dynasties having to legitimize their existence in competition with the Northern dynasties, the author argues that the former, particularly the Liang dynasty, instituted a new form of diplomatic relationship based on Buddhism, which was now expected to play an international role as the guarantor of dynastic legitimacy.
2 0 0 0 OA マムルーク朝末期の都市社会 : ダマスクスを中心に
- 著者
- 三浦 徹
- 出版者
- 公益財団法人 史学会
- 雑誌
- 史学雑誌 (ISSN:00182478)
- 巻号頁・発行日
- vol.98, no.1, pp.1-47,141-142, 1989-01-20 (Released:2017-11-29)
- 被引用文献数
- 1
I.M.Lapidus, an American specialist of Middle Eastern history, argued that the ruling Mamluks' role of combining the 'ulama' (religious and legal scholars) and the common people into one political and social unity, was characteristic of the structure of urban society during the Mamluk dynasty. He called such a system of political and social relations the 'Mamluk regime' and insisted that it worked well even after the rise of the Ottoman dynasty. At the end of the Mamluk era, that is during the time from the accession of Sultan Qa'itbay to the decline of the dynasty (1468-1517), the state suffered from a severe financial crisis due to the decrease of iqta revenue and the increase in the payment of salaries for soldiers and civil officials. Also at that time, impoverished Mamluks often revolted against the Sultan for the fulfilment of these payments. These social instabilities forced the Mamluk state to reform its financial and military regime, which had solely depended on the iqta' system and the Mamluks. This article examines those reform policies and their influence over administration and control of cities in the Mamluk state, in an attempt to reinterpret Lapidus' thesis on the structure of urban society. First, concerning financial policy, Sultan Qa'itbay started taxation on property of citizen and waqf endowment. The state intended it to absorb the accumlated wealth in cities for the betterment of bugetary conditions. For the same purpose the state adopted a policy to take bribes at appointments of officials and to confiscate their property during their tenures of office. It accelerated both a plutocratic tendency among officials and the prevalence of bribary in the administration. This tendency was especially noticeable in the legal administration of cities. The chief judge (qadi al-qudat) appointed many legal officials such as deputy-judges (na'ib), notaries (shahid) and executors (naqib, rasul) and formed them into his own faction (jama'a). He and his party gained profits on the legal system by means of bribary, services charges and so on. In Damascus the governor (na'ib) often levied taxes on its quarters (hara). Especially on expeditions, he conscripted both the arquebusier infantries and their wages from each quarter. He adopted this policy to resolve at once the problems of the financial crisis and the defense of the city. Administrators of each quarter (arif) and the governor's subordinates, such as the majordomo (ustadar) and executive secretary (dawadar), were in charge of collecting taxes. The governor managed to rule the city by embracing these officials and private mercenaries in his faction. As for the commn people, inhabitants of each quarter took remarkable political actions. They almost overwhelmed the military power of the Mamluks in the rebellion of the year 903 / 1497 and in the revolt of 907 / 1501. It was a social group called the zu'r that set up these popular movements. They were outlaws who lived on plunder and assassination. They were employed as infantry and private merconary by the governors, while they dominated markets and stores in their quarters and prevented the governor from taxation in exchange for protection fees. In the cities at the end of the Mamluk era, both the governor, a military-executive, and the chief judge, himself a civil official, formed their own factions (jama'a) and strengthened their domains and exploitation of the people. The commom people coudn't seek shelter anywhere other than under the protection of the zu'r, who built their bases of power in each quarter. The urban society in this period was co structured that various factions and groups were struggling with each other forcibly. Lapidus began his thesis by assuming that the Mamluks, the 'ulama' and the common people were the major strata and actors in the cities.(View PDF for the rest of the abstract.)