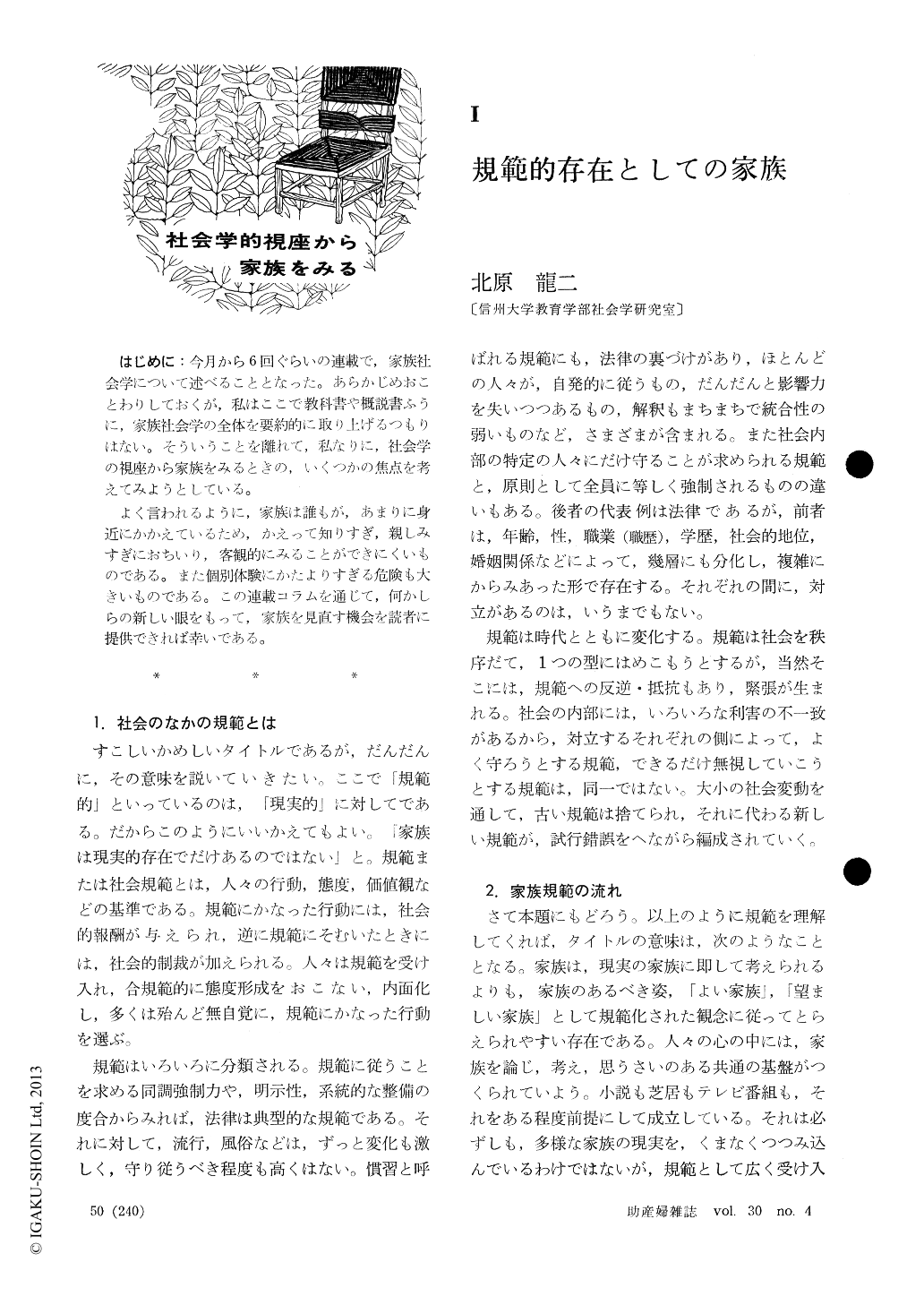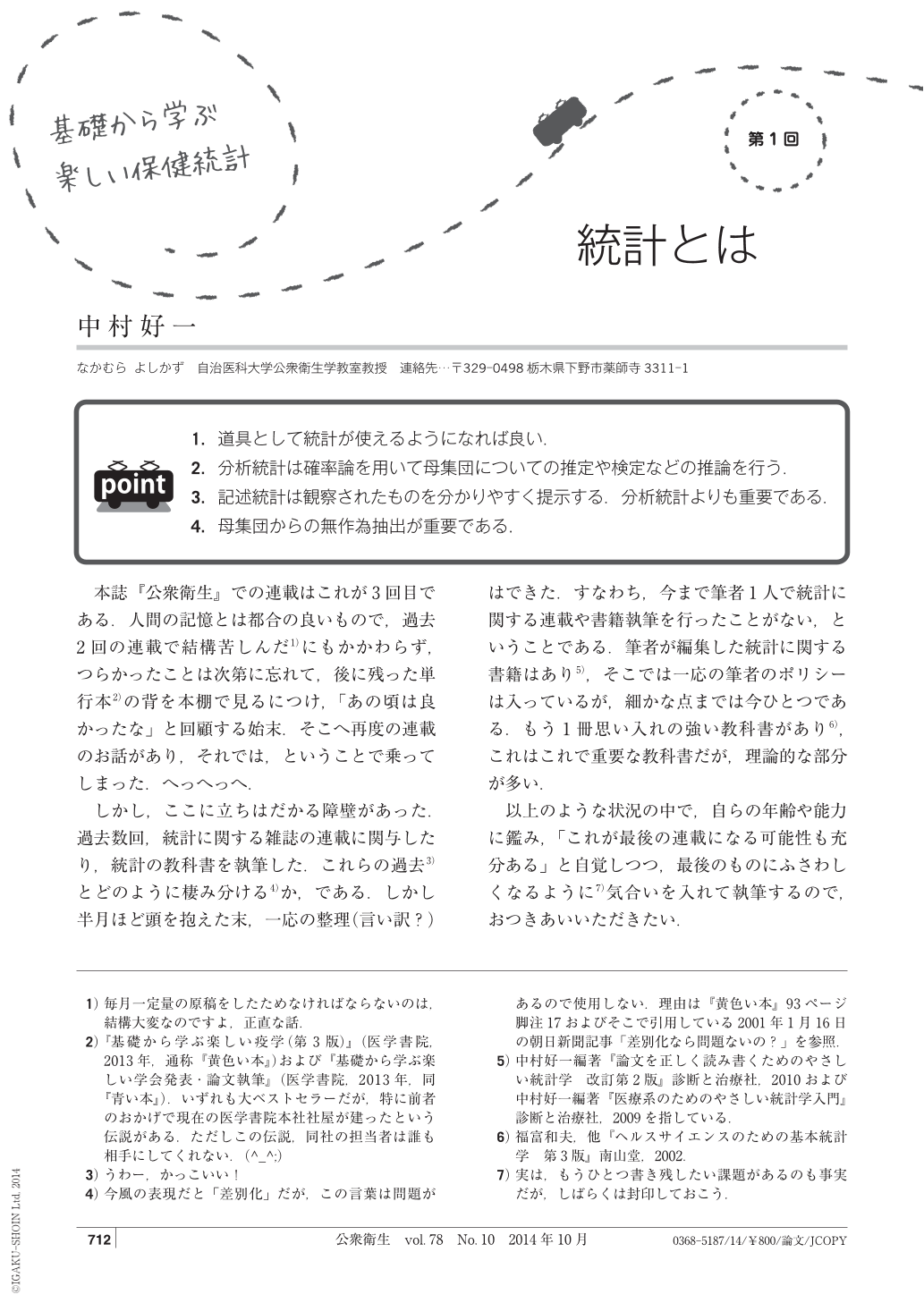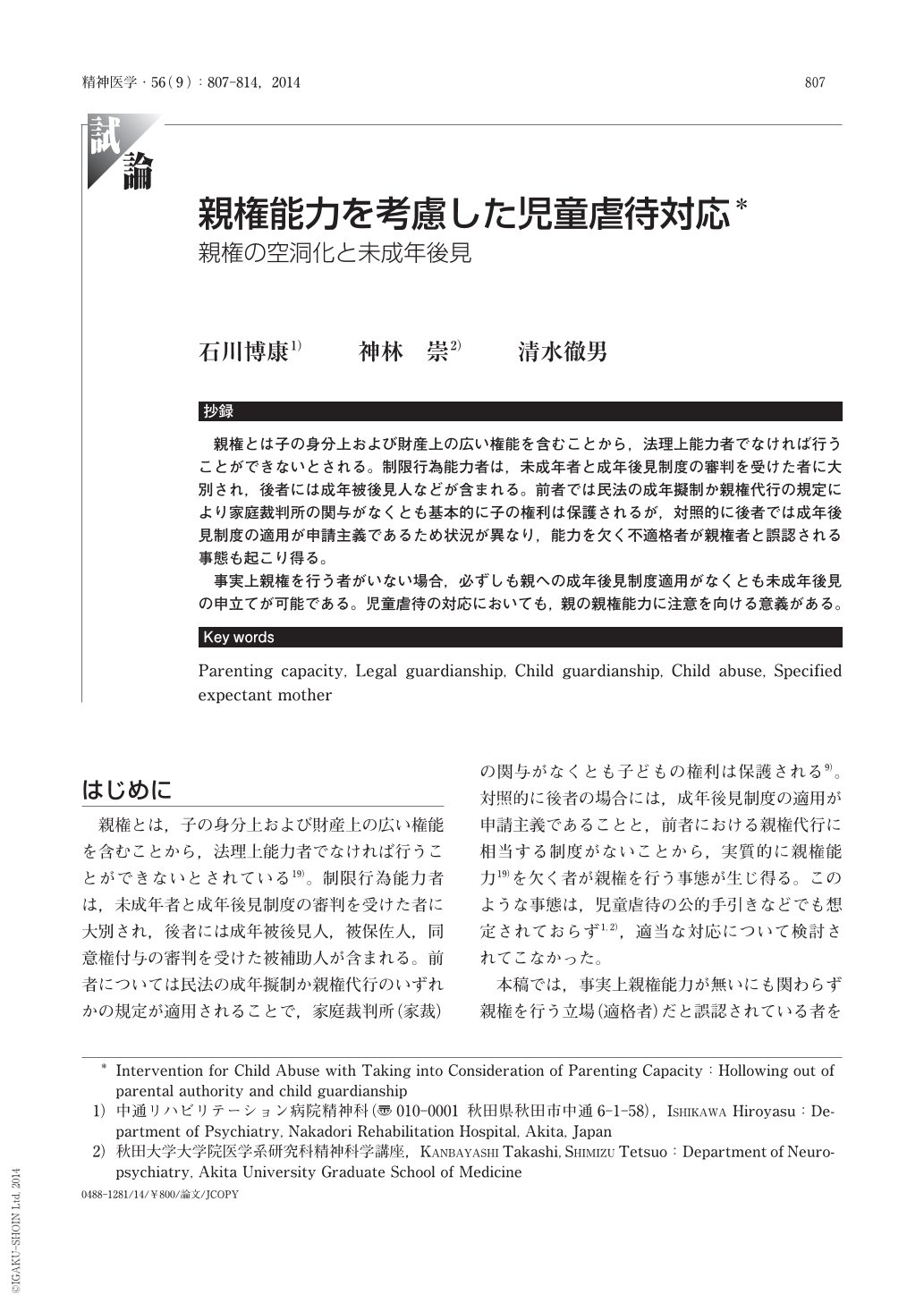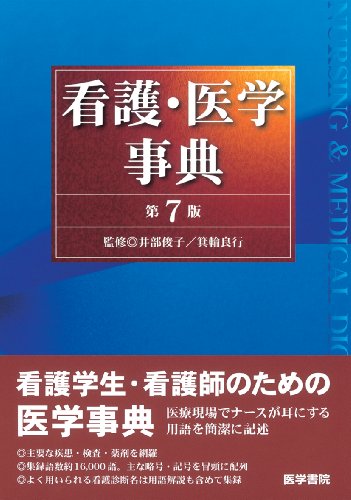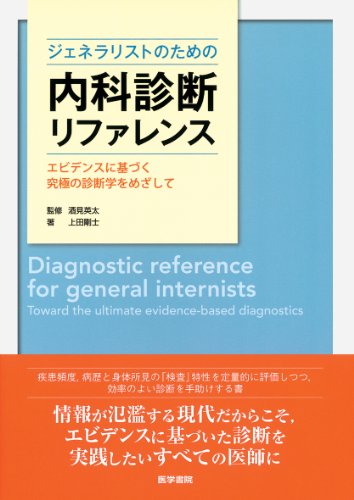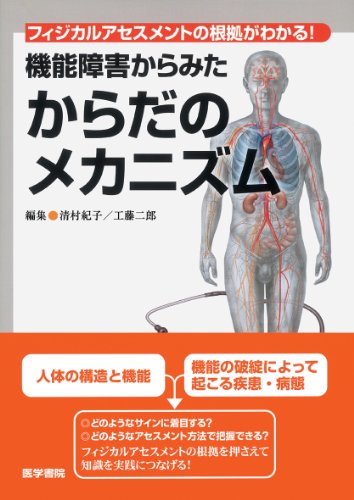1 0 0 0 てんかんに並存する精神病―本邦における歴史と新たな展望
- 著者
- 兼本 浩祐
- 出版者
- 医学書院
- 雑誌
- 精神医学 (ISSN:04881281)
- 巻号頁・発行日
- vol.56, no.3, pp.255-257, 2014-03-15
「癲」の歴史―たおれ病から精神病,精神病から再びてんかんへ2) てんかんと精神病が言葉として混同されるようになったのは実は歴史的にはそれほど古いことではない。「癲」がてんかんを意味する医学用語として初めて登場したのは,紀元前200年の秦の始皇帝の時代に宮廷医によって編纂された中国最古の医学書である『黄帝内経太素』によるとされる。「癲」という文字はもともと転ぶことを意味する「顚」にやまいだれを付けたものであり,転ぶ病,つまりは“falling sickness”という意味が原義であったとされる。もともと日本ではてんかんは,いびきを意味する「くつち(鼾)」,「くつちふす(鼾臥す)」,「くつちかき」などと呼ばれていたが,中国医学の「癲」の伝来によって日本でもてんかんは「癲」と呼ばれることになった。7世紀初めの隋の煬帝の時代,『病源侯論』という書物に初めて「癇」という言葉が使われ,10歳以下の小児てんかんを「癇」,10歳以上の成人のてんかんを「癲」と呼ぶ現代でも通用しそうな合理的な命名法が生まれ,これを受けてわが国でも奈良時代以降,「癇」という言葉が導入されたといわれている。「癲」と「癇」が合わさって「癲癇」として用いられるようになったのは9世紀の唐で編纂された『千金方』以降とされ,室町時代以降には庶民の間でも「癲癇」という言葉が使われるようになった。 中国では明代の16世紀前半以降,日本でもその影響をいち早く受け,安土桃山時代の16世紀後半から,「癲」と「狂」との同一視が始まったが,少なくとも日本での「癲」と「狂」の混同は,明代の代表的な医学書『医学正伝』の影響が大きかったとされる。江戸文政2年(1819年)に書かれた本邦で最初の精神医学書であるといわれる漢方医,土田獻の手になる『癲癇狂経験編』では,「癲」はその大部分が精神疾患を表しており,ごく一部にてんかんかと思われる記載が含まれるのみである5)。興味深いのは17世紀末,江戸の漢方医の間で巻き起こった論争で,当時名医として知られていた香川修庵が「癲癇」と「狂」が同じ原因で起こり病態の現れ方に違いがあるだけで両症が互いに並存すると主張し大方の漢方医がこれに賛同していたのに対して,岡本一抱は『黄帝内経太素』に遡り,「癲」を狂と同一視し,「癇」を日本古来の「くつち」と考えたのは後世の誤りで,「癲」と「癇」は同一の疾患でありこれは「くつち」であって,「癲」を狂と考えるのは後世の誤謬であると主張している。癲と狂とのこの同一視に由来する癲狂という言葉が使われなくなるのは,大正時代を待たねばならなかった。
- 著者
- 青木 真輝
- 出版者
- 医学書院
- 雑誌
- 看護教育 (ISSN:00471895)
- 巻号頁・発行日
- vol.50, no.10, pp.910-913, 2009-10
1 0 0 0 規範的存在としての家族
- 著者
- 北原 龍二
- 出版者
- 医学書院
- 雑誌
- 助産婦雑誌 (ISSN:00471836)
- 巻号頁・発行日
- vol.30, no.4, pp.240-242, 1976-04-25
はじめに:今月から6回ぐらいの連載で,家族社会学について述べることとなった。あらかじめおことわりしておくが,私はここで教科書や概説書ふうに,家族社会学の全体を要約的に取り上げるつもりはない。そういうことを離れて,私なりに,社会学の視座から家族をみるときの,いくつかの焦点を考えてみようとしている。 よく言われるように,家族は誰もが,あまりに身近にかかえているため,かえって知りすぎ,親しみすぎにおちいり,客観的にみることができにくいものである。また個別体験にかたよりすぎる危険も大きいものである。この連載コラムを通じて,何かしらの新しい眼をもって,家族を見直す機会を読者に提供できれば幸いである。
- 著者
- 内田 一徳
- 出版者
- 医学書院
- 雑誌
- 臨床外科 (ISSN:03869857)
- 巻号頁・発行日
- vol.67, no.1, pp.112-114, 2012-01
- 著者
- 武部 啓
- 出版者
- 医学書院
- 雑誌
- 助産婦雑誌 (ISSN:00471836)
- 巻号頁・発行日
- vol.56, no.9, pp.772-775, 2002-09
1 0 0 0 高齢初発の大うつ病性障害患者の在院を長期化させる因子について
- 著者
- 松本 卓也 小林 聡幸 加藤 敏
- 出版者
- 医学書院
- 雑誌
- 精神医学 (ISSN:04881281)
- 巻号頁・発行日
- vol.56, no.12, pp.1045-1052, 2014-12-15
はじめに 近年,わが国は世界でも類をみないほどの速度で高齢化を迎えている。精神科医療においても,高齢化は重要な懸案事項である。高齢化と関係するのは,認知症だけではない。大うつ病性障害(以下「うつ病」)の頻度は加齢とともに増加する5)ことが知られており,老年期のうつ病は重症度と致死率が高いことも指摘されている19)。また,高齢の患者は入院が長期化しやすく,わが国の医療費の増大にも拍車をかけていることが知られている。そのため,高齢者のうつ病入院患者の在院を長期化させる因子について検討することは,当該患者に対する適切な治療,および適切な医療資源の配分を考える上で重要であると考えられる。 しかし,うつ病患者の在院日数についての研究は,意外なほど少ない。大学附属病院を中心とした研究では,大うつ病性障害の平均在院日数が64〜94日13),高齢気分障害患者の在院日数の平均が112.3日18),60歳以上の高齢気分障害患者の在院日数の平均は約70日であった14)。ドイツとアメリカでのうつ病患者(全年齢)の平均在院日数はそれぞれ51日と11日であり2),日本は諸外国に比べても入院が長期に渡っていることが分かる。この理由には,国民皆保険制度によって比較的安価な医療費負担で入院治療を継続することが可能なことが挙げられるだろう。 うつ病入院患者の在院の長期化を規定する因子についての研究も,国内・海外ともに僅かしかみられない。Markowitzら15)は,大うつ病障害の入院患者(全年齢)に対して,ECTを施行することによって在院日数が平均13日間短縮されることを示している。国内のデータでは,当院での高齢気分障害患者(うつ病,および双極性障害を含む)について検討した玉川ら18)の研究では,65歳以上の患者は65歳未満の患者と比べて在院日数が約22日間長く,男性であること,合併症があること,および独居世帯に居住していることなどが在院の長期化の因子であった。高齢のうつ病入院患者の在院を長期化させる因子については,カナダのIsmailら11)の研究がある。彼らは2005〜2010年のうつ病入院患者についての検討から,高齢うつ病患者では,入院回数の多さ,独居世帯に居住していること,強制入院であることが長期在院を予測する因子であることを報告している。 先行研究をこのように概観すると,次に挙げるような諸々の点が明らかではないことが分かる。1.ライフイベントと在院日数の関係 高齢者は,本人や近親者が重大な病気を発症したり,ときには死に至ったりすることがある。事実,一般人口を対象とした研究において,死別をはじめとしたライフイベントが高齢者に多いことが知られている9)。また,死別が高齢者のうつ病の発症の重大なリスクファクターとなることは以前から知られている7)。同居家族が死去した後に発症したうつ病の場合,患者はうつ病から回復するという課題だけでなく,家族が喪失した家庭の中で新たな生活と役割を引き受けるという課題をも背負うことになる。この場合,在院が通常より長期化することは十分に考えられる。加えて,退職を契機としてそれまでの生活が一変することも,高齢のうつ病患者が生きる社会環境に大きな変化をもたらすと考えられる。しかし,これまで高齢者のうつ病におけるライフイベントと在院日数との関係は検討されていない。2.治療薬と在院日数の関係 うつ病患者がもともと居住していた自宅に退院するためには,ほとんどの場合で,薬物療法の効果によってうつ病を寛解ないし回復させる必要がある。このため,治療薬と在院日数には強い相関があると想定されるが,この論点についてもこれまでの研究では検討されていない。3.高齢初発うつ病の異種性 Ismailらが検討しているのは入院時に60歳以上であった「高齢うつ病患者」についてである。しかし,高齢うつ病患者には,若年初発群と高齢初発群が存在し,後者の高齢初発うつ病は重症度が高く,自殺既遂率が高く,予後も悪いことが知られており,両者を病因論的に区別するべきとされている21)。そのため,在院日数の研究についても,若年初発の高齢うつ病と高齢初発うつ病を区別することが必要だと思われる。 そこで我々は,対象を高齢初発うつ病入院患者に絞り,その在院を長期化させる因子を,患者背景や合併症,家庭環境,職歴,ライフイベント,うつ病の重症度と種類,薬物療法やECTなどの治療との関係から多角的な検討を行った16)。本稿では,以下にその研究から得られた10年分のデータを紹介することにしたい。
- 著者
- 末岡 浩
- 出版者
- 医学書院
- 雑誌
- 臨床婦人科産科 (ISSN:03869865)
- 巻号頁・発行日
- vol.68, no.10, pp.954-959, 2014-10
1 0 0 0 データの種類と特徴
- 著者
- 中村 好一
- 出版者
- 医学書院
- 雑誌
- 公衆衛生 (ISSN:03685187)
- 巻号頁・発行日
- vol.78, no.11, pp.782-790, 2014-11-15
point 1.データは数量データと質的データに分類される.分析手法が異なるので,扱っているデータがどちらなのかは常に意識しておく. 2.数量データはカテゴリ化して質的データに変換できるが,質的データを数量データに変換することはできない. 3.データ入力には必ず入力ミスがつきまとうと考えて対処する. 4.エクセルの基本的な使い方を習得しよう.
- 著者
- 木下 忠敏
- 出版者
- 医学書院
- 雑誌
- 精神看護 (ISSN:13432761)
- 巻号頁・発行日
- vol.9, no.1, pp.35-37, 2006-01
1 0 0 0 内臓体壁反射 : 皮電計による範例図譜
1 0 0 0 統計とは
- 著者
- 中村 好一
- 出版者
- 医学書院
- 雑誌
- 公衆衛生 (ISSN:03685187)
- 巻号頁・発行日
- vol.78, no.10, pp.712-718, 2014-10-15
point 1.道具として統計が使えるようになれば良い. 2.分析統計は確率論を用いて母集団についての推定や検定などの推論を行う. 3.記述統計は観察されたものを分かりやすく提示する.分析統計よりも重要である. 4.母集団からの無作為抽出が重要である.
1 0 0 0 親権能力を考慮した児童虐待対応―親権の空洞化と未成年後見
抄録 親権とは子の身分上および財産上の広い権能を含むことから,法理上能力者でなければ行うことができないとされる。制限行為能力者は,未成年者と成年後見制度の審判を受けた者に大別され,後者には成年被後見人などが含まれる。前者では民法の成年擬制か親権代行の規定により家庭裁判所の関与がなくとも基本的に子の権利は保護されるが,対照的に後者では成年後見制度の適用が申請主義であるため状況が異なり,能力を欠く不適格者が親権者と誤認される事態も起こり得る。 事実上親権を行う者がいない場合,必ずしも親への成年後見制度適用がなくとも未成年後見の申立てが可能である。児童虐待の対応においても,親の親権能力に注意を向ける意義がある。
1 0 0 0 発達過程作業療法学
- 著者
- 福田恵美子編 加藤寿宏編集協力 福田恵美子 [ほか] 執筆
- 出版者
- 医学書院
- 巻号頁・発行日
- 2014
1 0 0 0 看護・医学事典
- 著者
- 『看護・医学事典』編集委員会編
- 出版者
- 医学書院
- 巻号頁・発行日
- 2014
1 0 0 0 看護教育学
- 著者
- 杉森みど里 舟島なをみ著
- 出版者
- 医学書院
- 巻号頁・発行日
- 2014
1 0 0 0 臨床でよく出合う痛みの診療アトラス
- 著者
- Steven D. Waldman著 太田光泰 川崎彩子訳
- 出版者
- 医学書院
- 巻号頁・発行日
- 2014
- 著者
- 清村紀子 工藤二郎編集
- 出版者
- 医学書院
- 巻号頁・発行日
- 2014