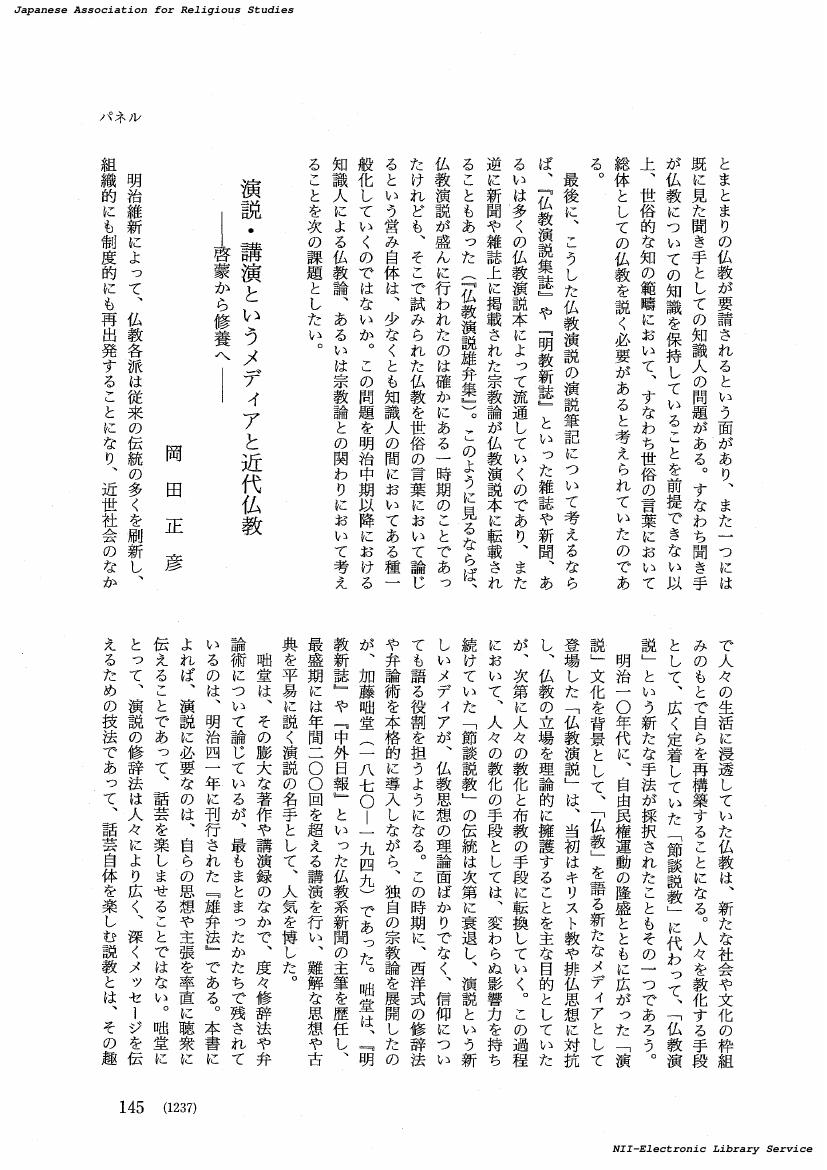- 著者
- 西村 玲
- 出版者
- 日本宗教学会
- 雑誌
- 宗教研究 (ISSN:03873293)
- 巻号頁・発行日
- vol.89, pp.323-324, 2016
- 著者
- 寺尾 寿芳
- 出版者
- 日本宗教学会
- 雑誌
- 宗教研究 (ISSN:03873293)
- 巻号頁・発行日
- vol.77, no.2, pp.369-391, 2003
現代日本におけるカトリック教会が秘めるNPO的な可能性に配慮しつつ、宗教経営学の観点からことにその組織マネジメントを模索していく。現代の教会は、成長期であった戦後復興期と同様に生活上での激変つまり生活有事といえる事態を迎えるなかで、変革への条件を満たしつつある。また伝統的な小教区教会とその周辺に発生する諸共同体を加えた拡大形態を教会共同体と名づけるが、そこでは外国籍信徒の生活有事を背景とした流入により、「無縁」の原理さらにはコムニタスを体現したアジールたることが要請され、また文化相対主義に通じる多文化主義を採用せざるをえない現状を呈している。聖職者や修道者は場のマネジメントにおいてファシリテーターであり、現場の状況に添った形で教会共同体を運営する。ことに司祭は外部の公共イベントへの参加などを通じ、社会的認知の獲得のため、開かれた祭儀を企画するプロデューサー的機能を発揮する。このような視圏を提供する宗教経営学は共生の技法と呼べるものであろう。
- 著者
- 古荘 匡義
- 出版者
- 日本宗教学会
- 雑誌
- 宗教研究 (ISSN:03873293)
- 巻号頁・発行日
- vol.89, pp.151-152, 2016
1 0 0 0 OA 縄文土偶の故意破壊説をめぐる議論の問題点(第十部会,<特集>第六十六回学術大会紀要)
- 著者
- 古澤 歩
- 出版者
- 日本宗教学会
- 雑誌
- 宗教研究 (ISSN:03873293)
- 巻号頁・発行日
- vol.81, no.4, pp.1223-1224, 2008-03-30 (Released:2017-07-14)
- 著者
- 津城 寛文
- 出版者
- 日本宗教学会
- 雑誌
- 宗教研究 (ISSN:03873293)
- 巻号頁・発行日
- vol.86, no.4, pp.1118-1119, 2013
1 0 0 0 OA ジョン・ディーの自然哲学と魔術(第四部会,<特集>第73回学術大会紀要)
- 著者
- 武内 大
- 出版者
- 日本宗教学会
- 雑誌
- 宗教研究 (ISSN:03873293)
- 巻号頁・発行日
- vol.88, no.Suppl, pp.249-250, 2015-03-30 (Released:2017-07-14)
1 0 0 0 後期水戸学の祭政一致論(第六部会,<特集>第72回学術大会紀要)
- 著者
- 齋藤 公太
- 出版者
- 日本宗教学会
- 雑誌
- 宗教研究 (ISSN:03873293)
- 巻号頁・発行日
- vol.87, pp.301-302, 2014
- 著者
- 花野 充道
- 出版者
- 日本宗教学会
- 雑誌
- 宗教研究 (ISSN:03873293)
- 巻号頁・発行日
- vol.89, pp.81-83, 2016
- 著者
- 小柳 敦史
- 出版者
- 日本宗教学会
- 雑誌
- 宗教研究 (ISSN:03873293)
- 巻号頁・発行日
- vol.83, no.4, pp.1191-1192, 2010-03-30 (Released:2017-07-14)
- 著者
- 水垣 渉
- 出版者
- 日本宗教学会
- 雑誌
- 宗教研究 (ISSN:03873293)
- 巻号頁・発行日
- vol.80, no.3, pp.742-747, 2006-12-30 (Released:2017-07-14)
- 著者
- 橋迫 瑞穂
- 出版者
- 日本宗教学会
- 雑誌
- 宗教研究 (ISSN:03873293)
- 巻号頁・発行日
- vol.87, no.Suppl, pp.311-312, 2014-03-30 (Released:2017-07-14)
- 著者
- 浜本 一典
- 出版者
- 日本宗教学会
- 雑誌
- 宗教研究 (ISSN:03873293)
- 巻号頁・発行日
- vol.89, no.3, pp.521-544, 2015
宗教多元主義はキリスト教神学から生まれた思想であるが、これをイスラーム的に構成し直し、異教徒との共存を説くムスリムが増えている。その中には、来世における異教徒の救済可能性を主張する者と、そのような議論を避けて現世的問題に特化する者がいる。例えば、ペレニアリストでもあるナスルは、伝統宗教の多様性を神の意志に帰し、「相対的絶対」の理論により他宗教の真理性を認める。しかし、この立場は、ムスリムの間であまり支持されていない。イスラームが他宗教に優越するという大方のムスリムの信念に反するからである。これに対し、今日有力なのは、現世での市民権を論じる多元主義である。例えば、カラダーウィーは、信仰に対する賞罰は神のみに委ねられるとして、イスラーム国家における信教の自由の保障と宗教的差別の廃止を訴える。だが、イスラーム国家という前提そのものが多元主義と矛盾するとの見方もある。このように、市民権論においても、救済論と同様、イスラームの優越性と多元主義との衝突が問題となっている。
1 0 0 0 OA 浩々洞同人による『歎異抄』読解と親鸞像
- 著者
- 大澤 絢子
- 出版者
- 日本宗教学会
- 雑誌
- 宗教研究 (ISSN:03873293)
- 巻号頁・発行日
- vol.90, no.3, pp.27-50, 2016-12-30 (Released:2017-09-15)
本稿は、『出家とその弟子』の素材とされる『歎異抄』との関連に焦点を当て、特に浩々洞の暁烏敏を中心とした『歎異抄』読解を扱った。暁烏や多田鼎における『歎異抄』の読みとは、自己の罪悪の自覚と「絶対他力」の強調であり、その態度が彼らの描く親鸞像にも色濃く現れ、自分を愚かだと吐露する親鸞像が展開されていく。そしてそのような親鸞は、『出家とその弟子』の親鸞とも重なる点も多い。 だが『出家とその弟子』の親鸞は、悪人の往生を説く『歎異抄』とも、あるいは暁烏の『歎異抄』読解とも大きく異なり、善を志向し、念仏(「祈り」)の成就としての往生を理想とする。キリスト教的な愛にも、絶対的な他力にもすがることのできなかった倉田が生み出したのは、きわめて求道的な親鸞像であった。
1 0 0 0 OA 戦間期ルーマニア右翼思想における政治と宗教(第一部会,<特集>第73回学術大会紀要)
- 著者
- 大谷 崇
- 出版者
- 日本宗教学会
- 雑誌
- 宗教研究 (ISSN:03873293)
- 巻号頁・発行日
- vol.88, no.Suppl, pp.182-184, 2015-03-30 (Released:2017-07-14)
- 著者
- 平山 昇
- 出版者
- 日本宗教学会
- 雑誌
- 宗教研究 = Journal of religious studies (ISSN:03873293)
- 巻号頁・発行日
- vol.92, no.3, pp.590-597, 2018-12
- 著者
- 飯島 孝良
- 出版者
- 日本宗教学会
- 雑誌
- 宗教研究 (ISSN:03873293)
- 巻号頁・発行日
- vol.92, no.1, pp.53-77, 2018
<p>本論では、西田幾多郎(一八七〇―一九四五)や鈴木大拙(一八七〇―一九六六)の「即」の論理を、戦後日本に即応する形で展開するには如何にすべきかを構想した市川白弦(一九〇二―一九八六)の思索を追いかける。</p><p>市川の反省と問いとは、太平洋戦争に及んで禅の所謂「随処作主」が誤った方向へ転じたのではないか、ということであった。市川にとって、時代の趨勢と共に「不惜身命」が表され、禅が皇道へ従っていく有様は、痛切な反省を求めるものであった。そうした戦時体制への徹底批判を試みた市川は、大拙による「不二の自由」の看方から「無諍」という在り方を導出した。そこから市川は、「仏土は遠く離れた無限の彼方にしか無いから、即ち今=此処が仏土である」という「即」の構造として世界を捉えようと試みた。そしてそうした「即」の具体像として、「風流ならざる処も也た風流」という境涯を旨とした一休宗純(一三九四―一四八一)を論じるに到った過程を、本論は明らかにするものである。</p>
1 0 0 0 OA 『神学・政治論』におけるスピノザの信仰理解
- 著者
- 富積 厚文
- 出版者
- 日本宗教学会
- 雑誌
- 宗教研究 (ISSN:03873293)
- 巻号頁・発行日
- vol.82, no.1, pp.93-117, 2008-06-30 (Released:2017-07-14)
本稿ではスピノザ(Baruch de Spinoza,1632-1677)におけるスピノザの信仰理解について考察する。スピノザによれば、信仰とは啓示的認識においてのみ問題となる事柄であり、またそれは「神に従順であること」を意味する。そして彼は『神学・政治論』において信仰と行いが循環の関係にあることを主張する。つまり行いを成立させているのは信仰であるが、信仰は行いを媒介とすることによってのみ証しされる。スピノザに従えば、この信仰と行いの循環の関係は、或る人間が救済を得るためには、その人間によって、絶えず新たに産み出されなければならないことである。人間たちがその循環を生きるための起動力こそ、「自己で有り続けようとする努力」であるコーナートゥスに他ならない。またスピノザが提示する信仰の根拠は人間たちに対する神の愛であり、その対象は神である。要するに信仰を証示するための行いの根源は、神に由来するコーナートウスである。
1 0 0 0 OA マグダラのマリアの多様なイメージ(第三部会,<特集>第六十六回学術大会紀要)
- 著者
- 細田 あや子
- 出版者
- 日本宗教学会
- 雑誌
- 宗教研究 (ISSN:03873293)
- 巻号頁・発行日
- vol.81, no.4, pp.1013-1014, 2008-03-30
- 著者
- 小川 有閑
- 出版者
- 日本宗教学会
- 雑誌
- 宗教研究 (ISSN:03873293)
- 巻号頁・発行日
- vol.79, no.4, pp.1260-1261, 2006
- 著者
- 岡田 正彦
- 出版者
- 日本宗教学会
- 雑誌
- 宗教研究 (ISSN:03873293)
- 巻号頁・発行日
- vol.83, no.4, pp.1237-1238, 2010-03-30 (Released:2017-07-14)