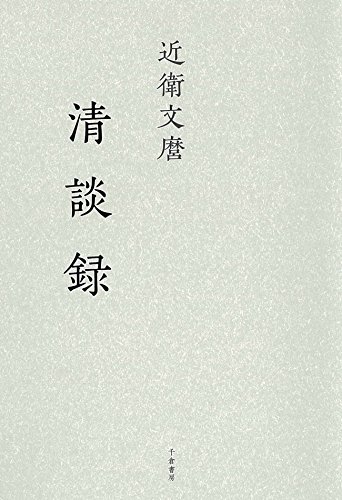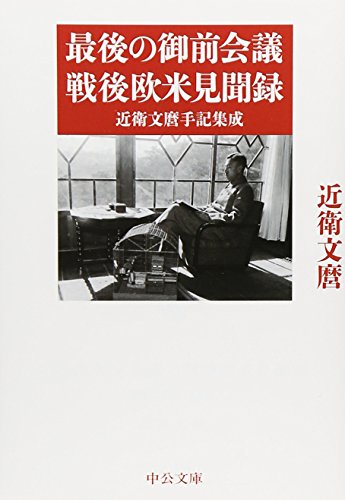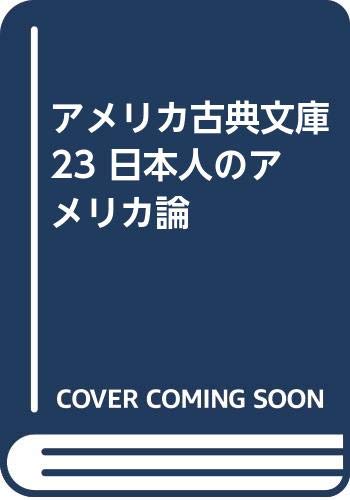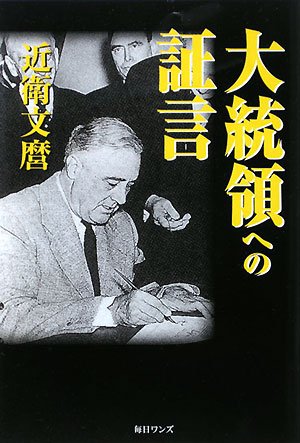1 0 0 0 最後の御前会議/戦後欧米見聞録 : 近衛文麿手記集成
1 0 0 0 革命及宣傳
- 著者
- 近衛文麿 今井時郎 [著]
- 出版者
- 冬夏社
- 巻号頁・発行日
- 1921
1 0 0 0 失はれし政治 : 近衞文麿公の手記
1 0 0 0 近衛日記
- 著者
- 共同通信社「近衛日記」編集委員会編
- 出版者
- 共同通信社開発局
- 巻号頁・発行日
- 1968
1 0 0 0 戰後歐米見聞録 : 全
1 0 0 0 平和への努力 : 近衞文麿手記
1 0 0 0 最後の御前会議 : 近衛文麿公手記
1 0 0 0 知られざる記録
- 著者
- 昭和戦争文学全集編集委員会編
- 出版者
- 集英社
- 巻号頁・発行日
- 1965
1 0 0 0 IR 戦前・戦中の比較プロパガンダ : ドイツ・満州・日本・アメリカ
- 著者
- 田中 公一朗 タナカ コウイチロウ Tanaka Koichiro
- 出版者
- 駒澤大学グローバル・メディア・スタディーズ学部
- 雑誌
- Journal of global media studies : gms = ジャーナル・オブ・グローバル・メディア・スタディーズ
- 巻号頁・発行日
- vol.22, pp.71-87, 2018-03
1 0 0 0 サッカー選手における股関節つまり感とその障害への影響
- 著者
- 和田 卓也
- 出版者
- 九州理学療法士・作業療法士合同学会
- 雑誌
- 九州理学療法士・作業療法士合同学会誌
- 巻号頁・発行日
- vol.2016, pp.270-270, 2016
<p>【はじめに】</p><p>サッカー競技は、スプリント動作やカッティング動作の反復、下肢でのボールコントロールなどの競技特性から下肢障害が多いとされている。また、障害の中でも股関節周辺部の問題(肉離れ、鼠径部痛症候群など)は多く発症しており、障害予防的な観点からも注目すべき点である。そこで今回、股関節機能に焦点を合わし、高校サッカー選手にメディカルチェック(以下、MDC)を実施した。その結果から、股関節つまり感の存在とその障害との関連を検討することを目的とした。</p><p>【対象と方法】</p><p>対象は、高校男子サッカー部員20名40脚中、立位股関節屈曲角度(以下SHF角度)時に股関節つまり感があった11名17脚(年齢16.2±0.6歳、身長171±7.3cm、体重61.4±7.6kg、競技歴9.3±1.9年、利き足:右10名 左1名)とした。MDC測定項目は、指床間距離(以下FFD)、踵殿間距離(以下HBD)、Thomas‐T、Anterior impingement(以下AI)、SHF角度、股関節屈曲・外旋・内旋可動域を測定した。さらに障害歴(現在も症状があるもの)についても問診にて聴取した。これらの各項目間での関係性を統計ソフトR version2.8.1を使用し、シャピロウィルク検定、スピアマンの順位相関係数を用いて算出した。</p><p>【結果】</p><p>統計の結果、FFD・HBD・Thomas‐T・SHF角度・股屈曲角度は相関がみられなかったが、股外旋と股内旋(r‐0.74、p<0.01)で相関がみられた。各項目の結果は、FFD 5.4±5.7cm、HBD -11.4±1.8cm、Thomas‐T -5.4±1.6cm、AI陽性 2名、SHF角度 101.5±6.6度、股関節可動域 屈曲129.4±6.3度、外旋45.9±7.3度、内旋36.5±6.1度、利き足側10名、軸足側5名、両側6名。障害がある選手は8名で、障害歴は、大腿部肉離れ5件、足関節捻挫4件、シンスプリント1件、鼠径部痛1件、腓骨筋腱損傷1件、肋骨痛1件。また、過去に骨盤帯骨折(坐骨骨折、恥骨剥離骨折)の経験ありが2件であった。</p><p>【考察】</p><p>股関節外内旋可動域において負の相関が得られた。これは、外旋可動域が大きく内旋可動域が小さく、その差が大きいことを示している。外旋筋群短縮により股関節の求心位が失われることで、代償筋の過活動や腸腰筋の機能不全が起こり、それが股関節屈曲時のつまり感として現れている可能性が考えられる。また、障害歴は大腿部肉離れや足関節捻挫の件数が多い結果となった。AIに関しては、2名中1名はつまり感と骨盤帯の骨折既往を同時に抱えており、つまり感は器質的疾患の存在も判断し得る可能性が示唆された。以上のことから、股関節のつまり感は、股関節に何らかの機能不全があることを示しており、下肢の土台とされる股関節が機能不全となることで、膝関節や足関節の連動性に問題が生じ、障害に繋がるのではないかと考える。</p><p>【理学療法学研究としての意義】</p><p>MDCの結果、実際につまり感を抱えながら競技を行っている選手の存在が明らかになった。つまり感の有無は、器質的疾患や股関節の機能不全が存在している選手の簡易的な選別になる可能性があり、これに対して、適切な評価と選手へのフィードバックを行うことで、二次障害の予防やパフォーマンス向上に繋がると考える。今後、MDCの測定項目などをさらに検討し、つまり感と障害との関係について探求していきたい。</p><p>【倫理的配慮,説明と同意】</p><p>対象者およびサッカー部所属の監督とコーチには、ヘルシンキ宣言に基づき、事前にMDCの目的と内容を文書及び口頭で十分説明し、同意を得た。</p>
1 0 0 0 中野重治の研究戦前・戦中篇
1 0 0 0 OA 意匠美術写真類聚
- 著者
- 意匠美術写真類聚刊行会 編
- 出版者
- 洪洋社
- 巻号頁・発行日
- vol.第2期 第5輯 (メストロウイッチの彫刻集), 1924
1 0 0 0 OA 液体窒素充てん時の警報および自動停止装置
- 著者
- 春山 富義 吉崎 亮造
- 出版者
- 公益社団法人 低温工学・超電導学会 (旧 社団法人 低温工学協会)
- 雑誌
- 低温工学 (ISSN:03892441)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, no.3, pp.179-180, 1982-06-25 (Released:2010-02-26)
- 参考文献数
- 2
1 0 0 0 OA 脳性麻痺のリハビリテーションに対する近年の考え方と評価的尺度
- 著者
- 近藤 和泉
- 出版者
- The Japanese Association of Rehabilitation Medicine
- 雑誌
- リハビリテーション医学 (ISSN:0034351X)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, no.4, pp.230-241, 2000-04-18 (Released:2009-10-28)
- 参考文献数
- 29
- 被引用文献数
- 2 2
There are now various therapeutic interventions for cerebral palsied children. Many of them were developed based on the theoretical speculation or empiricism, because it was difficult to know the pathophysiological process, which occurred in the injured brain before its development. It, however, is believed that synaptic formation and synaptic rearrangement play a main role in the first instance of motor development. In the therapeutic approach for cerebral palsied children, we should adopt the appropriate strategy based on the knowledge of neuro-developmental science. As same as the other diseases, for the cerebral palsy, we also should treat the various levels of problems, which was classified by WHO as impairments, disabilities (activities), and handicaps (participation). Therapeutic interventions for children with cerebral palsy have been directed mainly toward impairments of this pathological condition, such as spasticity, joint contracture and abnormal movement pattern. We should pay attention for the cerebral palsied children also to their function in the home activities and participation to the social affairs. At the end of the 20th century health professionals are expected to produce evidence of the effectiveness of the treatments that they provided to the clients. What we require in addition are measures that capture the “health status” of people. We have not been making enough effort to evaluate the effectiveness of therapeutic intervention for cerebral palsied children with the scientific documentation. In North America, various scales have been developed in the recent decades under the concept of the framework for health measurement indices. These scales were also standardized and were endurable for multi-institute's use. In the area of rehabilitation of cerebral palsied children, Gross Motor Function Measure (GMFM) and Gross Motor Function Classification System (GMFCS) were developed with this new concept. In this review article, the summary and the process of standardization in Japan of these scales were presented.
1 0 0 0 OA 本草匯18卷補遺1卷圖1卷
- 著者
- 清郭佩蘭撰
- 巻号頁・発行日
- vol.[3], 1000
1 0 0 0 IR 状況理論による法的推論の形式化
- 著者
- 東条 敏 Stephen Wong 新田 克己 横田 一正
- 出版者
- 情報処理学会
- 雑誌
- 情報処理学会論文誌 (ISSN:18827764)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, no.1, pp.51-60, 1995-01-15
- 参考文献数
- 23
- 被引用文献数
- 6
法的推論の研究は、人工知能の研究者にとっても司法の現場からも魅力的な話題であるが、法令文の解釈は常に背後条件や周囲条件に依存するため、その形式化を困難にしている.。本稿の目的は、法的推論のしくみを状況理論の観点から整理し、形式化することである。状況理論は、述語論理のみによる記述系に対して、以下の点で有利である。第一に、状況はそれに対応するルールとファクトの集合を定義できるため、モジュールの概念を用いて計算機上に実装が可能であり、モジュール間の集合演算や継承などを実現できる。第二に、いろいろな状況依存に関わる現象が同じ状況推論のルールの形に書くことができるため、法の適用範囲、背後条件、判例などが、一様な記述系で表現できる。本稿では、ひとつの判例を状況と見立て、その中だけで局所的に成り立つ判例に依存したルール、判例を一般化した状況で成り立つルール、普遍的な状況で成り立つ法令文ルールを区別する。これらルールを薪事件に対応させるため、ルールの中の個体名や変数を新しい個体名に書き替え、ルールの連鎖により新たな法的判断を求めることができるモデルを示す。また、新事件と過去の判例との類似性判断についても、状況理論的に形式化する。この枠組は灼知識べ一スシステムQuixoteを用いて実験的に実装されており、実際の判例を用いて推論のしくみの例を紹介する。