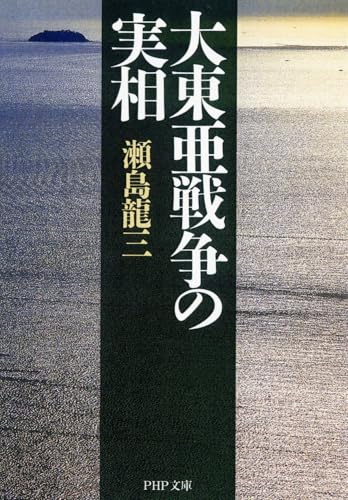1 0 0 0 OA 王状元集百家註分類東坡先生詩 25卷
- 著者
- (宋) 蘇軾 撰
- 巻号頁・発行日
- vol.[1], 1000
1 0 0 0 IR 大学院拡充政策のゆくえ:今どこに立ち,次にどこに向かうのか? (喜多村和之教授追悼特集)
- 著者
- 藤村 正司
- 出版者
- 広島大学
- 雑誌
- 大学論集 (ISSN:03020142)
- 巻号頁・発行日
- vol.47, pp.57-72, 2015-03
A quarter century has passed since the politics of expanding graduate school was promoted by MEXT in Japan. However, the number of applicants and enrollments of graduate students had already peaked by 2000, apart from the time of the Lehman shock. The politics of expansion has brought about various consequences and has arrived at a 'turning point'. The purpose of this paper is to examine the issues of phenomenal enrollment expansion in postgraduate education and to clarify where we presently are. The main findings are as follows; 1) The puzzling fact about Doctoral Courses (DCs) in Japan is that the supply (quota) for such education has continued to rise since the 1990's, although demand for that has been rapidly decreasing since 2000 except for engineering, where employment prospects have been guaranteed. Part of the explanation lies in the fact that the DCs have been considered to develop highly professional human resources regardless of the employment market. 2) Even though the demand for DCs is decreasing, quota regulation by MEXT, which brings capacity close to one hundred percent, makes the quality of graduate students spoiled. 3) The DCs ratio of students going on to higher schools has been increasing, because the numbers of students (denominator) who proceed to MCs has expanded and unemployment has worsened career prospects in academia. So, the number of students who repeat the same grade has doubled since 2000's. 4) Evolution of working adult students and women in graduate school. Today, ten percent of MCs and forty percent of DCs students are adult workers. Thirty years ago, few women chose careers in postgraduate study. In 2013 the ratio of female students of both MCs and DCs doubled in most fields. These findings suggest that there are excessive functions included in Master's programs and that drastic reform is necessary for Japanese Graduate Education to maintain its quality and effectiveness in the changing global economy.
1 0 0 0 OA 疎行列のキャッシュへの適合性分類に関する予備評価
- 著者
- 冨森 苑子 田邊 昇 高田 雅美 城 和貴
- 雑誌
- 研究報告ハイパフォーマンスコンピューティング(HPC)
- 巻号頁・発行日
- vol.2012-HPC-135, no.17, pp.1-7, 2012-07-25
エクサスケールマシンは複雑なメモリシステムとなることが予想されている.同マシンへの適用を視野に入れた疎行列ライブラリの実現に向け,本報告では疎行列のキャッシュへの適合性分類に資する疎行列の特性に関する新しい指標として 「列インデックス列の空間的局所性」 を提案する.さらに,入力疎行列および Fold 法前処理後の提案指標の値をフロリダ大学の疎行列コレクションを用いて評価した.その結果,疎行列ベクトル積処理性能と L1 キャッシュヒット率と新指標の間には有意な相関関係があることが確認できた.よって,従来から指摘していた行列サイズと併せ,本指標をアプリ固有の最適化を避けたメモリアクセス機構や前処理アルゴリズム自動選択の指標の一つとする.
1 0 0 0 OA 庭園の構想に関する研究I
- 著者
- 沢田 天瑞
- 出版者
- 社団法人 日本造園学会
- 雑誌
- 造園雑誌 (ISSN:03877248)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, no.1, pp.23-30, 1972-08-30 (Released:2011-07-19)
- 参考文献数
- 14
The ancient Chinese defines the spirit of zen as the followings; Zen is the name of heart. Thart is the body of Zen.The short sentence of FURI TSUMONJI, KYOGAIBETSUDEN represents also the basic metaphysical thinking of Zen sect, and is svmbolised ollly by a word of MU.It means that the essence of Zen is free or nothing in spirit, but is flexible something like an ecko in the deep valley or a reflected image upon the water.For zen sect gardens, therefore, there are no appreciation rules, and yet no written records about composition of gardens and techniques.The author believes that the zen sect garden is a reflection of human life and its composition represents metaphysical thinking and cosmology rooted in Zen. This is especially true for the ancient notable Zen disciples, in most of cases they were the founders of new temples, that garden is a part of the most ideal demonstration places for their original metaphysics and history of spiritual awakenning through designed forms and ornamentsIt is here that the need for research upon these hypotheses is necessary for knowing true meaning of the garden composition symbolise deeply behind, and for opening up a new method of approaching to study on traditional Japanese garden design.This study, therefore, is designed to clarify the followings;1. to find out the original source of the subject of garden, 2. to identify the main theme of the garden from the source, which is translated into modern language, 3. to analyse the garden composition along the main subject, 4. to conclude the identification by use of plan maps and literary quotations
- 著者
- 山田 朗
- 出版者
- 駿台史学会
- 雑誌
- 駿台史學 (ISSN:05625955)
- 巻号頁・発行日
- no.141, pp.5-16[含 英語文要旨], 2011-03
- 著者
- 辻 庸介 米田 勝一
- 出版者
- 日経BP社 ; 2002-
- 雑誌
- 日経ビジネスassocie (ISSN:13472844)
- 巻号頁・発行日
- vol.16, no.10, pp.4-7, 2017-09
第39回マネーフォワード2012年設立。自動家計簿・資産管理サービス「マネーフォワード」、ビジネス向けクラウドサービス「MFクラウドシリーズ」などを運営。「マネーフォワード」の利用者数は現在約500万人で、「MFクラウドシリーズ」のユーザー数は50万以上。
1 0 0 0 OA 13ア−25−ポ−06 肢体不自由児に対する体育授業の合理的配慮事例集の試作
- 著者
- 松浦 孝明
- 出版者
- 一般社団法人 日本体育学会
- 雑誌
- 日本体育学会大会予稿集 第67回(2016) (ISSN:24241946)
- 巻号頁・発行日
- pp.343_2, 2016 (Released:2017-02-24)
[はじめに] 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律が施行され、教育現場においても施設設備だけでなく、授業内での適切な教材の使用や障害の特性に配慮した指導が求められている。しかし、文部科学省等から合理的配慮事例集が示されているが、体育授業に関する事例はほとんど見られない。本研究では、地域の小学校等に在籍する肢体不自由児に対する合理的配慮事例集を作成し、今後のインクルーシブな体育授業の充実に寄与することを目的とする。[方法] 筑波大学附属桐が丘特別支援学校の教育相談による支援事例および地域の小学校や中学校から転入した児童生徒に対するアンケート結果から、体育授業の参加を困難とすると思われる要因(障害特性、認知特性など)を整理するとともに、適切な配慮について整理する。[まとめ] 体育授業への参加を困難にする要因は、身体の動かしにくさ、ボールや用具の扱いにくさ、車いすなど補助具の利用、視覚情報処理の難しさ等に整理された。また、合理的配慮の事例は、施設設備、教材、指導法、人的配置などに分類し、体育授業全般に共通するものと個別の指導内容に応じたものに整理することで利用しやすい事例集になると思われた。
1 0 0 0 OA 嗅覚ノーベル賞5周年記念 : 嗅覚メカニズムと応用
- 著者
- 倉橋 隆
- 出版者
- 社団法人 におい・かおり環境協会
- 雑誌
- におい・かおり環境学会誌 (ISSN:13482904)
- 巻号頁・発行日
- vol.41, no.2, pp.81-81, 2010-03-25 (Released:2016-04-01)
1980年代頃からの嗅覚関連分野の研究成果の発展には目覚ましいものがある.生理学・生化学,分子生物学の研究から嗅覚受容器細胞での情報変換機構が次々と解明され,嗅覚の受容システムは視覚の機構や生体内のホルモン受容や神経伝達と類似していることが明らかとなった.それらを基盤として1991年にBuck & Axelが「嗅覚受容体」を発見し,その業績に対して2004年にノーベル生理学・医学賞が授与された.この時期には世界中の多くの研究者が嗅覚に対して多角的なアプローチを行い,受容体の機構のみではなく,「不明瞭であった嗅覚の実体」を総合的に解き明かしたかたちになろう.「香りの創生」と言うと,それ以前にはややもすると芸術的・文学的な意味合いが強い分野であったが,この期間に科学のメスが入ったとも解釈でき,時代の大きなうねりの中で,基礎研究はもちろんのこと,香りにかかわる医学・産業・応用の分野にも少なからぬ影響があったことが多くの事例として挙げられる.例えば,今や医学研究ではヒトの細胞を利用して嗅覚・におい分子評価を行う試みがなされている(小林氏の項を参照されたい).また,創香の産業分野(福井氏の項を参照されたい)でも生体分子への効果からにおい分子のパラメータ(例えば悪臭を消すためのマスキング能など,坂井氏の項,竹内・倉橋の項を参照されたい)を推定できるほどになっているほどである.ところで,ノーベル賞に絡む意味で嗅覚の生体システムを分子的に眺めてみると,実はBuck & Axelらの仕事は一例である.嗅覚の情報変換に関与するG蛋白やcAMPは,生体の様々な臓器に共通するが,それぞれを発見したギルマン,ロッドベル(1994),サザーランド(1971)はノーベル賞の受賞に輝いている.分子の発見のみならず,昨今,嗅細胞でも盛んに利用される研究手法として強力な武器になるパッチクランプ法を開発したネーアー,サックマンは1991年の受賞,Ca感受性色素やケージド化合物を開発したツェンは2008年に受賞と,ノーベル賞クラスの研究にからむ事例が満載のシステムであるともいえよう.不斉合成に野依良治博士のテクニックが利用されていることは多くの人の知るところでもある(福井氏).また1987年に利根川進博士が免疫システムの解明に対してノーベル賞を受賞された際,「多様性」の意味で「免疫の次は嗅覚」に興味があると言われたことも思い出される.嗅覚は,複雑性ゆえに取り扱いが困難な一方で偉大な業績に絡む典型的な一例といえ,基礎研究でも魅力的な対象であるといえよう.今回の企画ではBuck & Axelの受賞5周年をきっかけに,「香りにまつわる様々な分野の一線の方たち」から,「嗅覚分野のノーベル賞受賞・科学的隆盛から刺激され発展していること」を執筆していただくことができた.関連する分野として,1.嗅覚の細胞分子生物学,2.嗅覚の心理物理学・生体計測,3.嗅覚研究の臨床医学応用,4.嗅覚研究の産業応用の4分野と広きにわたり,それぞれの専門家,第一人者の先生方からの御執筆を賜るだけでなく,全体を通して相関し,まとまりある内容としての集約性がみられた.基礎科学的内容では,決して嗅覚というトピックスにとどまることなく各分野の時代の最先端を垣間見ることができる.また,嗅覚に関連する医学・産業分野では分野の盛り上がりとともに基礎的知見を応用する可能性が無限に広がる様子が強く伝わってくる.執筆してくださった先生方に厚く感謝するとともに,読者の方々に嗅覚研究や応用の可能性の糸口がつかめるようであればと期待する.
- 著者
- 伊藤 美加 長井 誠 早川 裕二 小前 博文 村上 成人 四ッ谷 正一 浅倉 真吾 迫田 義博 喜田 宏
- 出版者
- 社団法人日本獣医学会
- 雑誌
- The journal of veterinary medical science (ISSN:09167250)
- 巻号頁・発行日
- vol.70, no.9, pp.899-906, 2008-09-25
- 参考文献数
- 39
2007年8月,石川県金沢競馬場において馬インフルエンザが発生した.感染馬の症状は主に発熱(38.2-41.0℃)および鼻汁漏出で,呼吸器症状を示した馬はわずかであった.全ての競走馬は不活化ワクチンを接種しており,ワクチンにはH3N8馬インフルエンザウイルス,アメリカ系統のA/equine/La Plata/93株,同じくヨーロッパ系統のA/equine/Avesta/93株,およびH7N7馬インフルエンザのA/equine/Newmarket/1/77株が含まれていた.鼻腔スワブ材料からH3N8馬インフルエンザが分離され,A/equine/Kanazawa/1/2007と命名した.系統樹解析では,A/equine/Kanazawa/1/2007株はアメリカ系統のフロリダ亜系統に属した.さらに,HA1サブユニットのアミノ酸解析を行ったところ,同じアメリカ系統のワクチン株であるA/equine/La Plata/93株と比較して,BおよびEの抗原決定部位に4アミノ酸の置換が認められた.また,回復期の馬16頭から採材した血清を用いて赤血球凝集抑制反応を実施したところ,A/equine/Kanazawa/1/2007株とワクチン株間に1〜3管の差が認められた.これらの結果から,流行株とワクチン株に抗原性状の差が示唆されたが,わが国の現行市販ワクチンは罹患率の低下や発症期間の短縮に貢献したと思われた.
1 0 0 0 牛ウイルス性下痢ウイルス2の石川県における浸潤状況
- 著者
- 長井 誠 源野 朗 村上 俊明 高井 光 上地 正英 明石 博臣
- 出版者
- Japan Veterinary Medical Association
- 雑誌
- 日本獣医師会雑誌 (ISSN:04466454)
- 巻号頁・発行日
- vol.51, no.9, pp.487-490, 1998
牛ウイルス性下痢ウイルス (BVDV) 2の石川県における浸潤状況を, 成牛1, 625頭, 2歳未満牛217頭, 豚298頭, あん羊57頭, 山羊12頭および鹿19頭について血清学的に調査した. BVDV 2; KZ-91株に対する抗体は成牛の1.1%にのみ認められ, 1986年以降の保存血清 (約1歳牛) では, 1988年の70例中1例, 1998年の51例中2例, 1994年の27例中1例が陽性であった. 1990-1997年に分離されたBVDV 10株について, 5'非翻訳領域を標的としたRT-PCRにより制限酵素 (<I>Pst</I> I) 切断パターンを調べたところ, 1990年に分離された2株がBVDV 2に分類された
1 0 0 0 OA 差分法に基づくフレネルホログラムの高速計算法
- 著者
- 岩瀬 進 吉川 浩
- 出版者
- 一般社団法人 映像情報メディア学会
- 雑誌
- 映像情報メディア学会誌 (ISSN:13426907)
- 巻号頁・発行日
- vol.52, no.6, pp.899-901, 1998-06-20 (Released:2011-03-14)
- 参考文献数
- 8
- 被引用文献数
- 4
ホログラムが微細な画素構造を有していることから, 隣接した画素間の差分を利用して計算機合成ホログラムを高速に近次計算する方法を検討した.その結果, 再生像に影響しない範囲で高速な計算が実現できた.
1 0 0 0 近衛文麿「六月終戦」のシナリオ
1 0 0 0 OA 官報
- 著者
- 大蔵省印刷局 [編]
- 出版者
- 日本マイクロ写真
- 巻号頁・発行日
- vol.1888年02月02日, 1888-02-02
1 0 0 0 OA 給食における供食温度の継時的変化――適温給食のための食事計画――
- 著者
- 上延 麻耶
- 出版者
- 名古屋経済大学 自然科学研究会
- 雑誌
- 名古屋経済大学自然科学研究会会誌 = Journal of the natural scientific society of nagoya keizai university (ISSN:13488058)
- 巻号頁・発行日
- vol.49, no.1・2, pp.63-67, 2016-10-31