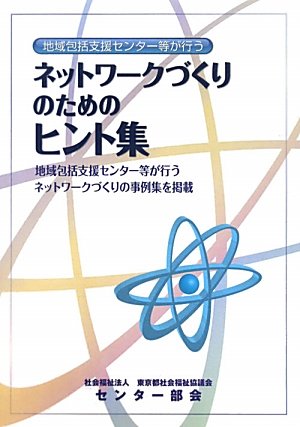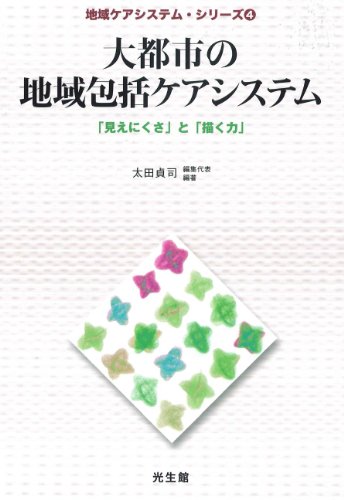1 0 0 0 地域包括支援センター等が行うネットワークづくりのためのヒント集
- 著者
- 東京都社会福祉協議会センター部会編
- 出版者
- 東京都社会福祉協議会
- 巻号頁・発行日
- 2011
1 0 0 0 大都市の地域包括ケアシステム : 「見えにくさ」と「描く力」
- 著者
- 太田貞司編集代表・編著
- 出版者
- 光生館
- 巻号頁・発行日
- 2012
1 0 0 0 平均スペクトル等化の検討(合成, 韻律, 生成, 一般)
- 著者
- 倪 晋富 河井 恒 津崎 実
- 出版者
- 一般社団法人電子情報通信学会
- 雑誌
- 電子情報通信学会技術研究報告. SP, 音声 (ISSN:09135685)
- 巻号頁・発行日
- vol.103, no.263, pp.19-24, 2003-08-14
波形素片接続型音声合成の音質を向上させようとすると,大規模な音声コーパスが必要となり,結果的に音声収録に数ヶ月〜数年という長期間を要する。録音セッションが異なると録音系の特性が変化する可能性があり,その結果多少とも声質が変化する。本稿では,1名の男性話者が2年間に677回発声した同一の日本語文の音声データを試料として用い,長時間平均パワースペクトルの等価に関する実験を行った結果について報告する。まず,フレーム長の設定など,長時間平均パワースペクトル推定の最適条件について検討する。さらに,4種類のフィルタ,すなわちLPC係数を介して設計されたIIRフィルタ,MLSAフィルタ,ケプストラムにもとづく平滑化を伴うFIR,メルケプストラムにもとづく平滑化を伴うFIR,を等価フィルタとして取り上げ,それぞれの最適な設計条件を検討する。各フィルタの等価効果の比較は,等価対象音声の音響的特微量のガウス分布に関する尤度にもとづいて行う。予備的な主観評価実験の結果,提案手法が録音系周波数特性の等価に有効であり,かつ音質劣化を生じないことが示唆された。
- 著者
- 河井 恒
- 出版者
- 一般社団法人電子情報通信学会
- 雑誌
- 電子情報通信学会技術研究報告. SP, 音声 (ISSN:09135685)
- 巻号頁・発行日
- vol.105, no.97, pp.19-24, 2005-05-19
- 被引用文献数
- 4
筆者らが100時間超の大規模音声コーパスを用いる波形素片接続型音声合成システムを開発した過程で得た知見にもとづいて、(1)音声コーパス規模と合成音声の音質の関係、(2)コーパス設計手法とその効果、(3)音声コーパス作成手順と若干のノウハウ、(4)音素自動セグメンテーションの精度と有効性、(5)声質変動、に関して述べる。
- 著者
- 西澤 信行 河井 恒
- 出版者
- 一般社団法人電子情報通信学会
- 雑誌
- 電子情報通信学会技術研究報告. SP, 音声 (ISSN:09135685)
- 巻号頁・発行日
- vol.105, no.572, pp.67-72, 2006-01-20
最良優先探索に基づく素片選択処理について検討を行う. 多くの素片接続型音声合成システムでは, 動的計画法に基づく素片選択処理が行われているが, それ以外の探索手法として, ヒューリスティックを基づく手法が考えられる. 本研究ではA^*アルゴリズムに着目し, 許容的でないヒューリスティック関数を用いた場合も考慮した, 素片選択アルゴリズムを導入する. 素片選択処理において, 複雑な処理を要するヒューリスティック関数の導入は現実的ではないことから, 本研究では, 平均コストを用いた単純なヒューリスティック関数を用いることとした. 実際の素片選択処理では, 可能な処理時間が限られているが, これに対応する実験として, 従来法であるビームサーチを併用した動的計画法に基づく探索と, 最良優先探索のそれぞれについて, 接続コスト計算回数が同一条件となるような素片選択実験を行い, それら結果をコスト上で比較した. 実験結果では, 従来手法と比較し, 最良優先探索により良い結果を得ることができなかったが, 素片選択への最良優先探索適用は, 同一仮説の重複展開の影響による探索の非効率性が現れやすいものと考えられる.
1 0 0 0 VCV規則音声合成の素片選択において考慮すべき音韻環境の長さ
- 著者
- 木本 雅也 並木 寿枝 清水 忠昭 井須 尚紀 菅田 一博
- 出版者
- 一般社団法人電子情報通信学会
- 雑誌
- 電子情報通信学会技術研究報告. SP, 音声 (ISSN:09135685)
- 巻号頁・発行日
- vol.101, no.270, pp.31-38, 2001-08-23
小規模な応用に向けたVCV規則音声合成方式において, 素片選択の為の2つの基準, i)音韻環境類似度とii)LSP距離による素片の接続歪みについて実験的に検討した.前者を採用した方式は, 後者より各素片に音韻環境情報を余分に付加しておかなければならない.後者を採用した場合, 前者より素片選択処理に時間を要する.VCV音素単位を選択するときに考慮する音韻環境の長さを短く出来れば, 音素片辞書の記憶容量を小さく出来る.筆者らは, 音質を保ちながら音韻環境の長さをどこまで短く出来るかを実験で調べた.実験の結果, 先行2音韻・後続1音韻にまで削減して素片選択しても, 先行5音韻・後続5音韻で素片選択した音声とほぼ同品質の音声を合成出来ることが判った.
1 0 0 0 波形接続型テキスト音声合成における素片選択コストの知覚的評価
- 著者
- 戸田 智基 河井 恒 津崎 実 鹿野 清宏
- 出版者
- 一般社団法人電子情報通信学会
- 雑誌
- 電子情報通信学会技術研究報告. SP, 音声 (ISSN:09135685)
- 巻号頁・発行日
- vol.102, no.291, pp.19-24, 2002-08-22
- 被引用文献数
- 2
素片選択に基づく波形接続型テキスト音声合成において自然性の高い合成音声を得るためには,知覚特性に一致したコストを用いることが重要である.本稿では知覚実験により求めた知覚スコアを用いることにより,コストの知覚特性に基づく評価を行う.その際に,コストと知覚スコア間の対応関係を明らかにするだけでなく,素片系列のコストを求めるために必要な各素片におけるコストを統合する関数についても検討する.実験結果から,合成音声全体における平均的な自然性劣化を表す平均コストは,局所的な自然性劣化を表す最大コストよりも知覚スコアとの対応が良いことを示す.また,平均的な自然性劣化と局所的な自然性劣化の両方を考慮するコストであるRMSコストを用いた際に,最も知覚スコアとの対応が良いことも示す.さらに,RMSコストによる素片選択に関しての検討を行うことにより,RMSコスト使用時には局所的な大きな自然性劣化を防ぐために,より短い単位の素片が多く用いられる傾向があることを示す.
- 著者
- 戸田 智基 河井 恒 津崎 実 鹿野 清宏
- 出版者
- 一般社団法人電子情報通信学会
- 雑誌
- 電子情報通信学会技術研究報告. SP, 音声 (ISSN:09135685)
- 巻号頁・発行日
- vol.101, no.603, pp.45-52, 2002-01-17
- 被引用文献数
- 2
本稿では, 日本語テキスト音声合成(TTS : Text-to-Speech)における新たな単位選択法を提案する.日本語では, 母音の無声化を除くとCV(C : 子音, V : 母音)とVから音節が構成されるため, 合成単位としてCV単位がよく用いられる.しかし, 波形接続型のTTSにおいてCV単位を用いて音声を合成すると, VからVへの接続によりしばしば不連続感が生じる.V-V接続を防ぐためにより長い単位(CV^*単位や可変長単位)がこれまでに提案されているが, V-V接続の問題はまだ解決されていない.そこで, V-V接続により生じる不連続感を低減する手法として, 音素単位とダイフォン単位に基づいた新たな単位選択法を提案する.提案法では, 音素境界における接続だけでなく, 母音中心における接続も考慮して単位選択が行われる.評価実験結果から, 提案法は音素単位に基づいた従来法と比較し, よりよい性能をもっことが明らかになった.
- 著者
- 曲 暁范
- 出版者
- 大谷大学真宗総合研究所
- 雑誌
- 真宗総合研究所研究紀要 (ISSN:13432753)
- 巻号頁・発行日
- no.26, pp.33-46, 2007
- 著者
- 矢野 哲也 酒井 將成 須藤 誠一
- 出版者
- 一般社団法人日本機械学会
- 雑誌
- 年次大会講演論文集 : JSME annual meeting
- 巻号頁・発行日
- vol.2010, no.6, pp.71-72, 2010-09-04
Recently, many researchers have been developing the various types of micro aerial vehicles (MAV). These developments are conducted on the basis of the computational and experimental fluid dynamics studies. We believe that the findings from the winged seed of plants would serve useful information for the development of such aerial vehicles. In this study, we investigated the gliding performance of the winged seed of Alsomitra macrocarpa. Furthermore, the microasperity structure on the surface of the seed was observed and measured using the conforcal laser microscope.
1 0 0 0 OA 改正商法釈義
- 著者
- 日本法律学校内法政学会 編
- 出版者
- 修学堂[ほか]
- 巻号頁・発行日
- 1899
1 0 0 0 OA 商法修正案参考書 : 附・商法修正案正文
- 出版者
- 八尾書店
- 巻号頁・発行日
- 1898
1 0 0 0 OA 改正商法釈義 : 附・改正商法施行法
1 0 0 0 OA ミヒャエル・エンデとロマン主義
- 著者
- 石田 喜敬
- 出版者
- 関西学院大学
- 雑誌
- 人文論究 (ISSN:02866773)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, no.3, pp.185-203, 2007-12-10
1 0 0 0 未固結堆積物の変形挙動
一般に石化作用や続成作用が十分に進行していない堆積性の物質を意味する, 未固結堆積物の定量的な定義を試みた。さらに未固結堆積物の変形挙動とその構成則および変形の素過程に関する主に工学分野の理論的研究を紹介した。その剪断変形挙動は岩相によって大きく異なり, さらに泥質なものでは先行圧密履歴と排水・非排水条件に, 砂質なものでは初期間隙比と排水・非排水条件に大きく支配される。また, 未固結堆積物を主要構成物質とする現世の付加体前縁部の変形構造に関する研究, および深海底掘削試料や人工試料を用いた実験的な研究を簡単にまとめた。