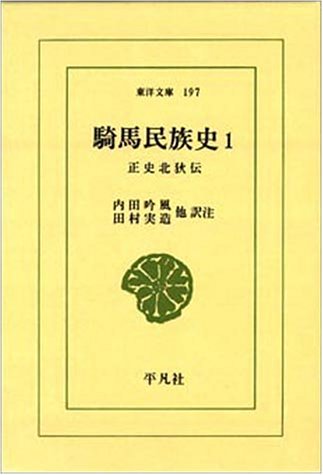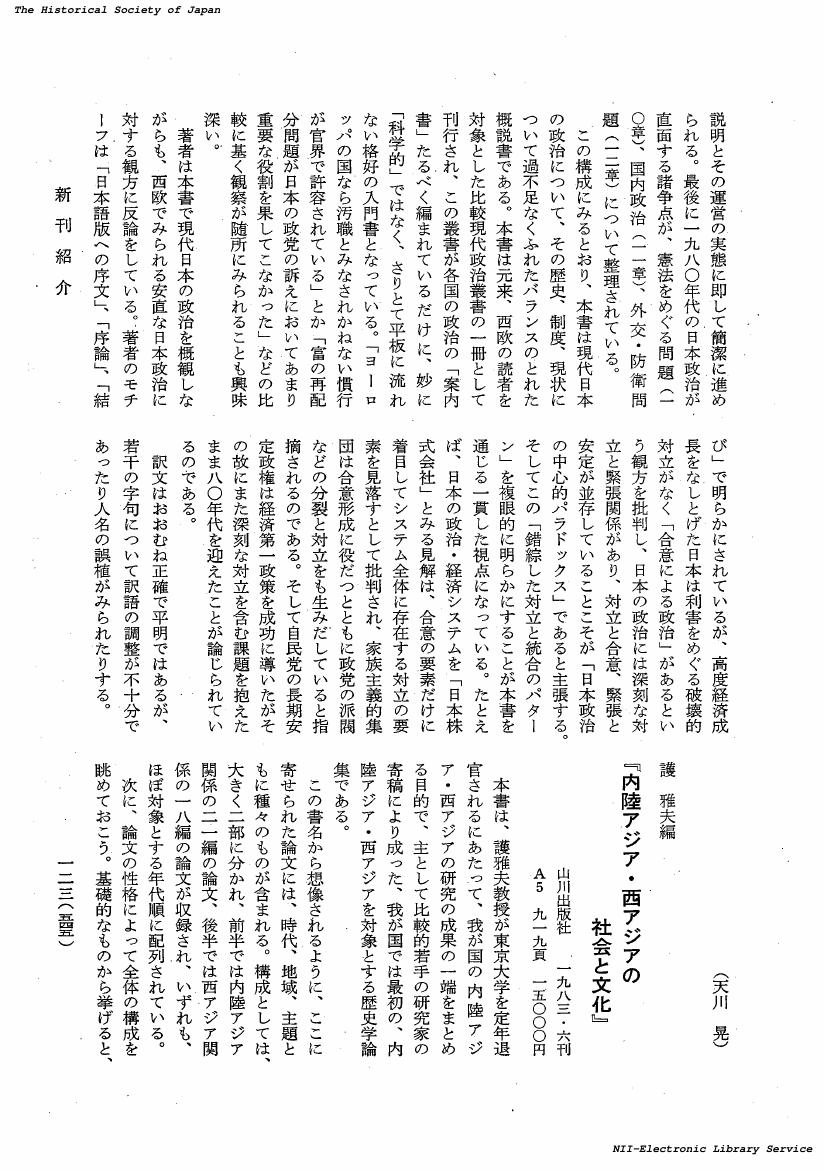2 0 0 0 OA 不便の効用に着目したシステムデザインに向けて
- 著者
- 川上 浩司
- 出版者
- ヒューマンインタフェース学会
- 雑誌
- ヒューマンインタフェース学会論文誌 (ISSN:13447262)
- 巻号頁・発行日
- vol.11, no.1, pp.125-134, 2009-02-25 (Released:2019-09-04)
- 参考文献数
- 32
- 被引用文献数
- 13
This paper presents a viewpoint of "benefit of inconvenience" based on the symbiotic thought and discusses several issues in the research field of systems design. Convenience generally implies "saving labor. " Designers aim to develop goods for sparing humans labor based on the assumption that "the more convenient life is, the richer it is." This assumption has yielded technical developments and outcomes that we generally appreciate. On the other hand, technologies have brought about several problems. One of the way to overcome such problems is pursuing further developments and convenience. But in the case where such developments yield further problems, symbiotic thought doubts of the final destination of this way. An alternative way is to get back to the basic focus on the problems. Benefits of inconveniences navigate us to the promising ways. Inconvenience enhances awareness, prompts creative contribution, and brews affirmative feeling.
2 0 0 0 OA 一谷嫩軍記 : 筑後芝居
- 出版者
- 本清
- 巻号頁・発行日
- 1859
2 0 0 0 OA 魯迅と白村、漱石
- 著者
- 林 叢
- 出版者
- 日本比較文学会
- 雑誌
- 比較文学 (ISSN:04408039)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, pp.77-90, 1995-03-31 (Released:2017-06-17)
Prior to or following the writing of Yaso (『野草』Wild Grass), Lu Xun took an interest in Hakuson Kuriyagawa and translated his Kumon no Shocho (『苦悶の象徴』 Symbol of Anguish) and Zoge no Towo Dete (『象牙の塔を出て』 Leaving the Ivory Tower). Through these translations Lu Xun came to agree with Hakuson's view of literature and absorbed it on his own terms. This point is clear in the criticisms, essays, and prefaces which he wrote at this time. We can see the influence of Hakuson’s literature and theory of dreams on the style and technique used in Yaso. Furthermore, Hakuson’s criticism of Soseki must have attracted the attention of Lu Xun who also had an interest in Soseki. When we think about the connection between Yaso and Soseki’s Yume Juya (『夢十夜』 Ten Nights’ Dreams), it can be seen that Hakuson’s criticism of Soseki was an inspiring intermediary for the author. In this paper I will illustrate two points: Lu Xun’s view of Hakuson and his interest in Soseki via Hakuson. For this purpose, I will employ an analysis of the translations of Kumon no Shocho and Zoge no To wo Dete, the prefaces and afterwords of these translations, papers written at this time, Yaso, and so forth.
2 0 0 0 OA 一言芳談抄 : 2巻
- 出版者
- 林甚右衛門
- 巻号頁・発行日
- vol.[2], 1648
2 0 0 0 OA 一言芳談句解 : 2巻
- 著者
- 元師 述
- 出版者
- 大森太右衛門 [ほか]
- 巻号頁・発行日
- vol.[4], 1688
2 0 0 0 OA 市川三升円 : 3巻
2 0 0 0 OA 「第三の場」としての学校図書館
- 著者
- 久野 和子
- 出版者
- 日本図書館研究会
- 雑誌
- 図書館界 (ISSN:00409669)
- 巻号頁・発行日
- vol.63, no.4, pp.296-313, 2011-11-01 (Released:2017-05-24)
- 被引用文献数
- 1
本稿は,日本の学校図書館について,アメリカで注目されている「場としての図書館」研究を導入し,実証的な検討を行った初めての試みである。学校図書館という場を包括的,多元的に考察することによって,子どもたちの学びや学校生活の中で果たすべき場としての学校図書館の役割と機能の一端を示すことを目的とする。先行研究として塩見の「ひろば」論などをふまえた上で,オールデンバーグの「第三の場」を主要な概念的枠組みとして採用し,検討する。そして,学校図書館が「第三の場」の空間を包摂しうることを実証的に明らかにした上で,その教育的意義を,ボルノウの教育論,パットナムの社会関係資本論,生涯学習論に基づいて提示する。
2 0 0 0 OA 伊曽保物語 3巻
- 巻号頁・発行日
- 1600
イソップ物語を翻訳した仮名草子。前段は伊曽保の伝記、後段は喩言の構成をもつ。『伊曽保物語』の国字本(キリシタン版のローマ字本に対する称呼)は、慶長・元和から寛永年間にかけて、数次にわたり活字開版が行われた。当館本は、〔慶長・元和年間〕刊の平仮名交じり古活字版で、最も古い刊本のひとつとされている。各巻首に目録を付し、上巻20話、中巻40話、下巻34話からなり、挿図はない。尾張徳川家旧蔵の善本類のひとつで、のち幕末・明治の蔵書家中川得基の手に帰していたものである。
2 0 0 0 西アジア世界
- 著者
- 荒松雄 [ほか] 編集委員
- 出版者
- 岩波書店
- 巻号頁・発行日
- 1969
2 0 0 0 騎馬民族史 : 正史北狄伝
- 著者
- 内田吟風 田村実造 [ほか] 訳注
- 出版者
- 平凡社
- 巻号頁・発行日
- 1971
- 著者
- 柳橋 博之
- 出版者
- 公益財団法人 史学会
- 雑誌
- 史学雑誌 (ISSN:00182478)
- 巻号頁・発行日
- vol.93, no.4, pp.545-546, 1984-04-20 (Released:2017-11-29)
2 0 0 0 OA 護雅夫先生を偲んで
- 著者
- 梅村 坦
- 出版者
- 東洋文庫
- 雑誌
- 東洋学報 = The Toyo Gakuho (ISSN:03869067)
- 巻号頁・発行日
- vol.79, no.1, pp.105-111, 1997-06