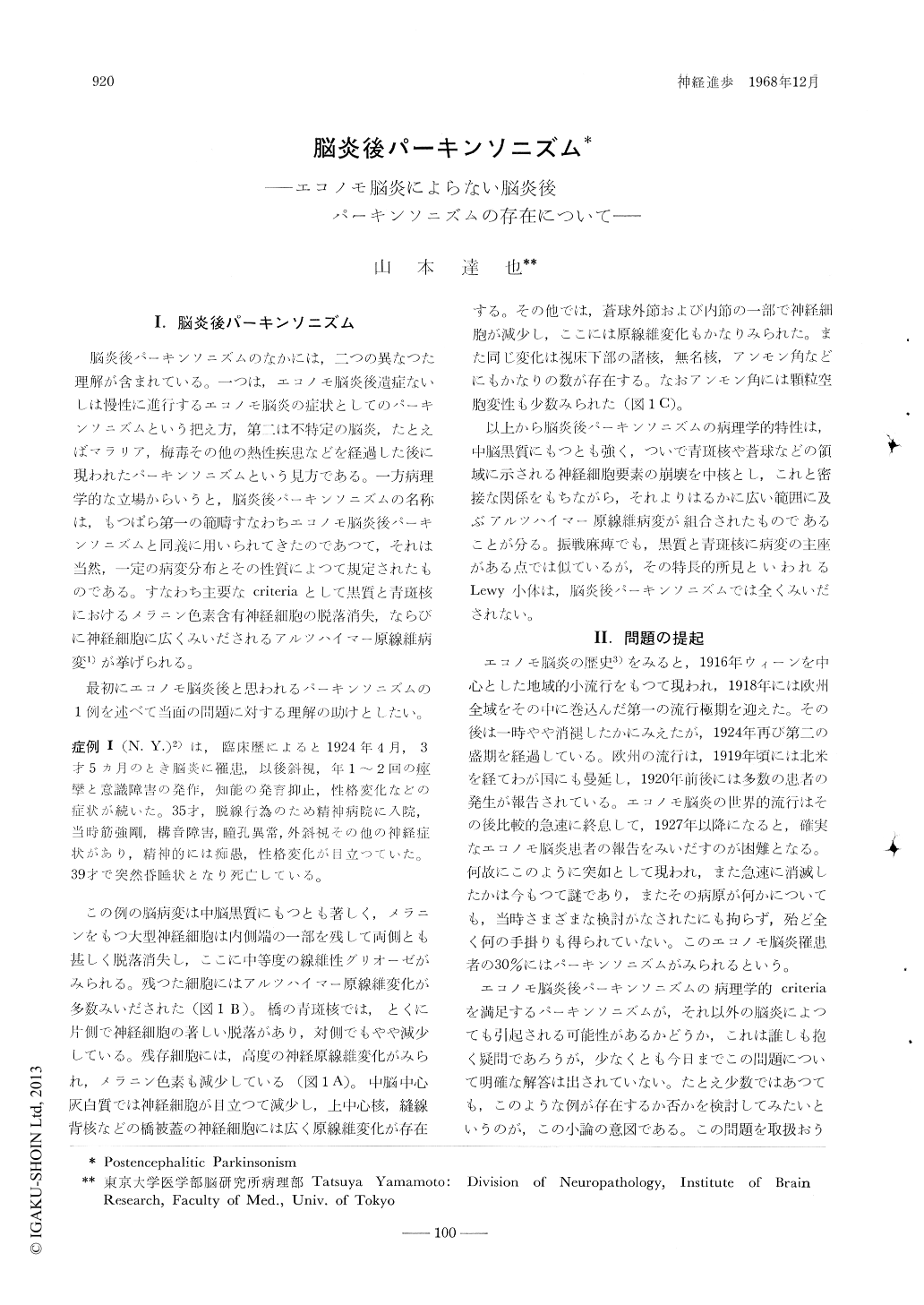7 0 0 0 OA イヌにおける腹部CT撮影により得られた体脂肪組織量とBCS評価の相関性
- 著者
- 神田 鉄平 前田 憲孝 井口 亜弥乃 柴田 和紀 野村 千晴 山本 達也 村尾 信義 加計 悟 古本 佳代 古川 敏紀
- 出版者
- 日本ペット栄養学会
- 雑誌
- ペット栄養学会誌 (ISSN:13443763)
- 巻号頁・発行日
- vol.14, no.Suppl, pp.Suppl_77-Suppl_78, 2011-10-01 (Released:2011-12-20)
- 参考文献数
- 2
イヌにおけるBCS評価の客観性および妥当性の向上を目的に、腹部CT撮影画像から算出された体脂肪組織量との相関性についての検討を行った。BCS評価はCT画像から得られた体脂肪組織量と有意に相関し、その基準が外観や触感といった間接的なものではあるものの、イヌの体脂肪組織量をある程度正確に反映していることが示唆された。
- 著者
- 山本 達也 大野 貴司
- 出版者
- 岐阜経済大学地域経済研究所
- 雑誌
- 地域経済 (ISSN:03866122)
- 巻号頁・発行日
- vol.35, pp.1-13, 2016-03
自由投稿論文Free Contributions
5 0 0 0 OA EROI指標が示す国際的なエネルギー危機と再生可能エネルギーをめぐる公共政策への示唆
- 著者
- 山本 達也 Tatsuya YAMAMOTO
- 雑誌
- 清泉女子大学紀要 = Bulletin of Seisen University (ISSN:05824435)
- 巻号頁・発行日
- pp.71-92,
- 著者
- 山本 達也
- 出版者
- 慶応義塾
- 雑誌
- 三田評論 (ISSN:1343618X)
- 巻号頁・発行日
- no.1149, pp.28-33, 2011-10
- 著者
- 山本 達也
- 出版者
- 中東調査会
- 雑誌
- 中東研究 (ISSN:09105867)
- 巻号頁・発行日
- vol.2011, no.2, pp.19-25, 2011-09
2 0 0 0 OA ポスト・コロナ時代における「旅」の価値の変質に関する検討
- 著者
- 山本 達也 岡本 岳大 Tatsuya Yamamoto Takehiro Okamoto
- 雑誌
- 清泉女子大学紀要 = Bulletin of Seisen University (ISSN:05824435)
- 巻号頁・発行日
- pp.121-140,
2 0 0 0 OA バフンウニ生殖腺の苦味の発現頻度
2 0 0 0 OA LLC共振形コンバータ用トランスに使用するリッツ線の素線数の検討
- 著者
- 茶位 祐樹 山本 達也 金野 泰之 川原 翔太 卜 穎剛 水野 勉 山口 豊 狩野 知義
- 出版者
- The Japan Society of Applied Electromagnetics and Mechanics
- 雑誌
- 日本AEM学会誌 (ISSN:09194452)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, no.2, pp.332-337, 2018 (Released:2018-08-23)
- 参考文献数
- 13
- 被引用文献数
- 1
In this paper, the results of examining the number of strands for high efficiency and low heat generation of litz wire used for transformer of LLC resonant converter are described. Converter used for switching power supplies are required to be smaller and more efficient. To reduce the size of the converter, examinations have been made by increasing the frequency of the driving frequency. However, due to the high frequency, heat generation in the winding increase due to an increase in AC resistance in the transformer, which is one of the programs of high frequency. In view of this, we study reduction in heat generation by making the wire diameter of the winding constant and changing the number of strands. As a results, it is possible to improve efficiency of the LLC converter by 0.3 % and suppress heat generation of the transformer at 37 °C.
2 0 0 0 石油減耗期におけるエネルギー技術政策の制約と国際秩序への影響
- 著者
- 山本 達也
- 出版者
- 名古屋商科大学
- 雑誌
- NUCB journal of economics and information science (ISSN:13466097)
- 巻号頁・発行日
- vol.55, no.2, pp.251-266, 2011-03
- 著者
- 山本 達也
- 出版者
- 日本緑化センタ-
- 雑誌
- グリ-ン・エ-ジ (ISSN:02879654)
- 巻号頁・発行日
- vol.38, no.3, pp.16-20, 2011-03
- 著者
- 山本達也
- 出版者
- 日本現代中国学会
- 雑誌
- 現代中国 (ISSN:04352114)
- 巻号頁・発行日
- vol.2022, no.96-2, pp.19-27, 2022 (Released:2023-08-25)
1 0 0 0 ニュー・ローカルと二十一世紀的なコモンズの創造に向けて
- 著者
- 山本 達也
- 出版者
- 渋沢栄一記念財団
- 雑誌
- 青淵 (ISSN:09123210)
- 巻号頁・発行日
- no.873, pp.31-33, 2021-12
1 0 0 0 OA 中東における情報化の進展と政治的変化
- 著者
- 山本 達也
- 出版者
- JAPAN ASSOCIATION OF INTERNATIONAL RELATIONS
- 雑誌
- 国際政治 (ISSN:04542215)
- 巻号頁・発行日
- vol.2005, no.141, pp.115-131,L14, 2005-05-29 (Released:2010-09-01)
- 参考文献数
- 41
The purpose of this paper is to examine how the external environments of Middle Eastern governments, which require a serious commitment to the promotion of Information and Communications Technology (ICT), affect policies to control Internet information flow, and how it leads to a change in their domestic politics.Currently, we cannot confirm any leading hypotheses about the impacts of the Internet on authoritarian regimes that are widely accepted by political scientists. The main reasons for this is lack of statistical data, difficulties in obtaining sufficient material to discuss this theme, and the low Internet penetration rates in such countries.Of course, these hypotheses must surely exist in the Middle East and undoubtedly the relationship between Internet development and the political impacts on authoritarian regimes is an attractive research topic. However, the reasons mentioned above have caused certain limitations in carrying out such research. Therefore, this paper focuses on the regimes' Internet controlling policies, which is designed to block the free flow of information, and tries to expose the implications of political influences on authoritarian regimes by Internet development.When we focus on Internet controlling policies in authoritarian regimes, we should carefully assess the degree of governmental interference to the flow of information on the Internet. As figure 1 in my paper indicates, conceptually there are two different types of models regarding Internet controlling in authoritarian regimes. One model is that the government mediates and tries to control the flow of information on the Internet (model C), and the other model is that the government renounces Internet control completely (model D).There are two effective concepts to classify authoritarian regimes into model C or model D. The first concept is “network architecture, ” which is defined as the structural character of a network based on a code (software). The second concept is “network infrastructure architecture, ” which is defined as the physical structure of infrastructure to ensure data communication.As a result of my examination, most of the Middle Eastern countries such as Syria, Tunisia, UAE, Bahrain, Qatar, Saudi Arabia, Lebanon, and Egypt are categorized as model C, with only Jordan categorized as model D. The difference between Jordan and the other countries is explained by the engagement of US governmental organization on ICT strategy-making and revising processes, and the leadership of King Abdullah II, the head of the regime, who favors the introduction of policies that create competition in the ICT sector.The Jordanian decision to adopt model D leads a change in policymaking processes in the ICT field in Jordan, with transparency and accountability indubitably improved in this country. My paper concludes that the Jordanian case implies authoritarian regimes could adopt model D while keeping their authoritarian characters, and the perception and leadership of these regimes' heads would grasp the key for this change.
1 0 0 0 神経疾患における排尿排便障害パーキンソン病を中心として
- 著者
- 榊原 隆次 内山 智之 劉 志 山本 達也 伊藤 敬志 服部 孝道
- 雑誌
- 自律神経 = The Autonomic nervous system (ISSN:02889250)
- 巻号頁・発行日
- vol.42, no.1, pp.9-16, 2005-02-15
- 参考文献数
- 13
- 著者
- 山本 達也
- 出版者
- 一般社団法人 日本建築学会
- 雑誌
- 日本建築学会計画系論文報告集 (ISSN:09108017)
- 巻号頁・発行日
- vol.445, pp.133-139, 1993-03-30 (Released:2017-12-25)
This paper researches about development of dervish lodge that relates with popularization of Sufism. Various bektash dervish lodges in Turkiye were analysed in this research. Popularization of Sufism had two steps. First, Sufism joined men came to the stage, constructing tombs, meeting and pilgrimage rooms which had axis and Islamic proportion were built. Second step was patterned training (style of whirling dance). Beside to whirling dance room, library, Turkish bath and madrasa were constructed. In these buildings Islamic proportion and axis couldn't seem except the axis through Mecca.
- 著者
- 山本 達也
- 出版者
- 医学書院
- 雑誌
- 神経研究の進歩 (ISSN:00018724)
- 巻号頁・発行日
- vol.12, no.4, pp.920-924, 1968-12-25
I.脳炎後パーキンソニズム 脳炎後パーキンソニズムのなかには,二つの異なつた理解が含まれている。一つは,エコノモ脳炎後遺症ないしは慢性に進行するエコノモ脳炎の症状としてのパーキンソニズムという把え方,第二は不特定の脳炎,たとえばマラリア,梅毒その他の熱性疾患などを経過した後に現われたパーキンソニズムという見方である。一方病理学的な立場からいうと,脳炎後パーキンソニズムの名称ば,もつぱら第一の範疇すなわちエコノモ脳炎後パーキンソニズムと同義に用いられてきたのであつて,それは当然,一定の病変分布とその性質によつて規定されたものである。すなわち主要なcriteriaとして黒質と青斑核におけるメラニン色素含有神経細胞の脱落消失,ならびに神経細胞に広くみいだされるアルツハイマー原線維病変1)が挙げられる。 最初にエコノモ脳炎後と思われるパーキンソニズムの1例を述べて当面の問題に対する理解の助けとLたい。
1 0 0 0 OA アフリカゾウの妊娠維持における胎盤性プロラクチン様物質の生理的役割に関する研究
- 著者
- 山本 ゆき 山本 達也 ALLEN Twink STANSFIELD Fiona 渡辺 元 永岡 謙太郎 田谷 一善
- 出版者
- 日本繁殖生物学会
- 雑誌
- 日本繁殖生物学会 講演要旨集 第104回日本繁殖生物学会大会
- 巻号頁・発行日
- pp.223, 2011 (Released:2011-09-10)
【背景と目的】ゾウの生殖メカニズムには未解明な点が多く,妊娠維持機構もその一つである。ゾウの妊娠期間は,約22ヶ月間と,陸上哺乳類で最も長く,卵巣には,妊娠期を通して複数の大きな黄体が存在している。アフリカゾウの胎盤では,ステロイドホルモンの合成が行われていないと考えられており,妊娠全期間を通して,プロジェステロン(P)は黄体から分泌されていると推察される。しかし,妊娠期中の黄体を刺激する因子は未だ発見されていない。私共は,ゾウの妊娠後半期に、血中プロラクチン(PRL)濃度が高値を示し、胎盤中にはPRL様物質が含有されていることを明らかにしてきた。本研究では,ゾウの妊娠維持機構の解明を目的として,アフリカゾウの全妊娠期間を通した胎盤中PRL様物質の局在を解析し,P分泌との関連性を検討した。 【材料と方法】南アフリカ共和国およびジンバブエで淘汰された妊娠アフリカゾウ38頭から,妊娠初期から末期にかけての胎盤および子宮内膜を採取し,抗ヒトPRL抗体を用いて免疫組織化学染色を行った。 【結果】着床前の,子宮内膜に接着している栄養膜細胞において,明瞭なPRL様物質の陽性反応が認められ、子宮内膜腺にもわずかに陽性反応が認められた。着床以降の胎盤組織においても,全妊娠期間を通し胎盤の栄養膜細胞に明瞭な陽性反応が認められた。 【考察】これらの結果から,アフリカゾウの妊娠期において,着床前の段階から栄養膜細胞がPRL様物質を分泌していると推察された。今回局在が認められたのが栄養膜細胞であることから,胎盤性ラクトージェン(PL)である可能性が示唆された。ゾウでは,排卵後、血中P濃度は上昇するがその後一時的に低下,着床の起こる妊娠約7週に再度上昇し,分娩まで高値を維持する。これらの結果を総合すると,ゾウでは着床以降,栄養膜細胞のPRL様物質がパラクリン的に黄体に作用し,P分泌を刺激して22ヶ月間の妊娠を維持しているものと推察された。 本研究は,乾太助記念動物科学研究助成基金によって支援された。
- 著者
- 山本 達也 大野 貴司 棟田 雅也
- 出版者
- 岐阜経済大学地域経済研究所
- 雑誌
- 地域経済 (ISSN:03866122)
- 巻号頁・発行日
- vol.33, pp.25-40, 2014-03
大垣市の経済・産業と地域づくりEconomy, industry and regional development in Ogaki City共同研究報告IICollaborative Research Report II
1 0 0 0 OA イヌにおける CT 撮影により得られた体脂肪評価と BCS 評価の相関
- 著者
- 神田 鉄平 前田 憲孝 井口 亜弥乃 柴田 和紀 野村 千晴 山本 達也 村尾 信義 加計 悟 古本 佳代 古川 敏紀
- 出版者
- 日本ペット栄養学会
- 雑誌
- ペット栄養学会誌 (ISSN:13443763)
- 巻号頁・発行日
- vol.16, no.1, pp.1-6, 2013-04-10 (Released:2013-05-17)
- 参考文献数
- 9
肥満はイヌやネコにおいて一般的な健康問題のひとつである。肥満を予防、あるいはコントロールするには、体脂肪の評価を正しく行うことが必須となる。しかしながら、これまで広く用いられているBCS評価法は、観察と触感のみに基づき主観的になりがちである。そこで、BCSによる体脂肪の評価が客観性を担保した適切な方法であるかを確認すべく、我々はイヌにおけるCT撮影によって得られた体脂肪評価とBCSによる評価に相関が認められるかを検討した。実験には体重が2.6から29.3 kgまでの8犬種15頭のイヌを用いた。「アメリカ動物病院協会 栄養評価 犬・猫に関するガイドライン」に従い、9および5段階によるBCS評価(9段階BCS、5段階BCS)を行い、CT撮影により得られたL3およびL5レベルの断層画像から-135/-105HUの範囲を脂肪組織とみなした。体脂肪面積/体幹面積比はL5レベルにおいて、9段階BCSと中等度の相関を示した。また、9段階BCSはL5レベルでは、腹腔脂肪面積/体幹面積比とも中等度の相関を示した。つまり、イヌにおいて9段階BCSはCT撮影により得られた体脂肪評価との相関を示す結果となった。本研究結果は、BCS9がイヌの体脂肪評価法方法として比較的客観的であり、かつ適切であることを支持するものである。
1 0 0 0 IR 多数性としてのゲスト--北インド・ダラムサラを事例に
- 著者
- 山本 達也
- 出版者
- 京都大學人文科學研究所
- 雑誌
- 人文学報 (ISSN:04490274)
- 巻号頁・発行日
- no.98, pp.205-228, 2009
本論は,チベット難民が多く居住する北インドのダラムサラに訪れる観光客に焦点を当て,そこで観光客たちが見せる,一筋縄ではいかない多彩な視点や反応に着目する。それらを通して,観光客という存在やそれを取りまいてきた研究の前提を問い直すことを目的とするものである。ブーアスティンに始まり,マッカネルを経由してその議論が始まった1970年代以降数々の理論的進展を成し遂げてきた観光社会学,観光人類学に代表される旧来の観光研究は,観光客という存在や彼らの実践を考える際に,特に「真正性」という観点を軸として考察を展開してきた。こういった研究は,観光客という存在を,「真正性を求める」「真正性に興味がない」というふうにアプリオリに定義し,その前提をもとに,こういった研究は議論を展開していった。だが,観光客はこのように定義されるべきものなのであろうか。このように特定の視点を持ってのみ観光に臨むのであろうか。むしろ,観光客は多彩な視点を持って観光に臨んでいるし,また,現地での情報や出会いを通して,状況に応じて極めてアドホックに視点を変えていく存在なのではないだろうか。「真正性」を軸にしてアプリオリに定義された観光客像を持って議論を展開してきた旧来の諸研究は,その前提にはまらない観光客を捨象してしまい,また,現地で遭遇した出来事により「真正性」に対する視点を変更したり,その間で揺れ動くような状況が生じたりした観光客を考察することができていない。こういった研究が保持しているのは,西洋近代が提示してきた,同一性を前提とした主体観ではないだろうか。こういった視点を保持するよりも,我々は,観光客をもっと開かれた視点から考察する必要があるだろう。本論が提示する事例は,旧来の研究がアプリオリに設定していた観光客という存在に再考を迫るものである。This paper explores different viewpoints and reactions from guests who visit at Dharamsala in North India where a vast majority of Tibetan refugee are living. Based on this case study, this paper reconsiders the premise of previous studies about "the guest". Since the 1970's, numerous scholars have developed their studies of tourism on a certain premise of 'the authenticity'. They have treated "the guest" and "the tourist" as either "those who desires the authenticity in tourism" or "those who are indifferent to the authenticity in tourism". Those earlier studies therefore have regarded them simply as the premised categories. However, I question the validity of such premises in previous studies, by asking if we can define them in advance, and if they actually enjoy a tour in such a simply perspective. This paper argues that guests and tourists approach their tourism with diverse interests and viewpoints. The tourists can change their perspectives when they learn some critical information or they come across someone who can significantly affect their thought on 'the authenticity'. In essence, this case study criticizes the previous studies on the tourism and reconsiders their premise on guests and tourists.